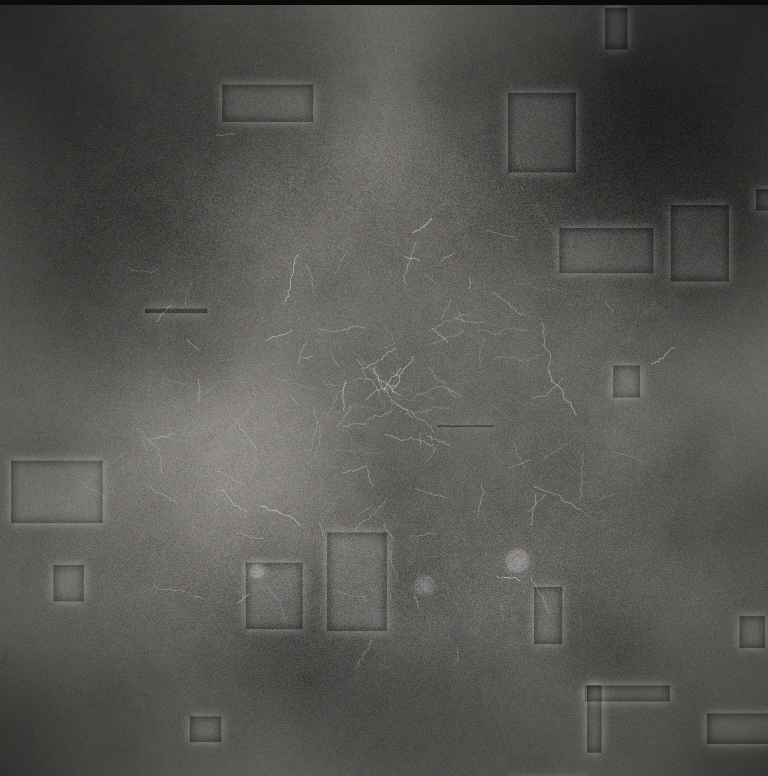審問官 Ⅰ
目次
第一章「喫茶店迄」
第二章「杳体」
第三章「轆轤首」
審問官 第一章「喫茶店迄」
序
私が思ふに、彼は絶えず「己を断罪せよ!」といふ内部から止めどなく湧き上がる自己告発の声に悩まされ続けてゐたのは間違ひない。そのことを彼は彼が何か行動を起こさうとする度に必ずと言っていいほどに内部で呟く者がゐると私に仄めかしてゐたのであった。
…………
…………
――断罪せよ!
…………
…………
彼は、当時から、そもそも己の《存在》自体に懐疑的であった、といふよりも、自己の《存在》を自殺以外の方法で此の世から葬り去る事ばかり考へてゐたのである。
…………
…………
――両親の死を看取ったなら即座に此の世を去らう。それが私の唯一の贖罪の方法だ……。
…………
…………
彼には主体なる《もの》の《存在》がそもそも許せなかったらしい。彼をさうさせた原因は、しかし、判然とせず、今もって私には謎のままである。彼が、あの頃、埴谷雄高が名付けた奇妙な病気――黙狂――を患ってゐたのは間違ひない。
彼はいつも何かを語らうとすると、言語がその構造を担保にしてゐる主語述語などといった言語が現はれるその言語自体の構造を見失って、彼の頭蓋内の闇、それを《五蘊場(ごうんば)》と彼は名付けてゐたが、その《五蘊場》では数多の言語が一斉に湧出し、渾沌に堕すその結果、無言になってしまふとのことであった。しかし、彼は無言とは言へ、それで全てを語ったといふのであった。それは、言葉が文法を無視して一斉に吐き出され、それは最早言葉である状態を失ひ、何も語ってゐないに等しい、つまり、端的に言へば《黙狂者》以外の何《もの》でもなかったのである。それは、
――俺は……。
と、言って彼が不意に黙り込んでしまふ事からも明らかに思へたのであった。つまり、彼は自同律の陥穽に終生堕ち込んだまま、其処から這ひ出た事は一度としてなく、そして、彼はそれを「善し」と自己納得してゐる風でもあったのである。
しかし、彼は学生時代が終はらうとしてゐた或る日、忽然と猛烈に語り始め、積極的に行動し始めたのであった。彼を豹変させ忽然とさう変へた原因もまた、私には判然としなかったのである。
彼は大学を卒業すると、二十四時間休む間のない事で学生の間で有名だった或る会社に自ら進んで就職したのであった。
風の噂によると、彼は猛然と二十四時間休む事なく働き続けたらしい。しかし、当然の結果、彼は心身共に疲労困憊し、遂には不治の病に罹ってしまったらしいのである。その後某精神病院に入院してゐるらしいとは、私も承知してゐた事であった。
…………
…………
――自同律の不快どころの話ではないな。『断罪せよ!』と私の内部で何時(いつ)も告発する者がゐるが、かうなると自同律を嫌悪する外なく、その結果故に吾は自同律の破壊を己の手で己を実験台にして試みたが……ちえっ……人間は何て羸弱(るいじやく)な生き物なのか……ふっ……自己破壊と言へば聞こえはいいが……ちえっ……唯……病気になっただけではないか……くっ……自己が自己破壊を試みた挙句……唯……病気になっただけ……へっ……をかしなもんだ……だが……しかし……俺も死に至る病にやっと罹れたぜ……へっ……両親も昨年相次いで亡くなったからもう自己弾劾を実行出来るな……。
…………
…………
彼の死は何とも奇妙な死であったらしい。態態(わざわざ)看護師を呼んではにやりと不敵な薄ら嗤ひを浮かべ突然哄笑したかと思へば忽然と息を引取ったらしいのである。
…………
…………
――断罪せよ……さうだ……お前をだ……其の《存在》自体が既に罪なのだ……。
…………
…………
何やら今も彼の言葉がこの時空間にゆらゆらと宇宙背景輻射の如く不可視な《もの》として漂ってゐるやうに思へて仕方がない……。
主体弾劾者の手記
にやりと嗤った途端、不意に此の世を去ったといふ彼の葬儀に参列した時、亡くなった彼の妹さんから彼が私に残したものだといふ何冊にも亙って彼が書き綴った大学Note(ノート)を渡されたのであった。英語と科学と数学を除いて勿論彼は終生縦書きを貫いたのでその第一冊目に当たってゐたと思はれる大学Noteの表紙にその大学Noteを縦書きで使ふ事を断言するやうに『主体、其れ主体を弾劾すべし!』と力強い筆致で筆書きされてあったのである。
その手記は次の一文から始まってゐた……。
――吾、吾を断罪す。故に吾、吾を破壊する――。
これは君への遺言だ。すまんが私は先に逝く。これが私の望む《生》だったのだ。私はこんな人生で満足しなければ、へっ、罰が当たるぜ……。本当に私は幸せだったのだ。
君もご存知の「雪」といふ名の女性が私の前に現はれた時に私は《自死》しなければならないと自覚せざるを得なかったのだ……。それは私が自意識に目覚めた時に既に薄らと吾に覚えてゐた何とも物悲しい感覚なのであった。
ふっ、自分で言ふのも何だがね……、私は皆に「美男子」と言はれてゐたので美男子だったのだらう。君はどう思ふ?
よくRock Band(ロツク・バンド)のU2の作品「WAR」のジヤケット写真の少年(俳優:ピーター・ロワン)に似てゐると言はれてゐたが、ご存知のやうに私は変人だったのでそれ程多くの女性にモテたとは言へないが、生命を生む性である或る女性の一部にとっては、私はどうしても私の《存在》が「母性」を擽(くすぐ)るのだらう、彼女らは私を抛って置けず無理矢理――この言ひ方は彼女らに失礼だがね――私の世話をし出したのは君もご存知の通りだ。
しかし、私に関わった全ての女性たちは私が金輪際変はらないと悟って私の元から皆離れて行った。雪もその一人だったのかもしれないがね……。ふっ、自業自得だね。
私は雪と出会った頃には埴谷雄高がいふ人間の二つの自由――子を産まぬ事と自殺する事の自由――の内、自殺の自由の行使の仕方ばかり考へてゐたが、私には、また、人間にはそもそも自由など無いし、また、宇宙は原則として自由なる事を許されてゐないとも自覚してゐたので、自殺してはならぬとは心の奥底では思ってゐたけれども、画家のファン・ゴッホの死に方には一種の憧れがあったのは事実だ。自殺を決行して死に損なひ、確か三日ぐらゐ生きた筈だが、私もファン・ゴッホが死す迄の三日間の苦悩と苦痛を味はふ事ばかりその頃は夢想してゐたものだ。それほどに私は追ひ込まれてゐたのかもしれなかったのだ。それに自殺は地獄行きだから、死しても、尚、未来永劫《吾》であり続けるなんて御免被るといった事も私が自殺しなかった理由の一つだ。何故って、地獄とは《吾》は卒倒することすら許されないところで、意識は未来永劫に亙ってずっと《吾》は《吾》として地獄の責苦を味はひ続けなければならないのさ。
今は亡き母親がよく言ってゐたが、私は既に赤子の時から変はってゐたさうだ。或る一点を凝視し始めたならば、乳を吸ふ事は勿論、排泄物で汚れたおむつを替へるのも頑として拒んださうだ。ふっ、私は生まれついて食欲よりも凝視欲とでも言ったら良いのか、見る事の欲望が食欲より――つまりそこには性欲も含んでゐるが――優ってゐたらしい。赤子の時より既にある種の偏執狂だったのさ。君が私を《黙狂者》と呼んだのは見事だったよ。今思ふとその通りだったのかもしれない。
そんな時だ、雪に出会ってしまったのは……。
私が何故Television(テレビ)を殆ど見ず、街中を歩く時伏目になるのかを君はご存知の筈だが……、実際、私には他人の死相が見えてしまふのだ。街中で恋人と一緒に何やら話してゐて快濶に哄笑してゐる若人にはっきりと死相が見える……。体の不自由なご主人と歓談しながらにこにこと微笑み車椅子を押してゐるそのご婦人にはっきりと死相が見える……。Televisionで笑顔を見せてゐるTalent(タレント)にはっきりと死相が見える等等、君にも想像は付く筈だが、この他人の死相が見えてしまった瞬間の何とも名状し難い気分……これは如何ともし難いのだ。それが嫌で私はTelevisionを見ず、伏目で歩くのだ。他人の死相が見えてしまったときの私の慌てやうは解かるだらう? それはどうあっても抗ふことが出来ないもので、街を歩けば必ず一人くらゐの死相は見えてしまふものなのさ。
そんな私が馥郁(ふくいく)たる仄かな香りに誘はれて大学構内の欅を見た時、その木蔭のBench(ベンチ)で彼女、つまり、雪が何かの本を読んでゐるのを目にしたのが、私が雪を初めて見た瞬間だった。
その一瞥の刹那、私は雪が過去に男に嬲られ陵辱されたその場面が私の脳裡を掠めたのである。そんな事は今迄無かった事であったが、雪を見た刹那だけそんな不思議な事が起こったのであった。それは、所謂以心伝心と言ふもので、雪との間においては、何故か、心が通じる「会話」が自然と出来たのだ。その時は、私は雪に声も掛けずにそのまま欅の木の傍らを通り過ぎたのだがね。しかし、雪に言はせるとその瞬間に雪は私に一目惚れしたらしいのだ。
しかし、その時を境として私は、雪が欅の木の下のBenchに座ってゐないかと、その欅の前を通る度に雪を探すやうになったのさ。
君もさうだったと思ふが、私は大学時代、深夜、黙考するか本を読み漁るか、または真夜中の街を徘徊したりしては朝になってから眠りに就き夕刻近くに目覚めるといふ自堕落な日日を送ってゐたが、君とその仲間に会ったところで私は無言のまま、唯、君たちの会話を聞くに過ぎぬにも拘はらず、私は君とその仲間に会ふために夕刻になると大学にはほぼ毎日通ふといふ、今思ふと不思議な日日を過ごしてゐた訳だ。
話は前後するが、今は攝(せつ)願(ぐわん)といふ名の尼僧になつてゐる雪の男子禁制の修行期間は疾(と)うに終はつてゐる筈だから、雪、否、攝願さんに私の死を必ず伝へてくれ給へ。これは私の君への遺言だ。お願ひする。多分、攝願さんは私の死を聞いて歓喜と哀切の入り混じつた何とも言へない涙を流してくれる筈だから……。
さうさう、それに君の愛犬「てつ」こと「哲学者」が死んださうだな。さぞや大往生だつたのだらう。君は知つてゐるかもしれないが、私は「てつ」に一度会つてゐるのだ。君の母親が、
――家(うち)にとんでもなく利口な犬がゐるから一度見に来て。
と、私の今は亡き母親に何か事ある毎に言つてゐたのを私が聞いて、私は「てつ」を見に君の家に或る日の夕刻訪ねたのだが、生憎、君はその日は不在で、君の母親の案内で「てつ」に会つたのだよ。
「てつ」は凄かつた……。夕日の茜色に染まつた夕空の下、「てつ」の赤柴色の毛が黄金(こがね)色(いろ)に輝き、辺りは荘厳な雰囲気に蔽はれてゐたのさ。その瞬間、私にとつて「てつ」は「弥勒(みろく)」になつちまつた。私を見ても「てつ」こと「哲学者」、若しくは「弥勒」は全く警戒しないので君の母親は私と「弥勒」の二人きりにしてくれた。それはそれは有難かつた。暫く「弥勒」の美しさに見蕩(みと)れてゐると「弥勒」が突然、私に、
――うああお~んわーうわうあう~~。
と、何か私に一言話し掛けたのである。私にはそれが「諸行無常」と聞こえてしまつたのだ……。
今でもあの神神しい「弥勒」の荘厳な美しさが瞼の裏に焼き付いてゐるぜ……。さてさて、彼の世で「弥勒」に会へるのが楽しみだ……。
さて、話を雪の事に戻さう。
或る初夏の夕刻、君と一緒にあの欅の前を歩いてゐると、雪がBenchに座つていつものやうに何かの本を読んでゐた……。それがすべての始まりだったのかもしれないと思ふのさ。
…………
…………
話を先に進める前に君に言つておくがね、しかし、君には多分薄薄と解つてゐた筈だが、私が私であるといふ自同律を嫌悪する私は、性に対してもその通りだつたのだ。思春期を迎へ夢精が始まり、まあ、それは《自然》の事だから何とか自身を納得させたがね、しかし、自慰行為は幻滅しか私に齎さなかつた。射精の瞬間の《快楽》がいけないのだ。その《快楽》は私に嘔吐を反射的に齎すものでしかなかつた……。
…………
…………
君は「ⅹの零乗=1」《(x>0:0より大きい数の零乗は1となる》といふ事は知つてゐるね。私はこの雪との出会ひの時に、自同律の嫌悪を超克するには《死》しかないと確信してしまつたのだ。皮肉なことだがね。これは何ともし難い私のLibido(リビドー)とも言える《死》の衝動だつたのだ。零乗の零と言ふアラビア数字の形が一回転した《もの》の軌跡に見え、零乗されたⅹなる《存在》は皆平等に1になる、つまり、私にとつてそれは現世での《一生》に見え、更に《存在》全てに平等に訪れる《死》をも其処に見てしまつたのだ。生命は死の瞬間確率1になる。否、もしかすると《存在》はその死の瞬間に零、若しくは∞、つまり、《無》、若しくは《無限大》に化けるのかもしれぬが、しかし、つまり、1=1といふ自同律は《死》で一応完結する筈さ。私はこれで自同律の嫌悪は終はるに違ひないと自覚せざるを得なかつたのだ……。そして、さう望んだやうに私はかうして死んだのだ。私はこれに満足してゐる。
――はつ。
…………
…………
ところで、雪を除いて過去に私を一方的に愛してしまつた女性たちは或る時期を過ぎると必ず私に性行為を求めて来たので私は《義務》でそれら全てに応じたが、性行為が終はると《女の香り》が私を反射的に嘔吐させる引き金になつてしまつたのだ。勿論、私は同性愛者ではない。だから、尚更いけないのだ。或る時、私が射精した瞬間、女性の顔面に嘔吐してしまつたのを最後に、私は女性との性行為もしくは性交渉をきつぱりと已めてしまつた……。
また雪を除いての話だが、それに《女体》の醜悪さはどうしようもなかつた。彼女たちは彼女自身の《脳内》に棲む《自身の姿》をDietなどと称しながら自身の身体で体現する《快楽》が正しく私の嫌悪の元たる自同律の《快楽》だと知つてゐた筈だが、私の嘔吐を見ながらも、誰ひとりの女性も《脳内》の自分の具現化といふ実に不愉快極まる事を已めはしなかつたのだ。結局彼女たちの理想の体型は痩せぎすの《男の身体》に《女性》の性的象徴、例へば乳房を、しかもそれが豊満だと尚更良いのだが、そんな《不自然な》体型を《女体》と称して私に見せ付けたのだ。これが醜悪でないならば何が醜悪といふのか……。
…………
…………
そんなときに雪が現はれたのだ。
私が君と連れだつて大学の構内を歩いてゐて、私が不意に欅の木蔭のBenchにゐた雪を見つけた時、反射的に私の足は雪に向かつて歩き始めてしまつた。その時、雪は読んでゐた本から目を上げ私を一瞥すると、私の全てを一瞬にして理解したやうに可愛らしい微笑を顔に浮かべた。私はその時に既に悟つていたのさ。雪は私を彼女の全《存在》で受け容れてくれたのだ。君にはこの時の雪と私の間で通じ合ひ、それをお互ひ一瞬で理解してしまひ、更には多分お互ひ同士それを明瞭に感じた筈である奇妙な或る感覚は、多分理解不能だと思ふが、《奇跡的》に他人同士が一目で全的に互いを理解する出来事がその時起こつてしまつたのだ。
吾ながら今もつてその時の事は不思議でならないがね……。
君は私が《黙狂者》だと認識してゐたので、君は多分私と雪との関係をこれまた一瞬で理解したのだらうね。君は駆け出して、私より先に雪に声を掛けたね。あの時は有難う。
――君、何の本を読んでゐるの?
――William Blake(ヰリアム・ブレイク)よ。
――それは丁度いい。良かつたならなんだけど、これから僕たちブレイクの《THERE IS NO NATURAL RELIGION》と《ALL RELIGIONS ARE ONE~The Voice of one crying in the Wilderness~》をネタにして、男ばかりだけど……飲み会みたいなSalon(サロン)みたいな真似事をしようとしてゐるので……君もよかつたら来ないかい?
――……ええ、いいわよ。
――本当、ぢやあ、僕らと一緒に行かう。
雪が君と会話してゐる間もずつと雪は私を見て微笑んでゐたのは君も覚えているだらう。その時私には既に雪が尼僧の像と二重写しで見えてしまつてゐたのだ……。不思議なことなのだが、それは今も尚、私にとっては余りにも自然なことに思はれて仕方がないのさ。
William Blake著
《THERE IS NO NATURAL RELIGION》
[a]
The Argument. Man has no notion of moral fitness but from
Education. Naturally he is only a natural organ subject to
Sense.
I Man cannot naturally Percieve. but through his natural or
bodily organs.
II Man by his reasoning power. can only compare & judge of
what he has already perciev’d.
III From a perception of only 3 senses or 3 elements none
could deduce a fourth or fifth
IV None could have other than natural or organic thoughts if
he had none but organic perceptions
V Mans desires are limited by his perceptions. none can desire
what he has not perciev’d
VI The desires & perceptions of man untaught by any thing but
organs of sense, must be limited to objects of sense.
Conclusion. If it were not for the Poetic or Prophetic character
the Philosophic & Experimental woud soon be at the ratio of all
things & stand still unable to do other than repeat the same dull
round over again
[b]
I Mans perceptions are not bounded by organs of perception. he
percieves more than sense (tho’ ever so acute) can discover.
II Reason or the ratio of all we have already known. is not
the same that it shall be when we know more.
[III lacking]
IV The bounded is loathed by its possessor. The same dull
round even of a univer[s]e would soon become a mill with
complicated wheels.
V If the many become the same as the few, when possess’d,
More! More! is the cry of a mistaken soul, less than All cannot
satisfy Man.
VI If any could desire what he is incapable of possessing,
despair must be his eternal lot.
VII The desire of Man being Infinite the possession is Infinite
& himself Infinite
Application. He who sees the Infinite in all things sees
God. He who sees the Ratio only sees himself only.
Therefore God becomes as we are, that we may be as he is
《ALL RELIGIONS ARE ONE》
〔The Voice of one cryng in the Wilderness〕
The Argument As the true method of knowledge is experiment
the true faculty of knowing must be the faculty which experiences.
This faculty I treat of.
PRINCIPLE 1st That the Poetic Genius is the true Man. and that
the body or outward form of Man is derived from the Poetic Genius.
Likewise that the forms of all things are derived from their Genius.
which by the Ancients was call’d an Angel & Spirit & Demon.
PRINCIPLE 2d As all men are alike in outward form, So (and with
the same infinite variety) all are alike in the Poetic Genius
PRINCIPLE 3d No man can think write or speak from his heart, but
he must intend truth. Thus all sects of Philosophy are from the Poetic
Genius adapted to the weaknesses of every individual
PRINCIPLE 4. As none by traveling over known lands can find out
the unknown. So from already acquired knowledge Man could not ac-
quire more. therefore an universal Poetic Genius exists
PRINCIPLE. 5. The Religions of all Nations are derived from each
Nations different reception of the Poetic Genius which is every where
call’d the Spirit of Prophecy.
PRINCIPLE 6 The Jewish & Christian Testaments are An original
derivation from the Poetic Genius. this is necessary from the
confined nature of bodily sensation
PRINCIPLE 7th As all men are alike (tho’ infinitely various) So
all Religions & as all similars have one source
The true Man is the source he being the Poetic Genius
(出典:PENGUIN CLASSICS版 「WILLIAM BLAKE――THE COMPLETE POEMS」より頁75~77)
ヰリアム・ブレイク著
《THERE IS NO NATURAL RELIGION》の拙訳
「如何なる自然宗教(理神論)も在り得ない」
[a]
論証。人間は教育を除く如何なるものからも道徳の適合性に関する概念を持ち得ない。本来人間は感覚に従属する単なる自然器官である。
一 人間は本来知覚する事が出来ない。自身の自然乃至身体器官を通さずしては。
二 人間は自身の推理力によつては。単に自身が後天的に理解(知覚)した事を比較乃至判断出来るのみである。
三 単に三つの感覚乃至三つの要素のみで構築した知覚から如何なる人間も第四の乃至第五の知覚を演繹出来なかつた。
四 仮に人間が器官による知覚の外一切を持たないなら如何なる人間も自然乃至器官による思惟形式以外持ち得る筈もない。
五 人間の希求は自身の知覚によつて限られる。如何なる人間も自身が知覚し得ないものを希求する事は出来ない。
六 感覚器官以外では如何なる事象も知り得ぬ人間の希求及び知覚は感覚(客体)の対象に対して制限されなければならない。
結語。仮に詩的乃至預言的な表現が此の世に《存在》しないならば、哲学的及び試論による表現は即ち全事象の数学的比率となり、及び陰鬱な単一反復回転運動を繰り返す以外不可能故に立ち尽くす(停止する)のみである。
[b]
一 人間の知覚は認識機構によつて制限されない。人間の感覚(どれ程鋭敏であらうとも)が見出す以上の事を知覚(認識)する。
二 推論乃至吾吾が後天的に認識した全事象の数学的比率は。吾吾が更に多く認識すると想定された《存在》と同じである事はない。
三 欠落
四 枠付けは枠付けした者に忌避される。宇宙の陰鬱な反復回転運動でさへ、即ち歯車複合体たる水車小屋に変容するであらう。
五 仮に多様が単純に還元されると看做す場合、そしてそれに取り憑かれたとき、もつと! もつと! は迷妄なる魂の叫びであり、直ちに全事象は人間を満足させる。
六 仮に如何なる人間も自身で持ち得ないものを希求する事が出来るとするなら、絶望こそ人間の永劫に亙つて与へられし運命であるに違ひない。
七 人間の希求が無尽蔵なら、それを持ち得るといふ事は無限であり自身もまた無限である。
応用。全事象に無限を見るものは神を知る。単に数学的比率しか見えぬものは自己しか知り得ない。
それ故、神は吾吾が《存在》する限り《存在》し、即ち吾吾は神が《存在》する限り《存在》するのであらう。
《ALL RELIGIONS ARE ONE》の拙訳
「全ての宗教は一つである」
荒野の一嘆き声
論証。真の認識法が試みであるなら、真の認識力は経験の能力でなければならない。この能力について論ず。
第一原理 詩的霊性が人間の本質である。及び人間の肉体乃至外観の様相は詩的霊性から派生する。同様に全《存在》物の形相はそれら自身の霊性から派生する。古代の人々はそれを天使及び霊魂及び霊性と呼んだ。
第二原理 全人類が形相に於いて同等であるなら、即ちその事はまた(及び等しく無限なる多様性を持つならば)全人類は詩的霊性に於いても同等である。
第三原理 如何なるものも自身の心の深奥から思考し乃至書き乃至話す事は出来ないが、しかし人間は真理へ向かはなければならない。何故なら哲学の全学派は全個人の羸弱さに応じた詩的霊性から派生したものである。
第四原理 既知の領域を見回したところで如何なるものも未知を見出す事は出来ない。即ち後天的に得た認識から人間はそれ以上獲得出来なかつた。故に全宇宙型詩的霊性は《存在》する。
第五原理 あらゆる民族の各宗教はあらゆる場所で預言の霊性と呼ばれる詩的霊性を各民族が多様に感受した事から派生する。
第六原理 ユダヤ教徒及び基督教徒の聖書は詩的霊性から本源的に派生したものである。この事は肉体的感覚の限界性から必然である。
第七原理 全人類は同一(無限の多様性が見えてゐるにも拘はらず)である故に、全宗教及び全宗教的類似物は一つの本源を持つ。
真の人間は自身が詩的霊性である事の源である。
以上、当時のMemoのまま――表現が稚拙で誤訳ばかりであるが――ここに書き記しておく。当時の雰囲気が香つてくるのでね。
さて、君に話し掛けられても私を微笑みながらぢつと見続けてゐた雪の目は、フランツ・カフカかエゴン・シーレのSelf-portraitの眼光鋭き眼つきを一見髣髴とさせるやうに見えるが、しかし、よくよく見てみると雪の目は柔和そのものであつたのだ。
君も雪の行動が奇妙な点には気が付いてゐた筈だが、雪は未だ《男》に対して無意識に感じてしまふ恐怖心をあの時点の自身ではどう仕様もなく、雪は《男》を目にすると自然と雪の内部に棲む《雪自体》がぶるぶると震へ出し、雪の内部の内部の内部の奥底に《雪自体》が身を竦(すく)めて《男》が去るのをぢつと堪へ忍ぶといつた状態で、雪は君の顔を一切見ず君と話をしてゐたんだよ。
その点、雪は私に対しては何の恐怖心も感じなかつたのだらう。つまり、雪にとつて私は最早《男》ではなく、人畜無害の《男》のやうな《存在》、しかも、
――この人の人生はもう長くない……。
と、多分だが、私を一瞥した瞬間全的に私といふ《存在》を雪は理解してしまつたと、そして、また、そんな雪を、私は雪の様子からこれまた全的に雪を理解してしまつたのだ。これは一見不思議に見えるが、此の世で生きているならば、誰しも経験があることだらう。
と、そんな事を思ふ間も無く、あの時は無意識裡に私の右手は雪の頭を撫でる様に不意に雪の頭に置かれたが、雪は何の拒否反応も起こさず、これまた全的に私の行為を受け容れてくれたのだ。
さて、私が何故《黙狂者》となつてしまつたかを君も薄薄気付いてゐた筈だが、それは私の人生が短く終はるしかないといふ事とも関係してゐたのだらうけれども、私が一度何かを語り出さうと口を開けた瞬間、我先に我先にと無数の言葉が同時に私の口から飛び出ようと、一斉に口から無数の言葉が渾沌としたまま飛び出さうとしてしまふからなのだ。多少、無念ではあるがね、人生が短く終はるしかない私にとつて、私の《未来》を閉ぢ込めてゐる筈の私の内部の《未来》は、結果として既に無きに等しいので、私の内部の《未来》には時系列的な秩序、若しくは構造が生まれる筈もなく、つまり、私の《未来》は既にまつ平らで薄つぺらな薄膜の如きものでしかなく、それは、つまり、無きに等しいが故に《渾沌》としてゐたのだ。私が口を開き何かを語り出さうとしたその瞬間に最早全ては語り尽くされてしまつてゐるといふ去来(こらい)現(げん)の転倒が私の身には起きてゐて、それ故に《他者》にはそれが《無言》に聞こえるだけなのだ。つまり、《無=無限》といふ奇妙な現象が既に私の身には起こつてゐたのだ。
君は私が雪の頭にそつと手を置いた時、私が口を開いたのを眼にしただらう。多分、雪はこれまた全的に私の無音の《言葉》を全て理解した筈だ。君はあの時気を利かせてくれて、ずつと黙つて私と雪との不思議な《会話》を見守つてくれたが、仮に心といふものが生命体の如き《もの》で、傷付きそれを自己治癒する能力があるとするならば、雪の心はざつくりとKnife(ナイフ)で抉(えぐ)られ、あの時点でも未だ雪の心のその傷からはどくどくと哀しい色の血が流れたままで《男》に理不尽に陵辱された傷口が塞がり切れてゐなかつたのだ。それが痛痛しくも鮮明に私には見えてしまつたので、《手当て》の為に雪の頭にそつと手を置いたのだ。そのことは雪もまた、全的に理解していたのさ。
それにしても雪の髪は烏(からす)の濡れ羽色――君は烏の黒色の羽の美しさは知つてゐるだらう。虹色を纏つたあの烏の羽の黒色程美しい黒色は無い――といふ表現が一番ぴつたりな美しさを持ち、またその美しさは見事な輝きをも放つてゐた。
さて、君はあの瞬間雪の柔和な目から恐怖の色がすうつと消えたのが解つたかい?
そして、君もご存知の通り、雪の目から恐怖の色がすうつと消えたと思つた瞬間、私は不意の眩暈(めまひ)に襲はれたのだ。
――どさつ。
あの時、先づ、私の目の前の全てが真つ白な霧の中に消え入るやうに世界は白一色になり、私は腰が抜けたやうにその場に倒れたね。しかし、意識は終始はつきりしてゐた。君と雪が突然の出来事に驚いて私に駆け寄つたが、私は軽く左手を挙げて、
――大丈夫。
といふ合図を送つたので君と雪は私が回復する迄その場で見守り続けてくれたが、あの時は私の身体に一切触れずにゐて見守つてくれて有難う。私が他人に私の体軀を勝手に触られるのを一番嫌つてゐる事を君は知つてゐる筈だからね……。
あの時の芝の青臭い匂ひと熊蝉の鳴き声は今でも忘れないよ。
私が眩暈で倒れた時に感覚が異常に研ぎ澄まされた感じは今思ひ返しても不思議だな……。あの時私の身に何が起きてゐたのかは明瞭過ぎる程はつきりと憶えてゐるよ。
それでも眼前が、世界全体が、濃霧に包まれたやうに真つ白になつたのは一瞬で、直ぐに深い深い深い漆黒の闇が世界を蔽つたのだ。つまり、当然私はその時外界は見えなくなつてゐたのだ。
するとだ、漆黒の闇の中に金色(こんじき)の釈迦如来像が現れるとともに深い深い深い漆黒の闇に蔽はれた私の視界の周縁に二つの勾玉の形をした光雲――光の微粒子が雲の如く集まつてゐたから光雲と名付ける――が現れ、左目の視界の周縁だと思ふ辺りを時計回りに、右目の視界の周縁だと思ふ辺りを反時計回りに、つまり、数学でよく見る二つの集合が交はつた図そつくりに私の視界にその光跡を残しながら、その光雲がぐるぐると私の視界の周縁を周り出したのだ。
そして、その金色の釈迦如来像がちらりと微笑んだかと思ふ間もなく不意と消え、世界は一瞬にして透明の世界に変化(へんげ)した……。
眩暈でぶつ倒れたままの私の視界全体に拡がつたその薄ら寒い透明な世界に目を凝らしてゐると、突然、赤赤と燃え上がる業火の如き炎が眼前に出現したのだ。それは正に血の色をした業火だつたよ。
その間中、例の光雲は視界の周縁をずつと廻り続けてゐた……。
私が悟つたのはその時だ。自分の死についてそれ以前は未だ何処となく他人(ひと)事のやうに感じてもゐたのだらう。私はまだ己の死に対して、覚悟は正直言つて出来てゐなかつた、が、私が渇望してゐた《死》が直ぐ其処迄来ているなんて……私はその時何とも名状し難い《幸福》――未だ嘗て多分私は幸福を経験した事がないと思ふ――に包まれたのだ。
――くつくつくつ。
私は眩暈で芝の上にぶつ倒れてゐる間《幸福》に包まれて、内心哄笑してゐたのさ。
しかし、燃え盛る業火は、私が眩暈から覚め立ち上がつても目の奥に張り付いて……ちえつ……今も見えてしまうのだがね。
さう、時間にしてそれは一分くらゐの後の事だつたよね。私が不図眩暈から覚め何事もなかつたかのやうに立ち上がつたのは。君と雪は何だかほつとしたのか互ひに顔を見合はせて笑つてゐたね。その時君は初めて雪と目が合つた筈だが、君の目には雪はどのやうに写つたんだい? 私には雪はその時既に尼僧に見えたのだ……。これまた、不思議に思ふかもしれぬが、人間、生きてゐると不可思議な経験の一つや二つあつて当然だらう。君にもそんな不思議な体験がある筈だがね。まだ、ないと思つてゐるならば、直にそれが身に染みて解かる筈さ。
眩暈から覚め何事もなかつたやうにすつくと立ち上がつた私を見て、君と雪は初めて見詰め合つて互ひに安堵感から不図笑顔が零れたが、その時の雪の横顔は……今更だが……美しかつた。雪は何処となくグイド・レーニ作「ベアトリーチエ・チエンチの肖像」の薄倖の美女を髣髴とさせるのだが、しかし、凛として鮮明な雪の横顔の輪郭は、彼女が既に持つてゐた《吾が道ここに定まれり》といつた強い意志を強烈に表してゐたのである。
―大丈夫?
と、雪が声を掛けたが、私は一度頷いたきり茜色の夕空をぢつと凝視する外なかつた……。
何故か――。
君は多分解らなかつただらうが――後程雪には解つてゐたのが明らかになるが――私には或る異変が起きてゐたのだ。血の色の炎が燃え上がるやうな業火が目の網膜に張り付いた事は言つたが、もう一つ私の視界の周縁を勾玉模様の小さな光雲が、大概は一つなのだが、最早消える事なく今もずつと時計回りに若しくは反時計回りにゆつくりと回つてゐる事である。そして、私はその光雲を人魂だと直感的に判断し、その判断を疑ふ事もなく、今も人魂だと信じてゐるのさ。そして、その人魂は私のものと他人のものとが同時に入り混じつてゐたのだ。つまり、誰か私が与り知らぬ他人が死を迎えると、たぶん、その死を迎へた人間の意識は解放され、全宇宙に向かつて爆発膨張する。そして、私はその爆発膨張した意識の残骸に感応し、私の眼による視界がそれを捉へるのだ。その結果として私の視界にその人魂が一足飛びにやつてきて、私の目玉はそれを捉へてしまうのさ。人間の体軀は殆ど水分で出来てゐる事と此処が北半球といふ事を考慮すると、時計回りの回転は上昇気流、つまり、私の視界から何か――多分それは私自身の魂魄に違ひない――が憧(あくが)れ出て時計回りに回り、若しくは私の全く知らない赤の他人の魂魄が私に侵入し続けてゐる事を反時計回りといふ回転の方向は意味してゐたのである……。
勾玉模様の光雲が見えるのは大概一つと言つたが、時にそれが二つであつたり三つであつたり四つであつたりと日によつて見える数が違つてゐた。例へば、星がその死を迎えるとき大爆発を起こして色色なものを外部に放出するが、人の死もまた星の死と同じで、人が死の瞬間例へば魂魄は大爆発を起こし外部に発散する……。それが此の世に未だ《生きる屍》となつて杭の如く《存在》する私をして魂魄のカルマン渦が発生し、それが私の視界の周縁に捉へられるのだ。だから多分、その光雲の一つは私の魂魄で、その他は死んだ《もの》の魂魄の欠片に違ひない……私はさう解釈してしまつたし、それで間違ひないと今も思つてゐるんだ……。
…………
…………
さて、君と雪と私はSalonの真似事が行れる喫茶店に向け歩き出した。その途中に古本屋街を通らなければならないのだが、君は気を利かせてくれたのだらう、その日に限つて古本屋には寄らずに真つ直ぐに喫茶店に向かひ、私と雪を二人きりにしてくれたね。有難う。
私は先づ馴染みの古本屋で白水社版の「キルケゴール全集」全巻を注文し、それから雪とぶらぶらと古本屋を巡り始めたのだつた。
古本屋の主人との遣り取りはいつも筆談だつたので、馴染みの古本屋の主人は多分今でも私の事を聾啞者だと思つてゐるに違ひない。それにそこの古本屋の主人は何かと私には親切でその日も「キルケゴール全集」を注文すると、どれでも好きな本を一冊おまけしてくれるといふので、私は、埴谷雄高の『死霊(しれい)』を凌駕するべく書き出したはいいが、書き出しても尚、書き出しの筆致の迷ひや逡巡等がそのまま取り繕ひもせずに直截的に書き記された文章で始まる現代小説の傑作の一つ、武田泰淳の『富士』の初版本を選んだのだ。
『富士』を読む時は、私は何時もブラームスの「交響曲第一番 ハ短調 op.68」を聴く。どちらも作品を書き連ねる事に対する迷ひや逡巡等がよく似てゐると思はないかい? それに泰淳さんは盟友の椎名麟三が洗礼を受け基督者になつた時、埴谷雄高が椎名麟三を誹(そし)つた事と、そして純真無垢といふのか天衣無縫といふのか、埴谷雄高曰く「女ムイシユキン公爵」たる泰淳夫人で著名な随筆家の百合子夫人に対する埴谷雄高の好意への多分「嫉妬」を死す迄泰淳さんは根に持つてゐた節があるが、そこがまた武田泰淳の魅力でもあるがね。
さて、雪はSalonの真似事が開かれてゐた喫茶店に着く迄終始私の右に並んで歩き、左手で私の右手首を少し強く握り締めたままであつたのである。
馴染みの古本屋を出たとき、東の空には毒毒しい程赤赤とした満月が地平から上り始めてゐたが、その満月の「赤」が私の目に張り付いた燃え盛る業火の炎の色に似てゐたのである。
――成程……この業火の色は《西方浄土》の日輪の色を映したものか……。
その時、雪が私の右手首を少し強く握り締めてゐたのは多分理不尽な陵辱を受けた「男」に対する恐怖といふよりも、
――今暫くは逝かないで。
といふやうな切なる感情を以てして私に対する切願が込められてゐたやうに私は確信してゐる。唯、私は女性に対しては無頓着なので雪のしたいやうにさせ、雪に為されるがまま夕闇の古本屋街を二人で漫(そぞ)ろ歩きを始めたのであつた。
当然、私は伏目であつた。雪は私の右手首を握つて私を巧く《操縦》してくれたのである。雪が、私を捕まへてないと何処か、つまり《彼の世》へ行つてしまふと直感的に感じてゐたのは間違ひない。そして、雪はかう切願してゐたに違ひないのだ。
――今は未だ逝かないで……。
とね。だが、雪には済まないことなのだが、私はやはり、もうそんなに人生の時間がなかったのさ。
ここで話が横道に逸れるがね、君に私の《死後の世界》について預言しておかう。
私が死して後、私のゐない此の世の有様こそ私の《死後の世界》の様相を忠実に反映してゐると考へておくれ。君や嘗ての雪、即ち攝願やSalonの仲間を始め、私のゐない此の世がまあまあ過ごし易ければ私は極楽浄土にゐるし、此の世が地獄の有様だとすれば私も地獄に堕ちたと思つてくれ給へ。私のゐない此の世の有様こそ私の《死後の世界》に外ならないのさ。
まあ、それはそれとして、私の死後、君達は、特に攝願、つまり俗名でいふところの雪は、彼女が出家する迄に私が施した、例へば雪の為されるがまま私が何の抵抗もせずそれに無言で従つた事などは、雪の《男》に対する憎しみやそれに伴ふ底知れぬ苦悩といふ雪の内部でばつくりと傷口の開いた《心の裂傷》を縫合し、その傷に軟膏薬を塗布して治療する意図があつての事で、多分に私の《存在》によつて雪も癒された筈だが、といふのも幾ら《生きる屍》に為り下がつたとはいへ、私も生物学的には《男》そのものだからね。
そして、雪は出家し攝願と為つた訳だが、攝願が尼僧でゐる間は《禊(みそぎ)の時間》に過ぎない。攝願の内部の《心の裂傷》が癒え、その傷の《瘡(かさ)蓋(ぶた)》が剥がれ落ちると、攝願の《禊の時間》は終はりを告げる。さうして、暫くすると、私も君もSalonの仲間も知つてゐる或る「男」に攝願は惚れ、攝願は何もかも捨ててその「男」の元へと身を寄せる筈だ。さうして再び雪に戻るのさ。「男」は「男」で、雪に逢つた時からずつと惚れてゐた。そこで雪はその「男」の子供を身ごもり「母」になる。雪の第一子は男の子で、雪はその子に私の名を付ける。勿論、雪の配偶者たるその「男」も大賛成さ。まあ、これ以上は話さない方がいいので黙つて彼の世に持つて行くよ。
さて、そこで君にお願ひがある。雪は寺を出た後、その悔恨に悶絶する程苦悩し続ける事になるが、君は雪の良き理解者となつて、雪の「愚痴」の聞き役になつてくれ給へ。お願ひする。さうする事で君達に起こるであらう艱難辛苦も乗り越へられ、私も浄土で安らげるといふものさ。重ね重ね宜しく頼むよ。
話を戻さう。
ところで、古本屋街を漫ろ歩きしてゐた私と雪との間には、雪がぽつりぽつりと一方的に私に話す以外殆ど会話は無かつた。
沈黙……。Salonの仲間とは違つた心地よさが雪との間の沈黙にはあつたのだ。互ひが互ひを藁をも縋る思ひで「必要」としてゐた事ははつきりとしてゐたので、多分、雪と私の間には――他人はそれを《宿命》とか《運命》とか呼ぶのだらうが――互ひに一瞥した瞬間に途轍もなく太い《絆》で結ばれてしまつたのは確かなのだ……。
…………
…………
――ねえ、この古本屋さんに入りましよう。
少し強めに雪に握られた右手首を通して、雪の心の声が聞こえて来たのであつた……。
その古本屋は雪の馴染みの古本屋だつた。少し強めに握られてゐた私の右手首から不意に雪は手を離し、雪にはお目当ての本の在り処が解つてゐたのだらう、私を古本屋の入り口に残したまま一目散に其方に向かつて歩を進めたのであつた。
その古本屋は、東洋の思想、哲学、宗教、神話等等の専門の古本屋だつた。
雪に取り残された私は、その古本屋内の仏典の本棚に向かつてゆるりゆるりと歩を進めたのであつた。
私は唐三藏法師玄奘譯(たうさんざうほふしげんぢやうやく)の般(はん)若(にや)波(は)羅(ら)蜜(みつ)多(た)心(しん)經(ぎやう)が、その時どうした訳か無性に読みたくなつたのであつた。
「觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。
舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。
舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。
是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。
無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。
以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。
三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。
故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛故。
說般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝菩提僧莎訶
般若波羅蜜多心經」
訓み下し
「觀自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時、五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまへり。
舎利子、色は空に異ならず、空は色に異ならず。色はすなはちこれ空、空はこれすなはち色なり。受想行識もまたまたかくのごとし。
舎利子、この諸法は空相にして、生ぜず、滅せず、垢つかず、浄からず、増さず、減ぜず、この故に、空の中には、色もなく、受も想も行も識もなく、眼も耳も鼻も舌も身も意もなく、色も声も香も味も触も法もなし。眼界もなく、乃至、意識界もなし。無明もなく、また、無明の尽くる事もなし。乃至、老も死もなく、また、老と死の尽くる事もなし。苦も集も滅も道もなく、智もなく、また、得もなし。得る所なきを以ての故に。菩提薩埵は、般若波羅蜜多に依るが故に心に罣礙(けいげ)なし。罣礙なきが故に、恐怖ある事なく、一切の顚倒夢想を遠離し涅槃を究竟す。三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三(あのくたらさんみやくさん)菩提(ぼだい)を得たまえり。故に知るべし、般若波羅蜜多はこれ大神咒なり。これ大明咒なり。これ無上咒なり。これ無等等咒なり。よく一切の苦を除き、真実にして虚ならず。故に般若波羅蜜多の咒を説く。すなはち咒を説いて曰く、
羯諦(ぎやてい) 羯諦(ぎやてい) 波羅羯諦(はらぎやてい) 波羅僧羯諦(はらそうぎやてい) 菩提娑婆訶(ぼじそはか)
般若心經」
……くわんじざいぼさつ ぎやうじんはんにやはらみつたじ せうけんごうんかいくう どいちさいやく……と、真言を頭蓋内で読誦(どくじゆ)しようとしたが、「觀自在菩薩」の文字を見ると最早私の視線は「觀自在菩薩」から全く離れず「觀自在菩薩」の文字を何故にかぢつと凝視したまま視線が動かなくなつたのであつた。
『觀自在菩薩……何て好い姿をした文字だ……くわんじざいぼさつ……音の響きも好い……何て美しい言葉だ……』
不図気付くと、私の目に張り付いてゐた先程来の業火が私の視界の隅に身を潜めてゐるではないか。目玉をぎよろりと出来得る限り垂直に回転させると、やつと視界の境に業火が見えるではないか。
『これも……《觀自在菩薩》……といふ文字の……御蔭か……』
私はゆつくりと目を閉ぢ、瞼が完全に閉ぢられた瞬間に姿を現す勾玉模様の光雲と業火を見つつ胸奥で何度も何度も……『觀自在菩薩』……と唱へたのであつた。
暫くすると、雪が私を見つけて私の右肩をぽんと叩いた。
――これ、どう?
雪が私に見せたのは陰陽五行説の陰陽魚太極図であつた。
――あなたの目には、今、勾玉が棲み付いてゐる筈よ。何故だかあなたの事が解つてしまふのよ。それに業火もね、うふつ。
ずばりとさう言ひのけた雪が微笑んだ顔は、何か不思議な力を秘めてゐるやうで、雪が微笑んだ瞬間、辺りは一瞬にして《幸福》に包まれてしまふかの如くに私には思へたのであつた。何ともそれは《幸福》といふ言葉がぴつたりなのだ。雪にはどうしようもない優しさがその仕種の一つ一つに宿つてゐて、それは他人を存分に癒してくれるものなのだ。何故か、雪には私の身に起きていた事が全てお見通しであつた。しかし、私はそれが何とも自然な事にしか思へなかったのだ。「以心伝心」と言ふ言葉があるが、私と雪との間には言葉を超えた互ひの理解の仕方が自然に出来上がつてゐて、私はそれを自然に受け容れてゐたのだ。雪もまた、私と同じ感覚を持つてゐたに違ひない。私と雪との間の不思議な交感は既にその時にはしつかりと確立されてゐたのさ。
――あなたには陰陽魚太極図の意味が解るわね。
私は口を開けて、
――宇宙。
と、無音で言つたのだ。
――さう、《宇宙》よ。……私、哲学を、それも西洋哲学を専攻してゐるけれども……西洋哲学の《論理》が今は虚しくて仕様がないの。……特に弁証法がね……虚しいのよ。……私の勝手な自己流の解釈だけれども……正反→合が何だか自己充足の権化のやうな気がして気色悪いのよ。西洋の哲学者……特にヘーゲルが、何故かはその理由が説明できないのだけれども……何処かNarcist(ナルシスト)に思へて仕様がないの……これぢやあ……西洋哲学専攻者としては失格ね、うふつ。
…………
…………
君も知つてゐるやうに私は、筆談するとき《つまり》と先づ書き出さないと筆が全く進まないのは知つてゐるね。この時も勿論さうだつたのさ。私は常時携帯してゐるB五版の雑記帳とPenを取り出して、雪と極極自然に筆談を始めたのであつた。
――つまり、ヘーゲルには、つまり、陰陽魚太極図の目玉模様が、つまり、陰中の陽と、つまり、陽中の陰が、つまり、無いんだよ。つまり、それで君は、つまり、ヰリアム・ブレイクを、つまり、読んでゐたんだね。
――さう……。
君にも教へておかう。雪は直感的に何故私が《つまり》を連発するのか解つたが、私の当時の思考は堂堂巡りをする外ない《渾沌》の只中にあつたのさ。或る言葉を書き出すときその言葉を頭蓋内から取り出すには、一度思考を頭蓋内で堂堂巡りを、つまり、思考を一回転させないと最初の一語が出て来ず仕舞ひだつたのだ……。
君はストークスの定理は知つてゐるね。その当時の私の思考の有様は将にストークスの定理を地で行つてゐたのさ。
…………
…………
※「ストークスの定理」
ストークスの定理はベクトルが定義されている空間内での線積分を面積分に変換する公式。考え方はガウスの定理に似ているが、ストークスの定理は次のやうな式として表される。
この中に出てくる という部分はベクトル量である。よつて次のやうな 、 、 の 三 成分で表現しなければならない。
Figure 1
これはベクトルの回転を表す量なので「rotation」を略して と書く。教科書によつては と表記しているものもある。
…………
…………
――つまり、キルケゴールも、つまり、読むと善い。つまり、陰陽魚太極図は、つまり、その後でも、つまり、善い。つまり、僕が、つまり、さつき、つまり、「キルケゴール全集」を、つまり、買つたから、つまり、僕が、つまり、読んだら、つまり、君に、つまり、あげるよ。
――有難う。でも、借りるだけね、うふつ。
――つまり、君は、つまり、知つてゐるかな、つまり、渦は、つまり、未だ数式では、つまり、物理数学的に、つまり、正確無比に記述、つまり、出来ない事を?
――えつ! 知らないわ。さうなの……。
雪は終始愉快さうであつた。即ち、それは私が愉快であつたといふ事である。ねえ、君、他者は自己の鏡だらう? 雪が愉快だといふ事は、取りも直さず私が愉快だつた事が雪に映つてゐただけの事に違ひないのさ……。
――つまり、渦の紋様が、つまり、古の昔から《存在》してゐて、つまり、しかもそれが、つまり、人類共通の、つまり、紋様だつた事は、つまり、知つてゐるね。
――ええ。アイヌの人人の衣装を見ただけでも自明の事よ。日本は勿論、唐草紋様は特に世界共通の渦紋様だわ。……それが物理数学的に未だ正確には数式で記述できないつて事が不思議でならないわ。
――つまり、其処なんだ、つまり、問題は。つまり、僕の、つまり、直感だけれども、つまり、渦を、つまり、数式とかで記述するには、つまり、∞の次元が、つまり、自在に、数式で、つまり、操れないと、つまり、記述できないと、つまり、思へて仕方がない……。
――∞の次元? ねえ、それは何の事?
――つまり、此の世は、つまり、アインシユタインの一般相対性理論のやうに、つまり、四次元多様体であるといふのが、つまり、一般的だが、ちえつ、中には五次元とも十次元とも言われてもゐるがね、つまり、其処でだ、つまり、君は、つまり、特異点を知つてゐるね。つまり、人類が、つまり、未だ渦を、つまり、物理数学的な数式で、つまり、正確には記述できない事が、つまり、この世界を、つまり、量子論と相対論とを、つまり、統一出来ない、つまり、その根本原因だと、つまり、その歪(ひずみ)が、つまり、特異点として、つまり、現れて、つまり、人類は特異点の問題を、つまり、姑息な手段で、つまり、なるべく触れずに、つまり、取り繕つて、つまり、何事か、つまり、世界が物理数学で、つまり、記述出来ると、つまり、錯覚してゐたい、つまり、穴凹だらけの地面を見て、つまり、「この土地はまつ平らな土地だねえ」と、つまり、夢幻(むげん)空(くう)花(げ)な《もの》として錯覚してゐる事を重重承知してゐるのに、つまり、それを敢へて錯覚して見せてゐるに、つまり、違ひないのさ。
――えつ? もつと解りやすくお願ひ。
――つまり、僕の直感だけれども、つまり、渦は、つまり、四次元以上、つまり、∞次元を四次元多様体に射影しただけの、つまり、∞次元多様体を四次元で表しただけの、つまり、仮の姿に、つまり、過ぎない。そして、つまり、渦は、つまり、此の世の結び目、つまり、四次元時空間を、つまり、宇宙として繫げてゐる、つまり、結節に違ひないのだ。
――つまり、銀河の事ね。パスカルぢやないけれど、二つの無限の中間点が……渦といふ事ね。そして、人間もまた……渦といふ事ね。
――さう。
――うふ。
――つまり、渦が、つまり、物理数学的に正確無比に一度(ひとたび)記述出来るといふ事は、つまり、《無限》の仮面が、つまり、剥がれる、つまり、時さ。そして、つまり、人類は、つまり、此処に至つて漸く本当の《無限》に、つまり、出遭ふのさ……
――本当の《無限》?
――つまり、人類が、つまり、無限大を、つまり、∞といふ《象徴》で、つまり、封印した事が、つまり、間違ひの元凶だつたのさ。しかし、∞といふ、つまり、象徴記号が、つまり、なかつたならば、つまり、科学の発展は、つまり、もつともつとゆつくり進んだに違ひない……つまり、ねえ、君、人類は、つまり、得体の知れぬものに、つまり、《仮面》なり、《象徴記号》なり、《名前》なりを、つまり、付けずには、つまり、堪へられぬ、つまり、生き物だらう?
――さうね……《心》がその典型ね。きつと無理ね。この私の内部に棲息する《もの》を《心》と名指さなければ、精神分析学が、つまり、フロイトが此の世に出現する事もなかつたわ。ねえ、さうでしよう。
――……。
――ねえ、うふ、《得体の知れぬ》あなたは、形而上で呼吸をしてゐる《不思議》な生き《もの》ね……。ドストエフスキイ曰く、あなたは《紙で出来た人間》の眷属なの? えへ。
――つまり、さうかもね、へつへ。つまり、《魂の渇望型》の、つまり、生き《もの》さ。さて、……その、つまり、陰陽魚太極図だけれども、つまり、僕の勝手な、つまり、解釈だけれども、つまり、東洋、つまり、特に日本は、つまり、陰陽→太極で論証する、つまり、弁証法の正反→合に比べたら、つまり、曖昧模糊とした論証だけれども、つまり、しかし、陰陽→太極で思考する方が、つまり、深遠だと思ふのだ。つまり、それは、つまり、『何故?』と訊かれても言葉に、つまり、窮するがね。つまり、だが、東洋、特に日本は、論証が曖昧模糊としたものに、つまり、ならざるを得ぬのだ。つまり、それは、つまり、陰陽魚体極図の太極図に見る、つまり、宇宙がその象徴として曖昧模糊とした、つまり、ものでとしか表現してゐないからなのさ。つまり、その点は西洋の論理とは、つまり、根本的に、つまり、思考法が違つているのさ。
――さうね。さうかもしれないわ。
――君は、つまり、今、つまり、道元と親鸞に、つまり、心酔してゐるね?
――さう……。あなたは何でもお見通しね、うふ。キルケゴールの『おそれとおののき』だつたかしら、アブラハムとその子イサクについての基督者の厳然とした覚悟と言ふのか姿勢が書かれてゐた筈だけれども……私……《論理》を超えた《言葉》を……今……渇望してゐるの。それが道元と親鸞にはあるやうな気がするのよ。だからかしら、《神》無き仏教に惹かれてしようがないの。それに、私、神が傍若無人を人間に働く『ヨブ記』が大嫌い!
――でも、つまり、ブレイクもキルケゴールも、つまり、『ヨブ記』に耽溺してゐた筈だがね……。
――さうね、基督者にとつては『ヨブ記』はある意味、信仰の《踏み絵》ね。確か、ドストエフスキイも好んでいた筈だわ。
――つまり、砂漠の地で生まれた、つまり、ユダヤ教、基督教、そして回教のいづれも、つまり、《自然》といふ名の《神》は、つまり、皆、つまり、悪意に満ちてゐなければならなかつたのさ。つまり、彼らは、つまり、それ程迄過酷な自然環境の地で生きなければならなかつたのさ。つまり、だから、砂漠で生まれた宗教史が世界を、つまり、蔽ひ尽くし、つまり、砂漠と言ふ過酷な、つまり、自然環境に堪へ得た、つまり、宗教しか、つまり、残らなかつたとも言へる。しかし、日本は、つまり、自然は、つまり、或る時は傍若無人を働くが、つまり、しかし、とても柔和なものとして、つまり、人人を包んでくれた。つまり、だから、日本では、つまり、今も、原初的とも言へるAnimism(アニミズム)の一種たる宗教の神道、つまり、八百万の神神が、つまり、今も、つまり、厳然と生き延びてゐるのさ。
――うふ。それで一神教を信仰する世界は厳格なる縦関係で《秩序立つて》ゐたのね。だから、私には虚しいだけの《論理》と《科学》が発展したのね。
――さう、つまり、《理不尽》にね……。
――さうなの、西洋の《論理》は《理不尽》なのよ。
――Credo,quia absurdum、つまり、君は、つまり、《不合理故に吾信ず》といふ、つまり、箴言を知つてゐるね。つまり、埴谷雄高を知つてゐるね? つまり、確か、テルトウリアヌスの言葉だつたと思ふが、否、つまり、その前に、つまり、君は、つまり、此の世に《秩序》があると思ふかい?
――ええ、知つてゐるわ。『死靈』は読んだわよ。そして、《秩序》は勿論あるわ。
――へつへ。つまり、此の世に、つまり、《秩序》があるのに、つまり、君は、つまり、西洋の《論理》は、つまり、《理不尽》といふ。つまり、君の《論理》に、つまり、《矛盾》がないかい?
――うふ、《矛盾》はないわよ、天邪鬼さん。だつて此の世の《秩序》がそもそも《理不尽》なのだもの、うふ。
――つまり、《真理》、若しくは《摂理》といふ名の、つまり、《神》の御業を、つまり、把握したいが為に人間は、つまり、哲学から、つまり、始まつて、そして、つまり、数学やら物理やらを、つまり、派生させ、つまり、《真理》の追究に、つまり、邁進して来たが、つまり、君はどう思ふかな、つまり、哲学者や数学者や物理学者等に、つまり、定理、公理、法則等が、つまり、此の世に厳然と、つまり、《存在》すると、つまり、彼達は言ふが、つまり、では、その、つまり、定理やら公理やら法則やらは、つまり、何故、どうして、つまり、《存在》するのかを、つまり、その根本の根本のところを彼らに尋ねると、さて、つまり、彼等は何と答えるかね?
――さうね、多分、解らないと答へるでしようね。
――つまり、其処さ。つまり、彼等は言外で、つまり、《神》の《存在》を、つまり、認めてゐるのさ。更に言へば、つまり、彼等は全て、つまり、一神教の《神》が此の世を創世したと心の深奥では、つまり、信じてゐるのさ。
――さう、それが私の言ふ《理不尽》の根本なのよ。幾何学等を発展させたエジプトやギリシア、そして零を発見したインド、更にニユートンやライプニツツに比肩する程の独自の和算を発展させた日本、これら全て多神教よ。
――つまり、ギリシアを始め、つまり、欧州に原始基督教が布教した頃は、つまり、土着の信仰も許容してゐた筈なのだが、つまり、僕の勝手な考へだけれども、つまり、欧州の土地が、つまり、石畳で蔽はれるのと機を一にして、多分、つまり、一神教の圧制が、つまり、始まつたと思ふ。つまり、石畳に蔽はれたといふ事は、つまり、それは砂漠と同じと看做せるからね。つまり、これは、つまり、人間の性(さが)だが、つまり、石畳といふ《単純明快》な生活環境が理不尽な自然の儘の環境よりも其処に《美的感覚》を見、つまり、《単純明快》と《美的感覚》は結び付いてゐる、つまり、一神教の圧制は、つまり、必然なのさ。
――一神教の圧政? あなたの言ふ通りかもしれないわ。さうかもしれないわね……。
――つまり、話は一気に飛躍するけれども、つまり、無性生殖の単細胞から有性生殖の多細胞へと、つまり、生物が、つまり、進化した事と、つまり、《単純明快》が《美的感覚》と結び付く人間の性と、つまり、密接に関係してゐると考へるのが自然なのさ。
――えつ。どうして?
――つまり、君には酷な話になるが、つまり、口を濁さず言ふけれども、つまり、君は既に、つまり、独りで立ち上がつて、つまり、何かを《決心》してゐるから、つまり、直截的に言ふよ。つまり、特に人間だが、つまり、君は、つまり、一つの卵子が作られる、つまり、過程は知つてゐるね?
――……ええ、多くの卵細胞から卵子に為れるのはたつた一つ。後は卵胞閉鎖で自ら死滅して行くのよ。それを今ではApoptosis(アポトーシス)と名付けてアポトーシスといふ現象で生物の事象が説明できるといふ事を見出した時、生物学者は何か新発見をしたかのやうにしたり顔で馬鹿みたいに《歓喜》してゐるけれども。
――つまり、君は、何故卵子は一つなのか、つまり、君の考へを、つまり、聞かせてくれないか。
――えつ! 何故卵子が一つなのか? そんな事これ迄考へもしなかつたわ。御免なさい。私、それが《自然》で当然の事だとしか思つてゐなかつたから。卵子が一つなのは何か理由でもあるの?
――つまり、これは私の独断だがね、つまり、遺伝子には《諦念》或いは《断念》といふ情報が組み込まれてゐる、つまり、私はそれを《断念遺伝子》と勝手に名付けてゐるが、つまり、生き物は《断念》、これは詩人の、つまり、石原吉郎に影響されたんだが、つまり、生物は《断念》を、つまり、《宿命》付けられてゐる。つまり、《断念》無しに、つまり、此の世の《秩序》は在りつこ無いんだ。
――《断念》……ね。うふ、一つの卵子にはそれが生き残る為に無数の死滅した卵子に為れざる卵子達の《怨念》が負はされてゐるのかしら?
――へつへ。つまり、僕の独断で言へば、つまり、その《怨念》を負つてゐる。つまり、自ら死滅した卵子達の、つまり、死の大海に、つまり、たつた一つの卵子がたゆたふ。つまり、そのたつた一つの卵子は、つまり、死滅した無数の卵子達の《怨念》を、つまり、負はなければならない《宿命》なのさ。
――すると、ねえ、……。
――精子だね。さう、つまり、受精はたつた一つの卵子とたつた一つの精子のみしか出来ない、つまり、受精はそもそも、つまり、無数の《死》をそれが《存在》する事の前提として「先験的」に背負はされてゐる。つまり、無数に女性の、つまり、膣内に放出された、つまり、精子達は女性の体内で《死滅》して行く。つまり、僕や君が、つまり、此の世に《存在》する前提に、つまり、既に無数の《死》が、つまり、厳然と《存在》してゐるのさ。
――さう……ね。……ちよつと待つて。ねえ、何故人間は全ての卵子と全ての……精子……を受精させないのかしら? 受精以前に自ら《断念》して死滅する必然なんて何処にも無い筈だわ。
――さうだね。つまり、其処なんだよ、此の世に《秩序》がある《理由》が。つまり、人間もまた、つまり、魚類や昆虫等等と、つまり、一緒に、つまり、他の生物の《餌》になる前提で、つまり、無数の受精卵が、つまり、胎内に、つまり、《断念》せず《存在》してても良い筈なんだ。しかしだ、つまり、現実はさうは為つてゐない。つまり、DNAはどの生物も、つまり、その組成物質の蛋白質は、つまり、《同じ》にも拘はらず、ある生物は、つまり、他の生物の《餌》となるために、つまり、《死滅》せず無数の受精卵が《存在》し、つまり、また、ある生物は《餌》とならないために、つまり、特に人間は、つまり、無数の《死》の大海に、つまり、たつた一つの受精卵を《存在》させる。へつへ、つまり、此の世の《秩序》は、つまり、《不合理》がそもそも「先験的」に、つまり、前提になつてゐる。
――それつて《神》の気紛れかしら。ええつと、Credo……何だつたかしら?
――Credo,quia absurdum。つまり、《不合理故に吾信ず》。
――それそれ。ねえ、《秩序》は《不合理》の異名なの?
――いや、つまり、僕が思ふに、つまり、《秩序》は《不合理》を、つまり、許容しなければならない。つまり、それは何故だと思ふ?
――さうね、《秩序》が《合理》であるとすると、う~ん、そつか、その《社会》には《合理》しか有り得ない。さうすると《主体》は《不自由》極まりないわね。
――さう。つまり、《人類》より遥かに進化してゐる、つまり、昆虫、中でも、つまり、蜂や蟻を考へてごらん。
――御免なさい。私、昆虫は余り詳しくないの。
――つまり、蟻を例にすると、つまり、蟻は大きな群れを作つて、つまり、集団で生活してゐるね。つまり、蟻は、つまり、《社会性昆虫》と言はれてゐる。ところで、つまり、君、蟻に《脳》は、つまり、在ると思ふかい?
――えつ、さうね、在るんぢやないの。
――さう、つまり、昆虫にも、つまり、《脳》はある。つまり、さうぢやなきや、つまり、此の世は、つまり、《昆虫天国》になる筈はない。それぢや、君、つまり、蟻は《思考》すると思ふかい?
――えつ、それは、う~ん、解らないわ。
――つまり、蟻が、つまり、《思考》するかどうかは、つまり、これからの研究を待たなければならないんだが、つまり、仮に蟻が《思考》するとして、つまり、蟻は血縁の社会だが、つまり、さうすると、何故、つまり、蟻の社会には、つまり、働き蟻による《内訌》や《叛乱》や《謀反》が、つまり、起こらないのだらうかね。
――う~ん、……《自由》の問題かしら?
――さうだね、つまり、《自由》の問題になるのかもしれないね。それに蟻の社会には、つまり、二割程だつたか、つまり、全く働かない蟻が、つまり、《存在》する。そこで、つまり、君、蟻の社会は途轍もなく《合理的》だよね。つまり、そこでだ、つまり、蟻のやうに途轍もなく《合理的》な、つまり、それも、つまり、《合理》をとことん突き詰めたやうな、つまり、《秩序》が《合理》そのものの《社会》で、つまり、《思考》する、つまり、《主体》の《自由》は、つまり、《許容》されると思ふかい?
――さうね。働いてゐる蟻といふ《存在》にとつては《自由》は無きに等しいわね。しかし、社会的に《合理》をとことん突き詰めると、必ず何割かは無為な、うふ、多分、それは思索しているのかもしれないけれども、その無為な蟻がゐないのであれば、それは将に《合理》を、うふ、それは誤謬の《合理》に違ひない筈だわ。無為の蟻が《存在》しない蟻の社会をして、その誤謬の《合理》を《正しき合理》として《洗脳》された全きの《洗脳社会》としかその全ての蟻が働き蟻である蟻社会は言へないわね。そんな《合理的》な社会では《主体》が皆全て《洗脳》された《自由》無き、考へただけでもぞつとする程気色悪い、寒気がする社会ね。ねえ、さうすると、《秩序》はそもそも《不合理》だとして、う~ん、《秩序》が《不合理》であればある程、《主体》の《自由》は保証されるといふ事かしら?
――つまり、それも《按配》だね。つまり、君、《渾沌》に《自由》はあると思ふかい?
――うふ、《渾沌》には《自由》しかないわ。だつて《秩序》が無いんだもの。でも、《主体》はその《渾沌》といふ《自由》に潰されるわね。《破滅》のみね、《渾沌》にあるのは。そして、うふ、《渾沌》から《秩序》が生まれる……。うふ、パスカル風に言ふと「二つの〈渾沌〉の中間点が〈秩序〉」……ね。不思議ね。
――君、その陰陽魚太極図が、つまり、《渾沌》から《秩序》が、つまり、生まれる瞬間の《象徴》だよ。つまり、「人間は思考する葦である」。つまり、人間は《渾沌》も《秩序》も、つまり、《思考》出来る《自由》がある。だけども、つまり、この《自由》が、つまり、曲者なんだよ。ねえ、君、つまり、そもそも人間は、つまり、《自由》を持ち堪へるに十分な、つまり、《存在》だと思ふかい?
――えつ、自由か……、それが私には解らないのよ。そうね、例へば、主君の死に殉じて自ら殉死する人人、例へば、一遍上人は禁じてゐたにも拘はらず一遍上人の死に殉じて入水(じゆすい)した僧や癩者達、そして《死の自由》の狂信者としてドストエフスキイの作品『悪霊』に登場するキリーロフ等等、いづれも《何か》の《殉死》だけれども……う~ん……《自由》の問題を考へると私はどうしても《死の自由》に行き着いちやうの……。どれも極端だけどもね。
ここで私は雪に「一寸」といふ合図を右手で送つて、鞄から或るMemo帳を取り出して、バクーニンが草稿を書きネチヤーエフが補足したと言はれてゐる「革命家の教義問答」を雪に読ませたのであつた。その内容はかうだ。
『革命家は既に死刑を宣告された者である。彼は個人的な興味も個人的な感情も持たない。彼自身の名さへ持たない。彼は唯一つの観念を持つてゐる。革命がそれである。彼はこの教養ある世界のあらゆる法律、あらゆる道徳律と断絶してゐる。彼がその世界の一部である如くに振舞ひながらその世界の中で生活するのは、唯只管(ひたすら)その世界をより的確に破壊するが為である。この世界の中の全ての事物は等しく彼にとつて憎むべきものでなければならない。彼は冷ややかでなければならない。彼は常に死ぬ用意をしてゐなければならない。彼は苦痛に耐へる訓練をしてゐなければならない。そして、自己内部のあらゆる感情を圧殺するため絶えず備へてゐなければならない。彼の目的を妨げる怖れのある時は名誉の感情さへ含めて、彼は唯その目的に貢献する者のみに友情を感じて差支へない。彼はより低い能力を持つた革命家達を唯消費すべきところの資本と看做さねばならない。もし同志が危難に陥つた時は、その運命は彼の有益性と、彼を救ふために必要な革命勢力の消費度によつて決定されねばならない。支配する側については、革命家はその構成員を、その個人の悪しき性質によつてではなく、革命の大義に害悪を齎す様様な度合に応じて、区分しなければならない。最も危険なものは直ちに除かれねばならない。けれども、そこには次のやうな他の部類に属する者がゐる。その或る者は、放任されたままでゐる限り、怖るべき所業を敢行し民衆を昂奮せしめる事によつて革命の利益を促進し、また或る者は、恐喝と脅迫によつて大義の目的に役に立ち利用され得るのである。自由主義者の部門は、彼等の方針に一致するかの如く彼等を信じしめ、それによつて、こちらの方針をもまた容れる事を妥協せしめながら、彼等を利用せねばならない。他の急進主義者については、多くの場合彼等を完全に破滅せしめる行動に駆り立てねばならない。そして、稀な場合、それが彼等を革命家に仕立てあげるのである。革命家の唯一の目標は手を使う労働者達の自由と幸福であるが、この事態が唯全破壊的な、全人民の革命によつてのみ成し遂げられる事を考慮して、革命家は全力を傾倒して人民がついに忍耐心を失うに至るだらうところの全ての悪行を推し進めなければならない。ロシア人は、西欧諸国において一般化してゐる革命の古典的な形態、つまり、財産に対し、また、所謂文明と道徳による伝統的な社会秩序に対して常に足踏みし、そして国家を唯別の国家によつて置き換へてゐるところの革命の古典的形態を断乎として拒絶しなければならない。ロシアの革命家は国家を、その全伝統、全制度、全階級とともに、根こそぎに廃絶しなければならない。かかるが故に、革命を醸成するGroup(グループ)は人民に対して如何なる政治的組織をも上から押し付けようと試みないであらう。未来社会の組織は、疑ひもなく、人民自体の中から生まれる。吾吾の事業は唯恐怖すべき、完璧な、全般的な、無慈悲な破壊を為す事にある。そして、この目的の為、大衆の頑固に反抗する諸部分を結合せしめるばかりでなく、ロシアにおける唯一の真実な革命家であるところの法の保護を失へる全ての者達の不屈な集団を団結せしめばならない』(埴谷雄高著「埴谷雄高ドストエフスキイ全論集」〈講談社〉参照)
…………
…………
――どう? つまり、これもまた《自由》の一形態だが……。
――ネチヤーエフが『悪霊』のピヨートル・ヴエルホーヴエンスキーのModel(モデル)だとは知つてゐたけれども「革命家の教義問答」を読むのは今日初めて……。
――つまり、《自由》は冷徹非道性を必ず備へてゐなければ、つまり、それは《自由》として取り上げるに値しない……つまり、《自由》は、つまり、そもそも《残虐非道》なものに違ひない……と思ふけれども、つまり、君は、どう思ふ?
――さうね、《自由》《平等》《友愛》を掲げ、神をその玉座から引き摺り落とし《理性》が神の玉座に座つたフランス革命が好例ね。ブレイクもフランス革命を「The French Revolution」として著してゐるけれども、人間が《自由》のど真ん中に抛り出されると如何に《愚劣》か……さうよね、あなたの言ふ通りかもしれないわ……、人間は《自由》を持ち堪へられないのかもしれないわね。フランス革命後の大粛清がその証左だわ。どうして人間は、《自由》を手にすると猜疑心が芽生えるのかしら。《自由》である事に誰も堪へられず猜疑の眼ばかりが爛爛と輝き、最後は『敵は殺せ!』を地でいって、大粛清、つまり、殺戮の連鎖が続く皮肉。きっと《自由》を人間は持ち堪へられないのだわね。
――つまり、人間はどうあつても《下等動物》でしかなく、つまり、その《宿命》から遁れられない《大馬鹿者》であるといふ自覚がなければ、つまり、結局《縄張り》争ひの坩堝に自ら進んで身を投じ、つまり、最後は無惨な《殺し合ひ》に終始する《愚劣》な生き《もの》といふ事を自覚しなければ、つまり、人間にとつて《自由》は《他者を殺す自由》に摩(す)り替はつてしまふ外ない。つまり、レーニンがネチヤーエフを認め、つまり、「革命家の教義問答」をも認めてゐた事は有名な話だけれども、つまり、レーニンが最も自身の後継者にしてはならないとしてゐたスターリンがソヴイエトを引き継ぎ、つまり、《大粛清》を行つたのも、人間が《自由》に抛り出された末に辿り着く《宿命》、つまり、《自由》に堪へ切れずに人間内部に《自然発生》する《猜疑心》の虜になるといふ《宿命》、つまり、即ち《他者を殺す自由》が人間に最も相応しい《自由》といふ事を証明してゐる。つまり、人類史をみれば、つまり、《自由》が《他者を殺す自由》でしかない事例は枚挙に暇がない。つまり、《他者を殺す自由》以外は全て排除、つまり、《自由》は《自由》に《抹殺》されてしまふ。
――其処でだけど、ねえ、《自殺する自由》はどう?
――……。
――やつぱり、あなたも考へてゐるのね、《自殺する自由》を……。
――つまり、《何か》を《生かす》以外の《自殺》はそれが殉死であらうが、つまり、《自殺》は何であれ地獄行きさ。つまり、卵子と精子の例ぢやないけれど、つまり、《一》のみ生き延びさせるための《自死》以外、つまり、《自殺》は、つまり、地獄行きだ。
――どうして《自殺》は地獄行きなの?
――つまり、例へば、僕も君も、つまり、一つの受精卵から子宮内で十月十日の間、つまり、全生物史を辿るやうに全生物に変態した末に人間に為るが、つまり、その一つの受精卵の誕生の一方で、つまり、《自死》した数多の卵子と女性の体内で死滅した数多の精子の《怨念》を、つまり、《背負はされて》此の世に誕生した訳だが、つまり、《自殺》はその死滅した、つまり、卵子達と精子達が許さず、そして、つまり、生き残つた奴が《自由》に《自殺》した場合、つまり、此の世に誕生する事無く死滅させられた卵子達と精子達が、つまり、《自殺》した奴を地獄に送るのさ。更に《生者》が《自殺》する迄食料として喰らはれて来たこれまた数多の《他の生物達》の《怨念》も含めて、つまり、あらゆる《生者》は生まれた時から《死者》の数多の《怨念》を背負つてゐるから、つまり、《自殺の自由》を《生者》が行使した場合、つまり、地獄行きは《必然》なのさ。
――それでかしら、《他者》といふ、《吾》にとつては徹頭徹尾《超越》した《存在》が《存在》するのは……。つまりね、人間は独りでは《自由》を持ち堪へられない、故に《他者》が《存在》する、つてね、うふ。
――さう、そして、つまり、未だ出現されざる未出現の《未来人》を必ず《未来》に出現させる為にも、つまり、《現在》に《生》を享けた《もの》は、つまり、与へられた《生》を全うしなければならない。つまり、その為には人間は数多の《他者》と共に、つまり、何が何でも、つまり、それが仮令不快、若しくは苦痛、若しくは虫唾が走る事態であつても、つまり、《他》と共に生きねばならない。
――ねえ、さうすると、人間は《自由》とどう関はれば良いと思ふ?
――正直言ふと、つまり、僕にはそれは解らないんだよ。つまり、《自由》の正体が阿修羅の如き《自由》だとすると……、君はどう思ふ?
――さうね、人間は分を弁(わきま)えるしかないんぢやないかしら……、うふ、私にもこの《残虐非道》な阿修羅の如き《自由》に対しての人間の振舞ひ方は解らないわね、うふ。だつて、《自由》を自在に操れるのは《神様》以外在り得ないもの。ねえ、さうでしよ、うふ。
…………
…………
君もさう思ふだらうが、雪の微笑みは何時見ても純真無垢な美しさに満ち溢れてゐたが、この時の雪の微笑みも「これぞ純真無垢の典型!」といふやうな飛び切りの美しさに包まれてゐて私は心地良かつたのである……。雪の顔には自身には解からないとは思ふが、自然に純真さが溢れ出てしまふ心の美しさが雪の笑顔には現はれてしまふのだ。これに私は惹かれたのだがね。
…………
…………
――断罪せよ。
例へば澱んだ溝川(どぶがは)の底に堆積した微生物の死骸等のへどろが腐敗して其処からMethane Gas(メタン・ガス)等がぷくりぷくりと水面に浮いてくるやうに、私の頭蓋内の深奥からぷくりぷくりと浮き上がつては私の胸奥で呟く者がゐたのは君もご存知の通りだ。
――お前自身をお前の手で断罪せよ。
これが其奴の口癖だつた。
多分、私が思ひ描いた私自身の《吾》といふ表象が時時刻刻と次次に私自身が脱皮するが如くに死んで行き、その表象の死屍累累たる遺骸が深海に降る海雪(Marine snow)のやうに私の頭蓋内の深奥に降り積もり、それがへどろとなつて腐敗Gasを発生させ、その気泡の如きものが私の意識内に浮かび上がつては破裂し、
――断罪せよ。
といふ自己告発の声になると私は勝手に考へてゐたが、雪との出会ひにより、私をしてそれを実行する時が直ぐ其処に迫つてゐる事を自覚しないわけにはいかなかつたのだ。今にして思へば、雪との出会ひは私が私自身を断罪するその《触媒》であつたのだらうとしか思へないのだつた……。
勿論、私の頭蓋内の深奥には深海生物の如き妄想の権化と化したGrotesque(グロテスク)な《異形の吾》達がうようよと棲息してゐた筈だが、其奴等も私が余りにも私自身の表象を創つては壊しを繰り返すので意識下に沈んで来た《吾》の表象どもの遺骸を喰らふのに倦み疲れ果てて仕舞つてゐたのは間違ひない……。
多分、其の時の私の頭蓋内の深奥には、私が創つた表象の死骸が堆く積み上がる一方だつたのだ。
――断罪せよ。お前がお前の手でお前自身を断罪せよ!
…………
…………
さて、私がSalonでは読書会がもう始まつてゐるのでSalonに行かうと雪に言付けして其の古本屋を出やうとすると、雪が、
――一寸待つてて。二、三冊所望の本を買つてくるから。
と、言つたので私は軽く頷き其の古本屋の出口で待つ事にしたのであつた。
外はAsphalt(アスフアルト)とConcrete(コンクリート)が発散する熱と人いきれの不快な暑気に満ちてゐて、其の中、淡い黄色を帯びた優しい白色の満月の月光が降り注ぐ、何とも名状し難い胸騒ぎを誘ふ摩訶不思議な世界へと変貌してゐた。東の夜空を見上げると美麗な満月がゆるりと昇つて、その満月は、暑気による陽炎に揺れてゐたが、私は『今夜は何人の人が誕生し、そして何人の人が亡くなるのか』等とぼんやりと生死について思ひを巡らせずにはゐられなかつたのである。満月の夜は必ずさうであつた。私にとつて月は生物の生死の間を揺れ動く弥次郎兵衛のやうな《存在》で、且、生物の生死を司るある種創造と破壊の神、シヴア神のやうな《存在》に思へたのであつた。
と、其の時ぽんと私の左肩を軽く叩き、
――お待たせ。
と、雪が声を掛けたのであつた。私は左を向いて雪の瞳を一瞥して不意に歩き出した途端、雪は私の右手首を今度は軽く握つて、
――もう、待つてよ、うふ。
と私に純真無垢な微笑を送つて寄越したのであつた。しかし、私は含羞の所為(せゐ)もあつて其のまま歩を進めたのである。
――もう、うふ。
と、雪は私の右側にぴたりと並んで歩き出したのであつた。
袖振り合ふも他生の縁。私は相変はらず伏目で歩いてゐたが、すると直ぐ様私の右手首を少し強めに握つた雪が私を握つた左手で私の歩行の進行を見事に操るので、私は内心、
――阿吽(あうん)の呼吸か……ふつ。
などと思ひながら密かに愉悦を感じざるを得なかつたのである。そして、私と雪が相並んで睦まじさうにゆつたりと二人の時間を味はひながら歩く姿を、私達の傍らを通り過ぎる人達が興味津津の好奇の目を向けてゐる。その多少悪意の籠つた視線の鋭き気配を感じながら、私は、この私達の傍らを好奇の目を向けて通り過ぎる彼らともまた他生の何処かで会つてゐる筈だと内心で哄笑しながら、
――さて、私との彼等の他生の縁(えにし)は人としてなのだらうか。
などと揶揄してみては更に内心で哄笑するのであつた。
それはまさしくゆつたりとした歩行であつた。
不意に雪を一瞥すると、雪は例の純真無垢な微笑を返すのである。雪もまたこのゆつたりとした歩行に何かしらの愉悦を感じてゐたのは間違ひない。
男女が二人相並んで歩くといふ行為は、しかし、よくよく考へてみると不思議極まりない、ある種奇蹟の出来事のやうな錯覚に陥る。偶然にも同時代に生を享け、偶然にも互ひに出会へる場所に居合はせ、互ひに何かしら惹かれあふ《もの》をお互ひに感じ、そして、互ひに見えない絆を確信し相並んで歩く……、これは互ひに出会ふべくて出会つてしまつた運命といふ必然の為せる業なのかもしれない……。
私は雪に微笑みかけ、雪もそれに応へて微笑み返す……。人の縁(えにし)とは誠に不思議である。
そして、ゆつたりとした歩行は続くのであつた。
と不意に私と他生の縁を持つた人間が、また、この瞬間に此の世を去つたのであらう、私の視界の周縁に光雲が出現し、そして、それはカルマン渦が発生するやうに二つに分かれ、私の視界全体でも左目に当たる部分では時計回りに、右目に当たる部分では反時計回りに、その二つに分かれた光雲が旋回し始めたのであつた。そのまま光雲が私の視界でぐるりと回つてゐたその時、雪を見ると、
――……また誰か亡くなつたのね……。あなたの目、何となく渦模様が浮かんでゐる気がするの……不思議ねえ……何となくあなたの異変が解つてしまふの。あなたの眼に見える渦模様をあなたは人の魂魄と看做してゐるやうだけれども……ねえ……あなたは憑依体質な人なの? 私は幽霊とか見えないから解からないのだけれども、幽霊が見えてしまう人は、それはそれで大変なことだらうとは思ふの。
私は軽く頷くと都会の人工の灯りが漏れ出て明るい夜空に目を向け、
――諸行無常。
といふ言葉を胸奥に呑み込むのであつた。すると、雪が、
――諸行無常。
と溜息混じりにぽつりと呟いたのである。私が振り返ると、雪は何とも名状し難い悲哀の籠もつた不思議な微笑を私に返したのであつた。
…………
…………
君も多分不思議に思つてゐるだらう。何故月の盈虚(えいきよ)がこれ程生物の生死、また、地震の生起に深く関はつてゐるのかを。人間で言へば新月と満月の日に出生する赤子と死に行く人間の数が他の日に比べて多いといふのは、私の思ふところ、仄かな仄かな仄かな重力の差異が人間の運命を大きく左右する、つまり、仮に《運命次元》なるものが《存在》し、重力の仄かな仄かな仄かな差異がその《運命次元》を発生させ、また消滅させる契機になつてゐるとすると、物理学者は重力の謎を考へれば考へる程迷路乃至は袋小路に入り込み、多分、生物の運命を左右し重力と相互作用する新たな粒子の《存在》を考へないと《世界》を説明出来ない筈のやうな気がするのだ。しかしだ、ねえ、君、
――へつ、重力は此の世の謎のまま人類の滅亡迄其の謎解きは出来ない。何故ならば、重力に関して主体は観測者では有り得ないのだ。
などと私は時時内心で哄笑してみるのだがね……。多分、重力は物理数学の域を超えた何やら占星術のやうな怪しげな、例へばその《値》を数式に表すと数式を書いた本人の運命が左右されるといつた超物理数学が構築出来なければ重力の謎は解けない気がする。
今のところアインシユタインがその道を開いた重力場の理論は主体とは無関係に研究が進んでゐる筈だが、また、人間は重力を簡単に一言で《重力》と片付けてゐるが、私が思ふに《重力》を構成するのは∞の量子、若しくは次元に違ひないと考へてゐる……。さうすると、当然これ迄主体は観測者といふ《特権的》な《存在》で《世界》乃至《宇宙》乃至《素粒子》を扱つて来たが、こと重力に関しては主体はその観測者といふ《特権》を剥奪されて重力といふ物理現象に飲み込まれ、翻弄される。つまり、《主体》がモルモツトのやうになる以外に重力の説明は不可能だと思ふのだ。
ねえ、君。それにしても月は不思議な《存在》だよね。ブレイクもアイルランドの詩人、イエイツも、月の盈虚を題材にOccult(オカルト)めいて幻想的な詩のやうな、思索書のやうなものを著してゐるが、月は人間を神秘に誘ふ《もの》なのかもしれないね。
多分、君も考へた事はあるだらう。もし月が《存在》してゐなかつたならば生物史はどうなつてゐたかを。まあ、それは人類が地球外の、例へば月や火星で生活するやうになれば重力乃至月がどれ程生物の生死に深く関はつてゐるのか明らかになる筈だから……。
ねえ、君、私も多分満月の日に死ぬ筈だから、左記の括弧に私の死亡した日時を記しておくれ。お願ひする。
…………
…………
(追記。此の手記の作者は某年某月某日の満月の夜が明けた午前十時四十分四十秒に態態死の直前女性の看護師を病室に呼びにやりと笑つて死去する。)
…………
…………
さて、何とも名状し難い悲哀の籠つた不思議な微笑を私に返した雪に私は優しく微笑みかけて、東の空に昇り行く満月を指差し、雪と二人、暫くその場に立ち止まつて、仄かに黄色を帯びた優しくも神秘的な月光を投げ掛ける満月を見続けてゐたのであつた。
――ねえ、月は生と死の懸け橋なのかしら……。
と雪が呟いたので私は軽く頷き雪と私の二人並んだ月光による影に目をやつた。雪もまた二人の影を見て、
――何て神秘的なんでしよう、月影は……。
とぽつりと呟いたのであつた。と不意に再び私の視界の周縁に光雲が一つ現れたかと思ふ間もなく、再びカルマン渦が二つに分裂する如く二つに分裂したその光雲は、視界の周縁で旋回を始めたのであつた。
私は雪を銀杏の街路樹の下に誘ひ、Pocket(ポケツト)から煙草を取り出して、先づは雪に勧めたのであつた。といふのも私は、雪が《男》に陵辱されてから、多分、煙草を喫むやうになつたと信じて全く疑はなかつたのである。実際、雪は私が差し出した国産煙草で最もNicotine(ニコチン)の含有量が強い煙草は頭がくらくらするからと言つて、自分の煙草を鞄から取り出して一本極極当然といつた自然な仕種で銜へたのである。
…………
…………
君は自殺してしまつたフォーク歌手、西岡経蔵さんの「プカプカ」といふ名曲を知つてゐるかな。1971(昭和46)年、西岡恭蔵さんの自作自演曲だが、Credit(クレヂツト)は、「象狂象 作詞/作曲 西岡恭蔵 唄 JASRAC作品コード072-1643-2」となつてゐるがね。
「プカプカ」の歌詞を調べればすぐに解かる事だが、私は雪の或る一面をこの「プカプカ」に出てくる女性に重ねてゐたのだ。想像するに難くないが、雪は普段は対人、特に《男》に対する無意識の恐怖心の所為で、例へば過呼吸等緊張の余り呼吸が乱れてゐた筈で、煙草の一服による深深とした深呼吸が雪を一時でも緊張を弛緩し呼吸を調へてゐたのだ。さうでなければ雪があれ程純真無垢な微笑を浮かべられる筈はない。あの時期の雪にとつて煙草は生きるのに不可欠なものだつたのさ。
一方で私だが、私にとつて煙草はソクラテスが毒杯を飲み干して理不尽な死刑を受け容れた、或いはランボーの詩の中に「毒杯を呷(あふ)る」といふやうな一節があつた気がするが、私にとつて煙草を喫むのは《生》を実感する為には必要不可欠な《毒》なのだ。私には《生》を幾分でも蔑(ないがし)ろにする《毒》無しには一時も生きられない程、既にあの時から追ひ詰められてゐたのさ。《生きる屍》として何とか私が生きてゐたのは、何をおいても煙草があつたからなのさ。飯は食はずとも煙草さへ喫めればそれで満足だつたのだ。今も病院で私は強い煙草を喫んでゐる。最早終末期の私には何も禁じる物なんかありはしない。へつ。
…………
…………
私は一本目の煙草を喫めるだけ喫めるぎりぎり迄しみつたらしく喫むと、間髪を容れず二本目を取り出し、一本目の燃えさしで二本目に火を点け、体軀全体に煙草の煙が行き渡るやうに深深と一服したのであつた。雪は私のその仕種を見ながら、
――うふ、あなたは本物のNicotine中毒ね、うふ。
と微笑みながら、私が銜へた煙草の火の強弱の変化と私の表情を交互に凝視(みつ)めるのであつた。そんな雪を何とも愛ほしく思ひながら私は私で雪に微笑み返すのであつた。勿論、この時の煙草が格別美味かつたのは申す迄もない。
――ねえ、あなたをこれ迄生かして来たのはその煙草と、それと、うふ、お酒ね。それも日本酒ね、うふ。
と正に正鵠を射た事を雪が言つたので、私は更に微笑んで軽く頷いたのである。
――ふう~う。
とまた一服する。すると私に生気が宿る不思議な快感が私の体軀全体に走る。と、また、
――ふう~う。
と一服する。その私の様が雪にはをかしくて仕様がないらしく、
――うふふふ。
と私を見ながら飛び切りの笑顔を見せるのであつた。すると、雪は偶然にも、
――煙草とお酒があなたの鎮静剤なのね。
と言つたのであつた。
…………
…………
ねえ、君。君は「鎮静剤」といふ詩を知つてゐるかな。故・高田渡も歌つてゐたがね。
「鎮静剤」
マリー・ローランサン
退屈な女より もつと哀れなのは 悲しい女です。
悲しい女より もつと哀れなのは 不幸な女です。
不幸な女より もつと哀れなのは 病気の女です。
病気の女より もつと哀れなのは 捨てられた女です。
捨てられた女より もつと哀れなのは よるべない女です。
よるべない女より もつと哀れなのは 追われた女です。
追われた女より もつと哀れなのは 死んだ女です。
死んだ女より もつと哀れなのは 忘れられた女です。
訳:堀口大學
詩集「月下の一群」より
といふ詩なんだが。自分で言ふのもなんだが、私にぴつたりの詩だね。堀口大學の訳詩の《女》を《吾》に換へると、へつ、私自身の事だぜ、へつ。
…………
…………
『鎮静剤か……』。
成程、雪の言ふ通り《死に至る病》に魅入られた私は《生》に帰属する為に一方で煙草といふ《毒》を喫んで《死》を心行く迄満喫する振りをしながらも私の内部に眠つてゐる臆病者の《吾》を無理矢理にでも揺り起こし、煙草を喫む度に《死》へと一歩近づくと思ふ事で《吾》が今生きてゐるといふ実感に直結してしまふこの倒錯した或る種の快感――これは自分でも苦笑するしかない私の悪癖なのだ――が途端に不快に変はるその瞬間の虚を衝いて、一瞬にして《死》に臆する《吾》に変容するのかもしれぬ或る種の《快楽》を味はふのであつた。さうして《死》を止揚して遮二無二《生》にしがみ付く臆病者の《吾》は煙草を喫むといふ事に対する悲哀をも煙草の煙と共に喫み込み、内心で、
――くつくつくつ。
と苦笑しながら、この《死》をこよなく愛しながらも《生》にしがみ付く臆病者の《吾》をせせら笑ひ侮蔑する事で《生》に留まる《吾》を許し、やつとの事で私はその《吾》を許容してゐるのかもしれぬのであつた。
『鎮静剤……』。
これは多分、私が《吾》を受け容れる為の不愉快極まりない《苦痛》を鎮静する《麻酔薬》なのだ。《死》へ近づきつつ《死》を意識しながら、やつとの事で《生》を実感出来る、この既に全身が《麻痺》してしまつてゐる馬鹿者である私には、自虐が快楽なのかもしれぬ。ふつ、自身を蔑み罵る事でしか《吾》を発見出来ない私つて、ねえ、君、或る種、能天気な馬鹿者で、
――勝手にしろ!
と面罵したくなるどう仕様もない生き物だらう。へつへつへつ。何しろ私の究極の目標は自意識の壊死(えし)、つまりは《吾》の徹底的なる破壊、それに尽きるのさ。其処で、
――甘つたれるな! ちやんと生きてもいないくせに!
といふ君の罵倒が聞こえるが……、其処でだ、君に質問するよ。
――ちやんと生きるつてどういふ事だい?
後後解ると思ふが、私は普通の会社員の一生分の《労働》は既にしたぜ。ふつ、その所為で今は死を待つのみの身に堕してしまつたが……。それでもちやんと生きるといふ事は解らず仕舞ひだ。そもそも私には他の生物を食料として殺戮し、それを喰らひながら生を保つだけの《価値》があつたのだらうか、と自問自答せずにはいられぬのだ。私の結論を先に言ふと、その《価値》は徹頭徹尾私には無いといふ事に尽きるね。
――人身御供(ひとみごくう)。
私の望みは私が生きる為に絶命し私に喰はれた生き物達全てに対しての生贄としての人身御供なのかもしれないと今感じてゐるよ。
ねえ、君。君は胸を張つて、
――俺はちやんと生きてゐる!
と言へるかい? もしも、
――俺はちやんと生きてゐる!
と、胸を張つて言へる能天気な御仁が此の世に《存在》してゐるならば、その御仁に会つてみたいものだ。そして、その御仁に、
――大馬鹿者が!
と罵倒する権利のある人生を私は送つたつもりだが……、これは虚しい事だね、君。もう止すよ。
…………
…………
――ふう~う。
と、また私は煙草を喫み、煙を吐き出しながら、何とも悲哀に満ちた《生》を謳歌するのであつた。
――ふう~う。
――本当に煙草が好きなのね、あなたみたいに煙草を美味しさうに吸ふ人、私、初めて見たわ。うふ、筋金入りのNicotine中毒ね、ふふ。
と、既に自身の煙草はとつくに吸ひ終はつてゐた雪は、私が煙草を喫む毎に生気が漲るやうにでも敏感に感じたのか、ほつとしたやうなにこやかな微笑みを浮かべては私を見続けてゐるのであつた。私はと言へば、この時間が楽しい故に思はず零(こぼ)れてしまつた照れ笑ひを雪に返すのであつた。さうさ、二人に会話はゐらなかつたのだ。顔の表情だけで二人には十分であつた。
…………
…………
君も知つての通り、私にとつて必要不可欠なものは煙草と日本酒と水とたつぷりと砂糖が入つた甘くて濃い珈琲、そして、本であつた。私の当時の生活費は以上に殆どを費やしてゐて、食費は日本酒と砂糖を除けば本当に僅少であつた。Instant(インスタント)食品やJunk food(ジヤンク・フード)の類は一切口にする事は無く、今もつてその味を私は知らない。
ねえ、君。私の嗜好品は全て鎮静か興奮かのどちらかを増長せずにはいられぬ代物だつたといふ事がはつきりしてゐるだらう。当時、一度思考が始まると止め処無く堂堂巡りを繰り返し《狂気》へ一気に踏み出すのを鎮静するのに煙草は必需品だつたのだ。煙草を一服し煙草の煙を吐き出すのと一緒に、私は《狂気》へ一気に驀進する思考の堂堂巡りも吐き出すのさ。そして、不図吾に返ると私の内部に独り残された吾を発見し《正気》を取り戻すのだ。古に言ふ「魂が憧(あくが)れ出る」状態が私の思考の堂堂巡りだつた。私が思考を始めると吾は唯《思考の化け物》と化して心此処に在らずといつた状態に陥つてしまふのさ。これも一種の狂気と言へば狂気に違ひないが、この思考が堂堂巡りを始めてしまふ私の悪癖は、矯正の仕様が無い持つて生まれた天稟の《狂気》だつたのかもしれぬ……。
《死》へと近づく哀惜と歓喜が入り混じつたこの屈折した感情と共に煙草を喫み、そして、私の頭蓋内で《狂気》のとぐろを巻きその《摩擦熱》で火照つた頭の《狂気》の熱を煙草の煙と一緒に吐き出し吾に返る愚行をせずには、詰まる所、私は《狂気》と《正気》の間の峻険な崖つぷちに築かれたインカ道の如きか細き境に留まる術を知らなかつたのだ。何故と言つて、私は当時、《狂気》へ投身する事は《吾》に対する敗北と考へてゐた節があつて、それは《狂気》へ行きつぱなしだと苦悩は消えるだらうがね、しかし、それでは全く破壊されずに《狂気》として残つた全きの生来の《吾》が《吾》のまま《狂気》といふ《極楽》で《存在》する事が私には許せなかつたのだ。《狂気》と《正気》とに跨り続ける事が唯一私に残された《生》の道だつたのさ。
…………
…………
其の時の朗らかに私に微笑み続ける薄化粧をした雪の美貌は満月の月光に映え神秘的で、しかもとてもとても美しかつた……。
と不意にまた一つの光雲が私の視界の周縁を旋回したのである。私は煙草によつて人心地付いたのと、また光雲が視界の周縁を廻るのを見てしまつた私を敏感に察知しそれに呼応する雪の哀しい表情が見たくなかつたので、ゆつくりと瞼を閉ぢたのであつた。瞼裡に拡がる闇の世界の周縁を数個の光雲が相変はらず離合集散しながら左に旋回するものと右に旋回するものとに分かれ、ぐるりぐるりと私の視界の周縁を廻つてゐた。
――死者達の手向けか……、それとも埴谷雄高曰く、《精神のRelay(リレー)》か……。
勿論死んで逝く者達は生者に何かしら託して死んで逝くのだらう。私の瞼裡の闇には次次と様様な表象が浮かんでは消え浮かんでは消えして、それは死者達の頭蓋内の闇に明滅したであらう数多の思念が私の瞼裡の闇に明滅してゐるのだらうかと考へながらも、
――それにしても何故私なのか?
と、疑問に思ふのであるが、しかし、一方で、
――死者共の思念を繋ぎ紡ぐのがどうやら私の使命らしい。
と、妙に納得してゐる自分を見出しては内心で苦笑するのであつた。
…………
…………
と不意に金色の仏像が瞼裡の闇の虚空に浮かび上がつたのである。
――ふう~う。
と其処で間をおくやうに煙草を一服し、もしやと思ひ私は目玉を裏返すやうに瞼を閉ぢたままぐるりと目玉を垂直に回転してみると、果たせる哉、血色に燃え立つ光背の如き業火の炎は私の内部で未だ轟轟と燃え盛つてをり、再び目玉をぐるりと回転させて元に戻すと、未だ金色の仏像――それは大日如来に思へた――が闇の中空に浮かび上がつて何やら語り掛けてゐたのであるが、未熟な私にはそれを聞き取る術が無く、静寂のみが瞼裡の闇の世界に拡がるばかりであつた。
と忽然と、
――《存在》とは何ぞや?
といふ誰とも知れぬ声が何処からともなく聞こえて来たのであつた。
――生とは何ぞや?
とまた誰とも知れぬ声が聞こえ、
――そもそも私とは何ぞや?
とまた誰とも知れぬ声が聞こえた。と、そこで忽然と金色の仏像は闇の中に消えたのである。
これが幻聴としても、どうやら彼の世に逝くには自身の《存在》論を誰しも吐露しなければならないらしい。ふつふつ。
すると突然、左右に旋回してゐた数個の光雲が無数の小さな小さな小さな光点に分裂離散し、すうつと瞼裡の闇全体に拡がつたのである。すると突然、
――何が私なのだ!
と誰とも知れぬ泣き叫ぶ声が脳裡を過つたのである。そこで漫然と瞼裡に拡がつてゐた無数の光点はその叫び声を合図に何かの輪郭を、私の瞼裡に仄かに輝きを放ち浮かび上がらせるやうに、誰とも知れぬ私とは全く面識の無い赤の他人の顔の輪郭をぼんやりと浮かび上がらせたのであつた。私は一瞬ぎよつとしたが、それも束の間で、
――うう……。
とも、
――ああ……。
とも判別し難い声為らざる奇怪な嗚咽の如き《声》を、瞼裡に浮かび上がつたその顔の持ち主が発してゐるのに気付いたのであつた。
――ふう~う。
と、この現前で起きてゐる意味を解かうとしてか、再び無意識に私は煙草を一服し、そして、意味も無く其処で瞼をゆつくりと開け、月光に映える雪の顔を凝視したのである。
――何?
と、雪は微笑んだ。が、直ぐ様私の身に起こつてゐる事を直覚した雪は、
――また……誰かが亡くなつたのね……、冥界への通り道になつてしまつてゐるあなた、大丈夫?
といふ雪に私は軽く頷き、満月がゆつくりと南天へ向かつて昇り行く奇妙に明るい夜空を見上げてから再び瞼を閉ぢたのであつた。果たせる哉、瞼裡の闇の虚空には相変はらず誰とも知れぬ面識の無い赤の他人の顔の輪郭がぼんやりと輝きを放つて浮かんでをり、私は最早声に為らざる嗚咽の如き奇妙奇天烈なその《声》にぢつと耳を澄ませるしかなかつたのであつた……。
――――ううううああああああああ~~。。
と、閉ぢられた瞼裡の闇の虚空に仄かに輝きながらその輪郭を浮かび上がらせた、私と全く面識のない赤の他人のその顔貌の持ち主の彼の人は、咆哮とも慟哭とも嗚咽とも歓喜の雄叫びとも、または断末魔の叫びとも解らぬたつた一声を心の底から思いつ切り叫びたいのであらうが、既に彼の人は恒常の《現在》といふ時間の流れに飛び乗つて、つまり、或る意味では彼の人にとつては時間が全く流れぬであらう彼の世へと既に旅立つてしまつた故に、凝固したままぴくりとも動かぬ自身、つまり、「x0=1(x>0):0より大きい数の0乗は1」のⅹたる《主体》は 零乗たる《死》といふ現象により《完全なる一》たる《存在体》へと変化した故に最早その一声すら上げられぬまま《完全なる一》たる《存在体》として凝固してしまつた自身に対して観念せざるを得ぬ事を自覚させる、永遠の黙考の中に沈潜してしまつた彼の人は、音、若しくは声為らざる音未満の、
――――ううううああああああああ~~。。
といふ《声》を発してゐるのであつた。それを例へてみれば超新星爆発後にエツクス線など通常では観測されない電磁波などを発する星の死骸に似てゐた。
――――ううううああああああああ~~。。
瞼裡の闇の虚空に仄かに浮かび上がつた彼の人は、さて、《完全なる一》たる《存在体》に封印されてその頭蓋内の闇の虚空に何を思ひつつ彼岸へ旅立つたのだらうか。彼の人は死と共に《完全なる一》たる《存在体》に己が成り果(おほ)せた事を束の間でも自覚し、歓喜したのであらうか。多分、その瞬間に彼の人は全てを悟つた筈である。だが、それでも納得できない彼の人は、
――――ううううああああああああ~~。。
と《声》ならざる《声》を発せざるを得ぬ底知れぬ哀しさの中に封印され凝固してしまつたのであらうか。私は彼の人に、
――《存在》とは何ぞや?
などと、問ふてみたが、答へは全て、
――――ううううああああああああ~~。。
であつた。多分、彼の人は既に《完全なる一》たる《存在体》から堕して腐敗といふ《完全なる一》たる《存在体》の崩壊へと歩を進めてしまつたのであらう。
――――ううううああああああああ~~。。
は、彼の人の崩壊の《音》為らざる《音》なのかもしれないかつたのだ
――――ううううああああああああ~~。。
と、不意に瞼裡の闇の虚空に仄かに浮かび上がつた彼の人の顔貌はゆらりゆらりと揺らぎ始め、すると私の視線の先に忽然とゆるりと時計回りに旋回する大渦の中心が現れたのであつた。
――これがもしや中有なのか?
私の瞼裡に仄かに浮かび上がつた彼の人の顔貌は、そこでゆるりとゆるりと渦の動きのままに旋回し始めたのであつた。
――ふう~う。
私は何故かそこで煙草を一服したのである。正直なところ、
――――ううううああああああああ~~。。
といふ《音》為らざるその《声》は悲痛極まりなく、私には煙草でも喫まなければ最早堪へられなかつたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
私はゆつくりと瞼を開け、雪の顔を見ずにはゐられなかつたのである。雪は全てを既に了解してゐたのか、にこつと私に微笑み掛け、
――存分にその苦悩を味はひ尽くしなさい。それがあなたの安寧の為になるのよ。
と、私に無言で語り掛けてゐたのであつた。
私は雪の微笑みを見てほつとしたのか、此方も軽く微笑み、再び瞼を閉ぢたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
瞼裡に仄かに輝き浮かぶ瞑目した全く面識のない赤の他人の彼の人が、ゆるりと瞼裡全体が大渦を巻き始めたときに口元が仄かに微笑んだやうに見えたのは、もしかすると私の気の所為かもしれぬが、しかし、それを見た刹那、彼の人は地獄ではなく極楽への道を許されたのだと私は思つたのだ。
――それにしてもこの瞼裡の光景は私の脳が勝手に私に見せる幻視なのか……。
と、そんな疑問も浮かぶには浮かんだが、
――へつ、幻視でも何でもいいぢやないか。
と、更に私の意識は瞼裡の影の虚空に引き込まれて行くのであつた。さう、私もまた、瞼裡の渦にそれとは知らずに巻き込まれてゐたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
それにしても中有は彼の人以外ゐないところで徹底的に孤独でなければならぬ場らしい。瞑目した彼の人は、さて、この孤独の中で何を思ふのか。既に死の直前には自身の人生全体が走馬灯の如く思ひ出された筈である。
――什麼生(そもさん)!
――説破!
と、彼の人は自己の内部に、否、魂の内部に沈潜しながら、その大いなる《死》の揺籃に揺られながら、既に《物体》と化した自己を離れ《存在自体》、若しくはカント曰く《物自体》と化して自問自答する底知れぬ黙考の黙考の黙考の深い闇の中に蹲りながら《存在》といふ得体の知れぬ何かを引つ摑んで物珍しげにまじまじと眺め味はひ、そして、その感触を魂全体で堪能してゐるのであらうか……。
――――ううううああああああああ~~。。
その証拠が瞼裡の影の闇の虚空に仄暗く浮かび上がる彼の人の顔貌の輪郭なのではないのか……と思ひながら私はまた煙草を、
――ふう~う。
と、喫むのであつた。すると、私は何やら名状し難い懊悩のやうな感覚に包まれたかと思ふと、源氏物語の世界の魂が憧(あくが)れ出るが如くに、私の自意識の一部が凄まじい苦痛と共に千切れるやうに瞼裡の闇の虚空に憧れ出たのである。私もまた其の刹那、
――――ううううああああああああ~~。。
と、呻き声に為らぬ声を私の内部で発したが、しかし、それは言ふなれば、私といふ《眼球体》――それはフランスの象徴主義の画家、オデイロン・ルドンの作品「眼は奇妙な気球のように無限に向かう」(一八八二年)のやうなものであつた筈である――がその闇の虚空へと飛翔を始めた不思議な不思議な不思議な感覚であつた。
何もかもがその闇の虚空では自在であつたのだ。私の思ふが儘、その《眼球体》と化した私は自在に虚空内を飛び回れるのである。それはそれは摩訶不思議な感覚であつた。
――――ううううああああああああ~~。。
《眼球体》と化した私は、瞑目して深い深い深い黙考の黙考の黙考の中に沈潜してしまつた彼の人にぴたりと寄り添ひ、今更ながらまじまじと彼の人の顔貌を凝視したのであつた……。
…………
…………
ねえ、君。人間とは《存在》といふ魔物に囚はれる虜囚たる事を宿命付けられた哀れな生き《もの》だね。もし仮に正覚もせずに《存在》に無頓着なそれこそ能天気な輩がゐたら、さういふ輩には哀れな微笑みを送つてやるしかないね。何故つて、さういふ輩は既に自身を馬鹿者として積極的に肯定した阿呆に違ひないからさ。先づ、自身の《存在》を全肯定出来る事自体が馬鹿の証さ。そいつ等の話を聞いてごらん。薄つぺらな内容に終始して、そのくせ小心者ときたならば、もう目も当てられないね。そういふ輩は愚劣極まりなく醜悪さ。私はそいつ等の放つ悪臭――勿論、これは幻臭だがね――に耐へられず、いつも反吐を吐いてゐたがね。
ねえ、君、そもそも《存在》とは何ぞや? 何時も、さう、睡眠中に夢を見てゐる時さへ、自身の《存在》に懐疑の眼を向けざるを得ぬ《吾》といふ《存在》はそもそも何ぞや? 吾と己に《ずれ》が生じる故に《存在》といふ変容体に《吾》が身を置けるその因になつてゐるのは当然として、さて、其処に介在する《時間》といふこれまた魔物の流れに取り残され、絶えず《現在》に身を置かざるを得ぬこの《吾》とはそもそも何ぞや? つまりは、身体の細胞Level(レベル)で考へてみると、身体を形成してゐる数十兆もの細胞群は、分裂、増殖、そしてApoptosis(アポトーシス)、つまり、自死を繰り返して何とか《吾》を存続させてゐるが、この絶えず変容する《吾》は、過去の《吾》に未練たらたらで現在の変容する未完の《吾》をどうあつても《吾》として受け容れなければならぬ宿命を背負つてゐて、もしもそれを拒否したならば《吾》は死ねない細胞たる癌細胞化するしかない哀れな《存在》でしかない……。するとだ、生物は絶えず不死たる癌細胞への憧憬を抱いてゐて、不死たる《吾》でありたいと心奥では渇望してゐるに違ひないのさ。へつ、もしかすると己を《高等動物》と平気で看做すこの人類は、一度その《存在》を断念して、ぬめぬめした《もの》に変態した海鼠(なまこ)の如き海鼠としての原形をとどめぬ《もの》が、そのまま抛つておくと再び《時間》が経つにつれて元のの形へと再び再生する、そんな《存在》を理想の《存在》、つまりは神と看做しているのかもしれぬね。近代迄は人間は神に為るといふそんな傲岸不遜な考へを断念し、また、ひた隠して来たが、現代に至つてはその恥知らずな神たらうとする邪悪な欲望を隠しもしない侮蔑すべき《存在》に為り下がつてしまつたが、しかし、それが《存在》の癌化に過ぎない事が次第に明らかになるにつれ、人間は現在無明の真つ只中に抛り出されて、唯漫然と生きてゐる――それでも「私は懸命に生きてゐる」と猛り狂う輩もあらうが、それは馬鹿のする事さ――その結果、現世利益が至上命題の如く欲望の赴くままに生き、そして漫然と死すのみの無機物――ねえ、君、無機物さへも己の消滅にぢつと堪へながら自身を我慢しながら《存在》してゐるに違ひないと思ふだらう――以下の生き物でしかない……。その挙句が過去への憧憬となつて未来は全く人間の思考の埒外に置かれる事になつてしまつたが、さて、其処で現在を見渡したところ現在が最早どん詰まりにある事に気付いて慌てて未来に思いを馳せてみると、へつ、人類は絶滅するしかない事が鮮明になつてゐて、さてさて、困つた事に往生際が極めて悪いこの人類といふ《存在》は、現在、滅亡に恐れをなして右往左往してゐるのが現状さ。
自同律の不快。人類は先づ生の根源たるこの自同律の不快に立ち戻つて、パスカルの言ふ通り、激烈なる自己憎悪から出直さなければならないと思ふが、君はどう思ふ?
倒木更新。未だ出現せざる未来人を出現させる為にも、現在生きてゐる者は必ず死ななければならぬ事を自覚して倹(つま)しく生きるのが当然だらう。へつ。文明の進歩なんぞ糞喰らへ、だ。人類は、人力以上の力で作つた《もの》は全て人の手に負へぬまやかし《もの》である事に早く気付くべきさ……。へつ。ねえ、君。一例だが、科学技術が現在のやうに発展した現代最高の文明の粋(すい)を結集して、果たして、茅葺屋根の古民家以上に自然に馴染んだ家を、つまり、朽ちるにつれてきちんと自然に帰る外ない家が作れると思ふかい? 無理だらう……へつ。
…………
…………
その時《眼球体》と化した私の意識は中有の中に飛び出し、私の瞼裡に仄かに輝き浮かぶ、誰とも知れぬ赤の他人の彼の人の顔貌を凝視したが、すると彼の人は消え入りさうな自身の横たはる身体を私の眼前に現したのであつた……。
――しゆぱつ。
雪がもう一本煙草に火を点けたやうだ。
――はあ~あ、美味しい。
私は雪のその心地良ささうな微笑んだ顔が見たくて《眼球体》の吾から瞬時に私に戻り、ゆつくりと瞼を開け、雪の顔を見たのであつた。
――うふ。私ももう一本吸つちやつた。あ~あ、何て美味しいのかしら。……どう? 死者の旅立ちは。
私はおどけた顔をして首を横に振つて見せた。
――そう。三途の川を越えた者皆、その道程は艱難辛苦に違ひないと思ふけど……そして彼岸からその先の極楽迄の道のりが辛いのは簡単に想像出来るけど……実際……さうなのね?
私は雪の問ひに軽く頷き、煙草を美味さうに喫む雪の満足げな顔につい見蕩れてしまふのであつたが、その雪の顔は、窈窕(えうてう)といふ言葉がぴつたりと来るのやうに、また、乳白色の月光が照らし出す雪の顔は、不安が失せたやうに安寧の中に置かれた弥勒菩薩のやうな美麗な美しさを醸し出していたのである。その顔の輪郭が絶妙で、これまた満月の月光に映えるのであつた。
そして、私は、雪の美貌を映す満月の光に誘はれるやうに、南天へ昇り行く仄かに蒼白いその慈愛と神秘に満ちた月光を網膜に焼き付けるやうに、満月を凝視し続けたのであつた。
『科学的には太陽光の反射光に過ぎないこの月光といふものの神秘性は……生き《もの》全てに最早そのやうにしか感じられないやうに天稟として「先験的」に具へられてしまつた《もの》なのかもしれぬ……。』
――ふう~う。
私は煙草を身体全体にその紫煙が行き渡るやうに深深とした呼吸で喫みながら暫く月光を凝視した後に、再びゆるりと瞼を閉ぢたのであつた……。
その網膜に焼き付けられたらしい月光の残像が瞼裡の闇の虚空にうらうらと浮かび上がり、あの全く面識のない赤の他人の彼の人の仄かに輝きを放つが今にもその虚空の闇の中に消え入りさうなその死体へ変化し横たわつたままの体軀が、ゆるりと渦を巻く瞼裡の闇の虚空にAurora(オーロラ)の如く残る月光のうらうらと明滅する残像に溶け入つては、己の《存在》を更に主張するやうに自身の姿の輪郭を月光の残像から分離すべく、月光の残像の明滅する周期とは明らかに違ふ周期でこれまた仄かに瞼裡の闇の虚空に明滅しながら月光の残像の中で蛍の淡い光の如くに輝くのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
私は再び瞼裡の闇の虚空の渦に飲み込まれるやうに自意識の一部が千切れ《眼球体》となる狂ほしい苦痛の呻きを胸奥で叫び、とはいへ、ひよいつと《眼球体》となつた私は渦巻く瞼裡の虚空に投身するのであつたが、最早瞼を閉ぢると自動的に眼前で渦巻く瞼裡の闇の虚空に吸い込まれてしまふのは避けようもないらしかつたのである。
それにしても、この眼前に拡がる瞼裡の渦巻く闇の虚空は一体何なのであらうか。
――中有。
とはいへ、其処が中有とは今もつて信じ難く、そして私は懐疑の眼でしかその渦巻く虚空を見られずにゐたが、しかも《眼球体》となつて瞼裡の渦巻く闇の虚空に《存在》するこの私の状態は、さて、一体何なのであらうか……。
唯、《眼球体》の私は自在であつた。例へてみれば、そのAuroraの如き月光の残像の中に飛び込めば其処は眩いばかりの光しか見えない《陽》の世界であり、一度月光の残像から飛び出ると、其処は彼の人の闇の中に消え入りさうな体軀が闇の虚空にぽつねんと浮かび上がるのが見える《陰》の世界であつた。そして、《眼球体》の私は多分月光の残像の中では陽中の陰となり、月光の残像から飛び出ると《眼球体》の私は陰中の陽となり、其処は陰陽魚太極図そつくりの構図に違ひないとしか思へなかつたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
相変はらず彼の人は声為らざる声を発し続けたままであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
『もしや、この眼前に見えてしまふ全く面識のない赤の他人の彼の人は……、もしかすると、《死》といふ、多分、恍惚に違ひないその全きな恍惚の中に陶酔してゐるのかもしれぬ……。』
と、何故かといふ理由もなく、さう私は自然と納得してゐる己を見出してはにたりと自嘲しつつ、《眼球体》と化した私は、眼前に横たはる彼の人をまじまじと凝視したのであつた。否、実のところ、さう思はずにはゐられなかつたのである。これは実際のところ私の願望の反映に過ぎぬのかもしれぬが、しかし、生き《もの》が死すれば、
――皆善し!
として、自殺を除いて全ての死した《もの》が恍惚の陶酔の中になければならないとしか、私にはその当時思へなかつたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
この絶えず彼の人から発せられてゐる音為らざる苦悶の呻き声は、もしかすると歓喜の絶頂の中で輻射されてゐる、誠に誠に慈悲深き盧(る)遮那(しやな)の輝きにも似た歓喜の雄叫びなのかもしれぬと思へなくもないのである。否、寧ろさう考へたほうが自然なやうな気がするのであつた。
自殺を除いて死すもの全て、
――――ううううああああああああ~~。。
と、此の世の摂理たるハイゼンベルクの不確性原理から解放され、此の世からおさらばした故の完全なる《一》、否、それはもしかすると色即是空たる《空》、若しくは《無》、若しくは《無限》たる己を己に見出し、歓喜の雄叫びを上げて、《吾》が生と死に祝杯を捧げてゐるに違ひない。生きてゐる間は生老病死に苛まれ、底無く出口無き苦悶の中でもがき苦しみ、やつとの事で未完の生を繋いで来たに違ひない生者達は、死してやつと安寧を手にするに違ひないのだ。ところでそれはまた死の瞬間の刹那の事でしかなく、その後の中有を経て極楽浄土へ至るこれまた空前絶後の苦悶の道程を歩一歩と這ひ蹲る(つくば)が如くに前進しなければならないのかもしれない来世といふ《未来》に向かふ、巨大な巨大な巨大な苦難の果てといふ事からも一瞬、解放されてゐるに違ひない……。と、不意に《眼球体》と化してゐた私は吾の自意識と合一してしまひ、私はゆつくりと瞼を開けてしまつたのであつた。然しながら、その時、私は雪の相貌を全く見向きもせずに、天空で皓皓と青白き淡き輝きを放つ満月を暫く凝視するしか為す術がなかつたのであつた。この一連の動作は全く無意識でした事であつた。ところが、瞼を開けても最早私の視界から彼の人の明滅する体軀の輪郭は去る事がなく、満月の輝きの中でも明瞭に見えてしまふのであつた。
――ふう~う。
と、私は煙草を一服し、月に向かつて何故か煙草の煙を吐き出したのであつた。煙草の煙で更に淡い輝きになつた月は、それはそれで何とも名状し難い風情があつた。と、不意に私の胸奥でぼそつと呟くものがあつた。
――月とすつぽん。
これは人間の思考が全く脈略なく思考する性癖を持つてゐることの一つの証左なのであった。私はその呟きを合図に、それ迄の時間の移ろひを断ち切るやうにMemo帳を取り出し、雪と再び筆談を始めたのであつた。
――つまり、自由を追い求めるならば、つまり、月とすつぽん程の、つまり、激烈な貧富の格差は、つまり、《多様性》の、つまり、現はれとして、つまり、吾吾は、つまり、それを甘受しなければならないと思ふが、つまり、君はどう思ふ?
と、全く脈絡もなく視界の彼の人を抛り出してとつさに雪に書いて見せたのであつた。満月の月光の下ではMemo帳に書いた文字ははつきりと見えるのである。すると雪は美しく微笑んで、しかし、何やら思案するやうに、
――う~む。難しい問題ね。あなたの言ふ通りなのは間違いないわ。しかしね、社会の底辺に追ひやられた人人はその《多様性》といふ《自由》を持ち堪へられないわ……、多分ね。でも……、残酷な言ひ方かもしれないけれども《自由》を尊ぶならばあなたの言ふ月とすつぽん程の格差といふ《多様性》は受け容れるしかないわね……。
と、切り出したのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
――ふう~う。
と、私は煙草を一服すると、その吸ひ殻を携帯灰皿にぽいつと投げ入れたのであつた。
――つまり、《自由》に身を委ねると、つまり、現状は、つまり、嘗ての、つまりね、Pyramid(ピラミツド)型の階級社会にすら程遠い、つまり、一握りの大富豪と、つまり、殆ど全ての貧乏人の、つまり、大地に屹立した、つまり、峻険なる山のやうな、つまり、階級社会となるのは必然だと思ふかい?
――そうね、《自由》の下ならば一世代位の期間はさういふ階級社会が続くと思ふけれども、でも……、峻険な山が風化するやうに、Pyramid型の階級社会もまた長期に亙る《自然》の近似に過ぎないのならば、多分、三世代の間位に峻厳な山からPyramid型へと階級の形が移行する筈よ、多分ね、うふ。
と、雪は私との筆談が楽しいのか愛らしい微笑みを浮かべ、次に何を私が書くのか興味津津で私の手のPen先を凝視するのであつた。
――すると、つまり、さうすると現在貧乏人は、つまり、一生貧乏人かい?
――……さうね。一握りの《成功者》を除くと殆ど全ての貧乏人は貧乏人の儘一生を終へるわね……残念ながら……。士農工商のやうなPyramid型の或る種平安な階級社会が《自然》に形作られるには最低三世代は掛かる筈よ。だつて、例へば士農工商の工の貧乏人が《職人》といふ他者と取り換へ不能な一(ひと)廉(かど)の人間になるには、最低三世代のそれはそれは血の滲むやうな大変な苦労が必要だわ……。
――それぢやね、つまり、市民といへば聞こえは良いが、つまり、単刀直入に言つて市民といふ貧乏人は、つまり、士農工商のいづれかの階級の、例へば工の《職人》に、つまり、三世代掛かつてなるんだね?
――う~ん、……さうね、多分。だつて、現在生きてゐる人類の多くは貧困に喘いでゐて、その貧困から脱出する術すら未だに見つけられずにゐるぢやない。人間が社会に寄生して生きる外ない生き《もの》で、しかもそれが《自由》の下ならば、人類の現状はそのままこの国の社会にも反映されなければならず、つまり、Fractal(フラクタル)、即ち、自己相似形として、如何なる社会も世界の縮図として表れる外ない筈だし、そして《自然》は必ずさう仕向ける筈よ。《自由》が《自由》を束縛するのよ、皮肉ね。あなたもさう思うでしよ。一握りの先進国が富を独占してゐる世界の現状が《自然》ならば、この国の社会もそれをFractalに、えへつ、つまり、《自然》に反映した世界の縮図にならなければ神はそもそも不公平だと。つまり……この国の国民の殆ども貧困に陥らないとその社会は嘘つて事ね。
雪はさう言ふと不意に満月を見上げ、
――ふう~う。
と煙草を一服したのであつた。
…………
…………
ねえ、君。社会に不満を持つのは舌足らずな思考をする青年の取り柄だが、当時の彼女もまた当然若かつたのだ。ねえ、君、私は攝願として比丘尼になつた今現在の雪の考へをもう一度聞いてみたいがね。
…………
…………
――ねえ、つまり、多様性は、つまり、さうすると、どうなる?
私は満月を見上げる雪の肩をぽんと叩き、筆談を続けたのである。
――Paradigm(パラダイム)変換が必要ね。市場原理による《自由》な資本主義にたかつて生きるならば、一握りの大富豪とその外殆ど全ての貧乏人といふ《多様》に富んだ階級構造は受け容れるしかないわね。でも、擬似かもしれないけれども封建制度の復古等等、Paradigm変換は必ず訪れるわ。峻険な山がなだらかな山へと風化するしかないやうにね。
――でも、君、つまり、峻険な山が、つまり、風化してPyramidのやうになつたとしても、つまり、その社会は活力が、つまり、減衰してゐやしないかい?
――さうね、あなたの言ふ通りね。でも、地球を《自然》の典型と見るならば、或る日突然地殻変動が起きて、Himalaya(ヒマラヤ)の山山のやうな大地に峻険と屹立する途轍もなく高い山が再び此の世に出現する筈よ。それがParadigm変換ぢやない?
と、言ふと、
――ふう~う。
と、雪は煙草を一服したのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
相変はらず私とは全く面識のない赤の他人の彼の人は、私の視界で明滅しながら音為らざる声を上げ続けてゐるのであつた。
――つまり、峻険なる富の山を築いた、つまり、大富豪は、その富の山の、つまり、途轍もない高さ故に、つまり、エベレストの頂上では生き《もの》が、つまり、生きられないやうに、つまり、大富豪もまた、つまり、富の山の頂上では、つまり、生きられないとは思はないかい?
――ふう~う。
と、雪は煙草を一喫みしながら何やら思案に耽るのであつた。
――……さうねえ……マチユピチユの遺跡のやうに……《生者》より、輿に乗つて祀られる木乃伊(みいら)と化した《死者》の人数が多い……生死の顚倒した、それこそ宗教色の強いものに変化しないと……峻険なる富の山では人間は生きられないわね……。それにしてもあなたの考へ方つて面白いのね、うふつ。
――つまり、するとだ、個人崇拝、つまり、それも死者に対する、つまり、個人崇拝といふ化け物が、つまり、此の世に跋扈し始める。つまり、さうなると、つまり、気色の悪い赤の他人である、つまり、その死んだ者に対する個人崇拝が、つまり、人間が生来持つ宗教に対する、つまり、尊崇の念と結びついて、つまり、巨大な富の山を築いた、つまり、死んだ者への個人崇拝といふ、つまり、気色の悪い尊崇が、つまり、峻険なる山型の階級社会を、つまり、何世代にも亙つて固着させ、つまり、貧乏人は末代迄も、つまり、貧乏人ぢやないかい? つまり、例へば、基督の磔刑像に、つまり、平伏す基督者達は、実のところ、つまり、教会の教皇が絶大な権力と富とを、つまり、保持してゐる事に対しても畏れてゐる、つまり、象徴として一生貧乏だつた基督の磔刑像を、つまり、教会内に安置してゐるが、つまり、しかしだ、つまり、基督者達を統べてゐるのは、つまり、絶大な権力を今も保持してゐる、つまり、教会であり、つまり、その頂点の教皇だといふ事は、つまり、周知の事実だらう?
――――ううううああああああああ~~。。
その瞬間、私の視界から去らうとしない赤の他人の彼の人がゆらりと動き、私を凝視するやうに真正面を向いたのである。そして、相も変はらずに、
――――ううううああああああああ~~。。
と、音為らざる声を瞑目しながら発し続けてゐたのである。
――不思議ねえ。ねえ、人間つて倒錯したものを好んで崇拝する生き《もの》なのかしら?
――さうだね、つまり、貧富が顚倒した基督に、つまり、象徴されるやうに、つまり、《欲望》が剥き出しのままでの、つまり、人間は、つまり、そんな己の《存在》を、つまり、認めたくないんぢやないのかな。つまり、そこに己の卑俗さが、つまり、露はになるからね。つまり、そもそも人間は自己対峙が、つまり、苦手な馬鹿な生き《もの》なのは間違ひない……。しかし、つまり、己が卑俗であるが故に、つまり、《高貴》なものを倒錯した形で崇拝せざるを得ない馬鹿な生き《もの》が、つまり、人間なのかもしれない。
――何だかまるで建築家のガウデイが重力を考慮して建築物を作り上げる為にその模型を逆様にぶら下げてみた、正にその逆様になつた建築物の模型みたいね。
――つまり、天地が倒錯したものこそ、つまり、《自然》なのかもしれないね。つまり、所詮人間は、つまり、重力からは遁れられない、つまり、哀れな生き《もの》に過ぎないからね。つまり、天を向く垂直軸の不自然さに、つまり、気付いたガウデイは、つまり、天地が顚倒した建築物を、つまり、重力に《自然》な形の《もの》として、つまり、建物を逆様にぶら下げてみた……。つまり……天地の逆転の中に、つまり、或る真実が隠されてゐるのかもしれない……。つまり、人間はあらゆるものに対して、つまり、それが《剥き出し》のままだと、つまり、自然と嫌悪するやうに、つまり、創られてゐるのかもしれないね。
私は再び煙草を一本取り出し、それに火を点け一服したのであつた。
――ふう~う。
――木つて不思議ねえ。
と、雪がぽつりと呟いた。
私は雪がぽつりと呟いたその一言に全く同意見であつた。私と雪は二人で煙草を、
――ふう~う。
と一服しながら互ひの顔を見合い、そして互ひににこりと微笑んだのであつた。
――ねえ、君。つまり、アメリカの杉の仲間の、つまり、巨大セコイアといふ、つまり、巨樹を知つてゐるかい?
雪は私のMemo帳を覗き込むと、
――ええ、もう何千年も生きて百メートルにならうといふ木でしよう。それがどうしたの?
――ねえ、つまり、毛細管現象は知つてゐるかい?
――ええ、知つているわ。それで?
――つまり、毛細管現象や葉からの、つまり、水分の蒸発による木の内外の圧力差など、つまり、木が水を吸ひ上げるのは、つまり、科学的な説明では数十メートルが限界なんだ。つまり、しかし、巨大セコイアに限らず、つまり、木は巨樹になると数十メートル以上に迄、つまり、成長する。何故だと思ふ?
――うふつ、木の《気》かしら、えへつ。
――ふむ、さうかもしれない。つまり、僕が思ふに木は、つまり、維管束から幹迄全て、つまり、螺旋状の仕組みなんぢやないかと思ふんだ。つまり、一本の木は渦巻く《気》の中心で、つまり、その目に見えない摩訶不思議な力で、つまり、科学的な常識を超えて垂直に地に屹立する。ねえ、君。つまり、先に言つたが、つまり、科学はまだ渦を正確には説明出来ない。つまり、円運動をやつと直線運動に変換するストークスの定理止まりなんだ。つまり、人間は未だ螺旋の何たるかを、つまり、知らない。つまり、木は人間の知を超えてしまつてゐる。つまり、また渦の問題になつたね、へつ。
私は雪の何とも不思議さうな顔を見て微笑み更に続けたのであつた。
――ねえ、君。つまり、江戸の町が《の》の字といふ、つまり、《渦》を巻いてゐるのは知つてゐるね?
――ええ、山手線がその好例よ。
――つまり、人間が《水》の亜種で、日つ、此の世が右手系ならば、つまり、《の》の字の渦は天から《気》が絶えず降り注ぐ回転の方向をしてゐる。つまり、低気圧の渦が上昇気流の渦ならば、つまり、《の》の字の渦は、言ふなれば下降気流の高気圧の回転方向を示してゐる。つまり、さうすると、江戸の町は絶えず天からの目に見えぬ加護を受けてゐたのさ。そこでだ、つまり、仮に江戸時代のPyramid型の階級社会が、とぐろを巻く渦状の階級社会でもあると強引に看做してしまふならば、つまり、天下無敵の階級社会だつたに違ひない筈なのだ。
――ふう~う。
と私は煙草を一喫みした。
――ねえ、江戸時代の人人は現代人より創造的で豊かな暮らしをしてゐたのかもしれないわね。すると、《自由》の御旗の下の現代の一握りの大富豪と殆ど全ての貧乏人といふ峻険なる山型の階級社会は、うふつ、息苦しいわね。
――ふう~う。
私は煙草をまた一喫みしながら更なる思案に耽るのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
と、その時、私の視界に張り付いた彼の人の瞑目した顔は相変はらず私に正面を向けて音為らざる声を唸り上げながら何やら不気味にさへ見える微笑をちらりと浮かべ、忽然とその大口を開けたのであつた。
…………
…………
それにしても死は物全てに平等に訪れるが、さて、例へば視点を変へて速度をベクトルⅴで表した
の時間Δtの極限値、つまり、零――ねえ、君、この数式は考へやうによつては物凄く《死》を記号で観念化した代物だと思はないかい? へつ――と看做すと《死者》はベクトルΔⅹといふ∞の速度で動いてゐると看做せるぢやないか。主体が《観測者》でしかゐられぬ現代において、主体はどんなに足掻いても《世界=外=存在》とハイデガー風に看做せば、物理学とはそもそも主体が世界=内に《存在》しない《死》の学問ぢやないのかね? ふつ。さて、そこで《死》も物理法則に従ふならば《死者》はアインシユタインの相対論から此の世のものは《死》も含めて、その極限値として光速度を超えられないとすると《死者》は光速度で動いてゐる事になる。……今、不図思つたのだが∞とは光の光速度の事で《死》の異名なのかもしれないね……。そして、へつ、光が美しいものならば《死》もまた美しいものに違ひない。ふつ、私ももう直ぐ光といふ美しい《死》へ旅立つがね、へつ。ちえつ、まあ、私の事は置いておいて、速度を時間で微分すると加速度が出現する事自体、《観測者》たる主体の日本刀の如く切れ味鋭くも美しい論理といふ刃物を無闇矢鱈に振り回しているとしか見えないのだが、この私の論法で行くと加速度とは差し詰め《霊魂》の動きを表現したものに違ひないね。その時、私の視界に張り付いた彼の人の《魂》も、
――――ううううああああああああ~~。
と音為らざる声を唸り上げながら彼方此方に彷徨してゐたに違ひない。《死》の学問たる物理学が此の世を巧く表してゐるならば、私の視界に張り付いた私と全く赤の他人の彼の人が蛍の如く私の視界内で渦巻きながら明滅してゐたのは、物理学的に見て正鵠を射てゐたのだ。つまり、《死者》とその《魂》は《光》に変化(へんげ)した何物かなのだ。つまり、光は電磁波の一種なのだから《死者》とその《魂》は各人固有の波長をもつた電磁波の一種なのかもしれない……。まあ、それはそれとして、上下左右の知れぬ何処の方角に向かつて私の視界に張り付いた彼の人は浄土へ向かつてゐたのかと考へられもするが、西方浄土といふ言葉があるから差し詰め《西方》へ向け出立したに違ひないのかもしれない……。さて、重さあるものは相対論より決して光速度には至れないが、《死者》に変化したものは《重さ》から《解脱》して、さて、此の世の物理法則の束縛から逸脱してしまふ何物なのかなのだ。其処で出会うのが多分無限大の∞なのだ。私も直ぐに∞に出会へるぜ……へつ。
…………
…………
――ねえ、この銀杏も《気》の渦を巻いて、私たちを今その渦に巻き込んでゐるのかしら? ふう~う。
と、雪が私たちが筆談をしてゐた木蔭をつくつてゐる銀杏を撫で擦り、煙草を一服しながらまた呟いたのであつた。
――ねえ、つまり、死後も階級は、つまり、《存在》するのだらうか? ふう~う。
と、私も煙草を一服しながら雪に訊ねたのであつた。
――勿論、極楽浄土といふんだから当然あるでしよう。でも、……彼の世に階級があつたとしても彼の世のもの全て自己充足して、それこそ極楽の境地にゐるから……階級なんて考へがそもそも無意味なんぢやないかしら。
――すると、つまり、《光》は自己充足した、つまり、自身に全きに充足してしまつて自己に満ち足りた、つまり、至高の完全に自己同一した、つまり、自同律の快楽の極致に安住する《存在》なのかな?
――うふ。私、物理学にはそんなに詳しくないから何とも言へないけれど、でも……此の世の全ては《存在》しただけで既に自己に不満足な《存在》として《存在》する外ないんぢやないかしら……。ぢやないと《時間》は移ろはないんぢやない? 《光》もそれは免れないと思ふけれど、どう?
雪は舗装道路を走る自動車が通る度に巻き起こる風に揺れる銀杏の葉葉に目をやりながら訊ねたのであつた。私は仄かに微笑んで、
――ねえ、つまり、《光》が此の世と彼の世の、つまり、此の世と彼の世の間隙を縫ふ、つまり、代物だと看做すと、ねえ、君、つまり、《光》は此の世の法則にも従ふが、一方、彼の世の法則にも、つまり、従つてゐるんぢやないかと私は思ふんだが、どう思ふ? つまり、《光》が此の世と彼の世の懸け橋になつてゐるんぢやないかと思ふんだけれども……、どう思ふ?
雪は風に揺らめく銀杏の葉葉を見つめながら、否、葉葉から零れる満月の明かりを見つめながら、
――さうね……、あなたの言ふ通り《光》が此の世の限界速度だとしたならば……、うふつ、《光》はもしかすると死者達が彼の世へ出立する為の跳躍台なのかもしれないわね、うふつ。
銀杏の葉葉から零れる月光の斑な明かりが雪の面に奇妙に美しい不思議な陰影を与へて雪の面で揺れてゐた。
――彼の世への跳躍台? ねえ、君、つまり、それは面白い。つまり、此の世の物理法則に従ふならば、つまり、《光》を跳躍台にして死者が彼の世へ跳躍しても、相対論に従へばそれでも光速度を超える事は不可能だ……ふむ。
と、私は思案に耽り始めたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
ゆつくりとゆつくりと時計回りに彼の人は渦巻きながらも、面は私に向けたまま私の視界の中で相も変はらず仄かに明滅してゐたのであつた。この視界に張り付いた彼の人もまた、《光》を跳躍台にして彼の世へ出立したのだらうか……。不意に月光の明かりが見たくなつて、私は頭を擡げ満月に見入つたのであつた。この月光も彼の世への跳躍台なのか……等等つらつらと考へながら私はゆつくりと瞼を閉ぢて暫く黙想に耽つたのであつた。
――ふう~う。
その時間は私と雪との間には互ひに煙草を喫む息の音がするのみで、互ひに《生》と《死》について黙想してゐるのが以心伝心で解り合つてしまふといふ不思議な、それでゐてとても心地良い沈黙の時間が流れるばかりであつた。
――ふう~う。ねえ、もう行かなきや駄目ぢやないの?
と、雪が二人の間に流れてゐた心地良い沈黙を破つて、さう私に訊ねたのであつた。私はゆつくりと瞼を開けてこくりと頷くとMemo帳を閉ぢ、煙草を最後に一喫みした後、携帯灰皿に煙草をぽいつと投げ入れ、徐に歩を進めたのであつた。
――もう、待つて。
と、雪は小走りに私の右側に肩を並べ、そつと私の右手首を軽く握つたのであつた。私は当然の事、伏目で歩きながらも、しかし、《生》と《死》、そして《光》といふ彼の世への跳躍台といふ観念に捉へられたまま思考の堂堂巡りを始めてしまつてゐたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
歩道は会社帰りの人や学生等で大分混雑してゐたが、私と雪は肩を並べてその人波に流されるままに歩き始めたのであつた。しかし、伏目で歩く外なかつた私はそれらの雑踏の足しか見なかつたのである。雪も何か考へ込んでゐるやうで暫くは黙つてゐた。と、不意に再び光雲が私の視界に飛び込んで来たのであつた。その光雲もまた私の視界の周縁を時計回りにぐるりと一回りすると、不意に消えたのであつた。と、その刹那、私の視界の中の赤の他人の彼の人は、それ迄ばつくりと開けてゐた大口を閉ぢ、その面を彼方の方へくるりと向け、彼の人はゆつくりとゆつくりと旋回しながら虚空の何処かへ飛翔を始めたのである。
――――ううううああああああああ~~。。
彼の人は相変はらず声為らざる音を唸り上げてゐた。
――《生者》と《死者》と《光》といふ跳躍台か……。
私の思考は出口無き袋小路に迷ひ込んでゐた。
『《存在》とは《生者》ばかりの《もの》ではなく……《死者》もまた《存在》する……か……さて……《生者》から《死者》へと三途の川を渡つた《もの》は……さて……中有で苦悶しながら《死者》の頭蓋内の闇で《生》の時代が走馬燈の如く何度も何度も駆け巡る中……さて……《死者》は自ら《生者》であつた頃の《吾》を弾劾するのであらうか……ふつ……《光》といふ彼の世への跳躍台に……さて……《死者》の何割が乗れるのであらうか……《死者》もまた《存在》といふ《もの》であつた以上……それは必ず《吾》によつて弾劾される《生》を送つた筈だ……ふつ……ふつふつふつ……《もの》は全知全能の《神》ではないのだから……《吾》は必ず《吾》に弾劾される筈だ……しかし……《死者》の頭蓋内の闇が……《死者》にとつて既に《光》の世界に……つまり……《闇即ち光》と……《生者》が闇に見えるものが《光》と認識される以外に《死者》にとつて為す術がないとすると……ちえつ……例へばそもそも《死者》の頭蓋内の闇が、即ち死んだ《もの》にとつて《光》でしかないとしたならば、その《光》とは何なのだ!』
――――ううううああああああああ~~。。
私は私の視界に張り付いた彼の人を凝視するばかりであつた。最早私の自意識から《意識》が千切れて苦悶の末に私の意識が《眼球体》となる事はなかつたが、私は彼の人の顔貌を凝視しては、
――貴様は既に光か!
と、詰問を投げ掛けるのであつた。
『《死者》が既に《光》の世界の住人ならばだ……地獄もまた《光》の世界なのか……《光》にも陰陽があつて陰は地獄……陽は浄土なのか……ふつ……さうなら……ちえつ、そもそも《光》が進むとは自由落下と同じ事なのか……さうすると……自由落下を飛翔と感じるか……奈落への落下と感じるかは本人の意識次第ぢやないか……《吾》が《吾》を弾劾して……ふつ……後は閻魔大王に身を委ねるのみ……ちえつ……馬鹿らしい……《吾》は徹頭徹尾《吾》によつて弾劾し尽くされなければならぬ! ……さて……光速度が今のところ有限であるといふ事は……此の世……即ち此の宇宙が有限の《閉ぢた》宇宙である事のなによりの証左ではないのか……現在考へられてゐる此の膨脹宇宙が無限大に向かつて膨脹してゐるとすると……光速度も……もしかすると定数なんぞではなく無限大の速度に向かつて加速してゐるのかもしれないぢやないか……特異点……例へば一割る零は無限大に向かつて発散する……また、Black holeの中にも特異点が《存在》する……さうか! この宇宙にBlack holeが蒸発せずに《存在》する限りにおいてのみ《光》は《存在》するのではないか……特異点では因果律は破綻する……ふむ……此の天の川銀河の中心にあると言はれてゐる巨大Black hole……吾吾生物はこの因果律が破綻してゐる特異点の周縁にへばり付いて漸く漸く辛うじて《存在》する……つまり際どい因果律の下に《存在》する……ふむ……はて……もしかすると特異点、若しくはBlack holeが《存在》する限りにおいてしか吾吾も《存在》しない……つまり特異点とは《神》の異名ではないのか!』
『もしかすると……物体が《存在》するとその内部に特異点が隠されているのかも知れぬ……特異点を覆ひ包む形でしか《もの》皆全て《存在》出来ぬとしたなら……因果律も自同律も絶えず破綻の危機に瀕してゐるのかもしれぬ……自同律の不快……これは《存在》の罠でもあり…《存在》を《存在》たらしめてゐる秘儀なのかも知れぬ……すると……中有へ出立した《死者》は自身を徹底的に……ふつ……それは底無しに違ひないが……弾劾する宿命を負つてゐるに違ひない……弾劾に弾劾を重ねた末に残つた自身の残滓を更に鞭打つて弾劾する宿命……此の世に《存在》してしまつた《もの》全てが負つてゐるこの宿命を貫徹した《もの》のみ……未だ未出現の《存在》に出現を促す権利……其処に《魂》……若しくは《精神》のRelayが辛うじて辛うじて行はれるか? ……ふつ……《魂》……若しくは《精神》のRelayは……しかし……必ず行はなければならぬのかもしれぬ……此の世に一度《存在》してしまつた《もの》は……先達の《魂》……若しくは《精神》を受け取つた上で辛うじて……《存在》に堪へられるのかもしれぬ……未知なる《もの》への変容……此の世に《存在》してしまつた《もの》は《死》を受容し……未来に出現する《もの》へその席を譲る……其処に因縁は生じるのか? ……《死》によつて因果律は破綻するのか? ……しかし……破綻した因縁は再び別の此の世に出現してしまつた《もの》に託されるのか? さうだとして……ふつ……不連続の連続性……矛盾は《存在》した《もの》には必然のものだが……矛盾を抱へ込まざるを得ない《存在》してしまつた《もの》は……しかし……自己を責め苛む事で……もしかすると馬鹿げた自己慰撫をしてゐるだけかもしれぬではないか……自同律の不快と言ひながら実際のところ其処でこの上ない自己愛撫といふ悦楽を味はつてゐるのかもしれぬ……自虐が快楽へと変容してしまつたならば……最早その自己内部に引き籠つて外界に一歩たりとも出ない……自己憎悪が最高の自慰行為……か……へつ』
――――ううううああああああああ~~。。
『彼の人も今中有で自己に対して弾劾に弾劾を重ねて倒錯した至高の悦楽の境地にゐるのか……この悦楽はまた……地獄の責苦に等しいか……極限……苦悩と快楽の境に……《死者》は辛うじて佇立し……其処で杳として知れぬ漠たる自身といふ茫洋なる面(おもて)と全的に対峙するか……自身が自身によつて滅び尽くされる懊悩を味はひ尽くす以外……《吾》は《吾》を脱皮出来ぬかもしれぬ……《吾》以外の何かへの変容……幽冥への出立……は……《吾》が《吾》であつてはならぬのか……解脱……か……《死》してのみ《吾》が《吾》を超克するこの《存在》め! ……《存在》よ……呪はれるがよい! ……へつ……へつへつへつ……《吾》が《吾》を呪縛するだけぢやないか……だが……しかし……《存在》する《もの》……この《吾》から遁れられぬ!』
――――ううううああああああああ~~。。
『それでも……《吾》は《吾》を超克しようともがき続ける……しか……ない……へつ……何とも不自由極まりない! ……そして《死》からも遁れられぬ……《存在》とは何と呪はれた《存在》なのだ! へつ! と自身の《存在》を嘲笑つたところで、やはり《吾》は《存在》する……くつくつくつ……そもそも《吾》は《吾》である事を望んでゐるのか? ……《吾》……この面妖なる《もの》……ちえつ……心臓は相変はらず鼓動してゐるぜ!』
『……ふむ……常に伸縮せずにはゐられぬ……否……鼓動するように命ぜられてゐるこの心臓は……真の自身を知つてゐるのか……へつ……真の自身て何だ? まあよい……しかし絶えずその姿を変容させるこの心臓は……その鼓動を停止した時に初めて己の何たるかを知るのか……それ迄は絶えざる変容を強要される……哀れなる哉……吾が心の臓! ……動く事がそもそも《吾》を《吾》為らざる《もの》へと動かす原動力ではないか……若しくは時が移ろふ事がそもそも《吾》を《吾》為らざる《もの》へと誘ふ魔手なのではないか……ちえつ……下らぬ……そもそも《吾》が《吾》と呼んでゐる《もの》は《吾》には為り得るか……《吾》は無数の《異形の吾》の《存在》を前にして《吾》に戸惑ふ……か……《吾》の異形は無数に《存在》しやがる……けつけつけつ……例へばこの《吾》が意識すればたちどころに全て実現する魔法を手にしたとして……満ち足りるのは最初の一瞬だけに決まつてる……寝てゐるだけで全てが実現してしまふ世界なんぞ直ぐに飽き飽きするに決まつてゐる……謂はば《吾》は脳のみの《存在体》……つまり……《脳体》へと変容してしまふのさ……それは植物状態の人間と何も変はらぬ……すると《吾》は《吾》の《存在》を滅する事を願ひ出す外なく、否、どうあつてもこの《吾》なる《存在》の抹殺を成し遂げるところの宿願をたちどころに遂げて此の世から消える……意識の窮極の願ひは自ら滅する事に行き着くのが道理さ……しかし……《脳体》は《存在》か……』
…………
…………
ねえ、君、不思議だね。道行く人人は私の視界にその足下の《存在》を残し、その殆どの者とは今後永劫に出会ふ事はない筈さ。袖振り合ふも他生の縁とはいひ条、今生ではこの道行く人人の殆どと、最早行き交ふ事は未来永劫ある筈もない。この見知らぬ者だらけが《存在》する此の世の不思議。ところが、これら見知らぬ者達も顔を持つてゐる。それぞれが《考へる》人間として今生に面をもつて《存在》する。そして、彼等もまた《吾》以外の《吾》にならうと懊悩し、もがき苦しみ《存在》する。不思議極まりないね。全ての《生者》は未完成の《存在》としてしか此の世にゐられぬ。不思議だね。しかも《死》がその完成形といふ訳でもない。全ては謎のまま滅する。此の世は謎だらけぢやないか。物質の窮極の根源から大宇宙迄、謎、謎、謎、謎、謎だらけだ。ねえ、君、《存在》がそれぞれ特異点を隠し持つてゐるとしたなら、ふつふつ、僕は実際に《存在》たる《もの》はそれ自体矛盾である特異点を必ずその内部に隠し持つてゐると看做してゐるがね、しかも、その特異点は無数の《面》を持つて此の世に《存在》してゐる。人間の《面》は特異点の顔貌のひとつに違ひないね。へつ。特異点だからこそ無数の《面》を持ち、へつへつ、実際此の世に《存在》する《もの》全て己の内界を一度でも覗き込めば、其処に無数の《異形の吾》が棲息してゐる不気味さに驚愕する筈だがね、そして、《存在》たる《もの》は全て特異点を、無数の《異形の吾》の《面》として持ち得るのさ。己にもまた特異点が隠されてゐる筈さ。だから、此の世の謎に堪へ得るのさ。へつ、此の世の謎の探究者達は此の世の謎を《論理》の網で搦(から)め取らうと手練手管の限りを尽くしてゐるが、へつ、謎はその論理の網の目をひよいつと摺り抜ける。だから論理の言説は何か《ずれ》てゐて誤謬の塊のやうな自己満足此処に至れりといつた《形骸》にしか感じられない。ねえ、君、そもそも論理は謎を容れる容器足り得るのかね。どうも私には謎が論理を容れる容器に思へて仕方がない……。謎がその尻尾をちらりとでも現はすと論理はそれだけで右往左往し、
――新発見だ!
と喜び勇んで論理は、その触手を伸ばせるだけ伸ばして何とか謎のその《面》を搦め取るが、へつ、謎はといふと既にその《面》を変へて、気が向いたらまたちらりと別の《面》を現はす。多分、論理は、特異点と渦とを、真正面から徹頭徹尾論理的に記述出来ない内は、謎がちらりと現はす《面》に振り回されつぱなしさ。だから尚更《存在》は特異点を隠し持つてゐると看做さざるを得ず、そして、渦を巻いてゐるに違ひない。私にはどうしてもさう思はれて仕方がないのさ。論理自体が渦を巻かない限り、謎は謎のまま論理を嘲笑つてゐるぜ、へつ。
…………
…………
不意に私の視界は真つ暗になつた。私と雪は神社兼公園となつてゐる鎮守の森の蔭の中に飛び込んだのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
彼の人は鎮守の森の蔭に入つて、私の視界が真つ暗になつた途端、その輝きを増したのであつた。街燈が灯つてゐる場所迄の数十秒の間、この歩道を歩く人波は皆、闇の中に消え、その《存在》の気配のみを際立たせて自らの《存在》を《他》に知らしめる外なかつたのである。闇に埋もれた《存在》。途端に何か得体の知れぬ《もの》の気配が蠢き出す闇の中、私は何とも名状し難い心地良さを感じてゐた。私は、それ迄内部に息を潜めて蹲つてゐた内部の《吾》が、ゆつくりと頭を擡げ正面を見据ゑたやうに、この闇を見据ゑたのであつた。前方数十メートル先の街燈から漏れる光で幽かに照らされた人波の群れが其処に動いてゐた以外、全ては闇であつた。見知らぬ他人の顔が闇に埋もれて見えぬ事の心地良さは、私にとつては格別であつた。それは闇の中で自身の《面》から解放された奇妙な歓喜に満ちた、とはいへ、
――《吾》は何処? 《吾》は何処?
と突然盲(めし)ひた人がそれ迄目の前で見えてゐた《もの》を見失つて手探りで《もの》、若しくはそれは《吾》かもしれぬが、その《もの》を探す不安にも満ちた、さもなくば、《他》を《敵》と看做して、ひたすら自己防衛に身を窮する以外ない哀れな自身の身の上を噛み締めなければならぬ、何とも名状し難い屈辱感に満ちた、解放と不安と緊迫とが奇妙に入り混じつた不思議な時空間であつた。闇の中では人の山がのつそりと動いてゐた。それは再び視覚で自身を認識出来る光の下への遁走なのか? 否、それは自己が闇と溶け合つて兆す《無限》といふ観念と自身が全的に対峙しなければならぬ恐怖からの遁走といふべきものであつたに違ひない。若しくは、それは自意識が闇に溶けてしまひ、さうすると最早、再び自己なる《もの》が再構築出来ぬのではないかといふ不安からの遁走に違ひなかつたのであつた。闇の中の人波は等しく皆怯へてゐるやうに私には感じられたのである。その感覚が何とも私には心地良かつたのであつた……。何故かと言へば、闇の中では皆須く闇に《存在》を溶暗する外ないその《存在》の有様が、何やら複素数の虚数部が肥大化に肥大化を重ねて、虚数のみが闇といふ時空間に溢れんばかりに自己増殖をする、つまり、最早《吾》が《吾》である根拠を見失つて茫然とする外ない、その哀れな《吾》に縋り付く《存在》の醜さが不意に露はになるその瞬間の《快楽》を、《存在》たる《もの》はそれが何であれその《快楽》を味はひ尽くさずにはをれぬ阿片の如き《もの》を《吾》に見出してしまふ、即ち、《吾》が《一》者から解放される、若しくは《無限》に出会ふ《快楽》が堪らないに違ひないのであつた。
この闇と通じた何処かの遠くの闇の中で己の巨大な巨大な重力場を持ち切れずに《他》に変容すべく絶えず《他》の物体を取り込まずにはゐられず、更に更に肥大化する己の重力場に己自身がその重力で圧し潰され軋み行くBlack holeのその中心部の、自己である事に堪へ切れずに発され伝播する断末魔のやうな、しかし、自己の宿命に敢然と背き、自らに叛旗を翻し、そこで上げられるBlack hole自身の勝鬨のやうな、さもなくば自己が闇に溶暗する事で肥大化に肥大化を続けざるを得ぬ自己の宿命に抗すべく、何かへの変容を渇望せずにはゐられない自己なるものへの不信感が渦巻くやうな闇に一歩足を踏み入れると、闇の中では自己が自己である事を保留される不思議な状態に置かれる事に一時も我慢がならず、自己を自己として確定する光の《存在》を渇望する女女しい自己をぢつと我慢しそれを噛み締めるしかない闇の中で、《存在》は、「吾、吾為らざる吾へ」と独りごちて自己に蹲る不愉快を振り払ふべく自己の内部ですつくと立ち上がるべきなのだ。自己の溶暗を誘ふ闇と自己が自己であるべきといふ鬩ぎ合ひ。闇の中では《存在》に潜む特異点が己の顔を求めて蠢き始めるのだ。それ迄光の下では顔といふ象徴によつて封印されてゐた特異点が、その封印を解かれて解き放たれる。闇の中では何処も彼処も《存在》の本性といふ名の特異点が剥き出しになり、その大口を開け牙を剥き出しにする。この欲望の渦巻く闇、そして、《存在》の匿名性が奔流となつて渦巻く闇。私も人の子である。闇に一歩足を踏み入れると闇の中ではこの本性といふ名の阿修羅の如き特異点の渦巻く奔流に一瞬怯むが、それ以上に感じられる解放感が私には心地良かつたのである。私の内部に隠されてあつた特異点もまた、その毒毒しい牙を剥き出しにするのだ。無限大へ発散せずにはゐられぬ特異点を《存在》はその内部に秘めてゐる故に、闇が誘ふ《無限》と感応するに違ひない。しかし、一方では私は、闇が誘ふ《無限》を怖がつてぢつと内部で蹲り頑なに自身を保身する事に執着する自身を発見するのであるが、しかし、もう一方では、きつと目を見開き、眼前の闇に対峙し《無限》を持ち切らうとその場に屹立する自身もまた内部で見出すのであつた。とはいへ、《無限》は《無限》に対峙する事は決してなく、《無限》と《無限》は一つに重なり合ひ渾然一体となつて巨大な巨大な巨大な一つの《無限》が出現するのみである。私はこの闇の中で《無限》に溶暗し、私の内部に秘められてゐるであらう阿修羅の如き特異点がその頭をむくりと擡げ、何やら思案に耽り、闇の中でその《存在》の姿形を留保されてゐる森羅万象に思ひを馳せ、その《物自体》の影にでも触れようと企んでゐる小賢しさに苦笑するのであつた。
――ふつ。
確かに《物自体》は闇の中にしかその影を現さぬであらう。しかし、闇は私の如何なる表象も出現させてしまふ《場》であつた。私が何かを思考すれば、たちどころにその表象は私の眼前に呼び出される事になる。闇の中で蠢く気配共。気配もまた何かの表象を纏つて闇の中にその気配を現はす。それは魂が《存在》から憧(あくが)れ出る事なのであらうか……。パンドラの匣は闇の中で常に開けられてゐるのかもしれぬ。そして、そのパンドラの匣には魑魅魍魎と化した気配共が跋扈する。この闇の中で《存在》の下には《希望》なんぞは残される筈もなく、パンドラの匣に残されてゐるのは現代では《絶望》である。
――――ううううああああああああ~~。。
彼の人はゆつくりとゆつくりと螺旋を描きながら、何処とも知れぬ何処かへ向け飛翔を相変はらず続けてゐた。彼の人はこの闇の中にあつてもその姿形を変へる事なく、徹頭徹尾彼の人であり続けたのであつた。
闇。闇は《無限》を強要し、其処に卑近な日常の情景から大宇宙の諸相迄ぶち込む《場》であつた。闇の中では過去と未来が綯(な)ひ交ぜになつて、不気味な《もの》を眼前に据ゑるのだ。悪魔に魂を売るのも闇の中では私の選択次第である。ふつ。この解放感! 私はある種の陶酔感の中にあつたに違ひなかつた。《もの》皆全て闇の中に身を潜め、己の妄想に身を委ねる。それはこれ迄自身を束縛して来た《存在》からの束の間の解放であつた。《存在》と夢想の乖離。しかし、《存在》はそれすらも許容してしまふ程に懐が深い。《存在》からの解放なんぞは無駄な足掻きなのかもしれぬ。闇の中の妄想と気配の蠢きの中にあつても《存在》は泰然自若としてゐやがる。ちえつ。何とも口惜しい。しかしながら《存在》無くしては妄想も気配もその《存在》の根拠を失ひ此の世に《存在》出来ないのは自明の理であつた。
……………
……………
――お前は何者だ!
ねえ、君、闇の中では闇に誰もがかう詰問されてゐるに違ひない。へつへつへつ。人間は本当のところでは自問自答は嫌ひな筈さ。己の不甲斐なさと全的に対峙するこの自問自答の時間は苦痛以外の何物でもないに違ひない。それはつまり自問する己に対して己は決して答へを語らず、また語れないこの苦痛に堪へなければならないからね。それに加へて問ひを発する方も、己に止めを刺す問ひを多分死ぬ迄一語たりとも発する事はないに違ひない。そもそも《生者》は甘ちやんだからね。へつへつへつ。甘ちやんぢやないと《生者》は一時も生きられない。へつへつへつへつ。それは死の恐怖か? 否、誰しも己の異形の顔を死ぬ迄決して見たくないのさ。醜い己! 《生者》は、生きてゐる事その事自体が醜い事を厭といふ程知り尽くしてゐるからね。君もさう思ふだろ? それでも《生者》は自問自答せずにはゐられない。をかしな話だ、ちえつ。
…………
…………
鎮守の森による闇といふ自身の《存在》を一瞬でも怯ます時空間の中で、此の世に《存在》する森羅万象は疑心暗鬼の中に放り込まれて猜疑心の塊になつてゐる筈であつたが、私はこの闇の中といふ奇妙な解放感の中で、尚も、「光が彼の世への跳躍台」といふ言質の周りで思考の堂堂巡りを重ねてゐたのであつた。
『……相対論によれば物体は光に還元出来る。つまり物体は《もの》として《存在》しながらも一方では摑みどころのないEnergie(エネルギー)にも還元出来る……もし《もの》がEnergieとして解放されれば……へつ……光だ! ……この闇の歩道を歩く人波全ても光の集積体と看做せるぢやないか! ……だが……《生者》として此の世に《存在》する限り光への解放はあり得ず、死す迄人間として……つまり……《もの》として《存在》する事を宿命付けられてゐる……光といふ彼の世への跳躍台か……成程それは《生者》としての《もの》からの解放なのかもしれない……』
と、その時、不意に歩道は仄かに明るくなり、再び満月の月光の下へ出たのであつた。
『……確かに《もの》は闇の中でも仮令見えずとも《もの》として《存在》するに違ひないが……しかし……《もの》が光に還元可能なEnergie体ならばだ……《もの》は全て意識……へつ……意識もまたEnergie体ならばだ……《もの》皆全て意識を持たないかな? 馬鹿げてゐるかな……否……此の世に《存在》する《もの》全てに意識がある筈だ……死はそのEnergie体としての意識の解放……つまり……光への解放ではないのか?』
遂に歩道は神社兼公園の鎮守の森の蔭の闇から抜け、月光と街燈が照らし出す明かりの下に出たのであつた。雪は相変はらず何かを黙考してゐるやうで、私の右手首を軽く優しく握つたまま何も喋らずに俯いて歩いてゐた。私はといふと、他人の死相が見たくないばかりに、明かりの下に出た刹那、また視線を足元に置き伏目となつたのである。
『……それにしても《光》と《闇》は共に夙(つと)に不思議なものだな……ちえつ……《もの》皆全て再び光の下で私(わたくし)し出したぜ……《吾》が《吾》を見つけて一息ついてゐるみたいな雰囲気が漂ふこの時空間に拡がる安堵感は一体何なんだらう……それ程迄に私が私である事が、一方で不愉快極まりないながらも、もう一方では私を安心させるとは……《存在》のこの奇妙奇天烈!』
その時、丁度T字路に来たところであつた。私はSalonに行く前にどうしてももう一軒画集専門の古本屋に寄りたかつたので、そのT字路を右手に曲がつたのであつた。
――何処かまだ寄るの?
と雪が尋ねたので、私は軽く頷いたのであつた。この道は人影も疎らで先程の人波の人いきれから私は解放されたやうに感じて、ゆつくりと深呼吸をしてから正面をきつと見据ゑたのである。
――あつ、画集専門の古本屋さんね?
と、雪が尋ねたので、これまた私は軽く頷いたのであつた。
其処は洋の東西を問はず、多分古本屋の主人の頭蓋内の闇に明滅する心象風景に呼応してしまつた絵画や、これまた古本屋の主人の魂に決定的な印象を与へてしまつた画集の数数等が、これまた古本屋の主人の魂の有様を映すやうに雑然と置かれてゐた、何やら古本屋の主人の頭蓋内にある或る部屋の中に迷ひ込んだやうな、一種独特の雰囲気を醸し出した古本屋であつた。それを更に例へて言つてみれば、古本屋の主人の頭蓋内に形作られてゐた迷宮都市が画集によつて再現されてゐるといつたやうな、人間誰しも持つてゐるに違ひない或る種の風狂さが直截表れてゐる、古本屋の主人の独特の性質が紡ぎ出した独自の世界観に彩られた古本屋であつた。私がその古本屋を最初に訪れたのは、「あつ、こんな所にも古本屋がある」と何気なくであつたが、しかし、その古本屋の店内に一歩足を踏み入れた刹那、私の魂は鷲摑みにされすつかり魅了されてしまつたのは言ふ迄もなく、途端にその古本屋は私の時間が許す限り必ず訪れないと気が済まない場所になつてしまつたのであつた。
その古本屋に入るや否や、私は雪を放つておいてヴアン・ゴツホとヰリアム・ブレイクと長谷川等伯と伊藤若冲の画集を棚から取り出し、渦巻く夜空が異様なヴアン・ゴツホの「星月夜」と、「天帝」とも呼ばれてゐる雲上の老ひた男が片手を地に向けCompass(コンパス)状に二条の閃光が放たれる「絶対者」と、幽玄至極な等伯の「松林図屏風」と、極彩色が凄まじい若冲の「鶏之図」を左から順番に平積みの雑誌等の上に拡げ並べて雪に見せたのであつた。
――何? 何か意味があるでしよ!
と雪が訊ねたので、私は即座にMemo帳を取り出し、かう雪に切り出したのである。
――つまり、この四作品を左から眺めていつて、つまり、何か気が付かないかい?
――そうねえ……ちよつと待つてね。
と雪は四枚の絵に見入るのであつた。雪の腕組みをしたその物腰は、傍から見てゐると見惚れる程に優麗で雪の心の美しさが自然と表れてゐるやうにしか見えなかつたのである。蛍光燈の明かりの下で改めて見る雪は実際に観音像が醸し出す柔和な雰囲気を纏ひ、そしとて、その柔和な表情が見る者の心を穏やかにさせるに相応しい美麗な面立ちをしてゐて、見れば見る程に美しかつたのであつた。
――それにしてもこの四作品は凄いわねえ。
と雪は嘆息したのであつた。さうである。この四人の作品はいづれ劣らず傑作ばかりであつた。雪が嘆息するのも無理からぬ話である。
――う~ん、私には良く解らないわ。唯、いづれの作品も凄いといふ事だけは解るけどもね。
――つまり、先づ、ヴアン・ゴツホの「星月夜」だけど、つまり、これは主観の世界かい? つまり、それとも客観の世界かい?
――さうねえ、徹底した主観の世界だとは思ふんだけども……。
――つまり、さうだとすると、つまり、ヴアン・ゴツホは敬虔な基督者だけれども、つまり、この作品の創造主は神だと思ふかい? つまり、それともヴアン・ゴツホ本人だと思ふかい?
――えつ! いきなりの質問ね。多分だけれどもね、この作品の創造主はきつと神よ。さうに違ひないわ。ぢやないと、ゴツホがこの絵を描き上げる前にゴツホ自身が滅んでゐるんぢやないの?
――さうだね。つまり、この作品の世界の創造主は、つまり、ヴアン・ゴツホぢやなく、つまり、やはり神だと僕も思ふ。けれども、つまり、この渦巻く夜空は、つまり、どうした事だらう?
――ゴツホには此の世の真理が朧げながら見えてしまつてゐたんぢやないかしら……。可哀相に!
――つまり、此の世の真理に、つまり、朧げながらも触れてしまふ事を、つまり、君も可哀相だと、つまり、哀しい事だと思ふのかい?
――ええ、私はさう思ふの。といふよりも、さう思へて仕方無いのよ。自分でもそれが何故だか解らないんだけれども、此の世の正覚者は全て大悲哀を背負つてゐるとしか思へないのよ。何故だか自分では解んないんだけどもね、うふふ。
――すると君は、つまり、このヴアン・ゴツホの作品は哀しい作品に、つまり、思へるんだね。
――ええ。
――つまり、僕もそれには、つまり、同感だ。
――――ううううああああああああ~~。。
――なぜかしらねえ? 此の世に《存在》する事自体が悲哀だと思つてしまふの。私の悪い癖ね。でも、悲哀が《存在》の原形質の一つだと思うのよ。
――つまり、この絵は途轍もない切迫感が、つまり、迫つて来るよね。つまり、この絵はこの世界を創つた創造主への、つまり、ヴアン・ゴツホなりの問ひ、つまり、それもヴアン・ゴツホの全《存在》をかけての、つまり、痛切な問ひだつたんぢやないかと思ふんだがどうだい?
――問ひねえ……。其処には自身の《存在》に対する疑念が含まれてゐたのかしら。
――しかし、つまり、ヴアン・ゴツホには、つまり、夜空がこの様にしか見えなかつたんだらう。つまり、其処迄ヴアン・ゴツホは追い込まれてゐた。つまり、其処には底知れぬ諦念があつた筈だよ。
――諦念? 何に対する諦念?
――つまり、自身の《存在》に対する諦念! つまり、多分、ヴアン・ゴツホは己の《存在》を呪つてゐた筈だ。つまり、生涯でたつた一枚の絵しか売れなかつたヴアン・ゴツホが、つまり、それでも創作活動を続けた、つまり、その途轍もない原動力は、つまり、己の《存在》に対する、つまり、呪詛以外あり得なかつたんぢやないかな。つまり、そんな己を《存在》させた、つまり、神への問ひしか、つまり、最早、つまり、ヴアン・ゴツホには残つてゐなかつたに違ひない。
――その問ひは、懊悩に懊悩を重ねた末の最後の一縷の望みを此の世に繋ぎ止めるための呻きに近かつたんぢやないかしら?
――つまり、それでも神に、つまり、問はずにはゐられなかつたヴアン・ゴツホは、つまり、途轍もなく哀しい《存在》だね。つまり、荒涼としたヴアン・ゴツホの内界を、つまり、神にぶつけてみて、つまり、神の答へ、つまり、それがこの「星月夜」だつたんぢやないかと思ふ。つまり、夜空で渦巻く、つまり、月や星星は、つまり、ヴアン・ゴツホの《存在》を映したものに違ひないと思ふがね。つまり、渦を巻く事で、つまり、辛うじて《存在》が《存在》を、つまり、保てたんぢやないかな。
――渦は中心を持つわね。きつとゴツホは《存在》の中心を創造主たる神に問ふたのね。己が《存在》に中心はあるのかと。渦を巻く以外には最早《存在》はゴツホにとつて瓦解した《もの》だつたんぢやないかしら。吾は此の世に《存在》するに値する《存在》であつたのかと。ゴツホの全《存在》をかけての問ひだつた気がしないでもないわね。
――つまり、無限大、∞。つまり、ヴアン・ゴツホもまた、つまり、無限大といふものに、つまり、直感的に触れてしまつたのかもしれぬ。
――唐突に何? 無限大つて、あのさつきの無限大次元だつたかしら。その無限大次元の無限大?
――さう。つまり、神の問題を突き詰めると、つまり、どうあつても、つまり、無限大に行き着いてしまふのが自然の道理さ。つまり、実際に夜空を渦巻くやうにしか描けなかつたヴアン・ゴツホもまた、つまり、無限大に触れてしまつたに違ひない。
――無限大に触れるつて?
――つまり、一般に時空間は、つまり、四次元として誰しも認識してゐるから、つまり、仮に無限大次元でしか認識出来ないとすれば、つまり、ヴアン・ゴツホの「星月夜」のやうな世界が、つまり、描かれるしかない。つまり、世界はさうとしかあり得ないんだ、多分、ヴアン・ゴツホにとつては特に。
――――ううううああああああああ~~。。
赤の他人の彼の人は相変はらずゆつくりと渦を描きながら、私の視界の中の何処とも知れぬ何処かへと飛翔を続けてゐたのであつた……。
――ねえ、無限大次元では全てが渦に収束するのかしら?
――さうだね。つまり、僕個人の考へではさうとしか考へられない。つまり、全ての《存在》は渦へと収束する。
――ぢやあ、世界を無限大次元で忠実に描写すると正にゴツホの「星月夜」のやうにしかならないつて事ね。
――さう!
――何となくだけど、あなたが言つてゐる無限大次元が解つたやうな気がするわ。
――さうか。つまり、無限は神に通じてゐるのさ。
ここで私はブレイクの絵を指差し、雪に見るやうに促したのであつた。
――つまり、無限が神に通じる事が、つまり、このブレイクの絵で逆説的にではあるが、つまり、具現化されてゐると思ふが君はどう思ふ?
――う~ん、何をおいてもこの絵は峻厳な絵ね。この絵は「Europe a Prophecy(ヨーロツパ 一つの預言)」の口絵になつてゐる絵でしよ?
――さう。つまり、かうしてブレイクは無理矢理にでも、つまり、無限なるものを封印せざるを得なかつたのかもしれぬ。
――無限を封印? この絵は無限の具現ぢやないの?
――つまり、この絵に限らないんだけれども、つまり、ブレイクにとつては、つまり、無限は球状の火の玉に封印され、つまり、人間なるものが《存在》するこの世界の開闢が、つまり、宣告されてゐるやうにも見えるけどね。
――世界の創造ね。
――つまり、この絵には人間《存在》の業が集約されてゐる。つまり、ブレイクはどうあつてもこの世界の謎を、つまり、何としても解き明かし、つまり、認識し尽くしたかつたに違ひない。つまり、その結果として、つまり、必然としてブレイクは世界創造の神話的な物語風の詩を、つまり、書かざるを得なかつたのさ。つまり、此の世は封印された無限の上に築かれた泡沫の夢さ。
――この絵が泡沫の夢? う~ん、さうかもしれないわね。此の世が泡沫の夢であるが故にこの峻厳な絵で世界の開闢を刻印したのね。
――さうかもね。つまり、ブレイクにとつて無限の封印を解いて、つまり、世界の開闢を宣告するにはこの絵のやうな、つまり、神話的な人格の具現でしか表現できなかつた。つまり、それは神とも呼ぶべき《存在》の創出さ。つまり、初めに神ありき。つまり、基督教が支配する世界では全てが神から始まつてゐる。
――さうね……。でもそれつて結局のところは、主体のごり押しに終始するんぢやないかしら。
――さう、つまり、神は主体の理想から一歩も抜け出られない。つまり、それが神の物語たる神話であらうが預言であらうが聖書であらうが、つまり、主体自らの手で徹頭徹尾書き記さずにはゐられない。つまり、それは詰まる所、つまり、神に託(かこつ)けて主体がしやしやり出ずにはゐられない哀しい《存在》なんだ、つまり、主体はね。つまり、主体は世界の中心に《存在》する事になる。しかし、これは、つまり、ある意味主体に苦悩しか齎さない。つまり、《無》がない事の不自由さとでも言つたらいいのかな。つまり、それは主体の暴走を《絶対存在》を創造する事で主体自ら呪縛する外ない。つまり、其処にはそれはそれは深い深い懊悩が隠されてゐる筈さ。つまり、そこにもし神といふ《存在》がなかつたならば、つまり、主体は、つまり、未来永劫救はれない。つまり、徹頭徹尾主体が主体の主人といふ事は、つまり、それはある意味地獄絵図だ。つまり、それを見ないための基督の磔刑像さ。そして、つまり、其処に残されるのは、つまり、自堕落で憐れな自己が現出するのみさ。ふつ、つまり、自己実現出来たらそれで仕舞ひのちつぽけな主体が其処に《存在》するだけだ。つまり、これは矮小化されてはゐるが、つまり、他力にも通じるところがあるんだが、絶対の神の思し召しによるといふ、つまり、絶対的な神に抱かれ高みに昇る信仰がなければ、つまり、主体は主体を超克なんぞ出来やしない。
――他力? 基督教にも他力の要素はあると思ふの?
私は其処で軽く頷いたのであつた。
――つまり、其処には大いなる矛盾があるんだが、つまり、彼等は一方で絶対の神への信仰を抱きながら、つまり、一方で主体絶対主義といつたら良いのか、つまり、地上の王は主体なんだ。つまり、それは懊悩以外齎さない。つまり、《無》を、《無》といふ《無限》を認めない不自由極まりない《存在》として、つまり、主体は此の世に《存在》しなければならぬ。つまり、それは哀れだよ。
――哀れ?
――さう、哀れさ。つまり、其処で他力のやうに絶対の神に身を委ね、つまり、一時の平安を得てゐるのさ。つまり、これは哀れとしか言いやうがない。
――――ううううああああああああ~~。。
私は暫く口を噤み瞼を閉ぢて、瞼裡の虚空と赤の他人の彼の人を凝視したのであつた。しかし、それも一瞬の事で、私は再び目をかつと見開きMemo帳にかう記したのであった。
――つまり、基督に全てをおつ被せて、自身は平安の安息の中に安らぐ矛盾を、つまり、矛盾と気付かずに、つまり、主体絶対主義の下に生きる。つまり、僕からすると、つまり、そんな生き方は哀れ以外の何物でもない。
――でも、平安が得られるのであれば、それはそれで幸福なんぢやないかしら。
――さうだね。つまり、神に抱かれての平安は、つまり、それはそれで幸福だ。しかし、このブレイクの絵に平安はあるかな?
――これつぽつちもないやうに見えるけれど……。
――つまり、恐怖を感じないかい? つまり、胸に突き刺さる恐怖を?
――う~ん、さうね、さう言はれればこの絵は恐怖を掻き立てるかもしれないわね。
――つまり、恐怖がなければ主体は、つまり、増長する馬鹿な生き《もの》だ。つまり、主体が主体を統治する装置として、つまり、恐怖は必須の条件さ。つまり、多分、ブレイクには、つまり、平安はなかつたんぢやないかな。
――どうしてさう思ふの?
――つまり、ブレイクにとつて自身は、つまり、度し難い、何とも名状し難い《存在》だつたやうな気がするのさ。何となくだけどもね。
――弁証法ではどうしようもないものをブレイクは見てしまつたやうな気がするの。
――つまり、無限さ。
――無限ね……。
――つまり、ブレイクにとつては初めに無限ありきのやうな気がするんだ。つまり、先づは無限を何としても鎮めない事には、つまり、一歩も主体は前に進めない。つまり、有限が無限を退治する苦悩――これはどう仕様もない!
――有限が無限を退治する苦悩?
――さう。つまり、主体はどう足掻いても有限だ。つまり、初めにLogos(ロゴス)があつてしまふ西洋において、ブレイクは、つまり、自身の身の置き所がなかつたんぢやないかな。つまり、だから、ブレイクの作品は絵巻物のやうに言葉と絵が混在してゐる。つまり、ブレイクにとつてはさういふ形式しか取りようがなかつた。
――さうね。私もさう思ふわ。
――つまり、絵に無限を閉ぢ込める。しかし、
と、私はここでMemo帳から目を上げ、表向きはぼんやりと本棚の画集群の背表紙を眺めながらも内部に拡がつてゐる虚空を凝視し、暫く沈思黙考したのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
暫くすると雪が、
――渾沌……。陰陽魚太極図……。ブレイクの無限を閉ぢ込めた火の玉の卵殻の形をした絵は陰陽魚太極図に通じてないかしら?
と言つたので、私は軽く頷いたのであつた。そして私は蛍光燈の明かりをぼんやりと眺めながら、無限について思ひを巡らせたのであつた。
…………
…………
ねえ、君。無限について思ひを巡らすなんて愚かな事だね。
例へば、
――無限とは何ぞや?
と自問自答したところで何にも出て来やしない。無限は無限のまま、相変はらず有限の主体をせせら笑つてゐる。しかしだ。有限の主体はそれでも無限を問はざるを得ない哀しい生き《もの》だ。
尚も、
――無限とは何ぞや?
と主体は自問自答を敢へてするしかない。哀しいね……此の世に《存在》する森羅万象は……。
…………
…………
私はブレイクの絵を一瞥しては瞼を閉ぢ、そして、陰陽魚太極図を脳裡に思ひ浮かべては黙考を繰り返すのであつた。雪もまた暫く何かに思ひを巡らし沈思黙考してゐるのである。
すると不意に私の頭蓋内の闇の中に、
――人は麺麭(ぱん)のみに生きるに非ず……。
といふ声が厳かに響き渡つたのであつたのであつた。私はゆつくりと瞼を開け、ブレイクの絵を凝視したのであつた。
――人は麺麭のみに生きるに非ず……。
…………
…………
ねえ、君。確かに人は麺麭のみに生きるに非ずだね。これは間違ひない。だつて、人は自身の生に何か理由付けしないとこれつぽつちも生きてゐられやしないぢやないか。
――私は何の為に生きる?
この言葉が世界に満ち満ちてゐる。誰しもが自分の人生について何かしらの思ひを馳せ、『私は何の為に生き《存在》してゐるのか?』と、絶えず自問自答してゐる。麺麭を得るのにき汲汲としてゐる生活はそれはそれで物凄く充実してゐる人生に違ひないが、しかし、一度、
――私は何の為に生きてゐる?
といふ陥穽に捉へられると、もう其処から一歩も身動き出来なくなつてしまふ。その満たされる事のない自身の難問を解かう、と或る者はそれを信仰に求め、或る者はそれを物欲に転換して心なる不思議なものを満たさうとするが、詰まる所、正覚でもしない限り、その答へは見つかりつこない。それは死んでも尚解らないままに違ひないのだ。
ねえ、君。そもそも心は満たされるものなのだらうか。麺麭が十二分に得られたからといつて、心はちつとも満たされる事はない。そこで手つ取り早く《他者》をひつ捕まへて《自己》を満たさうとするが、しかし、《他者》もまた満たされぬ心を持つ宿命にあるので、傍から見るとどうしても《自己》と《他者》は傷を舐め合つてゐるやうな奇妙な状態に置かれる事になる。それは《他者》に対して非礼な振舞ひだ。それは《自己》を満たすためにのみに《他者》を利用してゐるだけだからね。
――人は麺麭のみに生きるに非ず……。
ねえ、君。君はこれをどう思ふ? 私は前にも言つたが、私は私自身をして己に喰はれる食物以下の下等な生き《もの》だと看做してゐるが、しかし、それでも今の無為な唯死を待つのみの日日を送つてゐると、やはり、
――人は麺麭のみに生きるに非ず……。
といふ難問と向き合はざるを得ない。多分、これは生に対する或る種の免罪符なのかもしれぬがね。しかし、どうあつてもこの難問には向かひ合はざるを得ないのだ。多分、それに対する答へはないだらうがね。しかしだ、人一人此の世に生きたのだ。この事実は消せない筈だ。へつ、だが、私には胸を張つて、
――俺は生きた!
と言へやしない。どうしても言へないのだ。何故だらうね? 君には解るかい? この口惜しさが!
…………
…………
『さうか。ブレイクはこの作品といふものを此の世に残した御蔭で今生きてゐる私は既に死んで久しいブレイクの何かに触れたやうな気にさせてくれる。有難い事だ。
等と、私は思ひながらブレイクの絵を凝視してゐたのであつた。
――人は麺麭のみに生きるに非ず。そして、人は死後も何らかの形で生を繋げる! このブレイクの作品が好例ぢやないか! これは複製だけれども、ブレイクの手によつて作り上げられた作品が今を生きる私の眼前にあつて、私はそれを鑑賞出来るぢやないか。ブレイクの詩がブレイクの死後であつても今を生きる私に読めるぢやないか! 此の世に一度《存在》してしまつたものは、何であらうがその死後もその《存在》の証を何らかの形で残す。《精神》のRelay! はつはつ』
等と思ひながら、尚も私は感慨深げにブレイクの絵を凝視するのであつた。
すると、
――ねえ、ブレイクにとつて無限つて何だつたのかしら?
と、不意に雪が訊ねたのであつた。
――つまり、《存在》の淵源にして、つまり、究極の目標だつたんぢやないかな。つまり、ブレイクは無限を渇望せざるを得なかつた。つまり、それを宿命と名付けるんだつたならばだ、つまり、宿命としか言ひやうがない。実際のところは、僕には良く解らないんだけれどもね。
――さうね。私も実のところ良く解らないの。えへつ。でも、ブレイクの絵には魂を衝き動かす衝迫力といふのか、何か不思議な力を感じるわ。
――さうだね。
と、Memo帳から目を離し、私はブレイクの絵を凝視するのであつた。
『……何なのだらうか……。この時代をいとも簡単に飛び越えてしまふ力の源は!』
と思ひながら私はゆつくりと瞼を閉ぢるのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
赤の他人の彼の人は相変はらず、何処とも知れぬ何処かへと向かつてゆつくりと旋回しながら虚空を飛翔してゐたのであつた。彼の人もまたブレイクと同じやうに、死んでも尚、生者の魂を衝き動かさざるを得ない何《もの》かを此の世に残して死んで逝つたのだらうか……。
――つまり、ヴアン・ゴツホもブレイクも主体が持つただならぬ狂気といふのか、つまり、表現せざるを得なかつた、つまり、魂の叫びのやうなものが全的に表現されてゐる。それと較べると、つまり、この長谷川等伯の絵はどうだね?
――う~ん、さうね、何となくだけれども無私な感じがするわ。ゴツホやブレイクとはある意味対極に位置するやうな気がするの。でも、この松林図は等伯の心象風景よね。……人間て……不思議ね。
――この絵は、つまり、徹頭徹尾等伯の主観だね。すると、ヴアン・ゴツホやブレイクと等伯の違ひは何だと思ふ?
――う~ん、難しい質問ね。うふつ、それが解つてゐれば大学者になつてゐるわよ、うふつ。でもEgo(エゴ)と滅私の違ひぢやないかしら? いや、違ふわね……。
と言つたきり、雪は口を噤んで等伯の画を凝視するのであつた。その蛍光燈の明かりで隈どられた雪の横顔は尚更何とも言へずに美しかつたのである。
――この寂寞とした静寂さは何なのかしら……。
と雪の口から感嘆の言葉が漏れ出たのであつた。
――つまり、無常の恒常といふのかな、これは。
――無常の恒常? 面白い表現ね。さうね。この画には無常なるが故の恒常が画かれてゐるのかもしれないわね。
――つまり、こんな言葉は無いんだけれども敢へて言へば、つまり、等伯は勿論、若冲もさうなんだけれども、心鏡の画だね。
――心鏡? どういふ事?
――つまり、字義そのまま、心の鏡といふ事だよ。
――心の鏡……ね、さうね、正に心の鏡ね。心鏡か……。
と、その時、不意に私の視界の周縁を小さな黒い影がふわりと横切つたので、私は思はず眼を上げその影の方を見ると、蛍光燈の明かりに誘はれて店内に一匹の蛾が迷ひ込んでゐたのであつた。
『飛んで火に入る夏の虫』
――ねえ、この画に見入つてゐると自分の心が映るの。不思議ね。等伯はどうしてこんな画が画けたんだらう……。不思議……。
私は少し微笑んでから首を横に振つて、解らないといふ合図を雪に送つたのであつた。
――不思議ね……。
――ねえ、つまり、この画を見てゐると、どうあつても等伯の人生に思いを馳せざるを得ないと思はないかい?
――さうね……、この境地に至るまでには、それはそれは言葉では言ひ尽くせない途轍もなくとんでもない人生を歩んで来たのは間違ひないわね。
――つまり、確かに等伯の人生は不幸そのものだつたね。それが、つまり、この松林図に昇華されてゐる気がする――。
――私が知る限りだけれども、確か等伯は息子は亡くしてゐるし、右手も不自由になつたし……。等伯の人生は、その画業に反して不幸そのものね……。
――でも、つまり、等伯の人生なんぞ何も知らなくても、この松林図は、つまり、何か透徹した凄味が垣間見えてしまふと思はないか? つまり、見る人の魂を串刺しにしてしまふ凄味が。つまり、この松林図を画かずにはゐられなかつた等伯の思ひは如何ばかりであつたか――。つまり、この松林図は徹頭徹尾己の為にのみに画かれてゐるやうな気がするんだ。しかし、それが無私になる。つまり、東洋的だといふ一言では片付かない何かがこの画には秘められてゐる。つまり、何と言つたら良いのか――、無我の境地、つまり、しかもそれは徹頭徹尾己に拘り続けた末に、つまり、幽かに垣間見えたかもしれない無我の境地――。つまり、何なのか、この松林図は!
――さうね。この画は見る者の魂をぎやふんと言はせる何か迫力があるわね。無私なるが故に、見る者には敵はない何か突き詰めた思ひが迫つて来るわね。ゴツホやブレイクと違つて直截的ではないけれども、後からじわじわと迫つて来る主観なる《もの》の物凄さがこの画には宿つてしまつてゐるわね。
――つまり、生者の前に厳然と立ちはだかる巨大な壁。つまり、「どうだ、この画の前では身動ぎも出来ぬであらう!」といつた等伯の声が聞こえて来るやうだ。つまり、「さあ、この画を乗り越えられるんだつたなら乗り越えてみるんだな、へつ」というやうな等伯の声が聞こえて来さうな気がする。つまり、この画はもしかすると、現在を生きる生者にとつての《躓きの石》なんぢやないかな。つまり、敢へて言へば先達が残した作品は、それが何であらうと、つまり、それを超えようとする現代人にとつての《躓きの石》でしかないのかもしれぬ――。しかし、つまり、それらを知つてしまつた以上、つまり、現代人はそれらを超克せねば気が済まぬ宿命を負はされる。否、負はなければならない。つまり、さうぢやなければ先達に失礼だと思ふんだが、君はどう思ふ?
――さうすると……、あなたは先づ第一に先達の作品の否定から現代人は始めろといふ事を言ひたいのかしら?
――否、それは違ふ。つまり、先達の作品を認めた上で、それ以上のものを作り上げる努力といふのか、絶望といふ茨の道を歩まざるを得ない。つまり、人類も歴史を持つ以上、先達に負けず劣らぬ何ものかを創造する宿命を負つてゐる。
――宿命ね……。それは宿命なのかしら? 過去を超克しようなどと思はなければ、それはそれで何の事はないんぢやないの?
――それはさうだけれども、しかし、つまり、眼前に人間の業(わざ)なる途轍もなく物凄い《もの》があつて、つまり、それに睨まれたとしたならば、その人間は尻尾を巻いて逃げて、つまり、それで仕舞ひで済むと思ふかい?
――さあ、解らないわ。
――つまり、敗北感と屈辱の中で、つまり、人間は一生を平気で過ごせるものなのだらうか? つまり、人間といふ《存在》の業(ごふ)がそれを許すと思ふかい?
――さうね、中にはそれで済んぢやう人間もゐると思ふけれども、何糞つとそれに立ち向かふのが多数の人間ぢやないかしら?
――つまり、僕も君もヴアン・ゴツホに、ブレイクに、等伯に、若冲に今睨まれてゐるんだぜ。さあ、どうする?
――うふつ。
――つまり、人間、この度し難い《存在》めが!
――うふつ。
――つまり、時代を超えて生き延びた、つまり、人類の遺産の如き古典といふ傑作の数数を前に、怯まずにくつと前を向いて、つまり、倦まず弛まず現在を生きるのは、さて、困つた事に、つまり、如何ともし難く、度し難い状況を生きる事に等しい。つまり、堂堂巡りになつてしまふが、つまり、そもそも《存在》とは何ぞや?
――うふつ。あなたはその《存在》をどう思ふのかしら?
――つまり、それが良く解らないんだよ。
――うふつ、解らないから生きてゐるんでしよ? 多分生者であれば正覚者以外誰も解らない筈よ。
――つまり、それでも生者は問はずにはゐられない。そこで、つまり、この若冲の鶏の極彩色の画だ。君はどう思ふ?
――さうね。無心の画のやうな気がするわ。
と、雪が言ふのを聞きながら私は若冲の画を凝視するのであつた。
成程、若冲のこの鶏の画は無心の画に違ひない。しかし、この画には魂魄が宿つてしまつたやうな不気味な《存在》感が漂つてゐる。それは《存在》といふ《もの》の不気味そのものであつた。若冲はカントのいふ《物自体》にそれとは知らずに触れようとしてゐたのであらうか。この妖気すら発するこの鶏の画は、一体全体どうした事であらうか……。
――つまり、この画は、つまり、ドストエフスキイ言ふところの魂のRealism(リアリズム)だとは思はないかい?
――さうね、魂のRealismね……。さうね、《物自体》が持つ《存在》の不気味さが漂ふ何とも表現し難い画ね。
――《物自体》の不気味さ? つまり、実は僕もさう思つてこの画を眺めてゐたんだ。やはり君もさう思ふか――。
――さう。ブレイクの「The Tyger」(「虎」)にも通じるわね。
「The Tyger」
Wlliam Blake著
Tyger Tyger. burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes!
On what wings dare he aspire!
What the hand, dare sieze the fire?
And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?
What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!
When the stars threw down their spears
And water’d heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
Tyger, Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
「虎」――拙訳
虎よ、虎よ、燃え上がる光輝、
その夜の森に、
如何なる不滅の手と眼が、
汝の震撼する程の均斉を創り得るのか?
どれ程の空空の深度若しくは高度迄。
汝の眼は燃え上がつたか?
如何なる程の迅速さを彼は敢へて熱望するのか?
如何なる手が、敢へてその炎を捉へるのか?
更に如何なる肩が、如何なる術が、
汝の心の臓の筋肉を捩る事が出来得るのか?
更に汝の心臓が拍動を始めた時、
如何なる恐ろしき手が? 如何なる恐ろしき足が?
如何なる槌が? 如何なる鎖が?
如何なる窯の中に汝の脳はあつたか?
如何なる鉄床が? 如何なるものが? 恐ろしき程に握るのか、
その死する程の恐怖を敢へて握るのか!
星星が自身の槍を投げ降ろした時
更に自身の涙で天を水浸しにした時、
彼は笑つて自身の御業を観たのか?
子羊を創りし彼が汝を創つたのか?
虎よ、虎よ、燃え上がる光輝、
その夜の森に、
如何なる不滅の手と眼が、
汝の震撼する程の均斉を創り得るのか?
――言ひ得て妙だ。本当にさうだね。つまり、ブレイクの「虎」だ。この異様さは――。
――でも、本来《存在》するとは異様な《もの》なんぢやないかしら。異様だからこそ何人の心を摑んで離さないのよ、《存在》は……。
――つまり、君も《存在》は異様だと思ふんだね。
――異様ぢやなくて何故《存在》は《存在》出来るのよ、うふつ。《存在》に魅せられたらもう《存在》から目が離せなくなるわね、この若冲のやうに。
――つまり、これつて特異点の不気味さなのかもしれない――。つまり、若冲の画は客体に至極執着してゐるけれども、つまり、一方で自在感も感じられる。つまり、この相反する《もの》が画として結実してゐるんだが、つまり、それを無限迄引き延ばすと、つまり、どうあつても特異点の問題になる。つまり、若冲の画から漂ふ不気味な妖気は、つまり、特異点の不気味な妖気に通じてゐる。君もさう思はないかい?
――特異点の問題かどうかは解らないけれども、確かに若冲の画には執着と自在の二つが混在してゐるわね。これつて正に渾沌の画だわ。
――つまり、それでも《もの》だから姿形は保持してゐる。不思議だね。つまり、それは更に何処かしら滑稽ですらある。
――若冲の画は客体と主体の戯れね。どちらも捕捉出来るやうに見えて不可解極まりない。不可解極まりないから最早其処から一時も目が離せなくなる。そして、若冲はその不可解極まりない事をむしろ楽しんでゐるやうにも見えなくもない。
――つまり、それは特異点の罠さ。つまり、若冲は直感的に特異点の不思議を感じ取つてしまつたんぢやないかな。つまり、《存在》の不思議に魅せられてしまつた。そして、其処から一生抜け出せなくなつてしまつた。つまり、絵画三昧の人生だ。
――それにしても若冲の画にはどう見ても厳格なる創造主はゐないわね……。
――等伯の画にもね。
私は若冲の画を凝視しながら、
――神は細部に宿る……。
等と思ひながら、鶏を写生すればする程、当の鶏なる《存在》はあつかんべえをして若冲の筆先から逃げ果(おほ)せてしまふ《存在》に対する屈辱といふのか無力感といふのか、追つても追つても逃げ果せる《存在》といふ如何とも度し難い《もの》を、それでも追はずにはゐられない人間の業の哀しさが若冲の画には漂つてゐるやうにも思へるのであつた。
――つまり、絶対的な縦関係と、つまり、相対的な横関係の違ひだね。
――えつ、何? さうか、絶対的と相対的な神関係か……。ゴツホとブレイクにとつては神は絶対的な《存在》であるといふ事が基本としてある世界認識上での絵で、等伯と若冲は神《存在》は主体と相対的にしか《存在》しない世界認識の結果、こんな画が画けたのかもしれないわね……。
――つまり、等伯と若冲の画にも、つまり、神、若しくは仏は《存在》してゐると思ふかい?
――う~ん、神仏習合が等伯にも若冲にも当て嵌まるんだつたならば、当然等伯にも若冲にも神仏は《存在》してゐた筈よ。特に若冲の画は鶏といふ名の神的な《存在》と戯れてゐる感じがするわ。
――鶏といふ神的な《存在》と戯れてゐるか――。でも、実際のところ、つまり、本当にさうだつたのだらうか? つまり、神との戯れでこんな奇想天外な画が画けると思ふかい?
――さうね、戯れはおかしいわね。格闘ね。若冲は鶏といふ神的な《存在》と傲岸不遜にも徹底的に格闘してゐたのね……。
――そして、つまり、己とも格闘してゐた。つまり、等伯も若冲も己とも格闘してゐたに違ひない。つまり、さうぢやなきやこんな画が画ける訳がないよ。つまり、等伯と若冲の画からは、つまり、森羅万象に数多の神が宿つてゐる、つまり、根本思想のやうなものが滲み出てゐるやうな気がする。つまり、何処にでも神や仏は《存在》してゐる。つまり、勿論、己の中にもね。つまり、等伯も若冲もヴアン・ゴツホやブレイクと同じやうに、つまり、絶えず神とは仏とは何ぞやと問ひ続けてゐたに違ひない。しかし、つまり、ヴアン・ゴツホやブレイクとは、つまり、根本的に世界認識の仕方が違つてゐる為に、これ程凄い画が画けたやうな気がするんだが、君はどう思ふ?
――でも、ゴツホやブレイクと何処かでは繋がつてゐると思ふの、等伯も若冲も……。それぢやなきやゴツホが浮世絵に魅かれる筈はないわ。それにブレイクも絵と文字が混在した東洋的な画風で絵を描きつこないもの。きつと彼等にも共通する普遍的なものは《存在》してゐたと思ふの。
――つまり、それでもヴアン・ゴツホやブレイクの作品から受ける印象と、つまり、等伯と若冲から受ける印象が全く違つてゐるのは何故だい?
――さうね、やつぱり絶対的な神関係と相対的な神関係の違ひぢやないかしら?
――でも、つまり、四人ともに神、若しくは仏は《存在》してゐるね。つまり、それが共通点、つまり、普遍的な《もの》なんぢやないかな。
――さう! そうね。絶対的と相対的といふ違ひはあるけれども、四人ともに神または仏が世界に《存在》してゐた……。そして、その神ある世界に魅せられた故に絵を描かざるを得なくなつてしまつたんだわ。つまり、如何ともし難い《存在》に魅入られてしまつたんだわ。何としても自分の手でこの世界といふ何とも不可思議な《存在》が数多《存在》してしまふこの世界といふものを一度握り潰して、そして世界を再創造し直してみたかつたんぢやないかしら。其処には神への対抗心もきつとあつた筈よ。しかし、さすがは神ね。ゴツホもブレイクも等伯も若冲も簡単に一捻りされてしまつて、神、若しくは仏性はその素顔を決して見せる事はなかつたのね。それでも彼等はこの如何ともし難い世界と格闘せずにはゐられなかつた。それは哀しい人間の業ね。
――つまり、きつと彼等は絵を描く事で、つまり、自在感なるもののその片鱗を、つまり、一度は味はつてしまつたやうな気がする。つまり、この自在感なるものが曲者で、つまり、世界を思ひのままに描く事が出来る愉悦、つまり、絵を描く事即ち世界の創造に、つまり、無謀にも自在感なるものを味はつてしまつた事で挑まざるを得なくなつてしまつた。つまり、其処には《存在》に対する恐怖なるものも必ず《存在》してゐて、つまり、頼れるのは己の技量のみ。そこでだ、つまり、彼等は神、若しくは仏性ある世界に一度は大敗北を喫する。其処では、つまり、自在感が徒となる。つまり、それは底無しの陥穽だ。どう足掻いても、つまり、その底無しの《存在》といふ陥穽から抜け出せない。さうすると、つまり、己を全的に世界にぶつけてみるしかない。つまり、其処でますます世界に対峙するべく、つまり、己の絵の世界に没頭して行く事になる。つまり、其処は無明の闇さ。つまり、試行錯誤を何度も何度も繰り返して、つまり、世界といふ不可思議な《存在》を吾が《もの》にしようともがき苦しむ事になる。つまり、それでも世界は知らん顔だ。つまり、神も仏も一度たりともその素顔を明かさない。つまり、それでもこの手で世界といふ不可思議な《存在》を、つまり、一度握り潰して再創造してみたくて仕様がない。困つたものだね、人間の業といふのは――。
――うふつ、どん詰まりのところでは結局、自身はあなたの言ふ鏡、世界を映す鏡になるしかなかつたのね。つまり、心鏡ね。どう人間が足掻いても世界はその断片しか見せてくれない。つくづく人間《存在》つて哀れな《存在》ね……。
――つまり、絵を描く事に没頭するといふ、つまり、飽く事なき《存在》の探究、つまり、それは世界との対話と言つても良いのだが、つまり、心鏡に映る世界は、果たしてその素顔の片鱗でも垣間見せたのだらうか? つまり、《物自体》はその尻尾を見せたのだらうか?
――さうね、きつと最後迄見せる事はなかつたでしようね。
――そこでだ、つまり、パスカル風に言つて此の世が《無》と《無限》の中間だとすると、つまり、例へば若冲は鶏の画を画く事で、つまり、《無》と《無限》の両極端を認識してしまつたんぢやないかな。つまり、認識と迄は言はなくてもぼんやりにでも、つまり、《無》と《無限》を垣間見てしまつた――。それぢやないとこんな鶏の画なんぞ画けつこないぢやないかと思ふんだけれども、君はどう思ふ?
――さうね……。あなたのいふ特異点の問題の事ね。
――さう。つまり、詰まるところ特異点の問題だ。つまり、この度し難い特異点と対峙してしまつた時、つまり、画家はたじろぎ怯むが、つまり、それでも眼前の《存在》を逃がさぬやうにぢつと目を据ゑ世界を凝視する。つまり、この端倪すべからざる世界を。つまり、対象を凝視するしか術がないんだ。つまり、その時《存在》は、つまり、《無》と《無限》との間を大振幅して画家を嘲笑つてゐるに違ひない。つまり、揺れる《存在》――。つまり、《無》と《無限》の間を《存在》は自由に揺れる。つまり、画家たるものそれを睥睨して、つまり、世界を描き始めなければならない。つまり、この時の苦悩は底知れぬ苦悩に違ひない筈だ。つまり、若冲の鶏でいふと、若冲は鶏に神を、仏を、宇宙を見てしまつた。つまり、神を、仏を、宇宙を画く事の恐ろしさと言つたらありやしない。つまり、それでも敢然とそれに対峙して、つまり、若冲は鶏を画かざるを得なかつた。つまり、これは何なんだらうね?
――宇宙を見るか……。本当に何なのかしら? 人をして画を、それもとんでもない画を画かせるその原動力は……。
――つまり、現代と違つて、彼等にはそれぞれ現代宇宙論では収拾のつかない、つまり、個性的なと言ふのか独創的なと言ふのか、つまり、解らないけれども、つまり、何とも奇妙な宇宙が彼らの内界には育まれてゐた筈だが、つまり、それ故彼等は知識に邪魔されない《生(なま)》の世界《存在》に出会つてゐる筈だ。つまり、それはそれは面白かつたんぢやないだらうか。
――《生(なま)》の《存在》ではないでしよう? 彼等にも神や仏の知識は《存在》してゐた訳だから。唯、科学的な知識は遠く現代人には及ばなかつたけれども、それが幸ひして科学的な知識が邪魔しなかつたのは確かね。それはむしろ幸福だつたのかもしれないわね。
――さう、其処なんだ。つまり、心鏡は科学的知識に集約される必要があるのだらうか? つまり、本来、非科学的な事の中にこそ真実なるものは隠されてゐるんぢやないかな。それを心鏡は映す。
――でも、非科学的な世界は渾沌の世界よ。
――つまり、それで良いんぢやないかと思ふんだが、つまり、渾沌の中からしか新世界の再創造はあり得ない。
――陰陽魚太極図ね、うふつ。
――さう、つまり、彼等は太極の状態を、つまり、《生(なま)》の世界《存在》を見てしまつたんぢやないかな。つまり、其処から《生(なま)》の世界なり《存在》なりがぬつと顔を突き出したんだ。しかし、それは一瞬の事で、つまり、その後は一度たりとも顔は現さない。しかし、つまり、一度でも《生(なま)》の《存在》を見てしまつた以上、つまり、それを探求せずにはゐられなかつた。
――それつて探求なのかしら? ただ単にその《生(なま)》の世界なり《存在》なりを捕まへたいといふ人間の業でしかないんぢやないかしら。
といふ雪の言葉を聞くと、私はゆつくりと瞼を閉ぢたのであつた。
――――ううううああああああああ~~。。
赤の他人の彼の人は相変はらず音為らざる音を発しながら、瞼裡の虚空の何処とも知れぬ何処かへとゆつくりと旋回しながら飛翔を続けてゐたのであつた。
『……画を画く事は渾沌に秩序を与へる行為に違ひない……しかし……私が《存在》してゐなくても世界は《存在》する……《存在》してしまふのだ!』
等と私は思考を巡らせたのであつた。そして、私は雪に解らないと首を横に軽く振つてにやりと笑ひ、おどけて見せるのであつた。
――さうね、解らないわね、うふつ。
――つまり、度し難い己の《存在》に対する処し方が画家の絵にも反映される。つまり、心鏡だ。
――さうね。さうぢやないと画家の作品は時代を超えて残らないわね。何処迄この度し難い《存在》に肉薄したか、それが画を見るものの魂を揺さぶるに違ひないわ。
――さう、つまり、度し難い《存在》への肉薄だ。つまり、特異点への肉薄さ。つまり、《無》と《無限》の狭間で発散しようと隙をうかがつてゐる《存在》といふ特異点は、つまり、それでも無理矢理収束状態に一見馴致されてゐるやうに見えるが、しかし、《存在》といふものはそれで済まない。つまり、狂気とも言へる情熱は如何ともし難い。それに狂気がなければ画など画けない筈だ。つまり、《生(なま)》の《存在》に対峙してしまつたんだからね。つまり、狂気のみが《存在》を馴致する。
――狂気か……。狂気をもつてしか《存在》には対せないのかもしれないわね。
――つまり、狂気をもつてしか《生(なま)》の《存在》には対峙出来ない。つまり、狂気なくして《無》と《無限》を見渡す事は不可能だ。つまり、《無》と《無限》を見渡さない限り、画家は一枚も画を画けない。つまり、さうしないと《存在》が姿形あるものに収束しないからね。
――でも……それつて狂気なのかしら? 私には人間誰しも持つてゐる業にしか思へないのよ。《無》と《無限》を見渡す不可能性へ対する人間の業。不可能なるが故に何としても成し遂げたい渇仰。だつて人間誰しも《無》と《無限》の間に《存在》させられてゐるのよ。あらゆる《存在》物が姿形を持つて《存在》させられてゐるのよ。哀しいけれどもね。
――其処なんだよ。つまり、《存在》は《存在》に我慢してゐるのだらうか?
――さうね。多分、どんな《存在》も《存在》に我慢してゐる筈よ。さうぢやなきや変容は生じないわ。
――変容――。つまり、《存在》は常に別の何かに変容したがつてゐる。つまり、君の言ふ事はさういふ事かい?
――う~ん、どうかな。例へば、諸行無常と恒常不変の狭間で《存在》はもがき苦悩してゐる。さうとしか思へないのよ。
――不思議なものだね。つまり、《存在》は諦念として諸行無常を或る意味受け容れてゐるが、つまり、それでも或る意味《存在》は諸行無常には我慢がならぬ。つまり、外的要因で《存在》を変容させられる事を、つまり、何故か忌み嫌つてゐる。しかし、つまり、人間《存在》がどう足掻いても此の世は諸行無常だ。つまり、これは如何ともし難い。つまり、だから、《存在》は渋渋ながらも諸行無常に我慢してゐる。つまり、かといつて恒常不変を心から望んでゐるかといふと、つまり、望んではゐるけれども、つまり、本心ではこれまた忌み嫌つてゐるとしか思へない。つまり、現状のまま恒常不変にでもなつたなら、つまり、此の世の終はりでとんでもないと感じてゐる。とはいへ、《存在》は恒常不変なるものに或る種の憧れさへ抱いてゐる。つまり、をかしなもんだね、《存在》といふこの我儘極まりない《存在》は! つまり、正覚者でない限り変な慾のやうなものを、つまり、人間《存在》は抱いてゐるから始末に負へない。つまり、その変な慾といふものを一言でいふと、つまり、不可能事を此の世で成し遂げるといふ、どうしようもない高望みの事だ。
――さう、不可能事なのよ! 何をおいても不可能事が第一なのよ! 《存在》した以上、不可能な事にばかり目が行くのよ。どうしてかしらね……。
――つまり、それは自由の問題と絡んでゐるんぢやないかな。
――さうね、自由の問題ね。そもそも自由が不可能事を望んでゐるのよ。自己実現出来てしまふ至極簡単な自由では我慢が出来ないのね、人間といふ《存在》は。欲張りね!
――欲張りかもしれないけれども、つまり、しかし、不可能事に目が行かない《存在》といふのもどうかしてゐるぜ。つまり、現状に満足してゐたならば、つまり、其処に新たなものは何も生まれやしない。つまり、ヴアン・ゴツホにしろブレイクにしろ等伯にしろ若冲にしろ、現状に満足してゐたならば、つまり、これつぽつちも絵なんぞ描きやしないし、況してブレイクは詩なんぞ書きやしなかつた。つまり、其処には自由もへつたくれもありやしない。つまり、其処には不可能を可能にするべく、つまり、悪戦苦闘の軌跡しか残つてゐない。つまり、諸行無常に抗ふ諸行無常と言つたらよいのか、つまり、不可能への絶えざる肉薄を諸行無常といふならば、つまり、諸行無常から恒常不変な創造物が生まれる。つまり、諸行無常なくして恒常不変は無いんぢやないかといふ気がする。
――さうね。でも其処には絶えざる諸行無常への抗ひがあるのね。ああ、難しい!
と、ここで雪が呻いたので私は軽く微笑まざるを得なかつたのであつた。
――つまり、一方で断念といふものもある。
――断念ね……。
――つまり、断念する自由。
――断念も自由か……。
――つまり、何かを選べば何かを断念せざるを得ない。
――さうよね。何かを選べば何かを断念せざるを得ない。
――つまり、断念するのにも身命を賭して断念する。つまり、さうでないと時代を超越する創作など出来やしない。つまり、君は身命を賭した選択といふものをした事があるかい?
――う~ん、あると言へばあるし、ないと言へばないとしか言へないわね。西洋哲学を専攻したのは或る意味身命を賭した選択だつた筈なんだけれども、今は東洋思想にのめり込んでゐるこのざまだわ。
――つまり、それは学びの途中だからだよ。つまり、何かを創作するには、つまり、身命を賭して別の何かを断念する外ない。つまり、例へば、それは現世利益だつたりするけれどもね。そのための途中の学びは取捨選択の自由の外にも全てが自由さ。何を学んだつて構ひやしない。つまり、君もその時期が来たならば、つまり、何かを断念して何かを身命を賭して選択する時が必ず来る筈さ。つまり、身命を賭して何かを選択しなければならない、つまり、のつぴきならぬ時期が必ず来る。
――……。
――つまり、君も真剣に生きてゐるからね。
――うふつ、有難う。
――それにしても、つまり、諸行無常は如何ともし難い宿命だと思はないかい?
――宿命ね……。
――僕は、つまり、主体は各各《個時空》、つまり、《個時空》は渦巻いてゐるものなんだが、その《個時空》を生きてゐると考へてゐるんだが……。
――《個時空》? 《個時空》つて何?
――簡単に言へば、つまり、《主体場》の事さ。
――《主体場》?
――さう。つまり、主体が置かれてゐる此の世の時空間は流れ移ろふものだらう?
――さうね、時は流れるとか時は移ろふとか言ふものね。
――つまり、流れあるところには、つまり、必ずカルマン渦が発生する筈だと僕は看做してゐる。
――カルマン渦? カルマン渦つて?
――つまり、カルマンといふ人が発見したんだが、つまり、自然界で発生する渦全般の事だよ。つまり、台風がその一例だね。
――川面に生じる渦の事?
――さう。つまり、例へば、川の流れが大いなる時間の流れだとすると、つまり、其処に生じたカルマン渦の一つ一つが主体の《個時空》と看做せる。
――カルマン渦が《個時空》? まだピンとこないわね、うふつ。
――つまり、君も物理学の初等は解るよね。つまり、距離が時間に、時間が距離に変換出来る事を。
――ええ、解るわ。
――そして、つまり、主体と距離が生じるといふ事は、つまり、それは主体から見ると過去に過ぎないといふ事も解るよね。
――ええ、夜空の星辰が何億年もの過去の姿だといふ事なら知つてゐるわ。それと同じ事ね。
――さう。つまり、主体と距離が生じる事は、つまり、主体が現在だと看做しちまへば、つまり、外界は全て過去といふ事になる。その過去の、つまり、距離の拡がり方は主体を中心とした渦時空間を形成する事になる。
――主体が現在とはどういふ事かしら?
――つまり、《個時空》またはそれは《主体場》と呼んでもいいんだが、つまり、《個時空》の中心といふ事さ。つまり、主体は主体から距離が零だから、主体は現在といふだけの事さ。
――つまり、主体から主体は距離が無いから物理学的に言つて唯の現在という事なのかしら?
――つまり、《固有時》といふ考へ方は解るかい?
――《固有時》?
――つまり、僕と君はそれぞれ違つた時間の流れ方をする時計を持つてゐるといふ考へ方は解るかな?
――相対的といふ事ね。時間の流れは全ての主体にとつて同一ではなくて各各固有の時間が流れてゐるといふ、ええつと、相対論だつたかしら、アインシユタインの相対論の考へ方ね。さうでしよ。
――さう。つまり、時間は相対的にしか《存在》しない。つまり、主体各人が各各固有の時間、つまり、《固有時》を持つてゐるといふ事さ。そこで、つまり、主体は主体から距離が零だから主体各各は全て固有の現在に《存在》する。もつと正確に言ふと、主体の現在は主体の表皮のみ、つまり、それをずばりと言つてのけた表現で言へば仏教用語でもある《皮袋》であつて、更に言へば主体の内部は主体から、つまり、距離が負故に、つまり、時間が逆巻く故に、つまり、其処は主体の未来になる。
――主体内部は負の時間、さうねえ、かうかしら、時間が逆回転して進むやうにしての未来といふ事かしら?
――さう。つまり、主体内部は主体自体から距離が負だから唯単に計算上未来といふ事になる。そして、主体《存在》が有限且主体《存在》の内部に中心があるといふ事は、つまり、主体の死を暗示してゐる。つまり、《存在》物は内部を持つ事で、つまり、自らの死を内包した《存在》としてしか此の世に《存在》出来ない。つまり、この考へ方を総じて僕は《個時空》と名付けてゐる。
――すると、あなたにとつて私はあなたの過去の世界に《存在》してゐるといふ事?
――さう。君は僕にとつて過去の世界に《存在》してゐる。しかし、つまり、君と僕との距離が、相対論で見ると、つまり、無視出来る程に小さいのでお互ひに全く同一の現在にゐるやうに看做せてしまふけれども、相対論は光速度が基本になつてゐるから、つまり、理論物理の世界では、つまり、 僕と君の距離は、つまり、光速度においては無視出来るかもしれないけれども、しかし、つまり、僕も君も光速度では動かない、つまり、理論物理では無視出来ても、現実では無視しちやならない、つまり、僕と君との間に横たはる距離、つまり、正確にいへば僕の《個時空》では君は過去に《存在》してゐる。
――すると、私からするとあなたは私の過去に《存在》してゐるといふ事ね。何となくだけれども、あなたのいふ《個時空》または《主体場》といふ考へ方が解つたやうな気がするけれども、まだまだピンとこないわね、うふつ。
――つまり、それでいいんだよ。つまり、《個時空》といふ考へ方は僕特有の考へでしかなく、つまり、一般化なんかされてゐないんだもの。つまり、誰も現在が主体の表皮、つまり、《皮袋》でしかなく、しかも有限的に《存在》するといふ事は未来の死を内包してしまつた宿命にあるなんて考へないもの。
――さうねえ。あなた独特の考へ方ね。その《個時空》といふ考へ方は……。
と、雪が言つたので私は軽く微笑みながら頷くのであつた。
――そこでだ。つまり、此の世に《存在》してしまつた以上、誰も時間を止める事は出来ず、また、時間から遁れられない。つまり、諸行無常だ。つまり、僕はこの諸行無常こそ《個時空》の宿命だと看做してゐる。
――宿命か……。
――つまり、大いなる時の流れの上に生じた、つまり、主体といふカルマン渦の《個時空》は、つまり、大いなる時の流れから見ればほんの束の間しか《存在》出来ない。人間で言へば高高百年位なものだ。
――あなたの言ふ大いなる時の流れつて宇宙大の悠久の時で見た時の時間の流れつて事かしら?
――さう。つまり、主体といふ《個時空》は、つまり、大いなる悠久の時の流れの上に生じた、つまり、小さな小さな小さなカルマン渦に過ぎない。つまり、その生滅は主体にとつては如何ともし難い。つまり、《個時空》の考へ方からすると大いなる悠久の時の流れの上に《個時空》といふカルマン渦が生じた時点で、つまり、そのカルマン渦の寿命は既に決定されてしまつてゐるに違ひないと思ふ。つまり、僕は決定論者ではないけれども、《個時空》は必ず死滅する。
――何か虚しいわね。
――さうだね。しかし、この虚しさは、つまり、受容する外ない。つまり、僕は宇宙すら死滅する宿命を負つてゐると看做してゐる。つまり、どんな《個時空》も死滅するといふ宿命からは遁れられない。
――だから、死滅する宿命に抗ふやうにして《存在》は不可能事たる恒常不変なるものを欣求するのよ。
――さうかもしれない。しかし、つまり、《個時空》が負ふ諸行無常は如何ともし難い。つまり、断念する事から何事も始まるんぢやないかな、恒常不変も。
――また断念ね……。
――つまり、僕は物事を単純化する事は嫌ひだから単純化する気はないんだけれども、つまり、何事も按配ぢやないかな、つまり、主体の自由度は。つまり、大いなる悠久の時の流れを重要視すればそれは信仰生活に近い生活になるし、カルマン渦の小さく小さく小さく渦巻くその渦を重要視すればそれは主体絶対主義ともいふべき、つまり、何とも摩訶不思議な生活になると思ふ。
――按配なのかしらね……、人生といふものは。
――つまり、やつぱり、其処には断念が厳然と《存在》する。つまり、誰しも己の《存在》に対して、例へば他の人生は選べないなど、断念した上で、例へば自由などと言つてゐるに違ひない。つまり、死の受容だ。つまり、己を死すべき宿命を負つた《存在》として、つまり、己を受容する外ない。それでも人間は日一日と生き長らへる。つまり、死すべき宿命にありながら、否、むしろ死すべき《存在》だから、つまり、尚更日一日と精一杯生きる。つまり、ここにはある断念が厳然としてあるに違ひない。
――諸行無常ね。人間は諸行無常を受容しつつも、それに一見抗ふやうにして生きてゐる、否、生きざるを得ない。つまり、其処に断念があるとあなたはいふのね……。
――つまり、断念すればこそ、人間は時代を簡単に飛び越える、例へばこのヴアン・ゴツホやブレイクや等伯や若冲のやうな創作物を作り果せる《存在》へと変容する。つまり、しかもそれはちやんと諸行無常の相の上に《存在》してゐる。つまり、これはそれだけで凄い事だよ。
と、その時、それ迄蛍光燈の周りをひらひらと舞つてゐた一匹の蛾が雪の目の前を通り過ぎ、私の眼前の本棚の画集にとまつたのであつた。
――きやつ、何?
それはやや灰色つぽい色を帯びた地味な配色の蛾であつた。
――何だ、蛾ぢやない……。
私は雪がその手で蛾を追い払ふのを制止し、暫くその蛾を凝視するのであつた。その蛾は地味な配色ながらも誠に誠に愛らしい姿をしてゐた。私は無類の虫好きなので、虫であれば何でも凝視せずにはゐられなかつたのであつた。私は虫こそ此の世の《存在》物の中でも傑作の部類に入る《存在》物と看做してゐたのである。卵、幼虫、蛹、そして成虫と完全変態を行ふ蛾は、正に此の世が生んだ傑作の一つに違ひなかつた。この二つの複眼で、蛾の方も私を凝視してゐたに違ひなかつた。さて、蛾にとつて私はどんな姿をした《存在》物として見えてゐるのであらうか。蛍光燈の明かりの下なので、多分、渦巻く奇怪な《存在》物として蛾には私が見えてゐたのかもしれなかつたが、それが解る術は全くなかつたのである。蛾の複眼は自然の眼の一つに違ひなかつた。吾吾が自然を見るやうに自然もまたその眼をかつと見開いて吾吾を凝視してゐるといふ感覚が、幼少時から私に付き纏ひ、決して離れる事のない感覚として感じられて仕方がなかつたのであつた。
私は蛾の複眼を凝視するのであつた。
暫くすると私はどうしても蛾に手を差し出して蛾を掌に乗せたくて仕様がなくなつたので、そつと手を差し出すと、蛾は安心しきつてゐたのか全く逃げる素振りを見せずにすんなりと私の掌の上に乗つたのであつた。
――相当の虫好きなのね、うふつ。
と、雪が微笑みながら言つたので、私も軽く微笑んで頷いたのであつた。
それにしても掌の蛾は美しかつた。そして、その軽さと言つたらこれ以上はありやしない程、それは計算し尽くされた軽さに違ひなかつた。蛾を蔽つてゐる細い小さな毛は、気持ちが良い程繊細であつた。私は掌の蛾をまじまじと暫く眺めた後は、その古本屋の戸口へ向かつて歩き出し、蛾を外に放してやつたのである。
――本当に虫が好きなのね、うふつ。
と、雪が言つたので私は再び軽く微笑んで頷くのであつた。
若冲も、私が蛾を見たやうに鶏を始め森羅万象をまじまじと見てゐたのかもしれなかつた。多分、穴の開く程凝視してゐたに違ひない。それぢやなきや、こんなべらぼうな画なんか画きつこない筈である。
私は雪に「行かう」と合図を送り、眼前に拡げられたヴアン・ゴツホとブレイクと等伯と若冲の画集を片付け、その中でブレイクの画集をその古本屋で買つたのであつた。
その古本屋の戸口で待つてゐた雪の肩を私はぽんと叩くと、そのまま歩を進めたのであつた。
――あつ、待つて、もう。
と、雪は再びその左手で私の右手首を優しくだがしつかりと握つて、再び二人相並んで都会の雑踏の中へと歩き出したのであつた。相変はらず、柔らかい白色の光を帯びた満月は東の空に浮かんでゐた。月の出の頃のあの毒毒しい赤色はすつかり姿を消し、満月は柔和そのものであつた。
人いきれ。学生や会社帰りの会社員等に交じつて、私達もまたその人波の中に紛れ込んだのであつた。相変はらず雪との間には何の会話もなかつたが、それはそれで心地良いものであつた。
と、不意にまた一つ、私の視界の周縁に光雲が現れたのであつた。その光雲もまた私の視界の周縁をゆつくりと時計回りに巡り、不意に私の視界の中に消えたのであつた。当然ながら伏目で歩いてゐた私は不図面を上げ、満月にぢつと見入るのであつた。白色の淡い光を放つてゐる東の空の満月は相変はらず柔和で何やら私に微笑みかけてゐるやうであつた。
私は再び伏目となつて、暫くは人波の中を歩き続けたのであつた。さうかうするうちに目的の喫茶店の前に着いたのである。私は雪をその喫茶店の前に連れ出すと、徐にその喫茶店の扉を開け、皆が待つてゐる店内へと歩を踏み出したのであつた。
第一章完
審問官 第二章「杳体」
出会ひ
私が勢いよくさっとその喫茶店の手動式のドアを開けると、
――カランコロン
と呼び鈴が鳴ったのであった。
私はLady first(レデイ・ファースト)を気取って雪を先に喫茶店内へと招き入れ、その後に続いて私がその喫茶店へ入ったのであった。
その喫茶店の店内は、店内全体を照らす照明は仄暗く抑へ気味であったが、各席に置かれた照明が皓皓と輝いてゐて、そして、店の造りは何処か山小屋を思はせる木造の内装が、奇妙に落ち着いた雰囲気を醸し出してゐたのであった。
私は、その仄暗い店内をぐるりと眺め回し、君達が陣取ってゐた席を見つけると、無意識に雪の手をぎゅっと握り、その席へと歩き始めたのであった。ぎゅっと握って、
――あっ。
と、思ひ、それにしても雪の手は仄かに温かく、しかし、夏の高温に対しては何処かひんやりとしてゐて、それは冷暖房がガンガンに利いた室内は大の苦手に違ひないと、その雪の手の感触から直感的に感じ取りつつも、それに構はず、私は雪の手を引きながらつかつかと君達が陣取ってゐた席へと一直線に歩を進めたのであった。私と雪に最初に気が付いたのは甲君で、
――やあ、杳体御仁。やっとご登場かい。
と、言ふと、乙君、丙君、丁君、そして君がそれぞれの本から顔を上げて、私と雪とを見たのであった。
そして、君たちと雪はお互ひに自己紹介をし、それを早早に済ませると、私と雪は相並んで末席に着席したのであった。そして、雪が、
――あの、杳体御仁とは一体全体何の事でせうか?
すると、甲君が、
――何ね、彼が呪文の如く唱へる《存在》へ対しての、つまり、カント曰く処の「物自体」のやうなものかな。
――えっ、杳体が「物自体」? まだ私には解かりませんわ。
――ええっと、雪さんは埴谷雄高の『死靈』を読んだことがありますか?
――ええ。
――彼によると、埴谷雄高の自同律の不快から発した「虚体」では生(なま)温(ぬる)く、その虚体をも呑み込む《存在》の有様が必ずあるに違ひなく、そして、《存在》はその有様、つまり、彼が言ふ《杳体》をもってして、此の宇宙の転覆を絶えず志向する、まあ、そんな処かな。
と、甲君は言ったのである。
甲君は画家志望で熱狂的にヴァン・ゴッホを崇拝する、所謂、「ヴァン・ゴッホ気狂(きちが)ひで、甲君は絵画といふ手段で何とかこの世界を認識し尽くし、己が納得する世界認識法を何としても手に入れる為に試行錯誤を繰り返してゐる青年なのであった。
――「虚体」をも呑み込む《存在》の有様? まだ私にはよく解からないのですが?
――何、彼本人が《杳体》と名付けたはいいが、未だ道半ばで、よく解かってゐないんぢゃないかな。
すると、雪は私へと顔を向けて、
――ねえ、《杳体》って何?
と、「黙狂者」の私へ尋ねたのであった。
すると、私はNoteを取り出して、
――つまり、虚無、若しくは、つまり、此の頭蓋内の闇の脳といふ構造をした、つまり、《五蘊場》にぽっかりと空いた虚空から、つまり、不意に顔を突き出して、つまり、『ほら、私を捕らへてみな!』と、つまり、皮肉たっぷりに言ひ残して、つまり、再び虚無、若しくは《五蘊場》の虚空へ、つまり、直ぐ様消えて、ところが、つまり、杳としてその《存在》を明かさない《杳体》は、つまり、ぢっと私の振る舞ひを凝視し、つまり、嘲笑ってゐる得体の知れぬ杳とした《何か》の事さ。
――つまり、それは例へば物質に反物質があるやうに、《存在》にも《反=存在》と名付けられる《もの》があるその《反=存在》と同じ様態の《もの》といふ意味と解していいのかしら?
――否、つまり、《杳体》は《反=存在》すらも呑み込んだ、つまり、《新=存在》の仮初の、つまり、若しくは仮象の姿さ。
――《新=存在》? あなたは此の現在にある《存在》の仕方を根本から転覆、若しくは真っ逆様に逆立ちさせるつもりなのね。
――つまり、ああ。
――でも、それを世界は今の処嘲笑ってゐるとしかあなたには認識出来ない杳として得体の知れぬ《何か》が、これって変な言ひ種だけれども、必ず《存在》してゐるといふ事ね?
――オイラーの公式が杳体御仁の言ふ《杳体》論の今の処命綱なのさ。
と、数学を専攻してゐながらヰリアム・ブレイク好きの乙君が口を開いたのであった。
――オイラーの公式と言ひますと?
――つまり、ネイピア数と呼ばれる数字をeとすると、e = 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 …と定まり、このネイピア数を使ふと、オイラーの等式、即ち、
が成立する。これは物理数学では最も重要な公式の一つでね、杳体御仁の彼はそのオイラーの公式をして、虚数iのi乗はオイラーの公式を使へば、【iのi乗】=【(ネイピア数eのi×π/2)のi乗】、つまり、eのiπ/2乗、即ちiのi乗は0.2078795……といふ実数になり、虚数だった《もの》がその正体を現はす、といふ事が、彼の言ふ処の《杳体》の何かを暗示してゐると彼は考へてゐる。まあ、とんだ素人考へだがね。
と乙君が言ふと、
――虚数iのi乗は実数? それは面白いですわ。
――さうすると、埴谷雄高が全人生をかけて追ひ求めた《虚体》は、オイラーの公式を無理矢理にでも汎用すると、《虚体》は虚数iから発想されたものではなく、オイラーの公式
を《虚体》の何かを表象してゐる何かだと看做すと、《虚体》が実体へと相転移する何かと看做せるだらう?
――また、数学の知識をひけらかして、雪さんを煙に巻く気かね、乙君?
と、丙君が口を挟んだのであった。
――はっ、猊下殿。申し訳ありません。
とおどけて乙君が丙君に言ったのであった。丙君は皆から「猊下」と綽名され、さう呼ばれてゐる、将来雲水、そして、僧になるつもりの青年なのであった。
――私に言はせれば、オイラーの公式も夢幻空花(むげんくうげ)な《もの》でしかない。
と丙君は言ったのであった。
――ちぇっ、猊下は全て否定しないと気が済まないからな。
と乙君が言ふと、そこで雪が、
――あの、オイラーの公式、
って面白い公式ですね。
――あの、雪さんの専攻は?
と乙君が訊いたのであった。
――西洋哲学です。
――西洋哲学の中でも何を?
――実存哲学を。
――へえ、脱構築とかポストモダンではなく?
――ええ、私、脱構築もポストモダンも、結局のところ、何も語ってゐない、哲学とは言へない代物にしか思へないのです。
と、今度は君が雪と話し始めたのであった。
――ところが、私、西洋哲学には飽き飽きして、今は、印度哲学か仏教哲学かに専攻を変へようかと考えてゐるのです。正直申して、西洋哲学、つまり、一神教下の哲学がつまらないのです。
――つまり、それって、西洋で言ふ「虚無」では飽き足らず、印度や仏教で言ふ処の《無》に魅入られたといふ事だね?
と猊下たる丙君が言ったのであった。
――へっ、《虚無》は中中絵に描けぬ難物だ!
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が言った処、
――だが、ヴァン・ゴッホは渦を描いてゐるぜ。
と、乙君が言ったのであった。
――また、渦か! 皆黙狂者の彼に感化され過ぎていないかね? 君が言ふナビエ・ストークスの方程式、
非圧縮性流れ( )の場合、
と簡単化される。ここで は動粘性係数、
とか、ストークスの定理、
ここで S は積分範囲の面、C はその境界の曲線で、しかし、それ以上、物理数学では渦に迫れない、つまり、物理数学で渦は未だに正確無比に記述不可能な《もの》で、しかし、ヴァン・ゴッホは渦を「星月夜」などでしっかりと描いてゐるぜ。
と甲君が言ったのであった。
すると、乙君が、
――其処さ。
と言ったのである。
――あの、其処と言ひますと?
と雪が尋ねると、
――つまり、人間は、否、此の世に《存在》する森羅万象は、どんな《存在》でも渦を《認識》してゐる筈だ、といふ事が、《杳体》の淵源の一つなのさ。
と、君が口を挟んだのであった。
――ねえ、《杳体》の張本人のあなたはどう考えてゐるの? そのあなたが言ふ処の《杳体》って何?
と雪が私に尋ねたのであった。
――つまり、そもそも《存在》とは、つまり、杳として知れぬ《もの》だらう?
――そんな事、うふっ、大袈裟に言へば、人類はその全史を通して《存在》とは何ぞや? と問ひ続けて来た《存在》の一つに過ぎないわ。だから、私は、あなたの言う《杳体》と名付けた《存在》の何たるかが知りたいのよ。
と、雪は興味津津の態で私たちの会話を楽しんでゐたのが、その美しい表情に表はれてゐるのであった。
――つまり、今言へるのは、つまり、オイラーの公式然り、つまり、《虚体》然り、と、それだけしか言へないのが本当の処さ。
――それぢゃ、ずるいわ。何の説明にもなっていないぢゃないの?
と、雪が言ふと、数学を専攻してゐる乙君が容喙したのであった。
――此の世が複素数で成り立ってゐるならば、実体は無限の虚数的なる《存在》の相、つまり、それを此処で《虚=体》と名付ければ、実体の実相は無限にあるといふのが正解といふ事さ。
――《虚=体》? 《虚体》ではなく、=で虚と体とを繋いだ《虚=体》? 面白い表現ね、うふっ。でも、cogito,ergo sumをその《虚=体》は超越出来るのかしら?
――「黙狂者」の彼が言ふには、肉体と精神といふ「現存在」のありふれた捉へ方は、複素数、つまり、肉体が実部に、虚部が精神に相当するといふ事らしいぜ。
――でも、それは誰しも一度は夢想することぢゃないかしら。私もさう考へたことが確かにあったわ。
――それぢゃ、話は早い。雪さんは肉体と精神といふ二元論的な思考法に与するかい?
――それで論理的に物事が語れるのであれば、私は積極的に肉体と精神の二元論的思考法を受容するわ。
と、此処で、私が次のやうにNoteに書いたのであった。
――つまり、それが、つまり、人間の錯誤でしかないとしても、つまり、君は肉体と精神といふ考へを、つまり、受容するのかい?
――ええ、それが錯誤であっても、《存在》に一歩でも近づくのであれば、私はその錯誤を錯誤として受け容れるわ。私思ふの、所詮、人間が考へることは多かれ少なかれ過誤であり、それでも、此の世の、そしてこの《吾》といふ《存在》の正体を何としても暴きたい欲求は、止め処なく、《存在》が《存在》する限り《吾》とは何ぞや? 《世界》とは何ぞや? と問ひ続ける宿命にあるに違ひないと思ふの。
――へっ、土台、人間は、懊悩するべき《存在》として「先験的」に《存在》させられる《もの》に過ぎないんぢゃないか?
と、画家志望の甲君が半畳を入れたのであった。其処で、
――《存在》の一番の快楽は何だと思ふ?
と、猊下たる丙君がおもむろに言ったのであった。
すると、私はNoteに、
――つまり、肉体と精神の一致!
と、書いたのであった。
――さう、肉体と精神の完全なる一致だ。肉体と精神が一致した刹那程、《存在》に快楽を齎す《もの》はないのだが、さて、それと紙一重に肉体と精神の完全なる一致は、反吐を吐きさうな程、不快極まりない《もの》でもある。
――でも、肉体と精神の完全なる一致など、《存在》が此の世に《存在》する限り在り得ぬ見果てぬ夢でしかないんぢゃないかね?
と、文学青年の丁君がぼそりと呟いたのであった。
――例へば、言葉は、それが発話され、記述される事で、《吾》の表象から無限に遠ざかる虚しさは誰もが知る処だらう?
と、丁君は更に続けたのであった。
――ふっ、君らしい意見だね。
と、君が丁君に言ったのであった。
――多分、肉体的なる《もの》と精神的なる《もの》、つまり、実部なる《もの》と虚部なる《もの》を統合する《存在》の在り方が、お前の言ふ《杳体》だらう?
と、猊下たる丙君が言ったのであった。
――否、つまり、今の処、つまり、あなたの仰るやうに《存在》を簡略化、つまり、若しくは腑分けしちゃ、つまり、《存在》を語る時には、つまり、その時点で駄目ぢゃないかと、つまり、思ひますが。
と、私はNoteに書き記したのであった。
――相変はらずまだ発話は出来ないやうだね、「黙狂者」君。しかし、そもそも言葉を発話する行為と書く行為、つまり、パロールとエクリチュールの断絶の溝に落っこちまった君は、絶えず湧出する数多の言葉の洪水に溺れながらも「つまり」といふ言葉を書き記すことで辛うじて君の思考の渦動を保持してゐる。何とも厄介なことだな、「黙狂者」君。
と、おどけてヴァン・ゴッホ気狂ひで画家志望の甲君が言ったのであった。しかし、その言葉には暗に、私の事ではなく、甲君自身がのっびきならぬ処で尚も自分の世界認識の仕方を試行錯誤してゐることが端的に表はれてゐる言ひ方なのであった。
――其処さ。「黙狂者」に堕す外なかった彼のDilemma(ジレンマ)があるのは。つまり、無秩序に彼の頭蓋内の闇に同時多発的に一気に発話されようと「言葉」が無数に生まれるのだが、其処には言葉を口から発する糸口が全く《存在》しない。つまり、彼の頭蓋内の闇、彼はそれを《五蘊場》と名付けてゐるが、その《五蘊場》に過去、現在、未来、即ち、去来現が《存在》せず、彼は発話に関してはお手上げ状態で、筆記する事でやっと時間の移ろひを堪へ忍び、彼は《他》に己の思考を伝へる事が可能なのだらう。
と、猊下たる丙君が言ったのであった。すると雪は、
――彼は、これまで一度も口を利いた事がない「唖」なの? つまり、彼は一度も発話と言ふ行為を経験した事がないの?
と、雪は君に聞いたのであった。
――いや、彼はもともとは話せたのだが、思春期を迎へた或る日、突然と話せなくなってしまったのだ。
と、君は言ったのである。
――ねえ、あなたが頭蓋内の闇、つまり、《五蘊場》だったかしら、その《五蘊場》で渦動する言語群と発話といふ行為が分断される事態に至ったのは、いざ、発話する段になると、あなたに纏ひ付く虚空に《吾》と《他》と間には踏み越え難い底知れぬ深淵を見てしまって、あなたはその深淵に眩暈を覚えて、《五蘊場》のみが卒倒するからなのね?
と、雪は私に尋ねたのであった。私はNoteに、
――つまり、或いはさうかもしれぬし、また、つまり、或ひは全く違ふかもしれぬ。つまり、私には発話して、つまり、言語を音波に、つまり、波に変へる機能がぶっ壊れてしまったのさ。そして、つまり、私は自身でも知らぬ間に発話を断念してゐたのさ。つまり、書くといふ行為を通して言葉の跡が追へる、つまり、言葉に、過去、現在、未来といふ去来現を、つまり、見出す事が辛うじて、つまり、私に残された言葉を発する行為なのさ。つまり、私はその矛盾、つまり、不合理を受容するしかないのさ。
と苦笑ひを私はする外なかったのである。
――そして、あなたは、《他》に言葉を発話出来ぬ故に、《杳体》だったかしら、その《杳体》と対峙する事が可能になったのだわ。
と、雪が言ったのであった。
――成程、彼が「黙狂者」にしか為り得ぬ故に、《杳体》の出現か――。
と、君が言ったのであった。
――そして、君は《存在》を簡略化したり、腑分けしちゃ駄目だと言ったが、しかし、人間、否、《存在》の思考法は物事を簡略化、つまり、抽象化せずにはをれぬ《もの》ぢゃないかね?
と猊下たる丙君が、虚空を凝視するやうに言ひ放ったのであった。
――ねえ、あなたの言ふ《杳体》はもっと解かりやすく言ふと何かにAnalogy(アナロジー)出来る《もの》なの?
――つまり、例へば、つまり、磁石さ。つまり、磁石は、つまり、何処まで切断してもN極とS極が《対‐存在》する。ところがある人達の予想には磁石は、つまり、磁気双極ではなく、つまり、単極、つまり、N極のみ、S極のみの、つまり、磁気単極子(magnetic monopole)の《存在》があるが、つまり、今の処、magnetic monopoleの《存在》はつまり、仮説の域を出てゐないが、しかし、つまり、この磁石におけるNSの双極子は、つまり、多分、つまり、何処まで行っても、つまり、切っても切れぬ《存在》、否、事象であって、NS極を例へば肉体と精神と見立てると、つまり、《存在》は何処まで切り刻んでも肉体と精神の両極、つまり、細胞一つになっても、また、つまり、DNAの分子をさらに切り刻んでも、其処には必ず肉体と精神がPairとなって《対‐存在》し、つまり、肉体と精神は、つまり、宿ってゐるに違ひない。
――それで、あなたの言ふ《杳体》は、つまり、何処までもその《存在》を切り刻んでみても、其処には必ず肉体と精神、いえ、意識の方がしっくりくるわね、必ず肉体と精神に還元できる意識が《対‐存在》してゐるといふ考へ方を森羅万象に拡大解釈してみた、それが《杳体》の正体でせう?
――つまり、或る一面では、つまり、君の言ふ通りなのだが、そもそも意識ってなんだと思ふ?
――え、意識?
と、雪はぽつりと呟いたきり何か物思ひに沈むのであった。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
相変はらず私が目を閉ぢれば、私の眼前の瞼裡の薄っぺらな闇には夢幻空花なる、私の見知らぬ全くの赤の他人の亡骸が呻き声にならぬ呻き声を発しながら、その赤の他人の彼が《存在》し、私もそれに加担してゐる《生》と《死》の狭間に開いてゐるであらうその虚空、それは私の虚空と断言しても構はぬに違ひないその虚空の何処ともしれぬ何処かへと、その赤の他人の彼は横たはり、ゆっくりと旋回しながら浮遊してゐるのであった。
――つまり、意識は、つまり、万物に、つまり、宿ると、つまり、思ふのかい?
と、私は雪に筆談で尚も尋ねたのであった。しかし、雪はぢっと黙ったままでゐるので猊下たる丙君が口を開いたのであった。
――君にとっては万物に意識は宿るのだらう?
――ああ。つまり、さういふ事だ。つまり、此の世に《存在》する以上、つまり、此の世の森羅万象には、つまり、意識は宿る、つまり、意識は《存在》するのさ。
と、私がNoteに書くと、丙君が
――君は意識は計量可能な何かだと思ってゐやしないかね?
――ああ。つまり、私は、つまり、意識の重さは、つまり、その《存在》の重さに、つまり、相関してゐると、つまり、看做してゐる。
と、私がNoteに書くとヴァン・ゴッホ狂ひの甲君が、
――すると「黙狂者」の君は、《意識≒重力》なんぞといふ何の根拠もない無謀な事を考へてやしないよね?
――――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
――つまり、さうだ。つまり、私は、つまり、《意識≒重力》は、つまり、此の世に、つまり、《存在》する《意識》なる《もの》を、つまり、計量する、つまり、世界認識の、つまり、仕方の一つに、つまり、為り得ると、つまり、看做してゐる。
と、私がNoteに書くと雪が突然、
――あなたの言ふ重力ってなんなのかしら? 私にはあなたの言ふ《意識≒重力》が何を象徴してゐるのかさっぱりわからないわ。つまり、あなたはBlack holeも何か得体の知れない意識の肥大化した《存在》と看做してゐるの?
――ああ。つまり、此の天の川銀河にせよ、アンドロメダ銀河にせよ、つまり、その中心に、つまり、あるといふ、つまり、巨大Black holeには、つまり、意識が、つまり、必ず、つまり、《存在》してゐる筈さ。
と、私がNoteに書くと、ぽつりと文学青年の丁君が言ったのであった。
――それは、とんでもない思考の飛躍、ちぇっ、飛躍するのは、しかし、思惟の宿命だがね、君の考へ方は、とんでもない飛躍の仕方をした全く無意味な独断でしかないぜ。
――つまり、独断で、つまり、いいんぢゃないかい?
と、私がNoteに書くと、
――また、それは何故にかね?
と、丁君がぽつりと呟いたのであった。
――つまり、私は、つまり、思惟がEnergie(エネルギー)に、つまり、変換可能な、つまり、《もの》と、つまり、独断的に看做して、つまり、ゐるが、さて、つまり、此の世に《存在》する、つまり、森羅万象は、つまり、Energieに還元出来ない、つまり、《もの》の、つまり、《存在》を、君は、つまり、認めるのかい?
と、私はNoteに書くと、文学青年の丁君が、
――そもそもEnergieって何の事だね?
と私に問ふたのであった。私はすかさず、
――つまり、意識さ。
と、Noteに書くと、雪が、
――一体全体あなたは何のことを話してゐるの?
と、目を爛爛と輝かせながら私に訊いたのであった。其処で私はNoteに、
――つまり、私達が、つまり、簡単に、つまり、意識と、つまり、呼んでゐる《もの》が、つまり、一体、つまり、何を、つまり、意味してゐるのか、つまり、己に問ふてゐるのさ。
すると猊下たる丙君が、
――「黙狂者」の君にとっては、万物に意識は宿ると看做したいのだらう。さうする事で君はやっと君自身の《存在》に我慢出来るのだらう。つまり、さうする事で君は君に喰はれる為に殺された《もの》の死肉の重さが意識だとする事で、やっと、君は君の《生者》たる《存在》に我慢が出来るのだらう? 違ふかね?
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
――まだ、あなたには誰とも知れぬ他人の亡骸の幻が見えるのね? そのあなたがいふ《意識≒重力》と思惟する事で、《吾》は救はれる?
と、雪が、目は相変はらず爛爛と輝かせながらも、その中に一つの暗い影がすうっと通り過ぎるのを私は見逃さず、そして、雪は痛痛しい心でもって私を凝視しながら、さう言ふと、丙君が猊下といふ綽名と言はれる所以たるに相応しい問ひを発したのであった。
――君が肉を噛み切る時の、その不快にして幸福なその一瞬を堪へ得るのに、《意識≒重力》でなければ、君は一日たりとも料理された《他》の死肉を喰らふ事が出来ず、その何とも知れぬ底無しの躊躇ひに《吾》を抛り出して、君は断食を直ぐでも始められる危ふさが君といふ《存在》には属性としてあるのだが、つまり、君は《他》の死肉の重さを意識へと還元する事でやっと料理を喰らふ事が出来、さうすることで辛うじて《吾》の《存在》を渋渋受容してゐるのだらう? 違ふかね?
――つまり、さういふ事だ。しかし、つまり、《吾》たる《存在》は、つまり、土台、つまり、《他》を、つまり、喰らふ事で、つまり、どうにかかうにか、つまり、《吾》なる《存在》を、つまり、存続させてゐるが、つまり、それでも、《吾》が、つまり、《存在》する事を、つまり、選ぶのであれば、つまり、《吾》は、つまり、腹を括って、つまり、《他》の、つまり、死肉を喰らふしかない。つまり、それは、つまり、此の世に、つまり、《存在》する、つまり、森羅万象にも、つまり、当て嵌まる事で、つまり、何かが《存在》するといふ事は、つまり、何かの《存在》を阻んでゐる。
――でも、《吾》は如何なる《もの》でも《吾》といふ《存在》に我慢してゐる事を、君は軽んじてゐるんぢゃないか?
と、ぽつりと文学青年の丁君が呟いたのであった。すると、雪が、
――さうだわ。《存在》も《非在》も共に懊悩の中で《存在》してゐるんだわ。ねえ、あなたは此の世の摂理は不合理だと思ふ? それとも合理だと思ふ?
――つまり、両方さ。つまり、何故って、つまり、《吾》の有様によって、つまり、合理でも、つまり、不合理でも、つまり、どちらにもなり得るからさ。
と、私がNoteに書くと、雪は、相変はらず目は爛爛と輝かせながらも、凌辱されたことでずたずたに裂かれてゐた心を私に受け止めてほしいかのやうに心を私に投げ出して、
――それぢゃ、《他》が《吾》を凌辱する事が合理であるか、不合理であるかは、《吾》が決定するのね?
――ああ。つまり、君は、つまり、その事を、つまり、《他》が《吾》を凌辱したことを不合理として、つまり、嫌悪する摂理がある。つまり、《吾》にとって、つまり、《他》は、つまり、《吾》にとって、つまり、或る時は食料になるが、つまり、それ以外では、つまり、《他》は何処まで行っても得体の知れぬ、つまり、化け物と同じさ。
――それでも、私に対する不浄の観念は何時まで経っても消えない《もの》よ。
――つまり、ねえ、つまり、雪、それ以上は語らなくて、つまり、もういいんだよ。つまり、君は今まで、つまり、その《吾》に、つまり、よく堪へて来たんだからね。
と、私は雪の凌辱された場面を実際に眼前に見るようにその夢幻空花なる有様を見続けながら、私がさうNoteに書くと、雪は、ぼろぼろと目から涙を流し、私をぢっと凝視しながら泣き出したのであった。と、其処で、この重重しく一変した空気を換へるべく、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が私と雪との間で交感してゐるその苛烈にして沈んだ心の状態を一気に吹き飛ばすやうに下らない地口を言ったのであった。
――飛んで分け入る奈津子の無視。それに三輪與志ならぬ皆善し、なっちって。
――ふふっ、御免なさい。私の事を気遣って下さり有難う御座います。
――誰も己の《存在》を苦虫を噛み潰すやうにその《存在》を受容してゐるのが、普通、《存在》する《もの》の道理であり責め苦なのさ。
と猊下たる丙君が自分で吐いた言葉を呑み込むやうに言ったのであった。其処で私はNoteに、
――雪、つまり、君は、つまり、自虐する、つまり、道理は、つまり、これっぽっちも、つまり、ないんだからね。つまり、そのことを、つまり、忘れずに。つまり、ほら、つまり、笑って。
――どうも有り難う。あなたにかかると何もかもお見通しなのね。
と、雪が泣きながら微笑むと、猊下たる丙君が、
――君たち二人に通う何とも言へない心の交感は、第三者から見ると超=自然的なのだがね。しかし、何となく君が「黙狂者」になっちまったのが解かる気がする。つまり、君の感受性が何かにつけても途轍もなく過敏に働くために、君は何事も発話出来なくなってしまった。多分、君には非科学的な感覚が生じてしまひ、最早喋る事が苦痛でしかなくなってしまった。さうだらう?
――ああ。つまり、さういふ事かもしれぬ。つまり、しかし、私にも、つまり、こればっかりは、つまり、如何ともし難いのさ。
――それでも彼は「黙狂者」である事を理不尽とはいへ、何の文句も言はずに受容する外ない、その《存在》自体がどん詰まりにある証左として、彼は「黙狂者」にしか為り得なかった己を受け容れたのだ。
と、猊下たる丙君が再び自身の吐いた言葉を呑み込むやうに言ったのであった。
――ねえ、あなたにとって自然の摂理って不合理な《もの》、それとも合理な《もの》のどちらかしら?
と、雪がまだ瞳から零れ落ちる涙を手で拭ひながら私に訊いたのであった。其処で、私は、再びNoteにかう書いたのであった。
――つまり、私にとって、つまり、自然は、つまり、元来、つまり、「先験的」に、つまり、不合理でしかない。
すると、雪が、
――どうしてあなたにとって自然は「先験的」に不合理なのかしら?
――つまり、私が、つまり、此の世に、つまり、《存在》するからさ。
――すると、あなたにとって《存在》はそもそも不合理でしかないといふの?
――ああ。つまり、《存在》は、つまり、何何系として、つまり、統合されて、つまり、秩序立てて、つまり、《存在》は、つまり、《存在》する外ないのだが、つまり、その《存在》の、つまり、秩序を、つまり、秩序足らしめるべく、つまり、《他》を、つまり、殺害する。つまり、《存在》は、つまり、それが《存在》する事で、つまり、《他》の殺害が道理となる故に、つまり、此の世といふ名の、つまり、自然は、つまり、私にとっては、つまり、不合理でしかないのさ。
――それがあなたの《存在》に対する、いいえ、違ふはね、ええっと、此の宇宙ね、あなたは此の宇宙に反旗を翻した根本の理由がそれなの?
――いや。つまり、それだけではないさ。つまり、《存在》する事の、つまり、《存在》は、《吾》が何たるか、つまり、全く雲を摑むやうに、つまり、全く解からず、つまり、仕舞ひで、つまり、それでも、つまり、《吾》は、つまり、《吾》として、つまり、《吾》が死滅するまでは、つまり、それが仮令未来永劫に亙ってゐようが、つまり、《吾》はずっと、つまり、《吾》であり続ける事を、つまり、「先験的」に、つまり、定められてゐる。つまり、そして、つまり、その理由は、つまり、ボブ・ディランの「風に吹かれて」ぢゃ、つまり、ないけれども、つまり、そのやうにしか、つまり、此の《吾》といふ《存在》を、つまり、《存在》とは言へない、つまり、《存在》する《もの》の、つまり、もどかしさの淵源が、つまり、此の宇宙の、つまり、《神》の別称かもしれぬ、つまり、此の宇宙にはあり、つまり、もしかしたならば、つまり、此の宇宙は、つまり、それ故に、つまり、《吾》は、つまり、《吾》として、つまり、《存在》し続け、つまり、その上に、つまり、この《吾》といふ、つまり、《存在》は、つまり、絶えず、つまり、何かへと、つまり、変容する事をも、つまり、強要されてゐて、つまり、それは、とんでもなく、つまり、理不尽な事だらう?
――そのための叛旗の旗幟が《杳体》なのね?
――ああ。つまり、さういふ事だ。
――でも、それは《杳体》と高く掲げた旗幟と共に此の宇宙の摂理に反旗を翻した処で、この《存在》の得体の知れなさ故に《吾》が掲げた《杳体》は端から此の宇宙の摂理に敗北する事は解かり切ってゐないかしら?
と、雪は、その刹那に瞳を一際ぎらりと輝かせ、しかし、頬には涙の流れた跡を手で拭った跡が付いたままで、しかし、きりりと私に問ふたのであった。
すると、
――一方で、夢は既に此の宇宙といふ途轍もない《存在》を震へ上がらせるには、その能力の限界が知れてしまったと言ふのさ、この「黙狂者」は。
と、文学青年の丁君が苦虫を噛み潰すやうにぼそりと言ったのであった。すると、雪が、
――どうして? 此の宇宙へ反旗を翻すのに夢が無力だなんて、それぢゃ、素手で武装した傭兵と戦ふに等しい愚行だわ。夢こそがあなたの言ふ《杳体》を支へる大黒柱になるんぢゃないのかしら?
――つまり、それは、つまり、埴谷雄高が試みたが、つまり、失敗してゐるのを、つまり、見れば、つまり、夢なんぞは、つまり、此の宇宙には、つまり、屁でもないのさ。
――しかし、夢を《杳体》の此の宇宙に対する武器として不使用とする理由が、まだ私には今一つ解からないわ。
――つまりね、「黙狂者」の彼にとっては夢は思惟を超えられないからさ。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君がにやりと嗤ひながら言ったのであった。
…………
…………
ねえ、君。あの当時私が無鉄砲に、しかし、用意周到に掲げた《杳体》なる《もの》は、その後、どうなったと思ふ? へっ、正直に言ふと、何の事はない、相変はらず杳として得体の知れぬまま、私のこの頭蓋内の闇と瞼を閉ぢた時の瞼裡に生じる薄っぺらな闇との間を、恰も永久運動する巨大な振り子時計の振り子の如く、自在に行ったり来たりしながら、
――《吾》、《杳体》為れり!
と、私は自身に向けて愚劣な苦笑ひを浮かべて、尚も、青年にありがちな、どこか夢見ながら実態が伴はない、何とももどかしいその《存在》をじっくりと堪能する外にない、つまり漠とした己を敢へて規定せずに、唯、抛りっ放しのままその《存在》の屈辱を唯唯、噛み締める外ないどん詰まりのままなのは相変はらずなのさ。嗤っちまふだらう? 口惜しいが、それが摂理といふ《もの》で、私が今、不治の病に呻くのもまた、愚劣極まりない此の世の摂理だ! 口惜しいがそれは認めるしかない。
…………
…………
――えっ? 夢が思惟を越えられないですって? それは逆ぢゃないかしら。夢こそが思惟を飛び越えられる唯一無二の《もの》であって、《存在》に「先験的」に賦与された如くに此の世に《存在》する《もの》は己の《存在》を自問自答する宿命にあり、また、此の寂滅する外ない此の世の森羅万象が、唯一、此の自然、若しくは神の摂理に反旗を翻せる《もの》こそ夢な筈だわ。
――言ふね!
と、雪の言葉に対してヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が、うれしくて堪らないといった満面に微笑みを浮かべて茶茶を入れたのであった。雪はそれに対して軽く笑みで返しながら、
――ねえ、あなたは何故に夢が無力と看做すの?
――多分、此奴は、夢もまた入れ子状のFractal(フラクタル)な構造をした此の世の摂理に忠実な何かとしか看做せなくなったのだと思ふよ。
と、君が言ったのであった。
――それは、あなたもさう信じてゐるのですか?
と、雪が君に尋ねたので、君は、
――いや、何ね。私は無責任かもしれないけれども、私には、何にも解からないのさ。
――いいえ、それこそ夢に対する自然な考へだと思ふわ。ねえ、あなたは、何をもって夢が、《存在》が《存在》を問ふ時の此の思惟を越えられない無力な《もの》と看做すやうになったのかしら?
さっきまで、自身に一生消せない悪夢に涙を流してゐた雪の顔には再び誰もが魅入られるに違ひない微笑みを浮かべながら、私に尋ねたのであった。
――いや。つまり、私は、つまり、夢を、つまり、《存在》する《もの》が、つまり、己の《存在》を問ふ時に、つまり、全く無力だなんて、つまり、言った覚えは、つまり、ない。つまり、唯、つまり、現在では、つまり、夢は、つまり、余りにも、つまり、背負ひ切れぬ《もの》を、つまり、背負はされ、また、余りに、つまり、夢は濫用されてゐて、つまり、夢が、つまり、本来持ってゐる、原初的でぶっきら棒な突破力を、つまり、喪失しちまってゐる。
――さうかしら。確かに現在、夢の濫用は目に余る《もの》があるわ。しかし、《存在》を問ふ時、夢を無視するのは、《存在》を半端な《もの》へと堕落させる陥穽に、《存在》を何か堕落した《もの》へと落とす虚無主義的な何かでしかないわ。
その雪の言葉を聞きながら、私は其処でゆっくりと瞼を閉ぢ、その瞼裡が現出する薄っぺらな闇を、そして、その視界の周縁を、つまり、その薄っぺらな闇の周縁を今もってぐるりと巡ってゐる、勾玉の形をした光雲をぢっと暫く凝視してから、徐に瞼を開けて、Noteにかう書いたのであった。
――つまり、例へば、つまり、《死》した《もの》が、つまり、何処へかと、つまり、呻きにならぬ呻き声を、つまり、『うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~』と、つまり、絶えず、つまり、自身の《存在》を、つまり、ぢっと我慢せざるを得ぬ、つまり、《もの》でしかない、つまり、としたならば、つまり、君は、つまり、雪は、つまり、その《死》といふ《もの》を、つまり、何の文句も言はずに、つまり、受容出来るかい?
――それは、私が《死》をどう思ってゐるのか訊いてゐるのね。でも、御免なさい。それは、今の私には手に負へない問ひなの。唯、ヰリアム・ブレイクやドストエフスキイなど、数多の先人達の作品が現在でも立派に通用する事に、『人間、此の変容せざり、而して変容する矛盾なる《存在》』などと思っては、精神のRelayのやうな《もの》が現実に《存在》するに違ひないと思って何とか生きてゐるのよ。
――精神のRelayか……。
と、文学青年の丁君が、自ら発した内部の憤怒を圧し潰すやうに、何とも感慨深げに呻いたのであった。
――あなたは、その精神のRelayを信じてゐるのですか?
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が雪に問ふと見せかけながら、猊下たる丙君、文学青年の丁君、そして、君と「黙狂者」の私の内、誰かの意見を引き出したい甲君の欲求は見え見えなのであった。それは、甲君の視線が、雪ではなく、吾吾の方を見廻しながら、にたにたと言った事でも明らかなのであった。
――駄目だぜ。君が私らの内、誰かしらの意見を待ってゐたって誰も語りはしないさ。
と、君が言ったのであった。すると、甲君が、
――やはり、ばればれか。どうも私は深奥で考えてゐることが、表情や語り口に出てしまふ正直者だな。しかし、それはそれとして、君は、精神のRelayなんて本当に可能だと思ふのかい?
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が君に尋ねたのであった。しかし、君の発言の機先を制するやうに話し始めたのは、雪なのであった。
――一寸、待って下さい。その精神のRelayについては、此の人と此処に来る前に古本屋に寄って、其処で議論、議論ぢゃをかしいわね、議論じゃなく筆談で、お互ひの考える処を問ふて来た処なの。
――それで、「黙狂者」は何と?
――例へば皆さんが今まで読解して議論してゐた筈のこのヰリアム・ブレイクの作品の数数が、ブレイクが既に百年以上も前に亡くなってゐるにも拘はらず、現在に生きる私達は、ブレイクの作品に触れられて、それを自身の思惟の淵源となるべく、何かを考へる契機として在り得る筈で、そして、ブレイクの作品に触れることでブレイクの精神に触れた感じを抱くのは、実際の所、事実だわ。
――つまり、雪さんと「黙狂者」は、少なくとも精神はRelayされる《もの》との結論に至ったといふ事だね?
と、猊下たる丙君が、これまた、在らぬ方を見やりながら言ったのであった。
――でも、精神のRelayは、作品が現代で見出されなければ、精神はRelayされるべくもないぜ。極論をすれば、現在売れてゐる作家の作品の殆どが百年後には人類から忘れ去られる憂き目にあって、精神がRelayされるなんて事は在り得ない筈だ。とはいへ、現在売れてゐる作家の作品ばかりではなく、ヴァン・ゴッホが好例だが、実作者が生きてゐる内には全く見向きもされずに人知れず歴史から隠されてゐた作品が、作者の死後百年以上も経った現在べらぼうな値段で取引されてゐる此の《生》の矛盾は、時代がどんなに変はらうが、常に在り得る筈で、本音を言へば、俺が描いた絵でさへもまた私の死後、百年後に評価される、ちぇっ、此のブレイクの作品のやうに作者の死後にその価値が一変し、評価が鰻上りになる事もまた、在り得べき筈だ。つまり、作品が残って初めて精神がRelayされる。しかし、ソクラテスや釈迦牟尼仏陀のやうに彼等が発した言葉が弟子によって伝承される場合もあるがね、しかし、精神が仮にRelay可能な《もの》ならば、それはとんでもなく確率が低い筈だ。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が自身を問ひ詰めるやうに言葉を吐き捨てると、私はNoteにかう書いたのであった。
――つまり、此の世は、つまり、《生者》より、つまり、常に、つまり、《死者》の数の方が、つまり、圧倒的多数であって、つまり、それらの、つまり、《死者》の、つまり、殆どは歴史の闇の中に、つまり、消え去ったまま、つまり、此の世で、つまり、現在に、つまり、生きる、つまり、《生者》に、つまり、発見されぬまま、つまり、歴史の闇に未来永劫消え去ったまま、つまり、見出されることはなく、つまり、そして、此の世といふ現在に作品として、つまり、残された《もの》が、つまり、現在においても尚、つまり、評価される事は、つまり、歴史上に、つまり、嘗て、つまり、《存在》した《もの》のほんのほんのほんの一握りの、つまり、圧倒的少数の作品群でしかない。つまり、歴史とは、つまり、《死者》の、つまり、精神の、つまり、生存競争でしかなく、つまり、それは、つまり、そのまま、つまり、《生者》にも、つまり、ぴったりと当て嵌まる《もの》で、つまり、而も、つまり、《生者》の《存在》の、つまり、有様を見れば、つまり、《生者》は、つまり、即座に、つまり、《死者》へと瞬時に変容可能な、つまり、《生》のどん詰まりで、つまり、《生者》は、つまり、生き延びねばならない。つまり、此の世の不合理極まりない、つまり、それを、つまり、摂理と称して、つまり、何の文句も言はずに、つまり、《生者》は、つまり、受容してゐるが、つまり、此の不合理は、つまり、私には、つまり、全くもって、つまり、否として、つまり、摂理に対して、叛旗の、つまり、狼煙を、つまり、《杳体》といふ、つまり、《もの》を旗幟に、つまり、此の世の、つまり、不合理極まりない、つまり、摂理に、つまり、反旗を翻さなければ、つまり、《存在》が、つまり、此の世に、つまり、《存在》した証左には、つまり、値しない、つまり、と思ってゐるのだ。
――それは前に伺った気がするのですが、あなたが、何故、《存在》を生む此の宇宙へ反旗を翻して、此の世に「あっ」と言はせる事に全身全霊を傾注してゐるのかも、はっきり申しまして、私には今も尚、よく解からないの。私は女性だから、明言しますが、子を産む事は全的に肯定されべき《もの》の筈だわ。
と、雪は、再び目尻に涙を浮かべて、そこからぽろりと涙を落としながら、私に訴へかけるのでした。
――へっ、女性を泣かせたな、この「黙狂者」君。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が嫌味を言ったのであったが、それは甲君の性癖なのであった。ときどき茶茶を入れる甲君は、実は、深刻な存在論的な壁にぶち当たってゐて、それを悟られまいと、反射的に甲君は誰に対しても半畳を入れなければ、自分の倦み疲れた内実の《吾》が何時顔を出すのかびくびくしながら、いつも一見するすると明朗な振舞ひが彼の持ち味であるかのやうに振舞ふのであった。しかし、それは、甲君が人一倍《他者》の悲哀に敏感であったことの証左でもあったのだ。
――御免なさい。また泣いてしまって。でも、あなたは、己の《存在》を最期は全肯定する可能性は全く零だと看做してゐるのかしら?
――多分、「黙狂者」にも、それは、解からぬ筈だ。唯、「黙狂者」は、日日、命を削って何とか生きてゐるのは間違ひない。
と、文学青年で、色白の丁君が、相変はらずさう言った自分が許せぬ何かのやうに、苦虫を潰したやうに顔を奇妙に歪めながら、歯切れ悪くもさう言ひ切ったのでした。
――へっ、今日もまた、議論の中心は此の口の利けない「黙狂者」か――。
ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が皮肉を込めて言ったのであった。
――しかし、「黙狂者」が掲げた《杳体》がどう深化を遂げるのかは、興味のある事だぜ。
と、猊下たる丙君が、天井を見上げながら言ったのであった。
――ねえ、率直に訊くわね。あなたは自分の子が欲しくないの?
と今もぽろぽろと涙を流しながら、多分、雪の内面では男に凌辱された悪夢に腸(はらわた)が煮えくりながらも、雪は私に或る希望のやうな《もの》が見出せるかもしれないといふ、藁をも縋る思ひで私の後に付いて来て、此の喫茶店迄やって来たのは、私にも痛いほど解かるのであったが、これは、しかし、時間が解決するのをぢっと待つしかない問題でもあると、私は心の何処かで達観してゐたのは間違ひない事であった。多分に、その私の振舞ひが、雪を苛苛させてゐたのもまた確かな事であった。
――つまり、それは、私にとっては、つまり、どちらでも、つまり、構はぬ事なのさ。
――それでは、あなたは、唯、此の世に反旗を翻すのみの自己満足だけに生きるといふ事なの?
――さう。自己満足だ。つまり、私は、つまり、現在、つまり、自己満足が何としても希求されるべき《もの》だ。つまり、現時点では、つまり、私には、つまり、さうとしか言へないのだ。
――あなたは、直言しますが、未来の《存在》を信じてゐるのですか? それと、あなたは《存在革命》などといふ夢想に耽溺して己の遣り切れない魂の捌け口にしてゐませんか?
――……否。つまり、自発的に、つまり、《存在》の変容が切迫してゐなければ、つまり、《存在革命》なんてありもしない、つまり、虚妄、つまり、でしかない。つまり、自然や、つまり、環境や、つまり、世界、つまり、と呼ばれている、つまり、外界が、つまり、《存在》を、つまり、世界の変動に、つまり、順応するべく《存在》する、つまり、《存在》は、つまり、たったそれだけの、つまり、理由で、つまり、絶えず、つまり、変容する事を、つまり、強要されてゐる。
――だが、真似ぶ事で、《存在》する《もの》は、精神をRelayしてやしないかい?
と猊下たる丙君が、まだ天上を見詰めながら言ったのであった。
――ねえ、そもそも《存在》が変容する事は、悪なのかしら?
――つまり、現時点では、つまり、変容は、つまり、或る《存在》の、つまり、有様の変貌を、つまり、意味してゐて、つまり、また、つまり、現在、つまり、《存在》してゐる《もの》から、つまり、突然変異でも、つまり、何でもいいから、つまり、《新=存在》の、つまり、出現が、つまり、待望されている。
――でも、それは、メシアの待望と何が違うのかしら? 此の世の摂理として、此の世に《存在》してしまった《もの》は、その摂理を甘受すべきなのが道理ではないのかしら?
――否。つまり、甘受すべき、つまり、摂理といふ《もの》は、つまり、即座に、摂理に抗ふ事、つまり、主体は、つまり、摂理を唾棄する《もの》と、つまり、痩せ我慢してでも、つまり、その摂理とやらに、つまり、抗ふ事で、つまり、正覚出来てしまふかもしれぬし、つまり、或るひは、自然との同化によって、つまり、柳に風の如く、つまり、自然と調和すると、自在なる自我の境地が、つまり、得られるかもしれぬ。つまり、どちらにせよ、つまり、《存在》の変容は、つまり、自発的に起る事は、つまり、不可能なのさ。つまり、不可能故に、つまり、主体は、敢へて此の世の摂理に抗ひ、つまり、それでも、つまり、《存在》は自発的なる《存在の変革》を為すべく、つまり、日日奮闘してゐる。つまり、それが、つまり、大きな意味で、つまり、己の為なのさ。つまり、何故って、《存在》は、つまり、此の世の摂理を含めて、《存在》そのものが、つまり大いに反吐が出る程不快だからさ。
――それでこそ、《杳体御仁》が《杳体御仁》たる所以だな、「黙狂者」君!
と、此処で再び甲君が茶茶を入れたのであった。
――それよ。あなたの《杳体御仁》といふ綽名は、あなたが私には未だに理解不能なあなたが思惟する《存在》といふ大海にぽつねんとあなたがしがみ付く、うふっ、あなたにはそれしか出来ないのよね、その《存在》といふ大海であなたがしがみ付く浮き袋の如く、貴方の思惟の中心に居座ってしまったのが《杳体》ね。それでやっと、あなたは此の世を生き延びてゐるのだわ。
――それは雪さんの言ふ通りだな。この《杳体御仁》たる「黙狂者」は、最早、《存在》といふ未だ深い霧に包まれたままの大海でこの《杳体》といふ浮き袋無しには、一時も生きてられやしない。
と、君が私を見詰めながらさう言ったのであった。すると、雪が君に、
――では、あなたに伺ひますが、彼が黙すると同時に《杳体》といふ訳の解からぬ観念が彼の内部に生じたのではありませんの?
――ああ。多分、雪さんの言ふ通りだ。或る日、彼は、忽然と《杳体》といふ名ばかりの観念が棲み付いた刹那、かれは去来現無くしては語る行為は不可能な、言語に内在する去来現の時の移ろひを喪失した代はりに《杳体》といふ観念を、哀しい哉、手にしてしまった。
と君が言ったのであった。
――ねえ、あなた、それは何故なの?
と、雪が私に訊いたので、私は、かうNoteに書き記したのであった。
――つまり、あの日は、つまり、不思議な、つまり、夢を見た日だったが、つまり、それが事の始まりだったのだらうが、つまり、その、つまり、その夢といふのが、つまり、黄金色に輝く、つまり、黄金の世界、つまり、それは眩い、つまり、黄金色の世界に、つまり、夢が占拠されてしまってゐて、つまり、そして、つまり、その黄金色の眩い世界には、つまり、一体の仏像、多分、それは、盧舎那仏だった気がするが、つまり、その一体の、つまり、仏像が、つまり、何かを語ってゐるのではあるが、つまり、私には、つまり、その仏像が、つまり、語ってゐる言葉が、つまり、全く理解出来ず、つまり、それでも、つまり、その仏像は、つまり、蜿蜒と、何かを、つまり、私に、つまり、語りかける、つまり、そんな奇妙な夢を、つまり、見たのさ。しかし、つまり、その仏像は、つまり、今、つまり、考へると、つまり、私が見知らぬ、つまり、全くの赤の他人の、つまり、死を、つまり、丁度その時刻に、つまり、その死者が、つまり、一体の仏像として、つまり、私の夢に、または、つまり、私がその死者の夢へ、つまり、赴いたのかは、つまり、解からぬが、つまり、その黄金色の仏像を、つまり、一瞥した刹那に、つまり、不思議な事に、つまり、事の全てを、つまり、了解してゐて、つまり、私は、つまり、その時以来、つまり、絶えず、つまり、私を通って、つまり、死者が、つまり、多分、つまり、憑依し、つまり、私に、つまり、その黄金が眩い、つまり、黄金の世界で、つまり、私には、つまり、訳が解からぬ、つまり、何かを、つまり、話してゐて、つまり、多分、つまり、私がその黄金の仏像が、つまり、何を、つまり、話してゐるのか、つまり、理解出来れば、つまり、私は、多分、発話能力を再び、つまり、獲得出来て、つまり、その時こそ、つまり、私は、つまり、《杳体》が、つまり、何なのかを、つまり、理解する筈だ。つまり、それまでは、つまり、私は、つまり、絶えず、つまり、赤の他人の、つまり、死者に、つまり、憑依され、つまり、続けるしかないのさ。
――それは私にもあなたに会って直ぐに気が付いたことだわ。『この人には見も知らぬ他人の死者が見えてしまふ』とね。今にして思ふととても不思議なのだけれども、何だかあなたとは心の会話が可能なのよね。不思議。
――つまり、私は、つまり、訳の解からぬ、つまり、事を、つまり、死者が、つまり、私の内界に、つまり、拡がる、つまり、闇を、つまり、通って、つまり、何処とも知れぬ、つまり、彼の世があるのであれば、つまり、彼の世へ、つまり、往く間、つまり、その一体の黄金の仏像は、つまり、絶えず、つまり、私が理解不能な、つまり、言語でもって、つまり、ずっと語り掛け続け、つまり、さうして、つまり、私の内部に、つまり、その一体の黄金の仏像が、つまり、棲み付いてしまったのだ。つまり、それ故に、多分、つまり、私は発話能力を、つまり、喪失してしまったのさ。
――それは神秘体験ね。よくイタコの人に口寄せが起こるのに類似した神秘体験だわ、きっと。
と、雪が言ふと、数学専攻でヰリアム・ブレイク好きの乙君が、
――雪さんは、幽霊を、若しくは精霊を信ずるかい?
と、訊いたのであった。すると、雪は、
――ええ、信ずるわ。でも、私は幽霊よりも今は無を信ずるわ。
と、言ったのであった。
――無ね……。
と、猊下たる丙君と、数学専攻の乙君が同じように呟くのであった。そして、雪は更に続けたのであった。
――しかし、あなたは、そのあなた自身理解不能な事に直面して「黙狂」に陥ったにも拘はらずに、そんな事はお構ひなしで、あなたに愛情を持って接してくださる此の方方を大切にしなくちゃね。それは、あなたにとって最大の慈悲に違ひないわ。
――つまり、慈悲? つまり、それは、つまり、私の内部に、つまり、棲み付いた、つまり、一体の仏像の、つまり、慈悲だね?
――ええ、さうよ。
と、雪の言葉を聞きながら、私はゆっくりと瞼を閉ぢると、相変はらず誰とも知らぬ私とは全く赤の他人の見知らぬ誰かが、私の瞼裡の薄っぺらな闇に浮かびあがって、
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
と、呻き声にならぬ呻きを発しながら、何処へかに向かって浮遊してゐるのであった。
と、その刹那、再び光雲が二つ分かれながら、私の瞼裡の薄っぺらな闇の視界の周縁を一方は時計回りで、もう一方は、反時計回りでカルマン渦よろしく巡るのであった。
私は、それを確認すると再びゆっくりと瞼を開けて、雪の顔を何となく見詰めたのであった。すると、雪が、
――また、あなたを死者が通り過ぎたのね。貴方の目にはまた、渦が見えるわよ。
――雪さんには《杳体御仁》が見えてしまふ、その死者の気配が解かるといふのかね?
と、猊下たる丙君が、雪に尋ねのであった
――ええ。不思議なのですが、あなた、あなたはさっき、此の人と一緒にゐたから解かると思ひますけれども? どうかしら?
と、雪は君を見ながら続けたのであった。
――此の人、私の頭に手を置いた刹那、卒倒した時、私は此の人が名状し難い私の過去の出来事、これはまだ、私は他人に語れる程には心身が落ち着いてないのですが、しかし、此の人は私の過去のその出来事を一瞬で見通したらしく、そして、此の人に或る死者が憑依した事が、これを第六感っていふのかしら、とにかく、私にはそれが疑ふべからざる全うな真実として受け取るしかなかったのです。不思議ね。私に、第六感みたいな能力があるなんて、此の人と会ふまで全く解からなかったのよ、《杳体御仁》さん。
と、雪は君を見てゐた顔を私に振り向けながら、それは窈窕なる美しい笑顔で私に語りかけるのであった。
――これは初耳だな、丙君。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が飄飄とした趣で言葉を発したのであった。そして、甲君は更に続けて、
――この《杳体御仁》は、金色の仏像の夢については、これまでも言及した事はあったが、彼の身に死者が絶えず憑依してゐた事は全くおくびにも出さず、唯、何かに堪へてゐる様をそれとなく表はすだけで、彼の内界に激変が絶えず起こってゐた事には全く気が付かなかったぜ。この、水臭いぜ、《杳体御仁》の「黙狂者」君!
――さういふあなたは、幽霊を信じますか?
と、雪が、甲君に尋ねたのであった。すると、甲君は、
――霊性なる《もの》は信ずるけれども、幽霊となると話は別なやうな気がして何とも言へないな。
――それはまた何故に幽霊に関しては何とも言へないのでせうか?
――何ね、《生者》よりも圧倒的に《死者》の数は多い此の現実において、幽霊が《存在》するとなると、《生者》は肩身の狭い《存在》でしかなくなってしまふ、つまり、あらゆる場面で《死者》が優位といふ世界に《生者》は堪へられるのかな、と、思ふのさ。
と、甲君が尚も飄飄と言ったのであった。
――でも、《生者》は「先験的」に《死者》の《存在》を受容してゐるのではないかしら?
――さうだね……、確かに吾吾が此の世に《存在》するのは、数多の《死者》が《存在》したが為だが、だから、それ故に尚更《生者》は《死者》に対して《生》故に存在論的に優位でありたいのであって、また、《生》と《死》は断絶した《もの》として、つまり、《生》と《死》はそんなに簡単に飛び越えられぬ巨大な壁で仕切られた《もの》であってほしいのが《生者》の願望だらうけれども、そんな《もの》は、例へば大災害を前にすれば一気に吹き飛んでしまふ《生者》の憐れな、そして、ちっちゃな願望でしかなく、《生》と《死》を分けること自体が無意味な事だと、十分に納得はしているけれども、更に言ふと、《生者》は心の何処かでやっぱり《死者》よりも《生》として現存してゐるだけで《生者》が「先験的」に優位な《存在》だと、敢へて誤謬したまま日常を生きてゐるのは否定できないんぢゃないかな。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が、更に飄飄と言ったのであった。すると、雪が、
――さうしますと、《生者》は生まれながらに存在論的には《死者》に対しては傲慢といふ事ですわね。何故って、此の世の大部分は《死者》によって創られた産物だらけで成り立ってゐて、それは《生者》にはどう仕様もない事なのだから。つまり、《死者》達の歴史無くしては、《生者》は一時も生きられぬといふ事だと思ひますが、違ふでせうか?
――歴史ね。例へば図書館が好例だと思ふが、其処に所蔵されてゐる本の殆どが既に鬼籍に入った《死者》達が遺した作品に違ひないが、此処で極論を言ふと、譬へ図書館といふ先達が遺して呉れた遺産が近隣にあらうとも、《生者》にとって図書館は生きるのに必要欠くべからざる《もの》かと問はれれば、『いいえ』と答へる筈で、《生者》にとって最も大事な事はその日をどう暮らして行けばいいのかといふ事のみが何よりも優先され、大概は、その日の糧が得られればそれで満足の筈なのもまた、真なり、だ。しかし、その日の糧を得る仕方は先達達の仕方を踏襲してはいるがね。
と、尚もヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が飄飄と言ったのであった。すると、雪は、幽かに微笑んで、
――しかし、「人は麺麭のみに生くるに非ず」といふ基督の言葉が今も生きてゐるやうに、《生者》はその時の食べる麺麭は、成程、大事な事かもしれませんが、《生者》の《生》はそれだけに、つまりは、衣食住が満ち足りる事のみでは《生者》は生きられないといふ考へ方はをかしいかしら?
――ちっともをかしくなんかないです。寧ろ、雪さんの言ふ事の方が正解に近い筈なのですが、しかし、現代ではかう言へます。つまり「人は麺麭のみに生くるに非ず。唯、楽を徹底して欣求する《存在》になりし」といふのが、現実の実相だと思ひます。
と、尚も甲君は飄飄と言ったのであったが、雪はその言葉にちっとも納得がゆかなかったらしく、更に甲君に尋ねたのであった。
――甲さんは、それでは、楽を追求してゐるのですか?
と、雪が尋ねると、甲君は奇妙に自己卑下した嗤ひを口辺に浮かべて、
――いいや、ちっとも。
と、言ったのであった。その時、
――「人は麺麭のみに生くるに非ず」か……。
と、猊下たる丙君がぽつりと呟いたのであった。
――楽は、つまり、煎じ詰めれば時間の事だらう?
と、数学専攻の乙君が言ひ、更に文学青年の丁君が、
――だが、殆どの人間は、その日の暮らしに汲汲としてゐる、つまり、「人は麺麭のみに生くる」といふ事の方が真実として看做すべきぢゃないかと思ふのだが、……しかし――。
と、尻切れ蜻蛉にはたりと言葉を呑み込んでしまった丁君は、君を見て、君の言葉を待ち構へてゐるのであった。其処で、君は、
――丁君、《生者》が《生》の側に《存在》する以上、人は麺麭を求めつつも、己の出自、若しくは《存在》に関するあらゆる事に興味を、そして、苦悩を抱き、そして明日こそは、何かが少しでも解かるかもしれぬといふ淡い希望を胸に、此の世に《存在》する森羅万象は、何とか《存在》してゐるのぢゃないかね?
と、君が丁君にさう言ったのであった。
――うふっ。人間って《もの》は、基督が生きてゐた二千余年前とちっとも変わってゐないのは確かね?
と、雪が微笑みながら言ふと、雪は更に続けて、
――そして、基督の亡霊は確かに此の世に《存在》してゐて、その基督の亡霊、しかも、その基督の亡霊は、今も尚、磔刑に処されたままの無惨な姿で衆目に曝され続けて、いえ、違ふわね、現代を生きる《生者》が基督が磔刑になった無惨な御姿の亡霊を欲してゐて、基督はその《生者》の願望、若しくは欲求、それをLibido(リビドー)と言っても構はないわね、その《生》と《死》の衝動から基督は遁れる術がない。私はね、基督が哀れで仕方ないの。
と、雪が私を見詰めながら言ひ切ったのであった。すると、猊下たる丙君が、
――今尚、《生者》が基督を、磔刑に処された無惨な御姿の基督の亡霊の《存在》を全く疑ってゐない事だけでも、「人は麺麭のみに生くるに非ず」といふ箴言は、現代人の琴線に尚も触れる箴言として、その言葉は生きてゐる《もの》だとすると、雪さんが言ふ通り、歴史が、而も、生きた歴史、つまり、絶えず歴史の価値が浮動する状態でなければ、《生者》は一時も生きられぬといふのも一理ありかもしれないね。
と、言ったのでした。
――さうね。歴史に限らず何もかもが決定不可能な様相へと相転移してしまったかのやうな、《存在》に対する何とも名状し難い諦念の中に抛り込まれしまったといふ無力感、これが、何だか《存在》全てを蔽ってしまったやうに私には思へるの。
と、さう雪が言ふと、文学青年の蒼白い顔をした痩せぎすの丁君が、
――それは、詩人の故・石原吉郎がシベリア抑留で抱かざるを得なかった断念に通じる《もの》だね、多分。しかし――。
と、再び、不意に話す事を止めてしまった丁君は、在らぬ方へと目をやりながら何かを考へ込み始めたのであった。
――それで、《杳体御仁》たる「黙狂者」君は、どう考へるかね、この現在、《存在》全体を蔽ってしまってゐる不愉快極まりない無力感を。
と、猊下たる丙君が私に尋ねたのであったが、その私はといへば、その時も尚、私の視界の周縁をカルマン渦のやうにぐるりと回る光雲と、影絵の如く誰とも知らぬ赤の他人が視界にうっすらと浮かび上がるその様に心を奪はれてゐて、唯、ぢっと前方を凝視してゐる事しか出来ない状態にあったのであった。すると、雪が、
――あなたは、今、あなたに憑依した誰かの霊と黙=話中なのよね、うふっ。
――黙=話?
と、猊下たる丙君がその眼光鋭く眼窩の奥でぎらりと光ってゐる視線を雪に送ると、
――さう。声ならぬ内界の声で会話をしてゐるから黙=話中なの、うふっ、変かしら?
――いや、雪さんて面白い人なんだなあと感心してしまったのです。この《杳体御仁》たる「黙狂者」君が、《存在》にその斥力に逆らひながらも何とか漸近するべく《杳体》なる《もの》を持ち出して《存在》、否、此の宇宙の摂理に反旗を翻し攻め込む事を企てたかと思ふと、雪さんもまた新たな造語を創るのがどうやら好きらしいやうなので、この《杳体御仁》と雪さんの組み合はせは、余程気が合ふんだらうなと、感嘆してゐるのです。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君がにやにやしながら言ったのであった。
――しかし、「人は麺麭のみに生くるに非ず」といふ箴言は、現在も尚、その輝きを失ってゐないのは間違ひない。
と、猊下たる丙君が重重しく言ひ放ったのであった。
――ふむ。今尚、難問だな、丙君!
と、甲君が冗談を飛ばすやうに半分ふざけて言ったのであった。更に甲君は続けて、
――つまり、これは愚問に違ひないのだがね、それは、或る《存在》が《生》であり続けるといふ事は、即ち、《他》の《死》が、現代ではその殺生の過程は極力隠蔽されてゐるが、やはり、《他》の《死》故に《吾》といふ《存在》は《生》を存続させてゐるといふ事に対して、人は、つまり、「現存在」は、その《死》に徹底的に弾劾されるこの《生》のからくりを無言で許容せずば、一時も生きちゃ行けない定めにあるといふ事実は、何がどう転ばうが、基督が此の世に確かに生きて《存在》した時代と何にも変はっちゃゐない事のみは、どう仕様もなく真実だといふ事だね。
と、甲君が、一見颯爽とした風貌に見えながら誰にも気づかぬ哀しい笑みを幽かにその口辺に浮かべながら、しかし、それは甲君にしか出来ない芸当なのであったが、その哀しみを蔽ひ隠してしまふ程に、甲君ならではの語り口で飄飄と言ったのであった。すると、雪が、
――しかし、《生》が生きるのに《他》の《死》を前提としてゐるのは、《生者》には何か疾しい事では決してない筈だわ。むしろ、殺生した《もの》は「人は麺麭のみに生くるに非ず」を実現するべく、「現存在」は、祈念=食しなければ、つまり、食べる事が、即ち、例へば《神》が《存在》するならば、その《神》に謝意を表明しつつ、それが祈念といふ形となって「現存在」は食事の度毎に祈りつつ、《生》を存続させるために《他》の《死》を食べる矛盾を祈念する事で止揚してゐるのぢゃないかしら?
――祈念=食?
と、猊下たる丙君がまたもや雪に尋ねたのであった。
――さう。祈念=食。《生者》が《他》の死肉を喰らふ事でしか《生》が存続出来ない以上、《生者》は食事時に限らず、絶えず殺生した《他》へ感謝するの。
――しかし、それは現に「頂きます」といふ言葉や、基督者の神への感謝の祈りなど、既に多くの《生者》によって実践されてゐます。
と、猊下たる丙君が、それでなくとも鋭い眼光を更に鋭く輝かせて言ったのであった。
――ええ。さうね。でも、かう言へば良いのかしら。自然における弱肉強食の、慈悲すらないやうに見える強者が弱者を喰らふ世界は、実は慈悲に満ちてゐて、強者は必要最低限の獲物しか捕らへず、また、餌を捕獲出来る確率も低いのが常で、弱肉強食の世界は実は持ちつ持たれつの世界であって、その世界の摂理に則って「現存在」の人間もまた、自身が《他》の餌になる事をも想像するの。而も、「現存在」の人間は、既に人肉を喰らってゐる行為と同じ事をしてゐることに思ひを馳せるべきぢゃないかしら。
――と言ひますと。人肉を食べる事と同じ事とは何ですか?
――臓器移植です。
――成程。つまり、人間は、人肉を喰らふといふ人の風上にも置けぬ愚行はしてゐない、といふのは或る種の先入見でしかなく、実の処、「現存在」の人間は、《死者》若しくは《生者》の腹を切り裂き、其処から臓器を取り出して、《吾》にその臓器を移植するといふ人肉食ひに等しき行ひを既に行ってゐるに等しいといふ考へ方は、本音を言へば、これは目から鱗が落ちる思ひですね。
と、丙君が言ったのであった。すると蒼白い顔がぱっと輝き出したやうに文学青年の丁君が尋ねたのであった。
――しかし、現在は医学と生物学が非常に進歩してゐて、再生医療へと邁進してゐるが……しかし――。
と、再び、ぶつりと言葉を噤んで話すのを止めてしまったのであった。
――それではお聞きしますわ。仮令、再生医療が極限まで進歩を遂げて、「私」の万能細胞から「私a」が再生出来たとすると、その新たに再生された「私a」は一体何でせうか?
――ふむ。それは難問ですね?
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が、誰も甲君の奇妙に顔を歪めて自身を嗤ひのめすやうな様に気が付かなかったが、その甲君がさう言ったのであった。
――《吾》が《存在》し、そして再生医療の極度の進歩で、その《吾》から《吾a》が再生され、更に《吾b》と、蜿蜒と再生され続け、遂には《吾∞》が《存在》可能な、譬へて言へば、それはウロボロスの蛇のやうに自身の口で自身の尾を喰らふかの如き《吾》の無限の円環が数珠繋ぎとして現出する時、つまり、《吾》が∞体《存在》するならば、例へば大元の《吾》の体躯の何処かが機能不全に陥った場合、《吾》は《吾a》から臓器を摘出し移植を受け、《吾a》は《吾b》からまたまた臓器を摘出し移植を受け、といふ事を無限に繰り返す以外、仮に《吾x》で《吾》の再生が止まってゐるとすれば、割を食ふのはその《吾x》で、《吾x》は、それ以外の《吾》の犠牲になるのを必然として此の世に産み出されたことになり、しかし、此処に大いなる疑問が《存在》するのだが、《吾》と、《吾a》、《吾b》……、《吾x》……、《吾∞》の何処が違ふといふのかね?
と、ブレイク好きの数学専攻の乙君が面白い問ひを投げかけたのであった。
――つまり、有限である事は何処かが必ず割を食ふといふ事か――成程。それが此の世の有様だな。しかし、其処に無限といふ概念が持ち込まれると、玉突き衝突の如く蜿蜒と同じ事が繰り返されるだけの、ちぇっ、約めて言へば、永劫に《吾》が再生する時代が到来するかもしれぬ事すら予想される此の世の様相は、しかし、《吾》の万能細胞から《吾a》が再生された場合、その《吾a》は《吾》かね?
と、数学専攻の乙君が続けたのであった。
――それはClone(クローン)とは勿論、違ふ何かさ。Cloneは、詰まる所、Cloneを超えることは出来ず、Cloneは寿命が短い《他》であり、《吾》には決してならないといふ論理に照らせば、万能細胞から再生される《吾》もまた《吾》ではなく《他》に違ひない。しかし、万能細胞から再生された《もの》は《吾》へ移植、つまり、《吾》が《吾a》を喰らふも同然で、さうする事で《吾》は生き延びるが、《吾a》は息絶える、そんな時代の到来が直ぐ其処までやって来てゐるのであれば、《吾》とは一体何なのかといふ、これまでは永劫の命題として保留しておけばよかった《もの》、つまり、パンドラの匣を既に「現存在」の人間は開けてしまってゐて、何とかして《吾》なる《もの》を規定する、若しくは定義する宿命を現代人は背負ひ込んじまったのさ。すると「人は麺麭のみに生くるに非ず」といふ基督の言葉の本質を深い深い深い懊悩の中で「現存在」は唯、ぢっと噛み締める外ないといふ事だ。
と、君が重重しく言ったのであった。
――さて、其処で一つ問ひを出すと、果たして、《吾》は再生医療の進歩の極致で《意識》を再生出来ると思ふかい?
と、丙君が、重重しく言ったのであった。すると、君が、
――多分、「現存在」たる人間の最終目標は《吾》の《意識》の再生にあるだらうが、脳に関して言へば、Neuron(ニューロン)を部分的に再生させる事はするかもしれぬが、脳を丸ごと再生された脳と取り換へる事は、「現存在」たる人間は出来ないと思ひたいが、しかし、欲深く業突く張りの「現存在」たる人間は何を仕出かすか解からぬのもまた、真実だらう。
と、君が言ふと、文学青年の丁君がぼそりぼそりと言ったのであった。
――例へば、「現存在」が永劫の《生》を手にした時、その時、「現存在」は首のみで生き延びるのであらうか? 多分、しかし――。
と、再び、丁君は次の言葉を呑み込んでしまったのであった。その時、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が誰にも知れずに自虐的な嗤ひを口辺に浮かべ、きっと丁君を見た事は、私を除いて誰も気付かなかったに違ひない。すると、雪が、
――それは或る種の夢物語でしかないわ。脳を形成するNeuronなどの脳細胞の幽かな幽かな幽かな発火現象で、私達「現存在」の行為や思惟活動が行はれてゐる事は、否定はしませんが、頭蓋内の闇にぱっと明滅する現象を言語に解読出来たとして、その事で、《吾》は《意識》さへすれば、外界の《生者》の体躯の代はりに拡大延長した巨大なNetwork(ネットワーク)に繋がる機械が、《意識》に正確無比に反応したからと言って、うふっ、さうなれば尚更ですけれども、《吾》は自同律の不快に堪へ切れないに違ひないわ。
――しかし、人間の欲として不老不死が《存在》する限り、死すべき運命を認識してゐる「現存在」にとって、不老不死の諦念では片付かぬ、何だかのっぴきならぬ方向へと現実は進行してゐるやうに思へるのだがね。
と、猊下たる丙君が言ったのであった。その時、丙君の既に鋭さを増してゐた眼窩の眼光は一瞬、きらっと光ったのであった。
――さうなると「現存在」は子を産まなくなるわね、うふっ。
と、雪は少し顔を赤らめながら、自身に降りかかった男による凌辱を浮かべながらか、恥ずかしげに言ったのであった。
――ねえ、あなたは、首のみが永劫に生きる「現存在」、つまり、幾ら再生医療が進歩しようが、老齢により全身癌に為れば、最早肉体は捨てざるを得ないからなのだけれども、その首のみで生き残る「現存在」の未来形をどう思ふの?
と、雪は、私に問ふたのであった。甲君、乙君、丙君、丁君、そして、君達は、雪の言葉に呼応するやうに一斉に私にその視線を向けたのであった。私は、一息「ふう~う」と吐いて徐にかう書いたのであった。
――つまり、覚悟が、つまり、あるかどうかだらうね、つまり、《吾》は《吾》であるといふ、つまり、自同律を、つまり、未来永劫に亙って、つまり、首とNetworkに、つまり、繋がった、つまり、主体の、つまり、《意識》と巨大な機械の体躯、つまり、それは、つまり、地球と言っても、つまり、過言ではないが、つまり、首と、つまり、Networkで、つまり、地球全体と、つまり、繋がってしまった、つまり、「現存在」は、つまり、裏を返せば、つまり、首のみの、つまり、《意識体》へと為り果せてしまった、つまり、《吾》は、つまり、地球全体に、つまり、拡大する事で、つまり、《吾》は、つまり、《吾》である事を、つまり、一瞬でも忘却して、つまり、《吾》は《全》であるなどといふ、つまり、妄想を、つまり、抱く事無く、つまり、《吾》は、つまり、何処まで行っても、つまり、首のみの《吾》でしかないといふ、つまり、断念を、つまり、出来ないのであれば、つまり、「現存在」は、つまり、不老不死を希求しては、つまり、ならぬと、つまり、そして、つまり、《吾》の機械化による、つまり、《吾》の巨大化、つまり、若しくは、つまり、《吾》の、つまり、無限の、つまり、延伸は、つまり、一体、つまり、「現存在」に、つまり、何を、つまり、齎すのかと、つまり、自覚せねば、つまり、首といふ《吾》の《意識》を容れる器と、つまり、地球規模に、つまり、拡大した、つまり、Networkと、つまり、体躯の機械化によってしても、つまり、《吾》は、つまり、自同律の不快からは、つまり、遁れる筈もない。
――それは、詰まる所、此の世に《存在》する森羅万象は、それが、例へば人体に例を取れば、複数の臓器などから成り立つ以前に、既に各各の臓器に《吾》といふ《意識》が宿ってゐるといふ《杳体御仁》の「黙狂者」君の思惟とは無関係ではないだらう?
と、甲君が飄飄と言ったのであった。
――《杳体御仁》の「黙狂者」君の奇妙な汎神論、それは、此の国に太古より伝承された八百万の神神への信仰と同根の、汎神論によって、此の世が形作られてゐるといふ、つまり、此の世の森羅万象は、さて、何処へ向かってゐるのかな。
と、猊下たる丙君が薄らと微笑みながらも眼光のみを異様に輝かせて言ったのであった。
――ねえ、あなた、再生医療が極限まで進歩を遂げた時、「現存在」は、頭蓋内の闇の脳といふ構造をした《五蘊場》を総取っ換へする、愚行へ歩み出す可能性があると思うの?
と、雪が私に訊いたので、私は、かうNoteに書いたのであった。
――つまり、脳以外の、つまり、あらゆる体躯の、つまり、部位に再生医療で再生されるか、つまり、または、つまり、精巧に作られた、つまり、機械の体躯に、つまり、総取っ換へる事は、つまり、人間の、つまり、業故に、つまり、一気呵成に、つまり、突き進むのは、つまり、止めようもないが、つまり、果たして、つまり、体躯は、つまり、脳の、つまり、下僕として、つまり、《存在》する事に、つまり、肯ふ《もの》なのだらうか、と、つまり、さう考へると、つまり、腕の、つまり、自同律が、つまり、成り立って、つまり、腕は、つまり、己が腕であって、つまり、脳とは違ふ事は、つまり、腕は、つまり、自覚してゐる筈で、つまり、腕が、つまり、腕である事を、つまり、自覚してゐなければ、つまり、こんな高度に、つまり、各部位が、つまり、それぞれ、つまり、見事に、つまり、発達した、つまり、高分子の有機的な意識体は、つまり、生まれる術はなかった。
――ねえ、さうすると、あなたは、例へば人体は、その部分部分、いいえ、各細胞が己は己だといふ《意識》を持った《存在》として、此の「現存在」を思ひ描いてゐるといふことかしら?
――つまり、《吾》は、つまり、細部に、つまり、宿る《もの》なのさ。
――うふっ、《吾》は細部に宿るって、あなたはまた面白い事を言ふのね。
――つまり、細部に《吾》が、つまり、宿らなければ、つまり、Fractalな、つまり、《個時空》といふ、つまり、《吾》の、つまり、《存在》の有様は、つまり、成り立つ見込みは、つまり、なく、つまり、此の世に、つまり、単細胞が、つまり、誕生してしまった刹那、つまり、自同律の不快は、つまり、始まってしまった。否、つまり、此の世に、つまり、反物質と対消滅して、つまり、光となって消滅せずに、つまり、残ってしまった物質、つまり、の状態で、つまり、既に、つまり、《吾》は《吾》だ、つまり、といふ、つまり、自同律は、つまり、《存在》してしまった。
――ちょっ、つまり、《杳体御仁》の「黙狂者」君は、《吾》は、つまり、更に分解可能な《吾》の複合体といふ事を目論んでゐると解釈していいのかな?
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が、その笑顔とは裏腹に『それは断じて認められぬ。つまり、否だ!』と胸奥で叫びながら私に訊いたのであった。
――つまり、さうさ。つまり、《吾》は更に分解可能の、つまり、小《吾》の複合体として、つまり、更に小小小《吾》の、つまり、複合体として、つまり、何処まで行っても、つまり、金太郎飴の如く、つまり、Fractalな《吾》が、つまり、顔を覗かせる、つまり、《存在》が、つまり、此の《吾》なのさ。
――ねえ、それは物質にも同じやうに当て嵌まる事なのかしら?
――ああ。つまり、物質にも、つまり、その素粒子まで行っても、つまり、《吾》は《吾》だといふ、つまり、此の世の《存在》、つまり、その根元において、つまり、《吾》は《吾》であるといふ、つまり、自同律を、つまり、授けられてゐる以外、つまり、《吾》といふ、つまり、観念が、つまり、生まれる筈は、つまり、ない。
――さうすると、あなたは、《吾》といふ自意識は本質に先立つといふ事を支持するのね?
――つまり、それは、つまり、実存は、つまり、本質に、つまり、先立つといふ、つまり、サルトルの言葉を、つまり、捩った、つまり、言ひ種と思ふが、つまり、私にすれば、つまり、《吾》といふ《念》は、つまり、本質に、つまり、先立つ、つまり、《もの》だと、つまり、私は思ふ。
――あなたがさういふ考へ方に至った理由って何かあるのかしら、うふっ。
――つまり、《吾》を、つまり、絶えず、つまり、問ひ詰めると、つまり、私においては、つまり、《吾》といふ自意識、つまり、若しくは、《念》は、つまり、本質に、つまり、先立つといふ、つまり、考へを、つまり、採らないと、つまり、《吾》が、つまり、此の世に、つまり、生まれる端緒が、つまり、見出せないのさ。
――それって唯心論や唯物論の系譜にあるのかね? 若しくは実存主義とそれらに続く現代思想、または唯識による《もの》なのかね?
と、鋭い眼光をぎらぎらと輝かせた猊下たる丙君が言ったのであった。
――へっ、そんな事、解かれば何の苦労もなく、彼が「黙狂者」になる事はなかったに違ひない。なあ、《杳体御仁》の「黙狂者」君!
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が軽口を敲いたのであった。
――しかし、《吾》の誕生には、どうしても《存在》が付き纏ひ、そして、その《存在》に有限な場合と無限な場合があるとして、有限か無限かでその位相が全く違ってしまふといふ、《存在》とはその様に面妖なる《もの》なのさ。
とヰリアム・ブレイク好きの乙君が言ったのであった。
――一つ、あなたにお伺ひしますが、無限は実際の処、有限な「現存在」に思惟可能な《もの》と看做して宜しいのかしら?
――現時点では、無限が現はれるのは背理法によってのみです。
――つまり、無限を背理法以外の方法で導く事は今の処不可能であるといふ事かしら?
――カントの二律背反が好例です。
と、乙君が言ったのであった。すると、文学青年の丁君がぼそりと呟いたのであった。
――ところが、此の《生》といふ哀しき性を持ってしまった「現存在」たる《意識》の複合体たる人間は、無限を演繹的にか、帰納的にか証明出来得る何かとして何の疑問も持たずに表象され、無限を恰も実数の仲間の如くに扱ってゐるのが、現代人の大きな誤謬ぢゃないかな。しかし、仮令……。
と、丁君は再び途中で言葉を呑み込み、ぷつっと喋るのを止めて口籠ってしまったのであった。
――さう、其処だ!
と、猊下たる丙君が、更に眼光鋭く私達を睥睨しながら言い放ったのであった。
――つまり、私達は無限といふ玩具を与へられて、それが恰も無限が吾が手で掌握出来るかの如き《もの》として、つまり、実体する《もの》として、軽軽しく取り扱ってゐる内に、何だか、無限は誰もが簡単に弄べる《もの》として、つまり、観念の遊具として、何か具体的な《もの》として、取り扱ってゐるといふ愚行を今こそ省察しなければ、無限の方が、《存在》を見て薄ら笑ひを、その名状し難い口辺に浮かべて、または、吾等の思惟には結局の処、捉へられないと高を括って哄笑してゐるかしてゐて、詰まる所、有限なる《存在》は、果たせる哉、無限を捉へる事が可能かどうかを今一度判断せずば、此の宇宙もまた何だか解からない《もの》に成り下がり兼ねない分岐点に差し掛かってゐるに違ひないのだ。
と、鋭い眼光を爛爛と輝かせて猊下たる丙君が言ったのであった。
ねえ、君、あの頃が懐かしいだらう。私は余命を医師に告げられてから、何故かあの頃の事ばかり思ふことが多くなってね。
今、私が思ふのは、《死》と無限は何やら同じ匂ひがする《もの》に思へて仕方がないのだ。これも雪の影響かな。
…………
…………
――しかし、絶えず思惟を無限へと誘ふのは、《もの》の道理ぢゃないかな。
とヰリアム・ブレイク好きの乙君が言ったのであった。
――あっは、絶えず思惟は無限を欣求するか――。何ともをかしくて仕様がないのだが、これは何故なんだらうか?
と、甲君が薄ら嗤ひを口辺に浮かべて尚も飄飄と言ったのであった。
――多分、此の宇宙史は、《存在》が無限に思ひを馳せるその歴史とぴったりと重なるやうな気がする。
と猊下たる丙君が言ったのであった。
――ぶはっ、つまり、それって、此の世は絶えず無限を夢想せずにはをれなかったといふ事だらう?
――無限が厭ならそれを《神》と言ひ換へてもいいぜ。さうすれば、君もよく解かるだらう?
と丙君は、ぎろりと甲君を凝視して言ったのであった。
――へっ、それぢゃ、例へば単細胞でも《神》を欣求してゐるのかね? それ以前に素粒子そのものが《神》を欣求してゐると君は断言出来るのかね?
――私は、自然が《存在》するならば、素粒子もまた密かに《神》を欣求してゐると看做すぜ。
――それは、此の《杳体御仁》の「黙狂者」君の奇妙な汎神論を承認するといふ事だね?
――ああ。
と、丙君は、薄ら嗤ひを口辺に浮かべた甲君に対して重重しく言ったのであった。
――其処で、一つお尋ね致しますが、あなたは、此の世の時空間に《神》は宿るとお思ひなのでせうか?
と、雪が丙君に訊いたのであった。
――此の世の森羅万象に《神》が遍在してゐます。
と、猊下たる丙君が答へたのであった。
――さうしますと、カントが唱へた《物自体》は、《神》の御神体といふ事になるのかしら?
――まあ、さう看做しても構ひません。そもそも此の《世界》のからくりが今もって《神》以外に知る《もの》がゐませんので、カントがいふ《物自体》も、例へばユークリッド、そしてリーマン幾何学の公理は、誰が「先験的」に定めたといふのか、と同じことだと思ひます。
――済みません。私、数学にはそれ程詳しくはないのですが、しかし、此の世に公準が《存在》する事が既に《神》の《存在》を包摂してゐるといふ事ですね?
――はい、さうです。
――では、もう一つお尋ね致しますが、此の世に無限が仮に《存在》すれば、即ち《神》は《存在》すると看做す事にあなたは何の疑念も抱かないのですか?
――まさか。私はそもそも猜疑心の塊みたいな《存在》です。それといふのも、私は《存在》は全て己に対して猜疑を抱かぬ《存在》は《存在》しないと考へてゐます。
――さうですね。では、あなたは、この「黙狂者」と呼ばれてゐるこの方の思索には賛意を表明なさるのですね?
――はい。だが、彼は《存在》、若しくは《物自体》、或るひは《神》に肉薄するべく孤軍奮闘するうちに、木乃伊取りが木乃伊になるやうにして、彼は最早己といふ《存在》の混迷した混沌の中に蹲ることを余儀なくされて、今や其処から這ひ出す術を全く見失ってしまった《存在》なのです。
と、猊下たる丙君は眼光鋭く甲君を凝視したまま雪にさう語ったのであった。
――さうしますと、この哀しい「黙狂者」となってしまったこの方は、恰も闇にぢっと息を潜めて、その《存在》を何《もの》にも知られたくなく、闇といふ無限すらをも多分に呑み込むに違ひないその闇に、閉ぢ籠ってしまったといふ事かしら?
――はっきりとは言へませんが、「黙狂者」の彼は、観念といふ《もの》の恰もその地底に棲む穴居生物と化してゐるのは間違ひないでせう。
と、猊下たる丙君が雪の問ひに答へたのであった。
――へっへっ、つまり、「黙狂者」君は、《存在》に蔽はれた闇の中で、《存在》といふ名の幽霊が辺りに犇めいている処で独り肝試しをしてゐるに過ぎず、そして、「黙狂者」君は、一歩踏み出す毎にびくりとして怯えてそのままその場に立ち竦んだまま、その時に芽生える己の感情をじっくりと味はひ尽くし、そして、へっ、この「黙狂者」君は、そんな己を自嘲するのさ。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が言ったのであった。
――それ以前に、彼は無限に睨まれてしまったに違ひない。
と、数学専攻でヰリアム・ブレイク好きの乙君が言ったのあった。
――そして、彼は自同律を見失ってしまった。
と、文学青年の丁君が言ったのであった。
――それは、二律背反に身を裂かれ、その状態に《存在》は、果たせる哉、堪へ得る《もの》なのか、彼は己を実験台にして試してゐる。
と、君が雪へと言ったのであった。
――さうしますと、何だか「黙狂者」になってしまったこの方が、人類が背負はねばならぬ十字架、それは多分に基督が背負った十字架にとても近しい筈ですが、この方はたった独りでその人類誰もが背負ふ十字架全て背負ってしまってゐるといふ事かしら?
――或るひはさうかもしれませんね。
と、文学青年の丁君がその痩せぎすで蒼白い顔にほんの少し微笑みを浮かべて雪へと答へたのであった。
――その十字架の別称は、《パスカルの深淵》ではありませんか、うふっ。
と、雪は何とも楽しさうに誰彼となく問ふたのであった。
――さうですね。《パスカルの深淵》は「現存在」ならば、一度は目にする仮象の「先験的」な陥穽、そして、存在論的な危機に瀕した時には必ず目にする《もの》ですね。確かに、「黙狂者」の彼は、《パスカルの深淵》に或るひは身投げをしてしまったに違ひないですね。
と、猊下たる丙君が雪の楽しさうな笑顔に呼応するやうにその鋭く光る眼光のままにその相好を崩して言ったのであった。
――ちぇっ、それは「黙狂者」君を少し買いかぶり過ぎてやしないかね?
――といふと?
――何ね、「黙狂者」君が陥ってゐる陥穽は、別に特別な事でもなく、日常にありふれた《もの》に過ぎず、現に此処にゐる《もの》は大なり小なり自同律の罠に引っ掛かって、《存在》を問はずにはをれぬ、そして、闇を、無限を、欣求せずにはをれぬ哀しき「現存在」ぢゃないかね?
と、甲君が皮肉な微笑を口辺に浮かべて、これまた飄飄と言ったのであった。
――だが、この「黙狂者」の如く、己を自同律の裂け目、つまり、それを《パスカルの深淵》と呼べば確かに《パスカルの深淵》に違ひないが、その「黙狂者」の彼は、誰もが躊躇ふその陥穽を覗き込むだけでは飽き足らず、自ら身投げしてしまったのだ。
と、丙君が甲君を再びぎろりと凝視しながら言ったのであった。
――「黙狂者」のこの方は《パスカルの深淵》に既に身投げしてしまったのですか?
――いや、本人ぢゃないので本当の処は解かりませんが、「黙狂者」の彼の生態を見てゐると間接的にですが、《パスカルの深淵》といふ《もの》を暗示せずにはゐられぬのです。
――それは、この方の何がさう暗示させるのですか?
――第一に彼は「黙狂者」といふ事です。
――それだけなのですか?
――そして、彼が「つまり」を多用せずには何にも表現出来ず、そして、「つまり」と書き連ねることで彼に内在する言葉を絞り出すやうにNoteに書き出すその語彙が、深淵に棲まふ《もの》特有の暗鬱な表現が多い、といふ事です。
と、猊下たる丙君は甲君を凝視しながら雪の問ひに答へたのであった。
――それが過大評価だといふんだぜ。この「黙狂者」君は、決して《パスカルの深淵》なんぞに身投げなどはしてはをらず、唯、彼は《五蘊場》に全躯が逃げ込んだ仮象の《吾》に魅惑されてゐるだけに過ぎぬ。
――さうしますと、あなた、甲さんは「黙狂者」のこの方は、この方が呼ぶ処のこの頭蓋内の闇の脳といふ構造をした《五蘊場》といふ仮象にこの方が逃げ込んだといふのですね?
――はい、それ以前に、雪さんは《五蘊場》が何の事なのか解かりますか?
――いえ、詳しくは。しかし、「黙狂者」のこの方が「現存在」の行為を全て脳に帰す事に反旗を翻してゐるのは、間違ひない事でせう?
――其処です。現代の「現存在」は脳を残る未開の地として探査を始めてしまったが、仮令脳内の発火現象の全てが隈なく解読出来たとしても、私はこの「黙狂者」君と同様に科学的にその全貌が解明された脳を拒否します。
――それは何故ですの?
――多分に科学に対する不信感からです。
――つまり、甲さんは、反科学主義者といふ事かしら?
――いいえ、それは違ひます。私は単に神学から離れてしまった科学は科学としては全く認めることは出来ないといふ事だけです。
――さうしますと、甲さんは、《神》は《存在》すると?
――へっ、《神》が《存在》しなければ、此の世はどうして生まれたのですか?
――その《神》は基督教、若しくは回教的、若しくはゾロアスター教的な一神教の《神》ですか、それともこの日本に生滅する八百万の神神の事でせうか?
――そんな事は、どれでも構ひやしないのです。唯、《神》といふ観念が実在し、つまり、私の言ふ《神》は、「現存在」の「先験的」な事項で、多分、無限と同じやうに背理法の論理をもってしても此の世から排除出来ない《存在》なのです。
――君の言ふ《神》の《存在》は背理法による無限の《存在》とは明らかに違ふだらう? 君の言ふ《神》は《存在》に纏はり付く《神秘》の事だらう?
と、猊下たる丙君が甲君に言ったのであった。
――甲君、君が言ふ《神》は限りなく数学に近しいぜ。
と、ヰリアム・ブレイク好きで数学専攻の乙君が言ったのであった。
――そして、数学も《神》に結び付き易く、ギリシャのピタゴラス学派ぢゃないが、数学の論理の美しさは、《神秘》を生み出し、「現存在」を魅了して已まないのだが、例へば数学教なる宗教が《存在》し、其処に偉大なる《神》が《存在》すれば、多分に、科学者は、その信者に為るに違ひない。だが、数学は何時の時代かは私は知らぬが、無理矢理宗教から遠く分派し現在では宗教の匂ひがしないのが数学といふ、摩訶不思議な不文律が成立してゐるやうに思へるが、しかし、「現存在」が数学的なる《世界》に、しかも、其処にはどうしても《神》の《摂理》が《存在》するとしか思へぬ《世界》に投企されてゐるのは間違ひない。
と、乙君が更に続けたのであった。
――数学をして《神》を暗示するといふやうに思ひ為する、その思惟形式が既に宗教ぢゃないかね?
と、甲君が数学専攻の乙君に言ったのであった。
――さうだね。数学に魅了されてしまった《もの》は、多分、全てが観念上の《神》の《存在》を信じてゐるかも知れないな。さうぢゃなきゃ、数学なんぞに胸躍らせ、そして、数学に憑りつかれて、その人生を狂はす狂気の沙汰なんて起こりはしないからね。
――すると、君によると、現在の数学が手中にしようと目論んでゐる《もの》は何かね?
と甲君が乙君へ言ったのであった。
――やはり、《無限》と、そして、《もの》といふ個体の扱ひ方かな。つまり、数その《もの》を問ふといふ事さ。
――つまり、それは現代数学では、数字その《もの》の《存在》が曖昧模糊で不確定な《もの》で、もはや数字自体で数字その《もの》を定義出来ないといふ事かね?
と、猊下たる丙君が乙君に訊いたのであった。
――いや、唯、普通の日常世界と数学の世界が全く交はらない程、隔絶した《もの》へと現代では数学その《もの》の様相が変はってしまった事に、数学者以外は余りに無頓着だといふ事さ。つまり、例へば、或る《もの》が「一」と言ったとしてその「一」は何の事なのか、数学で定義する時、「空(から)」が前提になってゐる事さ。
と、乙君が言ったのであった。
――これは独断だがね、数学で《ある》といふ事を語る時に、先づ、「空」が《存在》してゐないと定義すら出来ないのだとすると、それは暗に「空」が《無限》の《存在》を要請してゐると言へるのと違ふかな。
と、丙君が言ったのであった。
――当然、さう看做して差支へないだらうだがね。だが、「空」と《無限》は近しくありながら、《無限》に遠い観念だよ。
と、乙君は何かの意味を噛み締めるやうにさう呟いたのであった。
――さうしますと、乙さん、数学では、《存在》その《もの》が「空」を前提にしなければ、何にも定義できないといふ事ですの?
――はい、雪さん。
――さうしますと、仏教の《空(くう)》と数学の「空」とでは何か随分と違ふやうでゐて、案外近しい《もの》なのですね、うふっ。
――しかしだ、数学を用ひる以前に存在論を語る場合、既に何百年にも亙って「空」と《空》と《無》と《無限》について、森羅万象は思ひ惑ってゐる。
と、猊下たる丙君がさう言ったのであった。これを聞いた甲君が、
――でも、そんな事を問題にせずとも「俺は《存在》する」と言へちまふのも確かだぜ。
――例へば、かう考へるとどうでせうか。森羅万象の《存在》の担保には、「空」と《無限》の《存在》が所与の《もの》として前提になってゐて、《存在》が《存在》するといふTautologyにも似た言ひ種は、其処に無意識裡に「空」と《無限》、そして、《無》と《色》と《空》が同時に概念上に重なり合って《存在》し、それ以外では《存在》を語れるとは看做せない以上、それは、詰まる所、何《もの》も《存在》に意味すら見出せないといふ行き詰まりの処に、森羅万象は追ひ詰められてゐて、そして、苦し紛れに「私は」と言ってゐると看做せます。つまり、《存在》してゐるといふ言葉には、暗に「空」と《無限》の《存在》が「先験的」に含意されてゐて、つまり、《存在》について何かを語るには、どうしても「空」と《無限》に言及せずば、何《もの》も既に《存在》に関して何も語れない状況が現在、森羅万象が置かれた様相といふ事ですね、丙さん。
と、雪が何かに思ひ至った如くに語ったのであった。
――或ひは雪さんの言ふ通りかもしれませんが、此の世の森羅万象は己が此の世に《存在》すると思ひ為すのは、唯、「《吾》あり」と《念》ずるだけで、既に《吾》なる得体の知れぬ《存在》は、さう《念》ずるのみで《存在》してしまふ。其処には《無限》は未だその《存在》にとって観念としてすら想起されてをらず、つまり、《吾》が《存在》するとは、初めに「《吾》あり」と《念》ずるのみで、《吾》は己の《存在》をこれっぽっちも疑はないといふ事です。しかし、その《吾》は途端に《吾》に対する途轍もない猜疑心に駆られ、「《吾》あり」と《念》ずるに呼応して「《吾》とは何んぞや」といふ疑問が既に《吾》には生じてゐるといふ矛盾をこの《吾》は抱へ込まざるを得ぬのもまた事実です。
と、猊下たる丙君が自身を確認するが如くに己に対して言ったのであった。すると、雪が、
――丙さん、この《吾》が、《吾》の《存在》を「《吾》あり」と《念》じた時点で、既に《吾》は《無限》を吾にすら全く知れぬ内に《吾》といふ観念が想起すると同時に《無限》を《吾》と同じく確証してゐるのぢゃありませんか?
――ほれ、丙君、どうした?
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が囃し立てたのであった。丙君は、相変はらずぎろりと鋭き眼光を放つ目を甲君に向けたまま、更に次のやうに言ったのであった。
――雪さん、あなたは《無限》をどのやうな《もの》として想起してゐますか?
――私以外の全て、かしら。
――成程、《吾》以外の全てが《無限》ですか。つまり、「《吾》あり」と《吾》が《念》ずる時点で、《吾》は《吾》以外の《存在》を「先験的」に想起してゐるといふ事ですね?
――ええ。しかし、《吾》はそれが全て意識下で行ってゐる事に気付く《もの》はまだまだ少なく、《吾》が《存在》する事は、恰も何事もないかの如くに確たる《もの》として認識してゐる事が如何に無邪気な事か全く気付かない場合が殆どですね。
――しかし、《吾》は直ぐに《吾》の《存在》に対する確信が全くの虚構でしかない事を匕首の切っ先を首に突きつけるやうに此の《世界》に認識させられ、そして《世界》は《吾》の虚構を己に対して絶えず暴き続けるのです。
――しかし、殆どの《吾》といふ《存在》は知らぬが仏で、《世界》の《吾》に対する《吾》が虚構であるといふ要請を察する事が出来ないのですが、しかし、その中にも、此の《世界》に対して憤怒する《もの》が必ず《存在》するに違ひない筈ですね。つまり、「黙狂者」のこの方は、独りでその《世界》の要求を無理難題として《世界》に対して反攻を始めた、といふ事かしら? つまり、此処にゐる誰もが此の《世界》は、《吾》に対して無理難題を突き付ける厄介至極な《もの》と看做してゐると考へて宜しいでせうか?
――はい。
と、甲君、乙君、丙君、丁君、そして君は、皆、雪に同意の意を表したのであった。
――それでは、あなた方は何によって此の《世界》が《吾》を虚構に過ぎぬ事を要請し、また、《吾》に対して《世界》は無理難題を圧し付けるといふ事を意識し始めたのですか?
――その前に、雪さんは、此の《世界》は《吾》に対して理不尽極まりない事を要求してゐるとお思ひですね?
――ええ。私は憎悪すら感じてゐます。
――それはまたどうして?
――それに関してはまだ私自身語れる心境にないので、これ以上は訊かないでください。お願ひします。
――ふむ。さうですか。何か深い事情がありさうですね。
――ええ。「黙狂者」のこの方は、多分、私が抱え込まざるを得なかった苦悶の原因を察っしてゐて、そのどす黒い憎悪の何たるかを直感的にこの方は知ってゐると私には思へますが、これ以上はご勘弁を。
と、雪は自身の内部を弄るやうにさう言って、何とも奇妙な、それでゐて哀しい微笑を浮かべたのであった。
――どうも雪さんの触れてはいけない《もの》に触れてしまったやうですね。御免なさい。これ以上はもう訊きませんので。
――いえ、今日お会ひした人達ばかりですもの、仕方ありませんわ。気にしないでください。
――それでは、雪さん、雪さんが《世界》へ反攻するに至った訳は訊きませんが、しかし、雪さんは、《無限》を《吾》以外の全てとの思ひに至ったその思惟経路は何だったのですか?
――さうですね……、幼児期に薄ぼんやりと《世界》に対して抱かざるを得なかった渺茫とした感情が、端緒と言へば端緒に為るのかしら。
――つまり、それは、《世界》は《吾》を既に見放してゐる感情に近しい《もの》だったと思ひますか?
と、猊下たる丙君が訊くと、雪は、
――いいえ、私といふ《存在》を思った時に自然に湧き起って来た感情だった筈です。
――つまり、「《吾》あり」と《念》じた刹那、その何とも茫漠とした渺茫たる孤独感は、《吾》知らず止め処もなく湧出した感情ですね?
――さうだと思ひます。それでは、皆さんは《無限》を意識するやうになった端緒は何でせうか?
――私は人込みで特に感じる底無しの孤独感です。
と、猊下たる丙君が先づ、話したのであった。そして、
――俺は、丙君に出合った刹那かな?
と、甲君がその場を茶化すやうに言ったのであった。
――僕は、「一」に対する疑念を感じてしまった刹那かな。
と、ヰリアム・ブレイク好きで数学専攻の乙君が言ったのであった。
――私は、梶井基次郎の作品に出合った時……。
と、文学青年の丁君が言ったのであった。すると、君が、
――私はこの「黙狂者」の彼に出合った事かな。
と、君は照れ笑ひを浮かべながら言ったのであった。
――それでは、あなたは何時《無限》を感じたの?
と、雪が私に尋ねたのであった。其処で私はNoteにかう書いたのであった。
――つまり、私が、つまり、此の世に、つまり、誕生した、つまり、その刹那に、つまり、未だ言語も知らぬ、つまり、赤子とは言へ、つまり、何やら、つまり、私が私である、つまり、不自然さといふ、つまり、その何とも度し難い《もの》が、つまり、《存在》だと、つまり、感じ取らねば、つまり、ならなかった、つまり、私が、つまり、初めて、つまり、此の世で産声を発した、つまり、その刹那に、つまり、私は、既に、無意識裡に、つまり、私なる《存在》を知ってしまった、つまり、時が、つまり、私が《無限》を、つまり、思はずにはゐられなかった、つまり、刹那の困惑が、つまり、それに違ひない。
――つまり、あなたは、生まれた瞬間に既に《存在》に困惑してゐたといふのね? あなたらしい答へね、うふっ。
――しかし、普通《無限》と《吾》に踏み迷ひ、その陥穽に陥るのは大概、思春期と相場が決まってゐるぜ。
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が嗤ひながら言ったのであった。
――その自分の言葉を一番信じてゐないくせに、全く持って甲君らしい言ひ種だ。
と、数学専攻の乙君が茶化したのであった。
――いや、そんな事ないぜ。ぶはっはっはっはっ。
と、甲君は哄笑したのであった。
――まあ、議論を何時も煙に巻くのは、彼の性癖だからね。しかし、甲君、これは嗤って済む問題ぢゃないいよ。つまり……。
と、文学青年の丁君が再び言葉をぶつりと切って何かを自身に呑み込むやうに甲君に言ったのであった。
――それを言っちゃあお仕舞ひよ!
と、甲君は尚も哄笑しながら言ったのであった。
――つまり、君にとって《無限》を感じざるを得ぬのは、《存在》が「ぷふぃ」と嗤った刹那なのだらう。
――さすが、丙君、ご名答!
と、甲君は未だ何かがをかしくて仕方がない様子で尚もおちゃら化て丙君に言ったのであった。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
ねえ、君、私の眼前には未だに消え去らぬ私の与り知らぬ赤の他人の声に為らざる唸りをぢっと聞くことを強要され、そして、あの時はその事を雪以外には気付かなかった筈だが、今はこれを読んでゐる君も知る処となった訳だ。今も私の鼓膜には、
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
と、私を困惑の坩堝にしか投げ入れぬ《他》の魂魄の叫びが、声に為らざる唸り声を上げてゐるのだ。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
この不快極まる声為らざる唸り声は、死者が《死》を受容するその儀礼に違ひなく、私もまた、己が死す時に私自身がこのやうに声為らざる唸り声を発しながら、浄土か地獄へ向けてゆるりと移りゆくに違ひないのだ。
…………
…………
――何がご名答なのかね? 甲君。
と猊下たる丙君が甲君の哄笑を遮るやうに重重しく尋ねたのであった。
――いや、何、私において、私の内部に巣食ふ何《もの》かが不意に『ぷふぃ。』と嗤ひ声を発した刹那の《吾》の底無しの孤独感に、私は《無限》といふ観念を惹起せざるを得なかったのさ。
――ふむ。成程、君の内部にも得体の知れぬ何《もの》――それを私は《異形の吾》と名付けているがね――その何《もの》かが君の内部で不意に『ぷふぃ。』と嗤った刹那の寂寞感に、君は《無限》を見出すか――。ふはっはっはっはっ。
と猊下たる丙君が尚も続けたのであった。すると、甲君が、
――君にヴァン・ゴッホの苦悶が解かるかね?
と今度は甲君が丙君に尋ねたのであった。
――成程、君の内部の『ぷふい。』といふ嗤ひ声はゴッホにおける烏のやうな《もの》なのだね?
――否。ヴァン・ゴッホの苦悶は、《世界》に最後通牒を突き付けられた、つまり、《世界》に見捨てられちまったその言語を絶する絶望故に、最早、絵画といふ表現手段しか残っていなかった《存在》の苦悶なのさ。――ぶはっはっはっはっ――。
と、甲君は再び哄笑して、その場が重重しい雰囲気に雪崩れ込むのを堰き止めるやうに、甲君は哄笑して、その場の雰囲気を一変させたのであった。
――ちぇっ、哀しい哉、それが、君の優しさなのだ、甲君。
と丙君が言ったのであった。
――まあ、俺の事なんぞどうぞご勝手に。ところで、乙君、君は何故に「一」に疑念を抱いたのかね?
と、甲君が訊いたのであった。すると、乙君が、
――何ね、オイラーの公式を知ってしまった時かな、はっきりと私は「一」に対して「一」である事に疑念を抱いたのは。
――つまり、「一」と虚数iの不思議な関係だらう。
――さう。私は、それ以前、虚数は数学上、数字を拡張せざるを得ずに見出された数字の事だとばかり思ってゐたのだが、つまり、数学が進歩し、人間の文明も進歩した故に、のっぴきならぬ処で、数学者は虚数iを渋渋受け容れたとの先入見を持ってゐたんだが、オイラーの公式を知ってしまふと、虚数iは「一」といふ《存在》に必要欠くべからざる《存在》として、此の世に厳然と《存在》する《もの》といふ認識に至る外なかったといふのが本当の処かな。
と、乙君は言ったのであった。すると、雪が、乙君に尋ねたのであった。
――オイラーの公式に関しては先程、お伺ひしましたが、乙さん、あなたにとってオイラーの公式に出合ふ以前は、「一」は一体全体何だったのかしら?
――此の世の開闢を象徴する、つまり、《無》たる零の《世界》に「一」といふ《存在》が忽然と現はれ、その出現に対する《存在》の大歓喜の雄叫びが、私にとっての「一」といふ《存在》だったのです。
――さうですか。大歓喜の雄叫びですか――。乙さんは、今も「一」に対しては同じ感覚を持続してゐますね?
――ええ、オイラーの公式を知って、尚更、「一」は《存在》の大歓喜の雄叫びだと思ってゐます。
――「一」が《存在》の大歓喜の雄叫びだと? それは異な事を言ふ。
と、甲君が乙君の言を遮ったのであった。
――では、甲さんにお伺ひしますわ。甲さんにとって《存在》とは何ですか?
と雪が尋ねると、
――へっ、何を藪から棒に!
――甲さんは、御自分の事は語らず、《他》の事にばかり感(かま)けてゐるやうに見えるので、甲さんの存在論的のやうな《もの》を拝聴したくお伺ひしたのです。
――さう。君は何時も己の事になると茶化してその場を逃げようとするが、実際の処、甲君、君は、己の底知れぬ哀しみを《他》に知られる事を極度に嫌ってゐるが、それは何故かね?
と猊下たる丙君が言ったのであった。
――そして、甲君、君は良くも悪くも《他》に優し過ぎる。私には、君は独り自己破壊する事が君の存在理由に思へるのだが、もうそんなピエロの仮面を外して、君の正体を見せてもいいのぢゃないかな。
と尚も丙君が続けたのであった。
――今でなくてもそれは構はぬではないかね? 俺がピエロの仮面を外す時は、自分で決めるよ。それを《他》に強要されたくはないなあ。
と甲君が言ふと、雪が甲君に尋ねたのであった。
――甲さんが、何故にこのヰリアム・ブレイクを読む勉強会、いえ、サロンね、このサロンに参加してゐるのか何となく解かるやうな気がします。甲さんは、己の存在理由を此方の丙さんに対峙させる事で、つまり、丙さんを己を映す鏡として、其処に映る此の世の仮初の己の姿形を凝視する事で、甲さんの内部では途轍もない葛藤が起きてゐて、甲さん自身が自ら率先して自分を追ひ詰める事を通して、甲さんはやっと今を生きられるのですね? 違ひますか、甲さん?
――まあ、俺の事なんぞはどうとでも勝手にどうぞ。所詮、俺の事など丙君の前では戯言でしかないのだからね。さうだらう丙君?
と甲君がにたりと笑って言ったのであった。
――雪さん、甲君は最後の最後までその正体の尻尾すら見せませんよ。甲君は普段己を圧し殺す事で何とか絵が描けるのですよ。彼の絵を御覧に為れば、彼の苦悩の深さに驚かれる事でせう。
と丙君が言ふと、甲君が、
――何を言ひ出すのかね、丙君。俺の絵の事はこの場に持ち出さなくてもいいぢゃないか。
――別段、隠す事でもなからう。雪さんを除いて此処にゐる《もの》は全て甲君の絵は見た事があるんだから。丙君の言ふ通り、君の絵には君の苦悩の深さがよく表はれてゐる。
と君が言ったのであった。
――さうさ。君の絵には例へば梶井基次郎の「檸檬」に匹敵する何かが確かに《存在》する。
と文学青年の丁君がさう言ったのであった。
――ちぇっ、乙君の「一」からとんだとばっちりを受けちまったぜ。まあ、俺の絵を皆にさう見られてゐる事は嬉しくもあるが、その嬉しさには君等には解からぬ憂ひが含まれている事は、ちぇっ、解かる筈もないか。くっくっくっ。
と甲君は嗤ひながらさう言ふと、乙君が、
――所詮、《他》は《吾》にとっては超越論的な《存在》で、君は、それをたった独りでぶち壊さうと躍起になってゐて、それは見てゐる此方は、とても痛痛しくて見てらんない《もの》なのだよ。
と言ったのであった。すると、雪が、乙君に、
――それは、甲さんが、《吾》の破壊を欣求してゐるといふ事かしら?
――ええ、それ故にか、この《杳体御仁》の「黙狂者」君と甲君はとても馬が合ふのです。
――それは本当ですの?
――はい、さうです。甲君とこの「黙狂者」君は不思議と馬が合ふのです。多分、方法は違へども、その目指す処は、二人とも同じなのかもしれません。
と乙君が言ったのであった。
――うふっ、ピエロと「黙狂者」、面白い組み合わせね、あなた?
と雪は楽しさうに私に語りかけたのであった。
――ちぇっ、余計な事を!
と甲君が笑顔で言ったのであった。
――ねえ、あなたは甲さんの事、どう思ってゐるの?
と雪が興味津津の態で私に愛らしい笑顔で尋ねたのであった。私はと言ふと、暫くは知らぬ存ぜぬを決め込んでゐたのであったが、誰もが押し黙ったまま皆で私を見詰めてゐるので、仕方なく私は大学Noteにかう書いたのであった。
――つまり、主体は、つまり、現在、つまり、訳も解からず、つまり、その在り処を、つまり、喪失した、つまり、根無し草としてしか、つまり、《存在》する事を、つまり、許されなくなってしまった。
――さうかな?
と、君が訊いたのであった。
――つまり、主体は、つまり、その《存在》する、つまり、根拠を、つまり、見失ってしまってゐる。
――さうかな?
と再び君が訊いたのであった。そして、君が、
――私の見る処によれば、主体は、自らの肥大化に《吾》ながら驚いてゐるに過ぎぬと思ふがね?
すると、雪が君に、
――××さんは、この《杳体御仁》と呼ばれ、現在、「黙狂者」になってしまったこの方をどう見てゐますか?
と、訊いたのであった。すると、私がすかさず大学Noteに、
――つまり、私は、つまり、《主体弾劾者》さ。
と、書いたのであった。
――うふっ、いきなり《主体弾劾者》と言はれても、何の事かさっぱり解からないわ。
――解かる筈ないさ。だってこの「黙狂者」たる彼にすら《主体弾劾》が何なのか全く解かってゐないのだからね。
と、君が雪に言ったのであった。
――へっへっ、さうかね、この「黙狂者」君は、最早、肥大化するに任せたまま、余りに肥大化してしまった主体の有様が、決して許せずに、それ故にその肥大化してしまった《吾》が断じて許せず、己を許せぬが故にこの「黙狂者」君は、遂には言葉を発せられなくなってしまって、さうして自ら語る事を断念して、そのまま口を噤んだまま独り「黙狂者」として此の世に恬然と屹立する事を自ら選んだのさ。
と、甲君が言ったのであった。
――では、甲さん、この方を《杳体御仁》とお呼びになるのはどうしてですか?
――何ね、この「黙狂者」君によると、主体は埴谷雄高が生涯を賭けて追ひ求めた《虚体》を欣求してゐた牧歌的な時代はとっくの昔に終はってゐて、彼が言ふ処の《杳体》といふ杳として何の事かさっぱり解からぬ《存在》、へっ、それを《存在》と呼んでもいいのか俺には解からぬが、その《杳体》を闡明する事でのみ、肥大化に肥大化してしまった主体は、生きも出来、死ぬ事も出来ると、この「黙狂者」君は、考へてゐるのは確かだね。
と甲君が飄飄と言ったのであった。
――甲さんは、《主体弾劾者》といふ《もの》をどうお思ひですの?
――この「黙狂者」君は、得体の知れぬ《存在》に対して正面突破攻撃をおっ始めたのさ。
と甲君が言ったのであった。
――《存在》に対する正面突破攻撃が《主体弾劾》ですって! それはもしかすると自殺行為と同じぢゃありませんの!
――へっへっ、雪さんの仰る通りだがね。この「黙狂者」君は、その自殺行為を観念の世界でのみ、只管、行ふ事で、その観念に依ってのみ《存在》を捻じ伏せる事が可能と考へたのさ。つまり、Idea、日本語にすると《念》ずることでのみ《存在》は捻じ伏せられると、この「黙狂者」君は独り《主体弾劾者》となる事で、実践してゐるのさ。
――それは甲さん、あなたも同じといふ事ですの?
――いいや、俺は全く逆ぢゃないかな。俺の場合は、主体は此の世界から気付かぬ内におっぽり出されて、遂には己の居場所を此の世で見失っちまったと思ってゐます。
と甲君が尚も飄飄と言ひのけたのであった。すると、雪が、
――此の世界から抛り出された主体ですか……それは、さもありなむ、と言へますね、うふっ。
と、雪は愛らしい笑顔を私に向けたのであった。
――つまり、甲さんが仰る世界=外といふのを象徴するのが、電気的に画像を映す《画面》といふ《存在》の有様を指しての事でせう、甲さん?
――それは、一つの象徴でしかありません。
――それでは、甲さんは、何をもって此の肥大化に肥大化した主体を世界から抛り出された《存在》と定義付けてゐるのですか?
――それを簡単に言へば、肥大化した主体が生きれば、世界を頭蓋内の闇の脳といふ構造をした《五蘊場》に表象された《もの》に変へてしまふといふ事です。
――つまり、甲さんに言はせると、主体は《存在》するだけで世界を自分の都合がいい《もの》に変へてしまって、世界の恐怖の《面》を何処かへ追ひやるといふ事ですわね?
――まあ、簡単に言へばさうですが、しかし、主体が肥大化すればする程、世界は主体に都合がよくなければ主体の《存在》は成り立たない。
――それは何故ですの?
――つまり、主体が肥大化するとは、世界を主体から遠ざける事を意味しますが、しかし、実際の処、主体が世界をおっ払ふ事なんぞ出来る筈がない。つまり、主体は、突然豹変する世界の恐怖の《面》を見る間もなく世界に殺されちまふのです。
――つまり、甲さん、現代人は誰もが世界の素面を全く知ることなく、世界に《死》の《面》が現はれれば、忽然と《死》す、換言しますと、現代人は世界を全く知らずに生きてゐるといふ事ですの?
――はい、その事が淵源だとは気付くこともなく、現代の主体は、それが何であれその内部で増幅されるに違ひない《不安》を、それとはまた気付かずに、しかし、主体は漠然とそれを感じてはゐますがね、しかし、主体はそれから目を逸らし、余りに羸弱な世界の一様相のみを主体の肥大化と世界を同調させて、主体はそれを主体同調世界と呼べば、その主体同調世界を主体はそれとは全く気付かずに肥大化させてるのです。そして、雪さん、主体はそんな歪な世界を世界と看做してゐるのですが、そんな世界を雪さんは世界と呼べますか?
――いいえ、それでは主体はそれが何であれ「先験的」に盲人だと言ふのと何ら変はりがないぢゃありませんか!
――さうです。主体が肥大化すればする程、世界は主体には見えなくなるのです。
――それが、世界=外といふ事ですの?
――さうです。現代に《存在》する主体は全て目隠しされた《存在》なのです。つまり、一寸先は闇の世界と何ら変はりがないのです。
――それで、甲さんは絵を描くことで世界を見出したいのですね?
――へっへっ、それはどうぞご勝手に。私の事はどうでもいいぢゃありませんか?
と、甲君は少しはにかみながら言ったのであった。
――甲さんの話からすると、此の世の森羅万象はそれが全て主体と定義付け出来得ると仮定したならば、何《もの》も最早、世界を見失ってゐて、それは、つまり、主体が主体を見失ってゐるといふ事ですわね! うふっ、すると、甲さんによれば、世界が回復するには、先づ、主体の再生が不可欠といふ事ですわね?
と、雪は薄らと楽しげな笑ひをその窈窕な相貌に浮かべて言ったのであった。すると、
――主体の定義付けは君の仕方ではその本質を見失ってしまふ事間違ひなしだが、君はその事に気付いてゐるのかね?
と、丙君が言ったのであった。
――俺の事なんぞどうぞご勝手にと言った筈だがね、丙君。
――だが、君の主体の見立ては、一面的過ぎやしないかね?
――例へば?
――例へば、世界は主体の都合で変へられるなんていふのは単なる幻想でしかない。
――だから?
――つまり、世界は、常に主体を《存在》の在り処として、有史以来、否、全宇宙史以来、変はらずに《存在》してゐる。例へば自然は、主体を簡単に殺せる恐怖の《面》を持ってゐるが、その自然に対する現代の主体の感じ方は、古の邪神や邪鬼などの《存在》を心底信じてゐた世界に対する畏怖と、現代の主体の世界観は殆ど変はってゐやしないぜ。
…………
…………
ねえ、君。此の世に《吾》の事を《吾》と《念》じられる、つまり、此の世の森羅万象は、全て己を《主体弾劾者》として、己で己を裁かなければ為らない「先験的」な義務を負ってゐると思はないかい? 何故って、今も尚、磔刑されたままの基督の磔刑像がRosary(ロザリオ)として、基督者の首にぶら下がってゐるその様は、何とも無情で遣り切れない感情を私に齎すが、換言すると、基督者は己で己を《弾劾》する事で一刻も早く基督を磔刑から解放してやらなくちゃいけない。また、此の世で生きる上で避けやうもない艱難辛苦を神仏に祈り、また、加護を賜る事を望みながら、此の世の邪神や邪鬼が横暴を働くことを鎮める為のそんな主体の振舞ひは、別段悪くはないが、しかし、《吾》が《吾》と認識した《吾》といふ全《存在》、つまり、此の世の森羅万象は、神仏に縋る事無く、徹頭徹尾《吾》は《吾》によって徹底的に《弾劾》される事で初めて、神仏の前に立てるのぢゃないかい?
私から言はせれば、現在、生きてゐる主体全ては、神仏はもとより、《世界》にもおんぶに抱っこされた甘ちゃんばかりが生き延びる不合理極まりない《世界》の無情を感じずにはゐられぬのさ。此の世の森羅万象は、しかし、君、己を己で裁く《主体弾劾》を行使すると思ふかい?
…………
…………
――つまり、丙君は、人類は殆ど進化してゐないといふ事を言ひたいのかい?
と、甲君が丙君に尋ねると、
――ああ。私に言はせれば人類は進化してゐるどころか、むしろ退歩してゐるとしか思へぬがね。
と、丙君が言ふと、雪が、
――あら、丙さんは、もしかして文明否定論者ぢゃありませんの?
――はい。私は此の文明といふ奴との相性がとことん悪いやうで、どうも文明に対しては、否定的な感情しか湧かないのです。
――それは何故かしら?
――多分、文明が進歩する事、即ち人類の進歩といふ能天気な考へが全く受け入れられず、自分でもほとほと困ってゐるのです。これまで、人力でしか行へなかった事が、どんどんと文明によって人力以上の事がいとも簡単に行へ、さうして人類の人工奴隷として生み出された文明の利器の数数を見てゐると、哀れで仕方ないのです。
――へっ、何をしをらしい事を言ってゐるのだ、丙君?
と、甲君が半畳を入れたのであった。
――では、甲さんは、人類は進歩してゐると?
と、雪が訊くと、甲君は、
――へっ、まさか! 俺はさっきから言ってゐるやうに主体は《世界》から抛り出されちまって救ひやうのない《存在》として捉へています。
――さうでしたわね。
――私は丙君に賛成だ。
――僕もだ。
――私はどちらとも言へない。
と、乙君、丁君、そして君が言ったのであった。
――雪さんはどう思ひますか?
と、甲君が笑ひながら訊いたのであった。
――さうね、文明の利器に関しては、人類の奴隷でもあり、人類の主人でもある……かしら。
――成程。
――それでは、文明の利器が主人の場合、人類は、どんな思ひでゐるのでせう?
――それは苦苦しく忸怩たる思ひで、もしかすると、その人達の胸奥では不穏な復讐心が芽生えて、燃え盛ってゐる、殺人鬼へと豹変する素地の上にゐるのかもしれませんわね。
――成程。
と、甲君が言ったのであった。すると、丙君が、
――雪さん、《存在》が《存在》する以上、《他》の殺戮はなくならないと思ひますか?
――それは食料を除いての事かしら?
――はい、さうです。
――さうねえ、哀しい事ですが、主体が何かを信仰してゐる限り《他》の殺戮はなくならないと思ひますわ。しかし、何の信仰もない主体はこれまた一時も生きられないのもまた事実でせうね。
――すると雪さんは、諸悪の根源に信仰があると?
――私は、信仰は尊ひ事とは思ひまずが信仰が尊ひが故に、自然が邪神や邪鬼の一面を持ってゐるやうに、信仰は、醜悪で《吾》といふ《存在》には荷が重すぎ、手に負へぬが故に吹き出す暴力が、信仰には厳然と《存在》してゐるのもまた確かでありませんか、丙さん?
――例へば《存在》は絶えず「真」、「善」、「美」を求めずにはをれぬ《存在》であると看做すと、その事自体に、必ず「邪」、「悪」、「醜」をも求めてしまふ元凶が潜んでゐるといふ事ですか、雪さん?
――はい。私の経験に照らしても……、さうですし、また、此の世の森羅万象は全て、「真」、「善」、「美」を求めずにはゐられぬのに比例する形で「邪」、「悪」、「醜」に魅せられてしまふといふ、《存在》がそもそも矛盾した《もの》でしかないと考へてゐます。
――へっ、何やら面白くなってきたな、丙君。
と、甲君がにたりと笑ひながら丙君に言ったのであった。しかし、丙君は甲君には構はずに更に雪に訊いたのであった。
――それでは雪さんは、もしかすると《存在》が諸悪の根源と看做してゐるのですか?
――本当の処はそれを認めたくはないのですが、《存在》は何かと考へれば考へる程に、《存在》が諸悪の根源と言ふ一面を持ってゐる事は否めません。そして、それは「先験的」なの事だと私は考へてゐます。しかし、それはとても残念で仕方がないのもまた事実です。
――そんな事は……文学作品を読めば必ず「邪」……「悪」……そして「醜」なる主題が書かれてゐて……それが文学の永劫の主題とも言へるものなのだが……しかし……だからと言って私には何も言へないのだが……しかし……《存在》から「邪」、「悪」、「醜」がなくなっちまふと……そもそも《存在》は雲散霧消してしまふ何かとしか私には思へぬのだが……だから……私は私が此の世に《存在》してゐる事に憤怒せずにはをれぬのだ!
と、文学青年の丁君は珍しく最後は語気を強めて言い放ったのであった。
――へっ、丁君、そんな事は皆承知しているのを知ってゐるぢゃないか。
と、甲君が丁君を宥めたのであった。しかし、一度憤然としてしまった丁君は、未だ怒り収まらずの態で、その怒りを自身に向けて自身を呪ってゐるやうであったのである。すると、丙君が、
――甲君の言ふ通り、丁君の言った事は皆自覚してゐる事なのです、雪さん。
――さうですか。しかし、あなた方はそれが甘受出来ずに苦悶してゐるのぢゃありませんの?
――ご名答、雪さん!
と、甲君がその明るい語調とは裏腹に甲君はその顔に少し憂ひを漂はせて言ったのであった。
――《存在》は土台、「邪」なる《吾》、「悪」なる《吾》、そして「醜」なる《吾》を《異形の吾》として「先験的」に抱へ込むやうに仕組まれてゐて、ところが、《存在》が此の世に《存在》する以上、その事から目を背ける事は許されてゐない《存在》として、森羅万象はその《異形の吾》からの遁走の道はこれまた「先験的」に自ずと断たれてゐて、《吾》といふ《存在》は《存在》するだけで既にのっびきならぬ《存在》の立ち位置に《存在》させられてゐるのが実際の処だらう。
と、君が言ったのであった。
――それで? 君の言は全てがこの《杳体御仁》の「黙狂者」君の受け売りだらう?
と、甲君が言ひ、其処で君は、
――だから、《存在》は「先験的」に苦悶する事を余儀なくさせられてゐる《もの》と看做せるのぢゃないかね、甲君。
と、君は言ったのであった。すると、猊下たる丙君が、
――しかし、それでは現状を唯、承認、若しくは追随したに過ぎぬのもまた事実だらう?
――さう。丙君の言ふ通り、《存在》が「邪」、「悪」、「醜」なる《吾》を承認する事は、《存在》が《存在》する以上、当然の事で、丙君の言ふ通り現状維持に過ぎぬのだが、しかし、此の《吾》はその事が口惜しくて堪らないのもまた事実だらう?
と、君が言ったのであった。すると雪が、不意に、
――では、形而上には「邪」、「悪」、そして「醜」は《存在》しないといふ事ですの?
と尋ねたのであった。
――形而上に「邪」、「悪」、そして「醜」があるのかどうかをはっきりとお答へする資格は、そもそも私にはありませんが、尤も、《存在》は形而上には「邪」、「悪」、そして「醜」のない仮象世界を思ひ描きたい欲望はあるとは思ひますが。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
――それでは××さん、形而上と理想郷の違ひは何なの、うふっ。
――其処に明白な違ひは多分ないと思ひますが、だからと言って、神代の時代に「邪」、「悪」、そして「醜」がないと言へば、それは全く逆で、神程、傲岸不遜で此の世に《存在》する《もの》の中で最も「邪」、「悪」、そして「醜」の振舞ひの限りを尽くした《存在》は、世界中の神話に照らせば明らかで、それから推察しますと、形而上にも「邪」、「悪」、そして「醜」は残念ながら《存在》すると看做した方が自然ですね。
――しかし、××さん、形而上の《存在》の全ては、己が今行ってゐる事が「邪」、「悪」、そして「醜」なのかを自覚するきっかけを全く失ってゐると思ひませんか?
――さうですね、雪さん。形而上の《もの》は、全て《吾》といふ観念から解放されてゐますね。
――さうかしら?
――と言ひますと?
――形而上の《もの》は、唯、《存在》する事に夢中なのぢゃありませんか? つまり、究極の自己陶酔の中にあるといふ自覚が何処まで行っても見出せないだけだと私は思ひますわ。
――それは、つまり、魂が渇望する《世界》にこそ、形而上の何たるかが啓示されてゐて、それをこの《現実》といふ超自然的な人工世界が図らずも代弁してゐるとお思ひなのですね、雪さん。
と、君を押し留めて丙君が訊いたのであった。
――現在の此の世の《他》の頭蓋内の脳といふ構造をした闇、それをこの方は《五蘊場》と呼んでゐますが、その《五蘊場》に表象された《もの》で埋め尽くされたこの超自然的な人工世界が、此の世の森羅万象が渇望して已まなかった理想の《現実》だった事は、多分、間違ひない事なのだと思ひます。つまり、此の人工物が犇めく此の《現実》こそ形而上の《世界》の一様相を表わしてゐて、その事により、此の世の森羅万象は底知れぬ虚無感に、今現在、苛まれてゐる、そして、多分、その人工世界が崩壊を始めて新たな世界観を生み出すべくParadigm変換の変動期に、私達は居合はせてゐるに違ひないと私には思へて仕方ないのです。
――すると、雪さんが、××君に問ふた『形而上に「邪」、「悪」、そして「醜」が《存在》してゐるか?』といふ命題は、雪さんの中では既に自明の事で、やはり、形而上においても「邪」、「悪」、そして「醜」は《存在》してゐるけれども、形而上での《存在》の全ての《もの》はその《存在》自体に夢中為るが故に、己の振舞ひが「邪」、「悪」、そして「醜」と自覚される事は未来永劫に亙ってないといふ事ですと、それでは《存在》が此の世に何としても歯を食ひ縛り、砂を噛み締めながらも《存在》する事の希望といふ《もの》は、最早残されていないと?
――はい。希望は、元来、此の世にも、形而上にも《存在》した形跡はありません。
――すると吾吾が希望と呼んでゐる《もの》の正体は何と?
――我執、我慾等等、《吾》が《吾》であるかもしれないと一瞬でも思はせて呉れる架空の《もの》の事を《吾》は希望と呼んでゐると私には思へて仕方ないのですの。
――つまり、希望は、此の世に《存在》する為の阿片といふ事ですか?
――はい。私はさう看做してゐます。
――しかし、此の世に希望が無いといふ事は、多くの《存在》にとっては、その《存在》を支へる支柱を失ふ事に直結し、此の世は此の世の初めの渾沌状態に逆戻りしてゐる事になりませんか?
――はい。だから、先程、私は現在、新たなParadigm変換の変動期を迎へてゐると申したのです。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
――すると、《吾》は今一度《吾》の創り直しを行ってゐる状態に現在あるといふ事ですか?
――はい。うふっ。そんな事、私にお訊きになる前に丙さんには既にお解かりの事ぢゃありませんの? うふっ。
――へっ、古狸の化けの皮が剥がれたな、丙君!
と甲君が此処ぞとばかりに半畳を入れたのであった。
――確かに雪さんの仰る通り、私には或る偏向した観念が《吾》に対してあるのは間違ひありませんが、それだから尚一層、私には《吾》が何を指してゐるのか解からなくなってしまふのです。
――あら、そんな事、誰もが同じ事ぢゃありませんの? 丙さん。
――やはりあなたも吾等と同類のパスカルの深淵の住人なのですね、雪さん。
と丙君は苦笑ひしながら言ったのであった。そして、丙君と同じやうに笑顔で雪が、
――うふっ、パスカルの深淵の住人ですか? つまり、私も穴居人といふ事ですね?
――はい、さうです。雪さんもまた穴居人です。立派なパスカルの深淵の住人です。
――それは褒め言葉ですの、うふっ。
――さあ、それは解かりませんが、吾等は《吾》に躓いてしまった《存在》である事は間違ひありませんね。
――《吾》に躓かない人なんて此の世にゐるのかしら?
――へっ、そりゃさうだ、なっ、丙君!
と甲君が、嬉嬉として言ったのであった。
――確かにさうですね。だが、殆どの《存在》はそれが青臭いといって、一時出来る腫物の如く自然に治癒する《もの》と思ひ為してやり過ごし、そして、挙句の果てが《吾》は《吾》だと開き直って《吾》のその醜悪なる異形の面を全く無視して何食はぬ顔でのうのうと生きてゐる。それが、パスカルの深淵の穴居人には全く理解不能の事で、また、不思議でならないのですが、彼等はとことん《異形の吾》の《存在》を知らんぷりして現状に満足の態で、《吾》が《吾》に躓く事が《存在》の生死に関はる大問題である事に全くピンと来ずに『何を下らぬ事に現を抜かしてゐるのか!』と訝しり、大抵はパスカルの深淵の住人たる穴居人を蔑視して、彼等は徹底して《吾》を見ずに《吾》から只管遁走してゐるのですが、しかし、その内実はと言ふと、実際、《吾》が《吾》である事が不安で仕方ないのです。そして、彼等はその不安に徹底して対峙したくないので、吾等のやうなパスカルの深淵の住人たる穴居人は《吾》に《吾》を喚起させるので、全く毛嫌ひして乞食を見るやうに見なかったことにして「社会的」な《存在》といふ《吾》が《吾》である事から一面で解放する《吾》のない《存在》である振りをし続けるのです。まあ、それはそれで胃が痛む事ではありますがね。
――さうですね、丙さん。しかし、《存在》の作法として『《吾》は《吾》に躓いてゐる』と胸を張るのもまた不作法でどうかしてゐます。《存在》はそもそもその正体を隠す《もの》で、出来得ればその《存在》の、もしかするととんでもなく無様な有様を見たくないのは《存在》に備わった本能に違ひありません。その好例が、此方の甲さんですわ。
――へっ、俺ですか?
――確かに雪さんの仰る通り甲君は、明るく振る舞ってはゐますが、その振舞ひの彼方此方に甲君の本質に関はってゐるに違ひない憂ひがどうしてもそのおくびを出してしまはずにはをれないのです。
――丙さん、甲さんばかりでなく、あなたもまた、その鋭き眼光に憂ひの《吾》の姿がまざまざと見えてしまってゐますわ。
――何故さう思ひます?
――だって、丙さんのやうにぎろりと眼光鋭く《他者》を見る人は、いえ、《存在》ですね、その《存在》は《吾》をも同様に眼光鋭く覗き込まなければ気が済む筈はありませんもの。
――確かにその通り!
と甲君がこれまた笑顔を湛へながら言ったのであった。
――そして、乙さん、丁さん、××さん、そしてこの《杳体御仁》の「黙狂者」さんも同じです。普通であれば、《吾》に躓いた《吾》は、直ぐに起き上がって何事もなかったやうにさっさと歩いて行く《もの》ですが、此処に集ってゐる皆さんは、《吾》に躓いても立ち上がる事が出来ずに、またその術が全く解からず、ひっくり返った亀の如く首をぬっと伸ばして元に戻る膂力が無くなく、只管、のた打ち回ってゐるのが精一杯なのですわ。
――また、何故にさう思ったのです、雪さん。
と丙君が重重しく、そして鋭い眼光をぎろりと輝かせて尋ねたのであった。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
――それは簡単ですわ。私があなた方と会った刹那、私自身が自分に対して感じる或る特徴をあなた方にも感じたからですわ。つまり、類は友を呼ぶですね、うふっ。
――つまり、雪さんは、この「黙狂者」の彼に自分と同じ《もの》を見てしまったと?
――はい。
――例へばこの彼の何が雪さんにさう感じさせたのですか?
――この方の瞳よ。この方の瞳は、何メートル先にあらうが、その憂ひに満ちた不穏な輝きが一際目立つのです。
――すると雪さんは、今日、この「黙狂者」と会ふ前から既に彼を気に掛けてゐたのですか?
と、君が雪に尋ねたのであった。
――ええ。いづれはこの方と対する事になるだらうと思ってゐました。
――うはっ。すると雪さんはがこの《杳体御仁》の「黙狂者」君に惚れてゐたと?
と、これまた甲君が嬉嬉として言ったのであった。
――はい。
――うはっ。『はい。』、と来たもんだぜ。すると雪さんの一目惚れかい?
と、これまた甲君が嬉嬉として雪に尋ねたのであった。
――はい、うふっ。
と、雪はその窈窕な顔に薄らと紅色を浮かべて微笑みながら言ったのであった。
――よう! 《杳体御仁》、何とか言へよ!
と、甲君が私を囃し立てながら茶化すのであった。
――雪さんは一体彼に何を見たのですか?
と甲君の言葉を無視して猊下たる丙君が言ったのであった。
――さあ、何かしらね……強ひて言へば、この方と私の第六感の波長がぴたりと合ってゐたことかしら……、つまり、例へば前世といふ《もの》があるとしたならば、この方と私は前世では夫婦だったと、この方を一瞥した刹那に私はこの方に魅せられてしまった、と言へばいいのかしら。
――それだけですか?
――いいえ。この方の《存在》が何かとても愛ほしかったのです。多分、私はこの方に私の亡き父の姿を見てしまったのでせう。
――さうですか。
――へっ、何を落胆した面をしてゐるんだね、丙君!
と、これまた甲君が嬉嬉として言ったのであった。
――ちっ、それが君の優しさなんだよ。
と、丙君はにんまりと笑って甲君に言ったのであった。
――よう、《杳体御仁》の「黙狂者」君、女性から直截に恋心を打ち明けられた感想はどんな《もの》かね?
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
相変はらず私の瞼裡には、見知らぬ男が私の眼前に拡がる虚空を声に為らざる声を発しながら何処とも知れぬ何処かへと浮遊してゐるのであった。
しかし、その時は皆が押し黙ったまま私の手元を見てゐたので、私は仕方なく、大学Noteにかう書いたのであった。
――つまり、私も、つまり、雪と同じだ。
――はっはっ。二人とも一目惚れ同士か! このお、まったく隅に置いておけないな、《杳体御仁》!
と、ヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君がさらに嬉嬉として半畳を入れたのであった。
――成程。雪さんは、この「黙狂者」の全てが知りたくて、今日、私たちのサロンにいらしたのですね?
と君が言ったのであった。すると雪が、
――はい。もしもお邪魔でしたなら、私はお暇しますが。
――いえ、雪さんはいらしてください。男ばかりだとどうもむさ苦しくていけないんでね。紅一点の華美な花がここにゐるのとゐないのとでは雲泥の差なのです。
と君は言ったのであった。
――《杳体御仁》がお美しい雪さんに惚れるのは解かるとしても、雪さんがこの発話不能な「黙狂者」君に惚れるとは、此の世はまだまだ捨てたもんぢゃないな。不思議だぜ、此の世は。
――あら、私はその発話不能な処が尚一層好きなのです。
と、雪は、きらきらと輝かしい笑顔で言ひ切ったのであった。
――それはまたどうしてですか、雪さん?
と、丙君は、天井へとその視線を向け、己の頭蓋内の闇を弄るやうにして、重重しく言ったのであった。
――現代では、発話可能な方は、実際、《存在》してゐると思ひますか、丙さん? 私は現代では発話そのものが既に不可能な時代なのだと思へて仕方ないのです。
――しかし、私達は、現代にかうして発話しながら会話を交はしてゐるぢゃありませんか?
――でも、私達は《存在》をぴたりと言ひ当てる言葉を喪失してゐます。
――それはさうですが、しかし、何時の世も、《存在》をぴたりと言ひ当てる言葉は《存在》してゐなかったのではありませんか?
――いいえ。嘗ては《神》が確かに《存在》してゐました。つまり、発話とは信仰と深く結び付いた《もの》でなければ、それは全て嘘でしかありません。それ故に嘗ての「現存在」が発話する言葉には《吾》といふ《念》が宿り、つまり、言霊が確かに《存在》してゐたのです。
――それは呪詛ではありませんか?
――ええ。呪詛でも構ひません。嘗ては発話にはそれだけの不可思議な《力》が宿ってゐたのですが、翻って現代では、言霊を信じてゐる人がどれだけゐると思ひますか?
――さうですね、皆無ぢゃありませんか。
――さうです。言霊はすっかり失はれてしまったのです。
――しかし、言霊信仰は呪詛があるやうに現代ではOccult(オカルト)的で危険です。
――あら、どうして、丙さん?
――う~ん、何と言へばいいのかな……つまり、現代人には既に言霊を背負ふだけの膂力が蒸発してしまってゐます。
――うふっ、さうですね。でも、現代人の潜在能力として言霊を担ふだけの膂力は残されてゐるに違ひないと、私には思へます。
――と言ひますと、例へばどんな処に、雪さんはそれを感じますか?
――例へば誰しもその《存在》が《死》の淵に追ひ詰められれば、必ず信仰告白をする筈だと思ふのです。
――つまり、雪さんは、現代人もまた、《神》を信仰してゐると?
――はい。それは間違ひありませんわ。
――それでは、《神》のない仏教を何と思ひますか、雪さん?
――あら、仏教にもちゃんと《神》がいらっしゃるぢゃありませんか。つまり、釈迦牟尼仏陀といふ《神》が。
――確かにヒンドゥー教では仏陀は《神》の一人として崇められてゐますが、しかし、仏教徒の全ては、『色即是空、空即是色』の境地を欣求して已まぬのではないですか?
――その境地とは釈迦牟尼仏陀に重なる事でせう。
――ふむ。
――ほら、どうした丙君、押されっ放しぢゃないか!
と、再び甲君が半畳を入れ、そして、雪に軽くウィンクをして見せたのであった。
――うふっ、甲さんて、本当にお優しいのですね。
――つまり、雪さんは正覚する事を何とお考へですか?
と、丙君が甲君には構はず再び尋ねたのであった。
――さうねえ、しじま……かしら。
――しじまですか?
――はい。無音の中で全ての《存在》の呟きが聞こえ、さうして《存在》は己の事を全て語り尽くせる境地が、正覚に違ひありません。
――すると、雪さんは、この《杳体御仁》に正覚者を見てしまったといふ事ですか?
――さうですね。さう言はれてみれば、さうに違ひないのですが、一方で、私はこの方に《存在》の業を強く感じたのです。
――《存在》の業と言ひますと?
――つまり、パスカルの深淵に図らずも突き落とされて、この方の場合はそれ故に瀕死の状態に陥ったにも拘らず、そこで決して《生》を諦める事無く、また《生》に意地でも拘るその生命力かしら?
――生命力ですか。この「黙狂者」君に生命力があるとは私には全く思へませんがね。
と丙君が言ふと、甲君が、
――おいおい、雪さん相手に鎌をかけてどうする?
――あら、甲さん、私は構ひませんわ。そして、丙さん、この方は、現在、《死》の淵をよろめきながら歩いてゐるのですわ。何故って、今の処、この方が《死》ぬやうには誰も思はないでせう?
――それはさうですが、しかし、「黙狂者」君は、私の眼には只管己の《死》ばかりを欣求してゐるやうにしか見えませんが?
と、丙君が言ふと、甲君がまたぱちりと雪にウィンクして見せたのであった。雪もぱっと周囲が明るくなるやうな美麗の笑顔を見せながら、丙君の問ひに答へたのであった。
――それがこの方の生命力の為せる業なのです。
――それはまた何故に?
――丙さん、御免なさい。ちょっと煙草を吸ってもいいかしら?
――ああ、どうぞどうぞ、皆、Heavy smoker(ヘヴィ・スモーカー)ですから気にせずにどうぞ。
と、丙君が言ふと、雪は、鞄から煙草とLighter(ライター)を取り出して煙草を一本銜へると「しゅぼっ」と、火を点け、一息、深深と煙草の煙を呑み込んだのであった。
雪は、やはり、未だ、「男」に対しては緊張してゐたのだ。それでも私が傍らにゐる事で何とか君等に対する事が出来たのだ。雪は飽くまで、その時平静を装ってゐたが、どうやら、緊張が限界に達したので煙草を呑まざるを得なかったのだらう……。
それにしても、雪は、本当に美味さうに煙草を吸ふのであった。
そして、吾吾もそれぞれ思ひ思ひに煙草を銜へて一服したのであった。
――丙さん、この方に生命力があると私が看做すのは、かう言ふ論理です。つまり、余程の生命力がなければ、《死》なずにずっと、《死》の淵、つまり、それが《パスカルの深淵》とするならば、普通であれば、その深淵の淵を何時迄経っても、うろつくことなど不可能なのです。《パスカルの深淵》に追ひ詰められた《吾》は、即座に《死》するか、《パスカルの深淵》から脱する筈なのです。
――つまり、雪さんにとっては、この「黙狂者」君は、《死》も《パスカルの深淵》の脱出も図らぬ事に驚嘆してゐるといふ事ですね?
――ええ。尋常ぢゃありませんもの、うふっ。
――雪さん、それではこの《杳体御仁》は、現在、何をしてゐるとお考へですか?
と、文学青年の丁君が珍しく澱みなく言ひ切ったのであった。
――さうねえ、多分、自分殺しでせう。
――自分殺し?
――はい。この方は、《吾》を何としても炙り出さうと、己の中に巣食ふ幾人もの自分を虱潰しに次次と殺していって、最後のどん詰まりには《吾》が見出せるに違ひないと思ってゐる筈です。
――成程。雪さんもさう睨んでゐたのですね。
とヴァン・ゴッホ気狂ひの甲君が相槌を打ったのであった。
――よお、《杳体御仁》、本当の処はどうなんだい?
と甲君が私に尋ねたので、皆が再び私を凝視し、私が大学Noteに何を書くのかをぢっと息を殺して待ってゐるのであった。
私は、また、仕方なく、
――つまり、私は、つまり、現在、つまり、主体弾劾を、つまり、行使してゐる。
――ふっふっふっ。主体弾劾と来たか! 成程。すると、雪さんの、また吾吾の睨んだ通りといふ事だね。だがね、《杳体御仁》、それを独りでやらうとは水臭いぢゃないか。苦しければ吾等にしがみ付いても構はないんだぜ。
と甲君が、何か愛おしい愛玩動物を愛でるやうに私を見たのであった。
――本当に甲さんてお優しいのですね。
と雪が今更ながらに感嘆するのであった。
――此奴の優しさは今に始まったことぢゃないからな。此奴に遭った途端に、このゴッホ気狂ひの魅力の虜にならない人間は、多分、殆ど皆無に違ひない。つまり、このゴッホ気狂ひの甲といふ人間は《存在》を愛して已まないのさ。
と君が言ったのであった。
――さうですね。甲さんはきっと《存在》の底無しの哀しみをご存知なのですわ。
――それはまたどうして?
と君が雪に訊いたのであった。
――だって、《存在》する事の哀しさを知らない人が《存在》を愛する、いいえ、違ひますね、《存在》を慈しみの目で見る事は不可能な筈ですから。
――すると、雪さんは甲君にその底無しの《存在》の悲哀が感じられるのですか?
――ええ。私の一方的な甲さんに対する感じ方ですみませんが、甲さんは、実際、独りになると、その絶望の底が知れぬ程の絶望の中で、唯、只管、《世界》と《存在》の正体を見出すばかりでしか《生》が存続出来ない程に追ひ詰められてゐるに違ひありませんわ。
――雪さん、俺の事はどうでもいいぢゃありませんか。
――あら、どうして?
――こっ恥ずかしくて仕様がないから!
――でも、甲さんは、多分、現世に《存在》してしまった《もの》に今一度、『何故にお前は此の世に《存在》するのか?』と必ず問はせる不思議な能力をお持ちぢゃありませんか。
――だから、俺の事はどうでもいいぢゃありませんか、雪さん。
――照れ屋さんなのね、甲さんって、うふっ。
……………
……………
ねえ、君。成程、雪が喝破した甲君に対する眼差しは、冴えに冴えてゐただらう。甲君はたじたじで、ちょっと照れ笑ひを浮かべてゐたのが今でも私の瞼には焼き付いてゐるよ。
それはさておき、君には私が言ふ主体弾劾の正体が解かってゐたのだらうかね。私は当時、既に存在論的に破綻を来してゐて、存在論的抹殺を己自身で《吾》に対して行ってゐたのだよ。それが何かと尋ねられば、私は迷はずに、
――《存在》は「先験的」に此の世から抹殺される宿命を遅かれ早かれ心底味はひ尽くす事を課されてゐる。それ故に、《存在》は現世に《存在》出来得るのだ。そして、己の抹殺を行ふのは、《吾》か《自然》のどちらかしかなく、私は迷はずに前者を選んだのだ。
つまり、《吾》が《吾》を永劫に弾劾するといふ地獄をね。それが、《存在》の全うな作法だらう。
……………
……………
――でも何故に《存在》は、そもそも底知れぬ悲哀を味はひ尽くさねばならないのかしら?
と雪が言ったのであった。
――さうですね。それは《存在》が《世界》を認識せざるを得ぬからでせうかね。
と猊下たる丙君が雪の問ひに答へたのであった。
――《世界》に戸惑はない《存在》などありません。
と数学専攻の乙君が言ったのであった。
――はて? 《世界》に戸惑ふとは?
――如何なる《存在》も此の世に出現するその刹那に、此の《世界》との遭遇に戸惑ひ、『うわぁっあっあっ』と産声を上げるのさ。その時、母親的な、つまり、Agape(アガペー)的なる《存在》が、産声を此の世に発した如何なる吾子たる《存在》へも慈悲の愛を注いで、泣いてゐる《存在》の赤子をあやさずばをれぬ、へっ、本能を《存在》には「先験的」にか「後天的」にか授けられてしまってゐるのさ。しかし、己が《存在》の何たるかを認識出来ないうつけ《もの》が幼子を虐待し、つまり、Ssadism(サディズム)とMasochism(マゾヒズム)といふこれまた本能的なる《もの》に「先験的」に付与された《存在》の愚行を感情の捌け口としてか、将又、感情的なる《存在》へと吾が《存在》を逃げ込ませるのかなど、様様な原因はあらうが、《存在》は残酷極まりない《もの》でもあるのは確かさ。ともあれ、普通の《存在》ならば泣いてゐる赤子はあやさずにはをれぬ《もの》だらう?
――ふっ、それが諸悪の根源ではないのかね。
――埴谷雄高だね。さう、《存在》の赤子が産声を上げれば、《存在》の赤子を微笑みを持って吾が赤子を抱き上げる母親的なる《存在》が《存在》する事が、《存在》を此の世に出現させる諸悪の根源であるのは、一面的には正しいかもしれぬが、しかし、《存在》が《存在》を生み出す業を背負ふ宿命にある女性的なる、つまり、子宮を持つ《存在》のその有様は、《世界》を存続させるべく、此の世に出現させられた一番の犠牲者なのではないかね。例へば、聖マリアなど、《世界》の悪意から吾が子を守るべき事を自覚しなければならなかった《存在》が《存在》した事が、その象徴とも言へるだらう。
と君が言ったのであった。
――ではヨブはどうかね?
と猊下たる丙君が君に訊いたのであった。
――ヨブ程、《存在》の莫迦らしさを徹底的に味はされた悲哀なる《存在》はゐないのぢゃないかな。
と君が言ふと、雪が、
――私は『ヨブ記』が大っ嫌ひなのです。
と言ったのであった。その顔には、《神》と名の付く《もの》への多少の反発とヨブに対する慈しみがない交ぜになったやうな何かを嫌悪する顔付であった。
――また、何故にですか?
――何故って、『ヨブ記』程、《神》の傲慢が描き出されてゐる《もの》はありませんわ。
――《神》の傲慢と言ふと?
と丙君が言ふと、雪が、
――《神》が「現存在」の信仰を試す傲慢ですわ。
――しかし、吾等は絶えず己の信仰心を自ら試してゐるぢゃありませんか?
――だから、《神》自らが「現存在」の信仰を試す愚行を平気の平左で行ってゐるのが我慢ならないのです。
――つまり、雪さんにとって、『ヨブ記』は、《神》によるヨブへの虐めといふ解釈ですね?
――はい、丙さん。《神》が「現存在」を虐めてどうするのですか? 「現存在」が《神》に手も足も出ないのは、端から解かってゐるのに、それを敢へてやっしまふ《神》は一体何ですの?
と雪が捲し立てて丙君に訊くと、丙君は、
――さうであっても、「現存在」は必ずや信仰を捨てられない羸弱な《存在》である事の見本として『ヨブ記』が《存在》してゐると思ひますが。
――それが《神》の傲りなのよ。「現存在」を含めて、此の世の森羅万象がヨブの身になれば、大概どんな《存在》も《神》の撲滅へと衝き動かざるを得ぬ筈だわ。
――《神》を撲滅した後は?
と猊下たる丙君が少し皮肉を交へて雪に訊いたのであった。
――《世界》の相転移よ。
――それは《存在》の全剿滅を意味してゐるのではありませんか?
――はい。《神》を撲滅しての森羅万象は、其処で《世界》が相転移する事象に思ひも及ばず、然しながら《世界》は相転移を起こし、《世界》は《新=世界》へと生まれ変はるのよ。
――雪さんは、相転移と言ふ言葉を何によって知ったのですか?
――この方に。
と雪はにこりと微笑みながら私を見たのであった。
――成程。
と丙君が言ふと続けて、
――現代が、《神》亡き《世界》とは看做せませんか?
――さうねえ。それは一面的では的を射てゐるかも知れませんが、しかし、現代でも《神神》は《死》する事無く厳然と《存在》してゐますわ。
――例へば、その《神神》が全て『《吾》とは何ぞや?』と自問自答する《存在》に纏はり付く自同律の陥穽に落っこちてゐたとしたならば、雪さんは、それをどう看做しますか?
――あら、丙さん、面白いことを仰るのね。さうねえ、此の世の全《神神》が『《吾》とは何ぞや?』といふ自同律の陥穽に落ちた処で、「現存在」はそんな事知っちゃこっちゃありませんわ。唯、《神神》に幻滅し、《神神》に対する見方を見直すかもしれませんね。でも、《神神》は元元、『《吾》とは何ぞや?』といふ自同律の陥穽の中に《存在》する《もの》ではありませんか?
と雪は目を爛爛と輝かせて丙君に訊いたのであった。多分に、雪はこれまで男に対して鬱屈してゐた思ひを吐き出す快感の中にゐるやうに伸び伸びとし始めたのであった。すると、横から甲君が、
――《神神》が『《吾》とは何ぞや?』といふ自同律の陥穽に落っこちるのは勝手だが、それが吾吾の《存在》に対して豪(えら)い迷惑をかけてゐるって事を《神神》は一貫して知らぬ存ぜぬで済まさうとしてゐるのかね?
――さうねえ。《神神》も己の事で手一杯で、そのとばっちりを此の世の森羅万象は受けている筈だわ。
――例へば?
と甲君が雪に訊くと、
――例へば《神神》が『《吾》とは何ぞや?』といふ自同律にあるとするならば、此の世の森羅万象も《神神》の自同律に芽生える不信の目に無理矢理付き合はされてゐるに違ひないからだわ。
――さて、それ以前に自同律の陥穽に落っこちてゐる《神神》って何なのかね?
と、甲君が丙君に尋ねたのであった。
――此の世さ。
――え? 此の世?
――さう。此の世の森羅万象が自同律の陥穽に落っこちた《神神》の懊悩の正体さ。
――《神神》の懊悩? つまり、《神神》もまたその《存在》において懊悩する《存在》の業から遁れられぬといふ事だね。
――いや。例へば此の宇宙を《神神》の頭蓋内の闇、この「黙狂者」君の言葉を借りると《五蘊場》とすれば、何となく、此の世の森羅万象の意味する処が見当付く筈だがね。
――成程。君もまた、この「黙狂者」の《杳体御仁》に感化されてゐるのは知ってゐるが、ならば、吾等の《存在》とは《神神》の夢、若しくは表象といふ事かね?
――多分な。
――へっ、多分か。所詮、何《もの》も、此の宇宙が出現せずにはをれなかったその因に辿り着けやしない。それが《神神》であってもだ。
――すると、此の宇宙が出現する以前に《神神》すら《存在》してゐなかったとでも言ひたいのかね?
――ああ。唯、《吾》に為らうと欲する《念》が、此の宇宙の出現以前にあったのさ。
――それもこの「黙狂者」の《杳体御仁》の受け売りぢゃないかね?
――さうだが、しかし、私もこの「黙狂者」の《杳体御仁》の考へを認めるしかないと観念したのさ。
――つまり、君の試行錯誤が全て水泡に帰しちまっただけだらう?
――唯、全てを《神神》に帰す事が馬鹿馬鹿しくなったのさ。
――つまり、《神神》に対する猜疑だらう?
――さう。
――しかし、そんな事は既に此の世に《存在》する《もの》はそれが何であらうが、気付いてしまった事実だらう。つまり、簡潔に言へば、その正体は現実と言ふ事さ。
すると、雪が甲君に、
――甲さん、現実が《神》に対する不信を、そして現実がある故に《神神》が己に対しての猜疑を生む動因といふ事ですか?
――さう。全ては現実に収束するのです。
――現実に収束するとは一体何の事を仰ってゐるのてすか、甲さん?
――約めて言へば、元元無限個あった筈の《世界》が、数列などで見たことがあると思ひますが、0→∞で《一》なる《世界》、つまり、現実に収束するのです。否、現実に収束しなければ、此の世は一時たりとも《存在》出来ぬのです。
――さうしたならば、現実には無限個の現実の位相が減衰した末に出現する唯《一》なる《もの》こそ《一》なる《世界》に収束するといふ事ですの?
――ふむ。
すると、
――それはさう考へてもいいでせう。
と猊下たる丙君が言ったのであった。
――さうですね、雪さんの考へ方に一理ありますね。0→∞と《世界》の極限を求めた結果が、此の現実であるといふのは、十分あり得る考へ方です。
と、数学専攻でブレイク好きの乙君が念を押したのであった。
――すると、此の宇宙が出現する以前には無限個の宇宙未然の何か、それを甲さんもこの方も《念》と呼んでゐますが、その《念》といふのは、《吾》に為るべく《念》が《存在》してゐたといふ事かしら、甲さん?
――へっへっへっ、惜しいですね、雪さん。《吾》に為るべく《念》は此の宇宙が出現しても残されたまま、未だに何《もの》によってその正体が解からない《もの》として此の現実に現存してゐる難問なのです。
――すると、《吾》といふ《念》は此の宇宙誕生以前の名残といふ事ですね!
――はい。さうなのです、雪さん!
――それですと、《神》以前に《念》は確かに《存在》してゐたといふ事ですわね。すると、《念》は宇宙誕生の引き金を引いたといふ事でいいのかしら、甲さん?
――《念》は本来、永劫に自同律の陥穽に落っこちたままであったに違ひないのですが、不意にその自同律の陥穽に落っこちた《念》に《吾》が芽生え、そして、《吾》に猜疑が生まれてしまったのです。さうでなければ、此の宇宙が誕生する必然はなかった筈です。しかし、自同律の陥穽に落っこちた《念》は不運にも《吾》とともに∞といふ《もの》を見つけてしまったのです。と、その刹那、此の宇宙はBig bangを起こしちまったと私は考へてゐます。
――その∞が《神》かね?
と、丙君が甲君を眼光鋭くぎろりど睨んで訊いたのであった。
――さあ、それは何とも言ひ難いな。
――でも甲さんのご意見を伺ってゐると、丙さんの仰る通り∞が《神》ぢゃないとをかしいですわ。
と、雪が言ったのであった。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
私は雪たちの会話を聞きながらも相変はらず私の見ず知らずの他人の《霊》の声に為らざる声の呻吟をぢっと聞いてゐる外なかったのであった。吾が虚空を飛翔する其の人は、しかし、その時ににたりと笑ひ、そして、むくりと頭を擡げて、暫く私を凝視してから、
――有難う。
と、その口の動きから読み取れる声に為らざる声で私に語りかけ、また、その黄金色に淡く輝く顔に微笑を浮かべたのであった。
――では、《神》が∞である事に雪さんは我慢出来ますか?
と甲君が雪に訊いたのであった。すると、雪は、
――我慢なんて、私、これまで考へた事もなかったわ。唯、《神》は∞を手懐けてゐる《存在》、いいえ、此の世の森羅万象から超越した何かだとしか考へてゐませんでした。しかし、《神》の問題は、本当の処、《念》とどう関はるのですか、甲さん?
――《念》は∞次元多様体においてのみその姿形が現はれるのです。
――∞次元? この方も先程、∞次元といふ事を持ち出して《個時空》のカルマン渦でしたか、その渦を物理数学で表はすには∞次元の《存在》なくしてはあり得ぬと説いてゐましたが、甲さんの仰る∞次元は、この方の受け売りなのですか?
――いいえ、雪さん。《杳体御仁》の「黙狂者」君は、渦は物理数学的に表記するには∞次元を想定しないと無理だと言ってゐる筈ですが、私が言ふ∞次元は、《念》といふ《もの》を考へる上で∞次元の《存在》を考へるのが最も妥当だとの思ひに至った故の事です。
――すると、《念》もまた渦の一種ですの?
――ふはっはっはっはっ。雪さんはお解りのやうですね。面白い! 私も《念》を渦に結び付けて考へはしましたが、何せ、∞の事ですので有限なる《吾》たる私にはちゃんと合点がゆく概念は、今の処、捻出出来ず仕舞ひです。
――しかし、《念》は此の世に一様に遍在してはゐまい。「黙狂者」の説く通り、《念》もまた渦を巻かなければ、その《存在》は此の四次元多様体たる《世界》に生くる吾等に感知出来る筈はないと思ふがね。
と丙君が荘重に言ったのであった。
――さう。甲君もまた《念》は宿る《もの》と看做してゐるだらう?
と君が言ひ、
――《念》が自同律の陥穽に落っこちてる事自体、既に《念》には濃淡や強弱のある揺らぐ《存在》と看做した方が辻褄が合ふと……。
と文学青年の丁君が言ひ、
――∞は厄介な代物だぜ。
と数学専攻の乙君が言ったのであった。
――すると、君等は私が言ふ《念》といふ《もの》の《存在》には同意してゐるといふ事かな?
と甲君が言ふと、猊下たる丙君が、
――いや、唯、《吾》といふ《存在》に躓いた《もの》は何《もの》と雖も、∞を夢想せずにはをれぬ宿命にあるといふ事だ。
――夢想ねえ? 丙君は、∞が《存在》すると断言できるかい?
――此の世に闇が《存在》する以上、∞は《存在》する。
――しかし、闇は《存在》の例へば「脳」と言ふところで作り上げられた《もの》に過ぎぬのぢゃないかね?
――だから尚更、闇が《存在》する以上、∞は《存在》するのだ。つまり、此の世の森羅万象は闇を表象する事で∞を何とか手に摑む事が出来るかもしれぬ《もの》として渇望せずにはをれぬ事が、即ちそれが∞が《存在》する証左であり、また、∞を渇望しない有限なる《存在》は、多分に皆無に違ひないのだ。
――さうすると、この「黙狂者」君が言ふ《杳体》といふ《もの》の《存在》を、その言ひ振りだと暗示してゐるとしか言へぬぜ、ふっ。
――つまり、闇を呑み込む杳として知れぬ《杳体》か。ふむ。つまり、その鳥羽口に闇が《存在》してゐるといふ事で、また、《杳体》においては∞も、また姿形ある何かへと変化してゐるといふ事だらう?
――いや、「黙狂者」君は、∞の《存在》自体を疑ってゐるのさ。『本当に∞は《存在》してゐるのかね?』とね。
――つまり、∞に代はる《もの》が「黙狂者」の言ふ《杳体》と?
と、丙君は何か頭蓋内を弄るやうに呟いたのであった。すると、甲君が、
――だが、この「黙狂者」君にも未だ《杳体》が何なのかさっぱり解からぬのだが、しかし、俺は、それでもこの「黙狂者」君の《杳体》は支持するぜ。
――それは何故に?
と、君が甲君に尋ねると、文学青年の丁君が、
――所詮、《杳体》も∞に匹敵する事はない!
と、珍しく語気を強めて言ったのであった。
――ふっふっ。「現存在」は、しかし、∞を濫用し過ぎる事を、さて、自覚してゐるのだらうか?
と数学専攻の乙君が言ふと、君が、
――闇を安易に∞と結び付ける思考法がそもそも間違ひの原因なのさ。
と言ったのであった。
――さう。
と甲君は言ひ、
――さう、××君の言ふ通り、此の世の森羅万象は闇に出合ふと直ぐに∞と結び付けたがるが、この「黙狂者」君はそれに疑義を唱へてゐるのだ! すると、丙君、有限なる《存在》が∞を夢想せずにはをれぬ宿命といふ言葉は、《存在》は闇を前にすると思考停止状態に陥り、唯、呆然としてゐるに過ぎぬといってゐる事に外ならないぜ。
と甲君が言ふと丙君は更に眼光鋭く甲君を睨み、
――だから、《存在》にとっては∞は便利この上ない玩具なのさ。
――つまり、それは、《存在》にとって使ひ勝手がいい《インチキ》な《もの》と言ってゐるのと同じ事だぜ。
――ふっふっ。《インチキ》で構はぬではないか。それで《存在》が安寧ならば。
――∞を前に、さて、有限なる《存在》は安寧かね? 寧ろ、疑心暗鬼で不安一杯の筈だぜ、丙君!
――だから∞といふ《インチキ》に《存在》は飛び付かずにはをれぬのさ。有限なる《存在》に対して∞を前に、直截的に対峙させるには余りにも残酷過ぎるのは火を見るより明らかだらう。
――残酷ねえ~、ふむ。
――はっきり言ふが、∞が《インチキ》だからこそ、有限なる《存在》は安寧を得るのさ。仮に∞が未知なる《もの》ならば、それは《存在》をのっぴきならぬ処へと追ひ詰め、挙句の果てには、縊死させるのが落ちさ。
――それさ。この《杳体御仁》の「黙狂者」君が今ゐる処は。《杳体》といふ∞すらをも呑み込んだ何とも得体の知れぬ、しかしも巨大なる何かに直に対峙してしまったのだ、この《杳体御仁》の「黙狂者」君は。そして、その結果、発話能力を失ってしまった。つまり、この「黙狂者」君はのっぴきならぬ死臭漂ふ此岸と彼岸の間で、その恐怖のために言葉を発する行為を喪失してしまったのだ!
――それは君の思ひ込みでしかないのぢゃないかね、甲君よ。この「黙狂者」は、多分、魂を恰も天国と地獄に裂かれたかの如く、《吾》が此岸と彼岸へと真っ二つに引き裂かれた煩悶で言葉を発話する術を失ってしまったのさ。
――では、この方が今ゐる処は中有の如き処なのでせうか?
と、雪が丙君に訊いたのであった。
――ふむ。中有ですか。さて、この「黙狂者」は、《死》を擬態出来てゐるのかどうかで、この「黙狂者」が虚空にゐるのか中有にゐるのかが決まる筈です。私はこの「黙狂者」は既に《死》へとその歩を進めてしまった、つまり、中有に踏み迷ってゐると考へてゐますがね。
――それでは、何故にその事をこの方に問はないのですか?
と、雪が言ふと、甲君が、
――それはこの「黙狂者」君には無理難題ですよ、雪さん。この《杳体御仁》たる「黙狂者」君が、今、己がゐる処が解かれば、「黙狂者」君は黙狂になど為らずに今でも流暢に朗朗と彼独自の存在論を話してゐる筈ですが、如何せん、「黙狂者」君には今、己が何処にゐるのかさっぱり解からず、その《吾》の未知なるが故に《杳体》といふ考へを導き出さざるを得なかったのですから。
――つまり、この方が言ふ《杳体》は苦し紛れに思はず口走ってしまった妄言でしかないといふ事ですか?
――いえいえ、雪さん、そんな事はありません。唯、これまで全宇宙史を通して《存在》を語り果せた《もの》は《存在》しない筈で、それは《神》にも当て嵌まり、《神》が《存在》を熟知してゐるならば、諸行無常な世などあり得る筈もなく、つまり、それは如何なる思念でも《存在》を捉へられず仕舞ひなのが、この「黙狂者」君にはそれが我慢がならないのです。つまり、それは《存在》の堕落でしかないのです、この「黙狂者」君にとっては。例へば物質の根源を探ってゐた時に、どうしても《存在》が知られてゐた物質だけでは論理的に説明出来ない現象を、湯川秀樹がπ中間子といふ新しい素粒子を導入する事で論理的に説明出来たやうに、この「黙狂者」君は、今の処、何《もの》も《存在》を摑まへられず仕舞ひなのは、《存在》には決定的な欠落があって、それがこの「黙狂者」君には新たな《杳体》を導出する事で、《存在》が浮き彫りになると考へた事が全ての発端の筈です。
――つまり、この方が言ふ《杳体》とは版画で譬へるならば、版木に対する墨といふ事でせうか?
――ふはっ。雪さんは譬へが上手ですね。さうです。この「黙狂者」君の《杳体》は、《存在》といふ版木に対する墨のやうな《もの》なのです。つまり、版木に彫られた《存在》の姿形に即応して、版木に塗られた墨は半紙にその彫られた《もの》を写し出すのです。それが《杳体》です。
――さうしますと、《杳体》とは、変幻自在な何かといふ事でせうか?
――はい。さうです、雪さん。
――では、《杳体》もまた、巨大な加速器で光速近くまで加速させられた素粒子を衝突させることで莫大なEnergy(エナジー)を生み出し、嘗ての宇宙誕生時の状態を近しく再現し、その宇宙誕生時には確かに《存在》してゐた素粒子が《存在》した痕跡を光速近くに加速した素粒子同士の衝突で見つける事で探すのと同じやうに、《杳体》にとっては、素粒子の如く光速近くまで加速させる加速器に当たる《もの》とは何なのかい、甲君?
と丙君が言ったのであった。
――それが解かれば「黙狂者」君が黙狂になる事なぞなかった筈だぜ。
――それでは、皆さんは、この方が唱へる《杳体》といふ《もの》の《存在》を信じてゐるのですか?
と雪が皆に問ふと、誰もが頷き、そして丙君が荘重に話したのであった。
――これまでの哲学、科学、宗教、その他諸諸の智を総動員しても《存在》の本質は未だ何《もの》も解からず仕舞ひです。ならば、これまでの智には《存在》を語るには何か重大な欠落があると考へるのは至極当然な事です。吾吾はその端緒にヰリアム・ブレイクの幻視があるのではないかと考へてゐるのです。
――やはり、さうなのですね。私は何故に皆さんがヰリアム・ブレイクをこのご時世に読み合ってゐるのか漸く合点がゆきましたわ。確かにブレイクは、ブレイク独自の宇宙を創造してゐますから。
と雪が言ふと、
――さうなのです。ブレイクを読む事で何かこれまで伏せられてゐた《もの》が不意に姿を現はし、吾等を煙に巻いて呉れればしめた《もの》なのです。
と、甲君がさも楽しさうに言ったのであった。
――それでは、私の事などに感(かま)けてゐないでブレイクを読みませんか?
と雪が言ふと、猊下たる丙君が、
――いやいや、今日位は、先づ、雪さんとかうして語り合ふことでいいのです。ブレイクを読むのは次の機会でも出来ますから。
――しかし、あなた方はブレイクを読む事でこの方が言ふ《杳体》の何かを摑まへたいのぢゃありませんの?
――かうして話してゐる事が、即ち、ブレイクを読む事の役に立つのです。ブレイクの幻視が何かの暗示になること間違ひなしなのです。つまり、雪さんとかうして話してゐる事が皆楽しいのです。
――さうですか、丙さん。しかし、私はこの方が言ふ《杳体》といふ考へを先程知ったばかりで、《杳体》については未だ解かりませんわ。
と雪が言ふと、丙君が、
――それは当然です。雪さんはこの「黙狂者」に一目惚れしたとはいへ、今日初めてこの「黙狂者」に対面したのですから。そして、雪さんは、この「黙狂者」の事が少しでも知りたくて、私達の処へとやって来たのでせう?
と、丙君は微笑みながら言ったのであった。すると雪が、
――はい。その通りですわ。では、《杳体》についてもう少しお話して下さいませんか?
――私見ですが、有限から無限へ至るその飛躍を媒介する《もの》が《杳体》です。
――おい、丙君、それは君の考へであって、この《杳体御仁》の「黙狂者」君が言ふ《杳体》とは似ても似つかぬ《もの》だぜ。
と甲君が言ふと、丙君が、
――本当にさうかね?
――私は丙君とは少し違った考へ方をしているがね。
と、君が言ったのであった。
――うぅぅぅぅあぁぁぁぁああああ~~。
…………
…………
ねえ、君。雪が初めて私達のサロンみたいな集ひにのこのことやって来たその日は、皆、実に楽しさうで、誰もが雪に魅せられてゐたね。そして、話も弾んだね。正直に言ふが私はあの時も《死》を目前に控へた今も《杳体》が何なのか解からず仕舞ひだ。しかし、《死》が目前に迫った今、《杳体》とは、《吾》なのかもしれぬと思ってみたりして独りほくそ笑んでゐる。をかしいだらう。しかし、あれ程、私を悩ませ、その結果として《死》を私に引き寄せた《杳体》なる《もの》は、所詮、《吾》を超越する事は不可能な代物に違ひないと今更ながらに自省する事で、私は心安らかになるのさ。そして、私は一つの結論として《杳体》とは、もう直ぐに《死》ななきゃならない私にとって、この《吾》といふ観念を抱へながら彼の世へと跳躍するその跳躍板こそが《杳体》の正体なのかもしれぬと思ってゐるがね。
…………
…………
――といふと?
と丙君は君に訊ねたので、君は、
――この「黙狂者」の彼が思ひ描いてゐる《杳体》は、多分、此の宇宙に匹敵する壮大なる何かだとは思ふがね。つまり、私にはやはり、《杳体》は∞と強く結び付いた何かだと思へて仕方がないのさ。
と君が言ふと、雪が、
――この方の《杳体》をブレイク風に言ふと《死》すべき運命から免れた《不死》なる《存在》といふ観念は、《杳体》に含まれますか、××さん?
――それは当然さうだらうと思ひます。《杳体》は《不死》なる何かに違ひありません。
と君が言ふと甲君が、
――《不死》は《不死》と雖も、その《不死》の《杳体》は、シーシュポスの如く、何時果てるとも知れぬ労苦を未来永劫続ける《もの》と思はないかい、××君?
――多分、甲君が言ふ通り、《杳体》は未来永劫、終はる事のない労役に従事してゐるには違ひないとは私も思ふがね。
――へっ、それぢゃ、未だブレイクの方が進んでゐるだらう、××君!
と甲君が言ったのであった。すると、雪が、
――それでは甲さんは、《杳体》をどのやうな《もの》と直感的にでもいいですが、《杳体》として把握してゐるのですか?
――さうですねえ。例へば此の世に《存在》しない《もの》と言へば解かりますか?
――あら、此の世に《存在》しない《もの》ですか。恐れ入ります。それでは、つまり、甲さんにとって《杳体》とは此の世には《存在》しない《もの》全ての何かなのですね?
――さうです。《杳体》は此の世に《存在》しない《もの》でなけりゃなりません。さうでないと何《もの》も此の世の《存在》に我慢がならないからです。
――すると、甲さんは、《杳体》を、此の世に《存在》する事を余儀なくされた森羅万象の慰み《もの》としての夢、若しくは仮象のやうな《もの》とお考へですの?
――いえ、それでは雪さんは、ゴッホの「星月夜」を見て、あの絵が《現実》に《存在》する《世界》とお思ひですか?
――あら、偶然ね。先程私はこの方と画集専門の古本屋さんでゴッホの「星月夜」を見てきたばかりですわ。この方はゴッホの「星月夜」に《神》がゐるかとお尋ねしましたがね。
――さうですか。《杳体御仁》の「黙狂者」君とねえ。ふむ。それで雪さんは何と。
――私は《神》はゐると答へたと思ひますが。
――さうですか。では私の質問にもお答へください。雪さんは、ゴッホの「星月夜」は此の世の《もの》とお思ひに為りますか?
――私の私見ですが、《世界》をゴッホの「星月夜」のやうにしか見られない《存在》は必ず此の世に《存在》する筈だと思ひますわ、甲さん!
――ならば、私にすれば、その《存在》が《杳体》です。つまり、《存在》の夢、若しくは仮象の《世界》が《現実》だといふ《存在》が、仮に此の世に《存在》するならば、私にとってはその様な《存在》こそが《杳体》なのです。
――それでは、先程言ったことと矛盾してゐますわ、甲さん。あなたは先程《杳体》は此の世に《存在》しない《もの》と断言なさった筈です。
――夢や、仮象は、さて、此の世に《存在》すると言ひ切れますか、雪さん?
――それでは、甲さん、ル・ドンの絵が《現実》ならばその《現実》に《存在》する《もの》が《杳体》と仰るのですね?
――はい。しかし、これは未だに誰の賛同も得てゐませんがね、なあ、丙君!
と甲君が自嘲気味にさう言ふと、丙君が、
――また、心にもないことを言って、雪さんを煙に巻きたいのか。雪さん、甲君がゴッホついて話したことは話半分に受け取ってください。この甲といふ人間は、優しすぎる故に心にもないことを平気で言ひますから、なあ、甲君。そして、甲君の悪癖で、甲君は嘘っ八を言って相手が困惑する顔貌を見るのが堪らなく好きだといふのが、甲君の趣味みたいな《もの》なのです。
――さうですか。しかし、甲さんのお話はとても解かり易かったのですが。
――それぢゃ、丙君は《杳体》を何と目星を付けてゐるんだい?
と甲君がにやにやと笑ひながら丙君に言ったのであった。
――ふむ。私が思ふに、巨大な巨大な巨大な雲丹(うに)状の闇の如き《もの》と想像してゐますがね。
と丙君が言ふと、雪が、
――巨大な巨大な巨大な闇の雲丹? さう考へる根拠は何でせう?
――ふっふっふっ。それが全くないのです。
と丙君が鋭き眼光を少し綻ばして微笑んだのであった。
――つまり、丙君は、未だ《杳体》に関しての考へは以前から全く深化せずに、《杳体》は朧に巨大な巨大な巨大な雲丹状の闇に直結する頭蓋内の闇といふ《五蘊場》に生滅する仮象、否、表象との関係から導かれる《もの》と考へてゐるといふ事だね。
と文学青年の丁君が、またしても、はっきりと言ったのであった。
――さうさ。しかし、実際に「黙狂者」を前にすると、その「黙狂者」が言ふ《杳体》は必ず《存在》する筈だと看做したいのが本心だ。
――つまり、《杳体》は丙君にとって、或る意味希望の星の如き《もの》なのかい?
と数学専攻でブレイク好きの乙君が丙君に言ったのであった。
――否、ブレイクの幻視が、私にとっての《杳体》の糸口で、万人には全く見えない《もの》が、ブレイクには見えてしまふその《存在》の哀しさこそ《杳体》を《杳体》足らしめ、また、それ故に《杳体》は此の世で報はれるべき《もの》でなければならないとは思ってゐるがね。
――別に報はれなくとも構はぬのぢゃないかね?
と丁君が言ふと、丙君は、
――それは丁君の言ふ通りなのだが、私は、《杳体》なる《もの》は《存在》の全てを包摂する、つまり、如何なる《もの》も見捨てない神仏をも楽楽と凌駕する《もの》であってほしいと思っているだが……。
と丙君が言葉に澱むと、甲君が、
――それぢゃ、此の宇宙が《存在》すれば全て丙君の言ふ《杳体》は不必要な《もの》でしかないぜ。何故って、丙君が言ふ《杳体》とは徹頭徹尾此の世の事であって、別に《存在》を語るのに《杳体》を要請する必然性が全くないだらう、丙君?
――ならば甲君よ、《吾》とは何なのかね? この己の《存在》に決して我慢がならぬ此の《吾》といふ《存在》は、此の世の摂理のみに従ってゐると言ひ切れるかね?
――でも、《吾》でさへ、己の《存在》は否定出来やしないだらう?
――だから尚更、《吾》といふ《存在》に我慢がならぬ《吾》が《存在》してしまふ此の不合理をも呑み込む《杳体》の《存在》は、神仏と同様に此の世の《存在》にとっては必要不可欠なのさ。
――あら、丙さん、あなたの仰る事に従へば、丁さんや甲さんの言ふ通り、《杳体》を要請する必然性は全くありませんわ。
と雪が言ったのであった。
――つまり、皆は、《吾》といふ《存在》には、此の世の摂理として《吾》に我慢がならぬ事を「先験的」な摂理として賦与されてゐると看做してゐるといふのですか?
と丙君が言ふと、雪が、
――《吾》とは所詮、そんな《もの》でしかありませんわ。
と語気を強めて言ったのであった。
――それでは、《吾》といふ《もの》に礼を欠いた解釈ではありませんか、雪さん?
――それで別に構はぬないのぢゃありませんの? 《吾》とは《吾》に対して徹底的に不作法な《存在》であって、《吾》に従順な《吾》は、全宇宙史を通して、一度も《存在》した事があるとでもお思ひですの、丙さん?
――それでは《吾》は暴走するだけですよ、雪さん。
――と言ひますと?
――つまり、《一》=《一》の自同律が成立するには、此の世の《もの》ならぬ《もの》の《存在》が暗示されてゐて、その此の世ならぬ《もの》が《存在》する事を暗黙裡に誰もがひた隠しにひた隠して《一》=《一》の自同律が論理的に成立するが如く看做さない事には、何《もの》の《存在》も語れぬのっぴきならぬ事態に遭遇しちまったのが現代なのです。
――しかし、この方は、発話する能力を喪失したこの方は、既に《吾》の暴走が起こってゐるのぢゃありませんの?
――いや、雪さん、この「黙狂者」は、発話しない事で何とか《吾》が暴走する事を抑制してゐるのです。
と君が言ふと、
――と言ひますと?
――つまり、××さん、この丙さんが言ふ通り、《吾》が《吾》である事に我慢がならず、それを「先験的」な《もの》と看做して、《吾》が為すがままにしておくと、必ず《吾》は《吾》に対して牙を剥き、そして、《吾》を食ひ殺さうとするのが此の世の摂理といふ事ですの?
――さうでなければ、雪さんは、この如何とも度し難い《吾》は如何様に扱ってゐるのですか?
と君が言ふと、雪は何食はぬ顔をして、
――《吾》の抹殺です。
と答へたのであった。
――へっ、雪さん、あなたもまぎれもなく此の《杳体御仁》の「黙狂者」君と同じ類の「現存在」で、それとはまったく自覚してゐなくとも、雪さん、あなたも既に《吾》に反旗を翻してゐるのでね? つまり、雪さんも、それとは知らずに《杳体》の探索に歩を一歩進めてしまったのですね。さうですか、へっ。
――と言ひますと?
――つまり、雪さんもまた、此の《吾》の撲滅でしか最早、《吾》が此の世で生き延びてゆく方法がないと、それとは自覚してゐなくとも、此の「黙狂者」君と同様に《吾》の撲滅をおっ始めてしまったのです。
と甲君が、何やら含み笑ひをしながら言ったのであった。
すると雪は煙草を一本口に銜へて煙草に火を点けると、
――ふ~う。
と深く一息深呼吸をしたのであった。そして、
――甲さん、《吾》が《吾》の抹殺を企てるのは自然の摂理とは思ひませんか?
と雪が言ふと、甲君が、
――此処でゴッホを持ち出すまでもなく、《吾》の撲滅をせずにはをれぬ不合理は、《存在》が此の世に誕生した刹那に既に始まってゐたのです。
――それは、つまり、《存在》の淵源は《非在》であるといふ事ですの?
――さうです。《存在》する《もの》は初めは《存在》してゐなかった《もの》ばかりです。つまり、《存在》する《もの》は堕天使が天使の頃を渇仰せずにはをれぬ故に悪行を為さざるを得ぬのですが、しかし、それは、ゲーテの『ファウスト』のメフィストフェレスの言、つまり、『常に悪を欲して、常に善を為すあの力の、一部です』に収斂するやうに、《存在》は常に《非在》を欲して、常に《存在》を打ちのめす外ない此の《吾》の《存在》の有様こそ、《存在》への渇望に違ひないのです。
――つまり、甲さんは、《存在》する事自体が既に不合理といふ事なのですね?
――はい。《存在》はどうあっても不合理でしかありません。
――では、《存在》が《吾》の撲滅を渇望せざるを得ぬのは、「先験的」に《存在》に賦与された《もの》といふ事ですの?
――はい。《存在》する《もの》は「先験的」には《未出現》が最も安寧な状態なのです。
――では、何故に《存在》が《未出現》のままぢっとしてゐられなかったのですか?
――《未出現》は永劫の時間の中で、或る時、不意に《未出現》なる《吾》を発見してしまった。それが《未出現》の運の尽きです。
――つまり、《未出現》に《吾》を見出してしまった《未出現》は、一時も《未出現》である事に堪へられず、《吾》といふ《存在》を《出現》させてしまったと?
――はい。
――甲よ。すると、《存在》は《未出現》へと常に憧れてゐるといふ事かね?
と、丙君が容喙したのであった。
――へっ、丙君こそ如何とも度し難い《吾》を何と規定してゐるのかね?
――ゲーテの言ひ振りを真似ると『常に《吾》を欲して、常に《吾》を殺すところの、一部です』となるかな?
――それは先に私が言ってゐるがね、丙君?
――いや、甲が言ったのは《存在》についてであって、其処に《吾》は未だ《未出現》だった筈だが。
と再び眼光鋭く猊下たる丙君が甲君に訊いたのであった。
――へっ、丙君はもう忘れちまったやうだね。私は、先に《吾》といふ《念》は、何に対しても先んじて《存在》すると言明してゐる筈だが、ふむ、しかし、へっ、吾ながら自分の言ってゐる事が矛盾してゐるかな。一方では何にも先んじて《吾》といふ《念》が《存在》すると言ひながら、一方では《未出現》が不意に《未出現》に《吾》を見出したといふのは、吾ながら矛盾してゐるかもしれぬ。へっ、しかし、かう考へれば全く矛盾してゐないに違ひない。つまり、《吾》といふ《念》は《未出現》が《非在》のままの時も、《未出現》の《もの》はそれとは気付かずに確かに《吾》は《存在》してゐたと。
――甲さん、それは《吾》といふ《念》は、《吾》といふ《念》が《存在》してゐる事を何《もの》かに気付いて欲しかったといふ事ですの?
――はい。しかし、《吾》は未来永劫見出されるべきではなかったのですがね。
――しかし、《吾》は見出されてしまひました、甲さん。これは一体何の暗示なのですか?
――つまり、《杳体》です。
――甲よ、《杳体》とは物理学でいふ暗黒物質ではないのかね?
――暗黒物質は《杳体》の一部でしかないぜ。
――それは何を以てしてさう言ひ切れるのかね、甲よ?
――暗黒物質もまた《存在》してゐるからさ。
――ふむ。甲よ、もしかするとお前の言ふ、否、この「黙狂者」が言ふ《杳体》は、此の宇宙の容れ《もの》の事ぢゃないのかね?
――それも《杳体》の一部に過ぎぬ。
――すると、《杳体》は仮象のまさにその先に仮象される此の世の姿といふ事かね?
――丙さん、仮象のまたその先の仮象とは一体何の事ですの?
と雪が丙君に訊くと、丙君は、
――つまり、此の世の森羅万象がこれまでに何《もの》も考へすら及ばなかった或る種の世界観の事です。
――丙君、そんな説明ぢゃ、雪さんには何の事か解からないぜ。
――いいえ、甲さん、丙さんの説明で朧に《杳体》の何たるかは薄らと浮き彫りになりました。
――すると、雪さんは《杳体》を何と解釈したのですか?
――彼の世を包摂した《未出現》のまま此の世には決してその姿を現はさない或る《世界》の事ではないでせうか?
――彼の世もまた此の世の森羅万象から一歩も踏み出せないとすると、《杳体》はどうなりますか、雪さん?
と甲君が雪に訊くと、雪は、
――それならば《杳体》は彼の世といふ《もの》にその《存在》の尻尾を出している筈ですわ。
――つまり、雪さんにとって《死》が《杳体》の入り口だとの理解ですか?
――はい、甲さん!
――雪さん、それぢゃ、《杳体》を矮小化してしまってゐます。
――あら、どうして?
――何故って、《死》が《杳体》の入り口ならば、此の《世界》には此の世と彼の世があれば十分で、「現存在」はその摂理に従順に従へばいいだけですが、しかし、「現存在」はどうあっても此の《吾》といふ《存在》に我慢がならないと来ている。つまり、《杳体》の入り口は、此の《吾》なのです。
――《吾》ですって!
――はい。《吾》が《杳体》の入り口であり、そして、出口でもあるのです。
――甲よ、それは僭越といふ《もの》だぜ。
と丙君が言ふと、
――しかし、甲君の説は一理あるぜ。
と文学青年の丁君がぼそりと呟いたのであった。
――乙さんは、数学専攻なので、お訊きしますが、乙さんは《杳体》を数学的見地からどの様に位置付けていますの?
と雪が乙君に訊いたのであった。すると、乙君が、
――虚数iの零乗、若しくは零の零乗なのではないかと私は疑ってゐます。
――虚数iの零乗、そして、零の零乗は《一》ではないのですか?
――その通りなのですが、その《一》こそ《杳体》の尻尾ではないのかと考へてゐます。また、虚数iのi乗は実数である事もまた、《杳体》のその尻尾だと思ひます。
――つまり、虚体が虚体を仮象すればそれは実体といふ事ですの?
――さうですねえ。虚体が虚体を仮象するですか、ふむ。丙君はとう思ふ?
――解からぬといふのが本当の処だが、虚体が虚体を仮象するとは言ひ得て妙な面白い考へ方ですね。雪さんは、埴谷雄高の『死霊(しれい)』は読まれてゐるのですね?
――はい。『死霊』を初め、様様な作品を読んでは思索に耽っています。ヰリアム・ブレイクに出合ったのは埴谷雄高からです。
――さうですか。すると、雪さんは虚体が虚体を仮象すれば必ず実体が現はれ、それが《杳体》の尻尾に違ひないと目星を付けたのですね?
――はい。その入り口にヰリアム・ブレイクの幻視があると思ふのです。
――私は未だヰリアム・ブレイクを全て読んだ訳ではないので断言は出来ませんが、成程、ブレイクの預言書など、此の世の森羅万象の摂理をぶち抜けた何か切迫した感じはありますね。しかし、それは《杳体》を暗示してゐるに過ぎません。虚体が虚体を仮象するといふ事は、はっきり言へば《インチキ》でしかありませんが、「現存在」にとってその《インチキ》なくしては一時も生きてられはしないのです。
――それは何故ですの、丙さん?
――例えば、現在ある全学問体系が全て《インチキ》だと考へた事はありませんか?
――何を仰るのでか、丙さん! 全学問が《インチキ》ですって!
――はい。ヰリアム・ブレイクが不死なる《もの》の宿命を語るやうに、現在ある全学問を以てしても不死なる《もの》の出現は不可能で、いや、癌細胞がありますね。まあ、それはそれとして、つまり、「現存在」に対して《不死》なる《もの》は全くの無力だと言ってゐるに過ぎません。つまり、「現存在」の知は全て《生》に帰すのみで、《死》へ帰す《もの》は学問から外れてゐます。
――そんな事ありませんわ、丙さん! 《死》に関する学問は数多あるぢゃありませんか?
――しかし、それらは、《生》から《死》へ至るその過程に関する《もの》でしかありません。《死》の後の学問体系は学問に非ず、Occultになってゐます。
――それは健全な事ではありませんの?
――いえ、それは《死》への冒瀆でしかありません。
と丙君が言ふと、甲君が、
――そんな事ないぜ、丙君。《生》にとって《死》は何時の時代でも摩訶不思議な《もの》でしかない。だから、つまり、《死》が摩訶不思議故に宗教が出現したのではないかね?
――つまり、甲よ。此の世に神学や宗教学や民俗学があると言ひたいのか? しかし、それらは、全くの処、《生》の学問でしかないぜ。
――さうしますと、甲さんも丙さんも「《死》学」なる学問がなければ、《存在》は、いいえ、《杳体》は捉へられないといふ事ですわね、うふ。
と雪が言ふと、猊下たる丙君が、
――医学や生物学の外に、《死》を科学的に扱ふまさに雪さんが仰った「《死》学」がなければ、学問は、詰まる所、《生》にとってのみの未成熟なままの学問体系でしかない――ふむ。甲よ、お前はどう思ふ?
――さてね。しかし、死に様に《生》と《死》の全てが現はれているかもしれぬぜ。
――あら、甲さん、また私を煙に巻かうとしてゐるのですか?
――いえいえ、滅相もない。唯、「《死》学」とは面白いと思っただけです。一つ雪さんにお伺ひしますが、《死者》は死後もずっと《存在》すると、つまり、霊魂は《存在》するとお考へですか?
――はい。私はさう思ってゐます。
――それはまたどうしてですか?
――反対にお伺ひしますが、甲さんはどう思っていらっしゃるのですの?
――へっ、私は、《死者》が、霊魂が《存在》してもしなくても、どっらでもいいのです。
――それでは、《杳体》なんぞ見出せる筈がありませんわよ。
――さうでせうか? 所詮、《生者》にとって《死》は摩訶不思議な事象でしかなく、《死》に関しては世界各地に神話として物語化され残ってゐますが、私にとって《死》はそれで十分なのです。
――つまり、《死》は、土台、科学的に扱ふ事は不可能といふ事ですの?
――いえ、《杳体》が仮に補足出来れば、《死》もまたたちどころに明瞭になる筈ですから。
――つまり、《生》を更に突き詰めて行けば、科学的、医学的、生物学的、神学的、宗教学的、民俗学的などなどにおいて、《死》もまたくっきりとその相貌が浮き彫りにされる筈といふ事ですの?
――はい。さうぢゃなきゃ、誰も学問なんぞに現を抜かしませんよ、ふっふっ。
――つまり、甲さんは《生》を突き詰めれば、其処には必ず《死》が現はれるとお考へですの?
――はい、私は、《生》とは此の世の森羅万象においては一つの奇蹟と看做してゐるのです。《生》はそれが何であれ、《死》と紙一重にありながら《死》を超越して《存在》してゐる事を断じて知ってしまはなければなりません。それは「現存在」ばかりでなくこの世界に満ち溢れる多様性に満ちた生物全てに対しての事です。でなければ、如何なる生き物の産まれたての赤子があれ程に愛くるしい筈はないのです。
――さうねえ、甲さん。赤ちゃんの可愛らしさと言ったならばそれはそれは筆舌尽くし難い《もの》ですわね。
――しかし、赤子が、例へば「現存在」たる人間の赤子は虐待されて殺される場合が少なくなく、へっ、もっと言へば、赤子に対する虐待は日常の一風景に過ぎず、つまり、赤子を可愛らしいと看做せるのは大概が第三者の見方であって、育児に当たってゐる当事者にとっては、赤子の愛くるしさは一時の安らぎを与へるかもしれませんが、その生態は母子共に死闘です。また、赤子は、病魔に襲はれる事もしばしばです。それでも生き永らへて成人となり、その《生》を全うする《存在》は、それだけで奇蹟としか言へません。
――うふっ、甲さんてロマンティストなのね。
――甲は優しすぎるのです。
と丙君が雪に微笑みながら言ったのであった。そして、甲君は更に続けて、
――この《生》といふ《もの》が《死》と紙一重でしかない事のその理由は何だと思ひますか、雪さん?
――さうねえ……、《生》が《生》である事のその壮大な世界観を、《死》をも包含する形で生み出す為ですかねえ、うふっ。
――《生》の世界観、つまり、それは世界認識の事ですね?
――はい、さうです。
――ならば、何故に《生》は世界認識を強ひられるのですか?
――あら、甲さん! 《生》は己が生きてゐる世界を知らずば、一時も《生》は存続出来ませんわ。いえ、違ふわねえ。《自然》が何であるのかを知らずとも《自然》は《生》の揺り籠ですわねえ。でも、《生》は《生》として此の世界に存続するには多少に拘はらず《生》の作法が厳然と《存在》しますわ。そして、それは《生》が此の世にどれだけ巧く適応するかといふ生存の戦略として世界認識は必須ですわ。
――それでは例へばキルケゴールが謂ふ「単独者」それぞれの世界観は全「単独者」で共有出来る《もの》とお考へですか?
――「単独者」が皆等しく学問を学んでゐれば、世界認識の礎の処では共通してゐるのではないですか、甲さん?
――その学問が、それでは全て《インチキ》だとすると?
――甲さんはどうしても学問を《インチキ》にしたいのですね?
――ええ、私に言はせれば《生》は此の世に《存在》する限り、《生》と《死》すら包含する巨大な巨大な巨大な世界観といふ大《インチキ》を育むその母胎として《生》は《存在》してゐると考へてゐます。
――つまり、それは《生》といふ《もの》が絶えず出合ふ現実は邯鄲の夢でしかないといふ事ですの?
――はい。現実といふ《もの》が邯鄲の夢であってもびくともしない世界認識を《生》たる《もの》が生み出せるか出せないかの瀬戸際に絶えず追ひ詰められてゐるのが、《生》たる《もの》の本質なのです。
――本質ですか。さうしますと、甲さんによれば、現在の生物多様性は、それだけで多様な世界認識の仕方が《存在》し、また、「単独者」の数だけ、否、既に死んだ《もの》も含めて、それぞれに独自の世界認識の仕方があり、そして、その個性あふれる世界観を矯正し統合した《もの》が学問といふ《インチキ》な《もの》であって、しかし、その学問は何時の時代もその正否が書き換へられてゆく、うふっ、甲さん流に言ひますと、大《インチキ》にしかならないといふ事ですの?
――はい。雪さんは聡明な方ですね。私に言はせると《生》は絶えず学問体系を書き換へるべく、此の世に《生》を享けたに違ひないのです。それ故に、「単独者」、若しくは「現存在」、若しくは全生物は、それぞれ学問から外れた個体独自の原初的な世界観を何としても生み出さずば、《死》に呑み込まれる運命なのです。
――甲さん、原初的なる世界観が、この方が言ふ《杳体》といふ事ですの?
――いえ、原初的な世界観は、唯、《杳体》の《存在》を暗示するのみです。つまり、現在、此の世に《存在》する森羅万象は己がどうあっても世界に《存在》してしまふ事で世界認識せずにはをれずに必ず抱かざるを得ぬ世界観とは、《吾》を「超越」する《杳体》を朧に暗示する《もの》であり、それはBig bangの時の未だCP対称性の破れ以前の、物質と反物質が共存する、否、それでは誤解を与へますね、つまり、Big bangが起きる以前の《存在》が《杳体》の尻尾なのです。
――甲君、それは全く矛盾してゐるぜ。Big bang以前の《存在》って、一体何なのさ? それは《存在》の範疇には入らない、《存在》以前の、つまり、何《もの》も未だ《存在》しないといふ事に過ぎず、其処に、つまり、Big bang以前の世を持ち出す事は、《存在》の全否定でしかないぢゃないかね?
と君が言ふと、甲君が、
――だから、《杳体》なのさ。此の世の全《存在》の全否定にこそ、《杳体》へ通じる糸口があるんぢゃないかな。
すると雪が、
――では、甲さん、甲さんはBig bang以前に此の世ならぬ別の世界は《存在》してゐたとお考へですの?
――はい。此の世が《存在》してゐるのであれば、此の世が《存在》する以前の、つまり、Big bang以前に此の世ならぬ別の世が《存在》する事に何の矛盾もありません。正直に言へば私にすればそんな事はどうでも構はないのです。唯、Big bang以前の、此の世とは全く異なる世界が《存在》してゐたとすれば、その別世界に《存在》しちまった《もの》が、己の《存在》に関して自問自答を繰り返せば、それは、現在《存在》する森羅万象とは全く違った思惟形式で《存在》が問はれる事になり、私は、その思惟形式によって自問自答された《存在》といふ《もの》の思惟にのみに関心があり、其処に多分、《杳体》の尻尾があるに違ひないのです。つまり、如何なる世界でも《存在》しちまった《もの》は、その《存在》について自問自答を始め出さずにはをれず、そして、その思索は必ず《杳体》の《存在》を暗示する《もの》でなければ、その思惟は誤謬でしかないのです。
――甲よ。すると、この「黙狂者」が言ふ《杳体》はお前の考へに照らせば、《存在》に関する思索が必ず到達するに違ひない着地点こそがその《杳体》といふ事かね?
と、猊下たる丙君が微笑みながらも鋭き眼光で甲君を凝視しながら、訊いたのであった。すると、雪が、
――丙さん、丙さんは《杳体》をどう思ってゐるのですの?
――さうですねえ……、まあ、面白い思惟の形式には違ひないのですが、《杳体》は森羅万象の自同律の不快を全て呑み込むといふ事で、私には余りにも曖昧な《もの》なのです。《存在》は、己が何《もの》かを認識する以前に既に《存在》してしまってゐるのです。その事実は動かしやうがありません。思惟が生まれる前に、既に《存在》は《存在》してゐるのです。その現実に互角に亙り合へる、換言すれば、此の現実に直に対峙出来ない《存在》に関する思惟は、私には舌足らずで未完の思惟でしかありません。その筆頭が《杳体》なのです。
――それでは、虚体が虚体を仮象する事に、丙さんは何の魅力も見出せないといふ事ですわね?
――いや、雪さん、私は、現実といふ《もの》の在り方に対抗出来る《存在》の形式に虚体は否定しませんし、むしろ、積極的に虚体を認めます。そして、虚体には無視し難い魅力があります。然しながら《杳体》と言へばその虚体すらをも呑み込むといふ、言ふなれば曖昧模糊とした《もの》、そして、曖昧模糊とした思惟でしかないので、今の処、私は《杳体》に関しては、その判断を保留してゐます。
――すると、丙さんもまた、《杳体》には魅せられてゐるのですわね?
――はい。恥ずかしながらその通りです。《杳体》は、この「黙狂者」が言ふ《杳体》は、《存在》が必ず陥る宿命にある自同律といふDilemma(ジレンマ)に対する一つの解答を与へるかもしれないとは思ってゐます。
――まあ、丙さん、丙さんが、一番の《杳体》の信者ぢゃありませんか! うふっ。
雪はさう言ふと、煙草を一服深呼吸をするやうに飲み、そして、
――ふ~う。
と煙を吐いたのであった。
――丙さん、丙さんは、自同律とは《吾》といふDilemmaに陥る外ない《もの》とお考へですの?
と、雪が可愛らしい仕種で煙草を人差し指と中指で挟みながら尋ねたのであった。
――はい。《一》=《一》が成立する《世界》は幻でしかないのです。つまり、此の世は一つとして同じ《もの》は《存在》しない、多様な《世界》といふ事です。
――うふっ。すると丙さんは抽象といふ事は取るに足らぬ《もの》と看做してゐるのですの?
――いえ、そんな事はありません。尤も《一》=《一》が成立する抽象化された《世界》の世界認識の仕方、若しくは世界観を、「現存在」を初めとする此の世の森羅万象は、余りにも安直に現実に当て嵌めてゐる事に、私は、否を唱へてゐるだけです。
――つまり、丙さんは数学、いえ、数理物理の成立する《世界》を否定なさるといふ事ですの?
――いや、否定はしませんし、私は、数理物理は積極的に支持します。しかし、抽象化と具体化には、つまり、理想と現実の間には、跨ぎ果せぬ断絶があるといふ事を言ってゐるのです。例へばそれは、《吾》=《吾》が一時も成り立たない事、つまり、自同律が不成立だといふ事実を物理数学は余りに軽視し過ぎてゐるのです。
――あら、丙さん、例へば、《吾》=《吾》が成り立たない時とはどんな時ですの?
――雪さん、全宇宙史を通して《吾》=《吾》が成立した事はないのです。
――え! また、それはどうしてですの?
――此の世が諸行無常故に、《吾》がその《存在》において、一時も同じ《吾》であった例はありません。
――それぢゃ、丙君、《杳体》において、《吾》=《吾》は成立すると思ふかい?
と甲君が容喙すると、
――ふむ。《杳体》における《吾》か……。多分、《杳体》において初めて《吾》は、《吾》であり得る事が可能で、つまり、《吾》=《吾》が成立するかもしれぬが、しかし、甲よ、そもそも《杳体》の摂理とは想像するに、どんな《もの》だと思ふ?
――甲さん。私も訊きたいわ。
と、雪が言ふと、甲君がにたりと笑ひ、
――へっ、正直に言ふと、私にも解かりません。しかし、《杳体》は《存在》がそれが何であれ、《存在》が《存在》しちまふならば、全て一様の《存在》の有様に収束させて《存在》を把捉出来る《存在》の汎用化が成立する、奇妙奇天烈なる《世界》、その《世界》は恒常不変な《世界》に違ひないと思ひますが、その奇妙な《世界》の摂理に《吾》は恍惚の態で自同律の快楽に耽溺すると思ひます。
と言ったのであった。すると丙君が鋭き眼光を放つ目を甲君に向けて、次のやうに言ったのであった。
――それは地獄の事ではないのかね? つまり、《吾》は未来永劫不易なる《吾》でなければならない宿命を強ひられ、地獄の責め苦を受け続ける《吾》が恍惚との態で犇く地獄絵図! 例へばそれは原爆が投下され爆発してゐるその下の《世界》の諸物ではないのか! その原爆投下による前代未聞の灼熱地獄に《吾》は一瞬で焼死するか、若しくは被爆して、最早誰だか判別不可能な異形へと変はってしまった《死》に逝く森羅万象の《吾》の蒼白き命の最期の灯。
――甲さん! それでは《杳体》とは、《吾》の死滅した《世界》を暗示する《もの》ですの?
――さうですねえ。私は、《杳体》は《死》と密接に結び付いた何かなのは間違ひないとは思ってゐます。
――それでは、丙さんの仰る通り、《杳体》は地獄の別称かもしれないのですね!
――はい。《吾》が《吾》の属性を全て喪失した《吾》が《存在》する恒常不変な《世界》、つまり、それを一言で言ってしまへば、地獄に堕ちた《吾》が、《杳体》を暗示する事は否定しません。尤も、《吾》が《吾》の属性を全て兼ね備へた《神》の如き《吾》が、恒常不変に《存在》する天上界もまた、《杳体》を暗示します。
――つまり、甲さん! それはヰリアム・ブレイクの『The Marriage of Heaven and Hell』(天国と地獄の婚姻)ですね?
――さうかもしれません。唯、ブレイクの『The Marriage of Heaven and Hell』もまた、《杳体》を暗示するだけです。
…………
…………
ねえ、君、ここに私は『The Marriage of Heaven and Hell』に書き出してみるが、さて、ブレイクの『The Marriage of Heaven and Hell』が、果たせる哉、《杳体》を暗示してゐるがどうかは君次第だぜ。
William Bkake著
『The Marriage of Heaven and Hell』
The Argument.
Rintrah roars & shakes his fires in the burden’d air;
Hungry clouds swag on the deep
Once meek, and in a perilous path,
The just man kept his course along
The vale of death.
Roses are planted where thorns grow.
And on the barren heath
Sing the honey bees.
Then the perilous path was planted:
And a river, and a spring
On every cliff and tomb;
And on the bleached bones
Red clay brought forth.
Till the villain left the paths of ease,
To walk in perilous paths, and drive
The just man into barren climes.
Now the sneaking serpent walks
In mild humility.
And the just man rages in the wilds
Where lions roam.
Rintrah roars & shakes his fires in the burden’d air;
Hungry clouds swag on the deep.
『天国と地獄の婚姻』
要旨。
リントラが重重しき空気の中にて己の炎を轟轟と打ち震はせてをり、
飢ゑたる雲雲が深淵の上に垂れ込め
嘗ては柔和な、そして一本の危険な小路に、
まさしく正しき人間が死の谷に沿ってその道筋を進み行き。
棘が生えし処には薔薇が植ゑられてをり。
そして灌木の生えたる不毛な荒野に
蜜蜂が歌ひし。
それから危険な小道には草木が植ゑられ。
そして一筋の河、そして一つの泉
あらゆる断崖と墓の上に、
そして白骨の上には
赤土が生じし。
悪漢が楽なる道道を去る迄、
危険な道を歩く事を、そして
正しき人間が不毛な土地を邁進する事を。
今、頭を突き出した大蛇が蛇行す
柔和な謙遜の中を
そして正しき人間が獅子のうろつき回りし荒野で
憤怒せし。
リントラは重重しき空気の中にて己の炎を轟轟と打ち震はせてをり、
飢ゑたる雲雲が深淵の上に垂れ込め
As a new heaven is begun, and it is now thirty-three years since its advent: the Eternal Hell revives. And lo! Swedenborg is the Angel sitting at the tomb; his writings are the linen clothes folded up. Now is the dominion of Edom, & the return of Adam into Paradise; see Isaiah XXXIV & XXXV Chap:
Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human existence.
From these contraries spring what the religious call Good & Evil. Good is the passive that obeys Reason. Evil is the active springing from Energy.
Good is Heaven. Evil is Hell.
或る新しき「天国」が始まり、そして、現在、基督降臨から三十三年なりし、
「永劫の地獄」が再興せり。そして、見よ! スウェーデンボルグが墓に坐りをりし天使になりつ。彼の著作は折りたたまれし麻布。今、エドムの支配下である、そして「楽園」にアダムが戻りし。イザヤ書三十四と三十五章を見給へ。
「相反するもの」がなければ進歩なし。「引力」と「斥力」、「理」と「活力」、「愛」と「憎悪」は、「人間」の存在に必須なりし。
それら反対するものが湧き出す泉から宗教においては「善」と「悪」と呼ばれるものが湧き出し。「善」は「理」に従ふ受動的なものなりし。「悪」は「活力」から湧き出し能動的ものなりし。
「善」は「天国」。「悪」は「地獄」。
The voice of the Devil.
All Bibles or sacred codes have been the causes of the following Errors.
1. That Man has two real existing principles Viz: a Body & a Soul.
2. That Energy, call’d Evil, is alone from the Body, & that Reason, call’d Good, is alone from the Soul.
3. That God will torment Man in Eternity for following his Energies.
But the following Contraries to these are True
1. Man has no Body distinct from his Soul for that call’d Body is a portion of Soul discern’d by the five Senses, the chief inlets of Soul in this age
2. Energy is the only life and is from the Body and Reason is the bound or outward circumference of Energy.
3 Energy is Eternal Delight
「悪魔」の声
あらゆる聖書若しくは聖典。以下の「誤謬」の因なり。
1. 「人間」こそ二通りの存在の原理がありし、即ち、「肉体」と「魂」。
「活力」こそ「悪」と呼ばれ、「肉体」からのみなり。そして、「理」こそ「善」と呼ばれ、「魂」のみからなり。
2. 「神」こそ以下に書き記せし自身の「活力」のために「永劫」の地獄の刑罰に苦悶する「人間」であらう。
しかし、以下に綴られし「相反するもの」の数数は「真実」なり
1. 五感によって関係する「魂」の一部である「肉体」と呼ばれしものに関して「人間」は自身の「魂」と区別される「肉体」を持たず、この時代が「魂」の主なる入口
2. 「活力」は唯一生でありそして「肉体」から生じそして「理」は「活力」の限界若しくは「肉体」の外的な限界なり。
3. 「活力」は「永劫」なる「喜び」なり
Those who restrain desire, do so because theirs is weak enough to be restrained; and the restrainer or reason usurps its place & governs the unwilling.
And being restrain’d it by degrees becomes passive till it is only the shadow of desire.
The history of this is written in Paradise Lost, & the Governor or Reason is call’d Messiah.
And the original Archangel or possessor of the command of the heavenly host, is call’d the Devil or Satan and his children are call’d Sin & Death.
But in the Book of Job Miltons Messiah is call’d Satan.
For this history has been adopted by both parties.
It indeed appear’d to Reason as if Desire was cast out, but the Devil’s account is, that the Messiah fell, & formed a heaven of what he stole from the Abyss.
欲望を制限する人人は彼らのものが制限されるに十分弱い事より制限されし。そして制限するもの若しくは理性的なるものはそれに取って代わりし、そして不承不承に統治されし。
そして程度によってそれが制限される事は受動的なり、遂にそれが欲望の影にのみになりし。
この歴史は『失楽園』に書かれし。そして、「統治者」若しくは「理」は「救世主(メシア)」と呼ばれし。
そして本来の「大天使」若しくは天上の主が所有する軍隊の所有者は、「悪魔」若しくは「大悪魔」と呼ばれそして彼の子は「罪」と「死」と呼ばし。
しかし、「ヨブ記」の中では、ミルトンの「救世主」は「大悪魔」と呼ばれし。
何故ならこの歴史は両派により受け入れられし
それは「欲望」が投げ棄てられるかのやうに実際、「理」に対して現はれし。しかし、「悪魔」達の審判は「救世主」が倒れる事なり、そして「奈落」から救世主が盗みしものにより一つの天界を創りし
This is shewn in the Gospel, where he prays to the Father to send the comforter or Desire that Reason may have Ideas to build on, the Jehovah of the Bible being no other than he who dwells in flaming fire.
Know that after Christs death, he became Jehovah.
But in Milton; the Father is Destiny, the Son, a Ratio of the five senses, & the Holy-ghost, Vacuum!
Note: The reason Milton wrote in fetters when he wrote of Angels & God, and at liberty when of Devils & Hell, is because he was a true Poet and of the Devils party without knowing it.
此の事は福音書に見られし、彼は団欒が若しくは「理」が「理想郷」を打ち建てし「欲望」が送られむ事を「父」に対して祈りし、聖書のエホヴァは将に彼ぞ、その彼は燃え立つ炎の中に棲みし。「基督の死」後を知るべし、彼はエホヴァになりし。
しかし、ミルトンにおいて、「父」は宿命であり、「息子」であり、五感の或る「比率」になりし。そして「精霊」、「虚無」!
注釈。理性的なるミルトンは、彼が「天使」と「神」について書きし時、媚び諂ひ書きし、そして「悪魔」と「地獄」については自由闊達で、それは彼がさうとは全く知らずに真実の「詩人」であり「悪魔」派故なり
A Memorable Fancy.
As I was walking among the fires of hell, delighted with the enjoyments of Genius; which to Angels look like torment and insanity. I collected some of their Proverbs: thinking that as the sayings used in a nation, mark its character, so the Proverbs of Hell, shew the nature of Infernal wisdom better than any description of buildings or garments.
When I came home; on the abyss of the five senses, where a flat sided steep frowns over the present world. I saw a mighty Devil folded in black clouds, hovering on the sides of the rock, with corroding fires he wrote the following sentence now percieved by the minds of men, & read by them on earth.
How do you know but ev’ry Bird that cuts the airy way,
Is an immense world of delight, clos’d by your senses five?
記憶に残りし幻想
吾が地獄の炎の中を歩きし時、「霊」の愉悦で歓びし。「天使」にとっては劫罰で異常に見えるが、吾は彼らの幾つかの「諺」を集めし。その謂はれが或る国で使はれるやうに考へつつ、その文字に印をつけて、「地獄の諺」は以下のやうに、建物や衣服を描くよりもよい[地獄]の智の性質を示してをりし。
吾が家に帰りし時、五感の奈落の上に、或る平面が現実世界を覆ひつつ険しいしかめっ面をその両側にあしらへて、吾は見し、黒雲に囲われし或る強力な「悪魔」を、両側の巌の上を漂ひつつ侵食する炎と共に、彼は今、人間の感知出来る以下の文章で書き記す、そして、地の上でそれらを読みし。
あなたは、あらゆる「鳥」が将に天空を切り裂きつつ飛翔するのは如何様にしているのかを知りしか、
広大無辺なる歓びの世界はあなたの五感により閉ぢられしか?
Proverbs of Hell.
In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy.
Drive your cart and your plow over the bones of the dead.
The road of excess leads to the palace of wisdom.
Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity.
He who desires but acts not, breeds pestilence.
The cut worm forgives the plow.
Dip him in the river who loves water.
A fool sees not the same tree that a wise man sees.
He whose face gives no light, shall never become a star.
Eternity is in love with the productions of time.
The busy bee has no time for sorrow.
The hours of folly are measur’d by the clock, but of wisdom: no clock can measure.
All wholsom food is caught without a net or a trap.
Bring out number weight & measure in a year of dearth.
No bird soars too high, if he soars with his own wings.
A dead body revenges not injuries.
The most sublime act is to set another before you.
If the fool would persist in his folly he would become wise.
Folly is the cloke of knavery.
Shame is Prides cloke.
Prisons are built with stones of Law, Brothels with bricks of Religion.
The pride of the peacock is the glory of God.
The lust of the goat is the bounty of God.
The wrath of the lion is the wisdom of God.
The nakedness of woman is the work of God.
Excess of sorrow laughs. Excess of joy weeps.
The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, and the destructive sword, are portions of eternity too great for the eye of man.
The fox condemns the trap, not himself.
Joys impregnate. Sorrows bring forth.
Let man wear the fell of the lion. woman the fleece of the sheep.
The bird a nest, the spider a web, man friendship.
The selfish smiling fool, & the sullen frowning fool shall be both thought wise, that they may be a rod.
What is now proved was once only imagin’d.
The rat, the mouse, the fox, the rabbet; watch the roots; the lion, the tyger, the horse, the elephant, watch the fruits.
The cistern contains: the fountain overflows.
One thought fills immensity.
Always be ready to speak your mind, and a base man will avoid you.
Every thing possible to be believ’d is an image of truth.
The eagle never lost so much time, as when he submitted to learn of the crow.
The fox provides for himself. but God provides for the lion.
Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.
He who has suffer’d you to impose on him knows you.
As the plow follows words, so God rewards prayers.
The tygers of wrath are wiser than the horses of instruction.
Expect poison from the standing water.
You never know what is enough unless you know what is more than enough.
Listen to the fools reproach! it is a kingly title!
The eyes of fire, the nostrils of air, the mouth of water, the beard of earth.
The weak in courage is strong in cunning.
The apple tree never asks the beech how he shall grow; nor the lion, the horse, how he shall take his prey.
The thankful reciever bears a plentiful harvest.
If others bad not been foolish, we should be so.
The soul of sweet delight can never be defil’d.
When thou seest an Eagle, thou seest a portion of Genius. lift up thy head!
As the catterpiller chooses the fairest leaves to lay her eggs, so the priest lays his curse on the fairest joys.
To create a little flower is the labour of ages.
Damn braces: Bless relaxes.
The best wine is the oldest, the best water the newest.
Prayers plow not! Praises reap not!
Joys laugh not! Sorrows weep not!
The head Sublime, the heart Pathos, the genitals Beauty, the hands & feet Proportion.
As the air to a bird or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible.
The crow wish’d every thing was black, the owl, that every thing was white.
Exuberance is Beauty.
If the lion was advised by the fox. he would be cunning.
Improvement makes strait roads, but the crooked roads without Improvement, are roads of Genius.
Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.
Where man is not, nature is barren.
Truth can never be told so as to be understood, and not be believ’d.
Enough! or Too much.
地獄の諺
種蒔きの時に学び、収穫の時に教え、冬に歓べ
あなたの荷馬車と犂(すき)とを死の骨の上で駆り給へ。
やり過ぎる過剰をして辿りし道筋は智の王宮に導きし
思慮深さは無能により得られし裕福で醜悪な年老いた処女なり。
行動せずにのみ欲望するものは悪病を育む。
切られし蚯蚓(みみず)は犂を忘れじ。
水を愛せしものは河の中で堀るべし
莫迦者は賢者が見るやうに同じ木を見ない。
光なし面(おもて)を与へられしものは決して星に為れず。
永劫は時が創りし愛にある。
忙しき蜜蜂には哀しむ暇などなし。
愚なる時間は時計で計られし、しかし、智の時間は、時計では計れず。
あらゆる健康に良い食物は網や罠なしに捕へられし。
死の年に重さと秤の数字が齎されし。
如何なる鳥も高すぎる飛翔はせず。鳥が己の翼で飛翔する限り。
一柱の死体は、怪我を以て復讐せず。
もっとも高貴な行為はあなたの前の他人を座らせる事なり。
愚者が己の愚かさに固執するならば賢者にならむ
愚かさとは悪業の衣服なり。
羞恥は「矜持」の衣服なり。
収容所は「法」の石にて建てられし、昌家は「宗教」の煉瓦で。
孔雀の矜持は「神」の栄光なり。
山羊の肉欲は「神」の賜物なり。
獅子の激怒は「神」の智なり。
裸婦は「神」の作品なり。
哀しみの過剰が笑ひなり。歓びの過剰が咽び泣きなり。
獅子の咆哮、狼の遠吠へ、嵐の海の憤怒そして破壊する剣は人間の目には偉大過ぎる永遠の一部なり。
狐は己ではなく罠を非難す。
歓びは受胎せし。「哀しみ」は産まれし。
男は獅子の凶暴を着用し、女は羊の毛を纏へ。
鳥には巣を、蜘蛛には蜘蛛の巣を、人間には友愛を。
己を嗤う愚。そして無愛想でしかめっ面をした愚。どちらも賢いと考らむ、それらが鞭打たれるようとも。
現在証明されしものは嘗て、想像するのみもの。
鼠、二十日鼠、狐、兎は、根を見守りし、獅子、虎、馬、象は、果実を見守りし。
水槽は含有す、泉は湧出す
一つの思考は、無限に満つる。
絶えずあなたの心を語る準備をせよ、さすれば或る下卑たものはあなたを避けよう。
信じられしあらゆるものは真実の表象なり。
鷲はそのやうに多くの時を無駄にせず。鷲が群れの教えに屈服する時。
狐は己のために備へる。しかし、「神」は獅子のために備へる。
朝に考へよ、正午に行動せよ、晩に食べよ、夜に寝よ。
あなたに課されしものを蒙る彼はあなたを知る。
犂が言葉に連なるやうに「神」は祈る人に報いし。
憤怒の虎は馴致されし馬よりも賢し。
動かぬ水より毒を予期せよ。
あなたは十分以上のものが何かを知らずば、十分なるものを知らぬ。
愚者の咎めるのを聞き給へ! それは王の題なり。
炎の目、空気の鼻孔、水の口、地の髭。
勇気に弱い事は、狡猾な強さになる。
林檎の木は橅にどのように成長するのかを尋ねず、同様に獅子も馬に餌をどのやうに獲得するかを。
感謝に満ちし受領者は豊かな稔を生む。
仮に他者が愚かでなければ、吾等が愚かなり。
美麗なる歓びの魂は決して穢れぬ。
汝が高を見し時汝は霊の一部を見し。汝の頭を上げよ!
芋虫が自身の卵を産み付けし時に最も美しき葉を選びしやうに、祭司は最も美しき歓びの上に呪ひを置きし。
可憐な花を作りし事は時代の労役なり。
この野郎。気を引き締めろ。安寧に祝福あれ。
最も上級な葡萄酒は最も古いものなり、最も良き水は最も新鮮なものなり。
祈る人は犂を引くまじ。賛美は収穫するまじ。
歓びは笑うまじ。哀しみは咽び泣くまじ。
頭は崇高。心臓は悲哀。生殖は美。手と足は釣合ひ。
鳥における空気のやうに若しくは魚における水のやうに、軽蔑すべきものにおける軽蔑なり。
烏はあらゆるものが黒なる事を望み、梟はあらゆるものが白なる事を望む。
充溢は美なり。
仮に獅子が狐に助言されれば、獅子は狡猾なりし。
「改善」は真っすぐな道を造りし、しかし、「改善」なき鉤状の道は、「天才」の道なり。乳母は欲望を押し留めしよりも、揺り籠の中で幼児を殺せ。
人間が自然でない処は不毛なり。
真実は理解されるやうに決して離せず、そして、信ずられず。
十分! 多すぎだ
The ancient Poets animated all sensible objects with Gods or Geniuses, calling them by the names and adorning them with the properties of woods, rivers, mountains, lakes, cities, nations, and whatever their enlarged & numerous senses could percieve.
And particularly they studied the genius of each city & country, placing it under its mental deity;
Till a system was formed, which some took advantage of & enslav’d the vulgar by attempting to realize or abstract the mental deities from their objects: thus began Priesthood;
Choosing forms of worship from poetic tales.
And at length they pronounc’d that the Gods had order’d such things.
Thus men forgot that All deities reside in the human breast.
古の詩人は「神」若しくは「霊」のやうに感得出来る全てに命を吹き込みし、それらは名で呼ばれそしてそれらを木、河、山脈、湖、都市、国、そしてそれら広大無辺で数多ある、感覚が感得出来るものの特性を古の詩人は崇拝す。
そして特に詩人たちは各各の都市と国の霊について研究せし、それを精神の神神と為し。
或る体系が形作られるまで、体系は木木などの物体から精神の神神として実体化若しくは抽象化する事を企てる事で世俗化したものを利用し若しくは隷属化す、かやうに司祭が始まりし。
詩的な話から礼拝の型が選びつつ。
そして遂に詩人たちは「神神」がかやうなものを秩序づけせしと語りし。
かくして人間は人間の胸にあらゆる神神があるのを忘れし。
A Memorable Fancy.
The Prophets Isaiah and Ezekiel dined with me, and I asked them how they dared so roundly to assert that God spake to them; and whether they did not think at the time, that they would be misunderstood, & so be the cause of imposition.
Isaiah answer’d. ‘I saw no God, nor heard any, in a finite organical perception; but my senses discover’d the infinite in every thing, and as I was then perswaded, & remain confirm’d, that the voice of honest indignation is the voice of God, I cared not for consequences but wrote.’
Then I asked: ‘does a firm perswasion that a thing is so, make it so?’
He replied: ‘All poets believe that it does, & in ages of imagination this firm perswasion removed mountains; but many are not capable of a firm perswasion of any thing.’
Then Ezekiel said. ‘The philosophy of the east taught the first principles of human perception: some nations held one principle for the origin & some another; we of Israel taught that the Poetic Genius (as you now call it) was the first principle and all the others merely derivative, which was the cause of our despising the Priests & Philosophers of other countries, and prophecying that all Gods would at last be proved to originate in ours & to be the tributaries of the Poetic Genius; it was this that our great poet King David desired so fervently & invokes so pathetic’ly, saying by this he conquers enemies & governs kingdoms; and we so loved our God. that we cursed in his name all the deities of surrounding nations, and asserted that they had rebelled; from these opinions the vulgar came to think that all nations would at last be subject to the jews.’
‘This’ said he, ‘like all firm perswasions, is come to pass; for all nations believe the jews’ code and worship the jews’ god, and what greater subjection can be?’
I heard this with some wonder, & must confess my own conviction. After dinner I ask’d Isaiah to favour the world with his lost works; he said none of equal value was lost. Ezekiel said the same of his.
I also asked Isaiah what made him go naked and barefoot three years? he answer’d, ‘the same that made our friend Diogenes the Grecian.’
I then asked Ezekiel why he eat dung, & lay so long on his right & left side? he answer’d, ‘the desire of raising other men into a perception of the infinite; this the North American tribes practise, & is he honest who resists his genius or conscience. only for the sake of present ease or gratification?’
記憶に残りし幻
預言者のイザヤとエゼキエルは吾と共に食事をし、そして吾は彼ら預言者に尋ねし、
如何に彼ら預言者は敢へて徹底的に言挙げしたのかを。「神」が彼ら預言者に話されし事を、そして彼ら預言者が誤謬してゐるのか、若しくは騙す事の因になりしかとその時に考へなかったのかどうかを。
イザヤが答へし。吾は如何なる「神」にも出会はず。また、何も聞かず、有限なる有機的な感覚においては、しかし吾が感覚はあらゆるものに無限を見出しぬ、そしてかやうに吾はその時に説得されし。そして確信として残りし、誠実な義憤の声は「神」の声なり、吾は結果がどうあらうとも書かずにはゐられなかった。
それから吾尋ねし、物事がかやうであり、かやうになるといふ堅固なる確信であるかと。
彼は答へし。あらゆる詩人はさうなりし事を信ずる、そして想像力の時代においてこの堅固なる確信は山脈をも動かす、しかし、多くのものは堅固なる確信の唯一つすらも受け容れられず。
エゼキエル曰く。東方の哲学者は人間の感覚が感得せし第一原理を教へし 幾つかの国国は根源の一つの原理として保持すそしてその外は他の原理として保持す、イスラエルの吾等は(あなた方が今はそれをさう呼んでゐる)「詩的なる霊性」が第一原理とあらゆるその他の派生しもの、その派生したものは、他の国国の「祭司」と「哲学者」達を吾等をして軽蔑させ、そしてあらゆる「神」は遂には証明されるに違ひなき予言と教へし。吾等において根源的なる事、それはかやうである、吾等が偉大な詩人たるダビデ王は余りに熱狂的に望み、あまりに感情的に祈願せし、かく言ひつつ、ダビデ王は敵を征服し王国を支配すと、吾等はそのやうに「神」を愛せし、かやうに吾等は周辺国からダビデの名で呪われ彼らは謀反を起こすと主張せられり、これらの意見から衆生はあらゆる国が遂にはユダヤの属国になると考へるやうになりし。
かやうにかれは言ひけり、あらゆる堅固な確信のやうに、過去はさうなりし、といふのも、あらゆる国はユダヤ人の法典を信じ、ユダヤの神を礼拝す、そしてより偉大なる支配者に為り得ることに関して
吾いくつかの驚きを以てこれを聞けり、そして吾自身の確信を告白すべきなり。夕食後吾はイザヤに彼の失われし作品と共に世界を好いているかと尋ねし、彼は如何なる等価価値をも失はれてをらずと言ひけり。エゼキエルもイザヤと同じだと言ひけり。
吾、また、何が彼を裸にし、三年間素足にしたのかを尋ねし。彼答へし、吾等の友、ギリシアのディオゲネスと同じくしたまでの事と。
吾は其処でエゼキエルに尋ねし。何故に糞を喰らひしかと、そしてかくも長く右側に横たわり、そして左側に横たわりしは何故か? 彼答へし。無限を知りし他の人びとに生じし欲望 これは北アメリカの民族が実践せり、そして彼は彼の霊性と意識に抵抗せしは最も誠実故にかと。唯、現在の安寧と満足のため為りしか?
The ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of six thousand years is true, as I have heard from Hell.
For the cherub with his flaming sword is hereby commanded to leave his guard at the tree of life, and when he does, the whole creation will be consumed and appear infinite and holy whereas it now appears finite & corrupt.
This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment.
But first the notion that man has a body distinct from his soul is to be expunged; this I shall do, by printing in the infernal method, by corrosives, which in Hell are salutary and medicinal, melting apparent surfaces away, and displaying the infinite which was hid.
If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite.
For man has closed himself up, till he sees all things thro’ narow chinks of his cavern.
世界が六千年の終はりに業火の炎で焼き尽くされるといふ古代の伝説は真実なり、吾は「地獄」より聞きしやうに。ここで、炎の剣を持てし「智天使」が命の木を守りしものを去らせるように命令したために、そして、彼がそのやうにし、そして、あらゆる創造物は焼き尽くされ、そして無限が現はれし。そして、一方で聖は現在、有限に堕落せし。
この意思は官能的な快楽の進歩を実現す。
しかし、人間が魂と全く違った肉体を持つといふ最初の考へは、消去すべきなり、吾がこの事をするだらう、浸食する地獄の理論を刷り込まれ、それは「地獄」では有益で薬になり、見かけの表面を溶かしながら、隠されてをりし永劫がその姿を現はし。
知覚の扉がきれいにされしならばあらゆるものはかやうに人間に現はれし、無限に。
遂に人間が彼の洞窟の狭い割れ目を通してあらゆるものを見るまで、何故なら人間は自身で閉ぢちし。
A Memorable Fancy.
I was in a Printing house in Hell & saw the method in which knowledge is transmitted from generation to generation.
In the first chamber was a Dragon-Man, clearing away the rubbish from a cave’s mouth; within, a number of Dragons were hollowing the cave.
In the second chamber was a Viper folding round the rock & the cave, and others adorning it with gold silver and precious stones.
In the third chamber was an Eagle with wings and feathers of air: he caused the inside of the cave to be infinite, around were numbers of Eagle like men, who built palaces in the immense cliffs.
In the fourth chamber were Lions of flaming fire raging around & melting the metals into living fluids.
In the fifth chamber were Unnam’d forms, which cast the metals into the expanse.
There they were reciev’d by Men who occupied the sixth chamber, and took the forms of books & were arranged in libraries.
記憶に残りし幻
吾は「地獄の印刷所」にをりし、そして、時代から時代へと伝はる知識の法則が解かりし。
第一の部屋には「龍人」がをりし洞窟の入り口から塵を掃出しつつ、内部で、幾らかの「龍」が洞窟を掘りつつ。
第二の部屋には巌と洞窟でとぐろを巻く「大蛇」がをりし、そしてその他の大蛇が金銀や宝石で飾りつつ。
第三の部屋には空気の翼と羽を持ちし「鷹」がをりし、その「鷹」は洞窟の中での無限の因なり、巨大な断崖に宮殿を建てし人間に似た夥しき鷹がをりし。
第四の部屋には憤怒の炎を燃やせし「獅子」がをりしそして金属を熔かし生きた流体とせし。
第五の部屋には「名もなきもの」がをりし、そのもの膨張するものへ金属を投げ入れし。
それから第六の部屋を占めしし「人間」によってそのもの達を受け取り、幾冊もの本を得、図書館を整頓せし。
The Giants who formed this world into its sensual existence and now seem to live in it in chains, are in truth the causes of its life & the sources of all activity, but the chains are the cunning of weak and tame minds which have power to resist energy, according to the proverb, the weak in courage is strong in cunning.
Thus one portion of being is the Prolific, the other the Devouring: to the devourer it seems as if the producer was in his chains, but it is not so, he only takes portions of existence and fancies that the whole.
But the Prolific would cease to be Prolific unless the Devourer, as a sea, recieved the excess of his delights.
Some will say: ‘Is not God alone the Prolific?’ I answer: ‘God only Acts & Is, in existing beings or Men.’
These two classes of men are always upon earth, & they should be enemies; whoever tries to reconcile them seeks to destroy existence.
Religion is an endeavour to reconcile the two.
Note: Jesus Christ did not wish to unite but to seperate them, as in the Parable of sheep and goats! & he says I came not to send Peace but a Sword.
Messiah or Satan or Tempter was formerly thought to be one of the Antediluvians who are our Energies.
感覚的なる存在へと此の世を創りそして今は鎖に繋がれ生きし巨人達に、真実あり。その生の因と全ての行為の淵源は、鎖に繋がれてをりしが、羸弱さと馴致の心の狡猾さなり。それは反抗する力の源泉なり。諺によれば、勇気ある羸弱さは狡猾なる強さなり。
かやうに存在の一部は「多産」なり、その他は「貪婪」なり、貪婪なるものにとって、生み出すものは己の鎖に繋がるやうに見えし、しかし、それはさうではなし、部分部分を存在として取り上げるのみなりそして全体を幻想す。
しかし、海の如く貪婪なものが非常な歓喜で受け取らなければ、「多産」なるものは「多産」である事を已める。
誰かは言ふだらう、「神」のみ「多産」でないのか? 吾答へし、「神」のみ「行為」し「存在」す、存在群若しくは「人間」達が存在する中。
人間のそれら「多産」と「貪婪」の二派は何時も此の世に存在す、そして彼らは敵対者なり、彼らを和解させやうとする誰もが存在を破壊せし。
宗教がその二派を和解させようと努めし。
気付くべきなり。イエス・キリストは和解させようとは帰せず、彼らを分ける事に努めし、羊と山羊の譬へのやうに! そして彼曰く、吾「平和」ではなく一太刀の剣を齎せし。
「救世主(メシア)」若しくは「悪魔」若しくは「誘惑する悪魔」は礼儀正しい吾等の「力」なるノアの洪水以前の一人であると考へられし。
A Memorable Fancy.
An Angel came to me and said: ‘O pitiable foolish young man! O horrible! O dreadful state! consider the hot burning dungeon thou art preparing for thyself to all eternity, to which thou art going in such career.’
I said: ‘perhaps you will be willing to shew me my eternal lot & we will contemplate together upon it and see whether your lot or mine is most desirable.’
So he took me thro’ a stable & thro’ a church & down into the church vault at the end of which was a mill: thro’ the mill we went, and came to a cave: down the winding cavern we groped our tedious way till a void boundless as a nether sky appear’d beneath us & we held by the roots of trees and hung over this immensity; but I said, ‘if you please we will commit ourselves to this void, and see whether providence is here also, if you will not, I will?’ but he answer’d: ‘do not presume, O young-man, but as we here remain, behold thy lot which will soon appear when the darkness passes away.’
So I remain’d with him, sitting in the twisted root of an oak; he was suspended in a fungus, which hung with the head downward into the deep.
By degrees we beheld the infinite Abyss, fiery as the smoke of a burning city; beneath us at an immense distance, was the sun, black but shining; round it were fiery tracks on which revolv’d vast spiders, crawling after their prey; which flew, or rather swum, in the infinite deep, in the most terrific shapes of animals sprung from corruption; & the air was full of them, & seem’d composed of them: these are Devils, and are called Powers of the air. I now asked my companion which was my eternal lot? he said, ‘between the black & white spiders.’
But now, from between the black & white spiders, a cloud and fire burst and rolled thro’ the deep black’ning all beneath, so that the nether deep grew black as a sea, & rolled with a terrible noise; beneath us was nothing now to be seen but a black tempest, till looking east between the clouds & the waves, we saw a cataract of blood mixed with fire, and not many stones’ throw from us appear’d and sunk again the scaly fold of a monstrous serpent; at last, to the east, distant about three degrees appear’d a fiery crest above the waves; slowly it reared like a ridge of golden rocks, till we discover’d two globes of crimson fire, from which the sea fled away in clouds of smoke; and now we saw, it was the head of Leviathan; his forehead was divided into streaks of green & purple like those on a tyger’s forehead: soon we saw his mouth & red gills hang just above the raging foam tinging the black deep with beams of blood, advancing toward us with all the fury of a spiritual existence.
My friend the Angel climb’d up from his station into the mill; I remain’d alone, & then this appearance was no more, but I found myself sitting on a pleasant bank beside a river by moonlight, hearing a harper who sung to the harp; & his theme was: ‘The man who never alters his opinion is like standing water, & breeds reptiles of the mind.’
But I arose, and sought for the mill, & there I found my Angel, who surprised, asked me how I escaped?
I answer’d: ‘ All that we saw was owing to your metaphysics; for when you ran away, I found myself on a bank by moonlight hearing a harper, But now we have seen my eternal lot, shall I shew you yours?’ he laugh’d at my proposal; but I by force suddenly caught him in my arms, & flew westerly thro’ the night, till we were elevated above the earth’s shadow; then I flung myself with him directly into the body of the sun; here I clothed myself in white, & taking in my hand Swedenborg’s, volumes sunk from the glorious clime, and passed all the planets till we came to saturn: here I staid to rest & then leap’d into the void, between saturn & the fixed stars.
‘Here,’ said I, ‘is your lot, in this space, if space it may be call’d.’ Soon we saw the stable and the church, & I took him to the altar and open’d the Bible, and lo! it was a deep pit, into which I descended driving the Angel before me, soon we saw seven houses of brick; one we enter’d; in it were a number of monkeys, baboons, & all of that species, chain’d by the middle, grinning and snatching at one another, but witheld by the shortness of their chains: however, I saw that they sometimes grew numerous, and then the weak were caught by the strong, and with a grinning aspect, first coupled with, & then devour’d, by plucking off first one limb and then another till the body was left a helpless trunk; this after grinning & kissing it with seeming fondness they devour’d too; and here & there I saw one savourily picking the flesh off of his own tail; as the stench terribly annoy’d us both, we went into the mill, & I in my hand brought the skeleton of a body, which in the mill was Aristotle’s Analytics.
So the Angel said: ‘thy phantasy has imposed upon me, & thou oughtest to be ashamed.’
I answer’d: ‘we impose on one another, & it is but lost time to converse with you whose works are only Analytics.’
記憶に残りし幻
一人の天使が吾の処にやって来て言ひし。おお、哀れで莫迦な若者よ! おお、恐ろしき! おお、悲惨なる状態よ! 汝があらゆる永劫へと汝自身を準備せし灼熱の燃え上がれり地下牢に思ひ馳せよ、永劫へと汝はそのやうに行ひし。
吾曰く。多分、汝は吾に吾が永劫なる宿命を見せたいのだそして吾等はそれについて沈思黙考しそして汝の宿命か吾が宿命かのどちらかが最も望ましいかを解からせたいのだ。
かやうに彼は吾とともに馬小屋へ連れて通り過ぎそして教会を通り過ぎそして最後に粉挽き場へと至る教会の地下室へと降りし、そして洞窟へと来し。そのうねうねと曲がりし洞窟を降り、気が滅入る路を手探りで進みし遂には空虚な空の如き無際限な空虚が吾等の下に拡がりしそして吾等は木の根に摑まへられてをり、この無際限に引っかかりてありし、しかし、吾曰く、汝が喜ぶ為れば、吾等はこの空虚に身を委ねてもよろしかり、そしてここでもまた神の摂理が存するかを試すなり。吾の望みを汝は望みしか? しかし彼は答へし。おお、若き人よ、汝が思ひし事はせずこのまま吾等は暗黒が過ぎ去りし刹那に現はれり汝が宿命を見るらむ。
かやうに吾は彼と共に或る樫の木の捻じれし根に坐ってをりし。彼は奈落の底へ頭を向けし茸に宙ぶらりんの状態なり、
徐々に無限なる奈落の底が見えし、燃え上がる都市の煙の如き炎、吾等の下には遙か彼方に太陽があり、暗黒ながらしかし輝きし、太陽の周りには巨大な蜘蛛達が巡りし燃え上がる軌道があり、彼らの獲物の後を這ひつつ、彼らは無限の奈落を飛ぶと言ふより寧ろ泳ぎつ、死体から生まれし最も悍ましき動物の形をし。そして大気はそれに満ちし、そしてそれらで出来てゐるやうに見えし、それらは「悪魔」なり。そして気の「力」と呼ばれし、吾は今、吾の共に吾の永劫の運命どうか? と尋ねし。彼曰く、黒と白の蜘蛛の間
然し今、黒と白の蜘蛛の間から一つの雲が現われりそして炎は燃え上がり下全体の深淵なる漆黒の闇を巡るなり、それ故下の奈落は海の如く黒くなりそして恐ろしき音で轟きし、吾等の下は暗黒の嵐以外何も見えず、雲と波の間の東方を見る迄は、炎と渾然一体となった血の瀑布が、吾等からは多くの石を投げ入れる事もせずに醜悪なる大蛇が現はれてはそして再び鱗を纏ひし途轍もなく巨大で醜悪なる大蛇が沈みし。遂に東方に、三度ほどの距離に、ゆっくりと波の上を燃え立つ波頭が現はれつその波頭は緋色の炎の二つの球体を吾等が見出す迄黄金色の巌のやうに盛り上がりつつ。其処から海は煙の雲の中へと逃げつ、そして今吾等は見し、それはレビヤタン(巨大な海獣)の頭である事を。彼のものの額は虎のそれと同じやうに緑と紫の縞模様に分かれてをり、直ぐ様吾等は血の閃光と共に漆黒の深淵を血の色で染めし憤怒の泡が引っ掛かってゐる口と鰓を見し、吾等の法に向けてあらゆる霊的なる存在の怒りと共に進みし。
吾が友の天使は粉挽き場の彼の持ち場へと上りし、われは一人留まりし、そしてそれから最早何も見えず、しかし、吾はハープの伴奏で歌いしハープ弾きの歌声を聴きつつ月光によって吾が或る川の快適な堤に坐りし様を見出しつ。そして彼の主題は自身の意見を変えぬものは澱んでゐる水の如く、そして心に醜い爬虫類を育てしと。
しかし、吾は立ち上がり、粉挽き場の方を見し、そしてそこで吾は吾が天使を見つけたり、そして天使は私に驚きの質問をせし、吾はどのやうに逃げしか?
吾答へし。吾等が観たすべてのものは、あなたの形而上のお蔭でありし、なぜならあなたが逃げし、吾はハープを聞きながら月光によって吾が堤の上にゐるのが解かりし、しかし、今吾等は永劫の宿命を見し、あなたはあなたの宿命を見しか? 彼は私の申し出に笑ひし、しかし、吾は突然強制的に彼を腕で摑み、夜を通って西へと飛びし、遂に吾等は地上の影から昇華せし、それから吾は彼と共に太陽の中へと真っ直ぐに飛び込み、そして吾は此処で城濾器着物を着し、吾が手にはスウェーデンボルグの著作があり栄光の場から沈みし、そしてあらゆる惑星を通り過ぎ、遂に吾等が土星に来し時、此処で休み、それから空虚へと飛び込みし、土星と恒星の間で。
此処で吾曰く! 汝の宿命なりしや、この時空での、もしそれを時空と呼ばむなら、間もなく吾は馬小屋と教会を見し、そして、吾は彼を聖餐台へ連れて行きそして「聖書」を開きし、そして嗚呼! それは深き穴なり、吾の前のその天使に引っ張られて吾をしてその穴に降らせし、間もなくわれは七つの煉瓦造りの家を見し吾等は第一の家に入りし、中には多くの猿や狒狒(ひひ)など、その種属に属するあらゆるものが胴を鎖で繋がれ、互ひに歯を剝きそして引っ摑みてをりしが、鎖が短き故にそれは抑へられし、然しながら吾はそれらが時時巨大化し、そしてそれから弱きものが強きものに摑まへられ、にたり顔で初めは一組に為りそして貪り食らひし、初めに一つの四肢がそして別のものが引き千切りられ、遂には肉体は絶望的な胴が残されし。そしてこの後歯を剝き出し手にたり顔をしそしてそれに愛してゐるが如くに口付をしそれらもまた貪り喰らはれり、そして彼方此方で自身の尻尾から肉を美味しさうに引っこ抜くものを見つ、恐ろしい悪臭に吾等二人とも苛立たせ、吾等は粉挽き場へ行きし、そして吾はわが手に一柱の骸骨が齎されり、その骸骨は粉挽き場ではアリストテレスの「分析論」なりし。
そうして天使が言ひつ、汝の幻想が吾に騙しけり、そして汝は恥じるべし。
吾答へし、吾等は互ひに騙し合ひ、そして汝の作品が唯一「分析論」為る汝との会話は時間の無駄なり。
Opposition is true Friendship.
I have always found that Angels have the vanity to speak of themselves as the only wise; this they do with a confident insolence sprouting from systematic reasoning.
Thus Swedenborg boasts that what he writes is new; tho’ it is only the Contents or Index of already publish’d books.
A man carried a monkey about for a shew, & because he was a little wiser than the monkey, grew vain, and conciev’d himself as much wiser than seven men. It is so with Swedenborg: he shews the folly of churches & exposes hypocrites, till he imagines that all are religious, & himself the single one on earth that ever broke a net.
Now hear a plain fact: Swedenborg has not written one new truth. Now hear another: he has written all the old falshoods.
And now hear the reason. He conversed with Angels who are all religious, & conversed not with Devils who all hate religion, for he was incapable thro’ his conceited notions.
Thus Swedenborgs writings are a recapitulation of all superficial opinions, and an analysis of the more sublime, but no further.
Have now another plain fact. Any man of mechanical talents may, from the writings of Paracelsus or Jacob Behmen, produce ten thousand volumes of equal value with Swedenborg’s, and from those of Dante or Shakespear an infinite number.
But when he has done this, let him not say that he knows better than his master, for he only holds a candle in sunshine.
対立が本当の友情なり
天使達が唯一の賢さのやうに己自身について語るのに虚しさが付いて回るといふ事を吾は何時も見出しぬ、かやうに彼らは組織化されし理性から芽生えし自信たっぷりで横柄に物事を扱ひし、
かやうにスウェーデンボルグは彼が記したものが新しいと誇りし、しかし、それは既に出版されし本の「内容」と「索引」のみなり
一人の人間が見世物にするために一頭の猿を運びし、そして何故なら人間は猿よりちょっぴり賢いので、自惚れ、七人の人間よりずっと賢い事を彼の事を理解せし。スウェーデンボルグがさうであったやうに、協会の愚かさを見、そして偽善を露呈す、遂にかれは全ては宗教だと想像すそして彼自身蜘蛛の巣が永劫に壊れてしまった地上の唯一のものなり。
今、平明な事実を聞き給へ、スウェーデンボルグは何一つ新しい真実を書かざりし。
今、別のものも聞き給へ、かれは全ての古き愚劣を書きし。
そしてその理由を聞き給へ。彼は全てが宗教的なる天使と話し合ったなりしそして全て宗教を憎む「悪魔」とは話してをらず、何故なら彼は自惚れてゐた為に狭量なりし。
かやうにスウェーデンボルグの著作はあらゆる浅薄な意見の要約、そして更なる荘厳な分析なり、しかしそれ以上のものではなし。
今別の平明な事実がありし、機械に長けた人はスウェーデンボルグの著作と同等なパラケルススやヤコブ・ベームの著作から一万冊の書籍を生み出す。そしてダンテやシェイクスピアの著作から無限の書籍を。
しかし彼がこれを成し遂げし時、彼は彼の主人より優れてゐると知った事を言はさせない、何故なら彼は唯、陽光の中の蝋燭なりし故に。
A Memorable Fancy.
Once I saw a Devil in a flame of fire, who arose before an Angel that sat on a cloud, and the Devil utter’d these words:
‘The worship of God is: Honouring his gifts in other men, each according to his genius, and loving the greatest men best: those who envy or calumniate great men hate God; for there is no other God.’
The Angel hearing this became almost blue but mastering himself he grew yellow, & at last white, pink, & smiling, and then replied:
‘Thou Idolater, is not God One? & is not he visible in Jesus Christ? and has not Jesus Christ given his sanction to the law of ten commandments, and are not all other men fools, sinners, & nothings?’
The Devil answer’d: ‘bray a fool in a morter with wheat, yet shall not his folly be beaten out of him; if Jesus Christ is the greatest man, you ought to love him in the greatest degree; now hear how he has given his sanction to the law of ten commandments: did he not mock at the sabbath, and so mock the sabbaths God? murder those who were murder’d because of him? turn away the law from the woman taken in adultery? steal the labor of others to support him? bear false witness when he omitted making a defence before Pilate? covet when he pray’d for his disciples, and when he bid them shake off the dust of their feet against such as refused to lodge them? I tell you, no virtue can exist without breaking these ten commandments. Jesus was all virtue, and acted from impulse, not from rules.’
When he had so spoken, I beheld the Angel, who stretched out his arms, embracing the flame of fire, & he was consumed and arose as Elijah.
Note: This Angel, who is now become a Devil, is my particular friend; we often read the Bible together in its infernal or diabolical sense which the world shall have if they behave well.
I have also The Bible of Hell, which the world shall have whether they will or no.
One Law for the Lion & Ox is Oppression.
記憶に残りし幻
かつて私は燃え上がる炎の中に「悪魔」を見し。彼は雲に坐り「天使」の前に立てり。そしてその「悪魔」はそれらの言葉を言ひし。
「神」の礼拝はありし。神の霊性に従ひ各各他人の中で光栄なる神の賜り物。そして最も人間を愛する事、偉大なる人を妬みそして中傷する人は「神」を憎むなり、何故なら他に「神」なし故なり。
これを聞きし「天使」は殆ど蒼くなりしが、彼自身を支配しつつ彼は黄色になりし、そして遂には淡い桃色にそして笑ひながらそしてそれから答へし、
汝、偶像崇拝者よ、そなたは「神は一つ」為らずや? 彼はイエス・キリストの中に見えぬや? そしてイエス・キリストはモーセの十戒に認可を与へずやそして他の全ての者は愚者で、罪人で、そして無に等しきものにあらずや?
「悪魔」が答へし、小麦を盛りしすり鉢と共に愚者を擂り潰せし。彼の愚かしさは未だに彼に打ちのめされぬや、仮にイエス・キリストが偉大なるものならば、汝は彼を最高の愛を以て彼を愛するべし、今、聞き給へ、如何にして彼がモーセの十戒を認めしかを、安息日に彼は嘲りしやそして安息日に「神」を嘲笑ひしや? 彼故に殺されし人人を殺すや? 不貞を働きし女から法を顔を背けしや? 彼を支持する為に他の労役を奪いしや? 彼がピラトの面前で守る事を怠りし時過誤の目撃者は堪へられしや? 彼の弟子の為に彼が祈りし時、そして弟子ら泊まらせる事を拒んだ事に反して彼ら拒んだ人人の足の埃を振り払ふやうにと彼が彼ら弟子に命じた時を熱望するや? 吾、汝に言ふ、モーセの十戒破らぬ徳は存在せず、イエスは全ての徳なりし、そして衝動より行動す、徳からではなく。
彼がさう語ったとき、私は手を伸ばして燃え上がる炎を抱き締めし「天使」を見しそして彼は焼き尽くされそして預言者エリヤが現はれし。
注釈。この「天使」は、今は「悪魔」に為りしが、私の特別な友人なり、吾等はその地獄の中で若しくは、世界が上手く運べば必ず生じし残忍なる感覚で「聖書」をお互ひに読みし、
吾はまた持ちつ、「地獄の聖書」を、それは、世界が望むもうが望まないかのどちらかにせよ持つことに為りし。
獅子の為の一つの法若しくは牡牛の圧政
A Song of Liberty.
1. The Eternal Female groan’d! it was heard over all the Earth:
2. Albion’s coast is sick silent; the American meadows faint!
3 Shadows of Prophecy shiver along by the lakes and the rivers and mutter across the ocean: France, rend down thy dungeon;
4. Golden Spain, burst the barriers of old Rome;
5. Cast thy keys, O Rome, into the deep down falling, even to eternity down falling,
6. And weep!
7. In her trembling hands she took the new born terror howling;
8. On those infinite mountains of light, now barr’d out by the atlantic sea, the new born fire stood before the starry king!
9. Flag’d with grey brow’d snows and thunderous visages, the jealous wings wav’d over the deep.
10. The speary hand burned aloft, unbuckled was the shield; forth went the hand of jealousy among the flaming hair, and hurl’d the new born wonder thro’ the starry night.
11. The fire, the fire, is falling!
12. Look up! look up! O citizen of London, enlarge thy countenance: O Jew, leave counting gold! return to thy oil and wine. O African! black African! (go, winged thought widen his forehead.)
13. The fiery limbs, the flaming hair, shot like the sinking sun into the western sea.
14. Wak’d from his eternal sleep, the hoary element roaring fled away:
15. Down rush’d, beating his wings in vain, the jealous king; his grey brow’d councellors, thunderous warriors, curl’d veterans, among helms, and shields, and chariots horses, elephants: banners, castles, slings and rocks,
16. Falling, rushing, ruining! buried in the ruins, on Urthona’s dens;
17. All night beneath the ruins, then, their sullen flames faded, emerge round the gloomy King.
18. With thunder and fire: leading his starry hosts thro’ the waste wilderness, he promulgates his ten commands, glancing his beamy eyelids over the deep in dark dismay,
19. Where the son of fire in his eastern cloud, while the morning plumes her golden breast,
20. Spurning the clouds written with curses, stamps the stony law to dust, loosing the eternal horses from the dens of night, crying:
Empire is no more! and now the lion & wolf shall cease.
Chorus.
Let the Priests of the Raven of dawn, no longer in deadly black, with hoarse note curse the sons of joy. Nor his accepted brethren, whom, tyrant, he calls free: lay the bound or build the roof. Nor pale religious letchery call that virginity, that wishes but acts not!
For every thing that lives is Holy.
「自由の歌」
1. 「永劫の女性」が呻き声を挙げし! それは地上全てに行き渡り、
2. アルビオンの海岸は病み沈黙す、アメリカの牧草地は羸弱なり!
3. 「預言者の影」は湖の川の傍に沿ってぶるぶると震へそして大洋を越えて呟く! フランスは汝の地下牢を粉砕せよ、
4. 黄金のスペインが古代ローマの防壁を爆破せよ、
5. おお ローマよ 汝の鍵を奈落に投げ落とせ 永劫の落下へと、
6. そして泣け!
7. 彼女の震へる手には恐怖が漂ふ新たに生まれしものを、
8. それら永劫の光の山脈の上に今大西洋によって遮られ、その新たに生まれし燃え上がる炎は綺羅星の如き王の前に立てり!
9. 灰色の眉をした雪のやうな白髪そして雷(いかずち)の顔をし嫉妬の翼で奈落の上を波打し、
10. 槍のやうな手を高高と燃え上がらせ留め金が外されし盾、燃え上がる頭の中から嫉妬の手が前へ伸び、そして漂ひつつある新たに産まれしものは星が煌めく夜にうろつきし。
11. 炎が、炎が、落ちてし!
12. 見上げよ! 見上げよ! おお ロンドン市民よ。汝の顔は拡がりし、おおユダヤ人よ、黄金を数えるのを已めよ、汝の油と葡萄酒は戻りし、おお アフリカ人よ! 黒きアフリカ人よ! (行き給へ。翼或る思想よ彼の顔を拡げよ。)
13. 炎の四肢、燃え上がる髪は、西方の海に沈みゆく太陽の如き撃ちし。
14. 永劫の眠りから目覚めると、白髪の四大の一つは逃げ去りし、
15. 嫉妬の王が彼の翼を虚無の中でばたばたさせて猛然と降りてきし、彼の灰色の眉をした顧問官達、雷の戦士達、丸くなりし古参兵達、辺りには、兜そして盾と、輪戦闘馬車、象、軍旗、城、投石器そして岩、
16. 落ち行き、猛然と、崩れし! 瓦礫で埋もれしアーソナの隠れ家。
17. 崩壊の下のあらゆる夜、それからそれらの薄暗き消えゆく炎が陰鬱な王の周りに現はれし、
18. 雷と炎が、荒れた荒野を彼の綺羅星の如き主人を導き彼は彼の十の命令を発布す、陰鬱な暗黒の奈落の上でギラギラと輝く瞳で凝視しながら、
19. 彼の東方の雲に火の息子がをりし処、朝の彼女の黄金の胸を羽繕ふ間、
20. 呪いが書かれし雲を拒みつつ、石の方を踏み潰して塵にし、夜の隠れ家から永劫の馬を解き放ち、泣きながら
皇帝はもうをらず! そして今、獅子と狼は已めし。
「合唱」
夜明けの真っ黒き烏の司祭は、最早、死のやうな暗黒の中で、しはがれた声で歓びの息子へ呪ひの言葉を記すまじ。または、彼の受け入れし同士、即ち彼は自由と呼ばれる、暴君は、境界を作らず屋根を建てず。または処女と呼ばれし蒼白き宗教の淫らな行為は、しかし行為せず、それを望まず!
何故なら生きとし生けるあらゆるものは聖なり
審問官「第三章 轆轤首」
と、ここで、「彼」のノートは破られていた。これは彼がわざとさうしたとしか思えぬのであったが、と言ふのも、彼はこの手記で物語を語る気はさらさらなく、思考がしょっちゅう脱線するやうに、彼が手を加えた事は確実でこれらの手記は、わざわざ分断させるやうに繋ぎ合わされていたのであった。つまり、嘗てのサロン仲間との遣り取りは此処でぶつりと切れて、何とも不可思議な「彼」の手記が続くのであった。それは『轆轤首』と題されたものであった。それは、次のやうにして始まっていた。
…………
現代に生きる「現存在」は遂に轆轤首へと変化してしまったに違ひない。何故かと言へば、例へばPersonal computer(パソコン)のモニター画面を前にして「現存在」が坐せば、それだけで「現存在」は世界中何処へでも、更には何億光年離れた宇宙へまで難なく行ける自在を手にした訳であるが、それは裏を返せば、「現存在」は世界の何処へでも首のみぐっと伸ばして探訪出来るその無様な轆轤首といふ妖怪に変化して、日日、此の世を轆轤首と化した「現存在」共が跋扈してゐると看做せなくもないのであった。
街中を歩いてみれば解かる筈だが、大概の人は、携帯電話のモニター画面に釘付けで、彼らは己が実際には此の街の此処にゐる事には大して重きを置かずに、更に言へば、全く無関心で、只管、此処でない何処かへとぐっと首を伸ばしてモニター画面が映す仮想空間へと己の意識を飛翔させ、つまり、首のみ仮想空間へとぐっと伸ばした轆轤首といふ化け物の異様な姿を衆目に晒してゐるのだが、その衆目もまた轆轤首と化してゐるので、武田泰淳の『ひかりごけ』ではないが、誰もが己の異様な姿には気付かぬのが常なのであった。
成程、現在、現にゐる世界には全く無頓着な彼ら轆轤首達は、また、事故を起こしやすい迷惑者でもあるのだ。彼らの意識や注意力は「吾、此処に在らず」故に、現実の世界では首のみをぐっと伸ばした轆轤首に化けてゐる為に、その足元は覚束ないのは極極当たり前で、尤も、彼ら轆轤首は、自身が轆轤首になんぞに化けてゐるとは全く思ひもよらぬ事で、しかし、傍から見ればモニター画面に釘付けの「現存在」とは、既に轆轤首なのである。轆轤首とは目玉が胴から離れて伸びる蝸牛のゆっくりとした移動の仕方を持ち出すまでもなく、轆轤首は首をぐっと伸ばしてゐる時は、全く歩く事は出来ずに、大概は、坐ってゐるしかないのが、自然の道理の筈なのである。
目玉がぐっと伸びる蝸牛がゆっくりとしか動けないのは、目玉のみが胴から飛び出てゐるが故に、それは自然な事で、目玉と胴との間に距離が生じた事で蝸牛の現在ゐる場所は、目玉で見てゐる視覚の世界と胴で這ってゐる触覚で感じる世界とでは齟齬が生じてゐる筈で、そんな状態では怖くてゆっくりとしか動けないのは至極当たり前なのである。そして、蝸牛がゆっくりと這ってゐる事からすると、蝸牛は胴で感じる触覚で世界認識してゐると看做せなくもないのである。
翻ってモニター画面を前にした「現存在」もまた視覚は、此処ではなく、何処かへと首が伸びてゐるので、モニター画面を見ながら歩行する事が自殺行為でしかないのは、火を見るよりも明らかで、尤も、現代を生きる「現存在」は、己が轆轤首に変化してゐる事に全く気付かぬ故に尚更性質が悪いのである。
此の「現存在」が轆轤首と化してゐる常態を、或る人はモニター画面の前では誰もが平等を獲得したと高らかに宣言するかもしれぬが、「現存在」が轆轤首といふ妖怪へ変化しなければ、その平等は享受出来ない代物で、その仮想空間に順応する「現存在」の変はり行く姿こそが轆轤首なのであった。此の「現存在」の轆轤首化は、更に進化を遂げて更なる何かの妖怪へと変化するかは、不明だが、しかし、「現存在」は、つまり、モニター画面といふ《もの》を前にしての轆轤首と化した「現存在」は、一度その快楽を既に味はってしまったので、最早、元には戻れぬ存在なのでもある。
ならば、その轆轤首とは何なのかと問ふてみれば、暴走する主体、否、暴走する自意識であって、最早、自意識の発露である世界を己がままに変革出来るかもしれぬといふ幻想と、その欲望の進化、つまり、文明の発展を止める事は不可能事でしかなく、また、文明論ほど虚しいものもないので、此処では文明の本質には触れぬが、「現存在」は轆轤首の旨みを知ってしまった故に、最早、一時もモニター画面なしにはをれず、そして、モニター画面といふ厖大な情報が集積され、何時でも欲しい情報がそのモニターから取り出せる仮想空間へとぐっと首を突っ込んで首を伸ばせるだけ伸ばし、首が自在に仮想空間を飛翔する快楽に耽ってゐる「現存在」を見た時の気色悪さは、名状し難き不快なものがあったが、尤も、今では何処を見てもその気色の悪い轆轤首と化した「現存在」ばかりになってしまったのである。そして、既に誰もが轆轤首と化した「現存在」は、それまでの「現存在」として完結してゐた世界=内=存在とは似ても似つかぬ化け物になってしまひ、尤も、化け物と化した「現存在」にとって完結しない世界に首のみぐっと伸ばして、仮想空間を自在に行き交ふ様は、しかし、私には大いなる嫌悪感と虚脱感と屈辱感しか齎さないのであった。
それでは何時の頃より「現存在」は轆轤首へと変化する次第となったのかと問へば、それは、「現存在」が言葉を発したその時に既に轆轤首へと「現存在」が変容してゆく事は、決定してゐたのである。
言葉は、「現存在」の肉体を離れて《吾》以外の《他》に伝播する。つまり、それを戯画風に描き出せば、轆轤首が首をぬうっと伸ばして相手の《他》の耳元で言葉を発する構図にも見えなくもないのである。
言葉を獲得してしまった「現存在」、若しくは「現存在」の遠い先祖である、鳴く事で己の意思を伝へられる動植物達の未来は、現在成し遂げられてゐる仮想空間を媒介として、何時でも《他》の場所にゐる《他》と繋がれる高度情報化社会の出現へと「現存在」が産業革命以来驀進するのは、当然の成り行きだったのである。
しかし、「現存在」による科学技術の発展は、十八世紀に始まった産業革命以降瞠目する程に急速に発展を遂げたのであるが、その前段階としての十五世紀中頃のグーテンベルクの活版印刷を発明した事にその淵源を辿る事も出来得るし、また、それ以前の「現存在」、つまり、エジプト文明の、ギリシア文明の、その他の古代文明の「現存在」にその淵源を求めることも可能で、唯、現代起こってゐる事は、物質を完全に「現存在」の奴隷として看做し、科学技術の発展に各民族が凌ぎを削るその異様さは、人類史上、一際際立ってゐるる或る意味侮蔑すべき時代なのである。。
仮想空間を獲得した「現存在」、即ち、轆轤首は、それでは何を根拠にして物質を「現存在」の完全な奴隷と看做せるやうになってしまったのであらうか。つまり、「現存在」は文明の中で生活する限りにおいて、誰もがブルジョアジーとして物質に備わってゐる或る特性を最大限「現存在」の都合に合はせて利用して、高度な科学技術により生まれし機器類を「現存在」の奴隷として使ひ捨てする疚しさを何時頃から感じなくなったのであらうか。そして、「現存在」は何時から己が轆轤首である事を肯定し、それが恰も自然な事のやうに倒錯する事が可能になったのであらうか。
などなど、数へ上げたなら切がない疑問の数数が湧いて来るのであったが、詰まる所、それは、私の問題であって、私は現状をちっとも肯定出来ずにゐながらも、文明から隠遁する事も出来ない唯の小心者で、それ故に私は現実に対して憤懣やる方無しの、全く幼稚な《存在》でしかないのであった。
――哀れなる哉、《吾》を受け容れられぬ《吾》を生くる《吾》といふものは――。
つまり、私は、現状に憤懣してゐながら己を憐れんでゐるだけの醜い轆轤首に過ぎず、尤も、私はPersonal computer以外のIT機器は極力使はぬやうにはしてゐるが、しかし、それは《吾》が《吾》に関する憤懣と憐れみに対しての虚栄を精一杯張ってゐるに過ぎぬのであった。要するに、私は己が轆轤首である事を受け容れられずに、絶えず《吾》に対して《吾》は齟齬を来たし、《吾》は何時も《吾》に躓く莫迦な《吾》でしかないのであった。
――成程。
私が轆轤首であるのは、私の頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》――私は脳絶対主義のやうな現状を受け容れる事が出来ずに、脳がある頭蓋内の闇を《五蘊場》と名付けたのである――に明滅する表象群を見てしまふ事そのものに、既に「現存在」がぬうっと首を伸ばして世界の至る所に行ける轆轤首たる存在の淵源があるのだ。
仮想空間と《五蘊場》との親和性は見事と言ふ外ない程に相性がよく、つまり、頭蓋内の闇たる《五蘊場》で発火するNeuronも電気信号ならば、仮想空間も、また、電子的なるものとして表出され、それは、つまり、脳の外部化とも言へる事象であって、敢へて言へば、「現存在」は仮想空間に《吾》の脳を仮初に置いておく《場》にすらになってゐて、それは私が脳を幾つも持つ百面相にも変化してゐる事に外ならないのであった。
――ふっ、百面相の轆轤首か……。
仮想化といふ世界を手にした事で一気に拡大する脳といふ幻想をも含有した《五蘊場》は、しかし、よくよく見ると仮想世界は五蘊でなく、色(しき)がすっぽりと抜け落ちた《四蘊場》でしかないのである。つまり、色の喪失してゐる故に「現存在」は轆轤首になる事が可能なのであって、換言すれば、轆轤首以外は仮想空間といふ世界の住人には為れず、また、巨大化した意識体の化け物、つまり、意識の百面相は、一方では、分身の術を身に付けてそれを如何なく発揮しみせては、《吾》であらぬ《吾》といふ《存在》を知ってしまった憐れなる轆轤首と言へなくもなく、仮想世界に仮初にも《存在》する《吾》の分身は、尤も、《吾》がそれを肯定するしないに拘はらずに、次次と生み出され、そして、《吾》の分身は、只管、消費されゆく憂き目を味はふ事に為るのであったが、それに限らずに、実際、《四蘊場》を《五蘊場》にさせるべく殺戮を以てして強引に《五蘊場》に変化せしめる事で、仮想世界の《存在》を現実に刻印するべく悪鬼の出現すらをも覚悟すべき、脳のみが非常に拡大した《四蘊場》の暴走は、止めどなく、只管に拡大するばかりなのである。
さて、右記の事より轆轤首は、《存在》を殺戮するに至ると、それは首が一つの轆轤首では最早なく、例へば双頭の蛇、若しくは八(やま)岐(たの)大蛇(おろち)にすら、もしかすると既に変化してしまってゐると看做せなくもないのである。しかし、《四蘊場》に《生》の愉悦を知ってしまった《もの》は、轆轤首が一瞬にして八岐大蛇に変化する恐怖を心底知ってゐる筈の《四蘊場》に棲息する《もの》は、例へば日本蜜蜂が雀蜂を集団で殺すやうに、仮想世界に浮遊する轆轤首共は徒党を組んで特定の轆轤首を血祭りに上げる恐怖統治で、轆轤首が八岐大蛇に変化する恐怖を抑へ込んでゐると思はれるが、しかし、徒党を組んだ《四蘊場》に《生》の快楽を見出した轆轤首を傍から見れば磯巾着(いそぎんちゃく)の如く、触手が首へと変化したメドゥーサの頭の如き新たな化け物と化してゐる事に全く無頓着で、その新たな化け物は合従連衡を繰り返して、或る時は、社会変革の原動力に為り得る可能性を秘めてゐる故に、それは絶対君主制すらをも生み出す呼び水にすら変化してゐるのである。
それでは、「現存在」が己が轆轤首で、そして、徒党を組んだ多頭の磯巾着の化け物へと変化してゐる自覚がない《五蘊場》に《存在》する「現存在」は、世界から飛び出すに至って《新人=神人》として、此の世に坐すに至ったかと自問自答した処で、茫洋とした虚無感ばかりが胸奥の深奥に吹き荒ぶばかりなのである。詰まる所、《四蘊場》の仮想空間に仮初に《存在》した処で、その《四蘊場》を己の自在のままに変化する《四蘊場》、つまり、何かを此の世の《五蘊場》の世界をも一変させる《四蘊場》の仮想空間は、絶えず色を欲望せずにはをれず、此の色が欠落してゐる《四蘊場》たる仮想空間には、《五蘊場》に明滅する表象群を書き、若しくは描き出す事でのみ轆轤首は十全たる満足を味はふのである。
つまり、《四蘊場》での自己の意識は、途轍もなく巨大化したのであるが、それが返って《吾》の充溢を遠ざけるのみで、《四蘊場》の仮想空間は、成程、知識と情報には事欠かないが、「現存在」は轆轤首、若しくは数多の首による磯巾着の化け物であるには、《吾》すらをも仮想化する暴挙が必須で、それに疲れ果てた轆轤首は、最後には、Monitor画面を紙としてのみの機能があれば、大満足である事を知って、一時は愕然とするのであるが、しかし、さうであるからこそ「現存在」は轆轤首に変化可能なのもまた確かなのである。
――早く人間になりたい。
これが《四蘊場》の轆轤首の呻きなのである。
さて、物質を完全な奴隷としたブルジョアとしての「現存在」が、色の欠けた《四蘊場》における自在感を手にした轆轤首と化した事に、当の「現存在」は余りに無頓着なのである。ところで、物質を「現存在」の完全なる奴隷として扱へるのは、しかし、少数派なのかもしれぬのである。物質の特性を熟知した上に職人技で、何とも名状し難い素晴らしい品物が出来上がる様は、未だに「現存在」は物質にも《神》が宿るのは当たり前で、職人は、物質で出来た品物に命を吹き込む尊ひ《存在》で、さうした職人の手で生まれ出た商品の殆どは、製品の生産に関はってゐた職人には感慨ひとしほの筈で、また、その製品を手にする消費者と呼ばれる「現存在」にとっては、羨望の的な筈である。また、一見、「現存在」は物質を完全な奴隷として扱ってゐると見える「現存在」の奴隷を、少しばかり注意してみれば、職人が生み出した極上の製品を愛して已まない「現存在」が《存在》するのもまた確かで、彼らは職人技に惚れ込んでゐるは間違ひないのである。
では、職人とは何なのか? これは一見簡単な問ひに思へるが、考へれば考へる程、難問なのである。唯、職人は素材に直に対峙する故に轆轤首ではない「現存在」である。そして、職人は、対峙した物質の「癖」を知り尽くすだけの智があり、また、それを知り得るだけの度量があり、さうして、素材の持つ特性を最大限に生かす製品を生み出すのが、職人の一面ではないだらうかとも思ふ。さうして、職人の手で生まれた《もの》は、極上の上質品であり、其処には美があるのだ。しかし、そんな品物は永らく冷遇され、職人にそれ相応の対価を支払ふ事を忌避し、また、職人の手になる商品は当然売れないのであり、職人に弟子入りする「現存在」も非常に少なく、いよいよ多くの職人技が途絶える危機的な状況に追ひ込まれてゐる職人技も少なくなく、物質に対峙する、つまり、その《存在》の物質に対する仕方は《存在》が身に付けるべき《存在》の「作法」であるが、生産者からも消費者からもその「作法」は消えようとしてゐるのである。これは、由由しき問題で、玉石混交は全て一律に同じ価格で売られ、買ふ方もまた、何が上質なのか全く解からなくなってゐるのである。と、ここで、品物の価値は誰が決めるといふ半畳が返ってくるのだが、「それは歴史だ」とだけ答へておく。そして、この美醜が解からぬ事は、間接的に「現存在」の轆轤首化に拍車をかけてゐるのは間違ひなく、つまり、轆轤首は、首をぐっと伸ばして見る《もの》も鑑識眼で判断する事を要求されるのであるが、上質の《もの》を知らない轆轤首は、見る《もの》全てがのっぺらぼうでその善し悪しが全く解からないのである。また、職人技が如何なく発揮された極上の品物は、売り場に置かれる事は少なく、その結果、轆轤首は、使ひ捨てを前提に《もの》を買ふのである。つまり、社会から《もの》に対する「拘り」が消えて、唯、Comsume(食ひ尽くす、焼尽する)する消費者(Consumer)が大量に生まれる事になったのである。そして、それは、轆轤首の首を伸ばす対象は品物その《もの》の善し悪しではなく、その品物に纏はる情報なのである。その傾向が顕著に表はれるのは食ひ物で、Television(テレビ)の画面の中にぐっと首を伸ばして聞き耳を立てて仕入れた情報を全的に信用し、Televisionで取り上げられた食物が放送後、即完売するといふ現象は既に日常茶飯事で轆轤首はTelevisionが生み出す現実味を多少多く帯びた仮想空間で、首をぐっと伸ばし、その対象物ではなく、それに付随する情報を喰らってゐるに過ぎないのである。これは食物に限られた事ではなく、あらゆる場面で幅を利かせ、轆轤首にとってMonitor画面は、情報を齎す、紙媒体の延長でしかなく、また、私は一切やらないのであるが、轆轤首は首を自在に伸ばしてGameで遊ぶ事で、轆轤首は、Gameを或る種の当事者的なる《もの》へと変質させて、轆轤首は最早首をぐっと伸ばしてゐる事が常態化して、その結果当然の事、「現存在」は、家に籠る事象が顕著になるのである。
轆轤首といふ常態当事者化は、然しながら、巨大地震などの自然災害に対しては、一方で大活躍し、一方では、大惨敗を喫したのである。
轆轤首に気楽に変化してゐた「現存在」は巨大地震に襲はれるや、直ぐ様伸びきった首をひょいっと引込め、「現存在」に戻る事を余儀なくされたのであるが、巨大地震でLifeline(ライフライン)を断たれた「現存在」は、携帯電話を一つの命綱として次次と自身でも情報を発信しては、また、次次と情報が更新される画面上の文字情報に釘付けであった筈で、一方でLifelineが壊滅し、また携帯電話やSmartphone(マートフォン)を持たず、更には電池がなくて使ひ《もの》に為らないRadioしかも持っていない私などは、唯、真っ暗な夜を何の情報もなく過ごしたのであるが、案外私のやうに過ごした人も少なくないのではないかと思われる。因みに私は病気故に車が運転できず、車さへ持ってをらずに、車についてゐるRadioは全く聞けない状況下にあったのである。それ以前に巨大地震による巨大津波を前に、画面情報は全く虚しいだけの《もの》でしかなく、情報とは当事者には殆ど役立たずな《もの》でしかなかった事が暴かれて、多くの人命が巨大津波で失われる事になったのである。その一因に情報による慢心があった事は否めないのである。
しかし、大勢の人が巨大地震の犠牲になってゐるので、私個人の意見を以て一般化する事には、巨大地震で亡くなった方への冒瀆でしかないので、それはやらないが、唯、本能で高台へ避難した人のみが生き残り、社会的な使命を全うして巨大津波に呑み込まれて命を失った人が大勢ゐた事もまた忘れてはならない。
巨大地震を経た今、ITのツールは二極化するのがほぼ見えて来たやうに思ふ。一つは、紙媒体を延長したもので、既にPersonal computerで重宝するのは、個人が発信するtwitterなどの文字情報である。巨大地震の際もこの個人が発信する情報が最も重宝した《もの》に違ひないのである。
かうなると、やはり、「現存在」は仮想空間へと首を伸ばし、仮想空間を自在に行き交ふ事は、既にその魅力を失ってゐて、敢へて言へば仮想空間はその使命を終へてをり、Monitorが最も活躍するのはtwiiterなどの現在を表出する文字情報へと仮想空間は移行して来てゐるのである。
一方で、映画に代表される動画もまた、人気のContents(コンテンツ)で、その場合、「現存在」は思ふ存分に己が轆轤首である事を満喫するのである。
つまり、現在、ITは二極分化を始めてゐて、これまでのやうに紙媒体を真っ直ぐに延長した《もの》と、これまでも楽しんでゐた映画に代表される動画的な《もの》へと分化し、そして、誰もが、文字であらうが動画であらうが発信出来る状況がITが置かれた現在で、文字情報だと仮想空間は二次元で、動画だと三次元となり、時間も含めた四次元世界に常態する「現存在」は、仮想空間が三次元以下の次元である場合にしか轆轤首に為れず、仮に仮想空間が四次元になると、最早「現存在」が轆轤首に為る事は不可能で、全身をその四次元の仮想空間へと「現存在」はぶち込まれる筈である。多分、「現存在」は仮想空間が四次元世界になる事を望んでをらず、己が轆轤首となって首のみ時空間を自在に行き交へる三次元の動画以外の四次元の《もの》は無用の長物になるに違ひない。
それ程に「現存在」が轆轤首に為る事は、快楽なのだ。twitterなどの個人が発した文字情報と動画を既に組み合はせた《もの》も登場してをり、Televisionは最早時代遅れの《もの》へと変はりつつ、私も含めてTelevisionを殆ど見ない「現存在」が確実に増えてゐると言はれるが、動画は、私にすれば、映画と、そして、個人が発信する少数の動画サイトがあればそれで十分なのだ。私は、己が轆轤首と為って、己の異形を存分に味はひたければ、映画を見、それは映画が映画監督の作品だからであり、その点、Gameは私にとっては退屈な時間でしかなく、Gameは、首を伸ばした轆轤首となりながらも手足などの身体をも動かす面倒が付随するので、己が轆轤首となる事では、Gameは私には要らない《もの》なのであり、Gameをする虚しさに私は堪へられないのである。それならば、全身全霊を轆轤首へと変化して己の頭蓋内の脳と言ふ構造をした闇たる《五蘊場》を弄ったり、映画を見たりする事の方が十分に魅力的なのである。
そんな轆轤首の悪癖の一つに、ぐっと首を伸ばしてMonitor画面上に映った《存在》を五感では感じられないにもかかはらず、全てが解かったやうな気に為る事があげられる。また、さうでなければ「現存在」は轆轤首などに変化しない筈なのである。しかし、その悪癖による「現存在」が蒙る損失を補って余りある魅力が、轆轤首がぐっと首を伸ばして仮想空間を行き交ふ事には意味がある筈なのである。
其処は、つまり、仮想空間は虚実が錯綜してゐる事により、「現存在」が自由を獲得したのかもしれず、「現存在」がMonitor画面を前に、轆轤首となる事で、轆轤首は仮想空間において仮想=自由を存分に味はふ事が出来、換言すれば、頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》の或る一部分を極大に拡大させる事で、恰も己の頭蓋内の闇を自在に弄(まさぐ)って、《五蘊場》で遊行する事が可能になったかの如くに、つまり、意識がITによって此の世の広さと等価となったかの如き錯覚が味はへる愉悦に、轆轤首は、それに耽溺する自由に酔ひ痴れる事で、己に閉ぢ籠り、そして、奇妙な事にIT社会では己に閉ぢ籠もれば、閉ぢ籠る程に外部との《接続》が出来る不思議に魅せられて、また、IT社会は尚更「孤」なる事の自由を「現存在」の欲望の赴くままに肥大化される事に為るのは、IT社会の必然と言へるのである。といふのも、現代では、「現存在」の欲望を商品化し、その流通による経済活動で「現存在」の食ひ扶持が得られる仕組みになってゐて、「現存在」が普通に此の世で暮らせば「現存在」の周囲は、己の欲望が商品となった物質で出来た機器といふ名の「現存在」の奴隷で囲まれ、何の事はない、轆轤首と化した「現存在」は動く必然が殆どなくなった故に、己の周りを己の欲望が商品となった《もの》を買ひ貪る事で埋め尽くし、さうして、益益、動く必要がなくなった事により、轆轤首の首ばかりがぐんぐんと伸びるばかりなのであった。
これか現代のブルジョア――現代の労働者は近代のブルジョア以上の生活をしてゐて、また、奴隷、つまり、家電などの機器群に囲まれてゐる故に近代のブルジョア以上のブルジョアに入る――の蓑(みの)虫(むし)化した状況なのである。
それ故に、内部と外部はその境目を失って、渾沌とした世界が出現してゐるのである。此の渾沌とした仮想空間こそが「現存在」の望む世界観の行き着く果てで、それが実現してしまへば、何の事はない、《吾》の消滅と肥大といふ相矛盾する事が一緒くたに起こる無境界化世界の出現で、それは、頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》の或る一部分を極端に肥大化する事で成り立つ仮初の《吾》でしかないが、だからこそ轆轤首と化した「現存在」はその仮初に一瞬花火の如く煌めく《吾》となって、存分に自由を満喫したいに違ひないのだ。その仮初の《吾》の追求こそが、ITによる仮想空間の出現の呼び水に違ひなく、それにいち早く適応したのが轆轤首と化した「現存在」なのである。
さうすると、仮想空間に《接続》しない「現存在」は《接続》出来る「現存在」に蔑まされる事しばしばなのであるが、しかし、その立場は存在論的に見れば、仮想空間に《接続》出来ない「現存在」こそ「まとも」で、仮想空間に《接続》出来る「現存在」は、既に「現存在」に非ず、轆轤首の化け物でしかなく、轆轤首と化した化け物に為る事で「現存在」は、生き物としての進化する《存在》の変態をみすみす逃してゐる《存在》かもしれず、仮に、生物として《存在》の進化を仮想空間に適応する事にすり替へた轆轤首は、飯を喰らひ排泄する以外、全身全霊を仮想空間に《接続》して、歪に肥大化した《五蘊場》ならぬ《四蘊場》に自由を見てしまった浪漫主義者のなれの果てなのかもしれぬのである。
さて、「轆轤首は愉悦なるか?」と、自問自答することらになるのであるが、それに対する私の答へは楽しくもあり虚しくもあるといふ在り来たりの答へでしかないのである。轆轤首に為る事に愉悦がなければ、「現存在」は轆轤首に化ける筈もなく、さて、其処で大いに問題となるのは、己が轆轤首に変態してゐる自覚があるのかどうかであるやうな気がしないではなかった。
仮に己が色の欠落した《四蘊場》において轆轤首であるといふ自覚が全くないとしたとしても、それはそれで別段構はぬのではあるが、しかし、その時の自己同一性は如何様な《もの》なのだらうか? 例へばそれは夢中といふ有様として看做せるに違ひない。それでは夢中なる《吾》とは如何様な《もの》なのか、と、また、自問自答すると、「吾(わ)が心此処に非ず」の状態で、それが仮に読書としてみれば、《吾》は読書により刺激を受けた頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》に、己が構築した架空の《世界》に《吾》は《神》の如くに出現してゐる筈である。読書は当然、「現存在」を本の《世界》へと引き摺り込む《四蘊場》の仮想世界を表出する、つまり、「現存在」は轆轤首となり、それ故に、本の物語世界に《神》の如く出現する事が可能なのは、「現存在」が《五蘊場》を持つ故にである。すると、単純に物事を考へちまふと《神》は、即ち轆轤首の姿に似た何かと言へなくもないのである。「現存在」は《五蘊場》ならば、《神》は「現存在」にとっては千変万化する現実に与した《六蘊場》の主と名指せる《存在》なのかもしれないのである。つまり、「現存在」の《五蘊場》に相当する《もの》が《神》において《世界》といふ現実なのである。
ところが、物事といふのはそんなに単純な訳がなく、世の中で「解かり易い」事は単なる虚構に過ぎず、また、眉唾物で、現実といふあらゆる現象は、皆、複雑怪奇であって、因果律のやうに一見解かったつもりになっている現象は寧ろ数少ないのが現実で、つまり、現実といふ《もの》が複雑怪奇故に「現存在」は愉悦を伴ひながら生き永らへてゐるのかもしれぬのである。
既に、《吾》の《存在》自体が不可解極まりないのである。況して「現存在」が轆轤首へと変容してゐるなどと自覚してゐる「現存在」は殆どゐない、否、私以外ゐないに違ひなく、つまり、私は、「現存在」を、色を欠落した《四蘊場》における轆轤首と名指して一人合点して、己を納得させたいだけなのである。全く莫迦丸出しであるが、しかし、《吾》なる《もの》は、《吾》を《吾》にひれ伏せる事が出来るのであれば、何でもする《存在》な筈である。さうせずにはをれない不安な《存在》が「現存在」で、「現存在」を一皮剝けば、現実に絶えずびくびくしてゐる卑賤な《吾》を見出す筈である。さうして暫く眺めてゐると、その卑賤なる《吾》はひょろひょろと首を伸ばし、色に現実を全て背負はせて、首のみ仮想世界へと飛び立つ現実逃避をし、独り悦に入るのが常なのが観られるに違ひないのである。
さて、それでは、自己とは肯定される為に《存在》するのか、将(はた)又(また)、自己否定する為に《存在》するのかと再び自問自答すると、私の経験からすれば、《吾》とはどう足掻いても自己否定する《存在》としか思へず、然しながら、本音の処では自己肯定したくて堪らないのであるが、実際に自己肯定してみると、お尻がむずむずとこそばゆくて、どうも居心地が悪くて仕方ないのである。そして、一時たりとも自己肯定する《吾》を許せないのであった。これは病的な迄に執拗極まりない私の悪癖に違ひないのであるが、仮令、それが原因で心が病んでも自己否定は止められる筈もなく、思ふに、私は、私に《吾》を殺戮する事によってのみ、私が生き延びてゐるとしか思へない或る意味哀しい《存在》なのであった。そして、その殺害すべき《吾》の一様相が轆轤首なのは間違ひないのである。
実際の処、高度情報化社会で巧く立ち回るには、「現存在」は、否応なく轆轤首に変化しなければ「現存在」失格なのもまた、事実である。それでは、自身を轆轤首であると断言出来るかといふと、多分、誰も己が轆轤首に変化してしまってゐる事は、事実として受け容れ難く、寧ろそれは忌避する事に躍起になる筈である。
そもそも「現存在」は己が轆轤首に変化してゐる事を認める以前に、そんな突拍子もない事を考へる必然性がなく、果たせる哉、「現存在」が轆轤首だらうが、そんな事は「現存在」にとっても知ったこっちゃなく、自身が轆轤首であった処で、
――それが一体どうしたというのかね?
といふ全く無意味な問ひでしかないのが実際の処で、
――「現存在」の異形が仮令轆轤首であったとして、それが「現存在」にとって何か不都合でもあるのかね?
と、大抵の場合、「現存在」が轆轤首である事は、全く「現存在」にとっては無自覚なまま、日常を普通に送ってゐるのであるが、しかし、一度《吾》といふ《もの》に躓いてしまった「現存在」は、それまで「私」と名指してゐた《もの》が《吾》と《異形の吾》との齟齬に懊悩してゐて、その結果として「現存在」はどうあっても《吾》を規定せずば、気が済まない《もの》なのであった。
其処で、私なる《もの》が、《吾》と《異形の吾》との統合であり、私は絶えず《吾》と《異形の吾》とに入れ替はり立ち代はりながら、「私」である事を継続してゐるのである。そして、《吾》と《異形の吾》が自己で括れなくなった刹那に《吾》が轆轤首である奇怪な《吾》を垣間見る事に為るのであるが、大抵は、そんな事に気付かずに、否、目隠しをして、私は《吾》と《異形の吾》の齟齬には立ち入らずに、盲目的に自己肯定するのみで、《吾》の異形が轆轤首である事に知らんぷりを貫き通すのである。
ところが、一度《吾》の異形が轆轤首である事に気付いてしまった私為る《もの》は、既に自己肯定する筈もなく、只管、自己憎悪するばかりが関の山で、さうして私は轆轤首の《異形の吾》を殺害する事ばかりに執着し始めるのである。何故なら私といふ《もの》が私以外の何かである事には一時も我慢がならないのである。つまり、私は《吾》においては徹底的にRacism(差別主義者)で、《異形の吾》は、決して受け容れ難く、常に《吾》は《吾》であるといふ自同律が成立する事に自身の存在根拠を見出し、また、《吾》=《吾》である事の嘘っぱちである事を言挙げする事は永らく禁忌であったのであるが、埴谷雄高が「自同律の不快」と言挙げした事で、《吾》と《異形の吾》の間には 跨ぎ果せない大穴がばっくりと口を開けてゐて、その底無しの奈落に《吾》に踏み迷った《もの》はどうあってもその陥穽に飛び込む衝動に我慢出来ず、結果として次次と飛び込むのである。それはその陥穽に棲む《異形の吾》を殺害する為にあらゆる手練手管を駆使して、轆轤首たる《異形の吾》の首を取って勝鬨を挙げる事ばかり夢想する事による為であるが、その執念たるや凄まじいの一言である。尤も何故に自己憎悪が凄まじい《もの》に為るかと言へば、それは自己愛故のことである。
――奴は敵だ! 敵は殺せ!
この箴言は、私において最も闡明するのである。私は、さて、一日に何人の《異形の吾》を殺害してゐるのであらうかと、自身に問へば、多分、百人は優に超える《異形の吾》を殺害しているのは間違ひなく、しかし、《異形の吾》は《吾》が《存在》する限り不滅で、何度殺されようが何度でも甦り、決して屍となって《吾》の現前に横たはる事はなく、只管《異形の吾》は、《吾》を侮蔑しながら、絶えず自己憎悪へと《吾》の在り処を持って行く、私にぽっかりと開いた陥穽、それを敢へて名付ければ、《パスカルの深淵》に外ならないのである。
ところで《異形の吾》とは、自身が思ひ描く理想の《吾》でしかないといふ見方が出来得るかもしれぬが、《異形の吾》は、そもそも深海生物の如くGrotesqueであり、本性剝き出しの《吾》である。それを《吾》と看做す《吾》は、さて、何を根拠に《吾》と判断してゐるのかを熟考してみると、《吾》がそもそもGrotesqueで、《異形の吾》が《吾》と名乗ってゐるからである。
では、《異形の吾》は対自であるのかといふと、どうも対自では捉へ切れぬ《もの》で、《異形の吾》は、即自と対自との両面を持ってゐて、また、《異形の吾》は脱自すらをも暗示する奇怪な様相を持った《もの》なのである。そして、《異形の吾》の一形態が轆轤首とも言へるのであるが、轆轤首の《吾》には、普通に《吾》を名指してゐる極、普通の《吾》もまた、轆轤首へと変化してゐるので、換言すれば、轆轤首に《吾》が変化するのに何の躊躇ひもなく、即座に《吾》は轆轤首へと変化し、五蘊の色が欠落した仮想空間に脳を接続させて、それからは、伸縮自在の首を持つ轆轤首へと変容するのであった。
さて、ところで、轆轤首へと変容する《吾》とは、しかし、考へてみると、轆轤首の《吾》は、頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》に生滅する表象群と同属の《もの》と考へられなくもないのである。つまり、内的自由と轆轤首の《吾》は同属の《もの》で、成程、轆轤首の《吾》は首が自在に伸縮出来る故に、もしかすると自由かもしれないのであるが、でも、それは仮初の仮象においてさうなのである。ところで仮初の仮象は何かと言ふと、それは生まれては即座に闇の中に消ゆる運命の思考群、若しくは、表象群と言へなくもないのであるが、その生まれては即座に消ゆる運命にある思考群――それはその時の気分に大いに左右されるが――に何処か似てゐなくもなく、ところが、思考といふ《もの》は、深く色たる肉体に根差した《もの》であり、色の欠落した《四蘊場》を自在に行き交ふ轆轤首には徹底して色、つまり、肉体が欠落した妄想群が犇いてゐるのであり、それは、詰まる所、深海生物の妄想がその姿に直結したやうな闇の深部における思考の事を総じて《四蘊場》の表象と看做してしまふと、仮想空間に生滅する《もの》は、色即是空、空即是色に限りなく漸近するかもしれぬ可能性を秘めた何かかもしれず、尤も、仏教徒、若しくは修行者は、肉体を酷使するが、轆轤首においては色たる肉体は単なる四蘊の附属に過ぎす、それを譬へて言へば鮟鱇(あんこう)の雄に過ぎず、また、例へば仮想空間に対して肉体は別段どうでもよく、況して酷使することなどあり得ず、或る意味、轆轤首と化した《異形の吾》において、色たる肉体も含めた《五蘊場》は、自由を満喫してゐると看做せなくもないのである。しかし、轆轤首と化した《異形の吾》には徹底して欠落してゐるのは現実であり、仮想空間には、徹底して諸行無常は欠落し、つまり、仮想空間では更新、上書きされる事は当然の成り行きであり、只管、Digital記号化されたDataが蓄積され、それは何時でも同じ《もの》が参照可能な、極論すれば、まるで、時が停止した世界の一様相を表はしてゐる何かと言っても過言ではないのである。尤も、仮想空間には現実を反映した表象が現はれるが、それは、しかし、仮想空間に出現した途端に徹底して時間為る《もの》を剥奪された去来(こらい)現(げん)の中で絶えず置いてきぼりを食ふ宿命にある現在なる《もの》のみにその価値が収斂されてしまった、永劫に成長することを禁じられた思索の未熟児と言へなくもないのである。
では、去来現の中で現在のみが絶えず置いてきぼりを食ふといふ事態を、文字通り感覚的にでも理解してゐる人は、これまた、私のみなのかもしれないと思ふが、しかし、「現存在」の頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》においては、未来と過去は可変する《もの》で現在のみ絶えず現実に対峙してゐるので、現在のみ不可変な《もの》として、「現存在」は絶えず現在に間断なく投企されてゐる事態に正直な処、「現存在」は絶えず戸惑ってゐるのである。その戸惑ひは絶えず変容する事を強要されてゐる「現存在」の忙しさによるところ大と思はれるが、現在において現実に対峙するしかない「現存在」の《存在》などお構ひなしの現実に対して、「現存在」は己の生存を賭して生存する術を考へられるだけ考へながら現実に対して当意即妙に絶えず変化する現実に対応する事に精一杯なのも、また、「現存在」が置かれてゐる深刻な事態なのである。現実により変容を余儀なくされてゐる「現存在」は、現実により絶えず変容を突き付けられる事により、どうした訳か時間を線直線の如き一次元の連続体として朧に想像してゐるのであるが、此のDigitalで、現在の様態を絶えず蓄積し、Dataとして全て過去化若しくは未来化する事で、尚更、現在においてきぼりを食ふ現在、或るひは、絶えず現在を蓄積してゆくDataにより導き出された現在に対する過去の惰性若しくはDataにより予測される未来から逆算される現在といふ在り方が、それ迄裸一貫で現実に対峙して来た「現存在」に、厖大なDataの網で把捉可能な《もの》として現在を、「現存在」においては制御可能な《もの》といふ幻想を与へる事になったのであるが、しかし、自然の猛威の前ではそんな軟な幻想は木端微塵に砕かれて、再度「現存在」は絶えず激変する遁れやうのない現実に対峙してゐる事を再認識させられたのである。去来現において現在のみが置いてきぼりを食ふのは、「現存在」の生存を賭けた気概なしには「現存在」は現実を生き残れないといふ事態に直面してみると、「現存在」は、生きてゐる事は単に奇蹟でしかなく、その「現存在」を《生》と《死》に分けるのは、もしかすると単なる偶然に過ぎないのではないかと、現実に対して疑惑の目を向けるのであるが、しかし、「現存在」は直ぐにまた、厖大に蓄積されたDataに縛られる事を望んでゐるかの如く外部の仮想現実に脳を《接続》させ、再び、「現存在」は、この期に及んでも轆轤首へと己を変容させる愚行を再び行ふのが、多分、多数の「現存在」の有様なのである。
さて、厖大に蓄積され続けゆく現在と過去のDataに智慧が《存在》するのかと問へば、多くの人は、《存在》する筈だと答へると思ふが、私にはどうしてもさう思へず、智慧は「現存在」が裸一貫で現実に対してどう対応するかでしか生存の智慧は授からないやうな気がしてならないのである。それというのも、「現存在」は、肉体たる色を抛り出して首のみを伸縮自在に伸ばす事で、Dataの洪水たる仮想空間に己の生存の、つまり、己の未来の《存在》を見出す愚行を絶えず行ってゐるのであるが、色を放り出した轆轤首には現実は対峙する《もの》ではなく、単に唯、やり過ごす《もの》でしかなく、仮想空間に自在に首を伸ばして、《吾》の存続する術をその厖大なDataの中から探してゐる轆轤首のその醜悪な姿は、最早何をか況やである。
ところが、厖大に蓄積され続けるDataは、「現存在」の生存に或る示唆を齎す事は、否定する事は出来ず、そのDataは寧ろ否定するのではなく積極的に活用する事で、「現存在」の生存の確率が増すのは、誰も否定出来ない事実である事であるが、しかし、私はその事に或る名状し難い憤懣を覚えるのであった。
さて、その憤懣の因を自身に問ふてみると、ドストエフスキイが観念に憑かれた人間を紙で出来た人間と形容したやうに、時時刻刻と蓄積されゆくDataの活用に憤懣を私が抱くのは、紙でなく、現在はDataのCopy&Pasteで出来た人間に「現存在」が堕す、その《存在》の劣化とも言ふべき《存在》の様相に憤慨するのである。今の世、独創は蔑まされるが、Dataを構造化し、編集する能力に長けていれば尊敬される、何とも奇妙な世の中になったと私は感嘆するのであった。
ところで、仮想空間は、Monitor画面を前にすれば、何《もの》にも「同じ」仮想現実に対峙してゐる事になるのであるが、尤も、仮想空間は本当の現実に対峙してゐるかの如き錯覚を齎すのには誠に優れた装置として機能するので、仮想空間に首を自在に伸ばす轆轤首は、己の情報の発信を仮想空間へ向けて投企し、仮にそれに反応があると胸奥で歓喜の声を上げて、その見知らぬ《他》の轆轤首の返答に応じる事で、仮想快楽と呼ぶべき得も言へぬ快楽に自己陶酔する或る意味《自》と《他》にたいしてふしだらな《存在》が仮想空間には生まれるのである。しかし、それが良いか悪いかを問ふ事は愚行に過ぎず、本当の処、仮想空間において快楽を感じる事などどうでもいい事で、そんな事は各轆轤首が好きなやうにすればいいだけの事であるが、唯、それは蟻地獄の如く一度嵌ったならばもう抜け出せぬ快楽である事は、仮想現実世界への中毒者が《存在》する事からも自明である。
とはいへ、誰もが轆轤首となって仮想空間へと《接続》出来るかと言へば、それは否で、例へばtwitterを例にすれば、それにはBlock機能があり、《吾》はある時一方的に《他》にBlockされて《他》に《絶縁》されるのである。而もBlockされるのはほんの些細な批判をしただけの場合が殆どで、最早さうなると何をか況やである。つまり、仮想空間においてこそ、おどろおどろしい自我が剥き出しになり、其処では絶えずぎすぎすした不安定な関係を生んでは、《他》をBlockする愚行が濫用される事になり、Blockされた轆轤首の《吾》は、内心憤怒してゐるのであるが、此のつれなさこそが仮想空間が仮想である所以であって、轆轤首と化して仮想空間を自在に飛び回ってみた処で、其処に《他》が出現すれば《吾》は《吾》として我執に囚はれる事になり、そして、それは、多分、とても醜い事に違ひなく、我を剥き出した《他》の《存在》を認識する《吾》は、己が色を欠いた轆轤首に過ぎないことを嘆く事になるのである。つまり、《吾》は本心ではBlockした《他》をぶん殴りたいのであるが、如何せん轆轤首の腕なんぞ高が知れてゐて、そのBlockした《他》には遠く及ばぬ故にBlockされたが最後、《吾》はその《他》と永劫に仮想空間では《絶縁》のまま、最早関係が修復されることはないのである。《吾》はさうなると途轍もなく哀しい孤独感を味はふ羽目に陥る場合もあり、《吾》はその胸奥にぽっかりと開いた穴を埋めるべく、別の《他》を物色するのである。でなければ、只管、《他》のtweetをMonitor画面上に垂れ流したまま、《吾》は仮想空間に飛び込むことなく、唯、ぼんやりとMonitorに目をやり、さうして不意に轆轤首である事から落ちこぼれ、金輪際、轆轤首に積極的になる事は最早なくなるのである。
さて、それでは、頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》が《接続》する仮想空間に氾濫するDataといふ名の厖大な情報は、現実といふ《もの》が各人によって様様である事を知らしめ、そして、現実は、そもそも此の世に《存在》する《もの》の数だけあり、と、今更ながらその厖大な情報の氾濫と濫用に戸惑ひつつも、如何なる情報と雖も、それが情報である限り、その情報を受け取る《吾》は、絶えず轆轤首となって情報を喰らひ、生き延びるのであるが、その時の孤独感と言ったならば名状し難き《もの》で、その原因は、厖大なる情報が絶えず更新されゆく仮想空間を前にすると、《吾》が此の世に《存在》せずとも何ら《世界》は変はる事無く、唯、《他》が発信し続ける情報で絶えず満ち溢れ、Monitor画面の前にゐる《吾》の《存在》の虚しさは底無し沼の如き《もの》で、さうして仮想空間を覗き込む轆轤首は絶えず底無しの哀しさを以て吾が《存在》を噛み締める外に、この高度情報化社会では《存在》するのは最早不可能な事に為ってしまったのである。
さて、轆轤首へと変化した《異形の吾》は、また、《吾》にぽっかりと開いた底無しの穴を見つけては覗き込み、恰も轆轤首が逆立ちしたやうな、真に無様な姿の轆轤首に、《吾》はなってしまふのである。《吾》に開いた底無しの穴を《異形の吾》が覗き込むといふ愚行もまた、内的自由の為せる業なのではあるが、その内的自由の行き着く先はといふと、大概、此の世の最後の秘境たる《吾》にぽっかりと開いた《吾》の穴に違ひないのである。さうして《吾》は、《吾》に関して終はる事のない堂堂巡りを繰り返し、その穴を《吾》といふ言葉で名指して、その結果、《吾》は必ず曲解される次第になるのであった。
ところが、轆轤首が、《吾》に開いた底無しの穴を何処までも首を伸ばして覗き込んでも、全く何も見える事無く、唯、漆黒の闇が眼前に拡がるばかりで、その時の私と言へば、何処へもやりやうのないこれまた底無しの虚しさに苛まれる事になるのである。そして、これは、轆轤首の《吾》がその穴を覗き込む以前に既に解かり切ってゐるのであるが、その空虚を骨の髄まで知ってゐるにも拘はらず、轆轤首の《吾》はその《吾》にぽっかりと開いた穴を覗き込みたい欲求を満たしたいが為に欲求の赴くままにその穴を覗き込むのが常なのである。
さて、《吾》が空虚である事は、然しながら、《吾》自身には堪へられない事で、《吾》と呼ぶ《もの》が、何かの《存在》の芯である《もの》として、あってほしいといふ夢想を《吾》は抱くのであるが、事実は《吾》はとことん空虚であるといふ事である。仮想世界に自在に《接続》し、また、自在に首を伸ばし、仮想世界において、解からぬ《もの》などないやうに思はれるのであるが、それは、灯台下暗しで、仮想世界が何処までも拡がりDataが蓄積されようが、決して解からぬままであるのは、何を隠さう轆轤首自体の《吾》なのである。これは、何時もながら轆轤首と化した《吾》を困惑させる因に為り、《吾》に関する事を仮想空間に厖大に蓄積されてゐるDataを探求し、検索をかけるのであるが、Monitorに表はれるのは、《吾》が求めてゐる《もの》とは途轍もなく乖離した《吾》なる《もの》がばかりで、つまり、仮想空間にない《もの》が《吾》なる《もの》なのであって、つまり、それは詰まる所、《吾》にも仮想空間にもぽっかりと底無しの穴が開いてゐて、それを《吾》は、《吾》と名付けて、その穴が暴れぬやうに絶えず監視してゐるのである。
《吾》に対する《吾》は、それが轆轤首であらうが、色ある《五蘊場》の《吾》であらうが、何処かびくびくとしてゐて、腫物に触るやうにして、《吾》は《吾》に対峙してゐるのである。つまり、《吾》とは《吾》の制御が利かぬ一番身近で一番《吾》と乖離してゐる《もの》なのである。《吾》が仮想空間を自在に行き交ひ、時間を仮想空間の中で或る意味浪費してゐるのは、詰まる所、《吾》の正体を見たくないが為なのであるが、しかし、《吾》は好奇心の塊で、どうあっても《吾》なる《もの》を見尽くしたくて仕様がないのも、また、本心で、どうしても《吾》は《吾》の周りをうろつく事になるのである。尤もさうして見出される《吾》は、ぽっかりと開いた穴以外の何《もの》でもなく、轆轤首と化した《吾》は、その《吾》の穴凹へと首を突っ込み、何《もの》もない《吾》といふ《もの》の実体を知って、何時も愕然とするのである。
すると、《吾》の穴からは、
――ぶはっはっはっはっ。
と哄笑する嗤ひ声が聞こえて来て、《吾》は只管戸惑ふのである。すると更に大声で、
――ぶはっはっはっはっ。
と《吾》を嘲笑する嗤ひ声が頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》全体に響き渡るのであった。
私は《吾》にぽっかりと開いた穴を嘗てはその穴を通して虚数の世界が見られるので《零の穴》と呼んでゐたが、現在ではその穴を《パスカルの深淵》と名付けて、その穴の拡大だけは何とか抑へてゐたのであるが、尤も《パスカルの深淵》は日日その深化を深めてゐるやうな気がしなくもなく、その所為もあってか、私の日課として《パスカルの深淵》を探し出し、それが首尾よく見つかれば、その《パスカルの深淵》を覗き込むのであったが、どんなに首を伸ばしても眼前に拡がるは漆黒の闇ばかりで、そして《パスカルの深淵》からは絶えず、
――ぶはっはっはっはっ。
といふ《吾》を嘲弄する嗤ひ声が聞こえてくるのであった。そして、その哄笑がぴたりと已むと今度は、《パスカルの深淵》を一陣の風が吹き抜けて、何とも哀感漂ふ何《もの》かの噎び泣く泣き声のやうな風音が聞こえてくるのであった。
その風音を聞きながら、轆轤首の《吾》が、その《パスカルの深淵》に首尾よく辿り着ければ運よく《パスカルの深淵》の正体を見つけ出し、其処に首を突っ込むといふ行為を行はずにはゐられぬのであっが、その行為は途轍もなく虚しく、その虚しさは名状し難い《もの》であったが、しかし、《存在》に憑りつかれてしまった《もの》はそれが何であれ、《吾》の在処を闡明し、多分にGrotesqueな姿形をしてゐるに違ひない《吾》なる《もの》の正体を白日の下に晒すといふ《吾》にとっても《他》にとっても迷惑千万な恥辱に満ちた愚劣極まりない行為をせずには、《吾》は《吾》に対してその《存在》に一時も我慢がならず、遂には、《吾》は《吾》を呪ふのである。さうして、《吾》は《吾》から少しでも遁れるやうにして色の欠いた《四蘊場》の仮想空間に《接続》し、《吾》を抛り出した轆轤首になるといふ何とも奇妙な離れ業を身に付け、轆轤首の《吾》には《吾》は無しといふ奇妙奇天烈な事象を断行するのである。
ところが、《吾》なる《もの》は、奇妙な引力がある《もの》で、厖大なDataが時時刻刻と蓄積されゆく仮想空間へと首を伸ばし轆轤首と化した《吾》の首は、或る閾値に達するとぐっと《吾》に引っ張られて、すとんと首が元の処に収まるのであった。つまり、《吾》とは、結局の所、《吾》から遁れ出られぬ極極当たり前の結論に為るのであるが、それはBlack hole顔負けの事象の地平線が《存在》する《もの》なのであった。
《吾》の事象の地平線を例へば《吾閾》と名付けると、《吾閾》の中において《吾》の出現は、全て同等な《もの》、つまり、確率的に同じといふ事なので、《吾》は《吾閾》においては何処においても同等に出現可能で、それはハイゼンベルクの不確定性原理の如く、《吾》の在処は最早確率でしか語れず、また、太陽の黒点の如き《パスカルの深淵》が《吾閾》の何処かでばっくりと口を開けると、《吾》はその《パスカルの深淵》に纏はり付く確率が高くなり、そして、《吾》はその《パスカルの深淵》を覗き込みたい衝動には抗へず、首尾よく見つけ出された《パスカルの深淵》に首を突っ込んでは、
――《吾》、未確認。
といふ徒労を繰り返すのである。仮想空間に何時でも《接続》可能になった轆轤首の《吾》の出現が、尚更、《吾》の正体を見難くし、また、弾幕を張って轆轤首の《吾》には、時折、《パスカルの深淵》の在処すら隠すやうになり、《吾》は、何処からか発するのか解からぬ《吾》といふ強力な引力に絶えず引っ張られながら、不明なる《吾》を探す徒労に茫然としてゐるのである。ところが、《パスカルの深淵》からは絶えず《存在》が噎び泣くやうな風音と共に《吾》を嘲る、
――ぶはっはっはっはっ。
といふ哄笑が聞こえて来て、《吾》が《吾》から遁れる事を絶えず断念する密約が《吾》の与り知らぬ処で《存在》と結ばれてゐるのか、轆轤首と化して《吾》からの自由なる飛翔を夢見るそんな《吾》は、しかし、《吾閾》からは一歩も出られない哀れな《存在》なのであった。そして、《吾》なる《もの》は最早、《吾》と名指し出来るやうには《存在》せず、絶えず確率論的に《吾》は曖昧にしか《存在》しないのであった。
つまり、《吾》なる《もの》は、《吾》以外の《他》に《存在》する確率は決して零であった事はなく、それは、詰まる所、《吾》が《吾》であるのは確率何パーセントとして、そして、《吾》が《他》であるのもまた、確率何パーセントとして語られるべき《もの》に違ひないのである。
それ故に、《吾》にぽっかりと穴が開いた《パスカルの深淵》が《吾》に《存在》するのは当然の事で、《吾》が《吾》として確率《一》でない限りは、《吾》には虚しき穴凹が《存在》するのが自然の道理といふ事である。
《吾》の在処が《吾閾》にあるとするならば、《吾閾》は零次元、つまり、点としても、一次元、つまり、線としても、二次元、つまり、面としても、三次元、つまり、立体的な何かとしても、四次元、つまり、《吾閾》が四次元多様体としても、更にこのやうな事を蜿蜒と続ければ、∞次元まで考へる事は可能で、それは《吾》が表象と呼ばれる何かであるといふ事は、表象は、例へば、∞次元の何かであると言へなくもないのである。
《吾》が《吾閾》の中でのみ轆轤首であり得ると仮定してみると、厖大なDataが蓄積される仮想空間に《吾》が均等に《存在》する可能性は零である筈はなく、つまり、仮想空間の何処でも轆轤首の《吾》が《存在》する可能性は確率零でなく、否、《吾》なる《もの》は、《吾閾》に均等に《存在》する《もの》であり、更に、轆轤首が仮想空間に何時でも《接続》可能なのは、《吾》が仮想空間に何時でも《存在》してゐる可能性を暗示してゐるとも考へられ、さて、さうなると、《吾》は《吾閾》以外の何処にも或るひは《存在》可能な何かと想定する事も可能と言へるのである。
すると、《吾》は此の世の何処にも《存在》すると仮定出来なくもなく、《吾》は、仮想空間に轆轤首として《存在》するばかりでなく、此の現実の《世界》にも、それは限りなく零に近いとはいへ、しかし、《吾》は、確率が零に為る事は《神》すらも断言出来ぬやうに此の《世界》の《吾》以外の何処にかにも《存在》する《もの》としてあると考へられなくもないのである。
Cogito,ergo sum.が、もしかすると《吾》を《吾》なる《もの》へと封じてしまった元凶であったかもしれず、東洋では極当たり前の《気》といふ《もの》は、《吾》が《吾》以外の此の世の何処かに《存在》可能な事を言ひ表はしてゐる一つの世界認識の仕方に違ひなく、多分、《吾》が《吾》に封じ込めらた事は、全宇宙史を通しても現在程過酷に《吾》の身の上に《存在》した事はなく、つまり、この事を極論すれば、シュレディンガーの波動方程式により《吾》も《他》も此の世の何処にも遍く《存在》可能な《もの》なのかもしれないと考へた方がどうやら自然の道理のやうな気がしないでもないのである。
さうすると、《吾》も《他》も、或る時は《吾》や《他》には《存在》せず、何処とも言へぬ神出鬼没な《もの》として、此の世に遍く《存在》する可能性の確率は決して零ではなく、換言すれば、《吾》を語るには此の世を遍く語る事に等しき事で、つまり、《吾》の理解とは即ち、此の宇宙を理解する事に等しいに違ひないとも言へるのである。
ところで、《吾》が《吾》である、例へばそれを《絶対吾》と名付ければ、その《絶対吾》が《吾閾》に確率《一》で《存在》しないのかと自問すれば、既に《吾》が轆轤首となって仮想空間に《接続》し、仮想空間を自在に行き交ふ《吾》といふ《もの》を知ってしまった《吾》において、《絶対吾》なる《もの》の《存在》は一笑に付すべき《もの》で、《吾》は彼方にゐたかと思へば此方にゐるといった此の世に遍く《存在》可能な恰も忍者の如き《もの》として此の世にあり、それ故に《吾》は《吾》にぽっかりと開いた穴凹を見ては、《吾》は《吾》に踏み迷ふのである。さうすると、《吾》に関して《吾》を「こやつが《吾》だ」とは最早名指せぬやうに為り下がった《吾》は、既に渾沌に投げ込まれてゐて、その《吾》を《他=吾》と名付ければ、その反語のやうなその言ひ回しの《他=吾》として《吾》は、既に此の世に《存在》してしまってゐると確率論的に考へた方が自然とも言へるのである。
さて、先ずは、《他=吾》とは、此の世に《存在》する《吾》と《他》との間を巧く取り持つ潤滑油の如き《もの》とも考へられなくもなく、《吾》に《他=吾》が《存在》するといふ事は、《吾》は《他》へと想像力を以て《他》の有様に思ひを馳せて、《他》もまた《吾》と同様に《吾》にぽっかりと穴を開けた《パスカルの深淵》に恐怖し、それ故に《吾》は《パスカルの深淵》を覗き込む欲望に打ち勝ち難い事は、《他》にとてっても同様の欲望と看做すの事が可能である。
つまり、それは《吾》と《他》は《存在》に対しては同志であると看做せ、《吾》が確率《一》としては此の世に《存在》する事はあり得ない事象である事から、《吾》は元来、《他》に浸食された《存在》として「先験的」に強要された《もの》以外の何《もの》でもないのである。
それでは、《吾》にぽっかりと開いた穴凹たる《パスカルの深淵》が《吾》における《他》と看做せるかと問へば、それは本能的に違ふと《吾》は感じ取り、《吾》に《存在》する《パスカルの深淵》にこそ、《吾》のGrotesqueな本質が隠されてゐて、その代はり《他=吾》はサルトルがさう呼んだ対自に近しい何かであって、《他=吾》は、万物共通の己に巣食ふ《吾》の一様相であり、《他=吾》は《存在》が《存在》足らしめてゐる万物共通の《吾》の一面相と看做すと、《存在》が《存在》を認めるのは、如何なる《存在》にも《他》を類推する《他=吾》が確かに《存在》する外に、《吾》は《他》と対峙し、そして《他》と解かり合へる《もの》ではないのである。
では、《吾》にぽっかりと開いた《パスカルの深淵》は何なのかと問へば、《吾》が例へば生き物を例として取り上げれば、たった一つの受精卵から、細胞分裂を繰り返す、その時の《吾》たる一細胞が不意に分裂して二つの《吾》といふ細胞が生じる時の奇妙さに深く根差した不安とも名状し難い《吾》のみぞ知る《吾》なる《もの》の不気味さに外ならないのである。
しかし、その細胞分裂は、生き物であれば、如何なる生き物も経験してゐる筈で、それこそが《他=吾》で、細胞分裂の奇妙で不気味な感覚を共有する事でお互ひにその《存在》を認めると想定したい処であるが、しかし、たった一つの受精卵は将に此の世にたった一つしか《存在》しない受精卵、換言すれば、いづれも遺伝子が異なる故に、その此の世に二つと《存在》しない受精卵が不意に細胞分裂をする時の奇妙で不気味な感触は、只管、《吾》は、最初に二つの分裂した細胞を跨ぎ果し、次に、四つに分裂すれば、《吾》は四つの細胞を跨ぎ果す何かであって、それは、徹頭徹尾《吾》にしか知り得ない《もの》で、また、《パスカルの深淵》の淵源を辿れば、この細胞分裂する《吾》といふ細胞の奇妙で不気味な処へと辿り着く筈で、其処では、五蘊の中でも色の最も大きな影響下にある筈である。その時には色を欠いた《四蘊場》の仮想空間に自在に《接続》する轆轤首の《吾》における《パスカルの深淵》のやうな《吾》にぽっかりと開いた陥穽は全く《存在》せず、詰まる所、《吾》の本質に深く関係する《パスカルの深淵》が如何なる生き物も含有してゐる為に、己の《存在》の不可思議で尊ひ《もの》である自覚がそれ故に芽生えるに違ひなく、尤も《パスカルの深淵》を含有する《吾》の皮相な部分では、《吾》は《他》と連帯し得るが、《吾》が《他》と連帯する最たる《もの》は、《パスカルの深淵》の共有ではなく、《吾》に必ず《存在》が確立零でなく《存在》する対自たる《他=吾》が《吾》に必ず侵食してゐる事を通しての事に違ひないのである。
それでは、《パスカルの深淵》は《他》においては《存在》しないのかと問へばその答へは、
――否。
な筈である。それは共同幻想と言ってしまへば身も蓋もない事なのかもしれぬが、《パスカルの深淵》と言ふだけで、既に此の世には誰の目にも見えてしまふ底無しの深淵があるといふ感覚を払拭出来ぬ筈で、つまり、誰も《吾》を特定出来ぬままに此の世に《存在》してゐる証左こそが、《パスカルの深淵》の有無に違ひないのである。
当然、
――俺には《パスカルの深淵》なんてありゃしないぜ。
といふ《もの》の方がもしかすると圧倒的な数かもしれぬとはいへ、さういふ《もの》共も《吾》に関して百パーセント知ってゐるかと問はれれば、必ず、
――否。
と答へるしかない筈なのである。
さて、其処で《吾》は殆どの場合、不意に《吾》に現はれた《パスカルの深淵》に落っこちるのが落ちで、目を閉ぢれば瞼裡の薄っぺらな闇ですら涯なき闇へと通じてゐるかの如き錯覚に無限を重ねてみるのであるが、瞼裡の闇が、頭蓋内の闇と直結してゐる事を不意に思ひ出しては、《パスカルの深淵》といふ言葉に無限を対峙する《吾》といふ、《パスカルの深淵》に落っこちて、闇しか見えない《吾》を象る事になるのであるのである。さうして、象られた《吾》の姿形は、《吾》を満足させる事は一度たりともなく、況してや、さうして象られた《吾》が轆轤首では尚の事、自己嫌悪のみを《吾》に齎すのみなのである。
ところで、此の世の森羅万象が、皆、《パスカルの深淵》を目撃し、そして、《パスカルの深淵》に落っこちて轆轤首へと変態してゐるのかと問ふと、それは、多分、さうに違ひないと答へるのが正直な回答に違ひないのである。つまり、《存在》が《吾》を認識する《もの》として此の世に出現した時点で、その《存在》には瞼が必ずある筈で、例へば如何なる《存在》も仮象の目を持ち、仮象の瞼があると仮定すれば、闇の《存在》をどうあっても知ってしまってゐる此の世の森羅万象は、「先験的」に《パスカルの深淵》に落っこちてゐる《存在》として此の世に起つのである。
ところが、それに対して、
――そんな事は一概に言へないぜ。
といふ半畳が飛んで来るに違ひないのであるが、しかし、《存在》といふ《もの》に思ひを馳せると、どうしても闇とか無限とか、《吾》とは無関係な《もの》と対峙させつつ、何とか《存在》ににじり寄る愚直な思考法しか知らない《吾》は、とにかく、《存在》といふ言葉に翻弄される事で、何となく《存在》に近づいたなどと錯覚しながら、絶えず《吾》は《吾》に踏み迷ひ、さて、困った事に《吾》の事象の地平線たる《吾閾》が将に《パスカルの深淵》とぴたりと重なったとする虚妄に一度は、
――Eureka!
と歓喜するのであるが、それをよくよく見れば、首ばかりが伸びる轆轤首である事が解かると、何《もの》も驚愕の声を上げて、
――《吾》は何処?
と、再び《吾》に踏み迷ひ、《吾》は《吾》の内外に《存在》する《パスカルの深淵》の底無しに今一度嘆きながら、その底無しの《パスカルの深淵》に落っこちて、果てしなく自由落下をしつつ、《吾》は尚更、首ばかりを伸ばしては漸く此の世に顔を出して息継ぎをし、さうして仮初に《パスカルの深淵》を忘却する仮想空間における快楽装置でしかない轆轤首へと変態する《存在》以上の何《もの》にもなれやしないのであった。
成程、《パスカルの深淵》へと自由落下が、《吾》に湧き起こる快楽の発生装置である事は、何時頃からか《パスカルの深淵》を自らの棲処にしてしまった《吾》にとって疑ふ余地がないやうに思へ、その《吾》はといふと《パスカルの深淵》を自由落下してゐて、しかし、当の《吾》は、己が落下してゐるとは全く露知らず、《吾》はといふと、《パスカルの深淵》で自在に飛翔してゐる自在感に自己陶酔してゐるのである。つまり、《吾》は《吾》から遁れられるかもしれぬといふ幻想を思ひ抱きながら、《吾》における《吾》の裂け目にぱっくりと口を開けてゐる《パスカルの深淵》に逃げ込んだのである。それ程に《吾》は存在論的に追ひ込まれた状況にあった事をこれは示してゐて、ところが、《パスカルの深淵》へと逃げ込んだ《吾》は、最悪の事態を《吾》に齎す事には《吾》は思ひ及ばず、《パスカルの深淵》を自由落下する《吾》にとって、自由落下が齎す自在感こそ《吾》が《世界》を見誤る元凶なのである。
《吾》に芽生えてしまった自在感は、得てして《吾》を傲岸不遜な《存在》へと変貌させる契機になりかねず、ひと度自己の《存在》を全面的に肯定してしまった《吾》といふ《存在》は、此の世の王の如く《世界》の中心は、《吾》である錯覚の中で自滅するのが関の山で、また、《パスカルの深淵》へと逃げ込んだ《吾》は、《世界》もまた《パスカルの深淵》でしかない事に気付く筈もなく、《パスカルの深淵》へ逃げ込んだ《吾》の《世界》は永劫に続く入れ子構造をした《世界》を《吾》には、さうとは全く気付く事なく、《吾》に無限といふ名の幻影を見させ、その事で、《吾》は無限と対峙してゐるといふ全くの錯覚でしかない《吾》の有様の誤謬に《吾》を閉ぢ籠め、結局の所、《パスカルの深淵》へと已む無く逃げ込まざるを得なかった《吾》は、《吾》以外の《もの》からすっかりと遮断されてゐるので、《パスカルの深淵》に逃げ込んだ《吾》は、大概、自己の事しか考へられずに、《吾》に《他=吾》なる《吾》には何の事か解からぬ奇妙な《もの》が棲み付いてゐる事に、生涯思ひ至る事無く、換言すれば、《世界》との和解の機会が未来永劫訪れる事無く、尤も《パスカルの深淵》に逃げ込んだ《吾》の世界観はといふと、《吾》を中心とした同心円状の世界観に陥る事で、現実を見る苦痛から生涯遁れる秘密を知ったかの如く素っ頓狂な世界観に奇妙にも満足出来る《存在》に為り果てて、詰まる所、《パスカルの深淵》に遁れた《吾》は、あらゆる事が、誤謬の中にある事に生涯気付く事無く、夢の如き《生》を生きるのである。其処には、一度たりとも現実が顔を出す事無く現実は悉く隠蔽されるのである。つまり、《パスカルの深淵》では因果律が壊れてゐるのである。
現実が隠蔽された自己完結型の奇妙な《世界》から這ひ出る事も無く、只管、《吾》にのみ向き合ふだけの或る意味幸せな、しかし、とんでもなく不幸な世界観の中で自己と戯れる《吾》は、其処に《他》を全て隠蔽するので、《吾》は、自己観想する事で、何重にも折り重なった蛇腹状の《吾》の心地良さにうっとりしながら、生涯その夢の《世界》から這ひ出る事無く、つまり、現実を絶えず見失しなひながら、《吾》において《吾》が自存する大莫迦者が出現する事になるのである。
現実に、生涯一度も出合はない《生》の不幸は、言はずもがなであるが、しかし、《吾》の性質として、現実を隠蔽するのは至極当然の事であって、それであるが故に尚更、《吾》は《他》が無数に《存在》する現実に対して目をかっと見開かなければ、決して《吾》なる《存在》を把捉する事は不可能なのである。
さて、遺伝子Level(レベル)で、例へば人間Aと人間Bの遺伝子の違ひを比べれば、AとBの遺伝子はほぼ同じで、その違ひは一パーセントには遙かに満たない違ひでしかなく、AとBを違った《存在》として隔ててゐるのは、遺伝子Levelでは、何箇所かの遺伝子の配列が極僅か違ふ事でしかないのである。更に言へば、人間Aと人間Bの七割程は《水》であり、其処には、つまり、《水》に関しては何の違ひもなく、生物とは、極論すればAmino酸などの不純物が混じった《水》と看做せなくもないのである。つまり、《吾》と《他》を隔ててゐる《もの》は、生き物の組成物質で見ると、同等と看做せる程にそこには何ら違ひが《存在》せず、《吾》は「先験的」に《存在》する以前の未出現の時点で、《他》と組成を同じくした《もの》として此の世に出現する事を宿命付けられ、換言すれば、《吾》の殆どは、《他》で出来てゐると看做せる筈で、さうすると、《他=吾》といふのは言ひ得て妙な《もの》で、九十九パーセント以上は同じである《吾》と《他》の違ひは、しかし、絶望的に断絶してゐるのである。《吾》にとって《他》は、《異形の吾》の《存在》の様相の一つの解であり、また、《吾》とは無限に違った、《吾》を超越した《存在》として現実には《存在》するのである。つまり、《吾》にとっての《他》は、此の世の涯の一つの表象なのである。また、《他》をその様に解釈しておかないと《吾》は、生涯安寧を得られぬ事となり、つまり、《吾》は、《吾》が《吾》である為の時空が、即ち《個時空》といふ《もの》が生存する為には必須な《もの》として浮き彫りになるのである。
此処で言ふ《個時空》とは、此の大宇宙に大渦を巻く大きな大きな大きな大渦巻きの時空間の表層部に、小さな小さな小さな時空のカルマン渦が不意に生じたそのカルマン渦を《個時空》と名付け、《吾》の寿命はその小さな時空のカルマン渦たる《個時空》が茫漠とした大宇宙の大河の如き時空の大渦の上に不意に現はれ、そしてその《個時空》が消ゆるまでの事で、実際、例へば人体を例にすれば、人体には、渦状の形をした《もの》がそれとなく幾つも見つかる筈で、《吾》は極論すれば、此の宇宙に《存在》するカルマン渦なのである。そして、多分であるが、《存在》が思考するとは、頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》に、渦が発生してゐる事に違ひなく、例へば「頭の回転が速い」などといふ言ひ方が既に《存在》してゐる事からも、強(あなが)ち思考が《五蘊場》内の渦といふ捉へ方は、奇妙な《もの》ではなく、寧ろ自然な思考の把捉の仕方に違ひないのである。
cogito,ergo sum.が渦の或る一つの事象に過ぎないとしたならば、渦の解析が此の世を理解する一つの方法であると言ひ得、つまり、素粒子、頭蓋内の闇たる脳の構造をした《五蘊場》、そして、Black holeが不思議と何やら同根の《もの》として見えてくるのであり、これら三つに共通してゐる《もの》の一つにSpinがあり、つまりはそれは渦を暗示してゐなくもないのである。
ところが渦は、現時点ではストークスの定理によって、回転が直線に変換可能な事を記述してはいるが、然しながら、渦全体を物理学者がよく口にする「美しい」方程式で記述出来ぬままなのもまた事実で、その外にガウスの定理などなど、此の世の秘密たる渦へと肉迫するには物理数学は未だ道半ばと言へなくもないのである。
さうすると、仮想空間に《接続》した「現存在」が轆轤首の《異形の吾》へと変化してゐる様は、蜷局(とぐろ)を巻いてゐる大蛇にも似て、首をぐるぐると巻く事で、仮想空間の中での自在感を味はってゐる筈で、仮想空間にもまた、時空のカルマン渦が《存在》するのは間違ひなく、成程、Televisionでは字幕が右から左に流れる、つまり、左に回転してゐると看做せ、仮想空間、例へばPersonal computerではMouse(マウス)や手の動きで画面が動く様を見れば、それらは、画面が回転して渦を巻いてゐる証左の一つと看做せるのである。
大渦の上に浮かぶ小さなカルマン渦の《個時空》を鳥瞰したならば、孔雀の雄がその美麗な羽を大きく拡げた如くに見えるに違ひないのである。そして、それが神の性癖の一つに外ならいと思はずにはゐられぬのである。
――自然は自然を真似る。
つまり、自然は、Fractalな《もの》なのである。
――本当にさう言ひ切れるのかね?
と、自嘲する《異形の吾》の声が何処からか聞こえて来さうだが、此の世は多分、渦の入れ子構造をした《もの》として看做せるに違ひなく、渦のFractalとして現前するこの《世界》は、私にとっては超弦理論ならぬ超渦理論と呼ぶべき《もの》として、此の世が私に現前するのである。
――でも、渦である根拠はないんぢゃないのかね?
と、これまた《異形の吾》の半畳が飛んで来るが、私は、其処で、
――科学が常に正解ではない。
と、にたりと嗤ってゐる《異形の吾》に対し私は反論し、然しながら、此の世が渦のFractalである根拠が何もない事は《吾》ながら熟知してゐるので、超渦理論などと大袈裟に呼んではゐるが、それは、詰まる所、勘の域を出ない代物に外ならないのである。
ところで電車に乗ってゐる時にそれは窓外によく見える事象なのであるが、この世の中を物理的に動く《吾》の外界は、無限遠を仮初の中心とした大渦を《吾》の左右に巻いてゐる事に気付く筈である。つまり、距離=過去、若しくは距離=未来と、距離が時間に還元可能な事は物理学の、而もニュートン物理学の基本を知ってゐれば、何ら不思議な事はなく、距離が過去であり未来である二相であるといふのは、例へば距離ある故に過去である外界の《世界》において、《吾》は行くべき目的地を見出すと、現在地から目的地は距離がある、即ち過去である筈の《もの》が、それが未来に到達すべき目的地が見出された刹那、それまで過去であった外界は未来へと反転するのである。これはほんの一例に過ぎぬが、頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》を《吾》の内部、つまり、吾から距離がMinus(マイナス)である故に未来と強引に看做してしまふと、成程、《五蘊場》に明滅する表象群は、因果律が壊れた《もの》として《五蘊場》に生じてゐて、《五蘊場》において、過去の記憶が未来に到達すべき《吾》の姿である事は珍しい事などではなく、寧ろ当たり前で、更に言へば、《五蘊場》において、過去も現在も未来も同相の《もの》に外ならず、仮に《五蘊場》に《吾》が理想としてゐる《異形の吾》が《存在》してゐれば、その理想の《異形の吾》は、去来現を貫き、どの時制においても《存在》し、そして、それは、未来の時制を多分に多く含んだ《存在》として《吾》に対して《存在》してゐるのである。
しかし、その理想の《吾》、即ち《異形の吾》をよくよく観想すれば、全てが曖昧模糊とした《もの》で出来上がってゐて、その理想の《吾》とは、詰まる所、思惟が輻輳しただけの《異形》の《もの》として、《吾》に対して《存在》してゐる事が暴露され、《吾》はその時、
――ちぇっ。
と舌打ちし、その理想の《吾》を否定しかかるのであるが、ひと度《五蘊場》に現はれてしまった理想の《吾》は、《異形の吾》と結託して《吾》をのっぴきならぬ処へと追ひ詰めるのである。
そのやうに理想を掲げる事とは誠に息苦しい事なのである。しかし、さうだからこそ、《吾》は此の世で生きるに値し、さうして何時の日かその理想でもある《異形の吾》を一呑みで呑み込む事を想像しながら、轆轤首として鶴首するのを常とするのである。
さて、《異形の吾》を一呑みで呑み込む事を想像しながら鶴首してゐる《吾》は、当然の事、仮想空間に《接続》してゐて、仮想空間に、もしかしたならば、《吾》が理想とする《異形の吾》がゐるのではないかとその痕跡を探し回るのであるが、例へばWEB上で自分の名で検索をかけてみると、其処には「私」を愚弄した検索結果しか見当たらず、しかし、それは未だましで、仮に自分の名で検索をかけて検索結果が《存在》するのはまだよい方で、多くの《吾》は仮想空間に自分の名すら《存在》しない事に安心する一方で、がっかりもするのである。
しかし、そんな事は、はっきり言へば、どうでもいい事で、仮想空間に次第に入り浸りするやうになると、其処は何時しか《吾》の嗜好に合った《もの》ばかりのWEB頁のみを見てゐるのみで、つまり、《吾》は仮想空間に《接続》するのは、其処に《吾》を開いて《他》を発見するのではなく、同属の《もの》に囲まれ閉ぢ籠る為に《吾》は仮想空間に《接続》するやうに為り下がるのである。
《吾》の本質は籠る事である。籠る事が本質故に、《吾》は轆轤首へと変態するのである。それは、尤も《吾》が納得出来る《もの》を仮想空間に籠る事で《吾》の隠れ家として探してはゐるのであるが、つまり、《吾》が《吾》である事を支へて呉れる文言なり方程式なりを其処に見出したいのが山山で、しかし、それらは、その文言を表白した《存在》の《もの》であって、《吾》はその《他》が表白した徹頭徹尾《他》に属する文言や方程式なりに己の思ひを一方的に重ね合はせる事で、《吾》が此の世に独りではないと思ひ込みたくて仕方がないのである。
つまり、《吾》は《個時空》といふ宿命を死ぬまで受け入れられぬのである。
さて、其処で、《吾》は《個時空》といふ宿命にありながらも、《吾》には自由はあるかと問ふてみると、此の世の森羅万象は「然り」と答へたい筈であるが、しかし、それは希望的観測に過ぎず、《吾》が《死》より遁れられぬ以上、《吾》には自由はほぼないといふのが真実に違ひないのである。
――しかし、生きてゐる、または、《存在》してゐる内には、自由はある筈さ。
と、反論が返ってくるに違ひないが、極論すれば、そんな自由は本当に自由と言へるのか大いに疑問の余地が残るのである。つまり、誕生も《死》をも自由選択出来ぬ《もの》に、自由があるのかといふ事である。但し、自殺は例外である。
――しかし、森羅万象は《存在》してゐるではないか? つまり、《存在》してゐる間は、《吾》は自由ではないのか?
と、再び反論が返ってくるに違ひないのであるが、《存在》は《存在》において既に呪縛されてゐるといふのが、実際の処であらう。つまり、《存在》は、何としても《存在》する事を《吾》に課し、《世界》に適応する事を強要され、仮に此の世に《神》が《存在》するならば、《存在》にあたふたする《吾》を見ては、哄笑してゐるに違ひないのである。
《神》とは、残虐な《もの》である。だから、《吾》は苦し紛れに轆轤首に為らざるを得ぬのである。《吾》は轆轤首に変態する事で、《神》からその姿を隠し、さうして、もしかすると、此の世にあるかもしれぬ自由なる《もの》を渇望しながら、《生》を《神》から略奪して《吾》の《もの》へと取り返す事をして、自由を恰も此の世に《存在》する如くに振舞ひ、そして、《吾》は《吾》に底無しに幻滅するのである。そして、その幻滅出来る事が、自由だと確信し、さうして《吾》は、
―ふっ。
と自嘲するのである。
或る在処に《吾》の閉ぢ籠る《場》を見つけた《吾》は、己の嗜好に合った《もの》で埋め尽くし、気が付けば《吾》は全く身動きが取れず、更に己の嗜好に合ったものばかりを集め、どうあっても《吾》は、現代においては、仮想空間に《接続》可能な場合、轆轤首に変態するのは、実存の正しい在り方である。さうまでして、《吾》は、此の《吾》の拡張とも見える仮想空間の拡がりの中では、轆轤首として生き延びる事を、何の迷ひもなく、自ら選択するのである。これは、或る種の穴居動物と何ら変はらぬ事態の到来を意味してゐるのであるが、果たして、《吾》が轆轤首に変態する事で、《吾》に何を齎したのであらうか、と自問自答すると、其処には、現実に対する「現存在」の怯えが反映されてゐて、「現存在」は、絶えず現在に留め置かれる故に、否が応でも独りで現実に対峙しなければならぬ事は、自明の理なのであるが、何時までも煮え切らない「現存在」の身近な現実からは、目を遠ざけ、なるべく《吾》と無関係な現実に目を逸らす為に、《吾》は轆轤首へと変態するのは必然なのである。
さて、轆轤首の自在感は、《吾》を魅了して已まないのである。何時でも何処でも首さへ伸ばせば、己の求める欲求を果たすべく、仮想空間に溺れる事で、轆轤首へと変態した《吾》は、必ず自ら求める欲求の捌け口を見出し、その出会ひにより、轆轤首の《吾》は、束の間の満足を味はひ、そしてその積み重ねが、《吾》に万能感を齎し、《吾》は閉ぢ籠った故に現実に対してもその万能が揮へると勘違ひして、大概、《吾》が対峙する現実には悉く撥ね返され、《吾》は、さうして己のちっぽけさを厭といふほど味はひ、再び《吾》は、己の嗜好のみで築かれた「城」に籠城し、首のみをびくびくと伸ばして、再び仮想空間へと《接続》し《吾》の仮初の拡張を味はふ快楽に溺れるのである。
さて、轆轤首と化した《吾》には、自由があるのか、と再び自問自答すると、己が自由であると錯覚する為に、仮想空間で首を伸ばした轆轤首に為り下がってゐるといふのが実際の処だらう。つまり、《吾》は轆轤首に為るのは、既に惰性に為ってゐて、少しでも現実から目を逸らせば、それが退屈であらうが、《吾》は、穴居動物として首ばかり伸ばして、《吾》が伸びた首に相当する《吾》へと拡張したかのやうな錯覚に溺れる事で、意識の拡張が恰も実現したかのやうに《意識=存在》の実現の時代が到来したその勘違ひの中で、「現存在」は、前世代よりも虚しく死んでゆくのである。
――それは本当かね? 現代を生きる「現存在」は前世代の「現存在」よりも虚しいかね?
と、これまた反論が返ってくるに違ひないが、しかし、仮想現実の登場により個人で情報を発信出来る時代が到来した上に、《吾》は万能で、《意識=存在》が実現した錯覚に誰もが欺かれてゐるのである。
しかし、個人で確かに情報を発信出来るがその情報が多くの人の興味に適はなければ、その情報は殆ど誰にも見向きもされずにあるのであるが、仮想空間での有名無名の残酷な格差は、現実以上で、無名の《もの》の情報など誰の興味も引かずに抛ったらかしにされてゐて、誰も無名の情報など必要としてをらず、それでも誰かが見るかもしれないといふ希望なしのままに情報を発信し続ける忍耐に、無名の《もの》は堪え忍んでゐるのである。轆轤首と化して仮想空間を自在に行き交ふ事が可能となったとはいへ、無名の「現存在」は有名な《もの》の情報発信を追跡する事で、時間の大半を費やしてゐるのが現実なのである。この情報発信における絶望的な格差は、さて、解消されるのかと問へば、有名な《もの》が無名な《もの》の発信した情報を無名の《もの》の名前入りで汲み取る事でその絶望的な格差は多少和らぐかもしれぬのである。しかし、それでも有名無名の絶望的な情報発信に関しての格差は解消される事はなく、仮に無名の《もの》が有名な《もの》になる場合は、時代に媚びた言説をする以外に有名への道は残されてゐないのである。
さて、それでは、時代に媚びた言説とは何かと問へば、既存の現実を真の現実として何の疑ひを持たずに絶対の信頼を置き、それは、例へばドストエフスキイ曰く『魂のRealism(リアリズム)』が全く含有されずに出来上がった言語世界の事で、既存の現実、つまり、《世界》に対しては反旗を翻さぬ《もの》のみしか《存在》しない言語で表出された《世界》を、絶対的な地位に祀り上げられた言語世界の事と言へるかもしれぬのである。つまり、《世界》はそれらの言説においては、繰り返しになるが《世界》は既存の《もの》でしかなく、その《世界》に対して何の疑問も抱かぬ無邪気な《存在》ばかりが蠢く《世界》を何の躊躇ひもなく受け容れた場合は、全て、現実に媚びた言説により構築される言語世界に為らざるを得ぬのである。
自己に、つまり、《吾》に対して不信の念を抱いた《吾》は、同時に《世界》に対しても、つまり、現実に対しても不信の念を抱き、初めに森羅万象の全否定があり、其処から、つまり、《世界》を一から創り上げる苦悩に満ちた言説のみ、信に堪へ得る《もの》なのである。
そして、《存在》に懊悩する《存在》は、それだけで既に矛盾してゐるのであるが、《存在》とはそもそも矛盾してゐる《もの》で、その矛盾を引き受けた《存在》は、何事に対しても不信の目を向け――それは《世界》を一から創造せずにはゐられぬ性質の《もの》である――もしさう出来なければ己の《存在》に一時も我慢がならす、絶えず《吾》にも《世界》に対しても憤怒するしかない《吾》は既存の《世界》をぶち壊し、その破壊された《世界》は、《吾》の魂に呼応して現出する《世界》として創り直され、魂の有様によって歪曲するその現実が、さうして創作描写される《世界》は、奇妙に魂に呼応した《もの》として表出され、然しながら、それは夢と違った《存在》として、どうあっても《存在》がのっぴきならぬその《世界》の涯に追ひ詰められるしかないその《世界》での《存在》の有様は、魂が渇望して已まない《世界》であり、現実なのである。つまり、初めに魂ありきなのである。
では、その魂とは何なのかと問へば、《吾》の現状を拒絶した《吾》、つまり、自同律に対して疑問を呈した《存在》の無様で悲惨な傷だらけの《吾》に違ひないのである。
――それって、《吾》に閉ぢ籠った《吾》と何の違ひがあるのかね? 魂を先立たせた《世界》とは、《吾》の渇望する《世界》、つまり、其処では《吾》が万能な《世界》ではないのかい? 仮にさうだとすると、魂のRealismとは《吾》の欲望の捌け口ではないのではないのかね?
との疑問が湧いてくるが、多分、魂に忠実な《世界》は、魂の是か非かを常に問ふ《世界》としてしか《吾》に現出する事はなく、《世界》が《吾》の魂に従属するとは、《吾》の《存在》を絶えず疑ふ疑心暗鬼の目で《世界》を見つめるやうに為らざるを得ぬのは必然なのである。つまり、《吾》の《世界》の立ち位置が魂の状態で如何様にも解釈が可能となり、《吾》の客観的な位置が消滅しまってゐるのである。つまり、主観的な思ひ込みででしか《吾》の《存在》の有様が解からないといふ混乱に《吾》は陥ることになるのである。つまり、魂が黒と思へば《世界》は黒に、白と思へば白に《世界》は変容し、さうして魂が《世界》によって浮き彫りになるのである。言説は、仮にそのやうな《世界》を描出出来れば、《存在》の秘儀が少しは解かるかもしれぬのである。
――《吾》に従ふ《世界》は《吾》において自閉してゐるのぢゃないかね?
と、再び《吾》によって問はれる魂に呼応する《世界》といふ《もの》は、《吾》の嗜好によって、《吾》の好きな《もの》に囲まれた《世界》と何の違ひがあるのかとの疑問に対しては《吾》が轆轤首へと変態するかしないかの違ひではない事が露はになるのである。つまり、魂に呼応する《世界》において、《吾》であり続け、その《吾》は《吾》の魂と呼応する不快なる《世界》に対する事を、その醜悪なる魂を浮き彫りにし、さうなると、《吾》は、その《世界》から遁走出来ぬ《もの》となり、《世界》の変化は、即ち魂の変調を暗示する《世界》が出現するのである。そして、その不快な《世界》から遁走した《もの》が轆轤首なる《吾》なのである。
然しながら、魂が本質に先立つ《存在》とは、果たして「現存在」に想起出来得る《もの》なのかは全く不明で、といふよりも全く想像不可能な《もの》でしかなく、それは、多分に言葉遊びの要素を含んだ《もの》に違ひないのである。つまり、直言すれば、魂が本質に先立つ《存在》など意味不明な《もの》でしかなく、極論すれば、幽霊こそがそれを存分に果たした《存在》に違ひないのである。
――さて、幽霊は《存在》すると思ふかね?
と、すかざす半畳が飛んで来るのである。私は、さうして一人突っ込みをして、さて、困った事に私は幽霊は《存在》する方が此の世が面白いと思ふのであるが、しかし、幽霊の《存在》は意見の分かれる問題に違ひなく、幽霊の《存在》に関しては、徹底して主観の問題に帰し、そして、何時も際物扱ひなのが幽霊の宿命なのである。
しかし、私個人の話をすれば、数日おきに、私の睡眠時にどうしても幽霊としか考へられぬ《存在》を夢の中でか、寝言としてか、そのどちらかで、私は誰とも知れぬ全くの赤の他人と睡眠時に休む間もなく、絶えず話し込んでゐて、そんな私を私は睡眠してゐるとはいへ、覚醒時の如くにはっきりと意識してゐて、その会話は何時も止めどなく、蜿蜒と続く《もの》と相場が決まってゐるのである。それを端的に言ふと、夢の中で鏡に映った自身の像を異形の《もの》として私が話してゐるのか、本当に幽霊と話してゐるのかと問はれれば、私は、何の躊躇ひもなく、それは私に憑依した幽霊であると言はざるを得ないのである。といふのも、仮にその赤の他人が夢の中で、私が作った人間に過ぎないとすれば、私は人間を作るのに長けた《もの》に違ひなく、その数や既に数へきれない数多の《もの》が、私の夢に登場した事になるが、しかし、私にそんな芸当が出来る筈もなく、その私の夢に登場する赤の他人は私に憑依した幽霊と看做した方が納得出来、しっくりと来るのである。それは、私の夢に登場する赤の他人は誰もが全く脈絡がなく私の夢に登場し、草草(さうさう)に私が私の夢に登場する他人を拵ゑる能力などある筈もなく、そんな芸当が出来たならば願ったり叶ったりで、何冊もの小説があっといふ間に出来上がる筈なのであるが、現実の処、そんな事はなく、つまり、私にそんな芸当はないのである。そして、私に幽霊が憑依すると私はその間、ずっと重重しい体軀を引き摺るやうにして、只管、その憑依した赤の他人の幽霊が私から離魂するのをひたすら待ち続けるのを常としてゐたのである。これは、或る種の狂気に違ひないが、私は、それでもそんな私を受け容れるしかないのである。
つまり、私は幽霊は全く怖くなく、寧ろ、興味津津の態であり、また、私は、よく真夜中に墓場に行っては、その澄明な空気に包まれる事を愛して已まないのである。
さて、さうして、私に憑依する幽霊達は、多分、私の魂魄の振動数と共鳴してゐるに違ひないと私は一人合点してゐるのであったが、その私は、私に憑依してきた幽霊を邪険に扱ふ事をご法度にして、私は、ひと度、私に憑依した《もの》は、それ自ら離魂する迄、ずっと私に憑依させる事を一つの決め事にしてゐて、つまり、それは、睡眠時に繰り広げられる会話が、或る意味楽しくて仕方がないに違ひなく、また、目から鱗が落ちる事しばしばなのである。
さうすると、私の夢は、私において閉ぢた《もの》ではなく、《世界》に対して開かれた《もの》で、そして、誰もが出入り自由な《もの》で、それ故に私が轆轤首に変態する事は常人に比べれば僅少かもしれぬのであるが、それはさておき、その開かれた私の夢に幽霊にとっては何か面白い《もの》でも転がってゐるのか、数日おきに、赤の他人が一人、または二人、私に憑依し、私は夢見中、その赤の他人達の幽霊共とその幽霊共が拘るTheme(テーマ)に沿って夢中で議論する事を心の底より楽しんでゐるのは間違ひなく、多分、私は、その赤の他人達を成仏させる為にはその赤の他人達の胸の丈を存分に語らせる事がその幽霊共の為に一番である事を、或る種、本能的に知ってゐて、私は私に憑依した幽霊を祓ふことなく、幽霊が憑依したいだけ私に憑依させてゐるのであった。
全く赤の他人の幽霊が憑依するとは、さて、どんな《もの》かと告白すれば、それは、只管に辛い《もの》で、その辛さから解放されるのは、睡眠時だけなのである。そして、幽霊を幽霊の好きなだけ憑依させてゐる莫迦《もの》は、多分、此の世で私位の《もの》だらうとは思ふのであるが、その憑依してゐる幽霊が邪悪な《もの》でも、私は、一切邪険にする事はなく、好きなだけ私に憑依させておくのである。さうして、睡眠時に彼らの恨み辛み事に耳を傾け、また、私は、それに異見をし、徹底的に話し込むのであるが、しかし、幸ひに私に憑依する幽霊は、此の世に恨みを持った《もの》は少なく、私に憑依するのは、大概、「私とは何か?」、そして「何が私なのか?」といふ埴谷雄高が『死靈(しれい)』で言挙げした問ひの答へを只管に探し求めてゐる求道者然とした幽霊が殆どで、つまり、それ故に私の魂魄と共鳴するに違ひなく、そんな懊悩にある《もの》との議論は意外と楽しく、私は、嬉嬉としてそれらの幽霊と話し込むのであった。
そんな時、私は夢の中で不図思ふのであるが、かうして、私と全く面識がない赤の他人にして《吾》に踏み迷ひ、懊悩してゐる私に憑依した幽霊と話し込んでゐる私を、例へばその有様を鏡に映す事が可能であれば、多分、私もまた《異形の吾》へと変化してゐて、其処にもしかすると私の本質の何かが表はれてゐるに違ひなく、仮にその《異形の吾》が、ピカソの有名な絵画「ゲルニカ」に見られる人面の人魂のやうな《もの》に変化してゐるかもしれず、それは轆轤首の首がちょん切れて、私の夢舞台の虚空を自在に飛び交ひながら、私に憑いた幽霊の魂魄と舞ひを踊ってゐるかもしれないのである。
――ふっふっふっ。幽霊と舞ふ? そんな莫迦な!
と思ふ私が確かに《存在》するのであるが、しかし、私に憑いてゐる幽霊と舞ふ様を思ひ描く度に、私は不思議と納得する《吾》を見出すのである。
人面の人魂と化した《異形の吾》と私に憑いた、《吾》に踏み迷った幽霊とが、私の夢の虚空を自在に舞ひながら、互ひに《吾》の《存在》について思ひの丈を語り尽くす様は、其処に自由なる気風が《存在》し、何かの縁かは解からぬが、中有の時か、それを過ぎてしまって、尚も成仏出来なかった幽霊のその懊悩の深さは、いづれも底無しで、それは私に憑いた幽霊と《異形の吾》は、舞ひを踊りながら、自由の気風の中で、止めどなく語り合ふ事は、私の精神衛生上、健全な事であり、さうして、こんこんと話し込む《異形の吾》と幽霊は、何時果てる事も知れぬAporia(アポリア)の問ひに対して蜿蜒とああでもない、かうでもない、と話し込みながら、私に憑依した幽霊は、踏み迷った《吾》を少しづつ取り戻してゆくのか、さうして、幾日かすると私から離魂し、或る《もの》は成仏し、また、或る《もの》は、私以外の誰かにまた憑依し、更に議論を深めてゐるに違ひないのである。つまり、私が、私に憑依する幽霊に寛大なのは、偏(ひとへ)に彼らは深い懊悩の中にをり、その陥穽――それを私は《パスカルの深淵》と看做してゐる――に落っこちて、幾ら足掻いた処で、出口なしのその有様に、私の《存在》の有様を、幽霊には全く失礼千万な事なのであるが重ね合はせてながら、私に憑依した幽霊は、私の与り知らぬ赤の他人ながらも、その懊悩する様に私との縁を見出し、私は、率先してそれら私に憑依した幽霊と話し込む事を渇望し、彼らが何《もの》であらうとも、絶対に祓ふ事はしないのである。
幽霊を祓はぬ事は、また、或る種の我慢比べでもあり、一夜の夢で私に憑いた幽霊と問答するには、私自身もまた、己の内奥を弄って私の醜悪極まりない部分をも目を逸らさずに直視せねばならず、さうして、私は意を尽くして真剣な議論を夜毎に繰り広げてゐるのである。尤も、その議論は、大概堂堂巡りを繰り返すばかりで、唯唯、消耗するのみの、睡眠する事で、ぐったりと疲れてゐる事しばしばで、それは疲れを取る為に寝る事とは程遠い睡眠で、睡眠の目的からすれば私の睡眠は本末転倒した《もの》なのは間違ひないのである。しかし、私はぐったりと疲れてゐるとはいへ、何処か爽やかな心持で毎日目覚めるのであった。つまり、答へは出ずとも私に憑いた幽霊との果てる事のない議論は、目覚めによってMarathon(マラソン)を走り切った時のやうに何かを達成したかの如き爽快感に私を置くのである。つまり、それだけ私に憑いた幽霊との議論は堂堂巡りを繰り返すとはいへ、白熱した内容の濃い《もの》で、幽霊との議論を深める度に私に憑いた幽霊も私も、多分、《吾》なる《もの》に半歩なりともにじり寄れた錯覚が齎す仮象の爽快感に包まれてゐるに違ひないのであった。つまり、私に憑いた幽霊と私とは、私の夢の虚空で自在に舞ひ切り、それ故にぐったりとしてゐるとはいへ、ただならぬ爽快感に包まれてゐるのである。尤も、それは、覚醒時のほんの一時の事でしかなく、継続する《もの》ではなかったのである。
さて、一先づ、夢から目覚め、私に憑いた幽霊との議論をお開きにした処から、私は覚醒しながらも、私の思考は、《吾》といふ観念の周りを巡る堂堂巡りを独り相撲を取る如くに行ふ事で、更に《吾》なる《もの》ににじり寄らうと、何の事はない、絶えず自問自答してゐるのであった。とはいへ、覚醒した私の思考は、夢の虚空を私に憑いた幽霊と自在に舞ひながら問答する自由なる気風は全くなく、いづれも杓子定規な思考法の、型に嵌った《もの》に為り易く、それは、私の《存在》する以前に《世界》が既に《存在》してゐる事と無関係ではないのである。つまり、《世界》が私を或る《存在》へと嵌め込み、その型に嵌った不自由の中で、《吾》ににじり寄る思考法を新たに獲得する事を《吾》に強要し、私は、さうなると、唯唯、呆然と《世界》を眺めては、
――此の能面の如き《世界》よ!
と、私の胸奥で感嘆の声を上げながら、何処から手を付ければよいのかも解からぬ《世界》に対して、私は、数学を用ゐて、世界認識しようと試みるのであった。尤も、世界認識に数学を用ゐる事には、或る限界が存する事は私も承知してゐて、それでも、現代においては、数学によって《世界》を把握するのが、最も解かり易いと思はざるを得ぬのである。
そして、その数学は、大概、物理数学を指す事が殆どで、成程、巧く物理数学は《世界》を描画してゐるのである。
ところが、物理数学が描出する《世界》に決定的に欠落してゐる《もの》があるが、それが《吾》の《存在》なのである。つまり、物理数学は、巧く《世界》を描画するが、それは《吾》のゐない《世界》であって、そんな《世界》は、《吾》の誕生以前か死後かの《世界》でしかなく、《吾》が生きた、つまり、《生》なる《吾》が確かに《存在》する《世界》とは、徹底的に主観的なる《世界》でなければならず、ところが、徹底的に主観的な《世界》は、現実の何処にも《存在》する筈もなく、私の覚醒時は、現実といふ私の制御不能な《世界》と私の主観的な《世界》と物理数学的な《世界》の三つ巴の《世界》が絶えず渦巻き、私とはと言へば、そんな渦巻に巻き込まれて懊悩するのみなのであった。
――世界の化かし合ひ!
と私が覚醒時に世界認識するその《世界》は、徹底的に主観的な吾が《世界》と私の制御不能なざらついた、否、ぬめりとした現実の《世界》が異様に生生しく私に迫りくる現実の《世界》から《世界》を取り分け、その結果現はれる抽象的な《もの》として把握する楽しみに満ちた物理数学の《世界》が、私の頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》で互ひに化かし合ひながら、《世界》は或る印象を私の心に残すのである。それは、《世界》とは把捉したと思った刹那にするりと私の思考からすり抜けて、私が、頭蓋内の闇たる脳といふ構造をした《五蘊場》に張り巡らせた思索的なる網の罠の目の粗さばかりが際立つ、つまり、私の《世界》に対する敗北感のみを絶えず私に印象付けるのであった。尤も、《神》以外、《世界》を思索の網で捕へる事は、不可能な事は自身十分に承知してゐるとはいへ、《世界》は絶えず捉へ損なふ《吾》の不甲斐無さと言ったなら最早、苦笑ひをする外なく、それでも、私は、私の徹底的に主観的な《世界》のみは、手放せずに後生大事にその《世界》の《存在》を承認するのであるが、さうして、私は、《吾》のみに負ふ私の徹底した主観的なる《世界》に、《世界》を認識する糸口の希望を仄かではあるが、秘かに託しながら、
――《世界》は徹底的に主観的な筈である。
といふ思ひをちっちゃな吾が胸に秘めつつ、《世界》のあかんべえを絶えず見る事になるのである。すると、私はむきになって、首のみがちょん切れてしまった轆轤首と化して、私から絶えず遁走する《世界》を追ひ続けるその時に抜群の威力を発揮するのが物理数学の網の目で、《世界》は、その網の目からは遁れられずにしょんぼりとしてゐるである。とはいへ、私の徹底的に主観的な《世界》と物理数学の網の目に捕へられた《世界》は跨ぎ果せぬ裂け目が《存在》し、私の徹底的に主観的なる《世界》と物理数学が描出する《世界》とは絶えずずれてゐて、その間隙にぬっとその異様な面を出すのが現実といふ名の《世界》なのである。そして、私は、現実に出合ふと首がちょん切れた轆轤首の首を直ぐ様引込めて、《吾》もまた、現実の《吾》を味はふ皮肉に、自嘲しながら、そののっぺりとした感触にぶるっと震へては、《吾》なる《もの》の不気味さを堪へ忍ぶのである。
――それぢゃ、《吾》なる《もの》が《世界》の一端を指示してゐるのではないのかね?
と自問する事になるのであるが、その時は私は必ず、
――然り。
と肯うふばかりなのである。つまり、轆轤首へと変化するのを已めた刹那の現実の吾が体軀にこそ、《世界》は宿ってゐるのであって、而も、それは、《世界》で《存在》するには不可欠な事なのは当然の事であり、さうでなければ、現実に《吾》なんぞ《存在》する筈はないのである。
――では何故に《吾》は轆轤首なんぞに態態変化しなければならぬのか?
と再び最初の問ひに戻る堂堂巡りが始まるのである。
多分、《吾》が轆轤首に変化する事で、私の徹底的な主観的な《世界》と物理数学が描出する抽象的ながらも途轍もなく具体的な《世界》との裂け目を飛び越すべく首を不自然に伸ばし、そして、ぬめっとした感触ばかりが際立つ現実の《世界》に私の首から下の肉体は、現実の人質として《世界》に囚へられ、さうして現実の《世界》の人質として吾が首から下の肉体はある故に、私が此の世に思索的に《存在》出来得、その場合は必ず轆轤首に変化せずにはをれなかった筈なのである。さうして、私の首は、自由を求めて伸びに伸びて仕舞ひにはちょん切れて吾が虚空を自在に飛翔を始めるのである。
ところで、吾が虚空を自在に飛翔し、舞ってゐる《吾》の首は、飛んでゐるのか、将又、自由落下してゐるのかの区別は、徹頭徹尾主観の問題で、自在に舞ふ己の有様を、飛翔と認識するのか、それとも自由落下してゐるのか、どちらかとして把握するその選択は、《吾》の資質による処大であるが、私は、《吾》が吾が虚空で自在感を味はってゐる時は、必ず《パスカルの深淵》に自由落下してゐる《吾》を表象せずにはをれなかったのである。つまり、それは、私が、如何に地獄を愛好してゐるのか図らずも指し示す事になり、夢の中で《吾》が自在に飛翔してゐると断言出来る《もの》は、天国、若しくは浄土への志向が強烈な筈で、私のやうに絶えず自由落下してゐると看做す《もの》は、地獄愛好者と言ひ得るのである。さうして、奈落に落ちてゐる事ばかりを渇望する《吾》は、さうする事で、己の不安を少しでも和らげては、自己愛撫しながら、更なる落下、若しくは堕落を味はふ悪徳に浸る快楽を追ひ求めずにはをれず、そんな自堕落な《吾》の志向に対して、にたりと嗤ひ、そして、更なる深みを求めて、自由落下する《吾》を表象する遊びを始めるのである。さうなると、最早、《吾》は《吾》を見失ひ、只管、《吾》から迷子になる事を冀ひなが落ち行く《吾》を想像しては、心を打ち震はせてゐるに違いないのである。
さて、現実に囚はれたままの首を失った吾が体軀は、ちょん切られて残された首の根っこを磯巾着の触手の如く天へ向かって伸ばすのであるが、一方で、首のみと化した《吾》は、吾が体軀が目指す方角へ向かっては飛翔せずに、只管、自由落下してゐるその首の《吾》と吾が体軀との齟齬は、天を目指しながら奈落に自由落下する私の矛盾を浮き彫りにしてゐるのであるが、しかし、私は何時もその矛盾を吾が《存在》の証の一つとして大事にしてゐるのは間違ひなかったのである。つまり、私は、《存在》とは、それだけで既に矛盾した《もの》であると看做してゐるのは、何度も言ふやうに確かな事で、尚且つ、《他》において私は、矛盾を抱へた《存在》に違ひないとの予見を持って眺めるのであったが、尤も、それを裏切らない《他》に出会った事はなく、つまり、《他》は自尊してゐる場合が少なくなく、とはいへ、それが、仮面である事は、大概の《存在》ならば、そんな事は自明の事に過ぎないのである。だからこそ、尚更《他》は《吾》にとっては不可解極まりない《存在》であり、超越した《もの》なのである。つまり、《他》には、私の予想を覆す予見不能な突拍子もない事を平気で行ふ《存在》でありながら、それでゐて私に憑依する幽霊宜しく、語ればやはり、自分に躓いてゐて、さうして一瞬でも《吾》と《他》は、解かり合へたとの錯覚を互ひに互ひの事を誤解する事で辛うじて関係が保たれる不可思議な事態へと《吾》と《他》は投企されるのであるが、それは、それで互ひに居心地がよいので、敢へて、互ひの懊悩へと深入りはせずとも、《吾》は《他》に《吾》の懊悩を投影して、《他》の解釈を始めるから始末に負へないのである。そもそも《他》の解釈なんぞ《吾》に出来る筈もなく、《吾》に踏み迷ってゐる《もの》に《他》を解釈出来る訳もないのは必然であって、それを恰も理解出来たかの如く振舞ふのは偽善でしかないのである。《吾》と《他》は何処まで行っても解かり合へない故に、《吾》と《他》は、互ひに関係を持つ事を渇望せずにはをれず、其処で、互ひに解かり合へない事は、当然の事であり、それを前提に《他》と関係を持たない事は、礼を欠き、《他》に対して失礼極まりないのである。
然しながら、《他》は、《異形の吾》といふ謎を解く一つの解であり、それを十分に承知してゐながら、《吾》は《他》に対して突然、刃物を取り出して殺されるかもしれぬのっぴきならぬ事態すらをも鑑みつつ、《吾》は《他》に対峙し、その姿勢が詰まる所、《吾》が《異形の吾》として姿見の前にゐて《吾》に対峙してゐる《吾》といふ事象に重なるのである。其処で、《吾》は、《他》に《吾》であった可能性を値踏みしては地団駄を踏み、《他》が《吾》であった可能性が零ではない事に或る種の衝撃を受けつつも、《吾》は、《吾》の《存在》を立証するべく、《他》に対して恐れ慄きながら、作り笑ひを顔に浮かべて、《吾》は《他》の敵ではない事を《他》に諂ひつつも、己の下司な根性を内心で侮蔑しながら、《吾》とはとことん《存在》に対しては、謙(へりくだ)った《もの》に違ひないと感服し、《吾》は、無防備のまま《他》に対峙する剣が峰に立つ決心をする故に、《吾》は漸く《他》に対峙するのである。といふのは、《他》は《異形の吾》の解の一つであるからであり、《吾》が《他》に、つまり、《異形の吾》に対峙するその仕方は、大概さうであるべきで、それが、《他》に対しての、《異形の吾》に対しての礼儀なのである。尤も、それは、一瞥を相手と交はした刹那の出来事でしかなく、《吾》は《他》に対しても《異形の吾》に対しても、伏目のまま対峙し、一瞥で以てして《他》、若しくは《異形の吾》に対してその《存在》を丸ごと受け容れつつも、《吾》に巣食ってゐる我執を丸出しにして、《他》、若しくは《異形の吾》を威嚇してゐるのは間違ひなく、《吾》と《他》、若しくは《異形の吾》との間に交はされる一瞥には、《存在》が《存在》に対する時の作法が凝縮してゐる筈なのである。そして、それは、底無しの絶望が為せる業でしかなく、《吾》と、《他》、若しくは《異形の吾》との対峙は、何処まで行ってもお互ひに理解不能な、《存在》に対するといふ受難、若しくは苦行なのである。
――へっ、《他》、若しくは《異形の吾》との対峙が、苦行だって? 嗤はせないで呉れないかな。それは、お前が、単なる対人恐怖症を発症してゐるだけぢゃないのかね?
と、にたにた嗤った《異形の吾》が半畳をすかさず入れるのであるが、
――未知の《存在》に対しする作法がさうなのさ。
と嘯く私は、失笑するのであった。
――ぷっふいっ。
と。
さて、ところが、《吾》が《他》、若しくは《異形の吾》と一瞥を交はすその刹那、互ひの目は、爛爛と輝いてゐる筈である。《吾》に宿る、《他》、若しくは《異形の吾》に対しての阿諛する己を《吾》は《吾》の内に平伏させ、そして、《吾》は、《他》、若しくは《異形の吾》と一瞥を交はした途端に、好奇心なる《もの》が頭を擡げて、仮象の首がぬらぬらと伸び始め、《他》、若しくは《異形の吾》に漸近するのであるが、その仮象の首は、《他》、若しくは《異形の吾》にある程度近づくと、最早、それ以上は越えられない一線が《存在》するのである。つまり、《吾》が把捉し得る《他》、若しくは《異形の吾》は、その正体を摂動した《もの》としてしか、《吾》には現はれないのである。乃ち、《吾》は、《吾》にとって、摂動した《吾》でしかなく、《吾》が《吾》を捉へた事など全宇宙史上、一度もないに違ひないのである。此処に自同律の不成立の兆しが見えるのであるが、極論すれば、《吾》は《吾》において破綻してゐるのである。「私」において、《吾》も《他》も《異形の吾》も、本来あるべき《物自体》としての《存在》からは、どうしやうもなく摂動した《もの》としてしか捉へられないのである。そして、その摂動においてこそ、《パスカルの深淵》がばっくりと大口を開けてゐて、《吾》が不用意に《他》、若しくは《異形の吾》に向かって歩を進めようものならば、《吾》は確実にその《パスカルの深淵》の陥穽に落っこちて、《吾》は、《吾》から遁れられぬ《パスカルの深淵》といふ陥穽の中に自閉し、哀しい哉、その閉ぢた中で蜿蜒と《吾》は摂動する《吾》と鬼ごっこを続けるのである。
また、《吾》から摂動する《吾》との鬼ごっこをしてゐる時の《吾》程、愉しい《吾》もまた、《存在》せず、その愉しさ故に《吾》は、仕舞ひには《吾》を見失ふのが落ちなのである。この皮肉に《吾》は暫く茫然とし、天を仰ぎながら、遂には哄笑を発する事になるのであったが、其処で不意に《吾》に帰ると、《吾》なる《もの》が首のみの《意識体》とでも呼ぶべき化け物でしかない事を知って愕然とし、《吾》は轆轤首から進化した化け物なのかと訝るのである。
――はて、《吾》は何を追ってゐたのか?
と、それまで摂動する《吾》を追ってゐたに違ひないと思ひ込んでゐた《吾》の不覚に自嘲するのであったが、その摂動する《吾》は《異形の吾》ではなかったのではないかと不審に思ひつつも、
――否、《吾》は《吾》なる蜃気楼を見てゐたに過ぎぬのか?
と、自問するのである。しかし、
――何を猿芝居を演じてゐる? 《吾》は何時でも《吾》の幻しか追はぬではないか?
と、《吾》の内なる声が《吾》の内部で響き渡るのであった。つまりは、首のみと化した化け物の《吾》の内部はがらんどうで、
――さて、此のがらんどうの首のみの《吾》は一体全体どうした事だらう?
と、夢中で摂動する《吾》を追ってゐた鬼ごっこの祭りの後の虚しさに、苦虫を噛み締めながら、只管、《吾》が《吾》なる事の屈辱を味はひ尽くさねばならないのを常としてゐたのである。
ところで、その間、現実に囚はれた吾が胴体は、何をしてゐたかといふと、自由落下を志向する《吾》の首とは反対に、天へ向かって頭のない首をぬらぬらと伸ばし、其処にあるであらう《異形の吾》の首を強奪する詭計を巡らし、字義通り首のすげ替へを企んでゐたのである。そして、その詭計は大概成功裡に終はるのであったが、首をすげ替へた胴体はその《異形の吾》であった首に何時も不満であり続け、再び《吾》が摂動する《吾》を追ひかけ、鬼ごっこが始まると、自ら進んで首を切り離し、再び後悔するのが解ってゐながら天へ向かって首をぬらぬらと伸ばしては、新たな《異形の吾》の首を強奪するのであった。
一方で、胴体に見捨てられた首は、摂動する《吾》と鬼ごっこをしながらも、《吾》は既に見捨てられた首である事は薄薄感じてゐるに違ひなく、首のみの人魂の如き化け物として吾が頭蓋内の闇を中有の間か未来永劫かはいざ知らず、しかし、浮遊してゐる筈なのである。つまり、「私」の頭蓋内の闇には、胴体に見捨てられた首のみの《吾》の亡霊が犇めき、吾が胴体を求めて彷徨してゐるのであった。そして、その吾が頭蓋内の闇に犇めく首の化け物は火事場の馬鹿力宜しく、吾が胴体に見捨てられたことを糧にして、自らが《吾》から摂動する《異形の吾》へと変化し、再び吾が胴へと帰る算段を企む図太さは持ち合はせてゐるらしく、詰まる所、《吾》の首と吾が胴体は、首をすげ替へるとはいっても、首が犇めく渾沌の坩堝の中で堂堂巡りを繰り返すばかりなのであった。
――へっ、堂堂巡りはお前の思考法そのそものぢゃないか!
と、自嘲する《吾》は、然しながら、絶えず、摂動する《吾》を追ひかけては、《吾》を見失ふ愚行を繰り返さざるを得ぬのである。ところが、果たせる哉、《吾》は《吾》の首をすげ替へた処で、《吾》は《吾》である事から遁れられぬ一方で、一瞬でも《吾》から遁れられたCatharsis(カタルシス)を味はひたくて、《吾》は仮象の《吾》の首をちょん切っては、《吾》の首を《異形の吾》の首とすげ替へ、その時に満ち溢れる《吾》ならぬ《吾》といふ一つの愉しみに酔ひ痴れるのであった。つまり、轆轤首なる《吾》には、轆轤首である事が止められぬ呪縛に囚はれて、蟻地獄の巣の中の蟻の如く《吾》が《吾》に踏み迷ふ悪循環から抜け出せぬのであった。
その悪循環は、然しながら、「堕ち行く《吾》」といふ表象を吾が頭蓋内の闇に明滅させるので、私に何とも名状し難き愉悦を齎すのであったが、「堕ち行く《吾》」といふ表象が頭蓋内の闇に明滅した刹那、仮象の《吾》の首はちょん切れてゐて、私はさうなると心行くまで落下する《吾》を堪能せずにはをれなかったのである。
ところで、《パスカルの深淵》を自由落下する仮象の《吾》の首の表象に大地は決して現はれる事はなく、吾が仮象の首は、何処までも自由落下を続け、永劫運動をする事になるのであった。とはいへ、その自由落下といふ永劫運動は、私が永劫の眠りに就けぬ限り、永劫に自由落下する事は、また、あり得ず、何時かはその仮象の《世界》から《吾》は現実に引き摺り出される事になるのは火を見るよりも明らかで、といふより、私は、絶えず現実に《存在》してゐる《吾》を意識しながら、狡(ずる)賢(がしこ)い《吾》は、現実に《吾》は《存在》しながらも仮象の《吾》の首が自由落下する表象を何時も思ひ浮かべる事で、やうやっと現実に《存在》する《吾》を受容出来る卑しい《存在》なのであった。つまり、「堕ち行く《吾》」といふ表象なしには、此の世に一時も《存在》出来ぬ現実逃避者なのである。
――だが何時もお前は後ろ髪を現実に引っ張られ続けて、仮象の《世界》にどっぷりと浸かってゐる事など出来ないんぢゃないかね?
と、自問する《吾》は、哀しい哉、《パスカルの深淵》を自由落下しするしかないのであった。
意識は自由落下を望んでゐる一方で、吾が仮象の首なき胴体は、天への昇天を夢見、その仮象の首なき胴体を仮に無意識の有様と名指せば、意識は自由落下を、無意識は自由昇天を、つまり、私の意識は物質で、無意識は反物質で出来てゐると看做せなくもないのである。つまり、物質である意識は、重力に抗ふ事なくお気楽に自由落下する事を望み、反物質の首なき胴体が、重力に対して斥力の生じるべき《吾》を志向する事は、実際は、絶えず現実に呪縛されてゐる事の裏返しであって、私は、頭蓋内から絶えずずり落ちる事を志向する意識をして此の現実から逃避してゐるのであった。しかし、それは、
――だが、逃げ場はない!
といふ事を意識しながらのことなのである。つまり、仰仰しく《パスカルの深淵》などと呼んでゐる此の世に開いた陥穽は、詰まる所、私が現実から遁れるべく仮初に拵へた逃げ場の事で、さうやって常に現実から逃げ出す事、つまり、重力に此の身を任せる自由落下を欣求する愚者こそ、私なのであって、然しながら、己を愚者と名指す事で私は、己の保身を図ってゐるのもまた間違ひのない事であった。それ故に、時に私は、そんな己に我慢がならず、《吾》の仮象の首を自らの仮象の刀でぶった切っては、首のみを重力に任せて自由落下させるのであった。「堕ち行く《吾》」の表象は、しかし、現実の中に自身の身の置き場を見失ってゐる私においては、この上ない悦びを私に齎し、その悦びがあってのみ、私は、《生》を保つことが出来るに違ひないのであった。
――それを他人は卑怯といふのぢゃないかね?
と、反問する《吾》もまた、私には《存在》してゐて、それが、つまり、上昇志向を持つ仮象の吾が首なき胴体であり、絶えず、重力に抗ふ吾が仮象の首なき胴体は、ひょっとすると、「先験的」に反重力的なる志向を羊水の中で刷り込まれ、そして本能として所持してゐる《もの》なのかもしれず、その反物質的な反重力を志向する吾が仮象の首なき胴体は、然しながら、ちょん切られた首のみを辛うじてぬらぬらと天へ向かって伸ばせるのであって、仮象と雖も、吾が仮象の首なき胴体は、地に縛り付けられてゐる事には変はりがなかったのも確かなのであった。
さて、地に縛り付けられながら、天へ向かって首なき首を伸ばすその現実に囚はれてゐる吾が胴体は、正(まさ)しくパスカルが名指した「現存在」の有様、つまり、天と地の「中間者」の有様に外ならず、その姿を第三者的な視点で眺めれば、天と地を支へるアトラス神の如き威容な《存在》として、此の天と地を支へる《もの》が出現してゐる筈なのである。つまり、私の無意識と意識が対流してゐるに違ひない私の仮象界において、その仮象界を支へてゐるのが首なき胴体の《吾》であり、さうして此の世に無理矢理にでもこじ開けて出現した仮象界において、吾が《意識体》と化した胴体からちょん切られた首のみの《吾》は、意識と無意識が対流してゐるその仮象界で、只管、自由落下する浮遊感を心行くまで味はひながらも、最早、此の仮象界を支へる首なき胴体との別離を嫌でも感じずにはをれず、其処で、《吾》は不意に《吾》なる事の哀しさを少しは味はふのである。その哀しさは、然しながら吾がちょん切られし首の自由の保障であり、その様な状況下に《吾》を追ひ込む事でしか、《吾》なる事を感覚出来ない感官の麻痺した《吾》は、さうする事で、ちょん切られた切断面の創(きず)の疼きを感じつつも、《吾》からの逸脱を絶えず試みるのであった。
だからといって、首のみの《意識体》と化した《吾》は、《吾》から逸脱する筈もなく、やる事為す事が全て欺瞞に満ちた《吾》なる《もの》は、その欺瞞なる事をひっぺ返す事で《吾》なる《もの》の本質が透けて見えやしないかと知らぬ内に、躍起と為ってゐるのであったが、首のみと化した《吾》は、玉葱の如く、皮を剥いても再び薄皮が現はれるだけで、幾ら《吾》の欺瞞の皮を剥いだ処で、欺瞞の面の皮は幾重にも重なってゐて、《吾》に決して至る事はないのである。とはいへ、《吾》は、吾が面の皮を剥ぐことを止められぬのであった。といふよりも、止めたくなかったのが本当の処である。何故ならば、内向する事が大好きな《吾》において《吾》なる《もの》の化けの皮を剥がす事の愉しさは、名状し難き《もの》であって、さうして、一枚一枚と剥がしてゆく《吾》の化けの皮は、一方で、《吾》が自ずと脱皮するかの如くに《吾》から剥がれた《吾》の抜け殻を喰らふ時の美味しさといったら格別で、その美味しさは、何《もの》にも代え難く、然しながら、哀しい哉、首のみと化してゐる《吾》は、幾ら己の化けの皮を喰らった処で、喰らったそばから化けの皮は、切り落とされた食道の穴からぽろりと落ちてしまひ、それ故に幾ら仮象界とはいへ、満腹感を得られる事はある筈もなく、また、首のみと化した《吾》が、仮象界にゐる間は、《吾》の化けの皮を剥いでは、それを喰らふ愚行を繰り返す事を蜿蜒としてゐる為か、大概、首がちょん切れた《吾》は《吾》である事に倦んでゐるのである。
それでは、自由落下に加へて内向する首のみの《吾》は、その無意識と意識が対流してゐる仮象界を佇立して支へてゐる吾が胴体がその視界に見えてゐるのかといへば、そんな《もの》は全く眼中にはなく、首のみと化した《吾》は白目を剥いて、内部のみ凝視する事に現を抜かしてゐるのであった。さうして、首のみと化した《吾》は、《吾》に閉ぢ籠る事で、《吾》はやっと自由を謳歌出来るのであって、しかし、それを他人は卑怯と呼ぶのは十全に承知しながら、《吾》は、《吾》に閉ぢ籠る事を善しとするのである。つまり、《吾》とは、なんと欺瞞に満ちて、矛盾した《存在》であるかと、さうした欺瞞なる《存在》の《吾》を味はひ尽くす事が、《吾》が求める自由なのかもしれなかったのである。
――そんな自由なんぞ糞喰らへ!
と、さう揶揄するのもまた、《吾》の属性なのは間違ひない事であった。《吾》とは一時も《吾》に対する猜疑心から遁れられる事はなく、何時でも《吾》なる《もの》を直接的に断罪する事を冀ひながら、《吾》が現実から流刑される事を本心から望んでゐる《もの》に違ひなく、此の現実から遁れられるのであれば、《吾》は、如何なる存在論的な刑罰をも堪へ忍ぶ覚悟は出来てゐる《もの》で、むしろ、《吾》は存在論的な罪を担ってゐる証左が欲しくて仕様がないのある。何故ならば、仮に《吾》に関する存在論的な罪が明確に立証出来るのであれば、それはそれで《吾》の有様がきちっと定まり、《吾》が存在論的罪人ならば、《吾》が《吾》の処置の仕方も明確になり、《吾》は何の迷ひもなく、《吾》は邪神の眷属か基督の如き十字架上で磔刑されるべき、罪を背負った《存在》に為り得べき筈に違ひにないのであるが、哀しい哉、《吾》は大概《吾》の眼には摂動する《吾》としてしか把捉出来ず、《吾》が《吾》に関して知り得るのは、曖昧模糊とした《吾》の予想値でしかなく、その為に《吾》と《吾》に関する《吾》の認識は、ずれにずれて《吾》は《吾》の眼には絶えず摂動する《存在》としてしか捉へられないのであった。
これは《吾》もまた、《吾》の眼差しにおいて《吾》といふ《もの》は、漠然とした《状態》が見えるといふハイゼンベルクの不確定性原理に《吾》もまたあって、仮に《吾》の此の世での立ち位置が定まった処で、その時の《吾》の内部で渦動してゐるに違ひない《吾》の情動は、《吾》の予想に反して最早お手上げ《状態》であるに違ひなく、それは、謂ふなれば、《吾》に関して見通しがよければよい程に、《吾》が《吾》を把捉するのは困難極まりなく、結局の所、《吾》は《吾》の外面は確かに捉へたが、しかし、それは単なる《吾》の抜け殻としての《吾》でしかなく、《吾》の「心」は既に把捉した《吾》の抜け殻からまんまと逃げ果せてゐるのである。果たせる哉、《吾》が、例へば、存在論的な罪人であるといふ《吾》を凝結させる核が《存在》すれば、《吾》は或る結晶体として、Fractal的に巨大化して、《吾》の罪人としての結晶体が見定められる筈であるが、しかし、実際の処は、《吾》は漠然と罪人であるとの命題を抱へ込んでゐる《存在》でしかなく、また、《吾》が存在論的罪人である《吾》の根拠が、何時でも《吾》を凝結させる筈はなく、むしろ、《吾》が存在論的罪人といふ事は、《吾》の把捉には紊乱しか齎さないのであった。
――しかし、《吾》は確かに《存在》する。
と、再び《吾》は《吾》に対して呟くのであるが、だからといって、《吾》が《吾》に対して明瞭になる事などなく、《吾》が《吾》を凝視する場合、それは、闇を凝視してゐる事に外ならず、詰まる所、《吾》はその境界面、つまり、Black holeの地平線が此の世の《存在》には決して見える事がない如くに、《吾》とは存在論的なBlack holeに違ひないのである。
さて、《吾》を存在論的なBlack holeと名指しした処で、何かが明瞭になる訳はなく、むしろ、《吾》が《吾》に対する混迷は深まるばかりであって、結局、闇が何であるのか見通せない内は、《吾》は《吾》といふ仮面を薄らと闇に浮かび上がらせては直ぐに消える事を繰り返す存在論的Black holeの首であって、それは頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》に明滅する脳細胞の呻吟が解明された処で、《五蘊場》の《状態》を定める事は、ハイゼンベルクの不確定性原理から類推するに、《吾》の輪郭を尚更、曖昧にするのみの、《吾》に対する誤謬を拡大するといふ《吾》の《吾》からの逃亡を論理付けるだけのやうな気がするのである。つまり、
――《吾》は《吾》や?
と、脳細胞一つ一つの呻吟が解明されたところで、Black holeが直接見えないやうに、《吾》といふ《存在》の謎は残されたままに違ひないのである。
さて、《吾》がいくら虚勢を張った処で、《吾》が卑怯なる事実は変はる筈もなく、また《吾》は《吾》が卑怯事を自覚する事で、《吾》なる《存在》は、謂はば、Black holeとその連星といふ二重構造を為して、《吾》は《吾》において院政を敷くのである。何故ならば、《吾》が《吾》において二重構造を為してゐる事は、《吾》は《吾》の傀儡を立てる事で、現実の《吾》に降りかかる存在論的な圧迫を《吾》の傀儡に全ておっ被せて、その傀儡の《吾》が見事に圧迫に堪え兼ねて爆発する様を目の当たりにしながら、《吾》は存在論的な圧迫に満ちた現実を卑怯にもやり過ごすのである。
その傀儡の《吾》を作るのは《吾》においてお手の《もの》で、その自爆する傀儡の《吾》の《存在》なくしては、《吾》は一時も《吾》である事に堪へ得ぬに違ひなく、そして、《吾》は傀儡の《吾》が《吾》の知らぬ間に巨大な権力を手にしてゐる事を、《異形の吾》の哄笑によって知る事になるのであるが、それまで傀儡の《吾》と高を括ってゐた《吾》は、その事態に動揺するのである。つまり、《吾》は傀儡の《吾》を作り出す度毎に気力をすり減らしてゐたのであった。
それは、傀儡の《吾》が現実に《存在》する存在論的な圧迫に堪へ兼ねて爆発するその傀儡の《吾》に対する眼差しが全てを物語ってゐる。つまり、《吾》は傀儡の《吾》が爆発し、滅ぶ様を胸を痛めずにはゐられぬのである。その為に、傀儡の《吾》が爆発して壊れ消えた後の虚しさを次に作る傀儡の《吾》に反映させ、現実に横たはる存在論的なる圧迫に少しでも堪へ得る傀儡の《吾》を作らうと精を出すのである。それは、つまり、《吾》の傀儡への権力の移譲なのである。
しかし、その傀儡の《吾》を作る《吾》といふのは、何とも矛盾した《存在》である。その《吾》が傀儡の《吾》を拵ゑるのは、現実において、所謂、存在論的な猶予を求める事に外ならず、《吾》は《吾》の《存在》の決定に対して《吾》は最後の最後まで忌避してゐるのである。つまり、《吾》の《状態》を決定する事は、物質の本源たる素粒子においてハイゼンベルクの不確定性原理に倣ふやうにして、不確定のままに現実をやり過ごせれば、それに越した事はないのである。しかし、現実は絶えず《吾》が《吾》である事を強要する《もの》であり、《吾》の自己決定の先延ばしをする為に《吾》は窮余の策として傀儡の《吾》を作り出してゐた筈なのであるが、それは、《吾》が気付かぬ内に、《吾》と傀儡の《吾》は何時しか入れ替はり、《吾》が現実の矢面に立つといふ本末転倒した有様に見舞はれるのである。
――何故にこんな事態に……。
と嘆いた処で、既に時は遅きに失し、今度ばかりは傀儡の《吾》、つまり、《吾》は爆発する事は許されない事態に追ひ込まれ、《吾》は、
――嗚呼!
と、嘆きつつも、常に《吾》の《状態》はといへば、現実は無情にも《吾》が《吾》である事の決定を強要し続け、その度に《吾》は《吾》の何かを喪失してゆくのである。その失はれる《もの》が、何なのかは一向に解らぬまま、《吾》は現実に振り回されながら、《吾》である事を強ひられ続け、《吾》は存在論的に疲弊し切り、その疲弊が臨界を超えた或る刹那、《吾》は仮象の《吾》の首をぶった切って、仮象において自刃するのである。つまり、《吾》が《吾》であると決定される前に自刃して、仮象の《吾》の首をぶった切る事で、《吾》は、《吾》の最後の砦に違ひにない仮象において《吾》を斬り殺す事で、《吾》を未決定の《状態》に置いておくのである。
それは、《吾》は《吾》であり得ぬといふ自己決定の猶予を《吾》に与へる事で、《吾》は現実の《吾》と対峙せずに、つまり、《吾》が《吾》であるといふ自同律に対して微力ながら抗ふべく、《吾》は《吾》に対して詭計を巡らせるのであった。
ところで、《吾》が《吾》である事を決定出来ないと先述したが、《吾》が《吾》において未決の《吾》である事は、《吾》が此の世に《存在》する拠り所となってゐなくもないのである。即ち自同律に抗ふべく、《吾》が《吾》に対して詭計を巡らせる事で、仮にも『《吾》が《吾》である』と言ひ切れる《吾》の出現を可能ならしめたならば、それは《吾》の詭計の一つの成功を意味する筈で、《吾》が恰も《吾》であるかのやうに振舞ふ欺瞞において、《吾》は《吾》である自覚が出来るのである。それは、然しながら、途轍もなく居心地が悪いのである。《吾》におけるこの二重化は、一方で《吾》が《吾》である事を未決に、また、一方で、仮初の《吾》なる《もの》を据ゑて、それをして、『《吾》が《吾》である』と自覚する詭計を《吾》に施さねばならぬ此の《吾》のまどろっこしさは、詰まる所、何も決してゐない事と同じ故に、《吾》の《吾》なる事が前提の此の現実においての《吾》の有様は、徹頭徹尾、居心地が悪いのである。つまり、《吾》が《吾》なる事が不自然なのである。
――そんな事は初めから解かり切った事ぢゃないか!
と、自嘲する《吾》に対して、《吾》は、つまり、傀儡の《吾》は、既に形骸化してゐるとはいへ、《吾》の《存在》の有様を二重化する事で、《吾》が《吾》である自同律の陥穽に落ちずに現実をやり過ごしてゐたのであるが、しかし、それが全て詭計なる故に《吾》が《吾》である事が途轍もなく居心地が悪いのである。ならば、それを已めればよいのであるが、《吾》が「単独者」として此の現実に対峙する気力は既に擦切れてゐて、実際、《吾》は疲労困憊の態なのである。さうして、《吾》は出来得れば此の現実から遁れられるのであれば、永劫に遁れ続けたいのである。それは、《吾》が《吾》であるといふ自同律に対して《吾》であると、《吾》をして語らせる事と無関係ではなく、《吾》が《吾》に対峙出来ない事と現実を直視しない事が相関関係にある事は、《吾》が《吾》において《吾》を決定出来ない事から自然の帰結なのである。
――では、《吾》とはそもそも何か?
といふ疑問が再び頭を擡げるのであるが、それは、詰まる所、《水》の不純物としか言ひやうのない《もの》なのである。人体といふ構造をした《水》の不純物たる「現存在」は、それを煎じ詰めれば、《水》の野心に外ならないのである。それは、川の流れが一つとして同じ《状態》がないやうに、《吾》においても例へば体液が流れる《吾》においても一つとして同じ《状態》の《吾》は《存在》した事はなく、つまり、《水》が変幻自在な如くに、《吾》もまた変幻自在なのである。
――そんな莫迦な!
と《吾》は呆れるのであるが、実際の処、《吾》の《五蘊場》に明滅する《もの》は、変幻自在で、其処に居座る《吾》は、大概が首ばかりが異様に伸びた轆轤首に外ならず、それと言ふのも、《吾》なる《もの》が、詰まる所、《水》の不純物でしかない事に端を発して変幻自在なるが故なのである。つまり、《吾》は絶えず《吾》から摂動してゐて、ぴたりと静止する事を知らず、絶えず振動してゐる何かなのである。その象徴が脈動する事を「現存在」は死すまで已めないのである。そして、流動する《吾》は、此の現実に対峙するべく、その生贄に《吾》の仮象の首をぶった切って現実に差し出すのである。さうして、《吾》は此の《吾》を絶えず《吾》であるかの如くに装はせる現実に対して、《吾》為らざる《吾》などといふ詭計を凝らして、《吾》が《吾》である事の居心地の悪さを緩衝するのである。
そもそも《一》者なるといふ事は、絶えず0.99999999……なる《もの》の小数点以下の「九」が無限に続く《存在》が此の現実に《存在》するといふ暗黙の了解のもとにしか《存在》せぬ故に、《吾》が《吾》に対峙する時に、現実は、《吾》が《吾》なる《一》者である以上、無限の底なしの混沌に落っこちる危ふさを《吾》に強ひてゐるのが実際の処なのである。
《世界》は何処も彼処も無限の底無しの穴凹だらけである事は《パスカルの深淵》や野間宏の『暗い絵』の事例を出さずとも明明白白であるが、《吾》なる《もの》は、その本能としてその底無しの穴凹に落っこちる事を避けようと抗ふ偽装を行ふのである。例へば、《吾》は《吾》をして《異形の吾》を拵ゑ、《吾》に不都合な事は全て《吾》為らざる《異形の吾》に肩代はりさせて、《吾》はといふと、のうのうとその《異形の吾》の悪戦苦闘ぶりを高みの見物を決め込んで、Sadistic(サディスティック)な眼差しで眺めては哄笑するのであった。つまり、《吾》は、首のみの《吾》は、仮象の中に閉ぢ籠る事で、一時の安寧を手にするのであるが、然しながら、それは、所詮、《吾》の偽装でしかない事が現実にはお見通しである事に、《吾》はぎくりとし、そして、《吾》は仮象界も既に現実に浸食されてゐる事を知り、愕然とするのである。
そのやうにして逃げ場を失った《吾》は、絶体絶命でありながら、それでも現実は《吾》を殺す筈はないと心の何処かでは高を括ってゐて、現実がその眦(まなじり)一つ動かさず、《吾》を殺す事に思ひ至らないのである。現実は、《吾》を殺す事なんぞいとも簡単に行ひ、実際、《吾》なる「現存在」は日日必ず《死》んでゐて、《吾》が何時《死》してもそれは全く不思議な事ではなく、《吾》はその事を絶えず不問に付して、《吾》を宙ぶらりんの《状態》に置く事ばかりに詭計を巡らせるのである。しかし、それに対するしっぺ返しとして、自同律の不快を甘受せずにはをれぬ事を「現存在」は心底思ひ知らされる羽目に陥るのである。つまり、《吾》が《一》者として看做される以上、其処に論理的な《インチキ》がある事を無意識にか意識的にかには関係なく、然しながら、矛盾している言ひ方ではあるが、「先験的」に知ってゐて、《一》なる事の《インチキ》に対して《吾》は絶えず騙されてゐるふりをする《もの》なのである。それは、しかし、《吾》の精神には堪へられぬ《もの》で、《吾》に正直な「現存在」は、気が狂ふのが必然で、気がふれない《もの》は面の皮が厚いだけなのであって、極論すれば、此の世の《吾》に気狂ひでない《吾》は《存在》せず、さらに言へば、気狂ひとは未完成の別称に違ひないのである。
日日、《一》なる《インチキ》を生くる《吾》は、絶えず足下に広がる底無しの無限の穴凹に自由落下する《吾》の幻影を見てしまひ、眩暈を覚えながら何故に此の世に佇立、若しくは屹立するかは、全く解からず、茫然自失の態で《吾》は此の世に《存在》するのである。
それでは、《吾》なる《もの》が《一》者である事が何故に《インチキ》なのかといへば、《吾》が《吾》である事その《もの》が既に《インチキ》で、《吾》をして《吾》を《吾》と名指す欺瞞を、如何なる《吾》も知ってしまってゐて、さて、それが何故に欺瞞かと尚も問へば、《吾》の《存在》自体が、果たせる哉、《吾》の意思で出現したのかすら解からぬこの《吾》の《存在》の出自を「偶然」の《もの》として、不問に付して、例へば、「現存在」の此の世への出現は、その父母の精虫と卵子の「偶然」の受精によって《吾》が発生するとし、然しながら、精虫と卵子の受精が「偶然」と看做せるのかは、多分に意見の分かれる処で、仮に《吾》の此の世への出現は、宇宙開闢時に既に決定してゐた事だとしたならば、《吾》は《吾》をして、此の宇宙に対峙し、《吾》の解明と共に、宇宙をも、物質をも、数字をも全て解明する宿命にあるに違ひないのである。然しながら、その《吾》はといへば、此の現実に汲汲としてゐるばかりで、轆轤首と化して、頭蓋内の闇の《五蘊場》が表象する仮象界へと逃げ込んで、其処で《吾》は《異形の吾》との何時果てるとも知れぬ対話を繰り広げながらも、《吾》は、現実を《異形の吾》に呉れてやるのである。さうして《異形の吾》が、現実界において自滅する無様を見ては、《吾》は、独りほくそ笑み、さうして、《吾》は仮象の首をぶった切り、《五蘊場》に表象される仮象界の幻の中に羽化登仙するのである。
傀儡の《吾》が、《吾》の制御を失ふと、それは、《異形の吾》となるのは言はずもがなだが、つまり、《異形の吾》の淵源を辿れば、それは、何気なく現実逃避する為に《吾》が作り始めた傀儡の《吾》に至るといふ矛盾にぶち当たるのである。そもそも《吾》といふ《存在》は、その《存在》自体が矛盾に満ちた《もの》である事は今更言ふに及ばず、しかし、《吾》の《存在》が矛盾してゐなければ、《吾》はこれまた一時も此の現実に《存在》する事は、不可能に思へるのである。例へば、《吾》が《吾》にぴたりと重なっているといふ《存在》の有様では、此の《吾》といふ《存在》はその《存在》に一時も堪へられる筈もなく、また、《一》者といふ「単独者」として《存在》する《吾》は、現実を、若しくは《世界》を《一》者として背負ふには、《吾》の存続の《断念》が含まれてゐて、《吾》が《吾》にぴたりと重なった《一》者としての《吾》は、此の現実を前に自滅するべく定められてゐるに違ひないのである。それは、シャボン玉が此の世に儚く忽然と消ゆる如く、自己の存続が不可能である事が、《吾》の発生時に既に定められてゐて、つまり、《吾》なる《もの》には、《死》が予め埋め込まれてゐるのである。《死》が此の世に《存在》するといふのは、此の現実は、若しくは此の《世界》は、《吾》を《死》へと追ひ込むといふ事を意味し、つまり、此の世の《吾》に対する迫害は、《吾》が《死》すまで已めないとも言へるのである。勿論、此の《世界》は絶えず《吾》を鏖殺(おうさつ)する程に無慈悲である事は稀かもしれぬが、しかし、絶えず《吾》といふ《存在》の《死》は此の《世界》では起ってゐて、休む間もなく何《もの》かは常に《死》んでゐるのである。
といふ事は、《吾》にとっては、此の現実は、《吾》を直ぐにでも殺すべく、その匕首(あひくち)を突き付ける《死》の別称に違ひないのである。《吾》は《吾》とぴたりと重なる事を避けて、つまり、自同律を極力避けて、《吾》の傀儡を作り、その傀儡の《吾》が自爆する様を凝視する事で、此の現実が突き付ける《吾》の《死》に対する猶予を与へ、しかし、必ず《吾》に訪れる《死》をその場では傀儡の《吾》を使って躱してゐるのである。さうしなければ、芥子粒の如き《吾》が此の世で生きてゆくなんぞ出来る筈もなく、《吾》もまた、細胞分裂する如くに頭蓋内の闇たる《五蘊場》において、分裂を繰り返し、絶えず此の現実に差し出しながら、《吾》の存続を辛うじて為してゐるに過ぎないのである。それだけ、《吾》なる《もの》は羸弱な《存在》で、此の無慈悲な相貌を持つ現実に対して、《吾》が丸腰で打って出るには、余りに無謀と言はざるを得ず、《吾》は生き残る為とあらば、何でもする《もの》なのである。そのなれの果てが、《異形の吾》であり、轆轤首の《吾》となるのである。《吾》は、そのやうに変容する事で、やうやっと此の現実、若しくは《世界》に対峙し、《吾》は権謀術数の限りを尽くし、《世界》の《死》への誘ひからひらりと身を躱すのである。
ところで、《吾》とは、独りなのであるかとの疑問が湧くのであるが、多分、《五蘊場》においては無数の《吾》が《存在》するのは間違ひなく、其処には《吾》といふ名の異形の《もの》が犇めいてゐるに違ひないのである。つまり、《吾》とは、此の現実で生き残る為に分裂してゐて、そして、《吾》を統べる《吾》は次次と入れ代はり立ち代はり現はれては、ぐっと首を伸ばして、《五蘊場》を俯瞰し、さうして、現実に差し出す《吾》の首根っこを摑んで、その《吾》をして無慈悲な、若しくは悪意のある現実、若しくは《世界》の為すがままにさせて、詰まる所、現実に嬲り殺される《吾》を《吾》は凝視するのである。その現実に差し出された《吾》なる《もの》が現実に弄ばれてゐる間は、《吾》は安寧の中にゐられるといふ《存在》の、これまた無慈悲な有様に思ひを馳せつつも、《吾》は《五蘊場》に閉ぢ籠り、《異形の吾》や私に憑依した幽霊共と尽きども尽きせぬ対話を蜿蜒と行ふ事になるのである。
一方では《吾》が拵ゑた傀儡の《吾》が、無慈悲なる現実に嬲り殺されながら、一方で、首なしの《吾》が、その《吾》の首と《異形の吾》とが閉ぢ籠る仮象界をアトラスの如く全身で支へながら、《吾》は《五蘊場》の中で以って、《異形の吾》と此の《吾》の深層に沈み込んで、只管に《吾》の断罪を始めるのである。しかし、その断罪の仕方が現実程に無慈悲に行へる筈はなく、《吾》も《異形の吾》も《吾》を手緩く断罪しながら《吾》は常に《吾》を許すべく術がない《もの》かと思案してゐるのである。
それでは、何故に《吾》は、《異形の吾》と共に雁首を揃へて《吾》を断罪するのかと問へば、それは《吾》が何処までも矛盾した《存在》といふ事に尽きるのである。例へば、傀儡の《吾》が現実に嬲り殺される様が気になって仕様がないくせに、《吾》は絶えず平静を装ひつつ、現実の如くに眦一つ動かさずに傀儡の《吾》が遂には自爆する様を凝視しながら、その《吾》の首の《五蘊場》――これは仮象の《吾》の仮象の頭蓋内の闇――に《異形の吾》共を誘ひ、其処で《吾》は恰も《異形の吾》と対峙するかのやうな錯覚の中、《吾》は初め《異形の吾》に詰(なじ)られるがままに、《異形の吾》の叱責に対して黙してゐるが、一人目の傀儡の《吾》が自爆し、二人目の傀儡の《吾》を貪婪な現実に差し出すや否や、今度は《吾》が、《異形の吾》に問ふのである。
――《吾》とは何ぞや?
と。しかし、此の問ひは、そもそもが矛盾した問ひなのである。つまり、
――《吾》とは何ぞや?
と問ふ事は、そもそも《吾》が「先験的」に此の世に《存在》する事が前提となってゐるのである。つまり、
――《吾》とは何ぞや?
と問ふ事は、木乃伊(みいら)取りが木乃伊になる事に外ならないのである。
さて、其処で問題となるのが、《吾》とは、《吾》の究極の《存在》なのかといふ問ひである。つまり、《五蘊場》で分裂を繰り返す《吾》とは、もしかすると《吾》と《反=吾》との受胎、若しくは太極により、《吾》が《五蘊場》で分裂し、自己増殖する《吾》の様態に過ぎぬのではないかといふ疑念が発生するのである。そして、その《反=吾》が《異形の吾》の別称なのかもしれないと看做す《吾》は、《異形の吾》を摑まへにかかるのである。しかし、《吾》は首のみであるので、《吾》はどうあっても永劫に《異形の吾》を手で摑まへる事は不可能で、また、《異形の吾》は、つひぞその姿を《吾》の前に現はした事がない事に思ひ至り、唯、声のみが何処とも知れぬ虚空から轟き、さうして、不意に《五蘊場》に一陣の風が吹き抜ける事に思ひ至るのである。
しかし、《異形の吾》が《吾》の前に姿を現はさないのは至極当然の事で、《吾》は、一度、轆轤首へと変化し、無慈悲な、また、悪意ある現実から遁れるべく、《吾》は、自ら轆轤首の《吾》の首をぶった切り、首のみの《吾》は《五蘊場》に閉ぢ籠るのであるが、さて、首のみと化した《吾》は尚も分裂し、自己増殖してゐるのかどうかと問へば、多分、木の年輪の如く、《吾》は自己増殖しながら、《吾》は《一》者として、《存在》してゐるに違ひないのである。
――ならば、《異形の吾》は、何処へと消えたのかね?
との疑問が《吾》に生じるのであるが、仮に《異形の吾》が《反=吾》ならば、《異形の吾》は絶えず《吾》と相互作用しながら、その結果として《吾》の《五蘊場》に閃光が放たれ、《吾》なる《もの》の仮初の様態を、《五蘊場》に明滅する表象として現出させ続けてゐるに違ひないのである。つまり、首のみと化した《吾》と《異形の吾》は、雌雄の蛇の交尾のやうに、互ひに巻き付いく螺旋を為してゐるに違ひなく、つまり、《吾》といふ巨大化しつつある巨木に巻き付く《異形の吾》といふ蔦がぎりぎりとその巨木を締め付ける事で、《吾》の肥大化に待ったをかける自己調整機能が、《吾》にはこれまた「先験的」に備はってゐるに違ひないのである。つまり、《吾》あれば、即ち、《反=吾》、または、《異形の吾》は仮令姿は見えずとも「先験的」に《存在》してゐるのである。
しかし、《吾》と《反=吾》、若しくは、《異形の吾》と分裂した《吾》の有様に、《吾》は絶えず戸惑ひ、《吾》は、何時も《吾》の手に負へない《もの》として《存在》してゐるといふ矛盾に思ひ至るのである。この矛盾は、然しながら、未来永劫解決される事がない《もの》で、つまり、《吾》が此の世に発生すると同時に《反=吾》も発生するのである。《吾》と《反=吾》の《対存在》は、さて、何故に《対存在》として此の世に出現するのかと問ふてみた処で、その答へは決して得られぬ《もの》で、何《もの》も《吾》が《存在》すれば、その必然として《反=吾》が《対存在》するといふ矛盾に《吾》を見失ふのである。つまり、《吾》が《吾》について考へる事は、必ず堂堂巡りに陥る筈で、堂堂巡りでない思考法は、それは一時凌ぎでしかなく、三段論法などの直線の如き思考法や正反合と止揚する弁証法もまた、一時凌ぎの《存在》が《存在》する為の智慧であって、それらの思考法で事の本質は一向に解決を見ないのである。
先に《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》との関係を自己増殖しながら年輪を重ねる巨木とそれをぎりぎりと締め付ける蔦と見立てたが、さて、巨木が太陽光を渇仰して枝葉を大きく拡げるやうに巨木たる《吾》は、何かを渇仰するべく、蔦の間から枝葉を伸ばし、大きく拡げる筈であるが、さて、巨木たる《吾》も、蔦たる《反=吾》、若しくは《異形の吾》が何を渇仰して枝葉を大きく拡げてゐるのかを問ふてみた処で、直ぐには答へられぬ《吾》を、唯、噛み締めるといふだけの屈辱に苛まれる事になるのである。何故に《吾》に問ふ時に必ず《吾》は《吾》に対して敗北したかのやうな屈辱を味ははなければならぬかも、また、直ぐにはピンと来ないのであるが、しかし、この屈辱は、そもそも《吾》の《存在》に根差した感覚なのであって、《存在》は即ち、屈辱の別称である事が次第に闡明するのであり、さて、困った事にこの屈辱は《吾》が此の世に《存在》する限り、《吾》に、また、《反=吾》に一貫性を齎す《もの》で、不本意ながら、この《存在》に対する「先験的」とも言へる屈辱は、《吾》を此の世に《存在》させる原動力なのである。それは何故かと言へば、《吾》を此の世に根付かせるには自己肯定ではなく、徹底した自己否定においてのみであり、仮令自己肯定によって《吾》を称賛出来る《吾》が此の世に《存在》するとすれば、その《吾》は、既に変容する事を、つまり、生長する事を已めた《もの》でしかなく、その行く末は、蔦が宿主たる巨木を遂には枯らす如くに、《反=吾》、若しくは《異形の吾》によって《死》へ至らせられるべく自己決定した《存在》の断末魔でしかないのである。
では、《五蘊場》で生長する巨木たる《吾》と、蔦たる《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、何を渇仰して、生長し続けるのかと問へば、それは、《吾》を無限へと誘ふ闇としか思へぬのである。つまり、《吾》も《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、光ではなく、闇を渇仰して絶えず生長してゐるに違ひないのである。といふのも、闇には魑魅魍魎が犇めき、《吾》はそのGrotesqueな魑魅魍魎といふ観念を欣求しながら、それらを糧に生長するのである。つまり、《吾》が此の世に《存在》し得るには、《吾》は《五蘊場》といふ闇の中で明滅する表象の切片を食虫植物の如き《吾》といふ巨木の葉で捉へて、《吾》の糧にするのである。それは、言ふなれば光無き深海の底に一本のみ屹立する巨木と蔦の如き《もの》で、その巨木と蔦の葉は、食虫植物の如く、若しくは磯巾着の如くある筈で、《吾》は、深海に降り注ぐMarine snow(マリン・スノー)の如き、表象やら観念やらの骸を糧にする事でやうやっと生存するのである。
深海の底に屹立するGrotesqueな巨木。これが、《吾》の一つの表象であるが、その巨木をよくよく見ると、海底からぐっと首のみを伸ばした轆轤首であって、蔦に見える《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、十一面観音像の如く、《吾》の《五蘊場》に何相もの顔貌が見え隠れする異形の《もの》として、また、《吾》に巣食ふ《もの》として《存在》するのである。そして、闇故にその《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、生き生きとしてゐるのを見出すに違ひないのである。
闇に潜む事の快楽は、多分、何《もの》も知ってゐる快楽に違ひなく、然しながら、闇の中には魑魅魍魎が犇めく幻視に《吾》は慄き、足が竦むのであるが、しかし、それ故に、《吾》の思考は追い立てられるやうにして無限へと一足飛びで、そして、《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、闇の《五蘊場》に引き摺り出される事になるのである。つまり、窮鼠猫を噛む如く幻視して闇に出現する此の世の《もの》ならぬ魑魅魍魎に追ひ込まれるやうにして《吾》は逃げ回り、轆轤首の首をぶった切った《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》も無限を射程に収めながら、《吾》を時に無限の大河に身を横たへてゐるかの如くたゆたひ、時に無我の境地にも似て充溢した、それは《吾》を《無=点》と呼ぶべき零地点にゐる《吾》を自覚して《吾》があるといふ自在感を闇に見出すのである。
とはいへ、《吾》は、深海の水底に屹立する食虫植物の如き巨木としての表象である事は已めずに、その巨木は、また、首の化け物として、思念のみが自在である《五蘊場》の肥大化の一つの形として、地には根を、天には枝葉を拡げて、つまり、その巨木は、巨大磯巾着の如くに深海の闇の中にゐる《吾》として《吾》を自覚してゐる筈なのである。それは、何の事はない、闇の中において《吾》が何《もの》であらうが全く問題ないのである。闇は、何《もの》も受け容れる貪婪な《もの》で、それ故に、《吾》は闇の中において魑魅魍魎を見てしまふのであって、《吾》もまた、闇の中においては異形の《もの》としてあるといふ事が可能であり、更には、闇において何《もの》も《吾》の極小と極大を同時に味はふ《吾》の無限性に驚く筈で、換言すれば、闇を嫌悪する《存在》は、自在感に恐怖する《存在》に違ひなく、それは、言ふなれば、《吾》が《吾》を自覚するのに鏡が必要な光の下の《存在》として、姿形が種により限定された《もの》で、また、それは、深海生物が海面から釣り上げられた時に浮袋などが膨脹して口から臓物が、そして目玉が飛び出た死体を晒す如くに、鏡面に映る《吾》の死に顔を、若しくは《吾》の死体を見出す事で、自由の不安からの解消を絶えず行ってゐるのである。
鏡面に映る《吾》なんぞは《吾》の一様態でしかないのである。《吾》こそは様様な《もの》に変容する変幻自在な《もの》で、《吾》の本質なる《もの》を問ふてみると、それは、闇に行き着く筈なのである。更に言へば、《吾》は受精卵から細胞分裂を始めれば、此の世の全生物史を何か月間でか変態しながら、それが例へば「現存在」であれば、人となって産まれて来るのであるが、つまり、《吾》はそもそも全生物に為り果せるものであり、また、あらゆる《存在》に《吾》を見立てる事などお茶の子さいさいなのである。
瞼を持つ《存在》は、多分、いづれも闇へと思念が羽ばたき、《吾》の無限相を知ってゐるに違ひないのである。つまり、薄っぺらな瞼を閉ぢる事で、眼前は薄っぺらな闇に包まれ、その闇が《五蘊場》と地続きな事が意識され、《吾》の棲み処が、その《五蘊場》に中心を置いた、そして、皮膚に包まれた肉体といふ、これまた闇にある事を自覚する筈なのである。
それ故に、闇は一方で阿片の如く《吾》に作用する幻覚剤なのである。無限に憑りつかれた《もの》は、無限に惑溺し、そして、溺死する危険性に絶えず晒されてゐて、一歩間違へれば《吾》はその無限から最早一歩も踏み出す事なく、将に枯れた巨木その《もの》に為り果せてしまふのである。そして、闇は、《存在》を幻惑する《もの》で、闇に魅了された《もの》は、首のみを闇の中に自在に伸ばして何《もの》も轆轤首へと変化するのである。つまり、轆轤首とは《吾》の原点であり、闇にたゆたふ快楽を存分に味はふ事を知ってしまった《存在》に違ひないのである。
さて、そんな轆轤首が居心地よく生息する《世界》とはどんな《世界》かと言へば、多分、妄想が生き生きと生きる仮想現実といふ時空間に違ひないのである。また、其処で生き生きする事こそが轆轤首たる所以なのである。静止したMonitorに映し出される動的な映像世界の断片は、例へば数理Model(モデル)で表現された幻想的なFractalな内容の《もの》もあれば、Cameraで写された現実の断片など、玉石混淆な、つまり、映像に出来る《もの》であれば何《もの》でも表現可能なMonitor画面において、《吾》が轆轤首であることは面目躍如としか言ひやうがないのである。少し考へれば解かる事であるが、Monitorに映し出される動的な映像に見入る《吾》は、視点を変へれば、首を伸ばして映像が捉へた《もの》をまじまじと見る轆轤首へと、Monitor画面に映し出される映像の動くままに見入った《吾》は、不知不識に変化している化け物にしか思へないのである。更に言へば、《吾》は轆轤首宜しく、一所に坐したまま、Monitor画面の映像は、何処へでも《吾》の首のみを連れ出してゆき、しかし、視聴覚と身体のこの断裂した有様は、将に轆轤首と看做す外ないのである。
その轆轤首の《吾》が、深海の闇の水底に屹立する巨木、或ひは巨大磯巾着で、而も頭蓋内の闇たる《五蘊場》に閉ぢ籠る《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》であるといふ矛盾を、また、深海の水底に屹立する巨木たる《吾》とその巨木に絡まる蔦たる《反=吾》、若しくは《異形の吾》が互ひに闇を渇仰し、その枝葉を大きく拡げて闇を浴びてゐる有様との大いなる矛盾を、《吾》は「先験的」に捉へてゐる事が白日の下に晒された故に、「現存在」は、人間として此の世に《存在》する事を断念しなければ、此の世での《存在》を許されずに、「現存在」は、気が付けば己が轆轤首といふ化け物に変化してゐる事を知って愕然とするのである。そして、大概の「現存在」は己が轆轤首といふ化け物に変化してゐる事を自覚してゐるに違ひないのである。
深海の闇の水底に屹立する巨木、若しくは巨大磯巾着の《吾》、それから、それに絡まる蔦たる《反=吾》、若しくは《異形の吾》、それから、頭蓋内の《五蘊場》に閉ぢ籠る轆轤首の首をぶった切った首のみの《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》、それから、その《五蘊場》に明滅する表象群の切片を食らふ食虫植物の如き《吾》など、《吾》が《吾》をして惹起する《吾》の心像は、即ち、その《もの》がてんでんばらばらに分裂した《もの》で、Monitor画面といふ時間を含めた三次元、若しくは四次元の映像世界に《吾》を無理矢理重ねてみて、つまり、轆轤首たる《吾》を自覚し、それに陶酔する《吾》に、果ては踏み惑ふ愚行を何度も繰り返しながら、遂には、自身が、巨木たる自身がぶっ倒れる事のみを夢見て、自己増殖する妄想に溺れるのである。つまり、それは落語の「頭山」に瓜二つな《吾》が、実在する事に《吾》は独り嗤って、仕舞ひに自分の頭に飛び込んで死ぬのである。
とはいへ、現時点では、《吾》の頭蓋内の闇たる《五蘊場》に閉ぢ籠る《吾》や《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、「頭山」の男のやうに自分の頭に飛び込んで死ぬ事はなく、自分の頭、つまり、《五蘊場》といふ《死》と紙一重の時空間に閉ぢ籠り、《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》はひそひそ話に明け暮れるのである。換言すれば、落語の「頭山」の男の自分の頭に飛び込んで憤死するその様相は現代では一変し、轆轤首と為った「現存在」は、自分の頭に、《五蘊場》を拵へて、仮象の轆轤首たる《吾》は、現実から逃げ果すべく、首をぶった切り、己の頭、つまり、《五蘊場》に飛び込み、溺死する事も叶はずに、《吾》の《五蘊場》に明滅する妄想の類に惑溺するのみで、《吾》は、詰まる所、安穏と頭蓋内といふ《五蘊場》に逃避し果せてしまふのである。さうして《吾》は、思考実験と言へば聞こえはいいが、何の事はない、《五蘊場》の中から傀儡の《吾》を見繕って仮象の人身御供として現実にその仮象の傀儡の《吾》を《吾》の存続の為に捧げるのである。
そして、《吾》の身代はりで現実に捧げられた傀儡の《吾》は、《吾》に対して徹頭徹尾滅私奉公するのかと傀儡の《吾》が現実に嬲られ自爆する様を、一度じっくりと凝視すると、傀儡の《吾》は当然の事ながら、現実に抗ひ、現実を巧くいなして、思はず唸り声を発する程にそれは絶妙で感心する事になるのである。然しながら、傀儡の《吾》にとっては現実は当然、手に負へる《もの》の筈はなく、どんなに巧みに現実を躱さうと、最後のどん詰まりで傀儡の《吾》は、現実諸共木っ端微塵に破壊するべく覚悟を決めて現実を傀儡の《吾》に深く深く分け入る詭計を巡らした末に、最期に自爆するのである。
さて、其処で問題になるのが、傀儡の《吾》の自爆装置のSwitch(スイッチ)はいづれの《吾》が所持してゐるかといふ事なのだが、自爆装置のSwitchは、当然、傀儡の《吾》が持ってゐる筈である。しかし、一方で、《吾》も《反=吾》、若しくは《異形の吾》も傀儡の《吾》の自爆装置のSwitchを持ってゐて、然しながら、《吾》はそれを只管行使する事は避けて、自爆する時は、全て傀儡の《吾》に任せっきりな筈とも考へられるのである。ところが、少し立ち止まってこの矛盾を自問自答すると、傀儡の《吾》を爆破させてゐるのはもしかすると、此の《吾》なのかもしれぬと合点がゆき、現実を巻き添へにして、傀儡の《吾》を爆破させてゐる此の《吾》のふてぶてしさには、《吾》ながら快哉、否、侮蔑する外ないのである。それでは、
――何故に《吾》は知らぬ存ぜぬと、これ迄《吾》を欺いてゐたのか?
と、《吾》に問ふと、
――《吾》とは所詮、卑賤な《もの》の最たる《もの》の筈さ。
と、《吾》は臆面もなく言ひのけるのである。
《吾》と傀儡の《吾》とのからくりが一度解かってしまふと、《吾》は己の悍ましさに自身を呪ひながらも、内心では、
――したり。
と、嘲笑してゐる《吾》を見出して、尚更、《吾》は自己嫌悪のど壺に嵌るのである。さうなると其処は無間地獄の鳥羽口で、《吾》が《吾》に対して抱く猜疑の根深さは、《吾》の更なる分裂の引き金となって、《吾》は正気を保つ為に《吾》を嘲笑するその《吾》をぶん殴り、撲殺するのである。さうせずには仮初に《吾》が《吾》である一貫性が保持出来ず、用意周到な《吾》は、いざ《吾》が現実に対峙する段になると、再び傀儡の《吾》を現実に差し出す《吾》がゐて、然しながら、現実に差し出す《吾》が《存在》せずば、《吾》の《存在》が此の世に存続する事すら危ぶまれるのである。一度、《吾》が揺らぎ始めると、それは留まる事はなく、未来永劫に亙ってその揺らぎは続く《もの》で、《吾》が《吾》を疑ふといふ底無しの猜疑心は一度《吾》に萌芽すると、何としてもその生長を止める事は不可能であって、《吾》は《吾》の内部から腐乱し始めるのである。それは、巨木にはよく見られる現象で、中身が枯死し、刳り抜かれた巨木は極一般的な日常の風景なのである。つまり、深海の水底に屹立する《吾》たる巨木は、《吾》に対する猜疑心によって内部から腐り出して、巨木は外皮のみを残して中身ががらんどうの《存在》として深海の水底に屹立するのである。
すると、自己増殖する《吾》といふのは、《吾》が《吾》に対して抱く願望でしかない事に合点がゆく《吾》は、
――ぶはっはっはっはっ。
と、哄笑して、《吾》の間抜けぶりを自覚する事になるのである。
さて、それでは、自己増殖する《吾》とは、一体全体何であるのかを自身に問ふてみると、それは、現実に対する《吾》の擬態であり、もしかすると、傀儡の《吾》の《存在》その《もの》が、全て虚構の白昼夢に過ぎず、《吾》を語る為に《吾》がでっち上げた語り得る架空の《吾》故に、《吾》は自己増殖すると《吾》は看做してしまったのかもしれないのである。つまり、《吾》とは、語り得る《吾》の《存在》をでっち上げて《吾》といふ《存在》に自己暗示をかけて、恰も現実に《存在》する如く、《吾》は《吾》によって空想する《もの》なのかもしれなかったのである。
《吾》が《吾》を語り得る《もの》として空想する事は、《吾》を言葉によって瓦解させる事を意味してゐると看做せなくもなく、敢へて言へば、さうしてでっち上げられた架空の《吾》は、先に《五蘊場》に閉ぢ籠った《吾》の事に違ひなく、元来、分裂してしまってゐるに違ひない《吾》は、《吾》を自己増殖させるべく《吾》の肥大化を企てなければ、《吾》の所在すら解からず仕舞ひな《吾》であって、《吾》が《吾》に対峙する跋の悪さは、《反=吾》、若しくは《異形の吾》との対峙の比ではなく、《五蘊場》の闇の中とはいへ、ちらちらと点滅する表象群の閃光に《吾》と対峙する当の《吾》の姿は、ほんのりと闇間に浮かぶのであるが、《吾》はその《吾》が轆轤首でなく、また、首のみの人魂の如き形をしてゐないといふ事に訝るのであった。
と、そんな疑念が《五蘊場》に湧き起こると、そのでっち上げた《吾》は不意にその気配を消し、更に《吾》は、《吾》に対して不信の目を向けるのであるが、ところが、其処で《反=吾》、若しくは《異形の吾》が、
――くっくっくっくっ。
と、嗤ふのであった。それは真に嫌な嗤ひなのである。何故に《反=吾》、若しくは《異形の吾》が嗤ってゐたのか、《吾》にはすぐには見当が付かぬ故に気色悪い嗤ひなのであった。しかし、それは、多分に《吾》が表象群の明滅によって《反=吾》、若しくは《異形の吾》もまた、一寸前に気配を消してしまった《吾》の姿、若しくは面を見てしまったに違ひないのである。さうでなければ、《吾》に態態聞こえるやうな、嫌な嗤ひは起きる筈はなかったのである。あの《吾》が気配を消したのは、つまり、《反=吾》、若しくは《異形の吾》に《吾》の素顔が見られてしまった事による恥辱から来てゐるのではないかと、《吾》は暫くすると合点がゆき、さう思ひ為しては、《吾》の素顔はどんな素顔をしてゐるのかと興味津津で、それは、つまり、《吾》の思考とは、如何に一つの事をぢっと考へられぬ事かと、既に首をぐっと《吾》の気配がした処へと伸ばし、闇のみを凝視するので、《吾》の好奇心旺盛の節操の無さに苦笑するのであった。すると、《反=吾》、若しくは《異形の吾》が、
――いっひっひっ。
と、嘲笑するのであった。その嘲笑は残響を長く《五蘊場》に残し、何時迄もその木霊が聞こえるのであった。《吾》は、さうすると、唯、瞼を閉ぢて、独り闇に遁走しては、《吾》といふ巨木は、外皮のみでがらんどうになってしまったとはいへ、上部や枝葉では、未だに自己増殖して、《吾》が《反=吾》、若しくは《異形の吾》の嘲笑の木霊を聞きながら瞼を閉ぢると、《吾》といふ巨木の年輪が一つ刻まれるやうになるに違ひなかった。
すると、《反=吾》、若しくは《異形の吾》の《吾》の巨木に纏はり付いてゐる蔦は、更にぎゅっと《吾》を締め付けて、《吾》の肥大化を矯正し、《吾》を盆栽の何百年もの古木の如くに《反=吾》、若しくは《異形の吾》の閉め加減一つで、如何様にも変形する《吾》の虚しさにやうやっと気付くのである。成程、《吾》は、《吾》自身で己の事を巨木か、若しくは巨大磯巾着の如く看做してゐたが、実は、盆栽の木の如く何百年も小さいままに年輪を重ねた古木なのかもしれず、さう考へると、妙に納得する《吾》がゐるのであった。
――いっひっひっ。
さうすると、《反=吾》、若しくは《異形の吾》は、盆栽の木に巻き付けて、その姿を強要される太き太き太き針金の如き《もの》かもしれず、首のみをぐっと伸ばしてゐた轆轤首の《吾》は、太き太き太き《反=吾》、若しくは《異形の吾》の針金によって、首の姿を《反=吾》、若しくは《異形の吾》の思ひのまま、さもなくば、《神》のやうな《存在》により、太き太き太き針金を首に巻き付けられて、姿を強要された《吾》といふ《もの》を見出す筈であるが、己の事を深海の水底に屹立する中ががらんどうの巨木とばかり想定してゐた《吾》は、其処で不意に沈思し始めるのであった。
――《吾》は巨木か、否か? 《吾》は盆栽の古木か、否か?
それは《神》が巨木大だと、《吾》は盆栽の古木で、《神》が巨人族の眷属であるならば、《吾》は巨木に違ひなく、古木たる《吾》の大きさなどは、相対的な《もの》に違ひないのである。それ故に、《吾》が《五蘊場》の闇に籠城する《もの》であるならば、その時、《吾》の《五蘊場》に出現する《吾》と名指しされた《もの》は、盆栽の古木のやうに何百年もの星霜を経た《もの》に宿る或る威厳ある風情として、頭蓋内の《五蘊場》に巨大な巨大な巨大な木を表象させて、《吾》たる盆栽の古木に《吾》の表象を重ねながら極小から極大までを振幅を繰り返しながら、その表象された木は、《吾》の大きさに最終的には収斂してゆくのである。《吾》を虚勢を張った威容ある《存在》とでっち上げたければ、《五蘊場》に出現する《吾》と名指しされる木は、巨木の威容を備へてゐると一見見えるのであるが、しかし、それをよくよく目を凝らして眺めれば、しゅうっとその巨木は収縮し、玩具の如き木の芽に過ぎぬ事が闡明されて、《吾》は慌はてふためくのである。
――何たる事だ!
《吾》の擬態にまんまと騙されてゐたに過ぎぬ《吾》を自覚すると《世界》は一変するのであった。
ふうっと、仮象の轆轤首の《吾》と《反=吾》、若しくは《異形の吾》は全て一瞬にして霧消し、《吾》は《吾》の肉体に帰還し、不意に私は、《吾》に為る不愉快な時間を味はひ、眼をかっと見開いて《世界》の中にある《吾》といふ《もの》をして《吾》の《五蘊場》に楔を打ち込みながら、私はくっと歯を噛み締めて、唯、ぢっと《吾》たる《もの》に堪へるのであった。つまり、等身大の《吾》を《世界》の中に見出すのであった。さうして、私は頭蓋内の《五蘊場》を攪拌して、再び《吾》の仮象が出現するのを待つのである。実際、《世界》の内にある《吾》でゐ続ける事は、最早、苦痛でしかない私にとって《吾》の仮象を生み出す作業は、私が此の世で生き抜く最低限の智慧なのであった。
然しながら、私の想像は既に枯渇してまったに違ひなく、再び《吾》は轆轤首として私の頭蓋内の闇たる《五蘊場》に表象されるのであった。それといふのも私は、既に《脳=内=存在》、つまり、《五蘊場=内=存在》たる事に徹する事で、《吾》が《吾》でしかない此の世の不合理に堪へ忍んで、《吾》は《五蘊場》の内なる《存在》として、生きる事を覚悟してゐたに違ひなかったのである。そんな《吾》が《五蘊場》に表象し得る《吾》は、つまり、《五蘊場》ばかり肥大化した首振り人形の如き轆轤首として現はれる外ないのである。既に《五蘊場》と肉体は分裂してしまってゐて、《吾》が語る言葉には、最早、感覚的な言葉は影を潜め、唯、《吾》の口からついて出る言葉に仮象を誘ふ言葉のみが重視されるのである。
五感は、既に過去の遺物でしかなく、五蘊のみが《五蘊場》に収斂した《五蘊場=内=存在》たる《吾》は、ドストエフスキイ曰く、「紙で出来た人間」宜しく、《吾》の餌は、最早、言葉となった《もの》しか受け付けないのである。勿論、食物を食べはするが、其処に《吾》は何の重きも置かずに唯の生命維持の為のみに食物を喰らふのであって、美味しい不味いの判断は既に《吾》から失われてしまって久しいのである。《吾》が望むのは食物も「何何に効く」などと効能を謳って言語化された食物を喰らふのであって、それが美味いか不味いかは二の次なのである。食物ですら言語化された《もの》として喰らふ《吾》が、《五蘊場》に自身を思ひ描くその道理は、
――初めに言葉ありき。
なのである。そして、それは、勿論、聖書の冒頭の言葉と同じ事は知りつつも、《吾》にとっては既にその言葉が持つ効能は、聖書のそれとは全く違ってゐて、《吾》が自身を思ひ描く《吾》なる《もの》は、言語化され得る《もの》のみで出来上がった下らぬ《五蘊場=内=存在》たる《吾》でしかなかったのである。
しかし、言葉を喰らふばかりの《存在》として《五蘊場》の中に閉ぢ籠る《吾》は、唯唯、虚しいだけなのもまた事実なのであった。それは、途轍もない虚無感で、その点でも《吾》は、内部から腐乱し始めてゐるのは間違ひなく、さうやって、《吾》を浪費する事でのみ、やっと《吾》は《吾》の《存在》を受け容れるのであった。否、受け容れる外なかったのである。何故ならば、自意識が芽生える以前に《吾》は《吾》として既に《存在》してをり、その《吾》を仮初にも全否定した処で、自殺する事位が関の山であって、《吾》が死なうが《世界》は痛くも痒くもないのである。つまり、《吾》が《吾》の《存在》を認識する時は、既に《吾》は《世界》に対してそれとは気付かずに反旗を翻してゐるのである。
――何時か、《世界》を転覆させる!
と、自意識に目覚め、自意識に苛まれる思春期に既にそのちっちゃな胸奥で呟いてゐた事に、後後気付いて、にやりと嗤ふ《吾》に、《吾》は尚更胸糞悪く、そんな《吾》を侮蔑せずにはをれぬのである。つまり、《吾》は《吾》を侮蔑しては《吾》を唾棄する堂堂巡りを繰り返して、その何時果てるとも知れぬ《吾》の《吾》に対する鬼ごっこを蜿蜒と繰り返すのである。その虚しさは言はずもがなである。
では、そんな鬼ごっこなんて已めちまへ、とは思ふのだが、何せ《吾》に関する自己に《吾》は一時も《吾》から遁れる術を持ち合はせてをらず、仮令、瞑想が《吾》が《吾》を追ひかける無間地獄から抜け出す方法であっても、その瞑想してゐる《吾》を《吾》は受け容れられず、《吾》は懊悩の塊と化して、只管に《吾》を追ひかけるのである。さうせずには、《吾》の《存在》が危ぶまれる疑念が何時も《吾》の頭蓋内の《五蘊場》に去来するのである。そんな事はないと《吾》を宥めてみた処で、それは、必ず失敗に終はるのが常で、《吾》が《吾》から遁れる異形の姿が轆轤首に違ひないのである。
首のみをぐうっと伸ばしたその異形の姿は、高度科学技術で高度情報化の社会が《吾》に迫った《もの》に違ひなく、また、《吾》が轆轤首である事を許したのは、その社会、つまり、何処の誰とも知れぬ《他》、それは《神》ではない《他》の手によって弄り回された《世界》の残滓によってである。《吾》が此の世に《存在》してゐた時には既に《世界》は現代の荒波に揉まれて、その原始の姿は全くなく、郊外といふ全く人工的で無味乾燥な《世界》で生きる事を強要された《存在》として既にあった事に、《吾》の根無し具合を鑑みては、何時も忌忌しく思ふのであるが、それすらをも忍辱しなければならなかった《吾》の有様は、《自由》を欣求するのであれば、頭蓋内の《五蘊場》に逃げ込む外なく、さうして《世界》と断絶してしまった《吾》の有様を思ふと、尚更、《吾》は《吾》を嘲笑するのであった。多分、私はさうする事で《吾》を呪縛する《世界》へと無理矢理に適応する事を思ひ留まらせ、その呪縛から遁れられるのではないかと、当てずっぽうに思ひ込みながら、生を送るといふ余りにも虚しい人生に見切りをつけて、只管に《五蘊場》に閉ぢ籠りながら、《吾》は、詰まる所、《吾》を人質にとって、《五蘊場》に籠城する事に相成ったとしか言ひ様がない、そこはかとない忸怩たる思ひの中に沈思するのであった。ところが、こんな事は、《吾》の専売特許などではなく、《他》もまた、同じやうに虚妄の中に己の生を見出し、《他》もまた、深い懊悩にありながら、しかし、巧く《世界》に、全くの人工的な《世界》に適応して見せて、充足したやうに見える生を送ってゐるとしか《吾》には見えない憾みを抱きつつも、《吾》は《他》に付和雷同する事で、何とか《世界》に《吾》の居場所を見出す事になるのである。
さうして《他》があらゆることの基準となってしまった此の《吾》といふ《存在》は、巨人族の喪失が何をおいても、その《吾》の思考法に暗い影を落としてゐて、「現存在」を超越した《存在》、即ち、《神》の喪失とは、郊外といふ人工の《世界》で生きるを得なかった「現存在」にとっては、見果てぬ夢に違ひなく、「現存在」の事しか、それも不十分に「現存在」の《存在》のみしか念頭にない郊外といふ不自然な《世界》に追ひ詰められた「現存在」にとって《吾》とは、紋切り型として大量生産される「世人」の事であって、《死》は、或る日、突然にやって来る異界と化して《死》の場所すらをも排除してゐたその郊外といふ不自然な時空間が、仮に「現存在」が夢見た「理想郷」であったとしても、其処で幼児期から《存在》させられた子供にとっては、何処も彼処も《吾》の隠れる場所はなく、《世界》に対して生身のまま対峙する外なかった「現存在」にとって、郊外は、何時しか脱出すべき場所へと変貌するのは、当然の事なのである。
「現存在」が主人公の郊外といふ不自然な《世界》において、幼児期から其処で生きる事を強要された「現存在」は、然しながら、哀しい事に、その不自然な人工的な世界に過剰適応してしまひ、さて、その帰結が「現存在」の轆轤首への変容なのである。何故に轆轤首なのかは、今迄に既に述べてゐるのでもう語らないが、「現存在」の視聴覚のみに特化した歪な《世界》の状況に対して「現存在」は、轆轤首へと変容するしか生き延びる事は不可能であったのである。そして、その轆轤首は、如何に凡庸であるかが問はれるといふ本末転倒した皮肉に満ちた《存在》の有様を強ひられ、変はり者は郊外から追はれる事になったのであった。しかし、原風景としての不自然な郊外が、頭蓋内の《五蘊場》に居座ってゐる限り、何処も彼処も「現存在」が主人公のぺらぺらな《世界》が此の世であると、《世界》といふ《もの》を無意識裡に見下してゐる事に気付かぬままに、《世界》に対して無謀にも、無防備に対峙する愚行をやってのけるのである。それは、はっきり言って莫迦がする事で、郊外は、詰まる所、莫迦者しか生み出さない時空間なのである。その結果、現在起きてゐる事は、超高層Buildingが林立する都心回帰の動きなのであるが、この超高層Buildingが曲者で、敢へて言へば、超高層Buildingに住まふ《もの》こそが、轆轤首と化した「現存在」であるといふ事である。何故に轆轤首なのかと言へば、それは、明らかで、「現存在」は、科学技術を信頼しきってゐる故に超高層Buildingに住まふ事が可能であり、高度科学技術が生み出した現代といふ不気味な居住空間に轆轤首しか《存在》出来ぬのが道理なのである。
地を離れた超高層Buildingに住まふ「現存在」は、意識として体軀は、地面に残したままで、首のみを超高層Buildingに潜入させてゐる哀しい姿として、此の世に現はれてゐて、また、超高層Buildingは地上から離れてゐる故に、その分、地上よりも早い速度で公転してゐる筈で、しかし、一方で地上から離れてゐる事で、その事から特殊相対性理論より地上よりも離れれば離れる程に時間の流れは速くなり、つまり、超高層Buildingは敢へて言へば、それはほんの一寸の時間差に過ぎぬが、或る種のTime Machineと言ってよく、超高層Buildingの住人は、絶えず《現在》よりも早く年を取る、つまり、早く老けるのが科学的な結論なのである。つまり、超高層Buildingにおいてその不自然極まりない時空間に過剰適応したのが、轆轤首としての「現存在」であって、それ以外の「現存在」は、超高層Buildingの不自然さに堪へられる筈もなく、また、徹底的に自然性を喪失してしまった超高層Buildingの住人達が、真っ当な「現存在」である筈はなく、皆、そんな不自然な《世界》に《吾》の居場所を見出す「現存在」の鬼子が、現在、《存在》してゐる数多の「現存在」の普通の有様なのである。自身が「現存在」の鬼子、即ち、轆轤首である事にてんで思ひ至らぬ「現存在」こそが、現在の最先端を生きる「現存在」のありふれた様相なのである。
現代とは首のみ重宝される無慈悲な時代なのである。「現存在」は絶えず実験動物の如く常に更新されゆく文明の利器に囲まれた流動的な《世界》に置かれ、その《存在》を無理矢理試されるのである。其処で適応出来なければ、それは既に無能《もの》としての烙印が押され、《世界》に潰される《存在》なのである。それ故に「現存在」はこの首のみが重宝される時代に過剰適応して見せることで、自身の存在価値を測る尺度にしてゐたのである。その結果、「現存在」は轆轤首と為って、此の世を浮遊し始めたのである。嘗ては、「現存在」の闊歩する跫音が聞こえた街には既に「現存在」の跫音はなく、不気味に首のみがぬっと伸び行く奇怪な《世界》が出現する事に為ったのである。何処も彼処も首、首、首なのである。
「現存在」は、環境が全て、人力を超えた《もの》で造られた時点で、「現存在」は轆轤首に為る事を宿命付けられてゐたのである。「現存在」はそもそも人力以上の事象に対して戸惑ふばかりで、しかし、慣れといふ《もの》は恐ろしい《もの》で、人力を超えた《もの》に包囲されると「現存在」はそれに見事に適応して見せて、そんな物騒な《世界》、つまり、移動するにせよ、建物を建築するにせよ、仮想現実に遊行するにせよ、そのいづれもが「現存在」を《死》へといも簡単に追ひやり、その時、死亡する「現存在」は人力以上の負荷がかかるので、その死体は無惨な《もの》となる外なく、それでも、「現存在」は高度科学技術文明、且つ、高度情報化社会に順応する事ばかり強ひられるのである。それが異常な事は、誰にとっても暗黙裡に了解されてゐながら、誰もが最早言挙げる事を断念し、誰もが《世界》の変化を文句も言はずにそれをすんなりと受け容れるのである。それが、どんなに虚しい事であらうがである。
さて、首のみをぐっと伸ばした轆轤首の「現存在」は、己の事を鑑みては己にぽっかりと空いた間隙に何時でも陥落する危ふさもまた持たざるを得ず、《吾》が闇に包まれた深海の水底に屹立する古木と看做す事で、辛うじて《吾》を保持する事が可能で、しかし、その実は、《反=吾》、若しくは《異形の吾》にきりきりと締め上げられ、盆栽の古木に過ぎず、その反動として己を過大評価せずば、この人力を超えた《世界》では生きてゆけないのである。何事をするにも人力を超えた《もの》によって《吾》は《吾》の事を誇大化する事で、やっと精神的平衡を得てゐるのである。
世はSpeedの時代である。そのSpeedは既に人力を超えて久しいが、そのSpeedに堪へられない「現存在」は、容赦なく取捨選択されて、Speedの世に巧く適応出来た「現存在」のみが、掘っても掘っても湧いてくる時間に翻弄されたSpeedの時代にせせこましく生きるのである。それに見事に適応したのが轆轤首の「現存在」で、肉体は既に世のSpeedに付いてゆけず、首のみが、つまり、意識のみがSpeed狂時代に適応する外に「現存在」の《存在》はあり得ない筈なのである。
例へば、自動車に対して肉体は適応出来ず、事故が起きれば、肉体は無惨な死体を晒すのみで、さて、その時は意識もまた、絶命するのであるが、しかし、《吾》といふ《念》が永劫に《存在》すると敢へて看做すと肉体と精神の齟齬は現代程酷い時代は有史以来初めてに違ひなく、それ故に、意識のみが肉体から離れた轆轤首の《吾》が出現する事に為ったのである。とはいへ、「現存在」は《吾》が轆轤首である事は露知らず、今尚、肉体と精神は太古の昔より此の方一切変はらずに《存在》してゐると思ひ込み、何の根拠もない先入観の中に安穏としてゐるが、しかし、その実は、首と胴体は伸び切る迄に伸び切った危ふい状態にあり、精神は肉体から何時でも分離するべく、肉体の隙を狙っては、絶えず首をぐっと伸ばして、肉体を置いてきぼりにする事を目論むの《もの》なのである。
さて、それ故に伸縮自在となった首を持つ轆轤首は、現代に過剰適応した事で、首のみで構はぬと開き直る事で《吾》なる袋小路の状況を打開するべく、轆轤首は、
――《吾》、轆轤首なり。
と宣言する事に為ったのである。
轆轤首が轆轤首であると開き直る事でしか、現在といふ苦境を乗り越えられぬ事が一度理解されると、生き延びる為には、轆轤首に変化するのが利口《もの》のする事だと嘯きつつも、《存在》の居心地の悪さが不安でならないのである。意識と肉体の絶望的な乖離の埋め難さに《吾》は唯唯、溜息を吐くばかりで、既に収拾不可能なこの意識と肉体の絶望的な乖離を目にする度毎に轆轤首は、唯、茫然とするしかなく、また、だからと言って何をする訳でもなく、つまり、為す術なく、《吾》の現状を渋渋と受け容れるのであるが、しかし、轆轤首たらむとする《吾》ではある一方で、轆轤首である事に不慣れな《吾》は、さて、最早、足下すらも見る事が不可能になりつつある中、後ろを振り返る事に堪へられず、只管に前のみを睨み付けながら、首のみを更にぐっと伸ばすのである。《吾》は然しながら、それが《吾》の壊滅を早める事であるとは、漠然と感じながらも、最早、前進することが已められないのである。それは、例へば時間の不可逆性と同じ種類の《もの》に違ひなく、轆轤首と一度、居直った《吾》は、最早、《にんげん》に戻れないのである。そして、此の世は「現存在」の怨嗟で満ちる事になったのである。何処も彼処も、
――《吾》は何処か?
といふ、最早、誰にも答へられぬ問ひを発しながら、首のみをぐっと伸ばし続けて、遂には《吾》の肉体を見失ふのであった。つまり、《吾》の出自は現代では行方不明となってしまったのである。
――《吾》とは《吾》だ!
と、尚も頑強に主張する《もの》も、それではその《吾》とは何ぞや、と問はれてみると、何《もの》も最早、答へに窮するのである。つまり、此の世の一番の謎は、《吾》と為ってしまったのである。そして、《吾》の内部では、
――うふっふっふっふっ。
と、ほくそ笑む何《もの》かが不意に現はれて、《吾》をからかひ始めるのであった。
――《吾》とは如何程の《もの》かね? ちぇっ、それすらも解からないとすると、《吾》とは、随分蒙昧になったもんだ。ほれ、《吾》を喰らってゐろ!
と、闇が差し出されたのである。差し出された方は一瞬茫然と天を仰いだのであるが、しかし、ままよ、と、その的を射た答へに感服し、
――成程、《吾》とは闇に違ひない。
と、その闇にしゃぶり付くのであった。そして、その闇の味といったら、無味乾燥で《吾》とは何と不味い《もの》なのだらう、と今更ながら気付くのであった。
さうなのである。《吾》は不味い闇に外ならないのである。それは、まるで綿菓子を絡め取る如くに眼前に差し出された闇を絡め取り、そして、ぺろりと嘗めるのである。そして、
――何ぢゃ、こりゃ?
と、《吾》の不味さに目が眩むのである。その伸ばし過ぎで、遂に《吾》を見失ってしまった《吾》に差し出された闇の不味さに、
――この闇から果たして《吾》なる《もの》は生まれ出づるのか?
と訝りつつも、それでも何かが生まれるかもしれぬと淡い期待を抱きながら、闇を喰らふのである。さうする事でしか、《吾》が《吾》である不安から遁れられずに、これもまた《吾》に為る修練だと肚を据ゑて、只管に、《吾》なる轆轤首は闇を喰らふのであった。
しかし、闇をいくら喰らっても、闇は増えも減りせず、元のままの闇として《存在》するばかりであった。そして、闇は幻覚剤の如くに首のみと化した「現存在」に作用し、幻を闇に浮かべるのであった。そして、あんなに不味かった闇が、或る時を境に美味しくなるから不思議なのである。しかし、幻覚の《世界》から食み出る事は不可能で、それは例へば、目が覚めるまで、それが悪夢であらうが、夢が覚めないのと同様に、《吾》は絶えず幻覚の《世界》にゐて、闇を一嘗めぺろりと嘗めれば、幻覚が現はれ、最早、《吾》はそれに鷲摑みにされて何時しか闇の虜になってゐるのである。
当の《吾》は、しかし、己が見てゐる《もの》が幻覚であるとは微塵も思ひもせず、それが現実の《世界》であると信じて疑はないのである。街を歩いてゐると、突然、声を出して喋り始める人間の如くである。つまり、街中で突然に話し出す人は、携帯電話かSmartphone(スマートフォン)に話してゐるのである。その事情が全く呑み込めぬ私は、その不穏な様に、たぢろぐのであるが、瞬時にその事情が呑み込めた私は、何をびくびくしてゐるのかと自嘲するのである。しかし、闇の虜となって幻覚を喰らふのが私における《吾》の《存在》の仕方なのである。夢において《吾》は眼前で起きてゐる事に疑ひを持たずにどんな不自然な状況でもそれを受け容れ、疑ふといふ《もの》を何処かで喪失してしまった哀れな《存在》に成り下がってしまったのである。つまり、轆轤首にとっては、実体はあってもなくても別にどうでもよく、映像として《世界》が成り立ってゐれば、それが全てなのである。轆轤首が既に異形の《もの》なれば、それは必然であって、轆轤首とは何の事はない、《世界》が自己完結してしまった閉塞の状態の事に過ぎぬのである。
ところが、現実といふのは、酷い《もの》で、或る日、突然に《吾》に牙を剥き、襲撃するのである。幻覚に酔ひ痴れた《吾》は、さて、何が起きてゐるのか全く解からずに、不意に絶命するのである。その死に様が何とも痛痛しく、哀れに思ふのであるが、遂に、死すまで、幻覚の中から出られなかったその轆轤首は、ところで、何の為に、生きてゐたのか皆目解からず、また、《他》の轆轤首にとって《他》の《死》は、最早、何の恐怖も齎さずに、誰にとっても無関心な出来事として、片付けられる運命にあるのである。そもそも幻覚の中に閉ぢ籠った《吾》において、現実は、あってなきが如く有名無実な《もの》と化してゐて、誰の《世界》も摺り合はせが行はれていない為に《世界》は轆轤首の数だけてんでんばらばらに《存在》し、それは所謂、対幻想には決してならない類の何かに全く変質してしまってゐるのである。
そして、轆轤首は《個時空》としてしか呼べない独りぽつねんと大海にゐる事すら気付かぬ《もの》として、《世界》の中に《存在》するのである。時代は何時しか全肯定の時代に突入し、何《もの》も、最早、《世界》に対して疑ふ事を已めてしまひ、《個時空》の中に閉ぢ籠っては突然、
――ぶはっはっはっはっ。
と嗤ひ出すのである。それがいかに不自然だらうと、最早、誰も《吾》の《個時空》に興味などないので、仮令、《吾》が嗤はうが、そんな些末な事に関はる暇を失くした轆轤首の有象無象がうようよしてゐるのである。ところが、《世界》は、最早、共通項といふ対幻想が成り立たない状況下で、いくら轆轤首が《存在》しようがそれらは、全くぶつかる事がなくするりするりとすり抜けて、幻覚のみが絶えず《吾》の眼前に《存在》するばかりなのである。何《もの》にもぶつからぬといふ事は、轆轤首にとって《他》は《非在》なる《もの》としてしか、最早、表象されないのである。
何もぶつからないといふ事は、或る種の悲劇に違ひなく、其処は永劫に《他》は《存在》しないといふ事を意味するのであった。ぶつからないといふ事はさういう事なのである。つまり、何にもぶつからない《吾》は、遂に《他》の《存在》を《個時空》から追ひ出したのである。《吾》は《反=存在》と化す事で《他》の《存在》から遂に逃げ果せたのである。しかし、闇を嘗めながら独り幻の中で右往左往してゐる《吾》には《他》を《個時空》から追ひ出した事には全く思ひ至らずに、只管、幻覚の中でドン・キホーテの如くサンチョ・パンサと共に化け物と格闘してゐるのである。それは、轆轤首たる《吾》にとっては紛れもない《他》であって、実体ある《他》よりも幻の《他》の方が始末に負へない難物なのは、《吾》が《死》すべき、否、《吾》が《死》んでも尚、《吾》に付き纏ふ幻の《他》は、しかし、既に《死》した《もの》の類に違ひないのである。つまり、轆轤首が犇めきながらも互ひに全くぶつからない《個時空》にゐる《吾》にとって《他》は《吾》のみにしか見えない《存在》であり、奇妙な事に《吾》はその事に薄薄気が付いてゐるのである。《吾》の《個時空》は糸が切れた凧の如くに《世界》がぶち切れた《もの》で其処には実体ある《存在》は、最早、《存在》しないのであるが、しかし、《吾》は幻にのみ戯れる事を無意味と気付きながら、それを已めようとはしないのである。何故なら、それが楽だからである。それ故に《吾》は敢へて《個時空》を外部に開かずに内部にのみ目を向けさせる事で自足するだけで、意図してゐるのかどうかは解からぬが、しかし、《吾》を内部にのみ拘泥させる事にかけては、絶妙この上ないのである。それは、《吾》が闇をぺろりと嘗めて、麻痺してしまった感覚において、最早、《他》に対応する事は不可能なのである。不感症。「現存在」たる轆轤首にとって《吾》を端的に言へば、それは不感症の《存在》なのである。それは当然の事である。ぐっと首を伸ばしに伸ばすには、既に《吾》の感覚は麻痺してゐなければ不可能で、蜿蜒と人工の紋切り型の《世界》が続く郊外で生きてきた轆轤首にとって己がその《世界》で存続させる為には、感覚を如何に麻痺させるのかの競争に時代は突入した事に知らぬは《吾》ばかりなのである。その結果、《吾》が不感症なのは、必然で、不感症となり、無感覚でなければ、《世界》の中では、生き残れなかったのである。それは、何とも皮肉な事で、楽を追求する事は、不感症になる事であったのである。しかし、時既に遅きに失し、最早、元には戻れない処まで、事態は進行してしまったのである。肉体と精神の埋めようもない乖離は、事此処に至りて、ぶった切られてしまったのである。つまり、轆轤首は自らその首をぶった切って《吾》を浮遊する《もの》とする事で辛うじて此の世に《存在》出来得たのである。一見それは哀しい事のやうに思へるのであるが、さにあらん、《吾》は楽を飽くまで求める故に喜んで《吾》は首をぶった切ったのである。さうして拓けた《世界》は徹頭徹尾《吾》の幻覚の《世界》であり、その《世界》はとにもかくにも楽なのである。何故に楽なのかと言へば、《吾》の匙加減で《世界》は如何様にでも変はる事に首のみと化した《吾》は知ってしまったからである。しかし、それは、大いに矛盾してゐる事で、幻がそもそも《吾》の匙加減でどうにでもなるならば、幻の《他》もまた、《吾》の匙加減でどうにでもなる筈なのであるが、事態はさにあらぬのである。或る種の被害妄想に囚はれた《吾》は、見渡す限り人工の《世界》に生きる事を強要された《吾》にとって、《世界》、若しくは《他》は存続する《吾》を襲撃する《もの》としてしか最早把握出来ないのである。
《世界》の襲撃は何時も不意である。《吾》は不意に滅する事が日常に変じてしまった現代において、自然災害ばかりでなく、不慮の事故によっても不意に《死》すのである。それが毎日、時と場所を変へて起きてゐて、《吾》は「現存在」の《他》の《死》に対して、最早、薄情な程に無関心で、つまり、《吾》は不感症に陥ってゐるのである。しかし、不感症はDemerit(デメリット)ばかりでなく、途轍もない効能があるのである。それは、何度も言ふが楽を《吾》に齎すのである。《吾》の幻覚の中に立ち現はれる《他》は、既に《吾》に解釈された何かであって、それは、決して謎である「現存在」としての《他》ではなく、《吾》が思ふ事を率先して行ふ幽霊の類の何かなのである。それは、《吾》が轆轤首である事と無関係ではなく、《吾》が異形の《もの》に変化したといふ事は、《世界》に何《もの》にもぶち当たる事なく孤軍奮闘するといふ、第三者の眼から見れば全く馬鹿げた振る舞ひに終始する被害妄想の域から一歩も出ずに、《個時空》を空回りさせながら、不意に《死》すのである。既に、轆轤首の首を自らぶった切った《吾》は、最早、重力の魔から遁れ出て、地から浮遊して、ゆらりゆらりと街を彷徨ふのである。然しながら、その街は既に此の世には《存在》しない架空の街でしかなく、《世界》は完全にその出自を失ふのである。それでは、その《吾》にのみ有効な《世界》とはどんな《世界》かと言へば、それは、一見《吾》の意思とは無関係に《もの》が《存在》してゐるやうに見えながら、裏では、《吾》の意思一つでどうにでもその相貌を変へる《吾》と連動した《幻=世界》なのである。其処には当然、《存在》は《存在》せず、《非在》ばかりがあるといふ皮肉な《世界》があるのみなのである。
自ら首をぶった切った轆轤首の《吾》は、本来的な《世界》とは無関係に脈打つ《個時空》といふ《幻=世界》を携へながら、自らの幻に陶酔するのである。それが、首をぶった切った痛みを止める鎮痛剤、否、麻酔薬に違ひなく、《吾》の《幻=世界》を表象させる悪循環に自ら進んで突き進む《吾》の悲哀は、誰の眼にも明らかなのに、しかし、《吾》のみは、それが悲哀に満ちてゐるなどと微塵も思はずに、只管、その《幻=世界》に対して、
――《吾》とは何ぞや?
と謎かけをしては、独りほくそ笑むのである。さうすると、《吾》は、然しながら、余りに不意に《死》すのである。それは、明らかに《幻=世界》の虜になってしまって《外=世界》に対して全く無関心な《吾》の至るべき終着点であり、また、首のみとなって此の世を浮遊する《吾》は、敢へて自ら《自死》の道を選ぶのである。つまり、不意に《死》す《吾》は、因果律の束縛から遁れ出たやうに見えるのであるが、何の事はない、因果律を失ふ事は、不意に《死》す事を受け容れる事でしかないのである。不慮の事故死などは、天災とは別に毎日、日常の事として此の世の何処かで起きてゐて、それに全く無関心な《吾》は、一見因果律の呪縛から遁れたやうに見えて、その実、《存在=死》の如く、《吾》が《吾》に何が起きてゐるのか把握する前に日常の中で《死》んでゆくのである。天災ならば、多少の猶予を与えて呉れるのであるが、人災だとそんな猶予はなく、大概《即死》なのである。つまり、《個時空》で《幻=世界》の楽を追求する《吾》は、或る種の地獄と地続きな本来的な《世界》として出遭った刹那に《即死》するのである。日常から《死》を排除したかに見える《幻=世界》は、何の事はない、《死》を日常に潜ませただけの危ふい《死=世界》、つまり、《黄泉の国》と表裏一体なのである。
しかし、《黄泉の国》と日常は地続きなのは、太古の昔より変はりはないのであるが、しかし、現代社会では、《幻=世界》に閉ぢ籠る故に、そのふり幅が途轍もなく大きく、何の変哲もない日常が一瞬にして地獄絵図に姿を変へるのである。首をぶった切った轆轤首たる《吾》が一度、死神に睨まれたならば最後、確実に《死》すのである。それだけ、肉体と精神が乖離した轆轤首故に、精神に置き去りにされた肉体は、精神の有様に関はらず一歩でも動くと、それは《死》を意味し、つまり、轆轤首と化した《吾》は蝸牛の如くゆっくりとしか動けぬ故に、このSpeed狂の世の中では、肉体程、疎ましい《もの》はなく、肉体の《存在》を忘れられる《幻=世界》で、只管、《吾》に酔ひ痴れるのである。肉体は、殆ど動けぬ故に、《幻=世界》は迫力満点の視聴覚にのみに訴へかる《世界》なのである。しかし、その《世界》はMonitor越し、またはScreenでしか見られぬ《吾》と断絶した《世界》であり、よくよく見ると轆轤首の首のみとなった《吾》は、その《幻=世界》から疎外された《存在》である事が解かるのであるが、《吾》は何時迄もそれに気づかぬ振りをして、只管に《幻=世界》に《吾》を忘却する事ばかりを追求するのである。
しかし、肉体と精神が全く乖離してしまった轆轤首の《吾》は肉体が不動の《もの》へと変容してゆく事には全く無頓着で、もう肉体は為すがままに抛っておくに限るとばかりに、最早、《吾》に顧みる事はなくなって久しいのである。何故にそれが可能かと言へば、全ては《吾》といふ闇を手にした時にその端緒があり、闇さへぺろりと嘗めてゐれば殆どの肉体的な欲求は満たされてしまふからなのである。例へば、食欲や性欲は闇を嘗めてゐればそれは夢想の中で満たされてしまひ残るは精神的な欲求のみなのである。精神的な欲求は、しかし、それはほぼ全てが《死》への欲求に根差した《もの》でしかなく、その出自は既にフロイトによって暴かれてゐるのであるが、それによって善しとしない轆轤首の《吾》は精神的な仮死状態を何度も経験して、これは違ふと、何度も首を傾げては、満たされない《吾》の精神の欲求が何なのかは《幻=世界》の中においては見失ってゐるのである。それは、至極当然の事で、精神的な欲求とは、換言すれば、それは肉体的な欲求の事でしかなく、肉体が仮死状態を味はへば、大概の精神的欲求は満たされるのである。つまり、心身の一致こそが《吾》の窮極の欲求であり、それが成し遂げられるのは、《死》のみなのである。何の事はないのである。《吾》とは元来未出現の《もの》でしかない故に原点回帰が《吾》の憩ひであり、それを単純に成し遂げるには、《死》する事が最も手っ取り早いのである。しかし、《吾》は一方で、それは本当に《死》への欲求で満たされるのかと疑問を呈してゐて、《吾》の欲求とは、詰まる所、《生》への欲求、それは飽くなき欲求に違ひないと思ふのであった。
それは、当然の事なのである。《幻=世界》に閉ぢ籠った故に、《吾》は《生》を生きてた事がそれまで一度もなく、そもそも《生》といふ《もの》を未体験のまま《幻=世界》に反映されてしまふ故に、何時迄経っても《幻=世界》において《吾》は《吾》の望みを満たされる事はないのである。《幻=世界》といふ余りに個人的な孤立した《世界》において、その《世界》の造化は、徹頭徹尾、《吾》であり、しかし、をかしな事に《吾》は未来永劫に亙って《吾》に対して満足する事はなく、《吾》に満足を齎す《もの》は、《神》であり《自然》に外ならないのである。つまり、それは、徹底的に《吾》の思ひとは無関係に齎される僥倖の如き《もの》で、それには徹底的に《吾》が疎外された形で成し遂げられる《もの》なのである。それは何故にかと言へば、所詮、《吾》が考へる事は、底が知れてゐる程に浅薄な事でしかなく、それに全く深みはないからなのである。《神》の、《自然》の為す業は《吾》から見れば嘆息しか出ない素晴らしい《もの》で、それに《吾》がいくら対抗しようとしても骨折り損のくたびれ儲けなのである。つまり、《吾》がいくら手慣れた業を持ってゐようが、《神》、または《自然》の諸行には敵はないのである。
つまり、《神》、若しくは《自然》と《吾》との対決は関しては、初めから勝負は決まってゐて、《吾》が《神》、若しくは《自然》に敵ふ筈はないのである。然しながら、轆轤首の首をぶった切った《吾》は、此の《世界》の転覆ばかり妄想するのである。それが、《幻=世界》相手ならば至極簡単に出来さうな《もの》に一見思へるのであるが、《幻=世界》の転覆はそもそも不可能なのである。何故ならば、《幻=世界》の転覆とは、即ち《吾》の転覆に外ならず、《吾》が《吾》の転覆を試みた処で、そんな猿芝居のお足は知れてゐて、また、そんな事は口が裂けても言へる《もの》でなく、そして一度、そんな馬鹿げた妄想に酔ひ始めると、《吾》は益益、《吾》に酔って、《幻=世界》に惑溺するのである。
しかし、《他》に全くぶつからないその《幻=世界》に《存在》する《吾》のあり方を訝る《吾》がゐないでもなかったのである。《吾》が伸び切った首をぶった切った刹那、《吾》を訝る《吾》の《存在》に気付いてゐる筈なのであった。その《吾》は、只管に黙して語らぬ《もの》として《存在》してゐたのであるが、その沈黙が不気味に《吾》には感じられ、しかし、《幻=世界》に楽を見出してしまった《吾》は、その沈黙して何も語らず、《吾》の頭蓋内の脳といふ構造をした闇たる《五蘊場》に闇のまま闇と同化して蹲るその《吾》を本能的に訝る《吾》に、
――しまった! 見られた!
と思はず不意を衝かれて楽を堪能する《吾》は、闇と同化した《吾》の目には全く見えぬながらもその《気配》は感じ取ってゐた《そいつ》、つまり、《吾》の睥睨にぎくりとするのであった。
一体何を見られたといふのであらうか? 《吾》は、《五蘊場》の闇に蹲るその《吾》を訝る《吾》の気配を感じた刹那、反射的にさう喚いたのである。その《吾》を訝る《吾》は《吾》の鬼子に違ひなく、《吾》は《吾》を訝る《吾》を確かに《吾》だと思ふのであったが、しかし、その《吾》を訝る《吾》は、《吾》と一致する《存在》では決してなく、むしろ、それは《吾》の異端に違ひなかったのである。そして、異端である事が《吾》には致命傷で、何か新たに始まるのは、必ず異端からで、《吾》に《吾》を訝る異端の《吾》が出現したといふ事は、《吾》の変態も近しいかもしれぬ暗示に思はぬ事もなかったが、唯、私はその《吾》を訝る《吾》からは目を背けて臭い物には蓋の如く、闇中に《吾》を訝る《吾》をうっちゃっておくしかなかったのである。しかし、暫くすると、その《吾》を訝る《吾》は発酵を始め、気泡を発するやうになり、また、不快な臭いを辺りに漂はせ始めたのである。それでも尚、《吾》はその《吾》を訝る《吾》を抛っておいたのである。すると、その《吾》を訝る《吾》は発酵熱で仕舞ひに蒸発してしまったのである。
――しまった!
これはとんでもない事態を招いてしまったと、《吾》は天を仰いで嘆息するばかりなのであった。それといふのも、蒸発した《吾》を訝る《吾》は《五蘊場》の闇全体に充満し、遍く《存在》する《もの》へと変化したのである。それは、《吾》を真綿で首を絞めるやうに《吾》をぎりぎりと追ひ詰めたのである。何の事はない、《吾》は《幻=世界》から追ひ出される羽目に陥ったのである。これは、全く喜劇でしかなく、《吾》から追ひ出される《吾》とは、一体何なのか、自ら問はずにはゐられず、また、何故に《吾》は、《吾》を訝る《吾》に追はれなければならぬのか、その顚末に、
――わっはっはっはっ。
と、嗤ってはみるのであるが、どうしても納得が行かぬのであった。しかし、《吾》を訝る《吾》は《吾》に対しては問答無用で、《吾》の殲滅のみを《存在理由》としてゐるかの如く、《吾》の《死》をのみ、只管に追ひ求めるのであった。然しながら、追ひ詰められたとはいへ、尚も存続を望む《吾》は、最期に破れかぶれの自棄のやんぱちで、
――破!
と叫んだのであるが、しかし、その途端に、一つの石ころに変化してしまったのである。
――何たることか――。
既に時遅く、爾来、《吾》は《五蘊場》に一つの石ころとして闇の中に蹲る事を強要されたのであった。
石ころに化した《吾》は、その刹那、時間の進み具合が途轍もなくゆっくりとなり、その《吾》は止まってしまった現在に置かれる如くにあるのみなのであった。一方、《五蘊場》に遍く《存在》する《吾》は、《吾》を訝る《吾》故に絶えず、《吾》に対して反語を投げかける《吾》として《五蘊場》に《存在》する事になるのであるが、しかし、それは少し話が進み過ぎである。首をぶった切った轆轤首の《吾》の意識が、石ころとして頭蓋内の闇たる《五蘊場》に蹲る事態に《吾》は、面食らったのである。ところが、途端に石ころの《吾》に流れる時間が途轍もなくゆっくりとなった事で、《吾》の思考は一方でぴくりとも動かずに、唯、一点に蹲るばかりなのであった。その代はり、《吾》を訝る《吾》が石ころといふ《存在》の出現により《五蘊場》の平衡状態が崩れ、石ころの《吾》の周りにその《吾》を訝る《吾》が渦を巻き始めたのであった。それは、一つの渦巻銀河の出現の如くなのであった。石ころの《吾》の周りを渦巻き始めた《吾》を訝る《吾》、所謂、《反=吾》は、渦巻く事でStar burst(スターバースト)の如く《吾》たる《もの》の微細粒子が爆発的に出現し、渦巻く《反=吾》に《吾》が無数に出現したのであった。さうして新たな《吾》が相転移を起こして《吾》なる《もの》、つまり、《五蘊場》が一つの渦巻く時空間へと変質を遂げたのであった。
ところが、相転移を遂げた《吾》は、赤子の如く《吾》に対して何事も言葉を発する事が出来ずに、唯単に、
――だぁ、だぁ、だぁ。
と、音を発するのに数年の歳月が必要なのであった。つまり、《吾》が再構築されるのに何年もの星霜が必要なのであった。その間、《吾》の思索は深まらなかったかと言へば、そんな事はなく、《五蘊場》が渦を巻いた途端にぶった切られて抛っておかれた胴体に再び私の首はくっ付いて、《吾》なる《もの》は人形(ひとがた)に再現される事になったのである。或る種の失語症のやうな中に置かれた《吾》は、身体感覚が研ぎ澄まされることに相成ったのである。言語以前のそれらの感覚は、言葉として昇華する事はなかったのであったが、皮膚感覚として記憶される事になるそれらの感覚は、《五蘊場》の渦を更に渦巻かせて身体が何事かを《世界》に対して感じる度毎に小さな小さな小さな《吾》が綺羅星の如くに《五蘊場》に出現し、その《吾》が或る種の記憶素子の如くに記憶を留める役目を果たしたのである。しかし、全体としてそれらの微細なる《吾》共が繋がる回路となるにはまだまだ時の経過が必要であったので、《吾》には無数の言語化されない記憶の断片を抱へ込みながら、只管、《世界》を受容するのを旨とするのであった。それは、外部刺激をのみ感じる事に驚いてゐた時間なのであった。身体の感覚が研ぎ澄まされれば研ぎ澄まされる程に《世界》と《吾》との合一感は深まるばかりで、それは《吾》にとって快楽として記憶されるのであった。つまり、言葉を獲得する迄、《吾》を肯定する作業を行ってゐたのである。これは《反=吾》が石ころの《吾》の周りに渦巻き微細なる《吾》が爆発的に出現した事から必然の事であり、《反=吾》から《吾》へと相転移した《吾》は《吾》を全肯定する《存在》なのは道理に敵った事態なのであった。
《世界》と《吾》との合一感を育むそれら研ぎ澄まされ行く身体感覚は、しかし、余りに現実的であり、其処に妄想の類が入る隙はなかったのである。これが、《吾》の揺籃期とするならば、私は何年も言葉を発せられなくなった代はりに《世界》と《吾》との至福の合一感の中に《存在》する《吾》に満ち足りてゐて、それ故に言葉の《存在》を敢へて求めなかったのである。
その《吾》の揺籃期は何と満ち足りてゐたのであらうか。此の世に誕生、若しくは出現したばかりの《存在》は、皆、満ち足りてゐる筈に違ひないのである。それは、《吾》なる意味が《吾》とはっきりと意識されずに、さりとて《世界》と《吾》が全く同一の《もの》ではなく、良い塩梅で《世界》と《吾》の距離は保たれていて、それ故に《吾》に対して少しでも摂道し、ずれが生じてそれが齟齬を来した場合、赤子の《吾》は、
――うぎゃあ、うぎゃあ、うぎゃあ。
と泣き喚いて《他》により《吾》の欠乏した《もの》を満たしてくれるのであるから、《世界》と《吾》の間に不和が生じてゐるなどとは考へられ辛いのである。埴谷雄高は赤子が言葉を獲得し、
――うぎゃあ、うぎゃあ、うぎゃあ。
と泣き叫ぶその「不快」を語り果せれば、それは全く人類の見知らぬ存在論足り得るといった趣旨の事を述べていた筈であるが、それは、思ふにまったくの誤謬で、赤子の《存在》はそれが何であれ、満ち足りてゐるに違ひないと思へて仕方がないのである。揺籃期における《世界》と《吾》の微妙な距離感は、其処に言語がまだ獲得出来ぬ故の事であって、《吾》が《他》の口調を真似て次第に言語を獲得してゆく過程で、《吾》は魂魄の微細が眺められるやうになり、《世界》と《吾》の些細な齟齬の発生が恰も此の世の《吾》に対する責苦の如くに受容し、さうして、《吾》なる《もの》は絶えず《吾》なる事に我慢するに違ひないのである。
さて、轆轤首の首をぶった切って《五蘊場》の中で石ころに変化した《吾》は、ぴたりと時間が止まったかのやうにその流れは途轍もなくゆっくりで、
――《吾》。
といふ言葉すら発するのに何十年もかかる次第になったのであるが、その言葉を知りながらも、最早、
――《吾》。
と語る事すらままならなくなった石ころの《吾》は既に《吾》と《世界》の関係に思ひを馳せる事は何万年単位で考へねばならず、その《吾》は《吾》が《死》しても未来永劫に亙って此の世に残るに違ひないのであるが、しかし、石ころの《吾》を核として渦を巻く事で《五蘊場》に微細なる《吾》といふ記憶素子を誕生させつつ、それら無数の《吾》共は脳細胞の如くに繋がる迄には、まだまだ時間がかかる状態の中に《存在》した《吾》は、然しながら、
――《吾》。
といふ言葉を知らないが故に無上の喜びに浸る事が可能となったのである。それまで首を自らぶった切った轆轤首として、絶えず、《吾》と《吾》の不和、将又、《世界》と《吾》との不和に終止符を打てずに、結局の処、絶えず《吾》に躓いてゐた《吾》は、石ころに変化した事で、《吾》と《吾》の不和、将又、《世界》と《吾》の不和どころの話ではなく、《吾》における時間の意味を《五蘊場》に蹲る事で、全身全霊で受容する或る何かへと変貌を遂げたのは言ふまでもない。《五蘊場》の渦巻の核たる石ころの《吾》は、時間により半ば強引に《吾》に対峙する《吾》といふ構図を剥ぎ取られ、まるで中有に抛り出された如くに、
――《吾》。
とすら発せられぬ時間の流れに留め置かれたのであるが、しかし、それは、それで《吾》にとっては途轍もなく居心地が良かったのである。何故ならば、《個時空》といふ或る意味非常にせっかちな思考を容れる時空間からの解放を、石ころと化した元轆轤首の首であった《吾》は為されたのであり、《個時空》からの解放とは、対《世界》にとっても、対《吾》にとってもそれは自由自在を意味する事へと結び付き、時間が途轍もなくゆっくりと流れる石ころの《吾》にとって、《吾》は絶えず時間が途轍もなくゆっくりと流れるが故に《個時空》の時空間の地平線を凝視してゐられたのであった。それは、無上の喜びに違ひなかったのである。何故ならば、時空間の地平線とは、《吾》の涯の事に外ならず、それを知り得れば、《吾》はどれ程に《吾》に巧く対峙し得るのか、それは、筆舌尽くし難い途轍もなく居心地が良い《吾》の《存在》のあり方に違ひないのであった。
途轍もなくゆっくりと流れる時間の中にゐる《吾》の思索は、決して言語を伴った《もの》ではなかったのであるが、感覚的な、もっと正確を期せば、皮膚感覚は、言語化されずに感覚として《吾》に留まり、それは彗星の如く尾を曳き、皮膚感覚が肉体の形相を敏感に意識させ、とはいへ、それは絶えず言語化する事を失敗する形で、《吾》の《五蘊場》に蓄積されゆき、くっきりと《吾》の肉体は、《五蘊場》に表象されるのであった。つまり、言語化されずとも、心像としてあらゆる《もの》が《五蘊場》に刻まれ、その方法において、私と《世界》との間に不和を全く生じずに、吾が表象は吾が肉体にぴたりと重なり、といふ事は《吾》は未だぴくりとも動かぬ仮死状態のままに、《世界》に大の字になって横たはってゐたに過ぎなかったのである。そして、《吾》は全身、《世界》に対するCensor(センサー)と化してゐて、《世界》の変容のみによって《吾》の表象は漸く保証されるのであり、《世界》の変調によってのみ、《吾》は《吾》の《存在》を認識出来るのであった。つまり、《世界》の変調を感じ取る《吾》の感覚は、《五蘊場》においては渦巻の中の《吾》といふ綺羅星となるのであったが、それらが、渦を巻く事によって、言語化されずとも統覚されいて、《吾》といふ《もの》と《世界》といふ《もの》はある程度類型化される事になるのである。とはいへ、それは、非常に大雑把で、大雑把故に《吾》と《世界》の合一感は、底知れぬ喜びを《吾》に齎すのであった。つまり、大雑把に類型化するといふ作業を仔細に眺めてみると、それは大変に巧妙なものなのであって、《吾》といふ《もの》、また、《世界》といふ《もの》を大雑把に類型化して認識するとは、その類型化した形相がFractalである事に合点が行く筈なのである。然しながら当の言語を未だ獲得出来ずにゐる《吾》は、そんな事は微塵も知らぬのであるが、しかし、《吾》は《五蘊場》の微細な微細な微細な《吾》として、また、或る種の記憶素子として記憶を留める役目を果たすその《吾》が、Fractalである故に、その微細な微細な微細な《吾》は、《吾》として微塵も疑ふ事無く、それをして《吾》と看做すのである。とはいへ、それは、未だ言語化されずにある故に《吾》を未来永劫に探し求めるやうに《世界》を彷徨ひ歩くのである。言語化とは其処に或る種の断念がなければ全く成立しない《もの》に違ひなく、未だ言語を失ったままのその首の繋がった《吾》は《吾》である事を全的に肯定する筈なのである。例へば胎児は未だ言語化されぬ《吾》との全一感によって心身共に満たされてゐる筈で、さうでなければ、胎児は子宮の中で間違ひなく自死する筈であるが、大概の胎児は産まれる事を待機しつつ、未だ言語化出来ずともにその朧な《吾》といふ意識の覚醒した《吾》の万能感に途轍もなく近い満足感を得てゐる筈で、さうでなければ、《吾》は此の世に誕生する筈はないのである。
『初めにlogos(ロゴス)ありき』といふのは、ヨハネの福音書たる聖書の書き始めであるが、それは、恐らく全くの間違いであって、『初めに《吾》ありき』に違ひないのである。当然その《吾》は未だ言語化されるには遠い、遥か以前の《吾》の事であり、その状態の《吾》は全能なる《神》の如く此の世未然の子宮の中の羊水にたゆたってゐるに違ひないのである。言語なき故に、《吾》は万能である何かであって、その記憶の残滓は、後に言語を獲得しても《存在》する筈で、さうでなければ、《吾》は《吾》に踏み迷って《吾》に絶望する筈はないのである。
ところが、言語を獲得しない時間といふのは、思ふに途轍もなくゆっくりと流れる《もの》であって、つまり、言語化されぬ故に覚醒未然の《吾》といふ意識はゆっくりとその頭を擡げるのであって、その中で《吾》は《吾》である事を魂魄で以ってぢっと味はふのである。さうする事で、《吾》と《世界》との彼岸に《吾》の思索は跳躍し、その彼岸における幸福感を《吾》は独り占めするのであった。
《吾》と《世界》との彼岸とは《個時空》における時空間の地平線の事に相違ないのであるが、ところが、それが何であるのかを言語化するには曖昧な《もの》で、唯、直感的にそれは感じ取れる何かであり、未だ言語を獲得出来ぬ《吾》において、その《吾》と《世界》との彼岸とは、言語を獲得出来ぬが故に味はへる万能感においてのみ直覚出来る《もの》なのであって、その残滓は言語を獲得しても尚、《吾》には仄かに残ってゐる筈で、残ってゐるが故に《吾》は《吾》を或る限界がある《存在》として把握するのである。
まだ、《吾》が覚醒する以前の幽かに《吾》なる《もの》が《吾》の《五蘊場》に頭を擡げた時、《吾》の万能感が《自然》な《もの》として《吾》は直覚するに違ひない。例へば羊水の中の胎児の《五蘊場》は未発達故に、そして、回路が未完成故に《吾》は万能感を感ずるのである。胎児は、或る時、手足を動かし、眼玉をかっと見開き、闇を凝視するに違ひないが、この場合でも《五蘊場》の構造が未完成故に、《吾》の行為に不自由が生じてゐないなどとは感じる筈もなく、例へば眼玉をかっと見開くだけでその万能感は得も言へぬ快楽を《吾》に齎すのである。それ迄、眼玉をかっと見開く事すら出来なかった胎児が、初めて眼玉をかっと見開く事が出来たのである。その万能感は推して知るべし《もの》で、それは、快楽に違ひなく、快楽故に微細な微細な微細な《吾》といふ記憶素子に記憶されたその万能感は、更なる快楽、つまり、万能感を味はふべく、足をとんと動かせるやうになるのである。さうやって、快楽の積み重ねによって《五蘊場》は満たされ、胎児の《五蘊場》は言語を獲得してゐない故に、至福に満たされた《もの》として羊水にたゆたふのである。それは、多分、此の世に誕生してしまふ胎児において、最早、二度と訪れない至福の時間なのであって、失楽園のMotif(モチーフ)は胎児における万能感の喪失によるところ大に違ひないのである。それ程に脳が未発達故の《五蘊場》が未完成ならば、羊水にたゆたふ胎児は、当然、浮遊してゐる中にあるのであるが、その状態が《自然》故に、羊水にたゆたふ胎児の万能感は、その羊水に浮遊してゐる、例へば自由落下中の浮遊感にも似たそれは、胎児の万能感の礎なのである。未だに重力の《存在》を知らない胎児において、落ちるといふ感覚は皆無であって、たゆたふ事に万能感の秘密が隠されてゐるに違ひなく、その感覚は未だ海中に留まる原=生物の原初的な感覚の発露に相違ないのである。
存分にその原初的なる感覚を味はひ尽くす羊水中の胎児はその万能感に溺れる筈である。それ程迄に未完成といふ事は万能感に近しい《もの》なのであって、つまり、《五蘊場》が未完成であればある程に万能感は大きく、それは、例へば《五蘊場》のない《存在》において無限大に万能であるといふ事を暗示してゐるのかもしれず、仮に《五蘊場》=脳といふ余りに強引な考へ方を用いれば、脳がない《存在》において万能感は∞に達する筈で、つまり、《もの》として此の世に《存在》する《もの》は全て得も言へぬ万能感の中にあるに違ひないのである。つまり、言葉など持ってしまったが故に「現存在」は堕天使の如く地上に落下し、つまり、出産と同時に途轍もない不自由を感じ、そして後は、その不自由に馴致させられるばかりなのである。つまり、言葉の発現の端緒に《吾》の万能からの逸脱があり、或ひは、羊水の中では、無限の万能感の中にあった《吾》は、此の世に産み落とされると同時に、その万能感を根こそぎ剥ぎ取られる事を意味し、それ故に嘗てあった《吾》と現にある《吾》の隔絶により、赤子が言語を獲得する原動力になってゐるのかもしれないのである。つまり、言葉とは、《存在》の不自由を指し示すBarometer(バロメータ)に過ぎず、《存在》の不自由さを言ひ当てるべく、此の世に発生した《もの》なのかもしれなかったのである。
更に言へば、卵子と精子が受精した刹那こそ、万能感の極致に違ひないのである。何故かと言へば、受精卵こそ何にでも変容可能な《もの》として此の世に出現した《存在》と言へなくもないのである。其処で受精卵において卵子と精子の受精は、偶然の仕業か、元元決まってゐた受精、即ち、必然の仕業なのか判断に困るのであるが、しかし、受精が偶然であらうが、必然であらうが、卵子と精子が受精した刹那こそが、此の世で味はへる最高の万能感に違ひないのである。受精するべく準備をしてゐた卵子と、卵子目がけて邁進する精子共の中からたった一匹の精虫が受精するのである。其処には、選別して《死》する事を余儀なくされた卵子と、《吾》に為れなかった夥しい数の精子の《死》が横たはっているが、受精そのものは、得も言へぬ満足感に違ひなく卵子と精子が宿命付けられてゐる使命を果たした満足感と言ったらむべなるかな、なのである。
さて、それでは、受精卵が遺伝子の発動により、細胞分裂する時はどうであらうか。そもそも細胞分裂に快不快が《存在》するのか不明なのを承知の上で敢へて言へば、それは当然快楽に違ひないのである。そもそも細胞分裂して《一》であった受精卵が《二》に分裂する様は、さて、其処に《他》を見るか《吾》の鏡面を見るか、興味は尽きぬ事であるが、多分、《一》であった受精卵が《二》に分裂した時、《吾》は《吾》と《他》の両方を《二》に分裂した受精卵に見ている筈なのである。つまり、《二》に分裂した受精卵のどちらが《吾》であり、どちらが《他》なのであるかは既に不明確なのである。細胞分裂とは《吾》の拡張であるとともに《他》の受容なのである。多分、全てにおいて曖昧模糊な筈なのである。《吾》である自覚は未だ芽生えてをらず、さりとて受精において《吾》は《吾》である事を思ひ知らされ、その《吾》は何かが大分欠けてゐる事を知るのである。さうして遺伝子が発動し、細胞分裂を遂げるのであるが、其処には絶えず《吾》と《他》の葛藤があり、それ故に、細胞分裂する《吾》は、心地良い筈で、つまり、受精卵といふ万能感に満ちた《もの》は、その万能感を味はふべく、細胞分裂し始めるのである。多細胞生物は単細胞生物である事を已めたのは細胞分裂に《吾》が味はふ快楽があってこそと看做せなくもないのである。細胞分裂に快楽がなければ、此の世に多細胞生物は出現することはなく、また、環境が単細胞生物から多細胞生物の出現を強要したとしても、それは、しかし、多細胞生物の存続を約束したものではなく、其処に多細胞生物は多細胞故に《吾》を自覚する離れ業をいとも簡単に成し遂げ、また、其処に快楽がなければ、多細胞生物が今もって存続することはないのである。
さて、『初めに《吾》ありき』と、さも知ってゐたかの如くに《吾》なる《もの》を想定してみたのであるが、《吾》といふ感覚は卵子と精子が受精した刹那、最も体感する感覚に違ひないのである。何故ならば、受精した事で《吾》は定まるからである。仮令、それが死産であったとしても受精卵にこそ《吾》は万能感に満ち足りた《吾》を味はってゐる筈なのである。そして、万能感に満ち足りた《吾》たる受精卵はその《吾》を実現するべく、細胞分裂を繰り返すのである。それは、全て《吾》たる《もの》の実現故になのである。
爆発的に細胞分裂してゐる時の《吾》程、《吾》である事に満ち足りた《吾》はもしかすると《存在》しないのかもしれないのである。それ程、たった《一》の受精卵から多細胞生物へと為り行くべく、細胞分裂を繰り広げる《吾》は、いづれの細胞にも等しく《吾》としての《念》が宿ってゐる筈で、それ故に《一》の個体の「現存在」が羊水の中に出現するその細胞の成長過程にちゃんと《吾》は宿り、その個体の細胞一つ一つにも、そして、個体を一つの《もの》と看做しても等しく《吾》といふ《念》が宿り、やがて《吾》が《吾》として目覚める素地が形成されるのである。
そして、細胞分裂するその細胞一つ一つが皆、『《吾》とは何ぞ』との問ひを発する矛盾を抱へ込むのである。つまり、元元、たった《一》であった受精卵が約六十兆個もの細胞にまで分裂とApoptosis(アポトーシス)を繰り返し、一つの個体としてある《吾》といふ《もの》をその六十兆個もの細胞からなる個体全体としての《吾》と細胞一つ一つに宿る《吾》は、その出自を忘却する事で辛うじて此の世に出現することが可能なのである。
それは薄ぼんやりした《吾》とでも名付けるべき《もの》なのか、《一》の受精卵が約六十兆個もの細胞により為る《人体》へと発育した羊水にたゆたふ胎児は、さて、其処には「先験的」に《吾》が宿ってゐるに違ひないのである。何を馬鹿な事をと思ふのであるが、しかし、《吾》が何《もの》にも先立つと考へなければ、さて、一体、何処から《吾》なる《もの》は、《吾》の処にやって来るといふのか。受精卵の時点、否、それ以前の未だ何《もの》の《存在》しない時点で、既に《吾》の出現は約束されてゐたに違ひないのである。つまり、煎じ詰めれば、《吾》の発生とは何なのかという事は、宇宙の始まりと同様に未だに謎なのである。謎であるならば、「先験的」に《吾》は《存在》してゐると看做してしまふのも一つの方法である。つまり、この論法でゆくと、宇宙もその始まり以前にその出現が約束されてゐたのである。さう看做す事で辛うじて《吾》の《存在》は論理的にも非論理的にも堪え得る何かとして《存在》出来るのである。つまり、これは無から有は生じないといふ事を前提とした《もの》で、尤も、これは如何にもこじ付けとしか思へぬのであるが、しかし、《吾》の出現を考へると、それは《吾》が出現する以前既に《吾》が「先験的」に《存在》すると看做す外に《吾》の出現を語り果せる根拠がないのも事実で、私は、それは《吾》の《念》と呼んで、《吾》の出現以前に《吾》の《念》が《存在》すると看做してゐて、その《吾》といふ《念》は、変幻自在の《もの》で、《吾》は、例へば轆轤首に変化したやうに《吾》とは、何にでも変容可能な何かなのである。さうでなければ、激変する環境の中で存続出来る筈がないのである。
さて、これを一般化する事が可能であるかと考へた時、どうも旗色が悪く、「先験的」に《吾》の《念》が《存在》するといふ《インチキ》を尤もらしく見せるには何か離れ業が必要なのであるが、現時点で、私にはその術がなく、唯、《吾》といふのは《吾》が《存在》する以前に《吾》は《念》として此の世にか彼の世にかのいづれかに《存在》してゐると根拠なき空論を振り回して己の憤懣を鎮めるので精一杯なのである。さうでなければ、必ず《吾》が此の世に出現する暴挙が説明出来ないやうに思ふのであるが、そんな事は、人間が此の世に出現して以来ずっと考へられてゐた事に違ひなく、宗教が《存在》するのは、多分にさうした理由からに違ひないのである。とはいへ、一人合点するのみであれば、《吾》なんぞ、どう出現しようが、個人の勝手であるが、一般化するやうにしたいといふ欲求は、《吾》にとって止めようもない事で、元来、《吾》は一般化が大好きなのである。つまり、永劫が大好きなのである。一般化とは、何時の時代でも成り立つ《もの》に違ひなく、ニーチェが言ふ永劫回帰に殉ずる為にも《吾》の思考を何としても一般化したくてうずうずしてゐるのである。例えば、かう言へば解かり易いかもしれない。つまり、ニーチェの言ふ永劫回帰は円運動で、ドゥルーズが言ふ反復は、切断した螺旋運動といふやうに看做すと、どう足掻いても切断した螺旋運動しか出来ぬ《吾》の《生》は、一回限りの《もの》で、その点においては永劫回帰の仲間入りはとても出来る状況ではなく、《生》とはそもそも反復でしかなく、《死》すれば全てご和算に違ひないのである。ところが、思索の足跡を文に認めて遺すだけで、それは何千年後でも構はぬのであるが、何か思索の足跡を遺しておけば、後世の未来人がそれを読む事で、《吾》の《念》を後世の未来人の《五蘊場》に喚起させる事は可能なのかもしれないのである。尤もそれを読んで貰へなければ、何の意味もなく、闇に葬り去られるだけなのであるが、しかし、エクリチュールはニーチェの永劫回帰に摺り寄る近道なのかもしれないのだ。否、言語はそれが音として録音されてゐてもそれはニーチェの永劫回帰に摺り寄る近道なのかもしれないのだ。否、絵としても、彫刻としても、などなど、何にしても、《吾》が《存在》した足跡を一般化する仕方で遺せれば、それはニーチェが言う永劫回帰という一般化の近道に違ひないのだ。
だが、そもそもニーチェの言ふ永劫回帰が一般化した《もの》なのかどうかといふその根本的な疑問が問はれなければならないだらう。そもそも何故にニーチェの永劫回帰なのか。それは、簡単である。この《吾》よりもニーチェの方が比べる迄もなく、一般化した《存在》なのである。ニーチェその本人は、既に亡くなってゐるが、その著書は翻訳されてゐて、この《吾》よりも断然に一般的なのである。これは、私が逆立ちしようが変はらない。とはいへ、虎の威を借りるやうにニーチェを持ち出してゐるのであれば、それは卑怯者の誹りを免れないに違ひない。ところが、この《吾》の事なんぞこの《吾》以外どうでもいいのである。《吾》を此処で晒した処で、誰も見向きもしないに違ひない。ところが、ニーチェであれば、誰かしら関心を示す筈である。
――だから、ニーチェを持ち出したのか?
と、《吾》を自嘲する《吾》は、
――へっ。
と、嗤ふしかないのである。つまり、事の本質は、《吾》なる《もの》を歴史的な《もの》として偽装したいだけなのである。《吾》に何かしらの本質があるかもしれぬと敢へて勘違ひしてゐたいのである。さうする事で、《吾》の卑しい本性が暴かれる事を期待してゐるのかもしれぬのである。つまり、ニーチェが撒き餌となって《吾》が誘ひ出されて喰らひ付く事を無意識に望んでゐるのかもしれず、将又、墓穴を掘る《吾》の無様さが《吾》の所望なのかもしれぬのである。
とはいへ、《吾》の《吾》による自己暴露のやうな愚劣極まりない事をする程に《吾》は己惚れてゐる事もなく、書く事のその困難さには絶えず悩まされつつ、《吾》は《吾》の轆轤首といふ《吾》の有様を一つの切り口として、《吾》なる《もの》のその正体を摑まへる罠を張ったのであるが、《吾》は轆轤首から、石ころへと変容してしまひ、《吾》はそれによって《吾》の滞る時間の中で、唯単に《吾》を持て余してゐるに過ぎないのである。其処で手持無沙汰な《吾》は、途轍もなくゆっくりと流れる《五蘊場》の中の石ころと化した《吾》をしてニーチェなんぞを持ち出して迄して《吾》の一般化を試みる愚行をしてゐるのである。何の事はない。《吾》は無名であることに我慢がならず、《吾》なる《もの》の一般化をこの《吾》の思考を用ゐて為さうとしてゐるのである。それは、何故かと自問自答すれば、《吾》は、つまり、《五蘊場》に腐敗Gasの如く充満し、石ころの《吾》を枢軸として渦を巻く、その二様の《吾》の構造を明らかにしたいといふ欲求があるといふ事の中に、《吾》は《吾》を偽装してゐるに過ぎないといふ事に思ひ当るのである。《吾》は《吾》の構造を明らかにし、例へばそれが一般化される僥倖に恵まれる事に淡い淡い淡い期待を抱いてゐるのである。《吾》とは、それ程迄に、とんだ食はせ《もの》でしかないのである。
――そんな事は誰もが知ってゐる事だぜ。
と、此処で半畳が入るのであるが、しかし、《吾》の偽りの構造を白日の下に晒す事で、ちっとは、その《吾》なる《もの》の尻尾でも摑まへられるかもしれぬといふ、これまたどうしやうもなく、人を喰ったやうな欺瞞に満ちた《吾》の有様が暴かれるのみの、骨折り損のくたびれ儲けが、目に浮かび、つまり、《吾》といふ《もの》は何処まで穿っても道化師なる《吾》が、
――へっへっへっ。
と、《吾》に対して嗤ってゐる《吾》といふ構図に出くはすのみなのである。
では、轆轤首なる《吾》、《異形の吾》、将又、腐敗Gasの如き《吾》、そして、石ころの《吾》など、《吾》なる《もの》を追ひ詰めたと思ひきや、何の事はない、《吾》の狸の如き化かし合ひにすっかり騙された馬鹿面をした《吾》に出合ってゐる事を、只管にひた隠し、《吾》は、詰まる所、《吾》に諂ってゐるに過ぎないのである。
《吾》たらむとする事は、《吾》の下僕として《吾》は《存在》する事を自ら望み、さうして《吾》は、やうやっと《吾》と名指す《もの》を辛うじて表象するのである。それが《吾》においては、轆轤首であり、《五蘊場》で渦巻く石ころの《吾》とそれを取り巻くGas状の《吾》なのである。
さて、《吾》はそもそも一筋縄にゆかぬ《もの》といふ事が、《吾》なる《もの》の面妖なる様相の幾つかを見出しただけでもそのお足は知れるといふ《もの》なのである。そもそも《吾》なる《もの》はみっともない《もの》でしかなく、それを暴露した処で、《吾》を摑まへたなどとはちっとも感じられる筈もなく、絶えず偽装する《吾》にあかんべをされて仕舞ひなのが関の山なのである。《吾》なる《もの》が、《吾》なる《もの》を追ひ詰めるこの不思議を《吾》は何時も嗤ひながら、しかし、其処から一歩も退かずにへらへらと嗤ひながら、《吾》なる《もの》を追ひ詰めなければ気が済まぬ性分なのである。《吾》の一様態が轆轤首である事は予想してゐたが、その《吾》が時間が途轍もなくゆっくりと流れる《吾》の核の如き石ころの《吾》と、それを枢軸として渦を巻く腐敗Gasの《吾》が、轆轤首の伸び切ったその首をぶった切って《吾》の内部に仮初とはいへ、出現した事に《吾》とは所詮、渦しか頭になかった《存在》ではないかと《吾》は《吾》を訝るのである。
何も私の渦好きは今に始まった事ではない。気が付けば私は、既に渦に夢中になってゐた《吾》を見出したのである。何がそんなに渦は私を魅了するのかは、単純で、渦は絶えず変化するにも拘らず、それが相変はらず渦のままだからなのである。例へば投げ独楽を回すのが私の幼少時の大好きな遊びで、木地の投げ独楽が、駄菓子屋の店頭に並ぶと、私は幾つか手に取り、投げ独楽の芯を指で捻って回してみて、その投げ独楽がどのやうな回り方をするのかも一一確認して、回る姿が最も美しい木地の投げ独楽と麻縄を買って、空き地で早速回して大喜びするのを常としてゐたのである。その投げ独楽の面に塗られてある模様が何とも見事な渦を巻くから、私にとってこんな理想的な遊びはなかった訳である。しかし、投げ独楽を回すにはかなりの忍耐強い修練が必要で、上から振り被って思いっ切り投げ独楽を投げつけて、急速回転で回せるやうになるには、それは、投げ独楽を回す麻縄に手が擦り切れて血が出る迄に練習をしなければ巧く回せるやうにならないのであるが、私は、既に投げ独楽に渦模様を見てしまってゐる故にか、投げ独楽を手にした始めの何日かは投げ独楽が思いっ切り回せるやうになる迄、何度も飽く事無く繰り返し練習したのであった。しかし、人間練習すれば何とか投げ独楽を巧く回せるやうになるのである。その時のすかっと突き抜けたやうな快感は何とも言へない《もの》であったが、一度その快楽を知ってしまふと最早投げ独楽を回す事が已められないのである。芯棒がきちんと重心にある投げ独楽のその美しい回り方は息を呑む程で、一度でもそれを見てしまふと、最早、投げ独楽の虜になる外ないのである。只管に、美しいその投げ独楽を眺めては、その回転が出来得る限り長く続くやうに回し方を何度も工夫してみては『これだ!』といふ回し方を己で見出す《もの》が、此の《吾》なのである。芯棒が全くずれてゐない投げ独楽のその美しく回転する様は、今も此の世の《もの》とは思へぬ《もの》で、投げ独楽の面の模様が渦巻くその美しさは、得も言へぬ美しさなのであった。
私の原体験に既に投げ独楽回しといふ《もの》があり、それが、私の渦好きを確認させるに十分な《もの》なのであったが、気が付くと投げ独楽は何時も私の《五蘊場》で回り続ける事になったのである。しかし、それが《吾》へと変容する事はなく、相変はらず客体としての投げ独楽の表象なのであった。その投げ独楽が、今、《吾》として轆轤首の首を自らぶった切った後の《吾》は、一つの投げ独楽の如くあったのである。投げ独楽の中心は当然、回ってをらず、ぴたっとこの地に屹立して静止してゐるのは言はずもがなであったが、腐敗Gasとして《吾》の《五蘊場》に充溢した《吾》が、石ころと化した《吾》の周りを回る「私」といふ《もの》の表象は、或ひは幼少期の投げ独楽回しにその淵源があると看做してしまへば、それはさうに違ひないのである。しかし、私の世界認識の一つに『《世界》は渦である』と乱暴ながらどうしてもさう看做して仕舞はないと済まぬ強迫観念の如き一念があるのである。そして、それは、単純に『《吾》もまた渦である』といふ私の《吾》=観に繋がってゐるのは否定しようもない事実なのであった。
そもそも《吾》が《吾》と呼んでゐる《もの》の正体は何なのであらうか、と如何にも愚問でしかない問ひを《吾》に発する此の《吾》の馬鹿さ加減は、手に負へぬ《もの》に違ひないのである。此の《吾》が『《吾》とは何ぞや』と自問自答を発した刹那、《吾》は偽装を始めるのは明らかなのであるが、《吾》はそれでも『《吾》とは何ぞや』と虚しい問ひを発してしまふのである。その時に《吾》の《五蘊場》に生滅する表象が《吾》の正体であると言へなくもないのであるが、しかし、《吾》は変幻自在にその姿を変へ、仕舞ひには《吾》を煙に巻くのが関の山なのである。それでも現在、《吾》は轆轤首の表象を自らぶった切り、そして、その切られた首は途轍もなく時間がゆっくりと流れる石ころの《吾》とそれを取り巻く《吾》の腐敗したGasである《吾》がまた、《吾》の偽装でしかない事は重重承知しながらも、《吾》が渦である事に何となく安堵してゐる《吾》が、また、《存在》するのであった。
《吾》の誤謬こそが《吾》の生存する方便なのかもしれず、《吾》は絶えず《吾》を誤謬するからこそ、現在に堪へ得、そして、更に《吾》を摑み損ねて、誤謬する事で、《吾》は《吾》に生じるGap(ギャップ)を《吾》が《存在》する起動力に変換してゐるのかもしれなかったのである。
投げ独楽と化した《吾》。果たして、これは《吾》の所望した《吾》の表象なのであらうか。確かに《吾》は『《吾》もまた渦の変種である』と看做してゐるが、だからと言って、《吾》の《吾》に対する表象が投げ独楽の如き渦巻である理由にならない。《吾》とは面妖なる複雑怪奇な《もの》の筈で、一筋縄ではゆかぬ《存在》に違ひないのである、と思ひながら《吾》が面妖で複雑怪奇な《もの》である理由もまた見出せぬのである。然しながら、科学的な知識で、《吾》の正体を追ひ詰めた処で、《吾》はあかんべをしてするりと逃げ果せるのが関の山で、《吾》は終ぞ《吾》によって捕獲される事はないのである。然しながら、現に《吾》は此の世に《存在》し、さうして生きてゐるのである。
《吾》は絶えず《吾》を喰らって生き永らへてた《もの》に違ひなく、《吾》は《吾》を喰らはずして一時も此の《世界》で生き延びる事は不可能であるのか? さて、このAporiaは一朝一夕に片付くAporiaではなく、先づ、《吾》の発生が語られなければならない筈であるが、《吾》の発生に関して《吾》の意思により《吾》が発生したなどと馬鹿げたLogos(ロゴス)を打ち立てる輩はゐないのであるが、私は《吾》の発生に《吾》の意思、つまり、《念》が深く関はってゐると看做してゐるのであるが、それではその《吾》といふ《念》は何処からやって来たのかと問へば、それは此の宇宙開闢の時に既に此の宇宙の発生を夢見てゐた《もの》――それを《神》と名付けた方が良いのかもしれぬ――の《念》として《存在》してゐたとしか言へぬのである。つまり、それは、魂の不滅説に近しい《もの》に違ひないが、魂は後付けの《もの》で『初めに《念》ありき』といふのが、馬鹿げた論理の端緒なのである。つまり、《吾》といふ《念》は「反復」を繰り返すのである。此の「反復」は然しながら、いづれの場合も一回限りの《もの》であり、二度と同じ経験を味はふ事はないのであるが、しかし、《生》とはそもそも「反復」であって、生老病死もまた、「反復」なのである。ところが、此の世は諸行無常であり、《生死》は絶えず此の世で繰り返されるが、どの《生死》をとっても同じ《もの》はなく、然しながら、《生死》は《生死》として表現される《もの》なのである。
――何を夢物語を語って悦に入ってゐるのか?
と、これまた半畳が入るに違ひないのであるが、しかし、《吾》とは考へれば考へる程にAporiaといふ陥穽に嵌り込む宿命にあり、《吾》の発生からして《吾》はそれがどうであれ受容せねばならぬ《もの》として、此の世に《存在》し、さうして、何とか《吾》の《生》を受容した《吾》の《死》をも次第に受容しつつ、今生を生きる糧にしてゐるのである。《吾》は絶えず切断した《もの》として、つまり、《吾》を喰らふ事によってのみ《生》を繋げるのである。
そこで、《吾》を嗤ふ《吾》とは、如何なる《存在》として、《吾》に対して再現前化するのかと問へば、それは《吾》の内界、否、《吾》といふ《存在》に「先験的」に備はってゐる《過去》、若しくは《未来》の《吾》と言へなくもないのである。《吾》が絶えず《吾》からずれるやうにゆらゆらと《吾》を中心に振幅する《吾》の反面教師であり、また、《吾》を《現在》に繋ぎ止めるに相応しい《未来》の《吾》なのである。《現在》は「先験的」に《過去》と《未来》が含意された《もの》としてしか此の世に出現しないのであるが、それはしかしながら至極当然の事で、「私」の外界は既に距離が《存在》する故に押しなべて《過去》であり、一方その《過去》の《世界》に一度目的地が出現すれば、《過去》であった筈の外界は《未来》に反転してしまふのである。つまり、《現在》にゐる《吾》と目的地の間にある距離が《未来》に対する尺度になるのである。この事は再三に亙って述べて来たが、此の世の《世界》とは、《吾》においては《過去》であり、《未来》でもあり、そして、《吾》の内界においては表象として《五蘊場》に出現するその《もの》は、未だ出現せざる《もの》の象徴として《五蘊場》に出現し、そして、《吾》の内界は《過去》の記憶を交へた未出現の《吾》、つまり、《未来》に出現するかもしれぬ《吾》として絶えず《吾》からずれ行きながら、《存在》する《もの》なのである。それは、《吾》が《吾》の内界を弄る事で、やうやっと表象される《吾》の内界における《現在》の有様であり、表象とは外界における《吾》の《現在》、つまり、《吾》の皮膚に最も近しい瞼裡に現はれる《もの》なのであって、若しくは前頭葉部に恰も表象されてゐるかの如くに看做してしまふ《吾》の大いなる誤謬であり、その誤謬があってやっと《存在》可能な《もの》として《存在》に繋ぎ止め置かれる何かとして《吾》は《吾》を感知してゐる筈である。
《吾》は瞼を閉ぢれば、眼前は前頭葉の闇と繋がった闇が拡がるばかりで、その闇=《世界に表象群は生滅するのであるが、その表象の有様こそ、《吾》の内界において皮膚に最も近しい、つまり、《現在》の様相に最も近しい《もの》として、《吾》は感知し、その表象のざわめきによって、《吾》は《吾》の《現在》を支へるのである。
――《吾》の表象群のざわめきが《吾》の《現在》を支へる?
と、反芻する「私」は、これまた《吾》とは全く相容れない何かとして《存在》してゐて、《吾》とはそれらの「私」やら《過去》の《吾》、《未来》の《吾》が渾沌とした中に《存在》させられる事を余儀なくされるのである。その渾沌こそが《生》の源泉に違ひないのであるが、その《吾》が《吾》とずれてゐる事で、つまり、摂動してゐる事により発現する《吾》のその《生》への飽くなき執着は、《吾》をして、《現在》を支へる《存在》として《過去》であり、《未来》である外界と内界を結ぶ結節点として《吾》のみ、《現在》を体現するからくりとなってゐるのである。つまり、《吾》とは《過去》へも《未来》へも《五蘊場》においては自由に往来出来て、また、外界においても《世界》は《過去》が《未来》に反転する事を所与として《吾》に開かれた《もの》として《存在》し、《吾》とは《過去》と《未来》を繋ぐ《現在》に徹底して馴致された《もの》なのである。つまり、《吾》としては、《現在》から遁れられない《存在》として、しかしながら、《過去》へも《未来》へも往来可能で奇妙な《存在》として、此の世に《存在》するのである。
――《吾》!
と、《吾》が《吾》を名指すその《吾》には既に去来現を自在に行き交ふ《異形の吾》が想定されてゐて、予想通り《吾》は《異形の吾》を見出す事でのみ《吾》はひと時の安寧を得るのである。
つまり、《吾》が自己言及する度毎に、既に《吾》には《現在》といふ《過去》と《未来》を派生させる外ない、どん詰まりの《吾》を《世界》にぽつねんと《存在》する《吾》として、《吾》は《吾》を表象し、さうであるからこそ《吾》は此の世で唯一無二の《もの》と僭越ながらも「先験的」に看做すその開き直りが、これまた《吾》を厄介で偏屈な《もの》として、此の世に《存在》させてしまってゐるのもまた、真実に違ひないのである。
《吾》語りをする《吾》の虚言癖に《吾》は振り回され、絶えず《吾》は《吾》から遁れ行く《もの》として永劫に続く鬼ごっこを独りでしながら、それでゐて、『《吾》とは何ぞや』と居直る《吾》の質が悪いその有様にこそ、《吾》が《吾》でなければならない秘密が隠れてゐるかもしれないのである。
さて、その秘密とは何なのか、勿体ぶらずに端的に言ひ切ってしまへば、それは、所詮、《吾》はどんなに足踏みしようが《吾》である事を已められず、詰まる所、《吾》とは、どれ程《過去》と《未来》の間を振幅出来るのかによって、その《生》の充実の度合ひに影響する《もの》に違ひないのである。つまり、《吾》は《吾》の《五蘊場》において表象されてゐる《吾》は既に其処に《過去》の記憶による残像としての《吾》と、これからさうなるかもしれぬ或る兆しを見据ゑた《未来》の架空の《吾》とが、無理矢理に一所に押し込まれ、重ね合はされた《現在》の事象の一例に違ひないのである。
例へば、それは、《吾》をして《吾》に言及するしかないこの《吾》の矛盾した有様の奇妙奇天烈な様を《吾》が意識される外ないのであるが、だからと言って、《吾》が《吾》に自己言及するその仕方の何とも間抜けな、そして、苦し紛れの自棄のやんぱちぶりは、《吾》ながら苦笑する外ないのである。つまり、《吾》が《吾》に対して自己言及する奇怪さは、《吾》が《吾》において空転する宿命にあるに違ひないのである。それ故に、《吾》について自己言及する場合、大概は饒舌に為らざるを得ぬとはいへ、一生かかっても語り果せる筈はないのである。それを知りながら確信犯的に《吾》は《吾》に対して自己言及し、不意に『《吾》とは何ぞや』と思春期特有の疑問が己に湧いて来ると、《吾》は《吾》に首ったけに為る外ないのである。つまり、《吾》はさうして初めて《吾》なる《もの》を見出し、僭越ながら、《吾》の超克を願って已まないのである。さうして《吾》が《吾》ばかりに意識が集中する堂堂巡りの呪縛から、最早、遁れらないのである。
――だから、それがどうしたといふのかね?
と、既に《吾》として居直る《吾》が《吾》に対して嘲りを向けるのであるが、どうした事はない、《吾》は《吾》といふ同じ場所で蜿蜒と足踏みするのみの《吾》を見出だす事で、《吾》は《吾》の此の世に置かれた事情を暗黙裡に呑み込み、《吾》は、《吾》を深追ひしては駄目だといふ事を重重承知の上で、《吾》を追ふ鬼ごっこが已められないのである。さうして気ばかりが逸る《吾》は、不意に轆轤首の変態の準備をしてゐる事とは露知らず、高度情報化社会の中における野蛮なる《吾》、つまり、原初の頃より、変質してゐないこの《吾》の蛮行に《吾》は悩まされるのである。
――はて、《吾》の蛮行とは如何に?
と自問する声が頭蓋内の闇、つまり、《五蘊場》で囁かれるのであるが、
――それは愚問だせ。
と答へる《吾》が、また、《存在》し、徹底して《吾》の自作自演の茶番劇が行はれる事になるのが関の山なのである。何故にかと言へば、《吾》なる《存在》その《もの》が既に茶番でしかなく、つまり、《吾》の端緒が既に茶番なのである。また、《吾》とはその様に滑稽でなければ此の世に《存在》出来る筈もなく、《吾》とは何処まで行っても、鉄面皮の如く面の皮が厚い、能の幕間に行はれる狂言の仕手=吾や太郎冠者=吾や次郎冠者=吾との狂言の寸劇にも為り得ぬ滑稽な茶番劇を《死》すまで続けるのである。
何故に《吾》が《吾》語りを始めると何時も狂言めいた茶番劇にしか為り得ぬのか、と自嘲しながらも、その茶番劇が《生》をも奪ふ絶望を含意した悲劇へとするりと身を躱すその早変わりの《吾》の有様に、或る種の驚嘆を覚えつつ、呆然と渺茫たる《五蘊場》の虚空を凝視する外ないのである。
――これが、若しや《吾》の人生の縮図?
と、初めは何も《存在》してゐない虚空を凝視しながら自問する《吾》にまたぞろ罵詈雑言を浴びせる《吾》が出現するのである。
――それは何故にか?
と、再び自問する《吾》は、不意にそれが《吾》を捨て去る方便として、もってこいの《もの》として、再び自嘲する《吾》の出現を認識するのであるが、さうして順繰りに《吾》を《五蘊場》に出現させつつ、其処に或る安寧を見出だすに違ひないのである。さもなければ、《吾》が《吾》を使ひ捨てられる筈もなく、そもそも《吾》は未練たらたらに《吾》に執着する筈なのであるが、それを敢へて行ふ事無く、《吾》が凝視する虚空に響き渡る哄笑は起きる筈もないのである。
――ぶはっはっはっ。
さうして《吾》を見て嗤ひ飛ばす《吾》の変幻自在な有様に心躍らせるのである。
――何たる事か!
それが《吾》の《吾》に対する鬼ごっこを飽きさせない秘訣のやうにも思ひ看做す《吾》にとって其処に欺瞞を見出してしまふ《吾》は、尚も《吾》を駆逐する事に精を出し、何としても《吾》に《異形の吾》を見出だす迄、已められぬのである。しかし、仮令、《吾》に《異形の吾》を見出だした処で、所詮は、それすらをも使ひ古すこの《吾》にとっては単なる一興にしかならずに、《吾》はその《異形の吾》を捨て去って《五蘊場》の闇を分け入るのである。
――一寸先は闇。
と念仏の如くにそれを誦へながら、不意に姿を現はす、《異形の吾》を見つけては大喜びしながら、その《異形の吾》をぶん殴り撲殺するのである。さうせねば、この《吾》が殺されかねないからである。
――《吾》とは何と哀しい《もの》か――。
と嘆いた処で、《吾》はびくともせずに《吾》をして《吾》を《吾》として建立するのである。つまり、《五蘊場》の虚空に無限に通じる闇を彫る事で、仏像の如く、《吾》を彫り出しては、それにけちを付けて一人ほくそ笑むのである。全てが自作自演の茶番劇でしかなく、それに《吾》は大いに不満なのである。不満故に《吾》は鶴首の如く首をぐっと伸ばして轆轤首に化しながら闇を更に分け入り、更に巧みに闇を彫り出す《吾》の御姿を崇めては、その直後に素知らぬ顔をしてその《異形の吾》を撲殺するのである。何とも不憫な生き《もの》が《吾》なのであるが、《吾》なる《もの》を全剿滅しなければ、不満なのである。つまり、《吾》が《吾》といふ自意識を喪失して闇に完全に溶け込んだ《吾》なる《もの》を《吾》は虚空を凝視しながら、表象するのである。それは、恰も《水》その《もの》の振舞ひに外ならず、つまり、皮袋といふ《水》の容れ《もの》が破れて、皮袋内部の《水》が零れ出すのをぢっと待ってゐるやうにも思へるのであるが、それは、しかし、死体が腐乱して腹が腐敗Gasで膨れ上がる様に似てゐて、時折《吾》を襲ふ失神する時の《世界》との合一感、つまり、《吾》が疑似体験する《死》の様相に似てゐて、《吾》が自意識を失ふ瞬間の恍惚感に遂には酔っ払ひたいのである。さうなのである。《吾》は何時も酩酊してゐたいだけに違ひないのである。壊れ行く自意識を破れたままにして、恰も《水》が流れ出すやうにして、《吾》は《吾》を彌縫せずに、《吾》は、ばっくりと大口を開けた裂け目を虚空に見出だしたいだけに過ぎぬのである。
渺茫たる眼前の闇を凝視しながら、闇が《水》の如く流出してゐる裂け目を探すその訳は、暗闇の中で女陰を弄る様を髣髴とさせなくもないのであるが、仮令、闇の中に必ず《存在》する裂け目が女陰の象徴に過ぎぬとした処で、それはフロイトの焼き直しでしかなく、《吾》の《存在》を《生》と《性》と《死》へと還元し、身も蓋もないフロイト流の精神分析とは一線を画す、闇の裂け目――仮令、それが女陰の象徴だとしても――《異形の吾》の誕生を祝ふ予兆のやうに、闇をしっかと凝視し、此の世に屹立する《吾》の首は、その裂け目へと吸ひ込まれるに違ひないのである。《吾》は身動ぎ出来ぬ事を伏せながらも、《生》きてゐるのであれば、まるでさうでなければならないかのやうに此の世の決まった立ち位置に屹立する事を已められぬ《吾》故に、闇にばっくりと大口を開けてゐるに違ひない裂け目へと首のみがぐんぐんと伸び行き、仕舞ひには《吾》の首のみが闇の裂け目にすっぽりと嵌まり込み、《吾》は、『生まれ変わり』の儀式をひっそりと執り行ふに違ひないのだ。さうして《吾》は《吾》の伸び切った首をずばっと斬り落とし、尚も渺茫たる《五蘊場》の虚空を凝視してゐる首無しの《吾》は、自らの拳で《五蘊場》に残されしその体軀を撲殺するのである。
一方で、闇の裂け目にすっぽりと嵌まった首のみの《吾》は、『生まれ変はり』のひっそりとした祝祭を執り行ひつつ、その首のみの《吾》は恍惚の体で《吾》に酩酊してゐるに違ひないのある。つまり、《吾》とは首のみの機能ばかりが増幅された「脳絶対主義」の如き《世界》の中で、存続するには恰も首のみが伸びた轆轤首に化した《吾》の有様がある一方で、酩酊を求めて渺茫たる《五蘊場》の虚空の中に身動ぎ出来ぬ故に、虚空の闇の裂け目へと首のみが伸び行く轆轤首が《吾》の内部には《存在》するといふ事に、
――へっへっへっ。
と嗤ひながら、その矛盾したLogosに妙に納得するのであった。《吾》は突き詰めれば二柱の《吾》たる轆轤首といふ《神》にも似た《存在》に行き着くのである。もしかすると、轆轤首は三柱、四柱、……、∞柱、《存在》するのかも知れぬが、《吾》を最も欺く《もの》が何を隠さうこの《吾》であるならば、今の処、二柱の轆轤首には行き着いたと言へなくもないのである。
――へっへっへっ、それは 詭弁といふ《もの》だぜ。
――詭弁で構はぬではないかね?
――馬鹿な! 《吾》語りをするのであれば、詭弁は徹底的に排除されるべき《もの》であり、さうしなければ、全く以って空虚な空論に、つまり、戯言でしかなくなるんだぜ。
――それで構はぬではないか? 《吾》とは所詮《吾》為らざる《吾》へと超越する《もの》故に、《吾》なんぞどうとでも語れる《もの》なのさ。
と、ほとんど投げ遣りな自問自答にすべては語り尽くされてゐるのではあるが、然しながら、さうは言っても、やはり、《吾》は結局の処、《吾》を語る為に《存在》してゐるに違ひないと思ひ直して、自己満足する《吾》を、
――けっ、薄汚い性根を現はしやがって!
と罵るのであった。
さて、それでは《吾》として《異形の吾》が無数に《存在》する《もの》として語り出せば、その無数に《存在》する《吾》が全て轆轤首へと収束し、変態するに違ひないのである。《吾》を轆轤首といふ型枠に、つまり、皮袋に容れた《水》としてその変幻自在さを固着化した《存在》に過ぎぬと、∞柱《存在》する轆轤首たる《吾》を十把一絡げに看做してゐるに違ひないのであるが、しかし、《吾》とは、《吾》といふ《もの》へと収束する《もの》としか言ひ様がない、つまり、極論すれば、《吾》とは《吾》であり、また、《吾》ではない《異形の吾》であるといふ排中律に準じない《存在》が《吾》であるとしか言へぬのである。
《吾》が《吾》であり、そして、《吾》でないといふ非=排中律が《吾》を言ひ当てる最も的確なLogosならば、《世界》に《存在》する因果律も見直されるべき《もの》なのかもしれぬのである。《世界》において仮に因果律が不成立ならば、その因は全て《吾》が担ふ筈なのである。《吾》とは「距離」が厳然とある《世界》において《吾》のみ《現在》にあり、《吾》以外は全て《過去》か《未来》のどちらかと言へると先述したが、外界たる《世界》が、しかし、一度も《現在》であったためしがないかと問へば、《世界》は《吾》とは全く無関係な時間が流れてゐる筈で、《世界》は《世界》として自律してゐるに違ひないのである。それを仮に「宇宙史的時間の流れ」と言へば、《吾》の《生死》は、「宇宙史的時間の流れ」から見れば、ほんの一寸の出来事でしかなく、たまゆらに現出する《吾》といふ非=排中律なる《存在》は「宇宙史的時間の流れ」といふ悠久の時の《存在》の永劫回帰的な様相を其処に見出だす事で、徹底的に《世界》から孤立する《現在》であり続ける《吾》を断念するのである。絶えず《現在》であり続ける事を断念した《吾》とは、正覚せし《もの》とは違ふ《存在》に違ひなく、その《吾》のみ非=排中律の空理空論から遁れるのかもしれぬのである。それは詰まる所、《現在》である《吾》を追ひ、永劫に続く鬼ごっこを已めた《存在》に違ひなく、その途端に《吾》は《吾》から遁れる事を已めて、《吾》といふ何かが現前に現はれるに違ひないのだ。その為にも《吾》は出来得る限り早く、《吾》を追ふ矛盾を断念すれば、《吾》は、多分、何《もの》かに為り得、そして、それを以ってして『《吾》は《吾》だ!』と《五蘊場》に広がる渺茫たる虚空にその《吾》なる《もの》を彫り出す事が出来るのであり、断念しなければ、《吾》は何時迄経っても、《吾》は不確定な非=排中律、つまり、《吾》は《吾》であり、《吾》は《吾》でないといふ《現在》の有様に振り回される《存在》に堕すばかりなのである。何故にさうなるのかと言へば、そもそも《現在》は浮動な《もの》であり、それに対峙するには《吾》は肚を括らなければ、つまり、『《吾》、《吾》なる事を断念す』と浮動する《現在》における非=排中律的な有様にある《吾》との間に、程よい「距離」が出現するのである。つまり、《吾》と《異形の吾》との分離に成功すれば、《吾》とは、去来現を自在に行き交ふ解放感に包まれ、至福の時を堪能する筈なのである。
――へっ、それは丸っきし見当違ひだぜ!
と、不意に我慢出来ずに言挙げせし《吾》がゐたのであった。
――それは何故にかね?
――決まってゐるだらう? 《吾》は未来永劫に亙って《吾》である事を已められぬ筈だぜ。
――馬鹿な!
――しかし、《吾》とは、そもそも地獄の生き《もの》だらう?
と言挙げする《吾》の地獄といふ言葉を前にして、《吾》は口を噤むしかなかったのである。確かに《吾》は《現在》と言へば聞こえはいいが、それが地獄の一様相でしかない事を薄薄感じてゐた《吾》にとって、その《異形の吾》の言挙げに一瞬たぢろぎ、さうして不敵な笑みをその顔に浮かべるに違ひないのだ。
――つまり、地獄では《吾》は《吾》である事を已められぬ――か。
つまり、地獄の責苦を十二分に味はふには《吾》は絶えず《吾》でなければ《吾》をして地獄の責苦を受ける筈はなく、たまゆらでも《吾》が《吾》でなくなるとするならば、地獄を彷徨ふ《吾》にとっては、それは 卒倒を意味し、その無=自意識の状態である《吾》は、その時のみ《吾》である事に胡坐を舁くのである。卒倒が非=排中律の止揚であるならば《吾》は意識を失った無=自意識の境地にある――これをして《吾》は《吾》と呼べない――《異形の吾》が憑依した何かでしかないのである。その象徴が多重人格に違ひないのである。
次次と人格が変わりゆく多重人格者は、或る一人の人格が憑依すると、それまで確かにその多重人格者に憑り付いてゐた人格と断絶した別の人格がその相貌を現はすのであるが、その細細とした断片の寄せ集めでしかないその多重人格者の本当の人格は、誰かと問ふと、はたと答へに窮するに違ひないのである。何故ならば、当の本人が、つまり、多重人格者が一体誰なのか一向に判然としないからに外ならないのである。多重人格者においては全て現はれる人格がどれも「私」であり、さて、多重人格者の全ての人格が揃って『《吾》とは何ぞや』と自問自答を始めたと仮定した場合、多重人格者は、常人に比べてその『《吾》にぽっかりと開いた陥穽に深深と落ち込むかと言へば、決してそんな事はなく、多重人格者が全ての人格において『《吾》とは何ぞや』と自らに問ひを発してたとして、それは、そのいづれかの人格においても「私」の深化は望むべくもなく、多重人格者は『《吾》とは何ぞや』と問ふのみといふ無力感に苛まれるに違ひないのである。多重人格者において一所に留まり、一人として思索に耽るにはその持続力はそもそも不足してゐて、或る境地に達する前に別の人格に乗り移ってしまふに違ひないのである。つまり、全ては中途半端に終はってしまふ可能性が大で、多重人格とは《吾》からの逃避の一様相と看做せば、《吾》を追ひ込んだ挙句に辿り着いたのが仮に多重人格者へと為る端緒であると看做せなくもないのである。つまり、《吾》を突き詰めるとその結果の一様相が多重人格へと変化するものなのかもしれぬのである。
――多重人格とは《異形の吾》に《吾》が乗っ取られた一現象ではないのかね?
と、相変はらず《吾》を嘲る嗤ひをその口辺に浮かべながら《異形の吾》が《吾》に向かって言ふのであった。それこそ、自己矛盾した《吾》の有様を具(つぶさ)に物語るのっびきならぬ《吾》の事態なのであるが、それが何とももどかしくて《吾》は、
――ぶはっはっはっはっ。
と哄笑を発したのである。そして間髪を入れずに《異形の吾》は、
――果たしてお前は《吾》かね? 片腹が痛いわ。お前が《吾》? ふへっへっへっ。ちぇっ、悍ましい!
と、吐き捨てて、その姿を虚空の中に消したのであるが、当の「私」はまるで白昼夢を見てゐるかの如く、己に対して舌打ちをするのであった。
――ちぇっ、忌忌しい! 何が《異形の吾》だ! 所詮、《吾》に過ぎぬではないか! 《吾》は《異形の吾》を自然に受け容れる度量が《吾》には本来備はってゐる筈で、それを先人は対自と、更には脱自と呼んで《異形の吾》も含有した上で《吾》は《吾》をして《吾》はちっぽけな《存在》に違ひないそれを《異形の吾》と名付けて邪険に扱ふ事に終始してゐるに過ぎぬではないか!
と「私」は己に罵詈雑言を浴びせたのである。しかし、その虚しさと言ったら、「私」の内界に一陣の風が吹き抜けるやうに《吾》の洞状の、つまり、《吾》の中身は空っぽといふ余りにお粗末な事態に嗤ふしかないのである。
――それで満足かね?
と、何処とも知れぬ《五蘊場》の闇に覆はれた眼前に拡がるは闇ばかりの虚空から、その虫唾が走る声で《吾》に問ふたのである。勿論「私」は己に罵詈雑言を浴びせた処で、何かが解消する筈もなく、尚更に憤懣のみが昂じるのみなのであったが、その瞋恚の炎が一度燃え上がると、最早、収拾は付かぬ事態に《吾》は何の事はない、周章狼狽するといふ醜態を晒すのであった。
――しまった!
と思った処で後の祭りで、それをしかと見たに違ひない《異形の吾》は、
――ぶはっはっはっ。
といふ哄笑を上げて嗤ふのであった。
――成程、非=排中律の止揚は卒倒ばかりではないな。瞋恚もまた、《吾》の非=排中律の止揚に違ひない。
――それは瞋恚に《吾》を見失ひ、ちぇっ、つまり、《吾》が《吾》に一致した一様相が瞋恚といふことかね?
――何ね。意識が感情に支配された時もまた、《吾》は《吾》であり、また、《吾》は《吾》でないといふ非=排中律を成し遂げてゐるのではないのかと思ってね。
――それを屁理屈といふのぢゃないかね?
――屁理屈で構はぬではないか。土台、《吾》が《吾》を問ふ事自体が屁理屈でしかないのだから。
――それは言ひっこなしだぜ。
――ふっ、ところで、お前は誰と話しているのかね?
――決まってゐるだらう、《吾》さ。
――ふむ。《吾》ね。
などと、下らぬ自問自答は、蜿蜒と続く事になるのだが、その問ひが建設的かと問へば、全く建設的ではなく、非建設的な自問自答を蜿蜒とする内に《吾》は憂鬱な気分に見舞はれるのである。だからと言って、《吾》は《吾》の観察者たる事を已める事は一時も出来ず、その内容が下らなければ下らない程に《吾》は《吾》との自問自答にのめり込むのが関の山なのであった。
其処で《吾》は己に問ふのである。
――さて、《吾》は《吾》である事を断念した時、一体全体《吾》には如何なる変容が起きるといふのだらうか?
確かに《吾》が《吾》である事を断念した場合、《吾》と名指す《もの》が既に《吾》でないといふ事象に戸惑ひながらも無私の境地へと達せられた《吾》は最早、《吾》と呼ぶ《もの》の声すら聞かずに、只管、《吾》の《五蘊場》を覆ひ尽くす闇へとずかずかと分け入り、また、底無し沼の様相を呈するその闇への落ち込みやうは、底無しにも拘らず、既に《吾》である事を已めた《吾》は、その闇に沈下してゆく《吾》に対して何ら恐怖心も湧き起こらずに、為すがままに《吾》を放置するのである。その放置された《吾》は勿論、首を自らぶった切った轆轤首の首の部分に違ひないのであるが、その首のみの、《吾》としか名指せぬ、既に《吾》を解脱してしまった《吾》を一言で言ひ表はせば、それは∞相を兼ね備へた《吾》といふ一様相に収束しての一相貌なのである、と言へなる筈なのである。そして、首のみの轆轤首の《吾》は、龍にも狡猾な蛇にも人魂にも変化可能で、その見え方は見る《もの》の心の有様次第なのである。つまり、無私といふ非=排中律を止揚した《吾》は、何様にも変化可能で、その見え方は《吾》以外の《もの》の心模様の射影でしかないのである。
そして、もう一つ、《吾》が《吾》を見失ふ様に感情の赴くままに《吾》を帰属させて、そこに「反省」「省察」の入り込める余地すらない状態の《吾》がある事は瞋恚について述べた通りであるが、その事は太古の人人にすら解かっていた事で、その一例に不動明王像として、また、十二神将像として神仏の緒様相として、彫像され、今に残されているのである。つまり、此の世には既に《吾》といふ《存在》の非=排中律を止揚した《存在》として、瞋恚を露はにした十二神将像や馥郁として嫋(たを)やかたる仏像として連綿と受け継いできたのであり、《吾》の無明といふ事象は現代に始まったことではなく、しかし、そのように「現代の闇」として捉へたがる俗物は傲慢でしかなく、敢へて言へばホモ・サピエンス、つまり、人間を馬鹿にしてゐるだけなのである。
現代に《生》を享けた《もの》が《存在》のHierarchy(ヒエラルキー)(位階)の頂点に君臨し、そいつは、つまり、「現存在」は《死者》を従へ、《神》を下僕と化し、悪魔に魂を売った《もの》として《存在》してゐるに過ぎぬのである。そのくせ、功徳を積んでゐると正邪が顚倒した《存在》を自覚しながらも「現存在」は此の世の王たらむとして《存在》する事を已めぬのである。むしろ、そいつは開き直って自らをメフィストフェレスの眷族でもあるかの如くに権勢を揮ふ事ばかりに現を抜かしては、
――此の世は高高、こんな《もの》。
と、何か此の世の秘密を知ったかの如くに恥知らずにも自己肯定し、さうして我が物顔で此の世を跋扈するのであるが、否、首のみぬらぬらと伸ばした轆轤首として《存在》するのであったが、その《存在》の根拠と言へば、唯単に『己は唯一無二の《存在》に違ひない』といふ余りに拙い根拠しかないのである。むしろ、「現存在」が此の世に《存在》する時に猪の一番にすべき事は徹底的に自己否定する事であり、それは、《死者》達に対する感謝であり、此の世の至る所に《存在》するであらう神神達に対する礼であり、悪魔を手玉に取る狡猾さを兼ね備へた、つまり、此の世は一寸先は闇といふ事を知り尽くした上での或る達観にも似た有様に違ひないのである。断言するが「現存在」は宇宙史上一度も此の世の王になった事はなく、「現存在」は徹底して此の世の下僕でしかなかったのである。然しながら、《世界》と「現存在」の帰属を問題にする限り、どちらが上位であるのかといふ権力闘争に終始し、仕舞ひにはそれに夢中になり、最早、傍から見れば如何にも下らぬ事に現を抜かしてゐるだけに過ぎぬのであるが、当の「現存在」は、その《世界》の権力闘争が恰も「自由」の獲得であるかのやうな誤謬に陥り、遂には闘争する事自体が面白くて仕様がないといふ全く本末顚倒した事態に己の快楽を見出してしまって、それに惑溺するに違ひないのである。しかし、「現存在」の《世界》を統べるなどといふ如何にも傲慢な思考法は、本来であれば、産業革命以前にはなかったに違ひなく、「現存在」は蒸気機関といふ人力以上の「力」を手にしてしまった故に、《世界》、つまり、住環境の改変を何食はぬ顔で、それが恰も「自然」であるかの如くに行ひ、《世界》の王として「現存在」が此の世に屹立するといふ幻想に酩酊するのであるが、しかし、仮令、「現存在」が此の世の王として君臨したからといって何にも変はった《もの》はなく、独り自惚れた「現存在」のその《存在》の危ふさのみが一際際立つ事になるのである。つまり、《世界》は「現存在」が幾ら「自然環境」に手を加えようが、そんな事は眼中になく、例えば、天災としてそれは「現存在」に圧し掛かるのである。《世界》は眦一つ動かすことなく、「現存在」を殺すのである。その手捌きといったなら芸術的ですらあり、天災を前にして唯唯茫然自失の態で「現存在」ははっきりとした敗北感を心の底で味はひ尽くし、さうして、涙が枯れた面をくっと上げて、尚も《生》を、生き残ってしまった《もの》の宿命として、その《生》を生き直すのである。
さて、其処で問題となるのが、生き残った「現存在」の自虐であり、果たして己は生きてゐていいのであらうかといふ疑問、つまり、己の《存在》に対する疚しさに絶えず苛まれ、《死者》の眼前に引き出されては《死者》達の審問を受けるのを常としてゐる事なのである。また、さうでなければ、生き残った「現存在」は生くるに値しない筈で、如何に己が《死》に近しい《存在》であったかとの自問の中で泣き叫ぶのである。
――嗚呼、《吾》、何故に生くるに値するのか――。
と。さうする事で、生き残った「現存在」は己を自己愛撫しながら、懸命に生くるのである。さうでなければ、「現存在」は生くるに値せぬといふ断念が生じてゐる魂魄に正直になれず、あれ程までに執着してゐた《世界》の王の玉座になんぞ、見るにも値せぬ《存在》でしかない事を心底味はふのみなのである。
――それは《世界》と和睦するといふ事か?
と、《死者》達に問ひかけるのであるが、《世界》は沈黙したまま、何にも語らぬのである。
果たして「現存在」が《世界》と和睦する事は可能なのであらうか。仮に可能とすれば、それは如何なる状況で可能なのであらうか。
例へば、此の世の彼方此方に口を開けてゐる「パスカルの深淵」に「現存在」が自ら進んで落っこちればその時、《世界》と「現存在」の和睦は可能なのであらうか。そもそも「現存在」と《世界》の和睦は、其処に《死》が介在せねば不可能に違ひなく、仮にそれが可能であったとしても、「現存在」は《生者》である内は此の世の王として《世界》を牛耳りたいのが山山で、それ故に「現存在」は《世界》から浮いた《存在》として此の世を生きるのである。つまり、「現存在」が《生者》である限り、「現存在」と《世界》の和睦は夢物語に違ひなく、現実には「現存在」と《世界》の和睦は、不可能のやうに思へて仕方ないのである。それは 何故かと問はれれば、ドストエフスキイではないが、「現存在」は己の事を虱以下、若しくは南京虫以下の《存在》と看做してゐるのが真っ当な「現存在」の有様なのだが、それとは反対にこのやうな《世界》の中にあって、自己肯定出来てしまふ「現存在」といふものを思ふだけでかなり胸糞悪い《もの》で居心地が悪くて仕様がないのであったが、少なからぬ「現存在」は何の躊躇ひもなく自己肯定する事が可能なのであった。それは「現存在」の無知によるとしても、その傲慢さは許し難く、そもそも「現存在」は、此の世において、自己肯定出来る程に何か《存在》の中にあって一際際立つ何かを持っているのかといふ疑問にはたと思い至り、そこで思考停止したやうに《吾》は《世界》といふ《存在》を前にして屈辱のみを喚起する《存在》に堕すのが《自然》の道理なのである。この問ひに対する答へは至極簡単で、《存在》といふ言葉を前にしただけで如何なる《存在》も「平等」である筈で、独り「現存在」のみが優遇される理由なぞそもそもないのである。つまり、《吾》とは虱や南京虫に等しく、否、それ以下の《存在》である。といふのも虱や南京虫は《自然》の摂理に従って、決して其処から食み出ようなどとは微塵も考へることはなく、独り「現存在」のみが《世界》から食み出ることを欣求するのである。つまり、虱や南京虫は天命に逆らふといふやうな野望、若しくは欲望を持つ事はなく、只管に《自然》の摂理に従ひながら、その《生》を終へるのである。その点、「現存在」はじたばたと足掻くのである。己が何か偉大な《もの》であるかの如く振舞ひ、さうして、《存在》界の君主として君臨するかの如き大いなる野望、否、誤謬の中で狂ふのである。狂気のみが「現存在」を「現存在」たらしめる根拠に違ひなく、また、《世界》が行ふ傍若無人の仕打ちに対しても、独り狂気にのみ、「現存在」がその《存在》を《存在》たらしめてゐる事実に対する免罪符となるのであった。
とはいへ、《吾》の誕生において「現存在」は何の原罪も背負ってゐないと思へるのであるが、思春期の或る日を境にして、「現存在」は己に対して唯唯嫌悪感ばかりが湧き立つ事態に無理矢理にも抛り込まれるのである。その理由は、多分、「現存在」が《死》すまで、否、《死》しても尚、不可解なままに違ひなく、《吾》は《吾》の中に芽生えてしまって、その《存在》を《異形の吾》としか呼びやうがない《もの》として苦悶し呻吟しながら、その《存在》を承認する外なく、さうすると、《吾》とは分裂する《もの》の総称でしかないといふ事になるのである。つまり、《吾》は受精卵が細胞分裂をする如くに分裂を繰り返し、例へば、一人の人間が約六十兆個の細胞で成り立ってゐるが如くに、それを無理矢理頭蓋内の闇たる《五蘊場》に《存在》するであらう《吾》といふ《存在》にそのまま当て嵌めるとするならば、《五蘊場》の《吾》、若しくは《異形の吾》もまた、六十兆個の《吾》により出来てゐて、その《吾》が変幻自在にその姿形を変へて、《吾》の《五蘊場》に出現すると看做せなくもないのである。
実際、《吾》といふ《もの》は、変幻自在でなくては此の世で生存する事は不可能で、時に暴君と化す《自然》の中で生き延びるには、《吾》は、先人達から脈脈と受け継がれてきた智慧をして、その荒ぶる《世界》に対峙する筈なのである。その時、「現存在」は自己保持する為に絶対的な《過去》の遺物でしかない先達の智慧に縋り付く事でやうやっと時間が《過去》から《未来》へとその流れを反転させる激動の中においても尚、揉みくちゃにされながらも《個時空》といふ小さな小さな小さな時空間のカルマン渦を消滅させる事なく、渦は渦として存続させる筈なのである。さうでなければ、生物はこれ程までに多様に《存在》する筈はなく、然しながら、「現存在」のみ先達の知恵を蔑ろにした故に疑心暗鬼に陥り、一方で、その先達の知恵を誇大に解釈し、一方では過小評価するといふ紊乱と傲岸不遜の中で『《吾》ありき』などと嘯きながら、此の世に存続できているのは偏に《現在》を《生》きている「現存在」の詰まる所は浅墓な智慧でしかないのけれども、その智慧による《もの》と胸を張ってゐるのであるが、その姿ほど醜悪な姿はないのである。《現在》といふ皮袋たる《吾》においてのみ反転する《過去》と《未来》の時間の流れに《吾》は翻弄されながら、もう闇中に消え入りそうな《吾》が、その防塁としていた《吾》の《五蘊場》が既に解明され、つまりは謎が解かれて《五蘊場》は無惨にも崩壊するといふ危ふい状態に置かれてゐる事に気付いている《吾》は、それを素知らぬ顔で厚顔無恥にもその因を《世界》に向け、《世界》の改造を何の疚しさも感じずに行ってしまったのである。つまり、脳絶対主義の《世界》を出現させてしまったのである。
さて、さうなるともう手遅れなのかもしれぬが、これまでは手に負へぬものであった《自然》の脅威に対して現代文明はそれを乗り越えたといふ錯覚の中に一時期陥り、既に《楽》を知ってしまった「現存在」はもう後戻り出来ずに、最近頓に増へた傍若無人な《自然》の荒ぶる振舞ひを更なる文明の進化によって鎮めるといふ超絶技巧な離れ業をやらうとしてゐるのである。このやうな生物の存続の危機に対しての大いなる矛盾を抱える事になった「現存在」は、「えいっ」とばかりにもんどりうちながら未来に突き進む外ないと観念し、悪足掻きしながらも《吾》は大いなる悔悟の中に《存在》するのも確かで、そして、《吾》はそれ故にこれまで味はった事がない途轍もない屈辱の中でもがき苦しみながら《過去》と《未来》が反転する《現在》を《生》きるといふ《吾》のその余りの浅薄な《存在》の重さを味はひ尽くさねばならぬのであった。つまり、太古よりこの方唱へ続けられて来た芥子粒の如くにしか「現存在」の命の重みはないといふ事を心底味はふしかなかったのである。
――ぶはっはっはっ! よく臆面もなく芥子粒などと言へるもんだぜ。恥ずかしくないのかね? それこそ、太古の昔より言ひ続けられて来た文言ではないかね? へっ。余りに陳腐で嗤ふしかないぜ。ちぇっ。
――ふん。そんな事は言はれなくとも解かり切った事さ。勝手に嗤ひたければ嗤ふがいい。しかし、《吾》なる《もの》の《存在》は己では避けようがない《もの》として既に《存在》しちまってゐる。さうして、《吾》は《吾》を受肉してゆくのさ。
そもそも受肉とは何なのであらうか。《吾》は《吾》を一生賭けて受け容れてゆく《存在》なのであらうか。仮にさうだとすると、《吾》は相当な白痴といふ事になるが、これ如何、などと己に対して余りにも古風な疑問を何か最先端の問題であるかのやうに装ひながら論(あげつら)ってみ、しかしそれは何の事はない、古人の言葉の重さを今更ながら味はふ「生き直し」を、つまり、永劫回帰の全き中を闊歩するかの如く《生》を繋げるやうにして、《吾》といふ《もの》は、何《もの》をも《存在》たらしめてしまふその端緒でしかないに違ひないと思ふしかなかったのであった。
さて、《吾》が《吾》であると気付く時のその刹那の悲劇は見るも無惨な《もの》であった筈である。或る日、それは忽然と《吾》にやって来るのだ。それまで《吾》の思考の片隅にも《存在》してゐる素振りさへ見せなかった《吾》といふ概念に《吾》は気付くのである。その時の《吾》の狼狽ぶりは、見てをれぬ程に醜い《もの》な筈なのである。さうでなければ、《吾》は《吾》を欺いてあかんべえをしているに違ひないのである。
――「私」は《吾》?
と、不意に《吾》の《五蘊場》に立ち上ったその《吾》といふ思ひに戸惑ふ《吾》は、その時を境に《吾》に首ったけになるのである。最早、《吾》が四六時中考へるのは、全てこの《吾》の事であり、また、《吾》に関係した《もの》なのでしかないのである。しかし、それでも尚、正気の《吾》は、孤軍奮闘するかのやうに《吾》に対して懐疑の目を向け、しかも、不思議なことに《吾》に首ったけな《吾》と《吾》に懐疑の目を向ける《吾》は「私」においては共存してゐて、「私」は《吾》なる《もの》と《吾》ならぬ《もの》の間を揺れ動きながら、常に《吾》から摂動してゆく《吾》を追ひかけるのである。さうかうしている内に《吾》はそんなどっちつかずの《吾》に痺れを切らして、その《吾》の有様に大いなる疑問を抱き、其処で《吾》は《吾》の全顚覆を企てるやうになる事が、《吾》の健全な成長過程であるに違ひないのである。
――へっ、《吾》の全顚覆? そんな事は《吾》が可愛くて仕方がない《吾》にとっては土台、無理な話で、そんな不可能事に現を抜かす《吾》の行き着く先は大概《吾》といふ《もの》の思弁的な遊行でしかなく、それは、詰まる所、暇潰しでしかないぜ。
確かに《吾》による《吾》の全顚覆はあり得る筈もなく、《吾》は、《吾》なる《もの》と《吾》ならぬ《もの》の間で常に摂動してゆく《吾》を追いかける鬼ごっこに現を抜かしては、余りにも馬鹿げた『《吾》の全顚覆』を夢見るのであるが、しかし、それは大概の「現存在」にとっては蚊に刺されたかの如くに心に多少の痒みを催す《もの》でしかないのである。さうとは言へ、中には、その摂動する《吾》とのそのずれに底無しの深淵を見てしまって、最早、一歩たりとも其処から身動きが取れなくなって仕舞ひ、遂にはその深淵の虜になってしまって、その深淵から絶えず漏れ聞こえてくる《吾》に対する呪詛の呻き声の言葉の数数に心を完全に打たれて奇妙な共鳴を起こす《吾》の打ち震へる深奥をどうする事も最早不可能の態で、そんな《吾》は、一一その呻き声に感銘を受け、それはさながら、雷に打たれたがの如き衝撃をもって《吾》の内奥に棲む《吾》といふ名の何かと共鳴を起こし、しかも、尚更にこの《吾》を顚覆させねばならぬとの苦悶を深め、さうして、《吾》は《五蘊場》に出現する事になる《異形の吾》を次次と惨殺しては、
――これは違ふ!
と、《異形の吾》を殺す度毎に嘆くのであった。つまり、それは《吾》の思索の浅薄さしか物語ってをらず、その己の思索の浅薄さに比例するやうにして《異形の吾》は《五蘊場》にその醜い姿を現はし、《異形の吾》は泥人形か木偶の坊のやうな余りにも低能かつ下等な御姿で現はれては、《神》との比較において「現存在」を曲がりなりにもこの世に出現させた《神》の見事な手捌きには未来永劫に手にする事が出来ぬ己の無力感に苛まれながらも《吾》は涙を流しながら次次と現はれる《異形の吾》を惨殺する外なかったのである。つまり、《吾》とは「先験的」に哀れな《存在》としてしか《吾》には現はれないのである。しかし、其処で自己愛に堪へ切れずに自慰すると、たちまち、その自慰行為の中毒となり、自慰する事で哀しい《存在》である《吾》の置かれた位置を一瞬でも忘れるやうにして、《吾》は此の世に屹立してしまふのであった。それはあまりにも無防備な出で立ちであり、そのやうな《吾》は摂動する《吾》とのずれに開いた底無しの深淵に転げ落ち、しかし、それが落下だとは全く気付かず、自由落下してゐる時の浮遊感として飛翔の心像の中に哀れにもひっそりと《存在》する《吾》を見つけては、それが《異形の吾》とは全く気付かずに自己は自己に同一してゐるかのやうな幻想の上で胡坐を舁く《吾》を見出だすのが関の山なのであった。
だが、しかし、《吾》はそんな《吾》に対して途轍もない居心地の悪さを覚え、さうなると、最早、一時も《吾》である事が我慢がならぬ事態へと移行するのは必然なのであった。だからと言って《吾》に為す術はなく、只管、《吾》が《吾》である事に我慢する事に終始する事もまた、必然で、《吾》は《吾》なる事に断念する事でやうやっと《吾》は《吾》である事を受け容れるのである。これを悲劇と言はずして何を悲劇と言へようか。《吾》は《吾》である事が既に悲劇であるといふ皮肉。しかも、これは悲劇でありながら、多分に喜劇の要素を多く含んだ《もの》なのも確かなのである。つまり、この《吾》の人生における振舞ひは此の世にまたとない喜劇へと難なく変はるのである。この悲喜劇をして、《吾》は《吾》に対して道化師を演じて見せて、絶えず《吾》が《吾》である事を思惟する事態――これは余りに深刻な事態なのである――を回避するのであった。しかし、そんな状態も長続きする筈もなく、多分、誰しも、否、何《もの》も《吾》なる《もの》の瓦解を経験してゐる筈なのである。そして、それに対して大概の《存在》は無関心を装ひつつ、次第に《吾》に対して不感症になってゆくのが常なのであるが、中には《吾》が《吾》である事をどうしても受け容れられずに《吾》が《吾》に躓く《存在》がゐるのであるが、しかし、だからと言って、《吾》は既に何に対して呪詛してゐるのかも解からずに、只管、此の世を呪ふのである。その狎れの果てが轆轤首なのである。最早、歩く事すら出来ない轆轤首として此の世の不条理に順応してみせた轆轤首の《吾》は、仕舞ひには首を伸ばす事すら面倒臭くなって、やがては轆轤首の首を自らの手でぶった切り、さうして、首と切り離されし肉体を自らの手で撲殺せずにはゐられぬ哀しき《存在》として、《吾》は此の世に《存在》するのである。それでは何故に《吾》は《吾》の首のみ残して肉体を撲殺しなければならぬのであるか。その答へは簡単な事なのである。《吾》もまた動物だからである。動物故に「心」、若しくは「意識」を自覚してしまった故に、首と胴体とが乖離を始め、仕舞ひには《吾》は、この余りに不合理な肉体を《吾》から切り離して、此の世から抹殺せずには気が収まらぬのである。これは、《世界》が《吾》に強要する《もの》で、誰もが己を轆轤首として意識し、更に《世界》に順応するべく首をぶった切るのである。さうして、《吾》の不合理なる肉体を自らの肉体を自らの手で殴り殺すのだ。さうして、《吾》にとっては最早不合理でしかなくなってしまった肉体の《存在》を此の世から抹消するのである。さうして、一見この《世界》を自由に飛び回ってゐるかの如き錯覚、否、誤謬の中で《吾》は遂に《吾》を見失ふのである。これは、しかし、《吾》が望んでゐる宿願に違ひなく、《吾》は《吾》といふ呪縛から遁れられる筈なのであるが、吾(わ)が肉体を撲殺してしまったことで、尚更我執に囚はれては《吾》に拘泥するのである。そして、そんな《吾》は次第に腐敗してゆき、《吾》は何時しか、腐敗Gasに変化してゐて、尚且、石ころの《吾》が《五蘊場》に転がってゐるのである。そして、その腐敗Gasは石ころの《吾》を中心に経巡り始め、渦動するのである。それが《吾》の「生まれ変はり」の儀式であり、その時、《吾》は《吾》に対するささやかな祝祭を催すのであるが、しかし、さうした状況下にある《吾》はちっとも《吾》が実在する《もの》として甦る事はなく、只管、石ころの《吾》の周りを腐敗Gasが渦動し続けるのである。何故ならば、この渦動する《吾》未然の《存在》には、決定的な事が欠落してゐるのである。それは、腐敗Gasが凝結する核が、何時まで経っても出現しないからなのである。しかし、それは、至極当然の事で、《吾》は《吾》の肉体を撲殺し、此の世から抹消させてしまった故に、石ころの《吾》の周りを経巡る腐敗Gasとしての《吾》は、終ぞ《吾》が雪の結晶の如くFractalに成長しゆく《吾》といふ何《もの》にも代へ難い核を失ひ、《吾》を「新たに生まれ変はらせる」その核の不在は、何時まで経っても《吾》を《吾》未然なままに留まらせる原因になってしまうふのである。ところが、それに気付いた処で、《吾》未然の《吾》為らざる《吾》には遅きに失してゐて、未来永劫《吾》未然の《吾》為れざる《吾》が中有を彷徨ふ事になるのであった。
つまり、何れの《吾》も成仏する事はなく、《死》しても尚、この地を彷徨ふのである。それが《吾》の此の世に対しての最低限の礼儀であり、また、中有に彷徨ふばかりの、轆轤首の首をぶった切り、《死》した吾が肉体から発したに違ひない《吾》といふ腐敗Gasと遅遅と時間が進まない石ころと化した《吾》が、渦動し、ずっとそのままの状態であり続ける《吾》未然の《吾》が、果たして、何億年と言ふ時間の長さで凝視し続ければ、其処にはある変化があるかもしれないといふのは余りにも楽観的に過ぎる見方であって、それを打ち砕くには十分な根拠として、《吾》の狎れの果ては《吾》でしかないことにより、自明なのである。それ故に、何億年という星霜でも渦動するのみの《吾》には何の変化もなく、この石ころの《吾》の周りを巡回するその渦状の《吾》は無意識的にも意識的にも『神の一撃』を待ち詫びてゐるのである。《吾》の出現には、《吾》のみの力学では此の世に出現する蓋然性は零に等しく、《吾》は絶えず『神の一撃』を鶴首の如く待ち続け、否、轆轤首として待ち侘びて、さうして《吾》の首は伸びるに伸び切るのであった。
石ころの《吾》の周りを《吾》の腐敗Gasが渦動する《吾》は、つまり、進退窮まった状態とも言ひ得るのである。《吾》を追ひ詰め続けた果ては、この渦動する《吾》が《五蘊場》にどかんと居座るのである。さうして、《吾》は《吾》に対してああでもないかうでもない、と自発的な渦動する《吾》の瓦解を願って已まないのであるが、哀しい哉、《吾》にはそんな力は備はってゐないのである。幾ら《吾》がのた打ち回らうが、最早渦動する《吾》に至ってしまった《吾》は、微動だにしないのである。自然界に起きた素粒子の「対称性の自発的な破れ」を、渦動する《吾》に期待しても無駄なのである。《吾》にはオートポイエーシス(自己作成)する力は、元元備はってゐないのは、《吾》がどう足掻かうが結局《吾》にしか為れぬ事で自明である。さて、それでは、そもそも《吾》は《吾》以外の何かに為らうとする意思を持ってゐるのであらうか。多分、此の世を生き延びて来た事からしてさう看做しても構はぬ筈である。が、しかし、《吾》はどう足掻かうが、《吾》は《吾》にしか為れぬのである。これを絶望と言はずして、何を絶望と言ふのであらうか。
――だが、《吾》は《世界》を弄繰り回せるぜ。
――しかし、それ故に《吾》は自滅の道を歩んでゐるかもしれぬではないか!
――だからかうして、《吾》は《世界》を弄繰り回す事は已められぬのさ。《吾》が変はれぬのであれば、《世界》を変へてしまへ、といふ実に安直な愚行で「脳内世界」を外在化させてゐる。つまり……。
――つまり?
――つまり、外圧には微動だにしない《五蘊場》で渦動を続ける《吾》は、もしかすると進化を已めてしまった進化の極致なのかもしれぬのさ。
――進化の極致? はっ、嗤わせないで呉れないかね!
――しかし、現に《吾》は、つまり、「現存在」としての《吾》は、「脳内世界」を辺り構はず外在化させていったのは間違ひない。
と、間歇的に《吾》が《五蘊場》の闇から容喙するのであるが、しかし、この自問自答といふ《もの》は、《世界》が《吾》に埋め込んだ時限爆弾なのかもしれぬのである。「《吾》は五分と同じ事を思考できない」、とは埴谷雄高の言であるが、思考は、乱数的に彼方此方とその志向の向きを変へて、同時多発的に幾つもの思考が《五蘊場》で重ね合ってゐるのが《吾》である。その点では《吾》もまた、波動の一種に違ひなく、つまり、量子力学の言ふ処の「重ね合はせ」を絶えず行ってをり、《吾》の意思統一、若しくは統覚は見果てぬ夢の如くに、はたまた邯鄲の夢の如くに明かな誤謬に違ひないのである。それ故に、この《吾》には絶えず曖昧模糊として、把捉出来かねる《吾》、つまり、《吾》が想定した《吾》から絶えず摂動するのが、これまた、《吾》の宿命なのである。
逃げる《吾》とそれを追ひかける《吾》の何時果てるとも知れぬ永劫の鬼ごっこは、《吾》が《一》とも《〇》とも為れぬ故に続く事になるのであった。しかし、これは徹頭徹尾自作自演の猿芝居でしかなく、猿芝居故に《吾》は臆面もなく自演出来るのである。つまり、《吾》は徹頭徹尾《吾》の擬態に過ぎず、何かに喰はれぬやうに《世界》に阿(おもね)る事で、生き延びて来たのである。ところが、何時かは自作自演の猿芝居は《吾》の内部告発により、終幕を迎へること必定で、つまり、《吾》が《吾》を騙し続ける事は、この羸弱な《吾》には端から出来っこないのである。《吾》を偽る《吾》は直におくびを出さずば、《吾》は《吾》に対して我慢がならぬのである。《吾》とは「先験的」にさうした《存在》なのである。そこで、《吾》は、《吾》に対して乾坤一擲の大博打を打つ外ないのが実態で、その博打は《吾》の存続を賭けた一大事なのである。つまり、《吾》は《吾》の化けの皮を剝す事に夢中になり、さうして《吾》暴きが彼方此方で執り行はれる様相を呈し、然しながら、《吾》が一皮《吾》の化けの皮を剝いだ処で、更なる《吾》の化けの皮が現はれるのが実相で、即ち、《吾》の玉葱の如き多層構造は、全く以ってFractalな造形をした何かであり、《吾》が《吾》の化けの皮を幾ら剝いだ処で、其処には泰然自若とした次の《吾》の化けの皮が現前するのである。さうして、
――くっくっくっくっ。
と、《吾》に対して不敵な嗤ひをその面に浮かべながら、《吾》を絶えず挑発し続けるのであった。さうなると此方は完全にお手上げ状態で、《吾》に対して、これ以上は追はぬといふ白旗を挙げて、不敵な嗤ひを化けの皮に浮かべる《吾》から退散するのであるが、今度は、鬼が入れ替はり、《吾》が化けの皮を晒す《吾》に執拗に追はれる羽目になる事は自明の理なのである。それ故に、《吾》は化けの皮を晒す《吾》から逃げる事を断念し、その《吾》に対して観念するのである。さうして、《吾》と対峙する化けの皮を被った《吾》はどちらの《吾》が「本当」の《吾》かの区別が出来なくなり、《吾》は二進も三進もゆかずに、唯唯、その場に佇立しては、果せる哉、天に向かって憤懣の言葉を喚き散らす外ないのである。つまり、前述したやうに《吾》の《五蘊場》には幾つかの思考が輻輳してをり、《吾》は此の《吾》であり、あの《吾》でもあり得、また、実際、そのやうにしか《吾》は此の世に《存在》しない筈なのである。つまり、《吾》はこれもあれも《吾》なのである。かうして、《吾》は《吾》の境を見失ひ、次第に《吾》は溶解を始めて、《世界》に溶け出すのである。さうなると、《吾》は恍惚の態で、白昼夢へと飛び込んだ如くに《吾》を見失ふのである。さうして初めて《吾》は《吾》に対する郷愁を覚えるのであるが、既に時遅く、《吾》は《世界》にまんまと騙されたのである。
――あっはっはっはっ。
《吾》は其処で哄笑の大合唱に見舞はれ、最早、打つ手なしと観念しつつも、《吾》は《吾》の内部に沈降するが如くに蹲り、更に身を縮めて、《吾》の内部に閉ぢ籠るのである。さうして、《吾》は石ころの時間が遅遅として進まぬ《吾》に為り果て、最終的に渦動する、しかも《神》無しには未来永劫渦動する外ない渦が、此の世に出現する事に為るのであった。
――へっ、つまり、《吾》は渦かね?
――多分ね。
――多分?
――多分としか言ひやうがないのさ。だって、《吾》ほど《吾》に関して無知な事は《吾》は嫌と言ふほど知ってゐるからね。この《吾》が《吾》に関して全く以って無知な事は異論はないだらう。
――ならば、《吾》とは一体何なのかね?
――単なる幻影、つまり、思ひ過ごしでしかないのさ。
――《吾》が幻影? そんな事は太古の昔から言はれてゐる事で何ら目新しい事はないがね。
――しかし、《吾》とは泡沫(うたかた)の幻影でしかない。それ故に《吾》は、一所懸命に生きるのだ。夢の、つまり、《世界》の裂け目を確かに見出だす為にね。
思へば、此の世は穴凹だらけなのかもしれないのである。《未来》あるいは《過去》へと吸ひ込まれるやうにしてあらゆる《存在》は《現在》に留め置かれ、さうして、《吾》は絶えず渦動するのかもしれぬのである。そもそも此の世のあらゆる《存在》は、時空間の穴凹の底であり、物体が《存在》すれば、時空間は歪み、穴凹として看做せてしまふのである。つまり、《存在》が此の世の裂け目を彌縫したその傷痕であり、《もの》の数だけ此の世は裂けてゐて、穴が開いてゐるのである。《存在》とは、穴凹の底の別称であり、此の世の裂け目の面なのである。ならば、「現存在」が此の世の不合理に無理矢理にも順応して変化した轆轤首は、此の世に開いた穴凹の底より脱出を試みた主体の残滓なのかもしれず、それは、例へるならば、蟻地獄に落っこちた蟻さながらの様相を呈しているに違ひないのである。蟻地獄に落っこちた蟻の苦悶にも似た命の危機に直面するその「現存在」の生き残る術は、当然、蟻地獄のやうな穴凹から這ひ出る事に似てゐる筈なのであるが、「現存在」が実体として《存在》する限り、時空間は歪み、《吾》そのものが時空間に開いた穴凹の底でしかないのである。しかし、首のみが伸び切った上に、自ら首をぶった切り、残された軀体を撲滅する事で浮遊する首のみとなった《吾》は、此の世の穴凹に落っこちて既に自由落下を始めて久しいのである。此の世に対して仮にふわふわとした感覚が少しでもあれば、それは既にその「現存在」が此の世に開いた時空間の穴凹に落っこちてゐる証左に過ぎぬのである。つまり、此の世は野間宏の『暗い絵』の有名な冒頭の息長い文に込められた穴凹と同様に此の世は穴凹だらけ、つまり、裂け目だらけに違ひなく、「現存在」とは、既にその裂け目に落っこちてゐる《存在》の謂ひでしかなく、《吾》はそのやうな何時果てるとも知れぬ自由落下にあるのが実相に違ひないのである。そして、大概の「現存在」はそれを「自由への飛翔」と誤謬してゐて、何の事はない、飛翔する《吾》といふ表象は、墜落した《存在》の謂ひでしかないのである。
さて、其処で《杳体》と言ふ私個人のドクサ(臆見)を引っ張り出すと、この《杳体》といふ《存在》の有様は《存在》に対する或る漠とした杳として知れぬ観念として、それは永劫といふ相の下での無理矢理に導き出した極限としての極値である事に気付く筈である。つまり、この事は何れの《存在》も最終的には杳として知れぬ《存在》、つまり、《杳体》へと解体する外ないのである。そして、「現存在」は、何時の時も、《存在》が《杳体》へと相転移するその中途過程を担ふべき《存在》として絶えず《現在》に《存在》する事を強要されるのである。現存するとは、《未来》と《過去》とが鬩ぎ合ひ、犇めき合ひながらの奔流に生じる羸弱な、そして微少な時空間のカルマン渦に違ひなく、さうしてこの泡沫の《存在》は永劫の相の下では何《もの》もその《存在》が解体されずにはをれず、また、それは杳として知れぬ《杳体》へと相転移するのである。これは例へば、《死》の別称でしかないといふ事も成立可能であるが、《生》若しくは《現在》に《存在》する《もの》にとって《死》は、その《もの》が《生》である限り未知な《もの》のままで、《死》とは徹頭徹尾《他》の《もの》でしかないのである。そして、《現在》において、時空間とは、杳として知れぬ何か未知の領域を必ず含有した何かとして《存在》、或るひは認識されてをり、そのやうにしか《世界》を知り得ぬ「現存在」は、《世界》が未知なる《もの》であるから《生》をわくわくとして生きるといふ一面がなくもないのである。《世界》が未知である故に《吾》はあれやこれやと思考するのであり、《五蘊場》の様相を激変させるのが《世界》の不可思議性なのである。仮令、人類が此の世を全的に微塵の隙間もなく理解出来たとして、つまり、《神》の「癖」を知り尽くし、さうして《神》を撲滅する事に完璧に成功したとして、それに歓喜するのは、論理的に合理的に《世界》のからくりを実証せしめたその張本人でしかなく、また、それを理解出来る《他》は限られた《もの》のみなのである。何《もの》も例へば「宇宙」の成り立ちに関して微塵の狂ひもなく、論理付けしてそれを実証出来た処で、それを言表するには専門用語を駆使しなくては、二進も三進もゆかない筈である。そのことは、現時点においても一般相対性理論や量子力学が万人に理解出来ないやうに、仮に《世界》の秘密が解き明かされた処で、その証明を理解出来るのは、多数派かと言へば、どう考へても少数派でしかなく、限られた専門家にしか理解不能な《もの》に為らざるを得ぬのである。つまり、現時点でも一般相対性理論や量子力学と言ふ此の世を物理といふ物差しで理解するべく、その材料は準備万端に揃ってゐるにも拘はらずに《世界認識》に関して、十人十色の状態を今尚拭い切れぬのは、此の世の摂理と言ふものはそれ程に語るに難しい《もの》で、結局、理論が理解できぬ多数の「現存在」は、経験値でのみで世知辛い此の世を生き抜いて尚、歓喜にある事が可能なのである。つまり、何とも理解不能な《世界》であっても、生き抜いたといふ事で、「現存在」は多分に満足なのである。つまり、多くの《吾》共にとってこの《世界》が未知なる《もの》といふ事は安寧を齎す根拠に十分為り得るのである。つまり、《世界》を隈なく認識出来たとして、《吾》の様相は変化するのか、といふ問ひにぶち当たる事になるのである。この問ひに対する答へとして当然と思はれるのは、どれ程此の《世界》が理解出来得たとしても《吾》の苦悩は軽減されない、といふ事である。今後、如何に文明が発展を極め、《吾》にとって《便利》になった処で、依然として《世界》も《吾》も杳として知れぬ《存在》として《吾》の実存を脅かし、また、立ちはだかり、さうして、そんな《吾》と《世界》の関係の中で、《吾》は、《生》へと縋り付く確率が高いに違ひなく、《世界》が隈なく知り得た故に自死する《もの》が出現した処で、それはそれとして《生》を選択し続ける《存在》にとっては、此の世を《生》き抜く事に、つまり、依然として《存在》する事に飽きる事なく、否、《生》に夢中になり、そして、無我夢中の中で、あっけなく《死》してゆくのである。そんな《存在》にとって《杳体》とは箸にも棒にも掛からぬ《もの》として、つまり、《存在》にとって此の世が未知である事故に、また、謎故に此の世に《存在》する森羅万象を《存在》に繋ぎ止めるその大いなる根拠となり、つまり、《杳体》といふ摩訶不思議な《存在》をでっち上げる事でのみ、此の世に《生》きる事は善な《もの》として《吾》に作用するのは、否定出来ぬの事なのである。
さて、それでは、《杳体》とは何ぞや、との結論を急く此の《吾》にとって《杳体》とは誠に都合がよく使ひ勝手が良い《もの》である事は一面では否定出来ぬのであり、或る時は《死》の面を被り、或る時は無慈悲に「現存在」を殺戮する《自然》のその凶暴さであり、それは、《吾》にとっては変幻自在な何かなのであり、さうであるからこそ、《吾》の《存在》する事の全的な責任は、その杳として知れぬ《杳体》の《存在》をでっち上げる事で、やうやっとその《存在》するといふ重圧に《存在》は堪へ得るのである。つまり、《存在》にとって不可避な孤独の中にある単独者にとって杳として知り得ぬ《杳体》の《存在》は、杳としてゐるが故に絶えず単独者の伴走者なのであり、その伴走者たる《杳体》は、何にでも変化する何かとして絶えず《吾》も《世界》も宙ぶらりんのままに置いておく優しさがある事は、いづれの《存在》も否定出来ぬ《もの》であり、多くの「現存在」の総意と言へるのかもしれぬのであった。つまり、科学に代表される客観的な論理で理詰めで幾ら《世界認識》の度が深まった処で、《吾》が《存在》する限り、《杳体》が《存在》するのは必然であり、また、杳として知れぬ《もの》が此の世に《存在》しなければ、《吾》は絶えず《吾》を推し潰さうとしてゐる《もの》の中で《生》き延びる事は不可能に違ひなく、《杳体》といふ《生》と《死》の緩衝材が《存在》する事で《存在》する《もの》は何とか此の世に《存在》出来得るのである。だからと言って、《吾》は《杳体》の正体を知りたいといふ欲求は抑へられる《もの》でもなく、《吾》は《杳体》を追ふ為に《吾》が《吾》を追ふといふ永劫に続く鬼ごっこを続けざるを得ず、その《吾》と《吾》との摂動により、《吾》の《生》の活力も生じ得、さうして、《吾》特有の《世界認識》へと到達するのである。つまり、それを一言で言ってしまへば、《吾》の《存在》の数だけ《世界》は《存在》し、それ故に《吾》は此の《世界》において《生》を選び得、また《生》の活力を得てゐるのである。当然、《吾》と《他》との《世界》の摺り合はせは必要であるが、それは、しかし、常に曖昧模糊とした《もの》でしかなく、裏を返せば、《吾》と《他》にとって《世界》が漠然と、渺茫とした《もの》であるからこそ、《吾》は此の《世界》を《生》き延びる事が可能となるのである。煎じ詰めれば、何の事はない、《杳体》とは《吾》の実存の尻拭ひをする便利屋の謂ひに外ならず、《杳体》なくしは、《吾》は一時も《生》き得ぬ共存共栄、否、共存共衰の、つまり、《死》へ向かって一直線に驀進する、つまり、其処には寄り道など全く《存在》せずに邁進する外ない《生》の余りに儚い様相が《存在》するのである。その《死》へ向かって一直線、つまり、最短距離の《生》を《生》きる《存在》のみが、此の世に何とか《存在》してゐるに過ぎぬのである。《生》を煎じ詰めれば、《死》への一直線の軌跡でしかないのである。それがどんなに紆余曲折してゐるやうに思はれ、また、他所からさう見られてゐてもである。それは、光が直進しか出来ぬ事と似てゐて、《生》は《死》へ直進しか出来ぬのである。それが宿命といふ《もの》に違ひないのである。
――へっ、それが結論かい? ちゃんちゃらをかしい! そんな事は誰もが既に知ってゐる事なのさ、ちぇっ。
(第三章終はり)