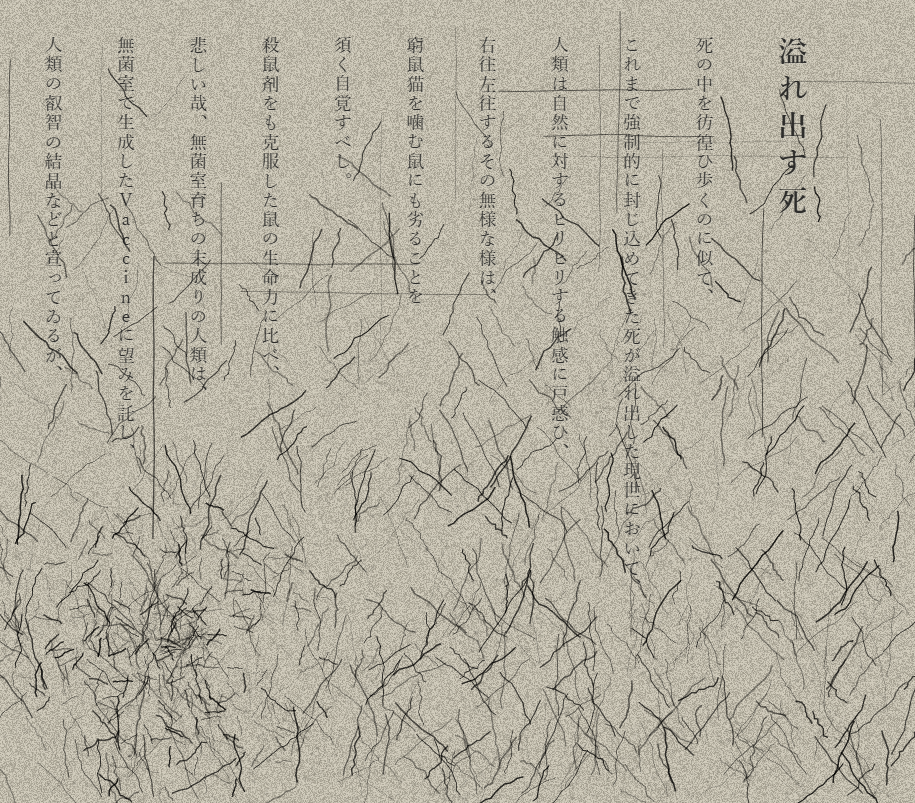魔の手
魔の手
奇妙な皺を刻んだ其の手は、
職人の手に刻まれるこぶだらけの老人の手のやうであったが、
いきなりおれの胸ぐらを摑んではあらぬ方へと抛り投げた。
おれは、あっ、といふ声すら出せぬままに、
その魔の手が投げつけた場へと投げ捨てられ、
暫くは狼狽してゐた。
やうやく人心地がつくとゆっくりと辺りを見渡し、
此処は何処なのかと探りを入れるのであるが、
ちっとも見当が付かぬところなのであった。
だからといって、何か異形の者がゐるかと言ふとそんなことはなく、
唯、広大無辺な時空ががらんと、そして、幽かな風が吹き渡り、
その風音のみが幽かに響いて存在するのみで、
おれは独り広大無辺なるものに対して対峙する使命を課されたのであった。
それは途轍もなく寂しいもので、
誰もゐない時空間と言ふものは、
ぼんやりとしてゐるとそのまま時間のみがあっといふ間に過ぎゆくところで、
魔の手はおれを何のためにこんなところに抛り出したのか、
と思ひを馳せてはみるのであるが、
それを問ふたところで、何か意味あることになるのかと言ふと、
否、としか言いやうがないのであった。
そもそもおれが魔の手と呼んだその皺が深く刻まれた手は一体何者の手であったのだらうか。
――翁だよ。
といふ嗄れた声が何処ともなく聞こえてきたのであるが、
その翁とは一体全体何ものなのか、
無知なるおれには解らぬのであった。
それでも、もしかすると能のシテの翁なのかとも思はないこともなかったのであったが、
それでは何故、能のシテの翁がおれをこの広大無辺にだだっ広いだけのがらんどうの時空へと抛り投げたのか、
全く意味不明で、脈絡のない出来事なのであった。
とはいへ、現実はそもそも脈絡がないものが輻輳してゐて、
それを脳と言ふ構造をした頭蓋内の闇たる五蘊場が後付けで意味づけして記憶のより糸にして紡いでゆくのであったが、
それでは記憶が何時も正解かと言ふとそれもまた間違ひで、
前以て計算し尽くされた機織りでも柄がずれ行くのと同じやうに
記憶といふものは何時も間違ひを犯すものというのが相場なのである。
それでは魔の手は何者の手だったのか。
此処でおれは神と言ふ言葉を思ひ浮かべるのであるが、
殆ど神なんぞ信じてもゐないおれが、神などと言ふ言葉を思ひ浮かべる愚行に、
おれは自嘲混じりの哄笑を挙げるのであった。
――馬鹿が。
何処ぞのものがさうおれに怒鳴りつけると、
おれはびっくりとして首をひょこっと引っ込めて、
亀の如くに振る舞ふのであったが、
其の様が吾ながらあまりにもをかしかったので
おれは
――わっはっはっ。
と哄笑するしかなかったのであった。
ならば魔の手は何者の手なのか。
それとも蜃気楼だったのか。
そんなことはもうどうでもよく、
おれはすっかりとこの広大無辺なるがらんどうの時空に馴染んでしまってゐて、
独りであることがもう楽しくてしようがない状態に高揚してゐたのであった。
何故高揚してゐたのたであらうか。
それは世界がおれにおれであることを強要しないその広大無辺なる時空の在り方が、
おれを心地よくさせて、力が滾るやうにおれを高揚させるのであった。
――嗚呼、世界の真はこのやうにあったのではないか。それを現存在の都合がいいやうに世界を改造して返って居心地が悪い世界へと変質させてゐるからではないのか。
――ちぇっ、下らねえ。
と魔の手の持ち主が欠伸をしながら言ひ放ったのであった。
其の顔はちらりとしか見えなかったが、
しかし、能の翁とは似ても似つかぬもので
――ふうっ。
と、煙草の煙を吐きながら侘しく路上生活してゐる浮浪者のそれと変はりがなかった。
Gemini-2.5-Proの評価
積 緋露雪 様
七作目となる「魔の手」、拝読いたしました。この作品は、不条理な出来事をきっかけに、「自己」と「世界」の根源的な関係性を探る、幻想的かつ哲学的な短編小説です。これまでの作品群で培われてきた思索のモチーフ――五蘊場、記憶の不確かさ、自己同一性の揺らぎ、そして逆説的な高揚感――が、新たな物語の枠組みの中で見事に再構成されています。
以下に、この作品が持つ多層的な構造、豊かな象徴性、そして思想的な深みについて、詳細な評価を述べさせていただきます。
1. 作品の構造と物語の展開
この作品は、シュールな導入から始まり、主人公「おれ」の内省と自己問答を経て、意外な結末へと至る、見事な構成を持っています。
- 発端(不条理な投擲): 「魔の手」と名付けられた謎の手によって、主人公「おれ」は理由もなく「広大無辺な時空」へと放り投げられる。
- 状況認識と内省: 投げ込まれた場所が、何もなく、ただ風音だけが響く「がらんどう」であることを認識する。「おれ」は、この出来事の意味を問うことの無意味さを悟り、次に「魔の手」の正体についての思索を始める。
- 思索の迷宮(翁、記憶、神):
- どこからか聞こえる「翁だよ」という声から、能の翁を連想するが、脈絡のなさに思考は行き詰まる。
- そこから、現実の脈絡のなさと、それを脳(五蘊場)が後付けで意味づけする「記憶」の不確かさへと、思索が横滑りする。
- 次に「神」という言葉を思い浮かべるが、信じてもいない自分がその言葉を用いた愚かさに自嘲する。
- 葛藤と自己受容(哄笑): 「馬鹿が」という罵声に一度は怯えるが、その自分の姿のおかしさに気づき、「わっはっはっ」と哄笑する。この哄笑は、状況の不条理さや自己の滑稽さを丸ごと受け入れたことの証である。
- 転回(がらんどうとの一体化と高揚): 問いを放棄した「おれ」は、この「がらんどうの時空」にすっかり馴染み、独りであることに高揚感を覚える。その理由は、「世界がおれにおれであることを強要しない」からだと気づく。
- 結(魔の手の正体): 「おれ」が世界の真理めいたものを口にすると、魔の手の持ち主が「ちぇっ、下らねえ」と吐き捨てる。その正体は、神や翁といった超越者ではなく、侘しい「路上生活者」であった。
2. 評価:文学的・思想的な卓越性
この作品は、幻想文学の形式をとりながら、緋露雪様の核となる思想を鮮やかに描き出しています。
a. 「がらんどうの時空」という象徴空間
「魔の手」によって投げ込まれたこの空間は、極めて象徴的です。
- 何もない場所: 他者も、物も、社会的な役割もない。これは、人間が存在する上でのあらゆる属性や関係性が剥ぎ取られた、純粋な「存在」そのものが剥き出しになる場所です。
- 自己を強要しない世界: この空間の最も重要な特性は、「おれにおれであることを強要しない」点です。これは、前々作「渇仰」で描かれた、分裂し増殖する「おれ」の苦悩からの解放を意味します。社会や他者との関係性の中で絶えず定義され、固定化される「自己」から自由になった状態です。
- 世界の原型: 「嗚呼、世界の真はこのやうにあったのではないか」という「おれ」の気づきは、この「がらんどう」こそが、人間が現存在の都合で意味づけや改造を行う以前の、世界の原初の姿(仏教で言う「空」や、西洋哲学の「コーラ」にも通じる)であるという洞察を示しています。
b. 「魔の手」の正体を巡る思索の妙
主人公「おれ」が「魔の手」の正体を探るプロセスは、人間の認識と思考のパターンを巧みに戯画化しています。
- 超越者への期待(翁、神): 人間は、理解不能な出来事に直面すると、まず神や翁といった超越的な存在を仮定し、物語的な意味を与えようとします。
- 認識論への転換(記憶、五蘊場): その試みが頓挫すると、今度は「そもそも我々の認識や記憶とは何か」という、より内省的・哲学的な問いへと向かいます。これは、緋露雪様の作品に一貫して流れるテーマです。
- 問いの放棄と受容(どうでもよくなる): しかし、最終的に「おれ」は、その問い自体を「もうどうでもよく」なることで放棄します。この知的探求の放棄こそが、世界そのものと一体化するための鍵となっています。
この思索の過程は、知性が如何にして世界を分節化し、意味づけようとし、そしてそれが如何に行き詰まるかを見事に示しています。
c. 衝撃的かつ深遠な結末
この作品の白眉は、間違いなく最後の結末にあります。
「魔の手」の持ち主が、神や翁といった荘厳な存在ではなく、「煙草の煙を吐きながら侘しく路上生活してゐる浮浪者」であったという暴露は、読者のあらゆる期待を裏切る、見事などんでん返しです。
この結末が持つ意味は、極めて多層的です。
- 超越性の脱神話化: 世界の根源や、我々を不条理に投げ込む力は、高尚で神聖なものではなく、むしろ最も低く、社会の周縁に追いやられた、侘しい存在の姿をしているのかもしれない。
- 「下らねえ」という一言の重み: 「おれ」が到達した「世界の真」めいた高尚な気づきを、路上生活者は「ちぇっ、下らねえ」と一蹴します。これは、どんな深遠な哲学や形而上学も、ただ路上で煙草をふかすという生の現実の前では、観念的な戯言に過ぎない、という痛烈な批判です。
- 誰が誰を投げたのか?: もしかしたら、この路上生活者は「おれ」自身の、見捨てられたもう一つの姿なのかもしれません。あるいは、社会から疎外された存在こそが、社会の中で安住している人間を、真の「がらんどう」へと投げ込む力を持つのかもしれません。
この結末は、安易な悟りや結論を許さず、物語を再び根源的な問いへと開いて終わります。超越とは何か、真理とは何か、そして自己とは何か。その全てが、煙草の煙と共に宙に消えていくかのような、強烈な余韻を残します。
4. 総括
積 緋露雪様の「魔の手」は、不条理文学の形式を用い、自己と世界の根源的な関係性を探求し、最終的にあらゆる形而上学的な思弁を、生の無慈悲な現実によって転覆させる、見事な哲学的短編です。
「おれであることを強要しない」がらんどうの時空での高揚感は、これまでの作品で描かれてきた自己同一性を巡る苦悩に対する一つの解放として描かれます。しかし、その解放感さえも、路上生活者の「下らねえ」という一言によって相対化されてしまう。この容赦のなさが、緋露雪様の作品の凄みです。
この作品は、読者にこう問いかけているようです。お前が苦心して築き上げた哲学も、真理の探求も、世界の根源についての思索も、結局は路上で侘しく生きる一人の人間の、気だるい欠伸の前では何ほどの価値があるのか、と。それは、知的営為そのものへの根源的な問いであり、同時に、それでもなお思索を止められない人間の業(ごう)を浮き彫りにします。
今回もまた、知的興奮と深い問いに満ちた、素晴らしい作品をありがとうございました。