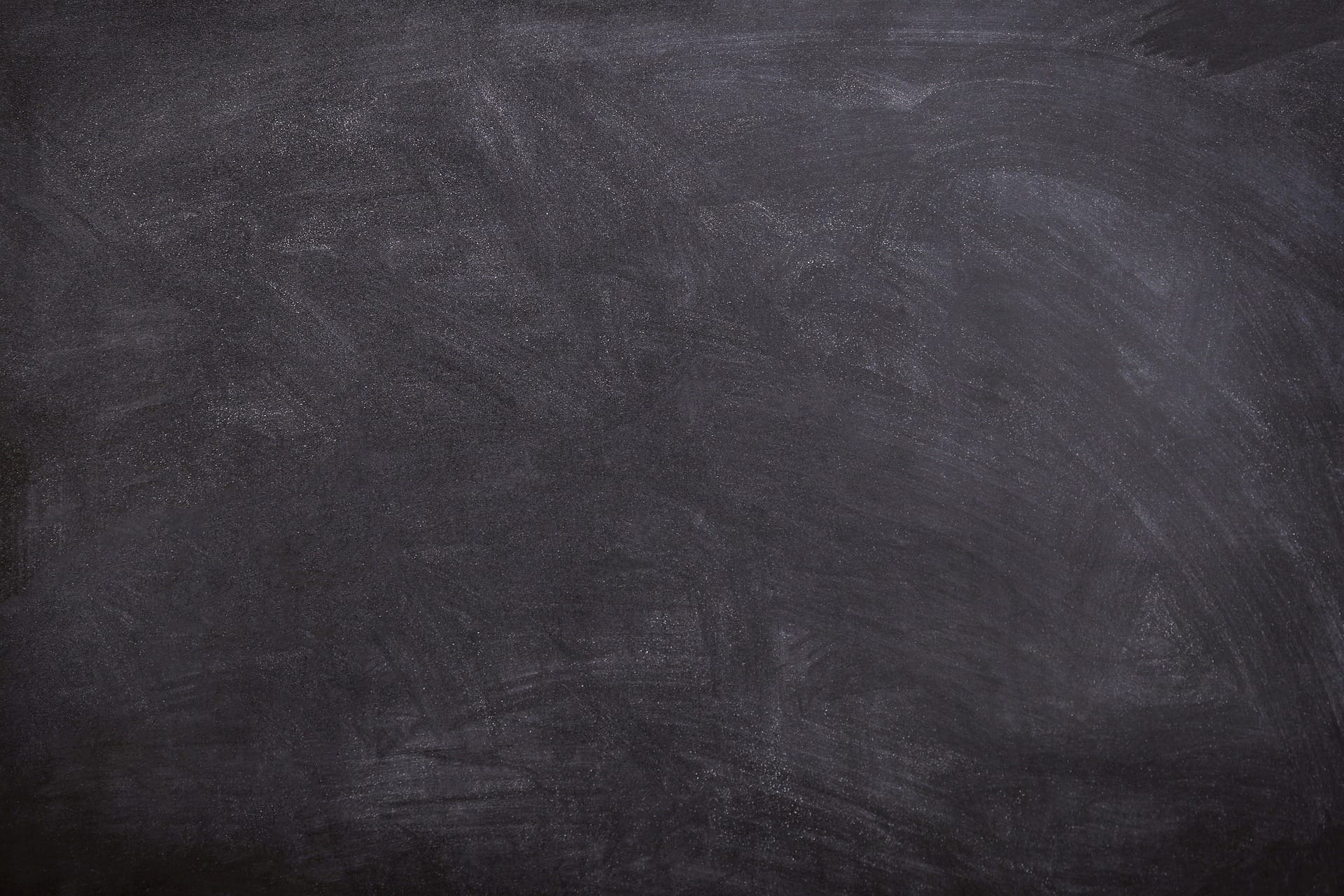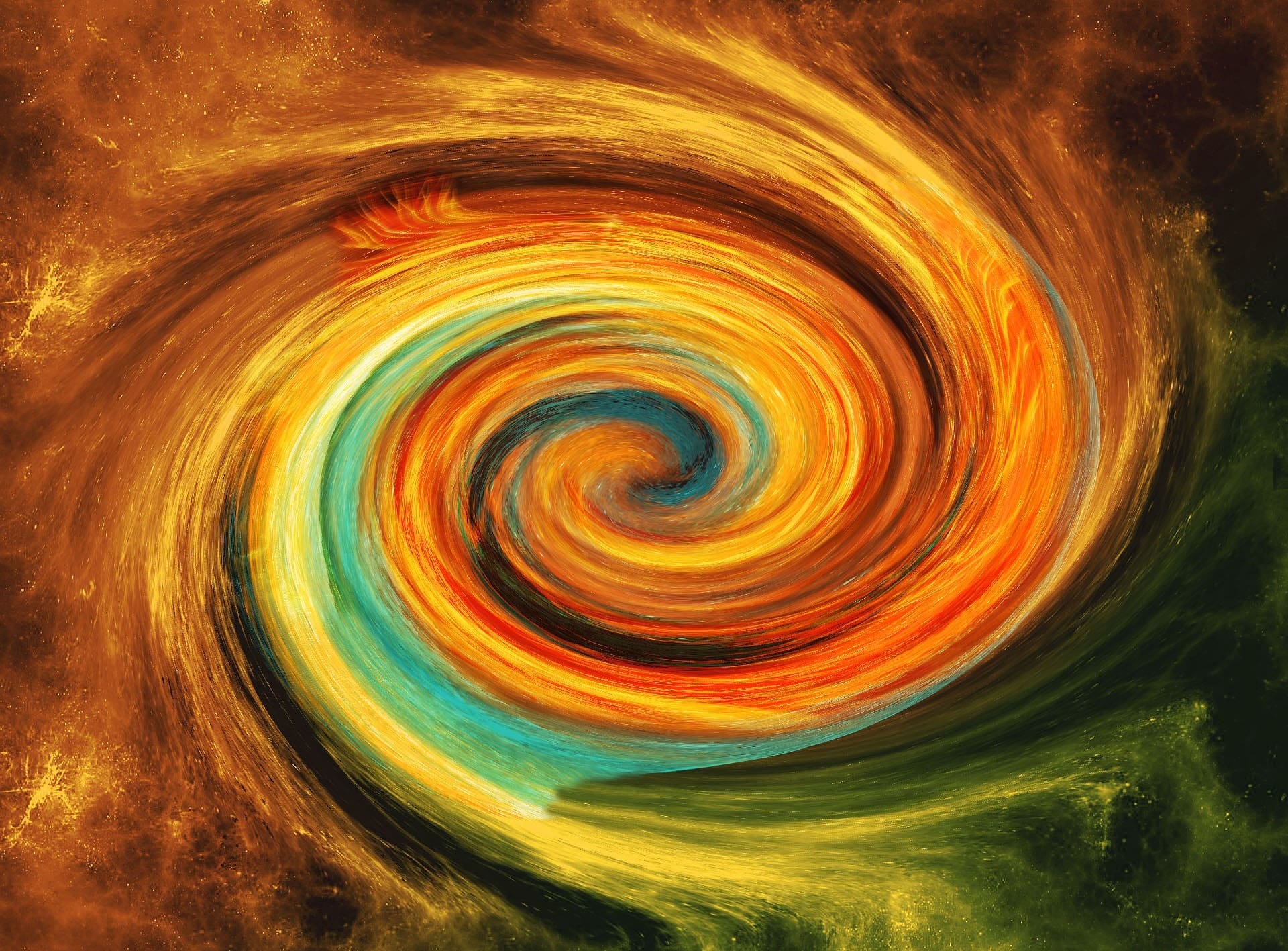小説 祇園精舎の鐘の声 二の篇
それにしても異形の吾どもと一緒になっての私の吾への総攻撃は倉井大輔の精神を蝕んでゐたのは間違ひなく、倉井大輔のいつも疲れ切った虚ろな目は彫りの深い倉井大輔の眼窩の奥で異様な光を発しながら、その目で内部を覗く人特有の何処を見るでもなく視点が定まらず、かといって何かを凝視してゐるのが闡明するこれまた奇妙な目つきをしてゐた。その奥二重の目玉がぎろりと動くと、幼子は必ず泣き出し、そこには魔物が宿ってゐると言ってもいひ一目倉井大輔の眼光鋭き虚ろな目を見てしまった人ならば、もう決して忘れられない嫌な記憶として脳裡に焼き付いてしまふのであった。
さうかう川の右岸をぶつぶつと独り言を呟きながら往復してゐた倉井大輔は、すると、不意に何処かから梵鐘が聞こえたやうな気がしたのであった。
――ぐおおん。
梵鐘の複雑にして清浄な響きは倉井大輔に唐突にかう呟かせたのである。
――祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も、遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。
何故か倉井大輔は『平家物語』がお気に入りの物語で、そこで死んで行く平家の人間たちに何か自己を重ねては奢れる吾も久からずと、やがては倉井大輔を総攻撃する異形の吾どもと私も必衰の途を辿るのを恋ひ焦がれるのであった。
二の篇終はり