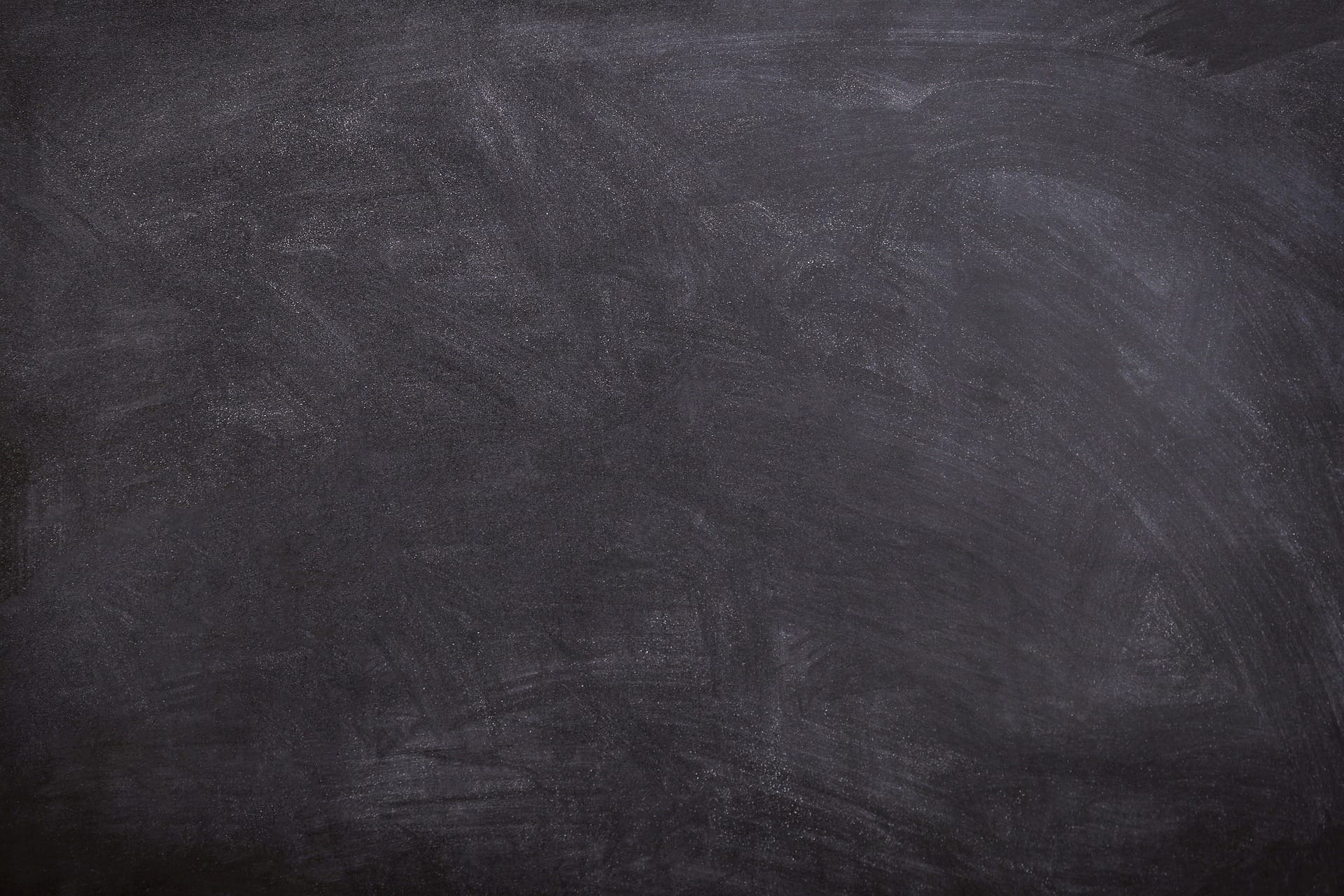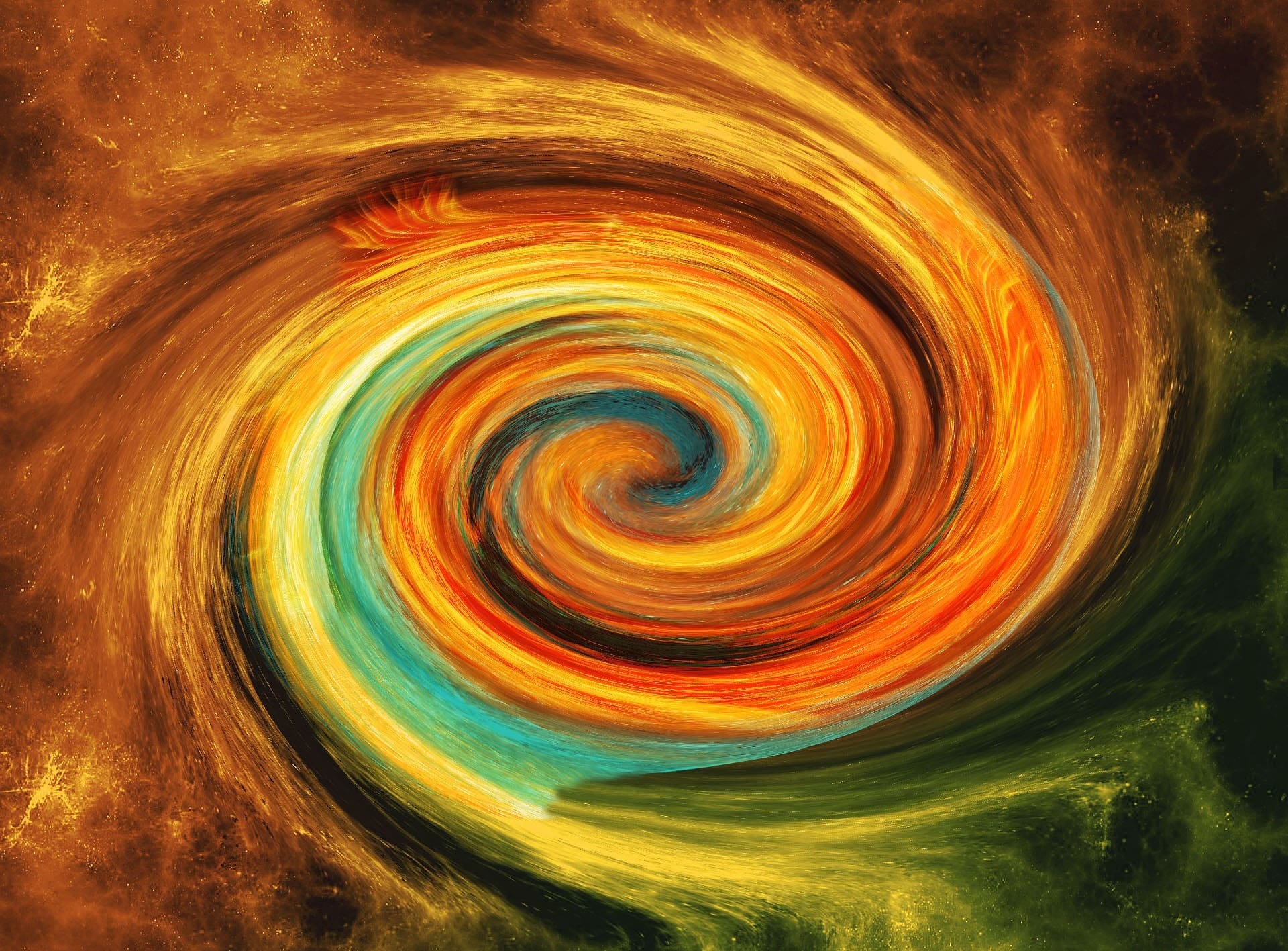小説 祇園精舎の鐘の声 六の篇
しかし、闇の中では一歩歩を進めるのにも一大決心が要り、びくびくと一歩を踏み出したならば、存在は闇の中を闊歩せねばならぬのである。自由の闇の中を闊歩せずしてどうして自由が満喫できるのか。やがて闇に目が慣れ、闇の中を次第に自在に逍遥できるやうになるのだ。さうなれば、存在は大胆になり、やがて、頭蓋内の闇と外部の闇の境目が消えて、それらは地続きとなり、現存在は奇妙な感覚に襲はれる。天地左右が曖昧になり、その場にへたりと座り込む。天地左右が曖昧の中、現存在は最早歩行不全に陥る。さうして妄想は肥大化の道を歩み、現存在の内部で押さへ付けられてゐた異形の吾群が、わあっと溢れ出、暗中の其処彼処を跋扈し始める。それも束の間、伸びをした異形の吾たちは私の周りをぐるりと取り囲み私を呑み込まうとして手ぐすね引いて待ってゐるのだ。つまり、異形の吾どもの自由の足枷がこの私の存在なのである。邪魔者は消せ、それが異形の吾どもの流儀であった。
倉井大輔は土塁の雑木林の中をぶらつき、異形の吾どもを自由にするべき、倉井大輔は異形の吾どもの人身御供になるべく、腰を下ろして胡座を舁きパイプ煙草を吹かし始めるのである。殺気に満ちた異形の吾どもとは対照的に倉井大輔は余裕綽綽なのである。倉井大輔の心は清澄で諦念の境地にあったのか、最早自我を押し通すことに何の意味も見出せないと悟ったかのやうに融通無碍なのであった。さうなると返って異形の吾ともは倉井大輔に躙り寄ることすらできずに、その場で地団駄を踏む以外術がないのである。それは何故か。倉井大輔は風に柳で、倉井大輔自身が自由に解放され、異形の吾どもはその神神しさ圧倒されるのである。その時の倉井大輔は、無敵であった。後光が射すとは将にこの時の倉井大輔のことで、倉井大輔が発する後光に異形の吾どもは怯むのである。
煙草を吹かしながら、倉井大輔はといふと、闇と戯れて為すがままに自我を棄てるのであった。自我を棄てるとはどういふことかといふと、倉井大輔は闇に紛れて闇に同化することのみに心血を注ぐのである。さうすると、倉井大輔はあらゆるものに対する執着が消え、それが束の間であらうが、一時の間、あれだけ執着してゐた苦悶から解き放たれるのであった。
六の編終はり