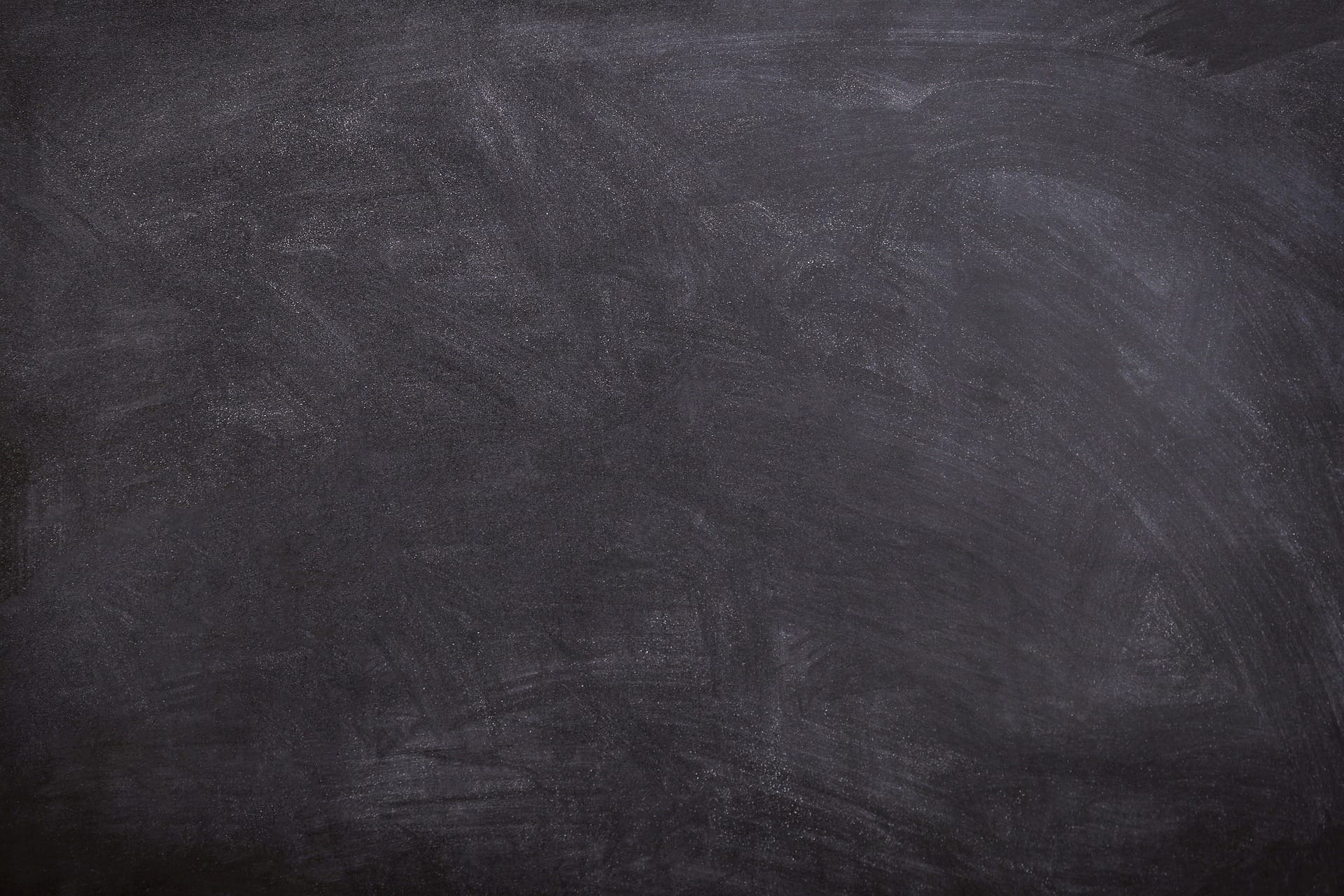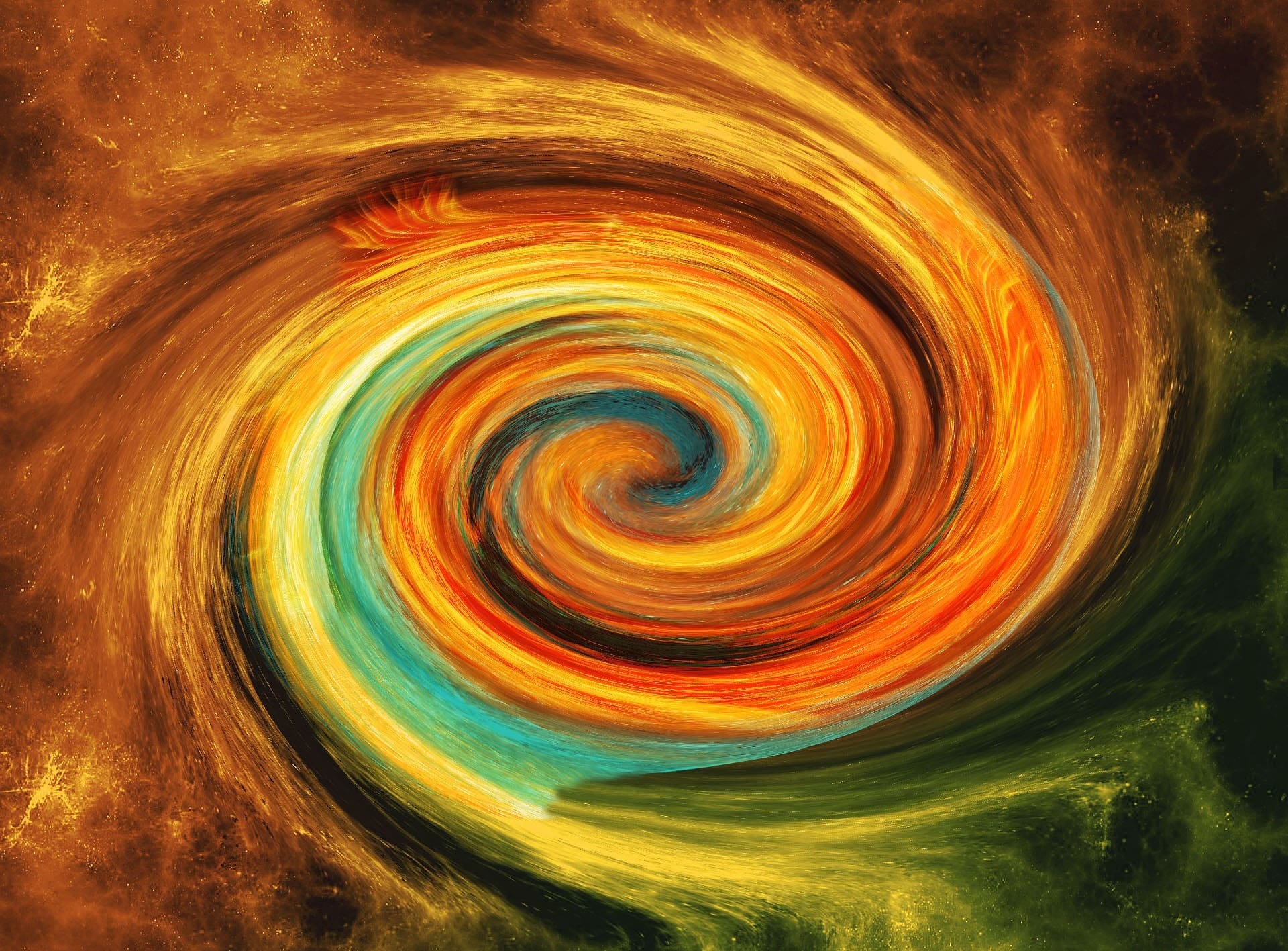それでその少年に何が残されたといふのか。射精後の虚脱感、つまり、どうしやうもない虚無が残された筈である。その虚無を求めてその少年は殺戮を次次と犯してゐたといふことになるが、少年では手に負へない虚無に対してその少年はどう対処したのであらうか。その少年は、だから、呪はれたやうに生き物を殺して回ったのだ。その虚無をしてその少年は己を透明な存在と叫ばせたのだらう。心の叫びといへば聞こへはいいが、それは徹頭徹尾その少年が招いたことである。その尻拭ひは自分でする外ないのだ。誰に己が虚無を訴へたところで、誰も聞く耳を持ち合はせてゐない。その挙げ句が幼子を殺戮し、首を刎ねて小学校の校門の前に置くといふ蛮行に走らせた。それがことの顚末である。当時少年であったそのものは、現在、何処かの街中で常人のやうに日常を送ってゐるが、あのときの恍惚状態は決して忘れられず、虚無に再び囚はれたときには風俗店に通ふか、激しいMasturbationをするか、恋人か伴侶がゐれば、強引な性行為を行って己のLibidoの捌け口にしてゐるのかもしれぬ。或ひは自傷行為を繰り返して己を傷つけてゐるやもしれぬ。しかし、過去の狂気の沙汰は消せないのだ。その重い重い重い十字架は、一生背負ってゐなければならぬ。自棄を起こさうが、その十字架はくっついて離れない。それが罪といふものだ。或ひは宗教に救ひを求めてゐるかもしれぬが、宗教は、慰みになるかもしれぬが神はそのものを救ひはしないのだ。神は唯見守ってゐるだけに過ぎぬ。
倉井大輔はふうっと煙草の煙を吐いて、まだ己に巣くふ異形の吾を叩き出すやうに己を内省したのであった。闇に染まると闇色に染まるとでは雲泥の差がある、と倉井大輔は思った。倉井大輔は己が「にんげん」に悖る存在に堕すことは望んでゐなかったので、闇の雑木林の中で、倉井大輔を取り囲む異形の吾どもに対峙し、異形の吾どもに倉井大輔が丸呑みされるのではなく、倉井大輔が異形の吾どもを全て丸呑みせねばならぬと覚悟を決めたのである。
――ごううううん。
倉井大輔は再び梵鐘の音を聴いたやうな気がした。それが空耳であるのは解ってゐたが、倉井大輔はそれで人心地がついたのであった。
――ふうんっ。
と、倉井大輔は踏ん張り気合ひを入れると、異形の吾どもを一匹づつ捕まへてはぐしゃりと握り潰し丸めてはごくりと呑み込み始めたのである。
九の篇終はり
Post Views: 159
関連