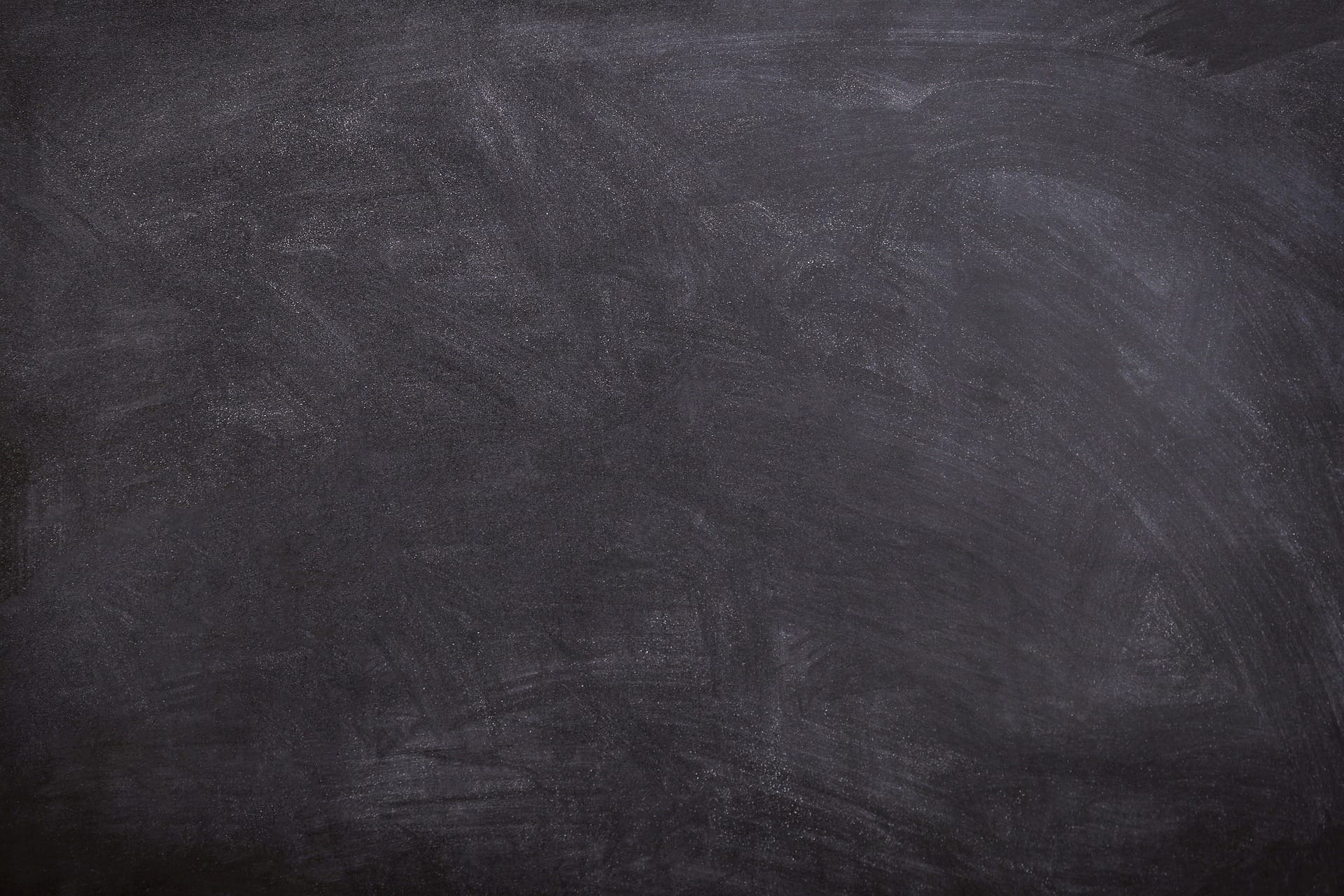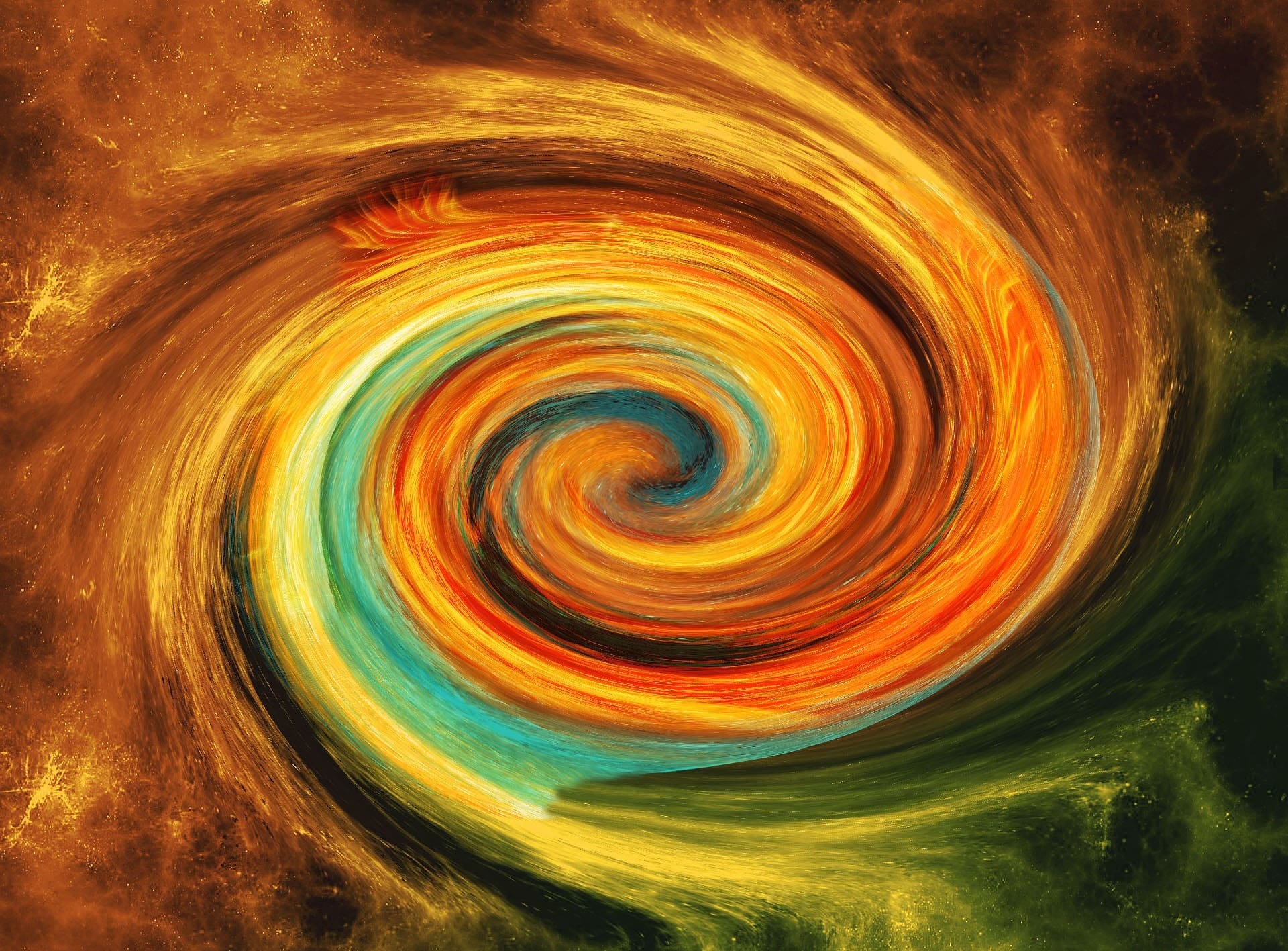小説 祇園精舎の鐘の声 十一の篇
――ちぇっ、あの赤い月がせせら笑ってゐやがる。そんなに可笑しいか。おれが鬼の形相で必死に魂にしがみつくことが。
赤い昇り立ての月は、しかし、せせら笑ってなどをらず、地球の大気を最後まで通過した赤色の波長の長い太陽光が月面で反射して地球に降り注いでゐるに過ぎず、単なる物理現象として月は赤いのであり、それ以上でもそれ以下でもなかった。然し乍ら、その赤い月は倉井大輔には異様にしか見えず、数理的な論理と倉井大輔の感情とのこの跨ぎ果せない巨大な溝は如何様にもできずに倉井大輔は、赤い月が身も蓋もない単なる物理現象に過ぎないと知りつつもどうしても赤い月に異様な胸騒ぎを覚えずにはゐられなかったのである。
それは葛藤といふ言葉で片付けるには余りにも似つかはしくない様相をしてゐて、強ひて上げれば数理的論理と内部から鬱勃と湧き上がる感情との全く相容れない、つまり、お互ひが全く次元の違ふところで、向き合ふことが逆立ちしても不可能なものとして、あらぬ方を向いて対座するといふ言葉が相応しく、倉井大輔はといふと其処に無限の断裂を見てしまふのであった。それはいつまで経っても感情は数理的論理とは違ふ論理で太古の昔より全く進歩なくあり続けてゐる、つまり、倉井大輔の魂と肉体との関係と相似形なのである。それはFractalフラクタルな関係にあるともいへ、感情は抑圧してでも数理的な論理を受け容れなければ、倉井大輔が世界に押し潰されてしまふ生死を分けるほどに重大な意味を持つことなのであった。然し乍ら、感情は理性の言ふ事など聞く筈もなく、理性と悟性、そして感性に対しての感情の不服従の姿勢は一貫してゐて、感情を抑へつつけるには理性による恐怖政治を布かなければ到底感情を抑へつけることなどできる筈もなく、然し乍ら、倉井大輔はといふと理性の恐怖政治にほとほと疲れてしまってゐたのである。現代社会に生きる現存在が抱へ込まざるを得ぬ科学的論理といふ洪水に呑み込まれることに倉井大輔は何のことはない、疲労困憊してゐただけなのであった。
十一の篇終はり