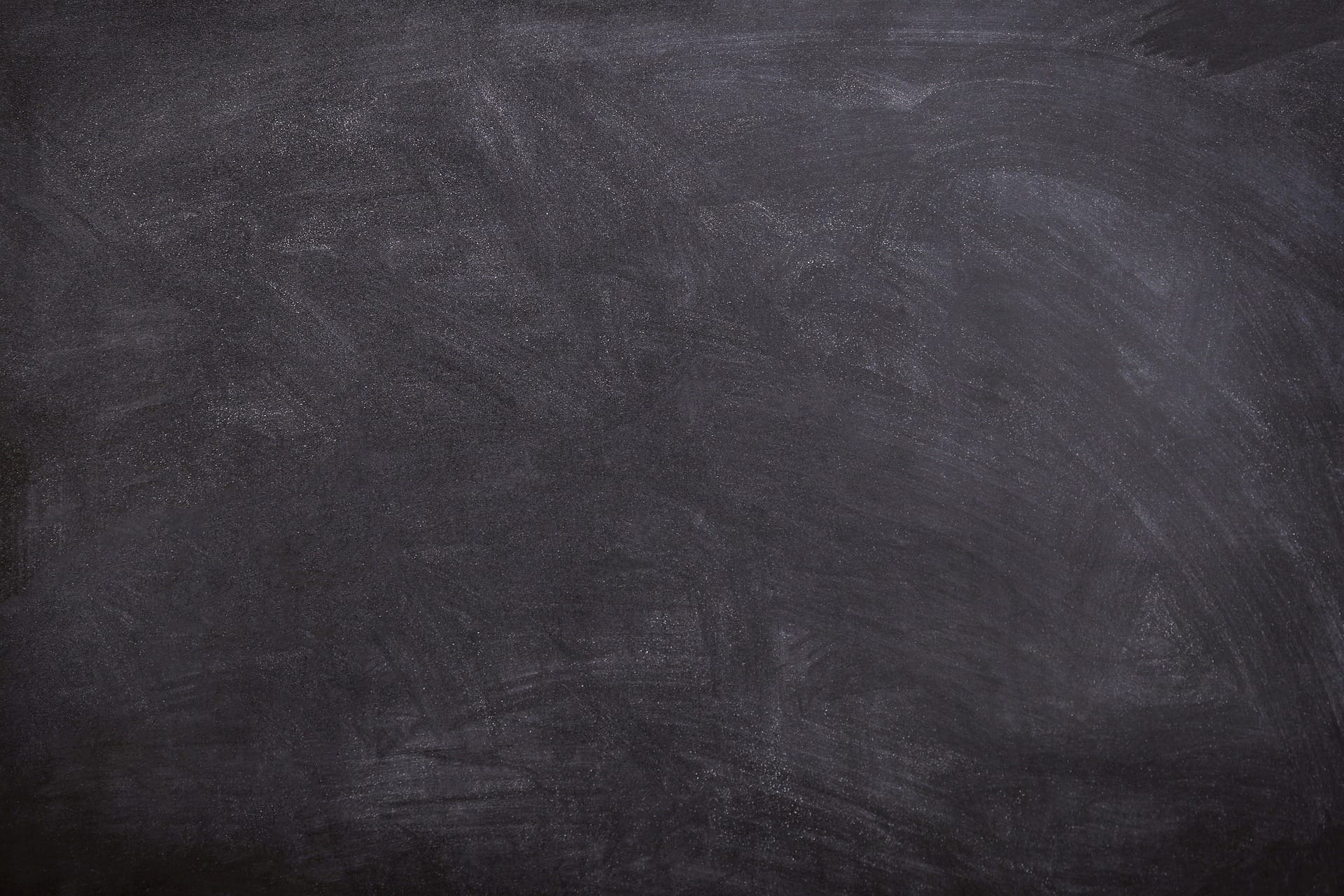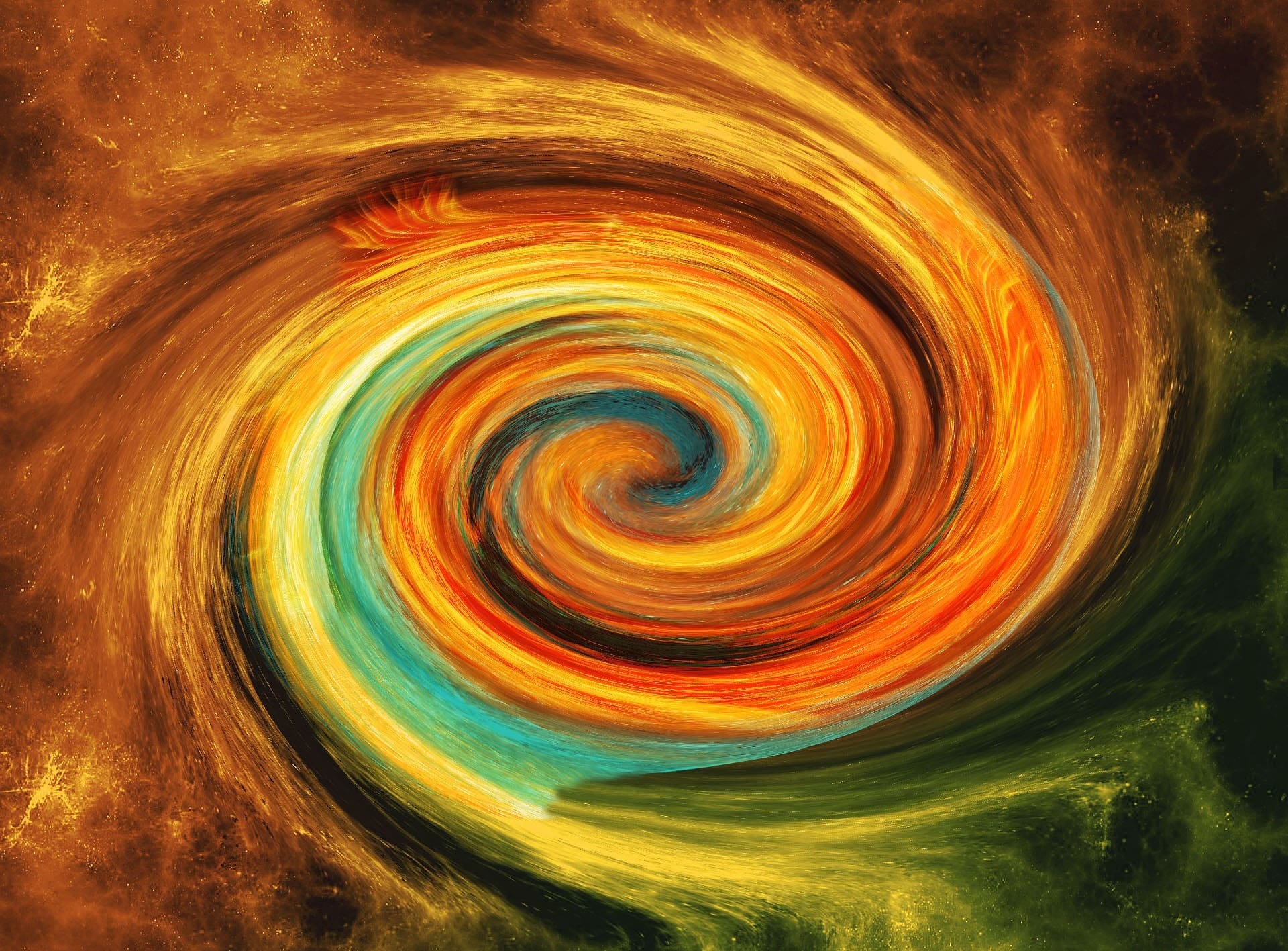小説 祇園精舎の鐘の声 十三の篇
尤も、社会から退避した籠もり人たちに戦略があるのかといへば、全くなく、追ひ詰められた末の已むに已まれぬ退避でしかないので、この文明の留まるところを知らぬ疾風怒濤の進軍のそのJargonで理論武装された難攻不落の要塞の如き有様に対して、自分をこれ以上壊されたくないので、籠もる外なかったのが実情である。それでは籠もった人人はこの先どうしやうとするのだらうか。さう考へると、籠もった人人は何の見通しもなく、自死覚悟でこの留まるところを知らぬ高度情報科学技術文明の発展から退避したに違ひなのである。一方で文明の進軍は驀進を已めず、一方で籠もり人たちは文明の火炎旋風の如き様相を呈したその残酷な一面から顔を背け、後退りするしかないこの分断は、最早埋めやうもなく拡がるばかりなのであった。籠もった人人はそれを見て絶望しか感じ取ることはできず、未来に希望を見出すことは不可能に思はれたのか、一度引き篭もってしまふと部屋から出ることすらままならず、それは文明が魔王の如き暗き影を纏ひ、その暗き影が部屋から一歩でも出れば自分を呑み込んでしまふ恐怖に引き篭もった人たちはぶるぶると震へてゐるに違ひないのである。倉井大輔はといへば、流石に科学理論の洪水には疲労困憊してはゐたが、根は理論好きなこともあり、引き篭もることはせずに、尤も、文明の異様な熱狂とは距離を置く立ち位置でゐたのであった。それもまた、一歩間違へればヘトヘトに疲れた上の自死へと踏み出す踏み台になりかねず、危険な世界との関係にあるのも事実であった。
十三の篇終はり