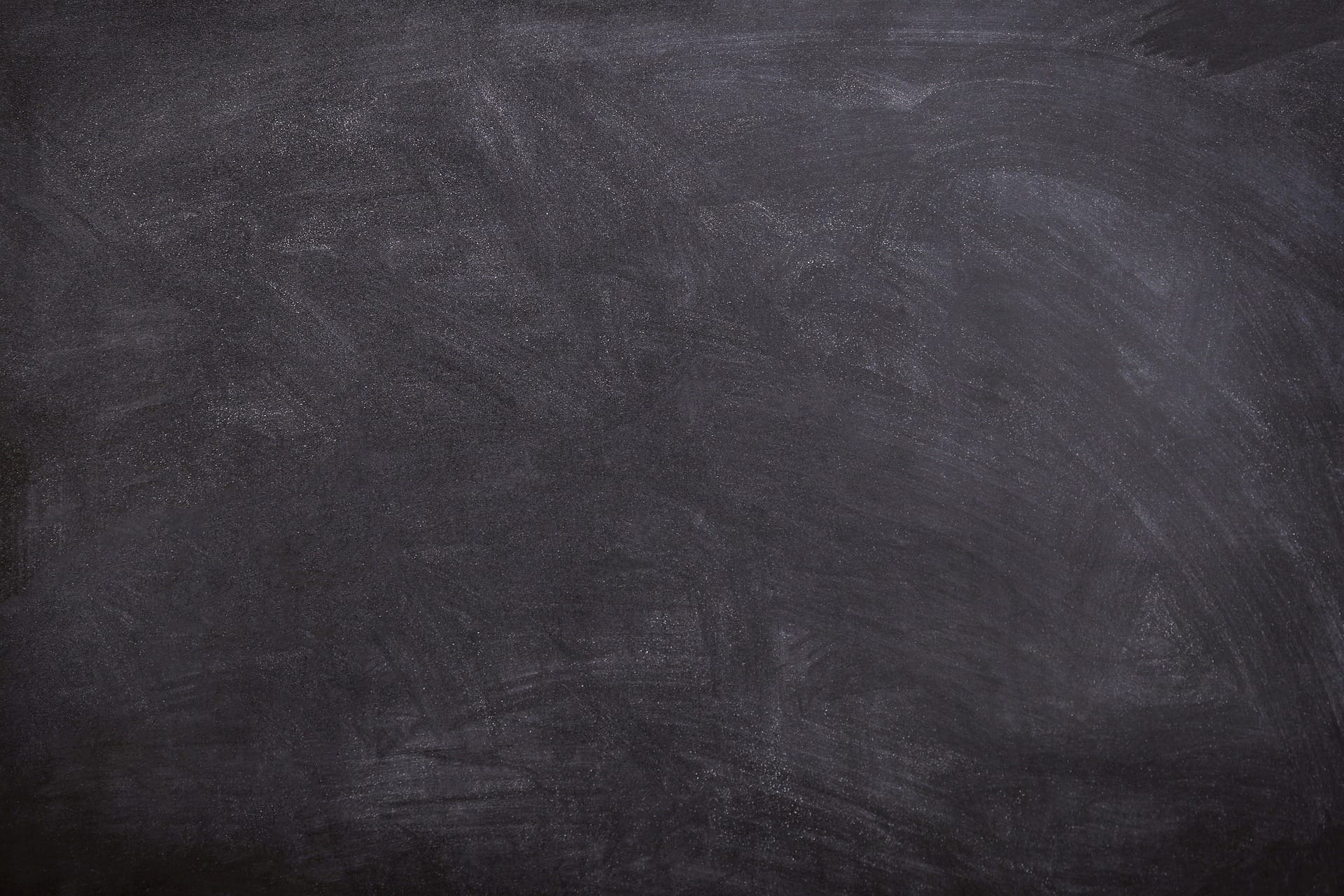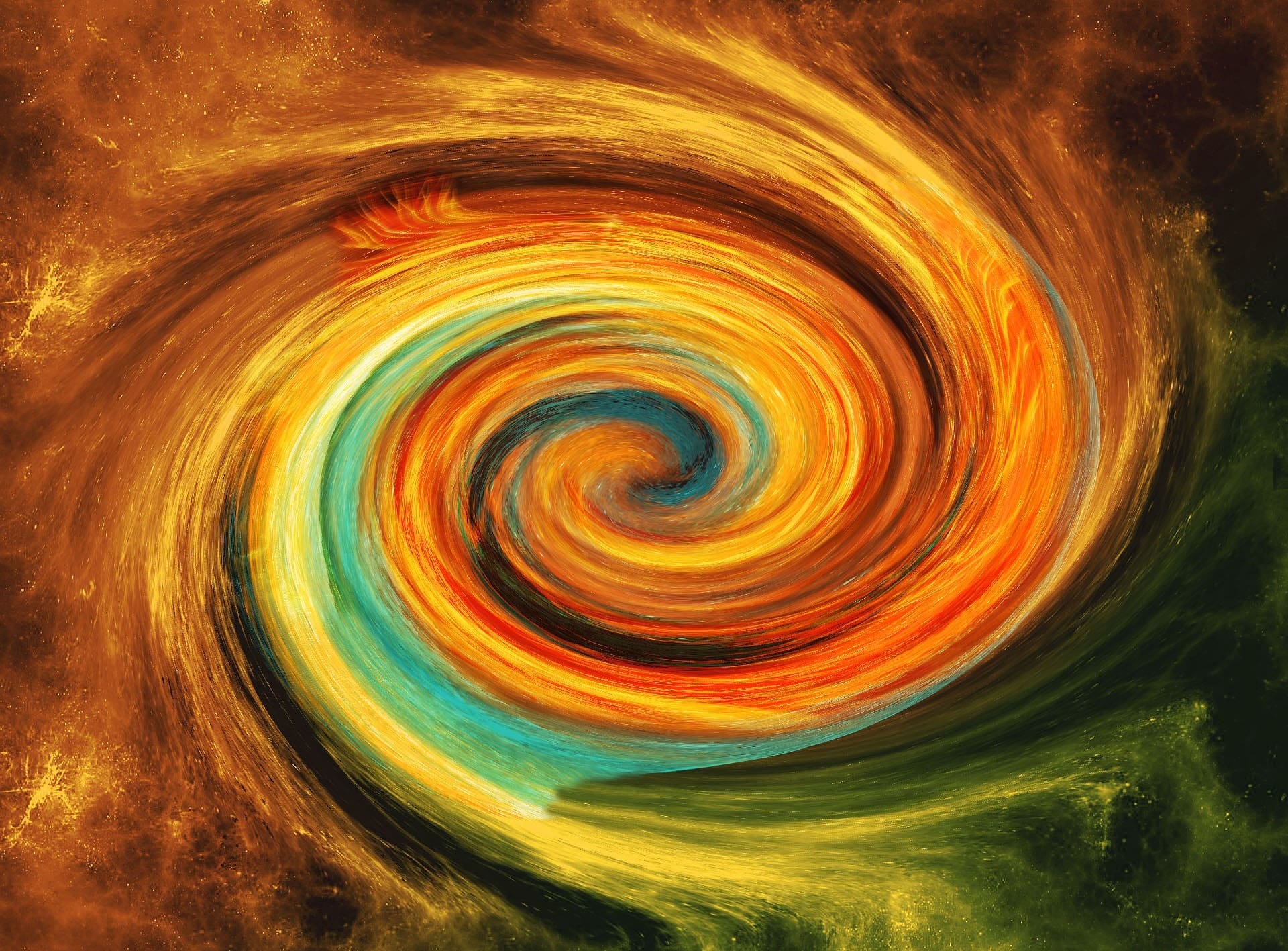小説 祇園精舎の鐘の声 二十二の編
――奴は敵だ。殺せ。
といふまもなく、問答無用に敵対者は殺される。そして、殺されたものは誰が己を殺したのか其の顔すら解らない。これでは成仏できずに此の世を彷徨ふ霊魂が、呪ひをかけるべきものの正体が解らず、彷徨ひ歩く霊魂は、切羽詰まった末に全く無関係の人たちに向けて呪ふことになる。さうして、現代は何の因果もないものがただ殺したいといふだけで殺される運命にあるのかもしれない。つまり、因果律が滅茶苦茶なのだ。偶さかその場に居合はせただけで、悲運にも殺されてしまふ。無闇矢鱈に殺されてしまふ。この現象は何としたことか。死んだものの中で、成仏できずに此の世を彷徨ふ霊魂の仕業とでもいふのか。赤の他人を殺したいから殺す。さうして自分は死刑になって死ぬといふ全く非論理的で非因果律な中に投企されてしまった現代人は、しかし、その因を探ると「楽」を追求したことと無関係ではないとだけはいへる。それほどに「楽」を求めることは罪深いのである。
それでも人間は「楽」を欣求して已まない。何故なのか。それは「楽」は麻薬と同じで、一度それを体験してしまったなら已められないといふことである。「楽」を知ってしまったものの顔を見るがいい。その懶惰な笑顔に恍惚とした快楽に浸ったなんとも相好が崩れたといふ外ない醜さ満載の笑い顔が見える筈である。ともかく、笑顔で溢れるのは間違ひない。とはいへ、その醜さといったならば、倉井大輔には反吐が出そうなほど気色悪いのである。然し乍ら、人類にとっては勝利の美酒に酔い痴れた笑顔だから始末に負へないのである。倉井大輔はそんな時、いつも苦虫を噛み潰したやうに顔がひん曲がった嗤ひを発して、
――巫山戯るな。これが勝利? これは敗北だ!
と、ぶつくさと自身に向かって独り言ちるのであった。
二十二の篇終はり